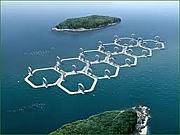|
|
|
|
コメント(16)
しかし、どうして、♂五郎っ〜さんとは、こんなに気が合うというか、物差しが一緒なんだろう???
実は、ボクも先日から福島の子どもたちがスゴく心配になっているんです。
そして、今月には、福島県から愛知県に避難してくる人(30キロ圏外でも)を支援する会を立ち上げるところです。
原発について、もっと学ばないといけないと思い、連休中には原発関連の講演を2本聞きに行く予定です。
だから、Ustも時間を作って見てみます。
太陽電池のパネルを全ての高速道路の防音壁に使用したら…という意見もあり、個人的には、賛同しています。
このコミュでいろいろ勉強させてください。
また、会を立ち上げたら告知させてください。
実は、ボクも先日から福島の子どもたちがスゴく心配になっているんです。
そして、今月には、福島県から愛知県に避難してくる人(30キロ圏外でも)を支援する会を立ち上げるところです。
原発について、もっと学ばないといけないと思い、連休中には原発関連の講演を2本聞きに行く予定です。
だから、Ustも時間を作って見てみます。
太陽電池のパネルを全ての高速道路の防音壁に使用したら…という意見もあり、個人的には、賛同しています。
このコミュでいろいろ勉強させてください。
また、会を立ち上げたら告知させてください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
脱原発・自然エネルギー推進運動 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
脱原発・自然エネルギー推進運動のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37862人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90060人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208308人