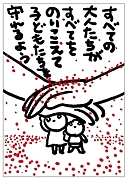先頃、NHKで食品や飲料のセシウムの放射能基準について放送があったようで、その放送の米国の放射能基準について記しておきます。
■被曝関連コミュより
NHKで食品の基準値について、
アメリカ1200べクレル
EU500べクレル
日本500べクレル
と放送。
<クローズアップ現代>
●世界の水道水の放射線基準値
WHO基準 1ベクレル(Bq/L)
ドイツガス水道協会 0.5ベクレル(Bq/L)
アメリカの法令基準 0.111ベクレル(Bq/L)
参考サイト:
1.
http://
http://
2.
http://
3.
http://
4.
http://
5.
http://
●NHKは、ツイッターで相当叩かれてますね。
問い合わせした人のツイート
https:/
-------------------------------------------------------------
■0.111Bq/Lと1200bq/kgの謎
〜米国の法令(安全)基準と介入基準の違い=
アメリカの平時、有事における法令(安全)基準値は0.111ベクレル(Bq/L) です。またもうひとつのネットで拾える「米国安全基準とされる1200bq/kg」は安全基準値ではありません。
FDA文書によると「食品・飼料の偶発的放射能汚染に対する政府・自治体機関への提言=FDAの介入基準(DIL)」となっていますので、安全基準とは意味が違います。
日本のように「安全基準そのものを引き上げる」のと、法令基準はそのままに「政府、自治体の介入のために別に儲けられる介入基準」は、その性質が全く異なります。
いわゆる1200bq/kgは、「食品、飼料の偶発的放射能汚染に対するDIL(推奨誘導介入レベル)=商業的に流通する食品で許容される1年限定の濃度の上限」ということです。
従って「政府や自治体は検査や規制や除洗によって、食品や飼料の汚染を1200bq/kgまで抑えるように介入すべき」とする努力目標ですので、被曝安全基準とは言えません。
安全基準とは、全ての国民に対して適用する「健康に害を及ぼさない範囲として設置した濃度上限」であり、介入基準とは「政府、自治体が安全基準を充たすために必要な措置を介入させる目的でのみ、極めて限定的に設けられる濃度上限」である。
「最悪の状況=世界核戦争などで世界中の食品や飼料が汚染されても、米国政府や自治体はこの1200ベクレルの濃度上限の範囲内で、可能な限り国民の被曝を0.111ベクレルの法令安全基準に近づけるための介入をする責任がある」というお達しですから、被曝安全基準値とは全く異なります。
※また米国FDA文書には「介入基準(DIL)は事故後1年間用いられる。食品が引き続き一年以上汚染されると懸念されるのならば、長期環境を評価に介入基準を引き続き用いるのか、他の指針を用いるのか決定する必要がある」とも記されています。
■FDA文書より
推奨誘導介入レベル(DIL Recommended Derived Intervention Level)もしくは放射性核種群の基準値
Sr-90 160Bq/kg
I-131 170Bq/kg
Cs-134+Cs-137 1200Bq/kg
Pu-238+Pu-239+Am-241 2Bq/kg
Ru-103+Ru-106 Ru-103濃度/6800+Ru-106/450<1
9-26放映クローズアップ現代
視聴者ドン引きのツイート集 - NAVER まとめ
http://
■被曝関連コミュより
NHKで食品の基準値について、
アメリカ1200べクレル
EU500べクレル
日本500べクレル
と放送。
<クローズアップ現代>
●世界の水道水の放射線基準値
WHO基準 1ベクレル(Bq/L)
ドイツガス水道協会 0.5ベクレル(Bq/L)
アメリカの法令基準 0.111ベクレル(Bq/L)
参考サイト:
1.
http://
http://
2.
http://
3.
http://
4.
http://
5.
http://
●NHKは、ツイッターで相当叩かれてますね。
問い合わせした人のツイート
https:/
-------------------------------------------------------------
■0.111Bq/Lと1200bq/kgの謎
〜米国の法令(安全)基準と介入基準の違い=
アメリカの平時、有事における法令(安全)基準値は0.111ベクレル(Bq/L) です。またもうひとつのネットで拾える「米国安全基準とされる1200bq/kg」は安全基準値ではありません。
FDA文書によると「食品・飼料の偶発的放射能汚染に対する政府・自治体機関への提言=FDAの介入基準(DIL)」となっていますので、安全基準とは意味が違います。
日本のように「安全基準そのものを引き上げる」のと、法令基準はそのままに「政府、自治体の介入のために別に儲けられる介入基準」は、その性質が全く異なります。
いわゆる1200bq/kgは、「食品、飼料の偶発的放射能汚染に対するDIL(推奨誘導介入レベル)=商業的に流通する食品で許容される1年限定の濃度の上限」ということです。
従って「政府や自治体は検査や規制や除洗によって、食品や飼料の汚染を1200bq/kgまで抑えるように介入すべき」とする努力目標ですので、被曝安全基準とは言えません。
安全基準とは、全ての国民に対して適用する「健康に害を及ぼさない範囲として設置した濃度上限」であり、介入基準とは「政府、自治体が安全基準を充たすために必要な措置を介入させる目的でのみ、極めて限定的に設けられる濃度上限」である。
「最悪の状況=世界核戦争などで世界中の食品や飼料が汚染されても、米国政府や自治体はこの1200ベクレルの濃度上限の範囲内で、可能な限り国民の被曝を0.111ベクレルの法令安全基準に近づけるための介入をする責任がある」というお達しですから、被曝安全基準値とは全く異なります。
※また米国FDA文書には「介入基準(DIL)は事故後1年間用いられる。食品が引き続き一年以上汚染されると懸念されるのならば、長期環境を評価に介入基準を引き続き用いるのか、他の指針を用いるのか決定する必要がある」とも記されています。
■FDA文書より
推奨誘導介入レベル(DIL Recommended Derived Intervention Level)もしくは放射性核種群の基準値
Sr-90 160Bq/kg
I-131 170Bq/kg
Cs-134+Cs-137 1200Bq/kg
Pu-238+Pu-239+Am-241 2Bq/kg
Ru-103+Ru-106 Ru-103濃度/6800+Ru-106/450<1
9-26放映クローズアップ現代
視聴者ドン引きのツイート集 - NAVER まとめ
http://
|
|
|
|
コメント(2)
米国介入基準の2倍編集する全体に公開
2011年10月01日01:21
■原発敷地外で微量プルトニウム…福島・双葉など
(読売新聞 - 09月30日 19:38)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1761197&media_id=20
この任意の場所のみによるプルトニウム4ベクレル検出は、放射線量として見れば確かにすぐに危険な数値ではないが、その地域全体の「飲料や食料、飼料への汚染」として見れば、米国FDAが提言した「偶発的放射能汚染という最悪の事態を想定した米国政府、自治体の介入基準」の倍の数値となる。
任意の何箇所かの土壌測定で検出されたプルトニウム検出は大きな問題は、その地域全体では何ベクレルになるのか想像もつかないからであり、放射性物質による土壌汚染は、地下水や植物に吸収され、それらは食物連鎖によって生物に蓄積されてその上位に位置する人間に内部被曝をもたらすからである。
-------------------------------------------------------------
【日本の暫定的安全基準】 2011年08月05日
プルトニウム及び超ウラン元素 のアルファ核種
(238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,
242Cm, 243Cm, 244Cm 放射能濃度の 合計)
乳幼児用食品 飲料水 牛乳・乳製品 1 Bq/kg
野菜類 穀類 1肉・卵・魚・その他 10 Bq/kg
-------------------------------------------------------------
【米国 偶発的放射能汚染に対する限定的介入基準】
■FDA文書より
推奨誘導介入レベル(DIL Recommended Derived Intervention Level)もしくは放射性核種群の基準値
全ての飲料 食品 飼料 Pu-238+Pu-239+Am-241 2Bq/kg
-------------------------------------------------------------
【介入基準とは】
■セシウム0.111Bq/Lと1200bq/kgの謎
〜米国の法令(安全)基準と介入基準の違い=
アメリカの平時、有事における法令(安全)基準値は0.111ベクレル(Bq/L) です。またもうひとつのネットで拾える「米国安全基準とされる1200bq/kg」は安全基準値ではありません。
FDA文書によると「食品・飼料の偶発的放射能汚染に対する政府・自治体機関への提言=FDAの介入基準(DIL)」となっていますので、安全基準とは意味が違います。
日本のように「安全基準そのものを引き上げる」のと、法令基準はそのままに「政府、自治体の介入のために別に儲けられる介入基準」は、その性質が全く異なります。
いわゆる1200bq/kgは、「食品、飼料の偶発的放射能汚染に対するDIL(推奨誘導介入レベル)=商業的に流通する食品で許容される1年限定の濃度の上限」ということです。
従って「政府や自治体は検査や規制や除洗によって、食品や飼料の汚染を1200bq/kgまで抑えるように介入すべき」とする努力目標ですので、被曝安全基準とは言えません。
安全基準とは、全ての国民に対して適用する「健康に害を及ぼさない範囲として設置した濃度上限」であり、介入基準とは「政府、自治体が安全基準を充たすために必要な措置を介入させる目的でのみ、極めて限定的に設けられる濃度上限」となります。
「最悪の状況=世界核戦争などで世界中の食品や飼料が汚染されても、米国政府や自治体はこの1200ベクレルの濃度上限の範囲内で、可能な限り国民の被曝を0.111ベクレルの法令安全基準に近づけるための介入をする責任がある」というお達しですから、被曝安全基準値とは全く異なります。
※また米国FDA文書には「介入基準(DIL)は事故後1年間用いられる。食品が引き続き一年以上汚染されると懸念されるのならば、長期環境を評価に介入基準を引き続き用いるのか、他の指針を用いるのか決定する必要がある」とも記されています。
-------------------------------------------------------------
2011年10月01日01:21
■原発敷地外で微量プルトニウム…福島・双葉など
(読売新聞 - 09月30日 19:38)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1761197&media_id=20
この任意の場所のみによるプルトニウム4ベクレル検出は、放射線量として見れば確かにすぐに危険な数値ではないが、その地域全体の「飲料や食料、飼料への汚染」として見れば、米国FDAが提言した「偶発的放射能汚染という最悪の事態を想定した米国政府、自治体の介入基準」の倍の数値となる。
任意の何箇所かの土壌測定で検出されたプルトニウム検出は大きな問題は、その地域全体では何ベクレルになるのか想像もつかないからであり、放射性物質による土壌汚染は、地下水や植物に吸収され、それらは食物連鎖によって生物に蓄積されてその上位に位置する人間に内部被曝をもたらすからである。
-------------------------------------------------------------
【日本の暫定的安全基準】 2011年08月05日
プルトニウム及び超ウラン元素 のアルファ核種
(238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,
242Cm, 243Cm, 244Cm 放射能濃度の 合計)
乳幼児用食品 飲料水 牛乳・乳製品 1 Bq/kg
野菜類 穀類 1肉・卵・魚・その他 10 Bq/kg
-------------------------------------------------------------
【米国 偶発的放射能汚染に対する限定的介入基準】
■FDA文書より
推奨誘導介入レベル(DIL Recommended Derived Intervention Level)もしくは放射性核種群の基準値
全ての飲料 食品 飼料 Pu-238+Pu-239+Am-241 2Bq/kg
-------------------------------------------------------------
【介入基準とは】
■セシウム0.111Bq/Lと1200bq/kgの謎
〜米国の法令(安全)基準と介入基準の違い=
アメリカの平時、有事における法令(安全)基準値は0.111ベクレル(Bq/L) です。またもうひとつのネットで拾える「米国安全基準とされる1200bq/kg」は安全基準値ではありません。
FDA文書によると「食品・飼料の偶発的放射能汚染に対する政府・自治体機関への提言=FDAの介入基準(DIL)」となっていますので、安全基準とは意味が違います。
日本のように「安全基準そのものを引き上げる」のと、法令基準はそのままに「政府、自治体の介入のために別に儲けられる介入基準」は、その性質が全く異なります。
いわゆる1200bq/kgは、「食品、飼料の偶発的放射能汚染に対するDIL(推奨誘導介入レベル)=商業的に流通する食品で許容される1年限定の濃度の上限」ということです。
従って「政府や自治体は検査や規制や除洗によって、食品や飼料の汚染を1200bq/kgまで抑えるように介入すべき」とする努力目標ですので、被曝安全基準とは言えません。
安全基準とは、全ての国民に対して適用する「健康に害を及ぼさない範囲として設置した濃度上限」であり、介入基準とは「政府、自治体が安全基準を充たすために必要な措置を介入させる目的でのみ、極めて限定的に設けられる濃度上限」となります。
「最悪の状況=世界核戦争などで世界中の食品や飼料が汚染されても、米国政府や自治体はこの1200ベクレルの濃度上限の範囲内で、可能な限り国民の被曝を0.111ベクレルの法令安全基準に近づけるための介入をする責任がある」というお達しですから、被曝安全基準値とは全く異なります。
※また米国FDA文書には「介入基準(DIL)は事故後1年間用いられる。食品が引き続き一年以上汚染されると懸念されるのならば、長期環境を評価に介入基準を引き続き用いるのか、他の指針を用いるのか決定する必要がある」とも記されています。
-------------------------------------------------------------
■プルトニウムの毒性
プルトニウムの同位体および化合物はすべて放射性物質である。化学毒性についてはウランに準ずると考えられている。しかし、その化学毒性が現れるよりもはるかに少ない量で放射線障害が生じると予想されるため、化学毒性のみでプルトニウムの毒性を論ずることはできない。
プルトニウムの急性毒性による半数致死量は、経口摂取で32 g、吸入摂取で13 mg。長期的に見た場合は経口摂取で1150 mg、吸入摂取で0.26 mg(潜伏期間として15年以上)である。また、プルトニウム239の年摂取限度(1 mSv/年)は、経口摂取で48 μg (11万 Bq) 、呼吸器への吸入では52 ng (120 Bq) である(1 ng(ナノグラム)は 0.000000001 g(グラム))。
プルトニウムは人類が初めて作り出した放射性核種であり、プルトニウムがα線を放出すること、同じα線を出すウランなどと比べて比放射能が高いこと、体内での代謝挙動が危険であることから、「かつて人類が遭遇した物質のうちでも最高の毒性をもつ」という意見もある[16]。ただし、α線は強いエネルギーを持つものの透過能力がなく、紙1枚や数cmの空気層で容易に遮蔽されてしまう。比放射能については半減期が短いほど強くなるため、239Pu(半減期2万4千年)は 235U(半減期7億年)や 238U(半減期45億年)と比べてさらに有害とされるが、これは 131I(半減期8.1日)や 137Cs(半減期:30年)といった他の核分裂由来の一般的な放射性物質と比較した場合は非常に低い比放射能である。たとえ 239Pu を摂取したとしても、長くて100年の寿命である人間が受ける放射線被曝総量(すなわち崩壊量)は0.3 %程度である(同期間で 131I なら全量が崩壊)。このようにα線では外部からは皮膚表面などで放射線は遮蔽され、半減期の長さと比放射能での被曝危険性は完全に反比例する。そのため、プルトニウムの危険性は主に体内に取り込んだ場合の内部被曝によるものである。
■体内摂取の経路と排出
プルトニウムを嚥下し消化管に入った場合、そのおよそ0.05 %程度が吸収され、残りは排泄される[17]。吸収された微量のプルトニウムは骨と肝臓にほぼ半々の割合で蓄積され、体外へは排出されにくい。生物学的半減期はウランやラジウムと比べても非常に長く、骨と肝臓でそれぞれ20年と50年である。放射線による有害さは核種や同位体によらずラジウム等の全てのα線を出す放射線物質と同じである。
最も有害な取り込み経路は、空気中に粒子状になったプルトニウムの吸入である。気道から吸入された微粒子は、大部分が気道の粘液によって食道へ送り出されるが、残り(4分の1程度)が肺に沈着する。沈着した粒子は肺に留まるか、胸のリンパ節に取り込まれるか、あるいは血管を経由して骨と肝臓に沈着する。そのため、他のα線・β線放射物質による内部被曝と同様に、IARC より発癌性があると (Type1) 勧告されている。また、動物実験では発癌性が認められているが、人においてはプルトニウムが原因で発癌したと科学的に判断された例はまだない[12]。α線を放射するために、国際放射線防護委員会が定める線量係数 (Sv/Bq) では 239Pu の経口摂取で2.5 × 10-7、吸入摂取で1.2 × 10-4と定められ、131I(経口摂取2.2 × 10-8)や 137Cs(経口摂取1.3 × 10-8)よりも1 Bq当たりの人への影響が大きいと想定されている(一般には、α線はβ線よりも20倍の危険性があるとされている)。
プルトニウムの同位体および化合物はすべて放射性物質である。化学毒性についてはウランに準ずると考えられている。しかし、その化学毒性が現れるよりもはるかに少ない量で放射線障害が生じると予想されるため、化学毒性のみでプルトニウムの毒性を論ずることはできない。
プルトニウムの急性毒性による半数致死量は、経口摂取で32 g、吸入摂取で13 mg。長期的に見た場合は経口摂取で1150 mg、吸入摂取で0.26 mg(潜伏期間として15年以上)である。また、プルトニウム239の年摂取限度(1 mSv/年)は、経口摂取で48 μg (11万 Bq) 、呼吸器への吸入では52 ng (120 Bq) である(1 ng(ナノグラム)は 0.000000001 g(グラム))。
プルトニウムは人類が初めて作り出した放射性核種であり、プルトニウムがα線を放出すること、同じα線を出すウランなどと比べて比放射能が高いこと、体内での代謝挙動が危険であることから、「かつて人類が遭遇した物質のうちでも最高の毒性をもつ」という意見もある[16]。ただし、α線は強いエネルギーを持つものの透過能力がなく、紙1枚や数cmの空気層で容易に遮蔽されてしまう。比放射能については半減期が短いほど強くなるため、239Pu(半減期2万4千年)は 235U(半減期7億年)や 238U(半減期45億年)と比べてさらに有害とされるが、これは 131I(半減期8.1日)や 137Cs(半減期:30年)といった他の核分裂由来の一般的な放射性物質と比較した場合は非常に低い比放射能である。たとえ 239Pu を摂取したとしても、長くて100年の寿命である人間が受ける放射線被曝総量(すなわち崩壊量)は0.3 %程度である(同期間で 131I なら全量が崩壊)。このようにα線では外部からは皮膚表面などで放射線は遮蔽され、半減期の長さと比放射能での被曝危険性は完全に反比例する。そのため、プルトニウムの危険性は主に体内に取り込んだ場合の内部被曝によるものである。
■体内摂取の経路と排出
プルトニウムを嚥下し消化管に入った場合、そのおよそ0.05 %程度が吸収され、残りは排泄される[17]。吸収された微量のプルトニウムは骨と肝臓にほぼ半々の割合で蓄積され、体外へは排出されにくい。生物学的半減期はウランやラジウムと比べても非常に長く、骨と肝臓でそれぞれ20年と50年である。放射線による有害さは核種や同位体によらずラジウム等の全てのα線を出す放射線物質と同じである。
最も有害な取り込み経路は、空気中に粒子状になったプルトニウムの吸入である。気道から吸入された微粒子は、大部分が気道の粘液によって食道へ送り出されるが、残り(4分の1程度)が肺に沈着する。沈着した粒子は肺に留まるか、胸のリンパ節に取り込まれるか、あるいは血管を経由して骨と肝臓に沈着する。そのため、他のα線・β線放射物質による内部被曝と同様に、IARC より発癌性があると (Type1) 勧告されている。また、動物実験では発癌性が認められているが、人においてはプルトニウムが原因で発癌したと科学的に判断された例はまだない[12]。α線を放射するために、国際放射線防護委員会が定める線量係数 (Sv/Bq) では 239Pu の経口摂取で2.5 × 10-7、吸入摂取で1.2 × 10-4と定められ、131I(経口摂取2.2 × 10-8)や 137Cs(経口摂取1.3 × 10-8)よりも1 Bq当たりの人への影響が大きいと想定されている(一般には、α線はβ線よりも20倍の危険性があるとされている)。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
■危機管理@放射能情報倉庫 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
■危機管理@放射能情報倉庫のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75498人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196030人