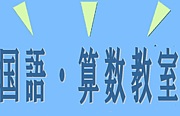これまでこのコラムで紹介してきたサービス産業のどの業種も、人口減少による需要収縮の影響が直撃している。これはサービス業が客商売であり、代金を支払う客の数が減っているからにほかならない。
高齢化が進む前は少子化が先行することから、とりわけ14才までの年少人口の減少が著しい。年少人口は当然のことながら、大半が学校に通う子供たちで構成されており、その減少が教育産業に大きな影響を与えることは容易に想像できる。
教育産業は幅広い。学習塾や予備校、専門学校、語学学校等だけでなく、料理教室やカルチャースクール、通信教育会社も含まれる。中でも、特に年少人口激減の影響を受けていると考えられるのが学習塾である。
ところが、経済産業省が実施している特定サービス産業動態統計調査によると、人口減少に相反してその市場規模は増加している。人口1人当たりの支出額は増加しており、一見すると学習塾が成長産業のようにも思える。
一方で、売り上げの増加以上に増えているのが学習塾数と講師数である。そのため、塾当たりの売上は市場全体の売り上げの動向と減少し続けている。また、講師1人当たりの売り上げも右肩下がりになっている。これは学習塾が、経済環境がより厳しいほかの業種の雇用の受け皿になっていることを意味している。しかし、市場規模の拡大以上に新規参入が続けば、ほかのサービス産業が直面しているように、学習塾も激しい低価格競争に襲われることは容易に想像することができる。
今回紹介するのは、激しい競争が繰り広げられているこの業界において、これまでにない指導方法で支持を集め、教育界の改革まで目指しているGLS予備校(東京都目黒区)である。
教育改革を実現するために学習塾を開く
GLS予備校は2005年、原田将孝塾長がまだ大学4年の時に開校した新しい学習塾である。教室は東京都目黒区に1つしかない。そこに中学生と高校生・浪人生が学び、高校受験と大学受験のために日夜、勉強に励んでいる。
原田塾長は自らの体験を通じて教育分野に多くの問題があると感じていた。何か新しい方法論が必要だと学生時代から考え、一時期は文部科学省で働くことや、学校や予備校に就職することも考えた。しかし文部科学省は現場から遠く、学校や予備校は組織が大きい。特に学校には様々な制約があり、制度などの改革が難しいと感じていた。一方、学習塾には部活動や生活指導がない。教えることだけに専念でき、教育分野で一番制約が少ないことから「GLS予備校」を自ら開校。民間の立場で教育改革に取り組み始めた。
2012年4月10日(火)
http://
原田塾長は「どうしたら成績が伸びるのか。そのノウハウすらない」と憤慨する。つまり、政策や制度の前に、教育方法の確立がそもそもできていない、ということである。学校や塾のような組織の中では、一人ひとりの講師は特定の教科しか教えることができない。教育の効果という観点から見ると、ここに根本的な問題がある。
例えば、英語ができない子供に英語を丁寧に教え続けてもダメなことがあるという。そのような子供は英語の前に国語ができないからだ。社会も同じである。子供によっては、国語ができないために教科書の漢字や表現が難しく、そもそもそこに書かれていることが理解できず、成績が改善しない。だから、そのような子供には国語力を徹底的に付けていかなければならない。同じように、理科が分からない子供の多くは数学ができない。基礎的な数学を理解していない子供に、どんなに物理を教えても成績を伸ばすことができない。この場合は、まず数学の基礎力を付けるところから始めなければならない。これが原田塾長の問題意識だ。
今の学校や塾は多くの生徒を効率的に教えるため、科目を分断している。それぞれの教師には特定の科目を教える権限しか与えられておらず、その仕組みを変えることも難しい。自ら学習塾を開校した原田塾長は、そのトップとして、まず教育方法のノウハウ化に取り組み始めた。
2005年の開校から約6年間は、6畳間の小さな教室で全教科の授業を原田塾長1人で受け持った。生徒数が増えため、2010年11月により大きな教室に引っ越し、今は講師数6人、生徒数は40人強までになった。
問題を解けたかだけなく、解答のプロセスを問う
授業の進め方は独特である。何しろ時間割がない。
GLS予備校は1対多人数の授業ではなく、基本的に1対1の個別指導で授業を進めていく自習型の塾である。しかしその方法は、個別指導型の多くの塾のように小さなブースで1人の教師が1人の生徒に教えるものではない。机と椅子が普通に置かれたオープンな教室に生徒たちは並んで座り、講師が個別指導を行う。まとめて多くの生徒に教えることがないので、教室に黒板はない。
生徒4〜5人に対し1人の講師が教室に入る。もし生徒数が7〜8人であれば教師を2人にする。10人を超えれば3人が入る。授業は一人ひとりの生徒に合わせて個別に進められるので、実際の授業は数名の講師が数名の生徒に教えるチーム指導という方法をとる。だから同じ教室には中学1年生から高校3年生までの様々な学年の生徒が一緒に勉強する。
講師達は一人ひとりの生徒に、いずれかの科目の問題を解いてもらう。国語であれば、知っている言葉や、語彙の意味などを問う。これは語彙力の不足が原因となり、他教科の成績の足を引っ張るからである。また、実際に文章を読ませ、問題を解けたかどうかだけでなく、文章の内容を説明してもらう。英語であれば文章の構造がどれだけ理解できているかを確認する。数学であればグラフを正確に書くことができ、また解答へのプロセスが論理的に説明できるかどうかも見る。
英語や国語の語彙力は知識量であり、そのための暗記力が必要になる。この力がなければ、同じ能力が求められる社会もできない。逆に英語や国語ができるのに社会の成績が悪いのはただ単に勉強が足りないだけでなく、頭の中で全体の大まか流れを論理的にイメージできないまま用語だけを暗記しているためである。同じように古文も単語の語彙力とともに、文法がどれだけ頭に入っているかどうかで決まる。
このようにGLS予備校では、単に解答の○×だけでなく思考のプロセスまで確認し、論理的な思考力や暗記力といった基礎学力を見る。子供は分かりやすい授業を受けると分かった気になるが、自分で人に説明できないことも多く、後で同じ問題を解かせてもできないことも多い。成績が良い子供は、無意識に分かったことを復唱し、それまで勉強したことを自分の中で組み立てている。逆に勉強ができない子供は授業の内容を聞いただけで、何も身に着いていないから説明もできず、成績も良くならないという。
だから、勉強の内容を教える前に、「どのように勉強しているか」という学習の作法がどれだけ身についているかを確認する。これまでの学校や塾と比較した時、GLS予備校は勉強そのものではなく、「勉強のやり方」という作法を教える点に大きな特徴がある。
目の前のテストの点数を上げるだけなら、教師が一生懸命教えればよいだろう。だが、それでは子供のためにならない。生徒が自分で勉強するようになるためには、勉強の作法を身に着け、物事をきちんと理解して論理的に説明できる思考回路を持つことが必要だと原田塾長は考える。
そのため、教え方は生徒ごとに変える。授業はどのような内容の勉強が必要なのかを細かくチェックしながら進めていく。生徒には実際に自分で勉強してもらい、できていないところは「勉強の仕方」のお手本を見せる。そして、正しいお手本が身に着くまで何度も反復させながら習慣にしていく。勉強の作法は「癖のようなもの」と原田塾長は言う。間違った勉強の仕方で長くやってきた子供はどうしても時間がかかる。逆に学年が低ければ低いほど、早く癖を抜くことができるという。
1回3時間という長時間授業の理由
授業は1回3時間。一般の塾に比べて授業時間が長いのは、考える時間、復習する時間を十分に確保して、「勉強の作法」を身に着けるためである。多くの塾では1時間から1時間30分だが、これでは教師が一方的にしゃべるだけで授業は終わってしまい、きめの細かい指導はできない。生徒の状況に合わせて3時間の中で複数の科目を教える。だから、決められた時間割はない。
1対1の個別指導は丁寧な教育ができるように思えるが、問題点もある。授業を講師1人の能力に依存するだけでなく、どのような教え方をしているのかを管理することもできない。講師と生徒の2人だけで授業が完結してしまい、外部から客観的に評価することができないのだ。
GLS予備校では複数名の講師を配置するチーム指導を行うことでこの問題を解決している。チーム指導により、講師と生徒の相性や教え方の良し悪しをより効率的に判断でき、1人の生徒をより多面的に見ることもできる。新人の講師をベテランの講師の見習いとして配置することで、講師の育成も効率的に行うことができる。何かあれば複数の講師が相談してより良い方法で対応することもできる。
勉強の作法をどれだけ修得ができているかは、毎回の授業でチェックし、あるレベルに到達しなければ次に進まないようにしている。達成率は講師が毎月数値化して報告書にまとめている。チーム指導は利点が多い一方、責任の所在が曖昧になる面もある。そのため、個々の生徒にはチーム指導を行うものの、担任制も設け、担任がほかの教師からの情報を集約して報告書を書くようにしている。
現在は講師が6人にまで増えた。授業の品質を維持するために、GLS予備校では講師マニュアルを開発し始めた。マニュアルといっても、画一的に授業を進めるのが目的ではない。教師の作業の中からルール化すべき点を切り出し、それ以外のところは生徒の状況に合わせて教師が臨機応変に対応できるようにするためである。
例えば、報告書などに書き込む内容や判断の基準はマニュアル化し、機械的に書けるようにした。これにより教師の作業時間が短縮されるだけでなく、塾長にとっても必要な情報がすぐに把握できるようになった。
有名校への合格者数より大事なもの
学習塾の効果は成績の伸びで評価されるべきだろう。多くの学習塾は有名高校や名門大学に合格した生徒の数などを前面に出して広告宣伝を行う。だが、GLS予備校は合格者数という「数字」を前面に出すことはしない。むしろ、どのような生徒が、どのように勉強し、その結果としてどこの大学に合格したかということを大事にしている。現在は出身高校と合格した大学をホームページに公表している。成績が悪かった生徒が一生懸命勉強して中堅レベルの大学に合格することは、優秀な生徒が一流大学に合格したのと同じぐらい評価すべきこと、というわけだ。
だから、成績による選抜を行って、成績のいい生徒だけを集めることもしない。にもかかわらず、これまでの卒業生はほぼ全員が、最低でもMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法制大学)レベルの大学に合格している。
原田塾長はこれまでに蓄積したノウハウを全国に広めるために、福岡県にある通信制の学習塾の未来研究所と提携し、2011年12月からはそこの社員にもなった。そこでは教務全般を担当し、通信教育でも勉強の作法を効率的に身に着けられるよう、教え方のマニュアル開発を行っている。原田塾長が目指す教育改革はこれからが本番だ。
http://
高齢化が進む前は少子化が先行することから、とりわけ14才までの年少人口の減少が著しい。年少人口は当然のことながら、大半が学校に通う子供たちで構成されており、その減少が教育産業に大きな影響を与えることは容易に想像できる。
教育産業は幅広い。学習塾や予備校、専門学校、語学学校等だけでなく、料理教室やカルチャースクール、通信教育会社も含まれる。中でも、特に年少人口激減の影響を受けていると考えられるのが学習塾である。
ところが、経済産業省が実施している特定サービス産業動態統計調査によると、人口減少に相反してその市場規模は増加している。人口1人当たりの支出額は増加しており、一見すると学習塾が成長産業のようにも思える。
一方で、売り上げの増加以上に増えているのが学習塾数と講師数である。そのため、塾当たりの売上は市場全体の売り上げの動向と減少し続けている。また、講師1人当たりの売り上げも右肩下がりになっている。これは学習塾が、経済環境がより厳しいほかの業種の雇用の受け皿になっていることを意味している。しかし、市場規模の拡大以上に新規参入が続けば、ほかのサービス産業が直面しているように、学習塾も激しい低価格競争に襲われることは容易に想像することができる。
今回紹介するのは、激しい競争が繰り広げられているこの業界において、これまでにない指導方法で支持を集め、教育界の改革まで目指しているGLS予備校(東京都目黒区)である。
教育改革を実現するために学習塾を開く
GLS予備校は2005年、原田将孝塾長がまだ大学4年の時に開校した新しい学習塾である。教室は東京都目黒区に1つしかない。そこに中学生と高校生・浪人生が学び、高校受験と大学受験のために日夜、勉強に励んでいる。
原田塾長は自らの体験を通じて教育分野に多くの問題があると感じていた。何か新しい方法論が必要だと学生時代から考え、一時期は文部科学省で働くことや、学校や予備校に就職することも考えた。しかし文部科学省は現場から遠く、学校や予備校は組織が大きい。特に学校には様々な制約があり、制度などの改革が難しいと感じていた。一方、学習塾には部活動や生活指導がない。教えることだけに専念でき、教育分野で一番制約が少ないことから「GLS予備校」を自ら開校。民間の立場で教育改革に取り組み始めた。
2012年4月10日(火)
http://
原田塾長は「どうしたら成績が伸びるのか。そのノウハウすらない」と憤慨する。つまり、政策や制度の前に、教育方法の確立がそもそもできていない、ということである。学校や塾のような組織の中では、一人ひとりの講師は特定の教科しか教えることができない。教育の効果という観点から見ると、ここに根本的な問題がある。
例えば、英語ができない子供に英語を丁寧に教え続けてもダメなことがあるという。そのような子供は英語の前に国語ができないからだ。社会も同じである。子供によっては、国語ができないために教科書の漢字や表現が難しく、そもそもそこに書かれていることが理解できず、成績が改善しない。だから、そのような子供には国語力を徹底的に付けていかなければならない。同じように、理科が分からない子供の多くは数学ができない。基礎的な数学を理解していない子供に、どんなに物理を教えても成績を伸ばすことができない。この場合は、まず数学の基礎力を付けるところから始めなければならない。これが原田塾長の問題意識だ。
今の学校や塾は多くの生徒を効率的に教えるため、科目を分断している。それぞれの教師には特定の科目を教える権限しか与えられておらず、その仕組みを変えることも難しい。自ら学習塾を開校した原田塾長は、そのトップとして、まず教育方法のノウハウ化に取り組み始めた。
2005年の開校から約6年間は、6畳間の小さな教室で全教科の授業を原田塾長1人で受け持った。生徒数が増えため、2010年11月により大きな教室に引っ越し、今は講師数6人、生徒数は40人強までになった。
問題を解けたかだけなく、解答のプロセスを問う
授業の進め方は独特である。何しろ時間割がない。
GLS予備校は1対多人数の授業ではなく、基本的に1対1の個別指導で授業を進めていく自習型の塾である。しかしその方法は、個別指導型の多くの塾のように小さなブースで1人の教師が1人の生徒に教えるものではない。机と椅子が普通に置かれたオープンな教室に生徒たちは並んで座り、講師が個別指導を行う。まとめて多くの生徒に教えることがないので、教室に黒板はない。
生徒4〜5人に対し1人の講師が教室に入る。もし生徒数が7〜8人であれば教師を2人にする。10人を超えれば3人が入る。授業は一人ひとりの生徒に合わせて個別に進められるので、実際の授業は数名の講師が数名の生徒に教えるチーム指導という方法をとる。だから同じ教室には中学1年生から高校3年生までの様々な学年の生徒が一緒に勉強する。
講師達は一人ひとりの生徒に、いずれかの科目の問題を解いてもらう。国語であれば、知っている言葉や、語彙の意味などを問う。これは語彙力の不足が原因となり、他教科の成績の足を引っ張るからである。また、実際に文章を読ませ、問題を解けたかどうかだけでなく、文章の内容を説明してもらう。英語であれば文章の構造がどれだけ理解できているかを確認する。数学であればグラフを正確に書くことができ、また解答へのプロセスが論理的に説明できるかどうかも見る。
英語や国語の語彙力は知識量であり、そのための暗記力が必要になる。この力がなければ、同じ能力が求められる社会もできない。逆に英語や国語ができるのに社会の成績が悪いのはただ単に勉強が足りないだけでなく、頭の中で全体の大まか流れを論理的にイメージできないまま用語だけを暗記しているためである。同じように古文も単語の語彙力とともに、文法がどれだけ頭に入っているかどうかで決まる。
このようにGLS予備校では、単に解答の○×だけでなく思考のプロセスまで確認し、論理的な思考力や暗記力といった基礎学力を見る。子供は分かりやすい授業を受けると分かった気になるが、自分で人に説明できないことも多く、後で同じ問題を解かせてもできないことも多い。成績が良い子供は、無意識に分かったことを復唱し、それまで勉強したことを自分の中で組み立てている。逆に勉強ができない子供は授業の内容を聞いただけで、何も身に着いていないから説明もできず、成績も良くならないという。
だから、勉強の内容を教える前に、「どのように勉強しているか」という学習の作法がどれだけ身についているかを確認する。これまでの学校や塾と比較した時、GLS予備校は勉強そのものではなく、「勉強のやり方」という作法を教える点に大きな特徴がある。
目の前のテストの点数を上げるだけなら、教師が一生懸命教えればよいだろう。だが、それでは子供のためにならない。生徒が自分で勉強するようになるためには、勉強の作法を身に着け、物事をきちんと理解して論理的に説明できる思考回路を持つことが必要だと原田塾長は考える。
そのため、教え方は生徒ごとに変える。授業はどのような内容の勉強が必要なのかを細かくチェックしながら進めていく。生徒には実際に自分で勉強してもらい、できていないところは「勉強の仕方」のお手本を見せる。そして、正しいお手本が身に着くまで何度も反復させながら習慣にしていく。勉強の作法は「癖のようなもの」と原田塾長は言う。間違った勉強の仕方で長くやってきた子供はどうしても時間がかかる。逆に学年が低ければ低いほど、早く癖を抜くことができるという。
1回3時間という長時間授業の理由
授業は1回3時間。一般の塾に比べて授業時間が長いのは、考える時間、復習する時間を十分に確保して、「勉強の作法」を身に着けるためである。多くの塾では1時間から1時間30分だが、これでは教師が一方的にしゃべるだけで授業は終わってしまい、きめの細かい指導はできない。生徒の状況に合わせて3時間の中で複数の科目を教える。だから、決められた時間割はない。
1対1の個別指導は丁寧な教育ができるように思えるが、問題点もある。授業を講師1人の能力に依存するだけでなく、どのような教え方をしているのかを管理することもできない。講師と生徒の2人だけで授業が完結してしまい、外部から客観的に評価することができないのだ。
GLS予備校では複数名の講師を配置するチーム指導を行うことでこの問題を解決している。チーム指導により、講師と生徒の相性や教え方の良し悪しをより効率的に判断でき、1人の生徒をより多面的に見ることもできる。新人の講師をベテランの講師の見習いとして配置することで、講師の育成も効率的に行うことができる。何かあれば複数の講師が相談してより良い方法で対応することもできる。
勉強の作法をどれだけ修得ができているかは、毎回の授業でチェックし、あるレベルに到達しなければ次に進まないようにしている。達成率は講師が毎月数値化して報告書にまとめている。チーム指導は利点が多い一方、責任の所在が曖昧になる面もある。そのため、個々の生徒にはチーム指導を行うものの、担任制も設け、担任がほかの教師からの情報を集約して報告書を書くようにしている。
現在は講師が6人にまで増えた。授業の品質を維持するために、GLS予備校では講師マニュアルを開発し始めた。マニュアルといっても、画一的に授業を進めるのが目的ではない。教師の作業の中からルール化すべき点を切り出し、それ以外のところは生徒の状況に合わせて教師が臨機応変に対応できるようにするためである。
例えば、報告書などに書き込む内容や判断の基準はマニュアル化し、機械的に書けるようにした。これにより教師の作業時間が短縮されるだけでなく、塾長にとっても必要な情報がすぐに把握できるようになった。
有名校への合格者数より大事なもの
学習塾の効果は成績の伸びで評価されるべきだろう。多くの学習塾は有名高校や名門大学に合格した生徒の数などを前面に出して広告宣伝を行う。だが、GLS予備校は合格者数という「数字」を前面に出すことはしない。むしろ、どのような生徒が、どのように勉強し、その結果としてどこの大学に合格したかということを大事にしている。現在は出身高校と合格した大学をホームページに公表している。成績が悪かった生徒が一生懸命勉強して中堅レベルの大学に合格することは、優秀な生徒が一流大学に合格したのと同じぐらい評価すべきこと、というわけだ。
だから、成績による選抜を行って、成績のいい生徒だけを集めることもしない。にもかかわらず、これまでの卒業生はほぼ全員が、最低でもMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法制大学)レベルの大学に合格している。
原田塾長はこれまでに蓄積したノウハウを全国に広めるために、福岡県にある通信制の学習塾の未来研究所と提携し、2011年12月からはそこの社員にもなった。そこでは教務全般を担当し、通信教育でも勉強の作法を効率的に身に着けられるよう、教え方のマニュアル開発を行っている。原田塾長が目指す教育改革はこれからが本番だ。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国語・算数教室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31946人