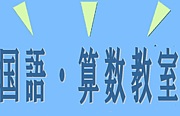どうすれば、記録を成長のエンジンへと変えることができるのか? 35万部突破の『働く君に贈る25の言葉』の著者・佐々木常夫さんと、シリーズ累計50万部突破の『人生は1冊のノートにまとめなさい』の著者・奥野宣之さんが語る、自分を見つめ直す「手帳・ノート」への向き合い方。
信頼関係を築くには、
相手の情報をメモすること
佐々木:私は仕事の効率化の両輪は、「コミュニケーション」と「信頼関係」なんだと思っています。信頼関係があると、仕事はすごく効率的なんですよね。信頼関係がないなかで上意下達でやっていても、部下はモチベーションが上がらないですよ。
だから、やっぱりマネジャーの仕事というのは、その人の能力を120%出すことにあるんです。相手に気持ちよく仕事をしてもらうということなんです。気持ちよく仕事をしてもらわないで、無理やりやらせたりしていると、効率は2割、3割落ちますよ。
それに信頼関係があると、部下は上司に提案したりすることもできるんですね。「いや、課長、それよりこうやってみたらどうでしょうか」と。これが、がなりたてるような上司だったら、部下も言われたとおりにしかやらなくなりますよね。
奥野:そうですね。信頼関係を築くには、部下や上司という以前に、ひとりの人間として興味をもつことが大事ですね。そういう考え方があれば、自然と「誕生日をメモしておこう」といった発想になってくるんだと思います。
僕の場合は、ライフログノートに行動記録を付けるタイミングで「そういえばさっきの飲み会で、あの人、○○の情報がほしいと言ってたっけ」と思いだしたりすることがよくあります。
で、ちょっと調べてメールしてあげようとか、参考になる本を送ってあげよう、となる。こういう口約束を守るのが大事だと思っています。
小さな約束でも、覚えてもらった人は必ず嬉しいものだし、ましてや、上司から誕生日のプレゼントをもらったりしたら、絶対に忘れないですよね。
佐々木:忘れませんよ。声かけてくれるだけで嬉しいですよね。打算的な話に聞こえるかもしれないけど、結局仕事をやる上でプラスになるんだから、やらないよりやった方がいいですよね。
例えば、手帳の右側に、去年の8月に「部下Aくんの父親が手術」とか書いておくんですよ。そうして「お父さん1年経ったけどどう?」って聞いてみたら、それはその部下は喜ぶよ。去年言ったうちの父のことを覚えてるんだって。家族みたいな気持ちになりますよ。
奥野:それは家族でさえ覚えていないことですね(笑)。佐々木さんのそうした部下への愛情は、先ほどお話にあった『散るぞ悲しき』にある硫黄島でゲリラ戦を指揮した名将、栗林中将に通じるものを感じます。上司の愛情が部下に伝われば、部下も頑張りますよね。
ところで、私のライフログノートと同じで、手帳にはプライベートな情報と仕事で扱う情報が全然分けずに書かれていますが、何か仕事の情報が家族の関係に役立ったりとか家族で学んだことが仕事に活かされるという面もあるんでしょうか?
佐々木:直接的にはないけれど、人は心配事がないと仕事は上手くいくというのはありますよね。だから、なるべく気になったことを溜めずに話ができるような雰囲気にできれば思っていますね。部下に悩み事があれば、それが仕事のことだろうとプレイベートなことだろうとメモしておきます。
人間ってね、嫌なこととか悩み事があっても人に言うだけで随分違うんですよね。誰か理解してくれる人がそばにいると安心するんですよね。
私は自閉症者の親の会に出て思ったんだけど、一人だと自分の子どもの将来を考えて重くなったりするけど、大勢で話し合うと「なんだ、みんな同じなんだって」思うんです。その上、自分はこうだと思っていたけどもっと簡単なやり方があったというヒントや気づきももらえるじゃないですか。
奥野:確かに、メモする効用として、「頭の中がスッキリする」というのは大きいですね。私も「自分だけのノートなんだから『何を書くべきか』なんて、かしこまらないでいいんだ」ということをよく言っています。
ちょっと聞いたこと、ちょっと気になったことでも、書いておくと、忘れる心配はなくなるし、もやもやした悩みも言葉にすると解決への見通しがつきやすい。
人間関係でも、実際はそうじゃないけど、人って勝手に嫌われているんじゃないかとか邪推しちゃいますから、メモを通して相手の言うことを素直に聞いたりとコミュニケーションを取ることは大切ですね。佐々木さんは、部下の方と飲みに行かれた時も、忘れないようにメモしたりもされるのでしょうか?
佐々木:飲みながら話すとやっぱり忘れちゃうけど、話を聞いてあげようというつもりでいれば記憶に残りますね。そして、帰る電車の中とか、次の日の朝などに、メモ用紙や手帳に書いておきます。
部下と飲みに行くときは聞こうと思っていないと、せっかくのチャンスが無駄になりますね。なるべく自分は話さないで、部下の話を聞いてあげるというスタンスで聞かないと頭に入ってこない。あいつはこんなことで悩んでるんだなというのは、仕事にも活かされますよね。自分のことだけしゃべっていたら何も収穫ないですよ。
2011年5月24日
http://
書くことは自分の立ち位置の確認
行動へのエンジンとなる
奥野:メモしたことでも、どうしたって時間がたてば次第に忘れていきますが、そこで重要になるのが、繰り返し記録して読み返すということです。私の本でも書いたのですが、自分の「行動記録」を残すという方法があります。
例えば、ライフログノートに自分のやったことをずっと時系列でメモしていると、「お酒を飲みすぎて寝坊した」といった具合に、ダメな自分の記録も頻繁に出てくるわけです。
人間は都合よく考えがちなので、同じようなミスを繰り返していてもなかなか気がつきませんが、記録して読み返し、体験をちゃんと自分のものにしていけば、そうした「やめたいけどやめられない」みたいな悪習が、嫌でも目に付くので自然とやめられる。
こういうこともあります。ノートの中の「やめたい行動」を減らして、「やりたい行動」を増やしたくなってくる。あるいは、目標達成したことを行動記録として書くと気持ちがいいので、「今日は予定通りトレーニングした」とか「ちゃんと期日までに原稿を書いた」などと記録して、自分のモチベーションをあげるという、達成感を味わうための書き方もあると思います。
佐々木さんも、記録を通した自分の盛り上げ方といった方法はお持ちでしょうか?
佐々木:直接的な答えになっていないかもしれませんが、例えば今、私は毎朝、毎夜に体重を測っているんですね。その数値を記録して壁に貼っている。これから2キロから3キロ痩せようと思ってるんですが、その目標を書くとね、書いた数字を意識して自然と体重が減ってきているんですよ。
書くことの強さというのは、きっとそこにあると思うんです。今は61.8キロだけど、先週は63キロあったから1.2キロ減ったとか、記録しておけば必ず意識に残るわけです。書いたことが、行動の一つのエンジンになるんですよ。
だから読んだ本のことを書く、出会った人のことを書くというのも、意識を高めることにつながるんです。今日会った人はこんな人だったな、こんなときにあの人に電話してみようか、助けを求めてみようかとか、書くことによっていろいろなことを考え、行動へと移すエンジンになるわけです。
奥野:体験をサッと通り過ぎていかせず、一回書くことで意識に残るようにする。そうすることで、何か問題点や解決策に気づくこともあるし、新たな行動を促すような発見にもつながる。特別なことは何もないような日常生活や雑務の中にも、前に進むヒントはいっぱいあるということですよね。
佐々木:以前、読書ノートをつけていたときに、著者と題名と出版社と読んだ印象を書いていたんですね。ある時、著者ごとに並べ替えてみたら、俺はこの作家の本をすごく読んでるなあとか、いいと思ったのにこの作家は実際はちょっとしか読んでないといったことがよくわかったんですね。
そうしたら、この作家をもっと読んでみようとか思うじゃないですか。それは書くからなんですよ。書くことによって自分の立ち位置を再認識したり、自分の進んでいく方向を確認することができるわけです。
奥野:そうした効果が生まれるためには、記録し続けて、情報を蓄積し、醸成していかないといけないですね。一日二日でなく、長い期間、自分を定点観測していくことで、「自分はこういう行動パターンがあるのか」「本当はこんなことを考えているんだな」と発見することは私もよくあります。
ところで、佐々木さんからご覧になって、今のビジネスマンは記録することはできていると思いますか?
佐々木:いやあ、ほとんどできていないと思いますね。少なくても、私の周りではあんまりやっている人はいませんね。ちょこちょこっとメモする人はいるけど、徹底して記録しようという人はあまりいませんね。
奥野:そうですね。私も体験したこと、読んだもの、聞いたことをノートを使ってライフログとして残すことをずっとやっていますが、長い期間続けていたり、些細なことでも漏らさず書いておいたり、ちょっとした紙片をとっておいたりという、ある種の徹底ぶりが大事だと実感します。
それは単なる情報ストックとしてのメモの効果を超えて、楽しく生きたり、仕事で充実感を感じるためにも大きな効果を生んでいると思います。
佐々木:みんな、記録することのメリットに気がついていないんですよ。だから、私や奥野さんの本を読んで、記録の大切さに気がついてくれるといいですね。少なくとも読者は最初から多少記録に対して意識を持っている人だから、読んだあとに行動に移しやすいですよね。
昔の手帳を読み返して
自分の成長を確認する
奥野:一家を支える立場としても、会社員としても、佐々木さんはこれまでものすごいご苦労された体験をお持ちだと思いますが、それらすべてのマイナスをプラスに変えたのは、まさに「記録の力」なんですよね。
佐々木:そうですね。毎年記録していたこの手帳は、もう20数冊になりますけど、いつもすぐそばに置いてありますよ。
奥野:20数年分の歴史ですね。今使っている手帳は読み返されたりするということでしたが、やる気を高めるために、何年の前の手帳を引っ張り出して見るといったこともあるのでしょうか?
佐々木:ありますね。人間がすごくモチベーションが上がる時というのは、自分で成長を実感したときなんですね。
例えば、10年前の手帳を見るとね、俺は10年前、こんな程度だったなというのがわかるんですね。ですから、昔の手帳を見返すというのは結構いいことがあるんですよ。
奥野:具体的にどういう進歩を実感されたりしているんでしょうか?
佐々木:10年前に手帳に記録しておいた、いいなあと思った本の感心したフレーズなんかは、改めて見るとなんでこんなものに感動したのかわからないということがありますね。
それは、自分が成長したからそう感じるんだと思うんです。その時は感動ものだと思って書いたつもりが、後から見ると大したことないと気がつくとのは、やっぱり成長した証じゃないですか。
奥野:ちょっと違うかもしれませんが、私も選挙とかがあると、やっぱり感想を書いておくんですよ。民主党が勝ったときも、これで政治はたぶんこうなるみたいなことを書いてるんですが、後で見返すとすごく一過性のもので感動したり、大騒ぎしたりしてるなというのがよくわかります。
それは、記録していないと決してわからないことですね。自分の軌跡が「見える化」されるというか。
節目に手帳と向き合い
「自分の棚卸し」をする
佐々木:みんな気がつかないですね。私は節目節目に「棚卸し」をしようと言っているんですよ。「自分の棚卸し」ですね。会社に入る時や学校を卒業した時、あるいは30歳になった時、40歳になった時、職場が変った時などの節目に自分を見つめ直して、自分が今いるポジションを確認するということをやってみようと、いつも部下には言ってるんですよ。
誰もが振り返ったりするんだけど、人間は連続性の中に生きてるから、みんな振り返り方がいい加減ですね。でも、自分はどこまで来たか、自分は何者であるか、何をしたいのか、自分は何になりたいのかということを考えるのは極めて重要ですよ。自分の立ち位置を確認するには、昔の手帳や日記を見返してみることがやっぱり有効ですね。
奥野:佐々木さんは、これまで6度も転勤をされていて、節目もいっぱいあったと思うんですが、手帳を読み返したりされたんでしょうか?
佐々木:転勤は大きな節目だからね。手帳と向き合って、その職場に着任すると、そこで何をやるかを2カ月以内に決めちゃうんです。簡単なことなのに、みんな手帳を見返すということはやらないですね。
奥野:普通の人より目標設定の見直しの機会は多かったんですね。そうした記録がすべて残っていたら、また次の目標設定に生かせるし、強力な成長のエンジンになりますね。他にも手帳の使い方で工夫されていることってありますでしょうか。
佐々木:例えば、年末になると、新年に使う手帳にお気に入りのフレーズなどを書き写したりしますが、そこで書き写すものと、書き写さないものを区別するということがありますね。
書き写さないものは、もう暗記してしまったとか、もう重要な言葉に感じないといった理由で不要になるわけです。今の自分のフィルターを通して選別することによって、成長を実感するという効果があるんです。
これから人生の記録を
始める人へのメッセージ
奥野:最後に、これから人生の記録やライフログを始めようという方に、ぜひメッセージとアドバイスをお願いします。
佐々木:私が一番大事だと思うのは、志を持つということです。自分を成長させたいとか、世のため人のために尽くしたいとか、いろんな志がありますが、そういう気持ちがあれば、記録の方法はきっと後からついてくるんです。
私は本でも、「自分を大切にすること」だと言っているんですが、自分を大切にしようと思ったら、人のため、世のためにやらなきゃいけなくなる。それをやると必ずリターンが返ってくる。私が部下のことをとことん面倒見てやると、部下は私を信頼していろいろ提案してくれたり、アドバイスもしてくれたりするんです。
だから、自分を大切にする気持ちが強ければ強いほど人を大切にし、もっと自分を伸ばしていこうという気持ちも生じるわけです。ノートや手帳を上手に使うというのはスキルの問題ですが、その下には流れているのは、「自分を大切にする」という気持ちなんです。
奥野:なるほど、ノートや手帳に記録するということには、「こうすれば、こうなる」的なノウハウ以上のものがあるわけですね。体験を使い捨てにせずとっておくことは、自分を大切にするという考え方につながり、自分を大切にしようとすれば、おのずと仕事で成果を上げたり、まわりの人や社会のために働くようになる、と。
数々の危機を乗り越えてきた佐々木さんの記録への考え方、よくわかりました。本当にありがとうございました。
(2011年4月12日収録)
http://
信頼関係を築くには、
相手の情報をメモすること
佐々木:私は仕事の効率化の両輪は、「コミュニケーション」と「信頼関係」なんだと思っています。信頼関係があると、仕事はすごく効率的なんですよね。信頼関係がないなかで上意下達でやっていても、部下はモチベーションが上がらないですよ。
だから、やっぱりマネジャーの仕事というのは、その人の能力を120%出すことにあるんです。相手に気持ちよく仕事をしてもらうということなんです。気持ちよく仕事をしてもらわないで、無理やりやらせたりしていると、効率は2割、3割落ちますよ。
それに信頼関係があると、部下は上司に提案したりすることもできるんですね。「いや、課長、それよりこうやってみたらどうでしょうか」と。これが、がなりたてるような上司だったら、部下も言われたとおりにしかやらなくなりますよね。
奥野:そうですね。信頼関係を築くには、部下や上司という以前に、ひとりの人間として興味をもつことが大事ですね。そういう考え方があれば、自然と「誕生日をメモしておこう」といった発想になってくるんだと思います。
僕の場合は、ライフログノートに行動記録を付けるタイミングで「そういえばさっきの飲み会で、あの人、○○の情報がほしいと言ってたっけ」と思いだしたりすることがよくあります。
で、ちょっと調べてメールしてあげようとか、参考になる本を送ってあげよう、となる。こういう口約束を守るのが大事だと思っています。
小さな約束でも、覚えてもらった人は必ず嬉しいものだし、ましてや、上司から誕生日のプレゼントをもらったりしたら、絶対に忘れないですよね。
佐々木:忘れませんよ。声かけてくれるだけで嬉しいですよね。打算的な話に聞こえるかもしれないけど、結局仕事をやる上でプラスになるんだから、やらないよりやった方がいいですよね。
例えば、手帳の右側に、去年の8月に「部下Aくんの父親が手術」とか書いておくんですよ。そうして「お父さん1年経ったけどどう?」って聞いてみたら、それはその部下は喜ぶよ。去年言ったうちの父のことを覚えてるんだって。家族みたいな気持ちになりますよ。
奥野:それは家族でさえ覚えていないことですね(笑)。佐々木さんのそうした部下への愛情は、先ほどお話にあった『散るぞ悲しき』にある硫黄島でゲリラ戦を指揮した名将、栗林中将に通じるものを感じます。上司の愛情が部下に伝われば、部下も頑張りますよね。
ところで、私のライフログノートと同じで、手帳にはプライベートな情報と仕事で扱う情報が全然分けずに書かれていますが、何か仕事の情報が家族の関係に役立ったりとか家族で学んだことが仕事に活かされるという面もあるんでしょうか?
佐々木:直接的にはないけれど、人は心配事がないと仕事は上手くいくというのはありますよね。だから、なるべく気になったことを溜めずに話ができるような雰囲気にできれば思っていますね。部下に悩み事があれば、それが仕事のことだろうとプレイベートなことだろうとメモしておきます。
人間ってね、嫌なこととか悩み事があっても人に言うだけで随分違うんですよね。誰か理解してくれる人がそばにいると安心するんですよね。
私は自閉症者の親の会に出て思ったんだけど、一人だと自分の子どもの将来を考えて重くなったりするけど、大勢で話し合うと「なんだ、みんな同じなんだって」思うんです。その上、自分はこうだと思っていたけどもっと簡単なやり方があったというヒントや気づきももらえるじゃないですか。
奥野:確かに、メモする効用として、「頭の中がスッキリする」というのは大きいですね。私も「自分だけのノートなんだから『何を書くべきか』なんて、かしこまらないでいいんだ」ということをよく言っています。
ちょっと聞いたこと、ちょっと気になったことでも、書いておくと、忘れる心配はなくなるし、もやもやした悩みも言葉にすると解決への見通しがつきやすい。
人間関係でも、実際はそうじゃないけど、人って勝手に嫌われているんじゃないかとか邪推しちゃいますから、メモを通して相手の言うことを素直に聞いたりとコミュニケーションを取ることは大切ですね。佐々木さんは、部下の方と飲みに行かれた時も、忘れないようにメモしたりもされるのでしょうか?
佐々木:飲みながら話すとやっぱり忘れちゃうけど、話を聞いてあげようというつもりでいれば記憶に残りますね。そして、帰る電車の中とか、次の日の朝などに、メモ用紙や手帳に書いておきます。
部下と飲みに行くときは聞こうと思っていないと、せっかくのチャンスが無駄になりますね。なるべく自分は話さないで、部下の話を聞いてあげるというスタンスで聞かないと頭に入ってこない。あいつはこんなことで悩んでるんだなというのは、仕事にも活かされますよね。自分のことだけしゃべっていたら何も収穫ないですよ。
2011年5月24日
http://
書くことは自分の立ち位置の確認
行動へのエンジンとなる
奥野:メモしたことでも、どうしたって時間がたてば次第に忘れていきますが、そこで重要になるのが、繰り返し記録して読み返すということです。私の本でも書いたのですが、自分の「行動記録」を残すという方法があります。
例えば、ライフログノートに自分のやったことをずっと時系列でメモしていると、「お酒を飲みすぎて寝坊した」といった具合に、ダメな自分の記録も頻繁に出てくるわけです。
人間は都合よく考えがちなので、同じようなミスを繰り返していてもなかなか気がつきませんが、記録して読み返し、体験をちゃんと自分のものにしていけば、そうした「やめたいけどやめられない」みたいな悪習が、嫌でも目に付くので自然とやめられる。
こういうこともあります。ノートの中の「やめたい行動」を減らして、「やりたい行動」を増やしたくなってくる。あるいは、目標達成したことを行動記録として書くと気持ちがいいので、「今日は予定通りトレーニングした」とか「ちゃんと期日までに原稿を書いた」などと記録して、自分のモチベーションをあげるという、達成感を味わうための書き方もあると思います。
佐々木さんも、記録を通した自分の盛り上げ方といった方法はお持ちでしょうか?
佐々木:直接的な答えになっていないかもしれませんが、例えば今、私は毎朝、毎夜に体重を測っているんですね。その数値を記録して壁に貼っている。これから2キロから3キロ痩せようと思ってるんですが、その目標を書くとね、書いた数字を意識して自然と体重が減ってきているんですよ。
書くことの強さというのは、きっとそこにあると思うんです。今は61.8キロだけど、先週は63キロあったから1.2キロ減ったとか、記録しておけば必ず意識に残るわけです。書いたことが、行動の一つのエンジンになるんですよ。
だから読んだ本のことを書く、出会った人のことを書くというのも、意識を高めることにつながるんです。今日会った人はこんな人だったな、こんなときにあの人に電話してみようか、助けを求めてみようかとか、書くことによっていろいろなことを考え、行動へと移すエンジンになるわけです。
奥野:体験をサッと通り過ぎていかせず、一回書くことで意識に残るようにする。そうすることで、何か問題点や解決策に気づくこともあるし、新たな行動を促すような発見にもつながる。特別なことは何もないような日常生活や雑務の中にも、前に進むヒントはいっぱいあるということですよね。
佐々木:以前、読書ノートをつけていたときに、著者と題名と出版社と読んだ印象を書いていたんですね。ある時、著者ごとに並べ替えてみたら、俺はこの作家の本をすごく読んでるなあとか、いいと思ったのにこの作家は実際はちょっとしか読んでないといったことがよくわかったんですね。
そうしたら、この作家をもっと読んでみようとか思うじゃないですか。それは書くからなんですよ。書くことによって自分の立ち位置を再認識したり、自分の進んでいく方向を確認することができるわけです。
奥野:そうした効果が生まれるためには、記録し続けて、情報を蓄積し、醸成していかないといけないですね。一日二日でなく、長い期間、自分を定点観測していくことで、「自分はこういう行動パターンがあるのか」「本当はこんなことを考えているんだな」と発見することは私もよくあります。
ところで、佐々木さんからご覧になって、今のビジネスマンは記録することはできていると思いますか?
佐々木:いやあ、ほとんどできていないと思いますね。少なくても、私の周りではあんまりやっている人はいませんね。ちょこちょこっとメモする人はいるけど、徹底して記録しようという人はあまりいませんね。
奥野:そうですね。私も体験したこと、読んだもの、聞いたことをノートを使ってライフログとして残すことをずっとやっていますが、長い期間続けていたり、些細なことでも漏らさず書いておいたり、ちょっとした紙片をとっておいたりという、ある種の徹底ぶりが大事だと実感します。
それは単なる情報ストックとしてのメモの効果を超えて、楽しく生きたり、仕事で充実感を感じるためにも大きな効果を生んでいると思います。
佐々木:みんな、記録することのメリットに気がついていないんですよ。だから、私や奥野さんの本を読んで、記録の大切さに気がついてくれるといいですね。少なくとも読者は最初から多少記録に対して意識を持っている人だから、読んだあとに行動に移しやすいですよね。
昔の手帳を読み返して
自分の成長を確認する
奥野:一家を支える立場としても、会社員としても、佐々木さんはこれまでものすごいご苦労された体験をお持ちだと思いますが、それらすべてのマイナスをプラスに変えたのは、まさに「記録の力」なんですよね。
佐々木:そうですね。毎年記録していたこの手帳は、もう20数冊になりますけど、いつもすぐそばに置いてありますよ。
奥野:20数年分の歴史ですね。今使っている手帳は読み返されたりするということでしたが、やる気を高めるために、何年の前の手帳を引っ張り出して見るといったこともあるのでしょうか?
佐々木:ありますね。人間がすごくモチベーションが上がる時というのは、自分で成長を実感したときなんですね。
例えば、10年前の手帳を見るとね、俺は10年前、こんな程度だったなというのがわかるんですね。ですから、昔の手帳を見返すというのは結構いいことがあるんですよ。
奥野:具体的にどういう進歩を実感されたりしているんでしょうか?
佐々木:10年前に手帳に記録しておいた、いいなあと思った本の感心したフレーズなんかは、改めて見るとなんでこんなものに感動したのかわからないということがありますね。
それは、自分が成長したからそう感じるんだと思うんです。その時は感動ものだと思って書いたつもりが、後から見ると大したことないと気がつくとのは、やっぱり成長した証じゃないですか。
奥野:ちょっと違うかもしれませんが、私も選挙とかがあると、やっぱり感想を書いておくんですよ。民主党が勝ったときも、これで政治はたぶんこうなるみたいなことを書いてるんですが、後で見返すとすごく一過性のもので感動したり、大騒ぎしたりしてるなというのがよくわかります。
それは、記録していないと決してわからないことですね。自分の軌跡が「見える化」されるというか。
節目に手帳と向き合い
「自分の棚卸し」をする
佐々木:みんな気がつかないですね。私は節目節目に「棚卸し」をしようと言っているんですよ。「自分の棚卸し」ですね。会社に入る時や学校を卒業した時、あるいは30歳になった時、40歳になった時、職場が変った時などの節目に自分を見つめ直して、自分が今いるポジションを確認するということをやってみようと、いつも部下には言ってるんですよ。
誰もが振り返ったりするんだけど、人間は連続性の中に生きてるから、みんな振り返り方がいい加減ですね。でも、自分はどこまで来たか、自分は何者であるか、何をしたいのか、自分は何になりたいのかということを考えるのは極めて重要ですよ。自分の立ち位置を確認するには、昔の手帳や日記を見返してみることがやっぱり有効ですね。
奥野:佐々木さんは、これまで6度も転勤をされていて、節目もいっぱいあったと思うんですが、手帳を読み返したりされたんでしょうか?
佐々木:転勤は大きな節目だからね。手帳と向き合って、その職場に着任すると、そこで何をやるかを2カ月以内に決めちゃうんです。簡単なことなのに、みんな手帳を見返すということはやらないですね。
奥野:普通の人より目標設定の見直しの機会は多かったんですね。そうした記録がすべて残っていたら、また次の目標設定に生かせるし、強力な成長のエンジンになりますね。他にも手帳の使い方で工夫されていることってありますでしょうか。
佐々木:例えば、年末になると、新年に使う手帳にお気に入りのフレーズなどを書き写したりしますが、そこで書き写すものと、書き写さないものを区別するということがありますね。
書き写さないものは、もう暗記してしまったとか、もう重要な言葉に感じないといった理由で不要になるわけです。今の自分のフィルターを通して選別することによって、成長を実感するという効果があるんです。
これから人生の記録を
始める人へのメッセージ
奥野:最後に、これから人生の記録やライフログを始めようという方に、ぜひメッセージとアドバイスをお願いします。
佐々木:私が一番大事だと思うのは、志を持つということです。自分を成長させたいとか、世のため人のために尽くしたいとか、いろんな志がありますが、そういう気持ちがあれば、記録の方法はきっと後からついてくるんです。
私は本でも、「自分を大切にすること」だと言っているんですが、自分を大切にしようと思ったら、人のため、世のためにやらなきゃいけなくなる。それをやると必ずリターンが返ってくる。私が部下のことをとことん面倒見てやると、部下は私を信頼していろいろ提案してくれたり、アドバイスもしてくれたりするんです。
だから、自分を大切にする気持ちが強ければ強いほど人を大切にし、もっと自分を伸ばしていこうという気持ちも生じるわけです。ノートや手帳を上手に使うというのはスキルの問題ですが、その下には流れているのは、「自分を大切にする」という気持ちなんです。
奥野:なるほど、ノートや手帳に記録するということには、「こうすれば、こうなる」的なノウハウ以上のものがあるわけですね。体験を使い捨てにせずとっておくことは、自分を大切にするという考え方につながり、自分を大切にしようとすれば、おのずと仕事で成果を上げたり、まわりの人や社会のために働くようになる、と。
数々の危機を乗り越えてきた佐々木さんの記録への考え方、よくわかりました。本当にありがとうございました。
(2011年4月12日収録)
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国語・算数教室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208324人
- 3位
- 酒好き
- 170697人