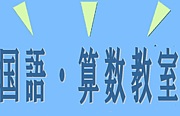なぜ、書くことが大切なのか? 記録にはどんな意味があるのか? 35万部突破の『働く君に贈る25の言葉』の著者・佐々木常夫さんと、シリーズ累計50万部突破の『人生は1冊のノートにまとめなさい』の著者・奥野宣之さんが語る、人生をマネジメントする「積極的メモ」のすすめ。
書くと問題の原因が見えてくる
よい習慣は才能を超える
奥野:佐々木さんはご著書『働く君に贈る25の言葉』の中でも記録の大切さについて書かれていますが、そもそも、記録を意識するようになったきっかけは何だったのでしょうか。
佐々木:きっかけは大学での講義のメモですね。私は先生が言ったことをほとんど書いていたんですが、誰よりも多く書くものだから、試験前になるとそのノートはみんなから引っ張りだこになっていたんです。
奥野:それはすごいですね。僕が今でこそ「ライフログノート」という習慣を持っているけれど、学生時代、ほとんどノートを取らなかったのとは対称的ですね。
「ほとんど書いていた」とは、あとで読み返してもわかるように、授業をそのままノートに再現していたということでしょうか?
佐々木:そうですね。それでメモすることの重要さに気づいて、会社に入ったあとも積極的にメモを取るようになりました。打ち合わせをしている時も、相手が話したことはほとんど全部書いていましたね。
メモすることに対して問題意識を持ったのは、社会人になって数年たったときかな。仕事で上手くいかないことがあったり、ミスしたりすると、上から怒られるじゃないですか。その時に、怒られたことをメモして、なぜそういうことが起きたのかを反省しようと思ったのがきっかけです。
奥野:私も『人生は1冊のノートにまとめなさい』という本に、「体験の使い捨てをしない」という言い方で、そうしたミスや反省を積極的に記録しておくように書いたのですが、佐々木さんも、メモすることで、同じ失敗を繰り返さないように、なぜミスが起こったのかを分析したり、次はどうすればいいのかを考えるようにするということでしょうか?
佐々木:書いてみると、原因がよくわかるんです。ノートを読み返せば反省も倍になるからですね。単に反省しているだけだとすぐに忘れてしまって身に付きませんが、書くと覚える。覚えると使う。使うと身に付くという好循環が生まれるんです。
奥野:記録と改善の好循環については、ご著書の『働く君に贈る25の言葉』でも書かれていましたね。
私も本の中で、まずは何を食べたのか、何時に寝たのかといったことから積極的にメモすること、次に、記憶のカギになるようなものを貼っておくこと、そして書いたものをあとで読み返すことの3つの重要性を主張したのですが、読者の方からは、なかなか日常的に記録したり参照したりするのは難しいと言われたりもします。どうすれば続けられるのでしょうか?
佐々木:慣れですよ。なんでも習慣になればなんてことない。今までほとんどメモしたことのない人が書けと言われても、それは大変だと思うかもしれないけど、慣れちゃうと別になんてことないです。書くことに慣れるかどうかの問題だと思います。
奥野:まずは、ああだこうだと考えずにとにかくやってみて、書くことをあたりまえの習慣にするしかないということでしょうか?
佐々木:そうですね。『働く君に贈る25の言葉』という本にも書きましたが、「よい習慣は才能を超える」ということなんです。メモを取ることが習慣になれば、別に苦痛でもなんでもないんです。習慣になれば、いいことばかりですよ。
2011年5月19日
http://
飛ばし読みは無駄ばかり!?
本はメモしながら読むと血肉化する
奥野:最初は書くより覚えておくほうがいいやと思っているような人でも、メモする習慣ができれば多くのメリットを実感すると思います。
例えば僕の場合は、スケジュールのダブルブッキングを防ぐといった実務的なことだけでなく、書くことによって「最近あんまりパッとしない感じだけれど、ちゃんと頑張ってるな」と自分を認めたり、読み返して、「自分がこんなこと考えていたのか」と気がつくことで目標を定め直したり、といったことにも役立っていると実感します。佐々木さんは、どういったメリットを感じられていますでしょうか?
佐々木:例えば、本を読むと8割や9割はすぐ忘れてしまうものです。人によっては、忘れてしまうのは気にせずたくさん読もうと言うかもしれないけど、1冊読んで1割や2割では寂しいですよね。
ところが、読んで印象に残ったことをメモすると、かなりの割合で自分の体に残るんです。だから、10冊読み飛ばしている人と比べても、2冊か3冊をしっかりメモしながら読んだほうが、実は効率がいいんですよ。
奥野:メモしながら読むほうが本の内容を血肉化できて、より知識が身に付く、行動や思考へ与える効果も大きくなる。つまり、?歩留り?がいいわけですね。
佐々木:そうそう。私はたくさん本を読み飛ばすという人はちょっと無駄なことをしてるなと思ってるんですよ。それぞれの流儀があるとは思いますが、私みたいに時間のない人間はそんなことやってたらロスが多過ぎちゃうんです。だから大事だ、いいなと思った本は、そこで学んだことをきちんとメモしておくわけです。
例えば、『プロフェッショナルマネジャー』という本はすごく感動して、目次から何から全部書きました。私のパソコンには、絶対に参考にすべき本の目次や内容が全部入っているんですよ。重要なことをきちんとメモすれば、経営論の本なら100冊も読む必要なんてなくて、2、3冊で十分です。
奥野:本を読んだら、「読みっぱなし」にするのではなく、手で書いて覚えたり、繰り返し読み返したりして身に付けることのほうが大事ですよね。
私も『読書は1冊ノートにまとめなさい』という本の中で、本の引用と自分の考えをセットにして書いておくという「ねぎま式読書ノート」を紹介しました。また、新刊の『人生は1冊のノートにまとめなさい』でも、帯をノートに貼っておいたり、電車の中で読んだ本もメモしておくほうがいいと書きました。
「何を読んでいるか」自体が、その時の自分の気持ちや状況を物語るからです。佐々木さんの場合は、具体的にどのように記録しているのでしょうか?
佐々木:私の場合は特別なやり方というほどのものはないんだけど、自分が気に入ったとか、これはためになると思った部分を書き出していくんです。
普通の本は、たぶん1割くらいしかないけど、先ほどの『プロフェッショナルマネジャー』みたいな本はね、始めから終わりまで宝物みたいな文章だから、ほとんど書き出しますよ。
奥野:そのまま抜き書きされるんでしょうか。それとも、ご自分の何か感じたことを書かれたりするんでしょうか?
佐々木:ケースバイケースですね。その本の感動のしかたによりますね。
例えば、『散るぞ悲しき』という本がありますが、あれはすごく感動したので、そのままほとんど全部抜き書きしましたよ。
成果を出すには、
仕事をとことん愛し暗記する
奥野:『働く君に贈る25の言葉』では、毎朝電車の中でメモを読み返すと書かれていますが、本のメモも読み返したりしているのでしょうか?
佐々木:電車の中で読み返すというのは、本のメモもそうなんだけど、主として仕事の関係のメモですね。若い頃というのは会社の中で覚えなきゃいけないことがたくさんありますよね。
私の場合は仕事柄、炭素繊維やプラスティックの生産や販売、開発などをやるんですが、覚えなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。ポリエステルのフィラメントの生産販売の仕事やってたときは、約400品種を全部書き出して暗記するんですよ。
奥野:400品種! ただそれでも、中には暗記せずに、その都度調べればいいんじゃないかという人もいますよね。
佐々木:暗記してた方が仕事が早いんです。上からパッと聞かれたときに、「ちょっと調べて連絡します」なんてやらなくても済みますよね。
私が営業課長をやっていた時は、自分の課の約10年分の売上利益を全部覚えていましたし、自分が売ってる全品種、月次の販売量、得意別先の数量なども暗記していました。これを覚えておくと、何か連絡するときにもかなり役に立ちますよ。
奥野:さすがにそんなことまで覚えている人なんて社内にいないですよね?
佐々木:いないです。だから周りを見ていても、他の人は探すまで時間がかかるので、私の方が断然早く処理できるんです。そうすると、上司からも頼られることになります。時々、上司から「おい、佐々木、あの件はどうなってる?」と言われても、全部暗記しているからすぐ対応できるわけです。
奥野:すごいですね。やっぱり手間はかかるけど、毎日のようにメモして、読み返して、という積み重ねをすることは、確実にメリットがあるんですね。
佐々木:自分の仕事を上手くやろうと思ったら、それぐらいの努力はしなきゃいけないですよ。だから、私は「自分の仕事を愛しなさい」って繰り返し言ってるんですよ。
奥野:なるほど。自分の仕事で成果を出そうと思ったら、品種や数字もすべて覚えてしまうくらい徹底して仕事に対して興味を持っておかなければならない、と。自分の仕事を心から愛していないと、義務感だけではそこまでできませんね。
日々の記録から名言、読書メモまで
すべてのメモを手帳に一元化する
奥野:メモは、具体的にどのようにされているのでしょうか? 本の中では僕と同じで1冊の手帳に時系列で書かれているということでしたが……。
佐々木:そう、手帳にメモしています。思いついたことや日々の記録をどんどん書いていくんですね。手帳のスケジュール欄のあとにメモのページがありますが、ここに書いていきます。
例えば……(パラパラとめくって)、「2008年日本の10大ニュース」「世界の10大ニュース」なんていうのも書いていますね。
奥野:10大ニュース! 私もまったく同じことをやっているので、びっくりしました(笑)。『知的生産ワークアウト』という本に書きましたが、自分の10大ニュースも作って、年末になると一年のとりまとめと来年の目標を立てるんです。
佐々木:そうなんですね(笑)。この年の手帳には、官公庁の審議会の委員をやっていたものだから、旅行の消費額とかも書いていますね。だいたい時系列に書いています。
それから、気に入った言葉も書いていますね。「天の時、地の利、人の和」とか、「正面の理、側面の情、背面の恐怖」とかね。
俳句も書いてありますね。「のどけさや 願うことなき 初詣」。これは、85歳のおばあちゃんが書いた句で、もう90歳に近いものだから、願うこともないほどのどかという状態ですね。きっと、そのときにグッときた俳句ですね。
「企業の盛衰は人が制し、人こそ企業の未来を開く」。これは私が働いていた東レの研修センターの前に貼ってある記念碑の言葉ですね。
奥野:本だけに限らず、いろんなところで気になった言葉をメモしているんですね。
佐々木:そうですね。本の引用もありますよ。(手帳を見ながら)これは先ほどの『散るぞ悲しき』を読んだ時のメモですね。「国のため重き勤めを果たし得で、矢弾尽き果て散るぞかなしき」って。これはこの頃暗記してたんですよ。
観た映画のこととか、ジョンソン・エンド・ジョンソンのタイレノール事件のことなんかも書いていますね。とにかく何でも書くんです。仕事のメモは前から書いて、それ以外のメモは後ろから書いていく。ずっと書き続けていくと、最後にぶつかるという感じですね。これを通勤中の電車の中で開いて、片っ端から暗記していくわけです。
仕事もプライベートも
1冊の手帳でマネジメントする
佐々木:あとは、社員の生年月日を書いていますね(笑)。これを見てね、「ああ、あの子は今月誕生日だからプレゼントを買ってあげようか」と思ったり。
それから、家内と子どもが飲んでいる薬の名前とか、私も花粉症だから自分が飲んでいる薬も書いていますね。バスの時刻表も書いているなあ。もうすべてこの1冊の手帳に何でも書いているから、これがないと生活できないですね(笑)。
奥野:家のことや仕事のことに限らず、人付き合いや健康管理のことまで、全部書いてあるんですね。
佐々木さんの処女作『ビッグツリー』に、「私は仕事も家庭も決してあきらめない」とありましたが、この手帳がまさにそんな佐々木さんのワークライフマネージメントを象徴しているように見えます。
佐々木:昔はこの手帳と別のノートを使っていたんですけど、今はノートは使わなくなりましたね。ノートの方が圧倒的に書けるスペースがあるんですが、若い頃と比べるとメモすることも減ってきたので、今は手帳だけで十分ですね。
奥野:最初に書かれた『ビッグツリー』でも、すごく昔のご家族の手紙などの引用がされていますが、どうやってそうしたエピソードを自在に引き出してこられたのかなと驚いたんです。それは、すべて手帳に記録されていたということでしょうか?
佐々木:そうですね。あと、家族のものは宝物ですから、捨てないんです。私の家族だけだけど、実はお袋の手紙も全部ありますよ。手紙や日記はすべて残していますね。子供の手紙なんて、なかなかもらえない貴重なものですよ。
奥野:僕もそういうもらった手紙とかを全部溜めていって、「ライフログノート」と呼んでいる、日々の記録をまとめる1冊のノートに貼っていっているんです。
『人生は1冊のノートに〜』でも紹介しているんですが、例えば子供の写真や成長記録をメモしていくと、あとで本当に貴重な記録になりますね。記念になるものを貼り込んだり、そのときに思っていることを手書きで書いておくと、もう二度と訪れない大切な瞬間が、そのままリアルに残せます。
佐々木さんの場合は、やっぱりご家族を大事する、ご家族との思い出を大切にするという思想が、仕事でも社員の方の生年月日をメモするといったことにつながっているんですね。
http://
書くと問題の原因が見えてくる
よい習慣は才能を超える
奥野:佐々木さんはご著書『働く君に贈る25の言葉』の中でも記録の大切さについて書かれていますが、そもそも、記録を意識するようになったきっかけは何だったのでしょうか。
佐々木:きっかけは大学での講義のメモですね。私は先生が言ったことをほとんど書いていたんですが、誰よりも多く書くものだから、試験前になるとそのノートはみんなから引っ張りだこになっていたんです。
奥野:それはすごいですね。僕が今でこそ「ライフログノート」という習慣を持っているけれど、学生時代、ほとんどノートを取らなかったのとは対称的ですね。
「ほとんど書いていた」とは、あとで読み返してもわかるように、授業をそのままノートに再現していたということでしょうか?
佐々木:そうですね。それでメモすることの重要さに気づいて、会社に入ったあとも積極的にメモを取るようになりました。打ち合わせをしている時も、相手が話したことはほとんど全部書いていましたね。
メモすることに対して問題意識を持ったのは、社会人になって数年たったときかな。仕事で上手くいかないことがあったり、ミスしたりすると、上から怒られるじゃないですか。その時に、怒られたことをメモして、なぜそういうことが起きたのかを反省しようと思ったのがきっかけです。
奥野:私も『人生は1冊のノートにまとめなさい』という本に、「体験の使い捨てをしない」という言い方で、そうしたミスや反省を積極的に記録しておくように書いたのですが、佐々木さんも、メモすることで、同じ失敗を繰り返さないように、なぜミスが起こったのかを分析したり、次はどうすればいいのかを考えるようにするということでしょうか?
佐々木:書いてみると、原因がよくわかるんです。ノートを読み返せば反省も倍になるからですね。単に反省しているだけだとすぐに忘れてしまって身に付きませんが、書くと覚える。覚えると使う。使うと身に付くという好循環が生まれるんです。
奥野:記録と改善の好循環については、ご著書の『働く君に贈る25の言葉』でも書かれていましたね。
私も本の中で、まずは何を食べたのか、何時に寝たのかといったことから積極的にメモすること、次に、記憶のカギになるようなものを貼っておくこと、そして書いたものをあとで読み返すことの3つの重要性を主張したのですが、読者の方からは、なかなか日常的に記録したり参照したりするのは難しいと言われたりもします。どうすれば続けられるのでしょうか?
佐々木:慣れですよ。なんでも習慣になればなんてことない。今までほとんどメモしたことのない人が書けと言われても、それは大変だと思うかもしれないけど、慣れちゃうと別になんてことないです。書くことに慣れるかどうかの問題だと思います。
奥野:まずは、ああだこうだと考えずにとにかくやってみて、書くことをあたりまえの習慣にするしかないということでしょうか?
佐々木:そうですね。『働く君に贈る25の言葉』という本にも書きましたが、「よい習慣は才能を超える」ということなんです。メモを取ることが習慣になれば、別に苦痛でもなんでもないんです。習慣になれば、いいことばかりですよ。
2011年5月19日
http://
飛ばし読みは無駄ばかり!?
本はメモしながら読むと血肉化する
奥野:最初は書くより覚えておくほうがいいやと思っているような人でも、メモする習慣ができれば多くのメリットを実感すると思います。
例えば僕の場合は、スケジュールのダブルブッキングを防ぐといった実務的なことだけでなく、書くことによって「最近あんまりパッとしない感じだけれど、ちゃんと頑張ってるな」と自分を認めたり、読み返して、「自分がこんなこと考えていたのか」と気がつくことで目標を定め直したり、といったことにも役立っていると実感します。佐々木さんは、どういったメリットを感じられていますでしょうか?
佐々木:例えば、本を読むと8割や9割はすぐ忘れてしまうものです。人によっては、忘れてしまうのは気にせずたくさん読もうと言うかもしれないけど、1冊読んで1割や2割では寂しいですよね。
ところが、読んで印象に残ったことをメモすると、かなりの割合で自分の体に残るんです。だから、10冊読み飛ばしている人と比べても、2冊か3冊をしっかりメモしながら読んだほうが、実は効率がいいんですよ。
奥野:メモしながら読むほうが本の内容を血肉化できて、より知識が身に付く、行動や思考へ与える効果も大きくなる。つまり、?歩留り?がいいわけですね。
佐々木:そうそう。私はたくさん本を読み飛ばすという人はちょっと無駄なことをしてるなと思ってるんですよ。それぞれの流儀があるとは思いますが、私みたいに時間のない人間はそんなことやってたらロスが多過ぎちゃうんです。だから大事だ、いいなと思った本は、そこで学んだことをきちんとメモしておくわけです。
例えば、『プロフェッショナルマネジャー』という本はすごく感動して、目次から何から全部書きました。私のパソコンには、絶対に参考にすべき本の目次や内容が全部入っているんですよ。重要なことをきちんとメモすれば、経営論の本なら100冊も読む必要なんてなくて、2、3冊で十分です。
奥野:本を読んだら、「読みっぱなし」にするのではなく、手で書いて覚えたり、繰り返し読み返したりして身に付けることのほうが大事ですよね。
私も『読書は1冊ノートにまとめなさい』という本の中で、本の引用と自分の考えをセットにして書いておくという「ねぎま式読書ノート」を紹介しました。また、新刊の『人生は1冊のノートにまとめなさい』でも、帯をノートに貼っておいたり、電車の中で読んだ本もメモしておくほうがいいと書きました。
「何を読んでいるか」自体が、その時の自分の気持ちや状況を物語るからです。佐々木さんの場合は、具体的にどのように記録しているのでしょうか?
佐々木:私の場合は特別なやり方というほどのものはないんだけど、自分が気に入ったとか、これはためになると思った部分を書き出していくんです。
普通の本は、たぶん1割くらいしかないけど、先ほどの『プロフェッショナルマネジャー』みたいな本はね、始めから終わりまで宝物みたいな文章だから、ほとんど書き出しますよ。
奥野:そのまま抜き書きされるんでしょうか。それとも、ご自分の何か感じたことを書かれたりするんでしょうか?
佐々木:ケースバイケースですね。その本の感動のしかたによりますね。
例えば、『散るぞ悲しき』という本がありますが、あれはすごく感動したので、そのままほとんど全部抜き書きしましたよ。
成果を出すには、
仕事をとことん愛し暗記する
奥野:『働く君に贈る25の言葉』では、毎朝電車の中でメモを読み返すと書かれていますが、本のメモも読み返したりしているのでしょうか?
佐々木:電車の中で読み返すというのは、本のメモもそうなんだけど、主として仕事の関係のメモですね。若い頃というのは会社の中で覚えなきゃいけないことがたくさんありますよね。
私の場合は仕事柄、炭素繊維やプラスティックの生産や販売、開発などをやるんですが、覚えなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。ポリエステルのフィラメントの生産販売の仕事やってたときは、約400品種を全部書き出して暗記するんですよ。
奥野:400品種! ただそれでも、中には暗記せずに、その都度調べればいいんじゃないかという人もいますよね。
佐々木:暗記してた方が仕事が早いんです。上からパッと聞かれたときに、「ちょっと調べて連絡します」なんてやらなくても済みますよね。
私が営業課長をやっていた時は、自分の課の約10年分の売上利益を全部覚えていましたし、自分が売ってる全品種、月次の販売量、得意別先の数量なども暗記していました。これを覚えておくと、何か連絡するときにもかなり役に立ちますよ。
奥野:さすがにそんなことまで覚えている人なんて社内にいないですよね?
佐々木:いないです。だから周りを見ていても、他の人は探すまで時間がかかるので、私の方が断然早く処理できるんです。そうすると、上司からも頼られることになります。時々、上司から「おい、佐々木、あの件はどうなってる?」と言われても、全部暗記しているからすぐ対応できるわけです。
奥野:すごいですね。やっぱり手間はかかるけど、毎日のようにメモして、読み返して、という積み重ねをすることは、確実にメリットがあるんですね。
佐々木:自分の仕事を上手くやろうと思ったら、それぐらいの努力はしなきゃいけないですよ。だから、私は「自分の仕事を愛しなさい」って繰り返し言ってるんですよ。
奥野:なるほど。自分の仕事で成果を出そうと思ったら、品種や数字もすべて覚えてしまうくらい徹底して仕事に対して興味を持っておかなければならない、と。自分の仕事を心から愛していないと、義務感だけではそこまでできませんね。
日々の記録から名言、読書メモまで
すべてのメモを手帳に一元化する
奥野:メモは、具体的にどのようにされているのでしょうか? 本の中では僕と同じで1冊の手帳に時系列で書かれているということでしたが……。
佐々木:そう、手帳にメモしています。思いついたことや日々の記録をどんどん書いていくんですね。手帳のスケジュール欄のあとにメモのページがありますが、ここに書いていきます。
例えば……(パラパラとめくって)、「2008年日本の10大ニュース」「世界の10大ニュース」なんていうのも書いていますね。
奥野:10大ニュース! 私もまったく同じことをやっているので、びっくりしました(笑)。『知的生産ワークアウト』という本に書きましたが、自分の10大ニュースも作って、年末になると一年のとりまとめと来年の目標を立てるんです。
佐々木:そうなんですね(笑)。この年の手帳には、官公庁の審議会の委員をやっていたものだから、旅行の消費額とかも書いていますね。だいたい時系列に書いています。
それから、気に入った言葉も書いていますね。「天の時、地の利、人の和」とか、「正面の理、側面の情、背面の恐怖」とかね。
俳句も書いてありますね。「のどけさや 願うことなき 初詣」。これは、85歳のおばあちゃんが書いた句で、もう90歳に近いものだから、願うこともないほどのどかという状態ですね。きっと、そのときにグッときた俳句ですね。
「企業の盛衰は人が制し、人こそ企業の未来を開く」。これは私が働いていた東レの研修センターの前に貼ってある記念碑の言葉ですね。
奥野:本だけに限らず、いろんなところで気になった言葉をメモしているんですね。
佐々木:そうですね。本の引用もありますよ。(手帳を見ながら)これは先ほどの『散るぞ悲しき』を読んだ時のメモですね。「国のため重き勤めを果たし得で、矢弾尽き果て散るぞかなしき」って。これはこの頃暗記してたんですよ。
観た映画のこととか、ジョンソン・エンド・ジョンソンのタイレノール事件のことなんかも書いていますね。とにかく何でも書くんです。仕事のメモは前から書いて、それ以外のメモは後ろから書いていく。ずっと書き続けていくと、最後にぶつかるという感じですね。これを通勤中の電車の中で開いて、片っ端から暗記していくわけです。
仕事もプライベートも
1冊の手帳でマネジメントする
佐々木:あとは、社員の生年月日を書いていますね(笑)。これを見てね、「ああ、あの子は今月誕生日だからプレゼントを買ってあげようか」と思ったり。
それから、家内と子どもが飲んでいる薬の名前とか、私も花粉症だから自分が飲んでいる薬も書いていますね。バスの時刻表も書いているなあ。もうすべてこの1冊の手帳に何でも書いているから、これがないと生活できないですね(笑)。
奥野:家のことや仕事のことに限らず、人付き合いや健康管理のことまで、全部書いてあるんですね。
佐々木さんの処女作『ビッグツリー』に、「私は仕事も家庭も決してあきらめない」とありましたが、この手帳がまさにそんな佐々木さんのワークライフマネージメントを象徴しているように見えます。
佐々木:昔はこの手帳と別のノートを使っていたんですけど、今はノートは使わなくなりましたね。ノートの方が圧倒的に書けるスペースがあるんですが、若い頃と比べるとメモすることも減ってきたので、今は手帳だけで十分ですね。
奥野:最初に書かれた『ビッグツリー』でも、すごく昔のご家族の手紙などの引用がされていますが、どうやってそうしたエピソードを自在に引き出してこられたのかなと驚いたんです。それは、すべて手帳に記録されていたということでしょうか?
佐々木:そうですね。あと、家族のものは宝物ですから、捨てないんです。私の家族だけだけど、実はお袋の手紙も全部ありますよ。手紙や日記はすべて残していますね。子供の手紙なんて、なかなかもらえない貴重なものですよ。
奥野:僕もそういうもらった手紙とかを全部溜めていって、「ライフログノート」と呼んでいる、日々の記録をまとめる1冊のノートに貼っていっているんです。
『人生は1冊のノートに〜』でも紹介しているんですが、例えば子供の写真や成長記録をメモしていくと、あとで本当に貴重な記録になりますね。記念になるものを貼り込んだり、そのときに思っていることを手書きで書いておくと、もう二度と訪れない大切な瞬間が、そのままリアルに残せます。
佐々木さんの場合は、やっぱりご家族を大事する、ご家族との思い出を大切にするという思想が、仕事でも社員の方の生年月日をメモするといったことにつながっているんですね。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国語・算数教室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人