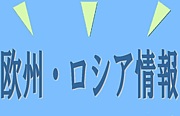政治家は落選したら「ただの人」
国民の痛みを無視できない民主主義の限界
民主主義の基本原理は多数決だ。国の政策は、多数決によって選ばれた政治家によって決められる。国会では、国民の代表者たる政治家の過半数が賛成する政策が採択され、過半数の賛同が得られない政策は採用されない。
今ここに、1つの政策があるとする。その政策は国の将来にとって必要不可欠で、しかも長い間に国民に多くのメリットをもたらす。その一方、短期で見ると多くの国民にとって痛みを伴うものだとする。果たして国民は、その政策に賛成するだろうか?
実際には、多くの国民が「ノー」という答えを出す可能性は高いだろう。おそらく国民の多くは、「今すぐに、大きな痛みを伴う政策を実行するのは避けたい。時間をかければ、きっと痛みを伴わない政策を思いつくはずだ」と主張する。
そして、「国民の負担を最小限にする政策を考案するのが政府の役目だ」というだろう。その意味では、国民は時として、わがままで、ないものねだりをする存在なのである。
それが現実の世界で起きることもある。そのため、時として、長い目で見ると避けて通れない政策が、痛みを伴うという理由で先送りされてしまうこともある。特に、その政策が一部の人たちに耐えられないような痛みを伴う場合は、なおさらだ。
政治家は選挙で当選しなければならない。「猿は木から落ちても猿だが、政治家は選挙に落ちるとただの人以下になり下がることもある」と言われるほどだ。そのため、どうしても有権者に耳触りのよい政策を前面に押し出すことになる。いわゆるポピュリズムである。
こうして政治がポピュリズムに走ると、国が危機的な状況になるまで、本当に必要な政策の実行が遅れることが考えられる。問題が深刻であればあるほど、国民は痛みを伴う解決策の実行を嫌う。結果として、ポピュリズムに走ったときの民主主義の政治体制では、経済的な危機の発生を止めることが難しくなる。
2012年1月31日
http://
あるファンドマネジャーが口にした懸念
ユーロの信用不安はポピュリズムの副産物?
最近、ロンドン在住でファンドマネジャーをしている友人が興味深いメールを送ってよこした。友人曰く、「今、ユーロ圏で起きている問題の大元を辿ると、民主主義の政治体制に行き着く」というものだ。
彼の言わんとするところは、ユーロ圏で最も多くのメリットを享受しているのはドイツだということだ。ユーロ圏諸国に関税がなく、しかも為替リスクを気にすることなく自由に輸出ができることは、ドイツ経済に大きな福音をもたらしているからだ。
そう考えると、ドイツにとって、ユーロ圏を維持することは中長期的に見て大きな利益をもたらすはずだ。そうであれば、ドイツは自国が得た利益の一部を使って、ギリシャやポルトガルを積極的に救済した方が有利になる。
ところが、ドイツ政府の姿勢は厳しく、南欧諸国の救済に消極的なスタンスを変えていない。そうしたドイツのスタンスが、ユーロ問題をここまで拡大させてきた最大の理由と考えられる。
ドイツ政府の厳しい姿勢を作っているのは、他ならぬドイツ国民の声=世論である。世論が変わらない限り、ユーロ圏の信用不安問題の本格的な解決を望むのは難しいことになる。
ということは、ある意味では「この問題の本源的な原因は、ユーロ圏、特にドイツの民主主義の政治体制にある」というのが、ファンドマネジャー氏の見解だ。
民主主義政治体制の弊害は、ユーロ圏以外にも存在する。たとえばわが国では、1990年代初頭にバブルが崩壊して以降、歴代の政府は国民に痛みが及ぶ構造改革を先延ばしする姿勢をとってきた。その結果、わが国は世界有数の財政悪化国になってしまった。
また、財政悪化にもかかわらず、民主党政権は“バラマキ”型の政策運営を続けることになっている。それもある意味では、民主主義政治体制の弊害が顕在化している現象と考えられる。
ラッセルの「民主主義論」が残した警鐘
民主主義はベストな政治体制ではない?
「民主主義は、必ずしもベストな政治体制ではない」
学生時代、バートランド・ラッセルの「民主主義論」を読んだときの印象として、今でも鮮明に脳裏に焼き付いている言葉だ。その通りだろう。
民主主義が多数決を基本原理としている以上、過半数の人が判断を誤れば適切ではない政策が実施される。さらに恐ろしいことは、過半数の人が間違った方向に走り出すと、間違った政治家に権限を与える可能性があることだ。
そうした例は、人類の歴史の中で頻繁に現れる。第一次世界大戦に敗れた後のドイツでは、ヒットラー率いるナチスドイツが圧倒的な国民の支持を得て政権を握り、第二次世界大戦へと向かってしまった。
あるいは、それとほぼ同時期に、わが国でも国民世論は軍部を支持し、結果的に大戦に至ってしまった。それを見ても、民主主義の政治体制下では常に正しいことが実行されるとは限らない。時に世論が間違えると、国自体も間違った方向に進むことはある。
ただ、長い目で見ると、国民の多くは誤りに気が付き、それを修正しようと方向転換することが期待できる。だからこそ、多数決の原理を基礎に置くことによって、長期的に見れば、民主主義の政治体制が誤りを永久に続けることはない。それが、民主主義にとって重要な“救い”になるのである。
有能な聖人君子が現れ、彼が1人で政治を取り仕切ることができれば、おそらく多数決を基本とする民主主義の政治に勝る政策運営を行なうことができるだろう。たとえ国民は痛みを感じたとしても、それが中長期的にはより多くのメリットをもたらすことを理解することができれば、おそらく短期的なデメリットを耐え忍ぶことができるはずだ。
しかし、そのような聖人君子がいつもいるとは限らない。仕方がないので、多数決の原理によって、長い目で見ると“最も間違いが続きにくい”と考えられる政治体制を選ぶ。それが、民主主義の政治体制ということになる。
ギリシャなどの国債が急落した教訓
民主主義の誤りを正す金融市場の機能
株式や為替などの金融市場には、時として大きな誤りを犯す民主主義政治体制の誤りを指摘する機能がある。
たとえば、足もとで起きているユーロ圏の信用不安問題の原因は、突き詰めて考えると、重大な構造的欠陥を持つユーロ圏の仕組みにある。
ドイツとギリシャの関係のように、大きな経済格差を持つ諸国を、単一の為替と単一の金融政策で経済運営できるはずがない。そのシステムを長期間運営しようとすれば、本来、強い経済を持つ国から、相対的に弱い経済の国への所得移転がなければ、ユーロ圏内の経済状況の均衡を図ることはできない。それは、最初から誰の目にも明らかだった。
ところが当該国の政治は、そうした要因に目をつぶって、ユーロを立ち上げることを最優先順位とした。世界経済が不動産バブルに酔っている間は、それなりの繁栄を謳歌することができた。
ところがバブルが崩壊し、大規模なバランスシート調整を行なわなければならない局面に入って、本源的な欠陥が露呈した。今まさに、それが信用不安問題となって顕在化している。
その事実を顕在化させるきっかけは、ギリシャの債務問題の表面化に伴い、国債価格が急落したことだった。ギリシャ国債などが急落したことで、国債の流通利回りが急上昇し、ギリシャやアイルランド、ポルトガル、さらにはスペインやイタリアにまで信用不安の波が押し寄せることになった。
金融市場は、ギリシャなどの国債価格を急落させることによって、ユーロ圏が抱える構造的な問題を指摘したのである。それは、民主主義の政治体制が犯しつつある誤りに、金融市場の価格メカニズムが警鐘を鳴らした行為に他ならない。
金融市場が発する警鐘を過少評価することは、適切ではない。ユーロ圏の盟主たるドイツは、その警鐘を真摯に聞く必要があるだろう。そうでないと、ユーロ圏の体制を維持することが難しくなる。
http://
国民の痛みを無視できない民主主義の限界
民主主義の基本原理は多数決だ。国の政策は、多数決によって選ばれた政治家によって決められる。国会では、国民の代表者たる政治家の過半数が賛成する政策が採択され、過半数の賛同が得られない政策は採用されない。
今ここに、1つの政策があるとする。その政策は国の将来にとって必要不可欠で、しかも長い間に国民に多くのメリットをもたらす。その一方、短期で見ると多くの国民にとって痛みを伴うものだとする。果たして国民は、その政策に賛成するだろうか?
実際には、多くの国民が「ノー」という答えを出す可能性は高いだろう。おそらく国民の多くは、「今すぐに、大きな痛みを伴う政策を実行するのは避けたい。時間をかければ、きっと痛みを伴わない政策を思いつくはずだ」と主張する。
そして、「国民の負担を最小限にする政策を考案するのが政府の役目だ」というだろう。その意味では、国民は時として、わがままで、ないものねだりをする存在なのである。
それが現実の世界で起きることもある。そのため、時として、長い目で見ると避けて通れない政策が、痛みを伴うという理由で先送りされてしまうこともある。特に、その政策が一部の人たちに耐えられないような痛みを伴う場合は、なおさらだ。
政治家は選挙で当選しなければならない。「猿は木から落ちても猿だが、政治家は選挙に落ちるとただの人以下になり下がることもある」と言われるほどだ。そのため、どうしても有権者に耳触りのよい政策を前面に押し出すことになる。いわゆるポピュリズムである。
こうして政治がポピュリズムに走ると、国が危機的な状況になるまで、本当に必要な政策の実行が遅れることが考えられる。問題が深刻であればあるほど、国民は痛みを伴う解決策の実行を嫌う。結果として、ポピュリズムに走ったときの民主主義の政治体制では、経済的な危機の発生を止めることが難しくなる。
2012年1月31日
http://
あるファンドマネジャーが口にした懸念
ユーロの信用不安はポピュリズムの副産物?
最近、ロンドン在住でファンドマネジャーをしている友人が興味深いメールを送ってよこした。友人曰く、「今、ユーロ圏で起きている問題の大元を辿ると、民主主義の政治体制に行き着く」というものだ。
彼の言わんとするところは、ユーロ圏で最も多くのメリットを享受しているのはドイツだということだ。ユーロ圏諸国に関税がなく、しかも為替リスクを気にすることなく自由に輸出ができることは、ドイツ経済に大きな福音をもたらしているからだ。
そう考えると、ドイツにとって、ユーロ圏を維持することは中長期的に見て大きな利益をもたらすはずだ。そうであれば、ドイツは自国が得た利益の一部を使って、ギリシャやポルトガルを積極的に救済した方が有利になる。
ところが、ドイツ政府の姿勢は厳しく、南欧諸国の救済に消極的なスタンスを変えていない。そうしたドイツのスタンスが、ユーロ問題をここまで拡大させてきた最大の理由と考えられる。
ドイツ政府の厳しい姿勢を作っているのは、他ならぬドイツ国民の声=世論である。世論が変わらない限り、ユーロ圏の信用不安問題の本格的な解決を望むのは難しいことになる。
ということは、ある意味では「この問題の本源的な原因は、ユーロ圏、特にドイツの民主主義の政治体制にある」というのが、ファンドマネジャー氏の見解だ。
民主主義政治体制の弊害は、ユーロ圏以外にも存在する。たとえばわが国では、1990年代初頭にバブルが崩壊して以降、歴代の政府は国民に痛みが及ぶ構造改革を先延ばしする姿勢をとってきた。その結果、わが国は世界有数の財政悪化国になってしまった。
また、財政悪化にもかかわらず、民主党政権は“バラマキ”型の政策運営を続けることになっている。それもある意味では、民主主義政治体制の弊害が顕在化している現象と考えられる。
ラッセルの「民主主義論」が残した警鐘
民主主義はベストな政治体制ではない?
「民主主義は、必ずしもベストな政治体制ではない」
学生時代、バートランド・ラッセルの「民主主義論」を読んだときの印象として、今でも鮮明に脳裏に焼き付いている言葉だ。その通りだろう。
民主主義が多数決を基本原理としている以上、過半数の人が判断を誤れば適切ではない政策が実施される。さらに恐ろしいことは、過半数の人が間違った方向に走り出すと、間違った政治家に権限を与える可能性があることだ。
そうした例は、人類の歴史の中で頻繁に現れる。第一次世界大戦に敗れた後のドイツでは、ヒットラー率いるナチスドイツが圧倒的な国民の支持を得て政権を握り、第二次世界大戦へと向かってしまった。
あるいは、それとほぼ同時期に、わが国でも国民世論は軍部を支持し、結果的に大戦に至ってしまった。それを見ても、民主主義の政治体制下では常に正しいことが実行されるとは限らない。時に世論が間違えると、国自体も間違った方向に進むことはある。
ただ、長い目で見ると、国民の多くは誤りに気が付き、それを修正しようと方向転換することが期待できる。だからこそ、多数決の原理を基礎に置くことによって、長期的に見れば、民主主義の政治体制が誤りを永久に続けることはない。それが、民主主義にとって重要な“救い”になるのである。
有能な聖人君子が現れ、彼が1人で政治を取り仕切ることができれば、おそらく多数決を基本とする民主主義の政治に勝る政策運営を行なうことができるだろう。たとえ国民は痛みを感じたとしても、それが中長期的にはより多くのメリットをもたらすことを理解することができれば、おそらく短期的なデメリットを耐え忍ぶことができるはずだ。
しかし、そのような聖人君子がいつもいるとは限らない。仕方がないので、多数決の原理によって、長い目で見ると“最も間違いが続きにくい”と考えられる政治体制を選ぶ。それが、民主主義の政治体制ということになる。
ギリシャなどの国債が急落した教訓
民主主義の誤りを正す金融市場の機能
株式や為替などの金融市場には、時として大きな誤りを犯す民主主義政治体制の誤りを指摘する機能がある。
たとえば、足もとで起きているユーロ圏の信用不安問題の原因は、突き詰めて考えると、重大な構造的欠陥を持つユーロ圏の仕組みにある。
ドイツとギリシャの関係のように、大きな経済格差を持つ諸国を、単一の為替と単一の金融政策で経済運営できるはずがない。そのシステムを長期間運営しようとすれば、本来、強い経済を持つ国から、相対的に弱い経済の国への所得移転がなければ、ユーロ圏内の経済状況の均衡を図ることはできない。それは、最初から誰の目にも明らかだった。
ところが当該国の政治は、そうした要因に目をつぶって、ユーロを立ち上げることを最優先順位とした。世界経済が不動産バブルに酔っている間は、それなりの繁栄を謳歌することができた。
ところがバブルが崩壊し、大規模なバランスシート調整を行なわなければならない局面に入って、本源的な欠陥が露呈した。今まさに、それが信用不安問題となって顕在化している。
その事実を顕在化させるきっかけは、ギリシャの債務問題の表面化に伴い、国債価格が急落したことだった。ギリシャ国債などが急落したことで、国債の流通利回りが急上昇し、ギリシャやアイルランド、ポルトガル、さらにはスペインやイタリアにまで信用不安の波が押し寄せることになった。
金融市場は、ギリシャなどの国債価格を急落させることによって、ユーロ圏が抱える構造的な問題を指摘したのである。それは、民主主義の政治体制が犯しつつある誤りに、金融市場の価格メカニズムが警鐘を鳴らした行為に他ならない。
金融市場が発する警鐘を過少評価することは、適切ではない。ユーロ圏の盟主たるドイツは、その警鐘を真摯に聞く必要があるだろう。そうでないと、ユーロ圏の体制を維持することが難しくなる。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
欧州・ロシア情報 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-