|
|
|
|
コメント(5)
通則2(a)で実際に取り扱っている商品で言えば...組み立て
前のカラーボックスや、組み立て前の自転車といったとこ
ですか?
通則3(a)はシーフードmixにヤリイカ等が入っている場合
は分離課税として扱うケース、(b)は...どういったものが
あるでしょう?
通則5(a)は...輸入した事はないですが、ヴァイオリン等の
容器は容器もヴァイオリンとして分類されるが、特別な容
器(高級な施しがしている場合)の場合は容器は容器と
して分類するということですよね。何処に分類されるか
までは調べてないので分かりませんが...(^^;)
で、(b)は...?
で、通則6は...?
ご免なさい。昨年不合格者のワタシの力ではこの辺までです。
前のカラーボックスや、組み立て前の自転車といったとこ
ですか?
通則3(a)はシーフードmixにヤリイカ等が入っている場合
は分離課税として扱うケース、(b)は...どういったものが
あるでしょう?
通則5(a)は...輸入した事はないですが、ヴァイオリン等の
容器は容器もヴァイオリンとして分類されるが、特別な容
器(高級な施しがしている場合)の場合は容器は容器と
して分類するということですよね。何処に分類されるか
までは調べてないので分かりませんが...(^^;)
で、(b)は...?
で、通則6は...?
ご免なさい。昨年不合格者のワタシの力ではこの辺までです。
自分が勉強していた頃は「部」「類」「節」の語句だけ覚えたような。取り合えず昔のテキストを引っ張りだして解説させていただきます。
通則2(b) 2つ以上の材料または物質を混合しまたは結合した物品の所属
通則2(b)は、他の材料または物質を混合しまたは結合した物品および2つ以上の材料または物質からなる物品に関するものである。この通則が適用される項は、材料または物質が記載されてある項(例05.03項の馬毛)および特定の材料または物質から成る物品であることを示す記載のある項(例45.03項の天然のコルク製品)である。この通則は、項または部もしくは類の注に別段の定めがない場合のみに適用される(例15.03項のラード油は混合していないものとさだめられているのでこの規定は適用されない)
調整品である混合物で、部もしくは類の注または項の規定にそうようなものとして記載されているものは、通則1の原則に従ってその所属を決定する。
この通則の効果は、ある材料または物質について記載した項の範囲を拡大して、各項には当該材料または物質に他の材料または物質を混合しまたは結合した物品を含む様にすることである。また同様に、この通則の効果は、特定の材料または物質から成る物品について記載した項の範囲を拡大して、各項には、部分的に当該材料または物質から成る物品を含むようにすることである。
しかしながら、この通則は、通則1の規定上項の記載に該当すると認められない物品までも含むように項の範囲を拡大するものでない。この問題は、他の材料または物質を添加することにより項に記載する種類の物品の特製が失われる場合に生ずる。
したがって、他の材料または物質を混合しまたは結合した物品および2つ以上の材料または物質から成る物品が、この通則を適用した結果、2つ以上の」項に属すると見られる場合には、通則3の原則に従って所属を決定しなければならない。
通則3(a)
所属を決定するに当たっての第1の方法は、物品について最も特殊な限定をして記載している項をこれよりも一般的な記載をしている項に優先させて適用することである。
いずれの項が他の項より特殊な限定をして物品を記載しているかを決定する上で厳密な規定を設けることは困難ではあるが、一般的には次のように考えられる。
(a)名称による限定は種類による限定よりも特殊な限定であると言える(例電動装置を自蔵するかみそりまたはバリカンは85.10項に属し、電動装置を自蔵する家庭用電気機器として85.09項に属さない)
(b)物品がより明確に同一性を確認できる項の記載に該当する場合、その項の記載は同一性の確認がより不完全な他の項の記載よりも特殊な限定をしている。
後者(b)の範疇に属する物品の例として、
(1)自動車用のものと認定できるタフト絨毯は、自動車の付属品として87.08項に属さず、絨毯としてより特殊な限定をして記載した57.03項に属する。
(2)強化ガラスまたは合わせガラスの枠付きでない安全ガラスで、特定の形状にし、飛行機用のものと認定できるものは、88.01項または88.02項の物品の部分品として88.03項には属さず、安全ガラスとしてより特殊な限定を記載した70.07項に属する。
ただし、」2つ以上の項のそれぞれが、混合もしくは結合した物品に含まれる材料もしくは物質の一部のみまたは小売り用のセットの構成要素の一部のみにつて記載をしている場合には、これらの項の内一の項が他の項に比べて一層完全なまたは詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。この場合において、物品の所属は通則3(b)または3(c)により決定するものとする。
通則3(b)
この第2の方法は通則3(a)により所属を決定することが出来ない場合にのみ適用するものとし、次の場合に限られる。
(1)混合物
(2)異なる構成材料から成る物品
(3)異なる構成要素で作られた物品
(4)小売り用のセットにした物品
これらの場合において、上記の物品は、この規定を適用することができる限り、当該物品に、重要な特性を与えている材料または構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。例えば、その材料もしくは構成要素の性質(容積、数量、重量、価格等)またはその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定することになる。
この通則の適用上、異なる構成要素で作られた物品には、当該構成要素が相互に結合し、実際上全体が分離不能となった物品のほか、分離可能な構成要素から成る物品を含む。ただし、後者の物品にあっては、当該構成要素は相互に適合性を有し、また相互に補完しあい、かつ、共に全体を構成するものであって個々の部分品として通常小売り用とならないものに限る。この後者の範疇に属する物品の例としては、次の物品がある。
(1)灰皿(取り外すことができる灰用ボールとこれを支えるスタンドから成るもの)
(2)家庭用の香辛料置き台(得別に作ったフレーム(通常木製)とフレームに適合する形状および寸法にした適当の数の香辛料用の空き瓶から成るもの)
一般にこれらの組み合わせた物品の構成要素は、一緒の包装されている。
通則5(b)
この通則は、物品を包装するために通常使用される包装材料および包装容器の所属を決定している。ただし、この規定は、明らかに反復使用に適するような包装材料および、包装容器には適用しない(例えば、圧縮ガス用または液化ガス用の金属製のドラムまたは鉄鋼性の容器)
通則6
上記通則1から5までは、同一項中の号レベルでの所属の決定について準用する。
通則6の適用に当たっては、次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「同一の水準にある号」とは、号の規定中の1段落ちの号(水準1)または2段落ちの号(水準2)をいう。
したがって、通則3(a)の文脈上、単一の項の中の二以上の1段落ちの号の内、いずれの号に該当するかを検討する場合には、問題となる物品についての特性または類似性は、競合する1段落ちの号の記載のみに基づき判断する。もっとも特殊な限定をしている1段落ちの号を選択し、かつ当該号自体に細分が設けられている場合、この場合においてのみ、2段落ちの号の内いずれの号に属するかを決定するため、2段落ちの号間の記載を考慮するものとする。
(b)「文脈により別に解釈される場合を除くほか」とは、部または類の注が号の記載または号の注と矛盾する場合以外の場合を指す。
2段落ちの号の範囲は、2段落ちの号の属する1段落ちの号の範囲を超えて拡大してはならない。また、1段落ちの号の範囲は、1段落ちの号の属する号の範囲を超えて拡大してはならない。
とあります。ご理解いただけたでしょうか? 物品の税番決定は実務でも一番頭を悩ませるところです。
分かり辛い説明で申し訳ありません。
通則2(b) 2つ以上の材料または物質を混合しまたは結合した物品の所属
通則2(b)は、他の材料または物質を混合しまたは結合した物品および2つ以上の材料または物質からなる物品に関するものである。この通則が適用される項は、材料または物質が記載されてある項(例05.03項の馬毛)および特定の材料または物質から成る物品であることを示す記載のある項(例45.03項の天然のコルク製品)である。この通則は、項または部もしくは類の注に別段の定めがない場合のみに適用される(例15.03項のラード油は混合していないものとさだめられているのでこの規定は適用されない)
調整品である混合物で、部もしくは類の注または項の規定にそうようなものとして記載されているものは、通則1の原則に従ってその所属を決定する。
この通則の効果は、ある材料または物質について記載した項の範囲を拡大して、各項には当該材料または物質に他の材料または物質を混合しまたは結合した物品を含む様にすることである。また同様に、この通則の効果は、特定の材料または物質から成る物品について記載した項の範囲を拡大して、各項には、部分的に当該材料または物質から成る物品を含むようにすることである。
しかしながら、この通則は、通則1の規定上項の記載に該当すると認められない物品までも含むように項の範囲を拡大するものでない。この問題は、他の材料または物質を添加することにより項に記載する種類の物品の特製が失われる場合に生ずる。
したがって、他の材料または物質を混合しまたは結合した物品および2つ以上の材料または物質から成る物品が、この通則を適用した結果、2つ以上の」項に属すると見られる場合には、通則3の原則に従って所属を決定しなければならない。
通則3(a)
所属を決定するに当たっての第1の方法は、物品について最も特殊な限定をして記載している項をこれよりも一般的な記載をしている項に優先させて適用することである。
いずれの項が他の項より特殊な限定をして物品を記載しているかを決定する上で厳密な規定を設けることは困難ではあるが、一般的には次のように考えられる。
(a)名称による限定は種類による限定よりも特殊な限定であると言える(例電動装置を自蔵するかみそりまたはバリカンは85.10項に属し、電動装置を自蔵する家庭用電気機器として85.09項に属さない)
(b)物品がより明確に同一性を確認できる項の記載に該当する場合、その項の記載は同一性の確認がより不完全な他の項の記載よりも特殊な限定をしている。
後者(b)の範疇に属する物品の例として、
(1)自動車用のものと認定できるタフト絨毯は、自動車の付属品として87.08項に属さず、絨毯としてより特殊な限定をして記載した57.03項に属する。
(2)強化ガラスまたは合わせガラスの枠付きでない安全ガラスで、特定の形状にし、飛行機用のものと認定できるものは、88.01項または88.02項の物品の部分品として88.03項には属さず、安全ガラスとしてより特殊な限定を記載した70.07項に属する。
ただし、」2つ以上の項のそれぞれが、混合もしくは結合した物品に含まれる材料もしくは物質の一部のみまたは小売り用のセットの構成要素の一部のみにつて記載をしている場合には、これらの項の内一の項が他の項に比べて一層完全なまたは詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。この場合において、物品の所属は通則3(b)または3(c)により決定するものとする。
通則3(b)
この第2の方法は通則3(a)により所属を決定することが出来ない場合にのみ適用するものとし、次の場合に限られる。
(1)混合物
(2)異なる構成材料から成る物品
(3)異なる構成要素で作られた物品
(4)小売り用のセットにした物品
これらの場合において、上記の物品は、この規定を適用することができる限り、当該物品に、重要な特性を与えている材料または構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。例えば、その材料もしくは構成要素の性質(容積、数量、重量、価格等)またはその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定することになる。
この通則の適用上、異なる構成要素で作られた物品には、当該構成要素が相互に結合し、実際上全体が分離不能となった物品のほか、分離可能な構成要素から成る物品を含む。ただし、後者の物品にあっては、当該構成要素は相互に適合性を有し、また相互に補完しあい、かつ、共に全体を構成するものであって個々の部分品として通常小売り用とならないものに限る。この後者の範疇に属する物品の例としては、次の物品がある。
(1)灰皿(取り外すことができる灰用ボールとこれを支えるスタンドから成るもの)
(2)家庭用の香辛料置き台(得別に作ったフレーム(通常木製)とフレームに適合する形状および寸法にした適当の数の香辛料用の空き瓶から成るもの)
一般にこれらの組み合わせた物品の構成要素は、一緒の包装されている。
通則5(b)
この通則は、物品を包装するために通常使用される包装材料および包装容器の所属を決定している。ただし、この規定は、明らかに反復使用に適するような包装材料および、包装容器には適用しない(例えば、圧縮ガス用または液化ガス用の金属製のドラムまたは鉄鋼性の容器)
通則6
上記通則1から5までは、同一項中の号レベルでの所属の決定について準用する。
通則6の適用に当たっては、次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「同一の水準にある号」とは、号の規定中の1段落ちの号(水準1)または2段落ちの号(水準2)をいう。
したがって、通則3(a)の文脈上、単一の項の中の二以上の1段落ちの号の内、いずれの号に該当するかを検討する場合には、問題となる物品についての特性または類似性は、競合する1段落ちの号の記載のみに基づき判断する。もっとも特殊な限定をしている1段落ちの号を選択し、かつ当該号自体に細分が設けられている場合、この場合においてのみ、2段落ちの号の内いずれの号に属するかを決定するため、2段落ちの号間の記載を考慮するものとする。
(b)「文脈により別に解釈される場合を除くほか」とは、部または類の注が号の記載または号の注と矛盾する場合以外の場合を指す。
2段落ちの号の範囲は、2段落ちの号の属する1段落ちの号の範囲を超えて拡大してはならない。また、1段落ちの号の範囲は、1段落ちの号の属する号の範囲を超えて拡大してはならない。
とあります。ご理解いただけたでしょうか? 物品の税番決定は実務でも一番頭を悩ませるところです。
分かり辛い説明で申し訳ありません。
実務でもとても難しいところですね。どの税番に属するかはよく税関ともめるところです。例えばこれは特殊な例ですが、プラスチック製の工具箱の場合、以前は39.26というプラスチック製品の税番で申告していましたが、「取っ手が付属していて、内部に仕切りがあるものはバッグで申告せよ」いう通達があり、それ以降は42.02で申告させられています。
税関としては少しでも関税率の高い方(39.26=3.9%、42.02=4.6%)に誘導したいのでしょう。
一般に税番は、最初に用途、次に外面の材質で決められます。繊維や木材などはそこから更に長さ、太さ、厚み等々のサイズが重要な要素となります。問題は「重要な特性を与えている材料」が半々だった場合で、例えば「上半分が金属の檻状、下半分が半透明のプラスチックで構成された鳥かご」が金属製品(その他の鉄鋼製品、73.26=関税Free)なのかプラスチック製品なのかを決定するような場合ですね。税関は明らかに有税のプラスチック製品に誘導するでしょうがそこを阻止できるかどうかが輸入者から見た「いい通関士」かどうかの判断になります。
税関としては少しでも関税率の高い方(39.26=3.9%、42.02=4.6%)に誘導したいのでしょう。
一般に税番は、最初に用途、次に外面の材質で決められます。繊維や木材などはそこから更に長さ、太さ、厚み等々のサイズが重要な要素となります。問題は「重要な特性を与えている材料」が半々だった場合で、例えば「上半分が金属の檻状、下半分が半透明のプラスチックで構成された鳥かご」が金属製品(その他の鉄鋼製品、73.26=関税Free)なのかプラスチック製品なのかを決定するような場合ですね。税関は明らかに有税のプラスチック製品に誘導するでしょうがそこを阻止できるかどうかが輸入者から見た「いい通関士」かどうかの判断になります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
通関士資格・貿易実務検定 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
通関士資格・貿易実務検定のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90014人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37150人
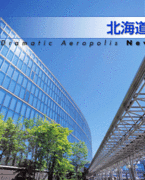


![[安・短・楽の資格取得法]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/61/79/476179_207s.jpg)




















