|
|
|
|
コメント(21)
昨年度合格者です。
最後の数年は、実務を徹底的にやったので、この分野は得意になりました。
所属の決定は、頭で考えてわかるものでもないので、覚えるしかありません。いろいろと試してみましたが、一番覚えやすいやり方は、出題されたパターンをリストアップすることだと思います。
とりあえず、自分の知っている範囲でかまわないので、このトピックにリストアップしてみてください。関税率表と照らし合わせて簡単な解説ならできると思います。
「通則1」〜「通則6」は、そのまま覚えるしかありません。
また、「関税率表の所属以外を徹底的に」というのもひとつです。
関税と加算税と課税価格の計算を何問もこなして、完璧にしておけば、所属の決定はボロボロでもなんとかなるでしょう。
最後の数年は、実務を徹底的にやったので、この分野は得意になりました。
所属の決定は、頭で考えてわかるものでもないので、覚えるしかありません。いろいろと試してみましたが、一番覚えやすいやり方は、出題されたパターンをリストアップすることだと思います。
とりあえず、自分の知っている範囲でかまわないので、このトピックにリストアップしてみてください。関税率表と照らし合わせて簡単な解説ならできると思います。
「通則1」〜「通則6」は、そのまま覚えるしかありません。
また、「関税率表の所属以外を徹底的に」というのもひとつです。
関税と加算税と課税価格の計算を何問もこなして、完璧にしておけば、所属の決定はボロボロでもなんとかなるでしょう。
ぽてとさん、アドバイスありがとうございます。
一度出た問題なら、それを覚えればいいのですが、
本試験で見たこともない内容のものが出てきたら恐怖・・・と思ってました。
例えば最近見た問題で、
第49.01項の印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する
印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。)には、本質的に
広告を目的とする出版物を含まない。
答えは○とのことですが、新聞が含まれるのに広告は含まないのか・・・
と思いました。覚えるしかありませんね。
ぽてとさんの書かれている通り、関税率表の所属の過去問を頭に入れるのと、
計算問題を完璧にする様にします。後、輸出入通関等の選択問題も完璧に
しないといけないですね!頑張るのみです。
どうもありがとうございました。
一度出た問題なら、それを覚えればいいのですが、
本試験で見たこともない内容のものが出てきたら恐怖・・・と思ってました。
例えば最近見た問題で、
第49.01項の印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する
印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。)には、本質的に
広告を目的とする出版物を含まない。
答えは○とのことですが、新聞が含まれるのに広告は含まないのか・・・
と思いました。覚えるしかありませんね。
ぽてとさんの書かれている通り、関税率表の所属の過去問を頭に入れるのと、
計算問題を完璧にする様にします。後、輸出入通関等の選択問題も完璧に
しないといけないですね!頑張るのみです。
どうもありがとうございました。
Pachacutiさん。
03類は魚・水産物(加工品以外)、
16類は動物調整品(肉・魚の加工品)
ですね。
関税率表をみたら、確かに03.06に「蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類」と書いてありますね。
このレベルになってくると実務ではともかく、試験レベルではそのまま覚えるしかないと思います。
-------------------------------
そういえば、本試験が近いですね。
通関業法、関税法等、輸出入申告は過去問・問題集中心で1ヶ月集中すればなんとかなるかもしれませんが、通関実務だけは、力作業だけでは迷路に迷い込む危険があります。
品目分類に関しては、
・関税率表は必ず目を通す
・類が何を指しているのか、についてはリストにまとめる。
・それより細かい部分は、過去問・問題集で1個ずつ覚える。
・通則1〜6や、何回も出ている有名な問題は、理由を考えずにそのまま覚える。
*類注や項、号レベルの分類などについては、合格圏内にある人が、悪問にあたっても対応できるように念を押す目的で覚えるようなレベルだと思います。
計算問題に関しては、
・とりあえず過去問を解く。
・ルールを覚える。
・過去問、問題集を数年分解く。
が、1ヶ月でできる中でコストパフォーマンスが高いやり方じゃないか、と思います。
前のコメントでも書きましたが、勉強の成果を途中段階でもいいので、書いていただければ、それに対しての解説を行います。
03類は魚・水産物(加工品以外)、
16類は動物調整品(肉・魚の加工品)
ですね。
関税率表をみたら、確かに03.06に「蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類」と書いてありますね。
このレベルになってくると実務ではともかく、試験レベルではそのまま覚えるしかないと思います。
-------------------------------
そういえば、本試験が近いですね。
通関業法、関税法等、輸出入申告は過去問・問題集中心で1ヶ月集中すればなんとかなるかもしれませんが、通関実務だけは、力作業だけでは迷路に迷い込む危険があります。
品目分類に関しては、
・関税率表は必ず目を通す
・類が何を指しているのか、についてはリストにまとめる。
・それより細かい部分は、過去問・問題集で1個ずつ覚える。
・通則1〜6や、何回も出ている有名な問題は、理由を考えずにそのまま覚える。
*類注や項、号レベルの分類などについては、合格圏内にある人が、悪問にあたっても対応できるように念を押す目的で覚えるようなレベルだと思います。
計算問題に関しては、
・とりあえず過去問を解く。
・ルールを覚える。
・過去問、問題集を数年分解く。
が、1ヶ月でできる中でコストパフォーマンスが高いやり方じゃないか、と思います。
前のコメントでも書きましたが、勉強の成果を途中段階でもいいので、書いていただければ、それに対しての解説を行います。
>瀬名さん
どのような勉強法をされていて、何がどのレベルまで達しているのかがわからないので、コメントはできませんが、主張したい部分以外の一部を引用してコメントをされると、まわりの皆さんに誤解を招く元になります。
・「通関業法と関税法と輸出入申告」 は、 「過去問・問題集中心」 で1ヶ月 「集中すれば」 なんとかなる 「かもしれない」 「が、通関実務だけは力技ではできない」、です。
これは、通関業法などが比較的パターン化されているのに比べて、通関実務は範囲自体が広い上にパターンから外して出題される傾向があり、したがって、対策方法も異なる、という事です。
声を聞く限りでは、「通関実務は合格点で、通関業法などで失敗した」という人よりは、「通関業法などは合格点だったが、通関実務で失敗した」という人の方が多いです。
どのような勉強法をされていて、何がどのレベルまで達しているのかがわからないので、コメントはできませんが、主張したい部分以外の一部を引用してコメントをされると、まわりの皆さんに誤解を招く元になります。
・「通関業法と関税法と輸出入申告」 は、 「過去問・問題集中心」 で1ヶ月 「集中すれば」 なんとかなる 「かもしれない」 「が、通関実務だけは力技ではできない」、です。
これは、通関業法などが比較的パターン化されているのに比べて、通関実務は範囲自体が広い上にパターンから外して出題される傾向があり、したがって、対策方法も異なる、という事です。
声を聞く限りでは、「通関実務は合格点で、通関業法などで失敗した」という人よりは、「通関業法などは合格点だったが、通関実務で失敗した」という人の方が多いです。
>おる さん
0.5%、という数字は覚えるしかないですね。実際にはビールでも数パーセント以上あるので、「酒」と出てきたらアルコール度数は気にせずすべて「22類」でよいと思います。
ビール、ワイン(葡萄酒)、日本酒、焼酎・ウイスキー・ブランデー・ウォッカ、リキュール、の酒類に加え、ビネガーと水・氷・雪が22類の仲間です。
22類は「飲料、アルコール、及び食酢」ですが、「飲み物」もしくは「水、酒、酢」と覚えた方が覚えやすいかもしれません。
「蒸留水」や「海水」は飲み物ではないので、22類からは外れます。
「果実ジュース」が20類なのは、「ジュースをつくる工程のうち、水で薄める前までの工程」を思い浮かべればなんとなく分類できると思いますが、これも有名なのでそのまま覚えてもいいと思います。
>しおりん さん
類が指す日本語を自分の言葉に置き換えて、さらに具体例を一つ出すと暗記しやすいと思います。
たとえば、1類なら、「動物(生きているものに限る。)」ではなく、「生きている動物」と覚え、例として、馬・牛・豚・カメ、と覚えます。
同様に、2類は「肉」、3類は、「魚・水産品」と、省略して覚えます。
1類から24類は「食品」という枠でおおざっぱにくくれるので、まとめて覚えます。
0.5%、という数字は覚えるしかないですね。実際にはビールでも数パーセント以上あるので、「酒」と出てきたらアルコール度数は気にせずすべて「22類」でよいと思います。
ビール、ワイン(葡萄酒)、日本酒、焼酎・ウイスキー・ブランデー・ウォッカ、リキュール、の酒類に加え、ビネガーと水・氷・雪が22類の仲間です。
22類は「飲料、アルコール、及び食酢」ですが、「飲み物」もしくは「水、酒、酢」と覚えた方が覚えやすいかもしれません。
「蒸留水」や「海水」は飲み物ではないので、22類からは外れます。
「果実ジュース」が20類なのは、「ジュースをつくる工程のうち、水で薄める前までの工程」を思い浮かべればなんとなく分類できると思いますが、これも有名なのでそのまま覚えてもいいと思います。
>しおりん さん
類が指す日本語を自分の言葉に置き換えて、さらに具体例を一つ出すと暗記しやすいと思います。
たとえば、1類なら、「動物(生きているものに限る。)」ではなく、「生きている動物」と覚え、例として、馬・牛・豚・カメ、と覚えます。
同様に、2類は「肉」、3類は、「魚・水産品」と、省略して覚えます。
1類から24類は「食品」という枠でおおざっぱにくくれるので、まとめて覚えます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
通関士資格・貿易実務検定 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
通関士資格・貿易実務検定のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90022人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
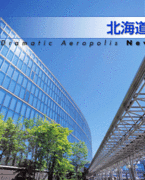


![[安・短・楽の資格取得法]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/61/79/476179_207s.jpg)




















