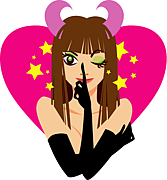例えば、二月の雨が凍えるほど冷たいのを自分ではどうにも出来ないことと同じように、ときおり、気を付けてはいても、ひと月に幾度かはどうしようもない孤独感に襲われる。不便なことに孤独はトマトソースの残りのように真空パックにして冷凍庫の奥に突っ込んで忘れることも出来ない。
ドヴォルザークの《新世界》が緩やかに帰宅を迫るというより、閉館まで残る閲覧者の背にとっととお帰りくださいと、丁重な冷や水を浴びせかけている。さすがにたむろしている学生も数えるほどで、倫太郎は所在無く読んでいた英字新聞を目がろくに文字を追わなくなったのを機に、仕方なく両脇をトラノオが茂った、大学図書館のエントランスを潜り抜けた。
乾いた冬の風を頬に受けたとき、目をしばたたくような孤独感に襲われた。それは海の底で横たわるような息苦しさ、胸を押す圧迫感。そんな孤独感は誰かと分かち合うようなものではないけれど、倫太郎は少なくとも、同じような寂寥感の持ち主を知っていた。
コートのポケットに手を突っ込み、朝から放り込みっぱなしだった携帯電話を取り出す。放り込みっぱなしでも一向に困る事のない、それが現実。特に誰かから連絡を待っているわけでもないが、またもや倫太郎は途方に暮れてしまった。まぁいいさ、小さい画面に文章を打ち込む。細長い空気管の先を海面に突き出す。開けゴマ。それは倫太郎に取ってそんな儀式行為。
*
拳の振り下ろし先は分かっているのだが、振り上げずに曖昧な笑顔で自分を誤魔化す。
いつものこととはいえ、だからといって慣れるほど心は単純じゃない。執拗に茶髪証明の提示を求める中学校の教師のようだ。ごちゃごちゃとした室長の指摘。男尊女卑とまでは言わないけれど、年齢がそう幾つも違わない奴にキャリアの差で文句をつけられたくはない。少なくとも図面と費用を自分で調べて計上してみれば、どれだけ無理難題を押し付けているか分かるだろうに。図面一つ引けない奴が、と殺意も芽生えるが、我が物顔で振舞えるのもさすがコネクションの力って奴ですか。
『ああ、柏木君ちょっと』『低コストに』『わが社の信用』『査定の時期』『私の責任』……。
君付けを止めさせたいとか、わが社ってお前の会社じゃないだろとか、責任って結局なすりつけてるでしょうとか。エトセトラ。エトセトラ。
室長の貧困な語彙のマシンガンへ適当な相槌を打ち、オフィスを定時で飛び出す。サービス残業して会社に貢献するような殊勝な心持は20代で使い果たしてしまった。会社を思うほど会社は自分を思ってはくれないのだ。未由はくたびれた溜め息を付いた。
座席を陣取り、念入りに手鏡を覗き込む女子高生の群れ。女性専用車両のどこにも自分の席はないと、ドア横の手すりに背を預ける。風潮に物言いたいわけでもない。ただ、慣れっことはいえ、一人何故か浮いてしまう寂寥感。未由はくすんだパンプスのつま先を見つめる。
その時、未由の携帯電話にピンクのクマがメール着信を知らせた。
*
――ご無沙汰。映画に誘いたいですけど今週末にでも。まぁ忙しいんじゃないかって思うんで、都合は未由姐さんにお任せ。予定はどうですか?
――ホントお久しぶりネ。そうなのー 忙しいのー(>_<) 映画観たいけどなー。名取クン何の映画を観る予定?
――前に観たいって言ってたホラー映画の続編、封切りしてますよ。先週末から。他にお誘いがあったら考えるけど。
――残念。今のところ、お誘いありましぇん^^; あ、今晩なら空いてる。何時から?
――……今晩って^^; もちろんこちらも。映画は九時四十分からデス。じゃあいつも通り、蔦屋前のコンビニに九時でOK?
――はい了解。……また電車乗り過ごしたら現地集合ってことで(苦笑)では待ち合わせは九時位ということで。宜しくお願いしますm(__)m
*
倫太郎は柏木を『姐さん』呼ばわりしているが、親戚でもなく、極道の妻でもましてや血の盃を交わした義兄弟でもない。倫太郎が三年ほど働いたコンビニエンスで朝シフトに入っていたのが柏木未由だった。その頃から年齢不詳の御姉様だったが、未だに実年齢は知らない。接客態度や物腰で30代であろうと推測していただけだ。倫太郎は特に知る必要を感じているわけでもなかった。二人とも趣味が怪奇映画鑑賞、と言って双方とも相当なB級、C級フリーク(要するに悪趣味なのだ)で、小劇場の情報や感想を述べ合ううちに、結局は一緒に通うようになったのである。
倫太郎は柏木に映画フリークとして接しているので、便宜上に『未由姐さん』と尊敬の意を込めてそう呼んでいるのだった。
冬時間で五時半に閉館しなければ、図書館で調べ物をしながら過ごせたのだけど、そういうわけにはいかない。待ち合わせにはまだまだ時間があるのだけど、どうしても腰が据わらなかった。時間の使い方に困ってしまう。
パスタを湯がき始める。手際よく刻んだニンニクと鷹の爪でバージンオイルに風味をつけ、冷凍庫から真空パックを取り出して固形になったトマトソースを小さく刻みフライパンにあけた。次第に赤い気泡が浮かぶ。そこに朝から砂出しさせていたアサリを投入する。白ワインと塩胡椒。喫茶店でアルバイトしているから手馴れたものだ。湯がいたパスタをフライパンに加え、仕上げにポットで栽培しているバジルの葉を散らす。パスタの、作る労力に見合わず無造作に食べてしまえるところが倫太郎は好きだった。早い晩ご飯を済ませて、と言っても夜更かし屋である倫太郎の時間感覚で言うところの《早い時間》だけれども。食器を流しに放り込み、そそくさと服を着替える。映画館の空調を頭に入れて選んだ服装だ。前回行った時は暖かすぎて隣で船を漕いでいた柏木を思い出す。深夜営業のファミレスであらすじを解説させられたっけ。一つ一つ部屋を見渡し指差し確認、忘れ物は無いか。本棚の上でろ過装置がこぷこぷと軽やかな水音をたてている。大丈夫、熱帯魚にもご飯はあげた。ライトは落とさなくても平気。夜行性のクーリー・ローチが喰いっぱぐれる恐れはあるけれど。多少の時間差はご容赦願いたい。待機電源の莫迦にならないご時世。湯沸かし器のコンセントを引き抜き、風呂の湯を抜く。下宿の狭い部屋だ。じきに確認するものもなくなった。先刻、流しに放り込んだ食器を丁寧に洗う。
ようやく携帯電話のアラームがなった。時計の針は八時五十分を指している。
倫太郎は二度、玄関の鍵を確認し、車に乗り込んだ。
*
思わず早く駅に着いてしまった。とはいえ家に戻り荷物を置いて着替えるほどの余裕があるわけではない。
両肩に食い込むショルダーバッグを下げながら、未由はショッピングモールのアーケードを潜った。蔦屋へ入り、地域の情報雑誌をめくる。最近試写会に行ってないので新しい映画情報を収集したいのだ。ひとしきりに目を通し、気まぐれに、読んだことのないミステリ作家の新刊を手に取り、あとがきから逆にページを繰ってみる。よほど気が向いたときにしかミステリなんぞには手を出さないので、特に問題はない。もし読もうと後に思い立ったところで、犯人が誰かなど、推理は二の次にストーリー自体を幻視して愉しむ未由にとって瑣末なことに過ぎない。最近、未由が通勤のお供にしているのはもっぱらクライブ・バーカーの《血の本》シリーズ。彼の作品はどれもスプラッタムービーを想起させる。総天然色の恐怖小説。だがあの黒塗りの表紙は未由を持ってしてもさすがに世間をはばかるので、ブックカバーは掛けたままだ。ゴーストモーテル、ミッドナイト・ミートトレイン。澄まして視線を落としていれば内容など他の客には見えないのだから。悪趣味? 大いに結構。
携帯を見るともう少し時間がある。そういえばご飯を口にする間も無かった。本屋と対面のドーナッツショップの店頭から鼻先をくすぐる香りに釣られ、未由は店に吸い込まれた。
揚げ立てドーナッツの香ばしい匂い。ココナツの香り。シナモンの香り。カカオマスのほろ苦い香り。蜂蜜の甘い香り。
未由は昔ながらの素揚げドーナッツが好きだった。自分用にオールドファッション、ブルーベリードーナッツとチュロス。甘いもの好きの名取にも、フレンチクルーラーにカスタードフレンチ、ツイストドーナッツを。
その場でポイントカードを削り、以前に貯めたポイントと併せ、弁当箱かランチマットか思うまま悩んだ末に、未由はランチマットを一緒に包んでもらった。
*
九時くらいとメールでは言っていても未由は時間前にはコンビニでペットボトルを物色し終わっていた。
時間通りに着いた倫太郎は車を降りて、窓越しに外を窺う未由に手を振る。
「お仕事ご苦労様。早かったですね」
「そうね、待ったのは10分ほど。すっかりお腹すいちゃった」未由はドーナッツの包みを持ち上げてみせる。
恐縮した倫太郎が助手席側のドアを開ける。「じゃあどうぞ」
「お邪魔しますっと。荷物後ろに置かせてね。これドーナッツ。名取クン。ご飯食べた?」
「いつもながら軽くは」
「お得意スパゲッティ? ニンニクの匂いがする」
「そう、アサリトマトソース、バジル風味」
「一度食べたけど器用よね。いつでもお嫁にいけるわ倫子ちゃん」
「未由姐さんを旦那にするのだけは御免こうむりますけどネ」お互いに相手の手の内を知っているので、安物の西部劇のように簡単には挑発に乗らない。
「ツイストドーナッツ買ってあるよ。ちゃんと食べてくれなきゃ。というより一人で映画館で食べるのはゾッとしない」
「では遠慮なく」苦笑しながら倫太郎がエンジンをかける。
「どうしたの? 笑ってさ」未由が釣られて何となく微笑む。
「いえ、大学の大講義室での授業のときに、バレないからって女友達が毎回、プリッツとかチョコとかのお菓子持ち込んでて、そのお裾分けを貰ってたのを思い出して」
「むう。別に餌付けしてるつもりはないけどね。なつかないでよ」未由がこれ見よがしに眉をひそめ、また軽く片目を瞑ってみせた。
「ええ、僕も餌付けされてるつもりはありません」名取も切り返す。
「我慢出来ない、一つ食べちゃおう」未由がツイストドーナッツを摘み上げた。
「あ、それは」「何よう」「食べ過ぎて寝ないでくださいよ。説明するの結構骨なんですから」「あ、言うようなったなぁ」「……運転中にわき腹を突付かないでもらえますか」
今夜行く映画館は郊外型のシネマコンプレックスで、ホラー映画を扱うのは珍しい。以前まであったホラーバッシングの時代を考えると、レイトショーの割引を狙って倫太郎や未由のようなフリークが通うには便利になったものだと思う。こういう時、車を持っている倫太郎には利がある。もちろん、未由が倫太郎を利用しているわけではない。全く利害の一致だ。とはいえ、満足の行くスプラッタ趣味の映画を観ようとするならば、矢張り、繁華街の片隅に埋もれた小劇場に通うしかないのだけど。
いつの間にか、どうしようもない孤独感は薄れていた。結局は二人ともお互いが精神安定剤なのだ。映画は月に何度かの処方箋。
風が強い所為か、フロントガラスの前方を雲が流れ、濃紺の空に一際火星が紅く映える。
「夜になると自然と血が騒ぐというか、怪奇趣味らしい」
「じゃ、わたしは女吸血鬼?」未由姐さんがくすくす笑う。
「さしずめ僕はお供の狼男。何処まで送りましょう、お嬢さん」倫太郎の口調がおどける。
「年上をからかうと、君も一人身で無駄に年食っちゃうんだから」未由の鋭い眼光に倫太郎が肩をすくめる。
「では参りましょうか、姫。今宵も恐怖の館へ」倫太郎が未由の手をささげ持つ振りをする。
「うむ苦しゅうない」
固く巻きつけたマフラーをほどき、座席シートに深く背を沈める。さながらの女王様は勝手知ったるカーラジオのボリュームをひねりつつ、FMの周波数を選び始めた。
|
|
|
|
|
|
|
|
恋愛小説創作同盟 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
恋愛小説創作同盟のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37863人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人