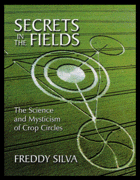ダイエット食品だけでなく、いろいろなところで食品の
「カロリー表示」が行われていますが、
どの程度、定量的に信憑性があるのでしょうか。
それとも、相対的なものなのでしょうか。
いろいろ調べてみても、納得できる説明に行き当たりません。
消化吸収能力には個人差があると思いますし、すべてが単純に水と二酸化炭素になるとも思えません。
それなのに、1234kcalなど有効数字4桁くらいで、扱われている例をよく目にします。
代謝熱から人間の消費カロリーを計算するのはわかるのですが、食品を摂取したからといって単純にその食品のもつエネルギーを摂取したことになるのでしょうか。
これも「ニセ科学」ではないでしょうか。
「カロリー表示」が行われていますが、
どの程度、定量的に信憑性があるのでしょうか。
それとも、相対的なものなのでしょうか。
いろいろ調べてみても、納得できる説明に行き当たりません。
消化吸収能力には個人差があると思いますし、すべてが単純に水と二酸化炭素になるとも思えません。
それなのに、1234kcalなど有効数字4桁くらいで、扱われている例をよく目にします。
代謝熱から人間の消費カロリーを計算するのはわかるのですが、食品を摂取したからといって単純にその食品のもつエネルギーを摂取したことになるのでしょうか。
これも「ニセ科学」ではないでしょうか。
|
|
|
|
コメント(9)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%9A%84%E7%86%B1%E9%87%8F
によると、
>食物を空気中で燃やして得られた熱量と、同量の食物を食べて出た排泄物を燃やして得られた熱量の差から、食物から吸収した熱量を推定する(ルブネル,1883など)。食物の栄養学的熱量は主にこの方法で測定され、消化吸収率などを考慮して補正される。日本では代表的な食品材料について測定されており、料理などに表示される熱量は、一般的に食品材料の分量と重量あたり熱量から推定する。
とのことなので、単純な酸化熱量を元に平均的な消化吸収率などを考慮して計算されているようですね。
無論吸収率は体調などによっても左右されるでしょうから、そこは理論上の計算値に過ぎないということで。
きちんと定義されていますし、ニセ科学ということはないでしょう。ただ個人差があるので単純な適用はできず、類推的な処理をするしかないというだけで。
によると、
>食物を空気中で燃やして得られた熱量と、同量の食物を食べて出た排泄物を燃やして得られた熱量の差から、食物から吸収した熱量を推定する(ルブネル,1883など)。食物の栄養学的熱量は主にこの方法で測定され、消化吸収率などを考慮して補正される。日本では代表的な食品材料について測定されており、料理などに表示される熱量は、一般的に食品材料の分量と重量あたり熱量から推定する。
とのことなので、単純な酸化熱量を元に平均的な消化吸収率などを考慮して計算されているようですね。
無論吸収率は体調などによっても左右されるでしょうから、そこは理論上の計算値に過ぎないということで。
きちんと定義されていますし、ニセ科学ということはないでしょう。ただ個人差があるので単純な適用はできず、類推的な処理をするしかないというだけで。
返答有り難うございます。
>芹沢文書さん
排泄物を燃焼した時に発生する熱量との差をとっているとは知りませんでした。
それなら、少なくとも相対的な値としては、信用が置けそうですね。
>ROCKYさん
恣意的な科学の誤用を含めて「ニセ科学」だと考えていました。(あるあるの捏造もしかりです)
しかし返答してくださった方の論調から、そうでないことがわかりました。
ただ、話が少しそれますが、カロリーはダブルスタンダードなので厳密に定義されているとは言い難いと思います。
カロリーのもともとの定義は
「1グラムの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量」ですが、
温度によって密度が違うので、必要な熱量も異なります。
そこで、
1気圧下で「14.5℃から15.5℃」にあげるのに必要な熱量として、「15℃カロリー」や
「19.5℃から20.5℃」にあげるのに必要な熱量として「20℃カロリー」、
さらには温度を指定しない「熱力学カロリー」「国際蒸気表カロリー」
0℃から100℃まで上昇させるのに必要な熱量の1/100である「平均カロリー」
もあります。
それぞれのカロリーの定義は、厳密にJ単位で計測されていますが、定義が複数あって定まらない以上、「カロリーの定義は厳密だ」とは、言えないと思います。
>Micaelさん
私は、まさにこのいい加減さが「ニセ科学」っぽいな、と思いました。
「ニセ科学」とは「科学的に定義されていないものを、いかにも定義されているかのように扱うこと」だと思います。
みなさんのお話からも、研究機関ではちゃんとした実験・計測が行われているであろうとはわかりました。
しかし、カロリー表示を行っている食品すべてがこのような実験を経て、計測された結果だとは思えなかったのです。
ご飯ひとつにしても、米の種類、炊き方、保存方法、個人差、などによって、吸収されるカロリーは違うと思われるのに、それを同じにしてよいのか?と、疑問を感じた次第です。
実際には異なっているかもしれない値を、科学的に正しいと盲信して表示しているのなら、「ニセ科学」に入るのではないか、と考えました。
>芹沢文書さん
排泄物を燃焼した時に発生する熱量との差をとっているとは知りませんでした。
それなら、少なくとも相対的な値としては、信用が置けそうですね。
>ROCKYさん
恣意的な科学の誤用を含めて「ニセ科学」だと考えていました。(あるあるの捏造もしかりです)
しかし返答してくださった方の論調から、そうでないことがわかりました。
ただ、話が少しそれますが、カロリーはダブルスタンダードなので厳密に定義されているとは言い難いと思います。
カロリーのもともとの定義は
「1グラムの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量」ですが、
温度によって密度が違うので、必要な熱量も異なります。
そこで、
1気圧下で「14.5℃から15.5℃」にあげるのに必要な熱量として、「15℃カロリー」や
「19.5℃から20.5℃」にあげるのに必要な熱量として「20℃カロリー」、
さらには温度を指定しない「熱力学カロリー」「国際蒸気表カロリー」
0℃から100℃まで上昇させるのに必要な熱量の1/100である「平均カロリー」
もあります。
それぞれのカロリーの定義は、厳密にJ単位で計測されていますが、定義が複数あって定まらない以上、「カロリーの定義は厳密だ」とは、言えないと思います。
>Micaelさん
私は、まさにこのいい加減さが「ニセ科学」っぽいな、と思いました。
「ニセ科学」とは「科学的に定義されていないものを、いかにも定義されているかのように扱うこと」だと思います。
みなさんのお話からも、研究機関ではちゃんとした実験・計測が行われているであろうとはわかりました。
しかし、カロリー表示を行っている食品すべてがこのような実験を経て、計測された結果だとは思えなかったのです。
ご飯ひとつにしても、米の種類、炊き方、保存方法、個人差、などによって、吸収されるカロリーは違うと思われるのに、それを同じにしてよいのか?と、疑問を感じた次第です。
実際には異なっているかもしれない値を、科学的に正しいと盲信して表示しているのなら、「ニセ科学」に入るのではないか、と考えました。
>カロリーはダブルスタンダードなので厳密に定義されているとは言い難いと思います。
ダブルスタンダードじゃないでしょう。
(yamazaksさんが挙げておられるだけで四つもあるし、ってのは余計なツッコミですが)
いくつもの定義はあるが、お互いの差はごく少ない。
だから一般に食物の熱量を言う場合などには、
どの定義を適用しているかを明示しなくても良い、
と言うだけの話ではないかと。
これが学術論文のレベルで、厳密な論議が必要であったら、もっと厳密な定義に従うでしょう。
そもそも「カロリー」自体がSI単位ではないので、
学術論文レベルで使用するのは推奨されないはず。
「食物のカロリー」云々が、そう言った意味では一般向けの話題でしかありません。
>ご飯ひとつにしても、米の種類、炊き方、保存方法、個人差、などによって、吸収されるカロリーは違うと思われるのに、それを同じにしてよいのか?と、疑問を感じた次第です。
じゃあ
「このカロリーは目安です。
個人によって体調によって調理法によって吸収が違います。」
とでも注意書きを書き添えるよう法律で規定したら良いかも知れませんね

ダブルスタンダードじゃないでしょう。
(yamazaksさんが挙げておられるだけで四つもあるし、ってのは余計なツッコミですが)
いくつもの定義はあるが、お互いの差はごく少ない。
だから一般に食物の熱量を言う場合などには、
どの定義を適用しているかを明示しなくても良い、
と言うだけの話ではないかと。
これが学術論文のレベルで、厳密な論議が必要であったら、もっと厳密な定義に従うでしょう。
そもそも「カロリー」自体がSI単位ではないので、
学術論文レベルで使用するのは推奨されないはず。
「食物のカロリー」云々が、そう言った意味では一般向けの話題でしかありません。
>ご飯ひとつにしても、米の種類、炊き方、保存方法、個人差、などによって、吸収されるカロリーは違うと思われるのに、それを同じにしてよいのか?と、疑問を感じた次第です。
じゃあ
「このカロリーは目安です。
個人によって体調によって調理法によって吸収が違います。」
とでも注意書きを書き添えるよう法律で規定したら良いかも知れませんね
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
トンデモ・疑似・エセ科学(w) 更新情報
-
最新のアンケート
トンデモ・疑似・エセ科学(w)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人