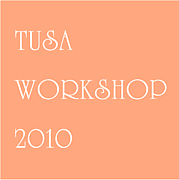福島
佐藤さんね。やっぱり建築はお祭りではない、終わってみんなハッピーであればよし。やっぱりものとして
20年30年はもつとする。もちろんドタバタということがたぶん学生の課題以上に実際の仕事のほうがいろんな要素があって、不確実なまま進まなくてはいけない。そのドタバタを作品の質につなげていくやり方っていうのがたぶんあると思うんですが、結局ドタバタしてダメでした、ものとしては良くない、イベントとしては楽しい、僕らのやっていることはイベントではないので、イベントとしてよければいいということを優先してはいけない。とすると、ものとして、クオリティーをドタバタにつなげていく方策というかそういったものがあれば教えていただきたい。
佐藤
たとえばまあ、我々構造家の中では研究者はすごく慎重派なんです。我々エンジニア派は極端な話数少ない研究されたことからいかに応用を利かせるか、例えばこういう研究がされて、こういう結果が出たなら、それを拡大して応用してこういうことができるに違いない、っていうことを提案したり、そういう発想を膨らませないといけないんですけど、それは単に冒険ではなくて、例えば研究成果に基づいてそれを知った上でそこから少し進歩させてこれはできるに違いない、とかそういうことだと思うんです。それがそのドタバタというかちゃんとした検討がちょっと足りない程度で進めていく感じなんです。我々はいつもそういうスタンスなんです。我々はいつも気になること全てを検討することはできずに着工しなければいけない。
実は構造で検討することってものすごくたくさんあるんです。なんですが、すべてはできないから、これとこれを使ってこれをチェックしておけばあとは何とかなるだろう、みたいなそういうドタバタの中で生きているんです。ちょっとわからないんですが、もしかしたら日本の構造エンジニアリングはすごく長けているんです。
福島
でも、何とかなるだろう。という実感があるわけじゃないですか。ドタバタであろうともこれはまずいだろう、じゃなくてなんとかなるだろう。それを感じる能力というのは、どっからくるわけですか。
佐藤
それは先ほど言ったとおり素材に触れるということがひとつすごく大事だと思います。実際時間がない中で設計して建物が建っていくと、それで最後の最後まで実際の建物が建っていく現場っていうのは最終決定をしたければならないと。その段階に至るまで全てちゃんと見張っていて、もし万が一何かまちがっていたならその場で直す。建物が立っていく現場を見ると問題点が発覚するんですよね。だからそれはちゃんと見ていないといけない。それが「ふれる」ということなのかもしれないんですけど。ちゃんとそれを肌で感じている、っていうことになるのかなと思うんですけどね。w
福島
たぶん佐藤さん、斉藤さんがおっしゃっていることは、ものをつくる上で二つ価値基準を置きなさいと。
一つではなくて、何かクオリティを上げるとかもしくはすべてを理解可能にするということではなくて、それは絶対にやるんだけれども、ある時そこを超えた、言語化不可能な、言葉にしえない世界が出てくる。それをポジティブにとらえて、それすら楽しもうとする行為に思えるのです。けど二つ基準を持つこと、ダブルスタンダード、これは精神病の特有の症状じゃないですか。ある人はAといいます。ある人はBといいます。その間でよくわからなくなっている。通常の精神状態では、病気になってしまうようなシチュエーションをものづくりにいかしていけるような特殊なトレーニングはしておられるのでしょうか。ふつうの人ならおかしくなってしまうと思うんですよ。w
佐藤
確かにやれる人とやれない人がいると思います。
福島
それは才能の話ですか?
佐藤
トレーニングとかあるとき気がつくとか、そういうやり方でいいんだと気がつくとか。
斉藤
僕が思うのは、いま言ったダブルスタンダードっていうんですか、それは今まで経験してきた感覚の中で絶対持っているものがあるんじゃないかと思っていて、これがやばかったらこの方法に切り替えればいい
というのが自分の中にあって、だからこそドタバタを楽しめるというか、そういう感覚はあると思う。
それと僕なんかがものづくりをするとなるとスタッフィングの問題もあって、どの人がチームの中にいてどういう能力を持っているのか。それはサッカーと同じで、その人にパスを出すとなんかやってくれるんじゃないか、っていう人たちが集まっている場では絶対ものすごいものができる。でなんかその理科大の中でグループ課題をやると思うんだけどその前にポスト3年生たちがこういうワークショップをやるのは難しいのかもしれない。だけど、なんか、このワークショップの中でこいつはこういうことに長けてるとかたとえばベクターがものすごいのか絵がうまいのか、なんかそういうのが見つかる一つのきっかけにはなるのかなとは思っている。だから僕の中であるのはいつもスタッフィングをすごいやっておくっていうのと、あとようやくたとえば金属でやるとどうしても肯定的に時間がかかるから、金属無理だったら木でなんとかやろうと、っていうようなバックアップをいつも頭ん中でなんかもっているから、だからドタバタができる、そしてみんながそれを共有していて、だからあーだこーだ言ってどんどんテンドンして上にあがっていくということが往々にしてあるかなと思う。
福島
基本的にはすごく同意をするんですけど、去年の二年生、三年生が抱くある種のクオリティの問題、すごく難しいんですけど、例えば僕の好きな映画で、Beautiful Dreamer (うる星やつら)があるんですが、あれは主人公の女の子が永遠に学園祭の前一週間続いてほしいと、だからずーっと一週間なんですよ。前日になると一週間前に戻る、それで明日学園祭だというドキドキ感が永遠に続くんです。ただ最後にやっぱり決着をつけないといけない。そういうドキドキ感ってやっぱり決着はつけられない、それだけでは。クオリティを担保できない気がするんです。お祭りとしてはすごく楽しい。それはわかる。それを最終的な作品につなげていくのはすごく難しいと思うんです。
佐藤
そのクオリティ的に若干去年の状況で気になったのは、そのクオリティの問題につながるかもしれないんですが、ちょっとやりすぎ感がありましたよね。素材を3つやるとか、椅子とか線の家とかちょっとやりすぎかなっていうのはありますよね。w
その辺は人数が多いからできるのかもしれないが、それにしても多かった気がしましたね。w
福島
もう少しゆっくり考えろと。w
佐藤
もう少ししぼってよかったんじゃないかと思いますね。
金田
この場があと5分ほどで締めないといけない事実がありまして。。
今佐藤さんがやりすぎなのではないかとおっしゃられましたが、また斉藤さんが24時間で線の家をやることに対する意見をいただいたわけですが、実際僕らの企画側としては、あまりにも詰め込みすぎた事実はあり実際24時間のときはみな力尽きていました。でも実際やっている時としては、たぶんものすごく経験値としては成長していて、一週間前の状態のドキドキ感と今終わって客観的に見る自分たちの状況ってやっぱりかなり違いがあってそこに対してどういう態度を今年のワークショップがとっていくのかなという問いかけがあるんですけど、その辺について御三方に意見を頂いて来年につなげていってもらいたいです。
斉藤
次のワークショップの企画側の頭ってもう決まっているの?
金田
三年の星君が代表です。
斉藤
今年はどんなことを考えているの。
星
今年は1・1を引き継ごうとはおもっているのですが、昨年の1・1というのはスケールだけの話だと思っていて、それは模型がそのまま拡大されたものに近いのではないかというふうに考えていて、そうではなくてより建築的なものをつくりたいのであれば、環境やその場所で起こる出来事だとかもっと細かいディテールだとか、そこら辺までこだわれたらいいんじゃないかと思っています。
斉藤
詰め込みすぎないようにね。w
佐藤
私は今までにいろいろなワークショップを見てきたんですけど、今の2,3年生がつくった去年の成果物はお世辞ではなくかなりいい出来です。批判的な意識も必要ではあるけれども、一方で自身は持っていいと思っている。あれが本当につくれたということはすごいことであって、それもわからないんですよ。現場でやらされている方はわからないんです。なんでこんなことをやるんだと。だけど、いづれわかるときが来るかもしれないんですが、去年できたものというのは、若干の物足りない部分はあるとは思いますが、
かなりいい出来だったということは自信をもって言っていいと思うんです。また、去年初めて1・1をやったということなんですがそれ以前の都市計画とかも参考にしたらいいと思うんです。1・1はすごく派手なイベントだしすごく盛り上がるイベントのように思うから、そっちに行きがちだと思うんですが、でかいものを作るのは建築が一番たけてると思うので、そういうことは大切にしながら、一方で都市計画など脈々と続いた今までの活動を十分に参考にしながら、次の企画を考えるといいと思います。
金田
最後に去年のワークショップで一番物足りなかった点を指摘してもらってこの場を締めたいと思います。
斉藤
僕はずっとマテリアルのことについて言ってきて、ダンボールでガムテープばっか張って中学生の文化祭じゃないんだからっていう話をずっとしてきて、それがスタイロになり、それが5年後には金属も木もウレタンも扱うようになって、これってすごいことだと思っていて、そこまで加工できるとか、道具が扱えるとか、
そこまでみんな力を合わせてものがつくれるとか、それはすごいことだとおもっている。特に去年のワークショップは素材感というものがすごく大事になっていたんだけど、そこは今年も大事にしてほしいなと思う。で、物足りない事はあんまりなくて去年はすごくいい成果というかひとつ理科大の文化祭のワークショップが確立されたんじゃないかなと思う。ただそれを今年どういう風にしていくのかがすごくたのしみではある。それで、あんまり難しく考えないほうが、もしかしたらいいのかもしれない、もう少し直観的な行動とか、さっき議論になったような形容的のものの表現をどう落とし込んでいくのかとか、あんまり考えすぎて墓穴掘るようなことにはしてほしくない。だからこれはありなのか無しなのかわからないけど、ノリが大切だったりもして、実は自分の直感は信じるところはしっかり信じたほうがよくて、なんか理科大ってやっぱりすごくリテラシーが高いし、いろんな情報を入れているし、いろんな所に参加しているし、だからすごく難しく考えるPhaseがあるなあとおもっている。それは悪いことじゃないんだけど、ものをバチっと作ってくことに対して、それが邪魔になる瞬間もあるから、そこは自分でいいあんばいにしてほしいなと思う。だからまじめすぎず、ふざけすぎず。そんな感じで進めてもらえると面白くなるんじゃないかなと思う。
佐藤
私が物足りないと思ったのはやっぱり、やりすぎ感ですかね。それであとは去年作ったものにどういう意味があるかちゃんと考えてほしいし、知ってほしい。特にさっき金属班がクオリティが低いんじゃないかという話があったんだけども、我々構造家からしてすごいと思うのは、あれに子供が座っていたことなんです。私も一回座ったんです。で、人が乗れるものをつくるっていうのはものすごく大変なことなんです。それができたということはひとつ、価値があることなんです。それはなかなか伝えられないことなのかもしれないんですが、こういうワークショップで何かを一個つくりましたという時に人が乗れるものってほとんどつくれないんですよ。さっき子供が平気で座ってたでしょ。それはすごい価値のあることなんですよ。人の重量ってものすごい負荷なんですよ。その負荷に耐えられるものってなかなかできない。そういう価値を、他のウレタンは壊れた後も楽しめたり、木に関しては空間として寝そべられたりできるものになっていて、比較的わかりやすい価値が見出せたと思うんですよ。で金属チームに限ってはその辺がわからないんだと思う。でもあれはすごい価値があるんですよ。子供が吸われてるというだけで。それで私大人一人が座れるというだけですごく価値のあることだから、そういう価値観を知ってほしい。特に普段の生活の中で、
そういうことを知る機会を持つといいのが理科大なんかはすごくいい先生がそろっているんですよ。意匠の先生だけではなくて構造や設備の先生もかなりのスペシャリストがそろっている、全国的に見てもかなりいい先生がそろっている。構造でいえば、北村先生だとか、皆さんあんまり意識しないでしょう。北村先生のことだけ言うと悪いけれども、うちにいた村先生の研究室出身の人いるからね。そういう理由で北村先生だけをあげるとすると、北村先生は構造の世界ではすごい先生なんですよ。でもすごく設計の好きな先生なんですよ。だからそういう先生の知識やアドバイスを引き出すことが必要だと思うんですよね。
ただおそらく環境の先生だとか、設備の先生だとかにも、そういう先生がたくさんおられると思うんですよ。普段敬遠しがちだけれども、それになんか聞きに行くと冷たいんですよねそういう先生たちって。そんなことできるわけないだろみたいなね、そういうころあるかもねーみたいな。だけどそれでめげないで、
すごい知識をもっている人たちなんだから、その知識をちょっとでも引き出そうと、事前調査をするなりして、ちゃんと知識を持った上で、こんなことはできないでしょうかと、聞いてみてほしい。そういう意識をもっていま作ろうとしているもの、設計しようとしているもの、課題でもそうですけど、そういうところにちゃんと価値を見いだせるといいのではないかと思いますね。
福島
もう圧倒的に美しいものを作ってもらいたい。
これでいいデザインはすごいあふれている、それは一つの存在価値だけど、これがいい!この野田に来なければ、君たちでなければデザインできないようなものをぜひ思考してほしい。これでいいデザインはありすぎ、理科大生は去年これでいいデザインを思考しすぎている。ドンキホーテであろうと世界中で自分だけがこれをデザインしているという気概が非常に弱い、それは理科大の強さでもあり理科大の最大の弱点でもある気がします。絶対にどんな人でさえ僕のデザインで美しいと言わせて見せるそういう気概をぜひこのワークショップで出し合ってほしいなと思います。
金田
かなり刺激的な言葉を頂けたと思いますし、三年生はもちろんかなりのものをつくってくれると期待されているので、それに応えてほしいと思います。今日この場で聞けた言葉が建築学科に身を置いている全員がそれをかみしめてこれから設計に励んでいけるようないい現場になったのではないかなと思っています。以上で今日の座談会を終了します。
佐藤さんね。やっぱり建築はお祭りではない、終わってみんなハッピーであればよし。やっぱりものとして
20年30年はもつとする。もちろんドタバタということがたぶん学生の課題以上に実際の仕事のほうがいろんな要素があって、不確実なまま進まなくてはいけない。そのドタバタを作品の質につなげていくやり方っていうのがたぶんあると思うんですが、結局ドタバタしてダメでした、ものとしては良くない、イベントとしては楽しい、僕らのやっていることはイベントではないので、イベントとしてよければいいということを優先してはいけない。とすると、ものとして、クオリティーをドタバタにつなげていく方策というかそういったものがあれば教えていただきたい。
佐藤
たとえばまあ、我々構造家の中では研究者はすごく慎重派なんです。我々エンジニア派は極端な話数少ない研究されたことからいかに応用を利かせるか、例えばこういう研究がされて、こういう結果が出たなら、それを拡大して応用してこういうことができるに違いない、っていうことを提案したり、そういう発想を膨らませないといけないんですけど、それは単に冒険ではなくて、例えば研究成果に基づいてそれを知った上でそこから少し進歩させてこれはできるに違いない、とかそういうことだと思うんです。それがそのドタバタというかちゃんとした検討がちょっと足りない程度で進めていく感じなんです。我々はいつもそういうスタンスなんです。我々はいつも気になること全てを検討することはできずに着工しなければいけない。
実は構造で検討することってものすごくたくさんあるんです。なんですが、すべてはできないから、これとこれを使ってこれをチェックしておけばあとは何とかなるだろう、みたいなそういうドタバタの中で生きているんです。ちょっとわからないんですが、もしかしたら日本の構造エンジニアリングはすごく長けているんです。
福島
でも、何とかなるだろう。という実感があるわけじゃないですか。ドタバタであろうともこれはまずいだろう、じゃなくてなんとかなるだろう。それを感じる能力というのは、どっからくるわけですか。
佐藤
それは先ほど言ったとおり素材に触れるということがひとつすごく大事だと思います。実際時間がない中で設計して建物が建っていくと、それで最後の最後まで実際の建物が建っていく現場っていうのは最終決定をしたければならないと。その段階に至るまで全てちゃんと見張っていて、もし万が一何かまちがっていたならその場で直す。建物が立っていく現場を見ると問題点が発覚するんですよね。だからそれはちゃんと見ていないといけない。それが「ふれる」ということなのかもしれないんですけど。ちゃんとそれを肌で感じている、っていうことになるのかなと思うんですけどね。w
福島
たぶん佐藤さん、斉藤さんがおっしゃっていることは、ものをつくる上で二つ価値基準を置きなさいと。
一つではなくて、何かクオリティを上げるとかもしくはすべてを理解可能にするということではなくて、それは絶対にやるんだけれども、ある時そこを超えた、言語化不可能な、言葉にしえない世界が出てくる。それをポジティブにとらえて、それすら楽しもうとする行為に思えるのです。けど二つ基準を持つこと、ダブルスタンダード、これは精神病の特有の症状じゃないですか。ある人はAといいます。ある人はBといいます。その間でよくわからなくなっている。通常の精神状態では、病気になってしまうようなシチュエーションをものづくりにいかしていけるような特殊なトレーニングはしておられるのでしょうか。ふつうの人ならおかしくなってしまうと思うんですよ。w
佐藤
確かにやれる人とやれない人がいると思います。
福島
それは才能の話ですか?
佐藤
トレーニングとかあるとき気がつくとか、そういうやり方でいいんだと気がつくとか。
斉藤
僕が思うのは、いま言ったダブルスタンダードっていうんですか、それは今まで経験してきた感覚の中で絶対持っているものがあるんじゃないかと思っていて、これがやばかったらこの方法に切り替えればいい
というのが自分の中にあって、だからこそドタバタを楽しめるというか、そういう感覚はあると思う。
それと僕なんかがものづくりをするとなるとスタッフィングの問題もあって、どの人がチームの中にいてどういう能力を持っているのか。それはサッカーと同じで、その人にパスを出すとなんかやってくれるんじゃないか、っていう人たちが集まっている場では絶対ものすごいものができる。でなんかその理科大の中でグループ課題をやると思うんだけどその前にポスト3年生たちがこういうワークショップをやるのは難しいのかもしれない。だけど、なんか、このワークショップの中でこいつはこういうことに長けてるとかたとえばベクターがものすごいのか絵がうまいのか、なんかそういうのが見つかる一つのきっかけにはなるのかなとは思っている。だから僕の中であるのはいつもスタッフィングをすごいやっておくっていうのと、あとようやくたとえば金属でやるとどうしても肯定的に時間がかかるから、金属無理だったら木でなんとかやろうと、っていうようなバックアップをいつも頭ん中でなんかもっているから、だからドタバタができる、そしてみんながそれを共有していて、だからあーだこーだ言ってどんどんテンドンして上にあがっていくということが往々にしてあるかなと思う。
福島
基本的にはすごく同意をするんですけど、去年の二年生、三年生が抱くある種のクオリティの問題、すごく難しいんですけど、例えば僕の好きな映画で、Beautiful Dreamer (うる星やつら)があるんですが、あれは主人公の女の子が永遠に学園祭の前一週間続いてほしいと、だからずーっと一週間なんですよ。前日になると一週間前に戻る、それで明日学園祭だというドキドキ感が永遠に続くんです。ただ最後にやっぱり決着をつけないといけない。そういうドキドキ感ってやっぱり決着はつけられない、それだけでは。クオリティを担保できない気がするんです。お祭りとしてはすごく楽しい。それはわかる。それを最終的な作品につなげていくのはすごく難しいと思うんです。
佐藤
そのクオリティ的に若干去年の状況で気になったのは、そのクオリティの問題につながるかもしれないんですが、ちょっとやりすぎ感がありましたよね。素材を3つやるとか、椅子とか線の家とかちょっとやりすぎかなっていうのはありますよね。w
その辺は人数が多いからできるのかもしれないが、それにしても多かった気がしましたね。w
福島
もう少しゆっくり考えろと。w
佐藤
もう少ししぼってよかったんじゃないかと思いますね。
金田
この場があと5分ほどで締めないといけない事実がありまして。。
今佐藤さんがやりすぎなのではないかとおっしゃられましたが、また斉藤さんが24時間で線の家をやることに対する意見をいただいたわけですが、実際僕らの企画側としては、あまりにも詰め込みすぎた事実はあり実際24時間のときはみな力尽きていました。でも実際やっている時としては、たぶんものすごく経験値としては成長していて、一週間前の状態のドキドキ感と今終わって客観的に見る自分たちの状況ってやっぱりかなり違いがあってそこに対してどういう態度を今年のワークショップがとっていくのかなという問いかけがあるんですけど、その辺について御三方に意見を頂いて来年につなげていってもらいたいです。
斉藤
次のワークショップの企画側の頭ってもう決まっているの?
金田
三年の星君が代表です。
斉藤
今年はどんなことを考えているの。
星
今年は1・1を引き継ごうとはおもっているのですが、昨年の1・1というのはスケールだけの話だと思っていて、それは模型がそのまま拡大されたものに近いのではないかというふうに考えていて、そうではなくてより建築的なものをつくりたいのであれば、環境やその場所で起こる出来事だとかもっと細かいディテールだとか、そこら辺までこだわれたらいいんじゃないかと思っています。
斉藤
詰め込みすぎないようにね。w
佐藤
私は今までにいろいろなワークショップを見てきたんですけど、今の2,3年生がつくった去年の成果物はお世辞ではなくかなりいい出来です。批判的な意識も必要ではあるけれども、一方で自身は持っていいと思っている。あれが本当につくれたということはすごいことであって、それもわからないんですよ。現場でやらされている方はわからないんです。なんでこんなことをやるんだと。だけど、いづれわかるときが来るかもしれないんですが、去年できたものというのは、若干の物足りない部分はあるとは思いますが、
かなりいい出来だったということは自信をもって言っていいと思うんです。また、去年初めて1・1をやったということなんですがそれ以前の都市計画とかも参考にしたらいいと思うんです。1・1はすごく派手なイベントだしすごく盛り上がるイベントのように思うから、そっちに行きがちだと思うんですが、でかいものを作るのは建築が一番たけてると思うので、そういうことは大切にしながら、一方で都市計画など脈々と続いた今までの活動を十分に参考にしながら、次の企画を考えるといいと思います。
金田
最後に去年のワークショップで一番物足りなかった点を指摘してもらってこの場を締めたいと思います。
斉藤
僕はずっとマテリアルのことについて言ってきて、ダンボールでガムテープばっか張って中学生の文化祭じゃないんだからっていう話をずっとしてきて、それがスタイロになり、それが5年後には金属も木もウレタンも扱うようになって、これってすごいことだと思っていて、そこまで加工できるとか、道具が扱えるとか、
そこまでみんな力を合わせてものがつくれるとか、それはすごいことだとおもっている。特に去年のワークショップは素材感というものがすごく大事になっていたんだけど、そこは今年も大事にしてほしいなと思う。で、物足りない事はあんまりなくて去年はすごくいい成果というかひとつ理科大の文化祭のワークショップが確立されたんじゃないかなと思う。ただそれを今年どういう風にしていくのかがすごくたのしみではある。それで、あんまり難しく考えないほうが、もしかしたらいいのかもしれない、もう少し直観的な行動とか、さっき議論になったような形容的のものの表現をどう落とし込んでいくのかとか、あんまり考えすぎて墓穴掘るようなことにはしてほしくない。だからこれはありなのか無しなのかわからないけど、ノリが大切だったりもして、実は自分の直感は信じるところはしっかり信じたほうがよくて、なんか理科大ってやっぱりすごくリテラシーが高いし、いろんな情報を入れているし、いろんな所に参加しているし、だからすごく難しく考えるPhaseがあるなあとおもっている。それは悪いことじゃないんだけど、ものをバチっと作ってくことに対して、それが邪魔になる瞬間もあるから、そこは自分でいいあんばいにしてほしいなと思う。だからまじめすぎず、ふざけすぎず。そんな感じで進めてもらえると面白くなるんじゃないかなと思う。
佐藤
私が物足りないと思ったのはやっぱり、やりすぎ感ですかね。それであとは去年作ったものにどういう意味があるかちゃんと考えてほしいし、知ってほしい。特にさっき金属班がクオリティが低いんじゃないかという話があったんだけども、我々構造家からしてすごいと思うのは、あれに子供が座っていたことなんです。私も一回座ったんです。で、人が乗れるものをつくるっていうのはものすごく大変なことなんです。それができたということはひとつ、価値があることなんです。それはなかなか伝えられないことなのかもしれないんですが、こういうワークショップで何かを一個つくりましたという時に人が乗れるものってほとんどつくれないんですよ。さっき子供が平気で座ってたでしょ。それはすごい価値のあることなんですよ。人の重量ってものすごい負荷なんですよ。その負荷に耐えられるものってなかなかできない。そういう価値を、他のウレタンは壊れた後も楽しめたり、木に関しては空間として寝そべられたりできるものになっていて、比較的わかりやすい価値が見出せたと思うんですよ。で金属チームに限ってはその辺がわからないんだと思う。でもあれはすごい価値があるんですよ。子供が吸われてるというだけで。それで私大人一人が座れるというだけですごく価値のあることだから、そういう価値観を知ってほしい。特に普段の生活の中で、
そういうことを知る機会を持つといいのが理科大なんかはすごくいい先生がそろっているんですよ。意匠の先生だけではなくて構造や設備の先生もかなりのスペシャリストがそろっている、全国的に見てもかなりいい先生がそろっている。構造でいえば、北村先生だとか、皆さんあんまり意識しないでしょう。北村先生のことだけ言うと悪いけれども、うちにいた村先生の研究室出身の人いるからね。そういう理由で北村先生だけをあげるとすると、北村先生は構造の世界ではすごい先生なんですよ。でもすごく設計の好きな先生なんですよ。だからそういう先生の知識やアドバイスを引き出すことが必要だと思うんですよね。
ただおそらく環境の先生だとか、設備の先生だとかにも、そういう先生がたくさんおられると思うんですよ。普段敬遠しがちだけれども、それになんか聞きに行くと冷たいんですよねそういう先生たちって。そんなことできるわけないだろみたいなね、そういうころあるかもねーみたいな。だけどそれでめげないで、
すごい知識をもっている人たちなんだから、その知識をちょっとでも引き出そうと、事前調査をするなりして、ちゃんと知識を持った上で、こんなことはできないでしょうかと、聞いてみてほしい。そういう意識をもっていま作ろうとしているもの、設計しようとしているもの、課題でもそうですけど、そういうところにちゃんと価値を見いだせるといいのではないかと思いますね。
福島
もう圧倒的に美しいものを作ってもらいたい。
これでいいデザインはすごいあふれている、それは一つの存在価値だけど、これがいい!この野田に来なければ、君たちでなければデザインできないようなものをぜひ思考してほしい。これでいいデザインはありすぎ、理科大生は去年これでいいデザインを思考しすぎている。ドンキホーテであろうと世界中で自分だけがこれをデザインしているという気概が非常に弱い、それは理科大の強さでもあり理科大の最大の弱点でもある気がします。絶対にどんな人でさえ僕のデザインで美しいと言わせて見せるそういう気概をぜひこのワークショップで出し合ってほしいなと思います。
金田
かなり刺激的な言葉を頂けたと思いますし、三年生はもちろんかなりのものをつくってくれると期待されているので、それに応えてほしいと思います。今日この場で聞けた言葉が建築学科に身を置いている全員がそれをかみしめてこれから設計に励んでいけるようないい現場になったのではないかなと思っています。以上で今日の座談会を終了します。
|
|
|
|
|
|
|
|
TUSA WORKSHOP 2010 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
TUSA WORKSHOP 2010のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人