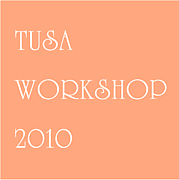金田
ここからは言いたいことがあれば特に3年生があると思うので先生方も含めて議論していただきたいと思います。
金田
まずは星くん。
星
まず質問になるんですけど、前回のワークショップのテーマが「ふれる」ということで
それが企画側と製作者側で理解し合っていなかったのではないかという疑問があり、
このテーマはものすごく漠然としていてそれに付随する問いかけがきちんとできていなかったのではないかと思ったのですが。
金田
テーマは漠然としていました。今回のワークショップというのは1・1を学生がつくるということを考えた時にどういった過程を踏んでいくことができるのかと。それに対して、今の四年生側としては、がむしゃらに
1・1で立ち上げることがどういうことなのかということをしたかった。そこで「ふれる」という言葉自体が漠然としていたけど、1から15までの段階でその言葉自体を手がかりに進めていけたのではないかと。
4年生側としてもテーマ自体に振り回されるということはあったけど、実際に寸法をはかってものを作ったり、ディテールにこだわってつくっていくという過程を経て、仮につくることが不可能となったなら「ふれる」という言葉自体を手がかりに、例えば木材を例として挙げると、規格として線材になり、その中からどいういった新しい試み、あるいは空間がつくりだせるか、ということ自体「ふれる」という言葉に幅があったから
こそ考えれるのではないかと思います。実際やっていた時は、2.3年生の制作者側としてはどうすればいいかわからなくもなっていたであろうが、また我々企画側もそういう場面にバンバン直面していくことで、その場ではよくわからなくても、今こうして振り返ることでその場その場での「ふれる」という言葉自体
それはどういうことなのかちゃんと再考する場が与えられていることによって、例えば「ふれる」という言葉
ひとつについても、いろんな考え方があるし、結局我々としてはディレクションがきちんとできていなくて、
実際に建てたらどういう風になるかということを全く想像できずにワークショップを行っていて、でも結局ディレクションがきちんとできていて成果物が見えている状況よりも経験として、過程を伝えていくことができたのでかなり過程自体は振り回されたけど盛り上がったのではないかと思っている。
星
製作者側としては振り回されたために結果できた作品というものが、それほど価値のあるものにならなかったという思いもあり、一応去年担当したそれぞれの班の代表者に去年の評価をしてもらいたいと思います。
佐々木
木材班です。
作品としては先ほどの話の通り線材がほぼ占めていてもとの木のイメージとは違う線材を用いることにより、ある種何か固いイメージのあるツールを使ってどれだけ木が本来持つ自然的というか柔らかい輪郭のないものがつくれるかということから、隙間と線材を連続させて輪郭をぼやかすような形を表現したかったのだけど、結局「ふれる」というテーマに対する回答が製作者側からのふれるなのか、見る人にとってのものなのか、はたまた身体的にふれるものなのか空間的にふれるものなのか、いろいろ疑問を抱きながら1・1をつくるプレッシャーから結局空間的にふれるということを考えざるを得なくなり、いまになってあれは何だったのか疑問が残る感じです。木材班としては以上です。
木村
金属班です。
金属班はみんなで「ふれる」ことが何を意味するのかを話し合って、その定義づけから始まり、そこからいろいろ進めたんですが、結果瞑想という形で幕を閉じてしまい、自分たちが思い描いていたものとは違うものができてしまったんですが、今金田さんの話を聞いてそもそも「ふれる」というテーマは制作物をつくるテーマとして必要なかったと思いました。モノをつくるうえでは、しっかりしたコンセプトや具体的なテーマがないと最後まで突っ走れないような気がしていて、ふわっとしたテーマで結果クオリティーの高い
しっかりした制作物をつくるのは難しいのではないかと思うので「ふれる」という言葉はコンセプトとしてなりうるのかという疑問があります。
中川
新素材班です。
新素材については、この素材は本当に自分たちにとって新しくて他の木とか金属とは違って全くわからない状態からのスタートだったので、新素材っていうものに自分たちが理解することに必死で正直、製作に
あたって「ふれる」というテーマを念頭に置いてやりきれなかったという事実があるのですが、結果として素材に触れることには出来たのでよかったなとは思っています。
金田
まず3年から「ふれる」というテーマ自体がコンセプトとしてあり得ないんじゃないかという意見をいただいたんですが、まず僕たち企画者側のモチベーションとして1・1の空間をどうにかしてつくってやろうという
きもちがありました。それに対してどういうどういうテーマを与えると1・1の実現性を感じれるだろうか、と考えた時に、「ふれる」という言葉が一番しっくりきました。実際かなりコンセプトとしてはなりえないんじゃないかということでしたが、実際立ち上がった制作物を見てみると、コンセプトを超える作品が出来があったと思っていて、コンセプトというより、実際に素材と直面したり、ジョイントから考えることからは不可能であることなどにどんどん直面していくことで自分たちには何が可能なのかということを考えるという意味では「ふれる」というテーマというかスタンスは僕たちとしては1・1があれだけのものになったという点においては間違っていなかったという風にとらえています。
斉藤
僕ちょっと援護射撃打っていいですか。笑
金田
はい。
斉藤
ワークショップもかれこれ4年見させてもらっていて、確か一昨年が本のある空間で、その前が東京、
その前がサプライズでしょう。で東京と本のある空間、特に本のある空間は、具体的すぎてつくる幅が
すごく狭かった気がしている。結局図書館とか家の中でも本棚とか、じゃあ本棚から構築、想像する家
とかそういうものが出てきて、あんまりその幅としては僕は狭かったんじゃないかという疑問が残る。
要はワークショップとしての位置づけの中での話ではあるけれど。それは面白くないんじゃないかとおもっていた。じゃあぼくがいつも思っているのは、とはいっても僕自身そんな建築にどっぷりひたっているわけではなくて、どっちかっていうと建築を創造するプロセスでとまっていてそれをoutputとしていつもだしている人間ではあるけれど、そこでいつもある疑問っていうのは、建築っていうこと自体が国語なのかそれとも算数なのか。要は算数なら具体的に1+1=2になるんだけど、国語というのはどっちかっていうと今回みたいな「ふれる」とかもうちょっとホワっとした空間とかもっとじゃあ早いかたちとか、そういう抽象的なものから創造するのはどっちかっていうと国語の顔なのかなと思っていて、例えば課題としてどこどこの集合住宅とか、なになにの家を建てなさいとか条件を与えられた時に思考的なプロセスを柔軟にするのはこういう題を持ってくるのはすごくありなんじゃないかと思う。実際にマテリアルに触れてっていうのはすごくありなんじゃないかなと思う。僕実は三年生の前半の課題でブチギレているんだけど、今年の考え方って与えられるのを待っている感じがしていて、実際に実施になった時にぶち当たる壁としてじゃあ、
ほわっとした空間をお願いしますと言われた時にどうつくるかで、最初にうちの班リサーチをガンガンやらして最終的に出てきたものってデータと言葉しかなくて、じゃあそれからどう作ろうっていうその発想というかそこのジャンプが必要で、でそこのジャンプっていうのが僕は一番大切だと思っている。つくるにあたって、だからこのワークショップのプロセスというか題材の決め方というのは、一つの課題ではなくて課題外のワークショップの中でやっていくというのでは、すごくいい訓練になったんじゃないかなとおもう。
で今回三年生すごく参考にしてほしいのは、ワークショップで今見せてもらったみたいにきっちりとドキュメントとってるじゃん。なにから思考して、どういうプロセスを踏んで今自分たちが何を作ってっていうのを毎回毎回アーカイブすることでどこ切っても作品になる。たとえば椅子をつくっているところでも木を切っているところでも全部作品になる。なんだけど、年々そのプロセスっていうのがあんまり大事にされてなくて、結局最終的な成果物を追い求める傾向があるなあと思っていて、特に僕がやっている仕事って個人的にそうなんだけどプロセスってすごく大事だからどこまでちゃんとドキュメントをとっているとか自分の頭の中で、今どの段階にいるのかを知るのはすごく大事なことだと思う。そういう意味では、今回の題材である「ふれる」はよかったと思うし、援護射撃を打ちたい。
佐藤
ぼくは、援護射撃は後でいっぱいしてあげるから、3年生の不満も大事だと思う。僕はむしろ聞きたい。今回出来たものが、たぶんクオリティの問題だと思うんですが、できたもののクオリティが低いんじゃないかっていう意識がつくっている側にはあるんじゃないかと思う。実際作った人としてそういうのは大事だとおもうんです。で、一方でお金の問題だとか時間の問題だとか新しいことにチャレンジするだとか、そういうことの中でどこまで到達できるのかというのもあるんだけれども、それは言い訳としておいといて、どういうところに不満を感じるかというのは結構みんなから聞いたほうがいいと思うんです。だからその木材チームで線材というものをいかに自然に近づけるかを考えていたと思うんですが、それは木材の使い方としてもう少し詳しく話をしてもらえますか。
木材というのは自然に近い形で利用すべきかということなんだろうか。
佐々木
そういうことではなくて、木を素材としてとらえて、木の本来の姿を考えた時に木にひかれる部分はどういうところなのかというのを考えた時に一番最初に木から想像できる部分って今もそこで大地からはえている木の状態のことなんじゃないかと思ったので、その状態にふれるってことがたぶん自分たちの頭の中では無意識的に感じていたんだと思います。普段接しているものとしては線材とかのほうが多いと思うんですけど本来木として「ふれる」を感じるのはそうした自然の状態の木のほうが強いんじゃないかというふうに感じてそう解釈しました。
佐藤
それはその木の幹だったりとか木材の皮を剥がない、ゴテゴテの皮がある状態とか有機的に枝別れしている状態とかのことなんですか?
佐々木
そういうことなんですけど、結局はスケジュールとか予算とかそういう問題に押されて本来「ふれる」に対してやるべき表現をないがしろにしてしまったところがあって、結局空間に走ってあまりその辺のことについては考えられていないという結果になってしまいました。
佐藤
より自然の形態に近いなにかその例えば木陰みたいなものを作りたかったってこと?
佐々木
そこまでは考え切れてはいないです。
佐藤
ウレタンチームは?金属チームでもいいけど。
金属チームが一番クオリティーに対しては不満があると思うんです。
木村
金属班がああいう形を作ったのは、金属というものが他の素材に比べて一番触れがたいというか「ふれる」というコンセプトに対して一番遠い存在だということをみんなが共有していて、その金属をどういう風にすれば人が視覚的にも感覚的にも触れられるのだろうかというところを考えていった結果あのように金属を曲げたりすることで形態的にそれが可能になるんじゃないかという結論に至りましたが、そこで、ふれるってことが考え切れてなくて、結局形的に最後なんだったのかっていう風になってしまったんです。あと金属で不満だったのが構造的な部分で、実際立ち上がったものがジョイントの部分だったりとか金属の自重とか加工性とか結局最後全部積み上がらなくて未完成のまま終わってしまったのが悔しいところでもあり不満を残した部分でもありました。なので意匠的な部分以外の構造などもしっかりプロセスの中に組み込めたらよかったのかなと思いました。
佐藤
金属というのは確かに難しい、金属を扱うのはほんとに難しい、やっぱり君たちが感じている通り接合がすごく難しい。で、一方で金属というのは本当は我々構造家としてはすごく扱いやすいんです。というのは、金属というマテリアルは計算通りに挙動してくれるから。だからそういうワークショップ的なスピード、規模でやるときと、実際の建物をやるときとの感覚若干違うというのはあるけれども、私としては、私は金属が好きなので、鉄骨が好きなので、こういうワークショップで金属を扱ったことは常々あるんだけども、
そのかわり金属を扱うのはすごく難しい。だからもしそういうことが伝わってないんだとしたら、それはぜひ知ってほしい。まあ後でその辺は話すとして、ウレタンチームは?
中川
新素材班は特に出来上がったものに不満などは一切なく、出来上がるまえっていうのは、例えばフィックスするかしないかとかで班の中でもめたりしたんですが、講師の方たちが来る時にある意見としては完成物を見せるためにフィックスするべきだといい、一方では先生方が来るからと言ってフィックスるのはおかしいという意見もあり、結局フィックスしない方向で話がまとまり、それがいま思うといい結果に結びついていて、壊れてもなお子供たちが楽しそうに遊んでいたりして、この素材だからこそ壊れても危険性もなく楽しめるマテリアルであったりして、自分たちが予想しなかったことが次々に起きていって、結果的にいいものができたということはみんながすごく思っているところではあると思います
佐藤
その議論はおもしろいですね。我々が来るからと言って何かやろうとかさ、でもそれはひとつのきっかけだとおもうんですよね。そこである程度のものに到達しておくというのもひとつの選択肢だとおもうんです。それは悪いことではないと思うんです。我々はいつもそういう世界にいる。与えられた期間の中でどこまでやれるか、ということを常にやるんであって、それが延長できるかどうか。というところのせめぎ合いなんです。後何か月伸ばせるんだとかを常に追求している世界だから、それはすごいおもしろい話だと思いますけど。
それで全体を通して「ふれる」ということを少し話をしておくと「ふれる」というのはすごく難しいことかもしれないけど、さっき理科大生に限った事なのかという疑問を投げかけたんですが、今、社会全体がそうなんですが、現代人間が生きてる中で、生活するのに必要なものを自分でつくるということがほとんどなくなっている。無意識に素材のことを知らずに生きていける時代なんです。例えば台風が来た時に窓ガラスが壊れるとか揺れるとかほとんど感じない時代になっている。「ふれる」といわれたときに、そんなこと当たり前じゃないかと思うでしょう。でも実際にそれができてない。そこが大事なところなんです。そこに気づかないといけないんです。それが古き良き時代にもどろうと言っているのではなく、それが説明されてはじめて認識するんじゃなくて、実感として個々に体験されなければいけない。だからこのワークショップはそれが体験できる貴重なイベントなんです。だから、そこを自分で解釈するというか、例えば「ふれる」という言葉が与えられた時に自分のやりたいことに関連させて、拡大解釈するっていうのは建築学科の十八番なんですよ。それが意識的であっても無意識的であっても。自分のやりたいことに関連させる、関連させて拡大解釈するというくんれんというかな、、、まあ得意技ですよね。先ほど斎藤さんからもあったように指示を受けてそれに従って動く。これはどういう解釈なんだということの元に納得して動くという状況ではなくて「ふれる」と言われたら、じゃあふれるを自分なりに解釈するとこういうことなんだな、というように動いて自分で盛り上げるということがやれるようになると参加していておもしろくもなりますよね。
もうひとつだけ言っておくとこうしたイベントもしくは実際建築をたてる現場。常にドタバタですよ。
前準備を確実にやって着実に進めていこうなんてことはありえない。だからそれはそれで楽しまなければいけない。常に我々はドタバタですよね。準備もドタバタ、こんな状況で着工できるのかと設計がこんな状態で着工していいのかという状態ではじまるんです。それは常にそうで、だけど常にチェックポイントがあって常にみんなこういうものが出来上がるだろうというイメージを共有した元で見切り発車をしていくんです。だからそれも大事なことなんです。笑
斉藤
ものつくっていて、僕もそれには同感で、僕もドタバタじゃなかったことってなくて、なんかそっちのほうが実はいいものができそうな気がする。これ最近ようやくわかったんだけど、長いスパンが与えられたと、例えば三か月与えられて予算がこれこれあって、お題はこれでこれを作りなさいって言われて。でも実際は1週間で作ったほうがいいものができる確率って高いなと最近僕はすごくそう思うんだけど、それはいいのか悪いのかわからないんだけど、なんかその思考の瞬発力というか、例えばものをつくる瞬発力って結構あるなとおもっていて、だから理科大のワークショップで毎年24時間で何かをつくるっていうのは僕はすごくいい訓練だし、いい核融合が起きるんじゃないかなと思う。今になってようやくわかったことなんだけど。それは往々にしてあるなと、ドタバタを楽しむというのは今おっしゃったように醍醐味だなと。終わった後のビールがうまいとはよく言ったもので。笑
ここからは言いたいことがあれば特に3年生があると思うので先生方も含めて議論していただきたいと思います。
金田
まずは星くん。
星
まず質問になるんですけど、前回のワークショップのテーマが「ふれる」ということで
それが企画側と製作者側で理解し合っていなかったのではないかという疑問があり、
このテーマはものすごく漠然としていてそれに付随する問いかけがきちんとできていなかったのではないかと思ったのですが。
金田
テーマは漠然としていました。今回のワークショップというのは1・1を学生がつくるということを考えた時にどういった過程を踏んでいくことができるのかと。それに対して、今の四年生側としては、がむしゃらに
1・1で立ち上げることがどういうことなのかということをしたかった。そこで「ふれる」という言葉自体が漠然としていたけど、1から15までの段階でその言葉自体を手がかりに進めていけたのではないかと。
4年生側としてもテーマ自体に振り回されるということはあったけど、実際に寸法をはかってものを作ったり、ディテールにこだわってつくっていくという過程を経て、仮につくることが不可能となったなら「ふれる」という言葉自体を手がかりに、例えば木材を例として挙げると、規格として線材になり、その中からどいういった新しい試み、あるいは空間がつくりだせるか、ということ自体「ふれる」という言葉に幅があったから
こそ考えれるのではないかと思います。実際やっていた時は、2.3年生の制作者側としてはどうすればいいかわからなくもなっていたであろうが、また我々企画側もそういう場面にバンバン直面していくことで、その場ではよくわからなくても、今こうして振り返ることでその場その場での「ふれる」という言葉自体
それはどういうことなのかちゃんと再考する場が与えられていることによって、例えば「ふれる」という言葉
ひとつについても、いろんな考え方があるし、結局我々としてはディレクションがきちんとできていなくて、
実際に建てたらどういう風になるかということを全く想像できずにワークショップを行っていて、でも結局ディレクションがきちんとできていて成果物が見えている状況よりも経験として、過程を伝えていくことができたのでかなり過程自体は振り回されたけど盛り上がったのではないかと思っている。
星
製作者側としては振り回されたために結果できた作品というものが、それほど価値のあるものにならなかったという思いもあり、一応去年担当したそれぞれの班の代表者に去年の評価をしてもらいたいと思います。
佐々木
木材班です。
作品としては先ほどの話の通り線材がほぼ占めていてもとの木のイメージとは違う線材を用いることにより、ある種何か固いイメージのあるツールを使ってどれだけ木が本来持つ自然的というか柔らかい輪郭のないものがつくれるかということから、隙間と線材を連続させて輪郭をぼやかすような形を表現したかったのだけど、結局「ふれる」というテーマに対する回答が製作者側からのふれるなのか、見る人にとってのものなのか、はたまた身体的にふれるものなのか空間的にふれるものなのか、いろいろ疑問を抱きながら1・1をつくるプレッシャーから結局空間的にふれるということを考えざるを得なくなり、いまになってあれは何だったのか疑問が残る感じです。木材班としては以上です。
木村
金属班です。
金属班はみんなで「ふれる」ことが何を意味するのかを話し合って、その定義づけから始まり、そこからいろいろ進めたんですが、結果瞑想という形で幕を閉じてしまい、自分たちが思い描いていたものとは違うものができてしまったんですが、今金田さんの話を聞いてそもそも「ふれる」というテーマは制作物をつくるテーマとして必要なかったと思いました。モノをつくるうえでは、しっかりしたコンセプトや具体的なテーマがないと最後まで突っ走れないような気がしていて、ふわっとしたテーマで結果クオリティーの高い
しっかりした制作物をつくるのは難しいのではないかと思うので「ふれる」という言葉はコンセプトとしてなりうるのかという疑問があります。
中川
新素材班です。
新素材については、この素材は本当に自分たちにとって新しくて他の木とか金属とは違って全くわからない状態からのスタートだったので、新素材っていうものに自分たちが理解することに必死で正直、製作に
あたって「ふれる」というテーマを念頭に置いてやりきれなかったという事実があるのですが、結果として素材に触れることには出来たのでよかったなとは思っています。
金田
まず3年から「ふれる」というテーマ自体がコンセプトとしてあり得ないんじゃないかという意見をいただいたんですが、まず僕たち企画者側のモチベーションとして1・1の空間をどうにかしてつくってやろうという
きもちがありました。それに対してどういうどういうテーマを与えると1・1の実現性を感じれるだろうか、と考えた時に、「ふれる」という言葉が一番しっくりきました。実際かなりコンセプトとしてはなりえないんじゃないかということでしたが、実際立ち上がった制作物を見てみると、コンセプトを超える作品が出来があったと思っていて、コンセプトというより、実際に素材と直面したり、ジョイントから考えることからは不可能であることなどにどんどん直面していくことで自分たちには何が可能なのかということを考えるという意味では「ふれる」というテーマというかスタンスは僕たちとしては1・1があれだけのものになったという点においては間違っていなかったという風にとらえています。
斉藤
僕ちょっと援護射撃打っていいですか。笑
金田
はい。
斉藤
ワークショップもかれこれ4年見させてもらっていて、確か一昨年が本のある空間で、その前が東京、
その前がサプライズでしょう。で東京と本のある空間、特に本のある空間は、具体的すぎてつくる幅が
すごく狭かった気がしている。結局図書館とか家の中でも本棚とか、じゃあ本棚から構築、想像する家
とかそういうものが出てきて、あんまりその幅としては僕は狭かったんじゃないかという疑問が残る。
要はワークショップとしての位置づけの中での話ではあるけれど。それは面白くないんじゃないかとおもっていた。じゃあぼくがいつも思っているのは、とはいっても僕自身そんな建築にどっぷりひたっているわけではなくて、どっちかっていうと建築を創造するプロセスでとまっていてそれをoutputとしていつもだしている人間ではあるけれど、そこでいつもある疑問っていうのは、建築っていうこと自体が国語なのかそれとも算数なのか。要は算数なら具体的に1+1=2になるんだけど、国語というのはどっちかっていうと今回みたいな「ふれる」とかもうちょっとホワっとした空間とかもっとじゃあ早いかたちとか、そういう抽象的なものから創造するのはどっちかっていうと国語の顔なのかなと思っていて、例えば課題としてどこどこの集合住宅とか、なになにの家を建てなさいとか条件を与えられた時に思考的なプロセスを柔軟にするのはこういう題を持ってくるのはすごくありなんじゃないかと思う。実際にマテリアルに触れてっていうのはすごくありなんじゃないかなと思う。僕実は三年生の前半の課題でブチギレているんだけど、今年の考え方って与えられるのを待っている感じがしていて、実際に実施になった時にぶち当たる壁としてじゃあ、
ほわっとした空間をお願いしますと言われた時にどうつくるかで、最初にうちの班リサーチをガンガンやらして最終的に出てきたものってデータと言葉しかなくて、じゃあそれからどう作ろうっていうその発想というかそこのジャンプが必要で、でそこのジャンプっていうのが僕は一番大切だと思っている。つくるにあたって、だからこのワークショップのプロセスというか題材の決め方というのは、一つの課題ではなくて課題外のワークショップの中でやっていくというのでは、すごくいい訓練になったんじゃないかなとおもう。
で今回三年生すごく参考にしてほしいのは、ワークショップで今見せてもらったみたいにきっちりとドキュメントとってるじゃん。なにから思考して、どういうプロセスを踏んで今自分たちが何を作ってっていうのを毎回毎回アーカイブすることでどこ切っても作品になる。たとえば椅子をつくっているところでも木を切っているところでも全部作品になる。なんだけど、年々そのプロセスっていうのがあんまり大事にされてなくて、結局最終的な成果物を追い求める傾向があるなあと思っていて、特に僕がやっている仕事って個人的にそうなんだけどプロセスってすごく大事だからどこまでちゃんとドキュメントをとっているとか自分の頭の中で、今どの段階にいるのかを知るのはすごく大事なことだと思う。そういう意味では、今回の題材である「ふれる」はよかったと思うし、援護射撃を打ちたい。
佐藤
ぼくは、援護射撃は後でいっぱいしてあげるから、3年生の不満も大事だと思う。僕はむしろ聞きたい。今回出来たものが、たぶんクオリティの問題だと思うんですが、できたもののクオリティが低いんじゃないかっていう意識がつくっている側にはあるんじゃないかと思う。実際作った人としてそういうのは大事だとおもうんです。で、一方でお金の問題だとか時間の問題だとか新しいことにチャレンジするだとか、そういうことの中でどこまで到達できるのかというのもあるんだけれども、それは言い訳としておいといて、どういうところに不満を感じるかというのは結構みんなから聞いたほうがいいと思うんです。だからその木材チームで線材というものをいかに自然に近づけるかを考えていたと思うんですが、それは木材の使い方としてもう少し詳しく話をしてもらえますか。
木材というのは自然に近い形で利用すべきかということなんだろうか。
佐々木
そういうことではなくて、木を素材としてとらえて、木の本来の姿を考えた時に木にひかれる部分はどういうところなのかというのを考えた時に一番最初に木から想像できる部分って今もそこで大地からはえている木の状態のことなんじゃないかと思ったので、その状態にふれるってことがたぶん自分たちの頭の中では無意識的に感じていたんだと思います。普段接しているものとしては線材とかのほうが多いと思うんですけど本来木として「ふれる」を感じるのはそうした自然の状態の木のほうが強いんじゃないかというふうに感じてそう解釈しました。
佐藤
それはその木の幹だったりとか木材の皮を剥がない、ゴテゴテの皮がある状態とか有機的に枝別れしている状態とかのことなんですか?
佐々木
そういうことなんですけど、結局はスケジュールとか予算とかそういう問題に押されて本来「ふれる」に対してやるべき表現をないがしろにしてしまったところがあって、結局空間に走ってあまりその辺のことについては考えられていないという結果になってしまいました。
佐藤
より自然の形態に近いなにかその例えば木陰みたいなものを作りたかったってこと?
佐々木
そこまでは考え切れてはいないです。
佐藤
ウレタンチームは?金属チームでもいいけど。
金属チームが一番クオリティーに対しては不満があると思うんです。
木村
金属班がああいう形を作ったのは、金属というものが他の素材に比べて一番触れがたいというか「ふれる」というコンセプトに対して一番遠い存在だということをみんなが共有していて、その金属をどういう風にすれば人が視覚的にも感覚的にも触れられるのだろうかというところを考えていった結果あのように金属を曲げたりすることで形態的にそれが可能になるんじゃないかという結論に至りましたが、そこで、ふれるってことが考え切れてなくて、結局形的に最後なんだったのかっていう風になってしまったんです。あと金属で不満だったのが構造的な部分で、実際立ち上がったものがジョイントの部分だったりとか金属の自重とか加工性とか結局最後全部積み上がらなくて未完成のまま終わってしまったのが悔しいところでもあり不満を残した部分でもありました。なので意匠的な部分以外の構造などもしっかりプロセスの中に組み込めたらよかったのかなと思いました。
佐藤
金属というのは確かに難しい、金属を扱うのはほんとに難しい、やっぱり君たちが感じている通り接合がすごく難しい。で、一方で金属というのは本当は我々構造家としてはすごく扱いやすいんです。というのは、金属というマテリアルは計算通りに挙動してくれるから。だからそういうワークショップ的なスピード、規模でやるときと、実際の建物をやるときとの感覚若干違うというのはあるけれども、私としては、私は金属が好きなので、鉄骨が好きなので、こういうワークショップで金属を扱ったことは常々あるんだけども、
そのかわり金属を扱うのはすごく難しい。だからもしそういうことが伝わってないんだとしたら、それはぜひ知ってほしい。まあ後でその辺は話すとして、ウレタンチームは?
中川
新素材班は特に出来上がったものに不満などは一切なく、出来上がるまえっていうのは、例えばフィックスするかしないかとかで班の中でもめたりしたんですが、講師の方たちが来る時にある意見としては完成物を見せるためにフィックスするべきだといい、一方では先生方が来るからと言ってフィックスるのはおかしいという意見もあり、結局フィックスしない方向で話がまとまり、それがいま思うといい結果に結びついていて、壊れてもなお子供たちが楽しそうに遊んでいたりして、この素材だからこそ壊れても危険性もなく楽しめるマテリアルであったりして、自分たちが予想しなかったことが次々に起きていって、結果的にいいものができたということはみんながすごく思っているところではあると思います
佐藤
その議論はおもしろいですね。我々が来るからと言って何かやろうとかさ、でもそれはひとつのきっかけだとおもうんですよね。そこである程度のものに到達しておくというのもひとつの選択肢だとおもうんです。それは悪いことではないと思うんです。我々はいつもそういう世界にいる。与えられた期間の中でどこまでやれるか、ということを常にやるんであって、それが延長できるかどうか。というところのせめぎ合いなんです。後何か月伸ばせるんだとかを常に追求している世界だから、それはすごいおもしろい話だと思いますけど。
それで全体を通して「ふれる」ということを少し話をしておくと「ふれる」というのはすごく難しいことかもしれないけど、さっき理科大生に限った事なのかという疑問を投げかけたんですが、今、社会全体がそうなんですが、現代人間が生きてる中で、生活するのに必要なものを自分でつくるということがほとんどなくなっている。無意識に素材のことを知らずに生きていける時代なんです。例えば台風が来た時に窓ガラスが壊れるとか揺れるとかほとんど感じない時代になっている。「ふれる」といわれたときに、そんなこと当たり前じゃないかと思うでしょう。でも実際にそれができてない。そこが大事なところなんです。そこに気づかないといけないんです。それが古き良き時代にもどろうと言っているのではなく、それが説明されてはじめて認識するんじゃなくて、実感として個々に体験されなければいけない。だからこのワークショップはそれが体験できる貴重なイベントなんです。だから、そこを自分で解釈するというか、例えば「ふれる」という言葉が与えられた時に自分のやりたいことに関連させて、拡大解釈するっていうのは建築学科の十八番なんですよ。それが意識的であっても無意識的であっても。自分のやりたいことに関連させる、関連させて拡大解釈するというくんれんというかな、、、まあ得意技ですよね。先ほど斎藤さんからもあったように指示を受けてそれに従って動く。これはどういう解釈なんだということの元に納得して動くという状況ではなくて「ふれる」と言われたら、じゃあふれるを自分なりに解釈するとこういうことなんだな、というように動いて自分で盛り上げるということがやれるようになると参加していておもしろくもなりますよね。
もうひとつだけ言っておくとこうしたイベントもしくは実際建築をたてる現場。常にドタバタですよ。
前準備を確実にやって着実に進めていこうなんてことはありえない。だからそれはそれで楽しまなければいけない。常に我々はドタバタですよね。準備もドタバタ、こんな状況で着工できるのかと設計がこんな状態で着工していいのかという状態ではじまるんです。それは常にそうで、だけど常にチェックポイントがあって常にみんなこういうものが出来上がるだろうというイメージを共有した元で見切り発車をしていくんです。だからそれも大事なことなんです。笑
斉藤
ものつくっていて、僕もそれには同感で、僕もドタバタじゃなかったことってなくて、なんかそっちのほうが実はいいものができそうな気がする。これ最近ようやくわかったんだけど、長いスパンが与えられたと、例えば三か月与えられて予算がこれこれあって、お題はこれでこれを作りなさいって言われて。でも実際は1週間で作ったほうがいいものができる確率って高いなと最近僕はすごくそう思うんだけど、それはいいのか悪いのかわからないんだけど、なんかその思考の瞬発力というか、例えばものをつくる瞬発力って結構あるなとおもっていて、だから理科大のワークショップで毎年24時間で何かをつくるっていうのは僕はすごくいい訓練だし、いい核融合が起きるんじゃないかなと思う。今になってようやくわかったことなんだけど。それは往々にしてあるなと、ドタバタを楽しむというのは今おっしゃったように醍醐味だなと。終わった後のビールがうまいとはよく言ったもので。笑
|
|
|
|
|
|
|
|
TUSA WORKSHOP 2010 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
TUSA WORKSHOP 2010のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6480人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19255人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人