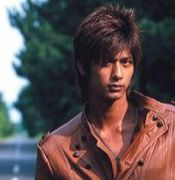|
|
|
|
コメント(181)
日本からの寝台列車の撤退が本格化したのは、やはり80年代の辺りからだといえます。
80年の秋のダイヤ改正では、北海道の急行すずらんは航空機に東京〜北海道を航空機にシェアを奪われて相次ぐ需要低下、普通からまつは翌年の石勝線開業を控えての廃止の一面があったといえます。
東日本の特急ゆうづるの一部の二段式寝台化と、北海道連絡をメインにしている電車1往復、北東北をメインにしている客車1往復の季節降格。
それに関連して、秋田の横綱あけぼの24系化による20系客車の寝台特急からの撤退。
西日本の航空機やフェリーや新幹線に転移が進んで利用不振が続く、山陽本線の夜行急行全廃を始めとして、特急明星1往復(電車)と特急彗星1往復(客車)の一部廃止。
この結果して残存したのが、特急なは、特急彗星の電車1往復、客車1往復、特急あかつき2往復、特急明星の電車1往復、客車1往復、季節1往復の他に名古屋始発の特急金星の合計9往復。
電車寝台使用列車中心に航空機の最終便の後に出発して、航空機の初便より前に到着するダイヤに建て替えした。
80年の秋のダイヤ改正では、北海道の急行すずらんは航空機に東京〜北海道を航空機にシェアを奪われて相次ぐ需要低下、普通からまつは翌年の石勝線開業を控えての廃止の一面があったといえます。
東日本の特急ゆうづるの一部の二段式寝台化と、北海道連絡をメインにしている電車1往復、北東北をメインにしている客車1往復の季節降格。
それに関連して、秋田の横綱あけぼの24系化による20系客車の寝台特急からの撤退。
西日本の航空機やフェリーや新幹線に転移が進んで利用不振が続く、山陽本線の夜行急行全廃を始めとして、特急明星1往復(電車)と特急彗星1往復(客車)の一部廃止。
この結果して残存したのが、特急なは、特急彗星の電車1往復、客車1往復、特急あかつき2往復、特急明星の電車1往復、客車1往復、季節1往復の他に名古屋始発の特急金星の合計9往復。
電車寝台使用列車中心に航空機の最終便の後に出発して、航空機の初便より前に到着するダイヤに建て替えした。
>>[169] ビジネス旅客は当然だけど、どうしても、速さの方を選択します。
結局の所からして、時間が短い方が出張手当が安く付くからです。
そこにも寝台列車の撤退の原因があるといえます。もう1つ見逃せないなのが、航空機の影響で、中心からの空港ヘのアクセスの時間、搭乗手続きに掛かる時間、搭乗する時間、搭乗を終えて空港からの目的地ヘのアクセスの時間をだいたい見積もると、やはり4時間辺りです。
そうなると4時間が交通機関選択の分かれ道であるといわざるを得ません。
4時間以上掛かるようだと、当然だけど鉄道に勝ち目がないのは、否定出来ない事実です。
夜行列車が廃れていった、もう1つの原因は宿泊施設の多様化にもあります。
もう1つは前日の新幹線や航空機の最終便で、前日ホテルに宿泊した方が安上がりなケースも出てきました。
特に大阪〜大分のように、寝台特急のB寝台利用が航空機よりも5000円以上も上回るようでは、論外です。
結局の所からして、時間が短い方が出張手当が安く付くからです。
そこにも寝台列車の撤退の原因があるといえます。もう1つ見逃せないなのが、航空機の影響で、中心からの空港ヘのアクセスの時間、搭乗手続きに掛かる時間、搭乗する時間、搭乗を終えて空港からの目的地ヘのアクセスの時間をだいたい見積もると、やはり4時間辺りです。
そうなると4時間が交通機関選択の分かれ道であるといわざるを得ません。
4時間以上掛かるようだと、当然だけど鉄道に勝ち目がないのは、否定出来ない事実です。
夜行列車が廃れていった、もう1つの原因は宿泊施設の多様化にもあります。
もう1つは前日の新幹線や航空機の最終便で、前日ホテルに宿泊した方が安上がりなケースも出てきました。
特に大阪〜大分のように、寝台特急のB寝台利用が航空機よりも5000円以上も上回るようでは、論外です。
日本の夜行列車が、国土の狭い韓国よりも撤退が早かった、もう1つの原因はダイヤ編成の仕方にもあるといえます。
日本の夜行列車の出発時間は大概にして、18時〜0時の時間帯で、目的地に到着するのは、大概にして、5時〜9時の朝の時間帯に組んでいるのが基本です。
韓国の夜行列車の到着時間帯は大概にして3時〜5時です。
ここで一番の問題になるのは、通勤列車で日本はその時間帯は通勤ラッシュに引っ掛かりやすい時間帯だからです。
その結果として、通勤列車の増発が思うように出来ないといった問題があるからです。
運営する側の都合からして夜行列車の存在が厄介であることは、韓国の夜行列車の到着時間帯と比較すると解るともいえます。
日本の夜行列車の出発時間は大概にして、18時〜0時の時間帯で、目的地に到着するのは、大概にして、5時〜9時の朝の時間帯に組んでいるのが基本です。
韓国の夜行列車の到着時間帯は大概にして3時〜5時です。
ここで一番の問題になるのは、通勤列車で日本はその時間帯は通勤ラッシュに引っ掛かりやすい時間帯だからです。
その結果として、通勤列車の増発が思うように出来ないといった問題があるからです。
運営する側の都合からして夜行列車の存在が厄介であることは、韓国の夜行列車の到着時間帯と比較すると解るともいえます。
寝台車・食堂車が姿を消す原因のもう1つは、火災事故(特に昭和47年の急行きたぐにの火災事故)などを始めとした保安管理上の問題(警備・清掃・設備管理)や開放式寝台がカーテン1枚で仕切るだけというのもあるけれど、開放式寝台の上中段が梯子を使って昇降するという、社会福祉上の問題(開放式寝台では車椅子専用のスペースを提供しにくい)。
もう1つは寝台列車や食堂車が連結されている列車は当然だけど、長距離を走行する為にダイヤが乱れた時に他の線区にその影響が波及するという、運転計画上の問題がある。
新幹線は最大座席数が100席提供出来るのに対して、寝台列車はB寝台を基準にすると、二段式寝台で34人、三段式寝台で最大48人しか提供出来ないといった接客サービスの提供上の問題がある。
もう1つは寝台列車や食堂車が連結されている列車は当然だけど、長距離を走行する為にダイヤが乱れた時に他の線区にその影響が波及するという、運転計画上の問題がある。
新幹線は最大座席数が100席提供出来るのに対して、寝台列車はB寝台を基準にすると、二段式寝台で34人、三段式寝台で最大48人しか提供出来ないといった接客サービスの提供上の問題がある。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
悪いか?鉄道マニアで… 更新情報
-
最新のアンケート