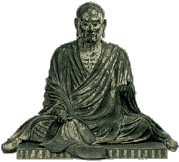大日如来 - Wikipediaから、一部抜粋。
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ (महावैरोचन [mahaavairocana])は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる汎神論的な如来(法身仏)の一尊。その光明が遍く照らすところから遍照、または大日という。
三昧耶形は、金剛界曼荼羅では宝塔、胎蔵曼荼羅では五輪塔。種子(種字)は金剛界曼荼羅ではバン(vaM)、胎蔵曼荼羅ではアーク(aaH)またはア(a)。
概要
大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の教主であり、大日経の説く胎蔵曼荼羅中台八葉院九尊の主である。また金剛頂経の説く金剛界曼荼羅五智如来の中心。空海の開いた真言宗において、究極的には修行者自身と一体化すべきものとして最も重要な仏陀である。不動明王は、密教の根本尊である大日如来の化身、あるいはその内証(内心の決意)を表現したものであると見なされている。
後期密教を大幅に取り入れたチベット仏教でも、大日如来は金剛界五仏(五智如来)の中心として尊崇される。チベット仏教では、宝飾品を身に纏わずに通常の如来の姿で表現されたり、あるいは多面仏として描かれることもある。
像形は、宝冠をはじめ瓔珞などの豪華な装身具を身に着けた、菩薩のような姿の坐像として表現される。これは古代インドの王族の姿を模したものである。一般に如来は装身具を一切身に着けない薄衣の姿で表現されるが、大日如来は宇宙そのもの存在を装身具の如く身にまとった者として、特に王者の姿で表されるのである。 印相は、金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結ぶ。
ヴィローチャナとの関連性
大日如来をインド神話のアスラ神族の王ヴィローチャナに求める学説がある。この名が華厳経の教主の毘盧遮那仏(ヴァイローチャナ)と類似することから、毘盧遮那仏から発展した大日如来とも同一視するというもである。この説は、チャーンドギヤ・ウパニシャッドの説話を根拠としているようだ。 また、インドの叙事詩「マハーバーラタ」においては、ヴィローチャナとは単に太陽神のことを指す場合があり、必ずしも特定のアスラ王を意味するわけではない。[1]
アフラ・マズダーとの関連性
大日如来(摩訶毘盧遮那仏、マハー・ヴァイローチャナ)の成立の起源を、ゾロアスター教の善の最高神アフラ・マズダーに求める学説がある。この説は太陽の属性と智の属性、火を信奉することを根拠としている。[2]
華厳経と盧舎那仏
大仏は姿の上では釈迦如来など他の如来像と区別がつかないが、華厳経に説かれる盧舎那仏という名の仏である。華厳経は西暦400年前後に中央アジアで成立し、中国経由で日本へもたらされた仏教経典で、60巻本、80巻本、40巻本の3種類の漢訳本があるが、うち奈良時代に日本へもたらされたのは60巻本と80巻本である。前者は5世紀、東晋の仏駄跋陀羅訳で「旧訳」(くやく)、「六十華厳」といい、後者は7世紀末、唐の実叉難陀訳で「新訳」、「八十華厳」という。盧舎那仏はこの華厳経に説く「蓮華蔵世界」の中心的存在であり、世界の存在そのものを象徴する絶対的な仏である。六十華厳では「盧舎那仏」、八十華厳では「毘盧遮那仏」と表記されるが、これらの原語はサンスクリットの「ヴァイローチャナ」であり、密教における大日如来(マハー・ヴァイローチャナ)と語源を等しくする。
東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、一般に「奈良の大仏」として知られる仏像で、東大寺大仏殿(金堂)の本尊である。聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会(かいげんくようえ、魂入れの儀式)が行われたが、現存する像は中世・近世の補修がはなはだしく、当初の部分は台座、腹、指の一部など、ごく一部が残るにすぎない。「銅造盧舎那仏坐像」の名で彫刻部門の国宝に指定されている。
大仏の正式名称は「盧舎那仏坐像」、大仏殿の正式名称は「東大寺金堂」であるが、本項では以下「大仏」、「大仏殿」と呼称する。
なお、奈良の東大寺は「行基菩薩」が関わったとされております。
「民衆のために活躍した行基は740年(天平12年)から大仏建立に協力する。このため「行基転向論」(民衆のため活動した行基が朝廷側の僧侶になったとする説)があるが、一般的には権力側が行基の民衆に対する影響力を利用したのであり、行基が権力者の側についたのではないと考えられている。741年(天平13年)3月に聖武天皇が恭仁京郊外の泉橋院で行基と会見し、同15年東大寺の大仏造造営の勧進に起用されている。勧進の効果は大きく、745年(天平17年)に朝廷より日本最初の大僧正の位を贈られた。」
以下、四国霊場八十八ヵ所をダイジェストで紹介します。
第七十五番・五岳山・「善通寺」・誕生院
本尊・薬師如来(座像一丈六尺)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派総本山
住所・香川県善通寺市善通寺町3〜3〜1
略縁起
弘法大師ご誕生の霊蹟である。
寺は屏風ヶ浦五岳山誕生院・総本山善通寺と号し、真言宗善通寺派の総本山である。
唐から帰朝した大師は大同二年(807)先祖の氏寺を建立せんとして、父善通郷から寺領として荘園四町余を拝受し、そこにかつて学んだ唐の青竜寺に模した堂宇を建てた。
寺号は父の名をとって、善通寺と命名。山号は背後の五つの山にちなんで五岳山と号し、院号は大師誕生せしところより誕生院と名づけられたという。
境内にはご両親及び稚児大師木像、産湯の井戸、御影池、瞬目大師、二十日橋、後嵯峨、亀山、後宇多の三帝御廊、大樟、法然上人逆修塔、足利尊氏利生塔仙遊ヶ原、西行庵と久之松、旅大師、雲気、大麻など五大明神があり、国宝に行基菩薩作地蔵尊、大師作吉祥天、大師母公筆の法華経序品一巻や三国伝来の金銅錫杖がある。
広大な境内に建つ五重の塔はときとして目も覚めるような黄金色に包まれて映える事がある。
詠歌
われすまば、よもきえはてじ、善通寺、ふかきちかいの、のりのともしび。
八十九メートルの戒壇めぐり
仁王門をくぐれば、西院坊の御影堂に進む。その地下に、能満所願の本尊をお祀りした戒壇めぐりがある。
真っ暗な中を、左手で壁をなでながら89メートルを行く。
だんだん怖くなり「南無大師遍照金剛」が自然に口に出る。中程の、大師がお生まれになった下の所に祭壇が設けられてあり、その御灯明の明るさでほっとする。
第七十三番・我拝師山・「出釈迦寺」・求聞持院
本尊・釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県善通寺市吉原町1091
略縁起
弘法大師七歳の時、仏道にはいる証しを得ようとして、四八一メートルの倭斯濃山(わしのざん)の頂きに立ち「仏道に入り、衆生を救わんとするわが願い、成就するものならば霊験を、さもなくば、賭したこの身を諸仏に奉げる。」と念じて截りたつ断崖から身を躍らせた。と、落下する大師の下方に紫雲がたなびき、蓮華の花に座した釈迦如来が出現「一生成仏」の宣を授け、大師の願いは叶えられたという。
そこで大師は、出現した釈迦如来の尊像を刻んで本尊とし、出釈迦寺と命名の寺をその麓に創建すると共に、得た霊験から山号を我拝師山と改称せられた。
大師が命をかけた霊蹟は捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがけぜんじょう)といい、寺より十八キロほど登った山の断崖に奥の院としてあり、麓の寺と共に衆生済度発願の根本道場として残っている。
詠歌
まよいぬる、とくどぅ衆生、すくわんと、とうとき山に、いずるしゃかでら。
西行法師の山里庵
仁安三年(1168)西行法師がここ讃岐の国へ下って来た。それは一つには歌の道の友であった崇徳上皇の陵(山峰)に詣でることであり、今一つは僧となった身として、弘法大師の遺跡を訪うことであった。
この寺の裏山に山里庵という庵を結んでいたことが、その歌集「山家集」に書かれている。
第二十四番・室戸山・「最御崎寺」(ほつみさきじ)・明星院
本尊・虚空菩薩(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗豊山派
住所・高知県室戸市室戸岬町
略縁起
大師十九歳のとき、室戸岬を訪れ、御蔵洞(みくらどう)という海に面した暗い洞窟の中で求聞持の法を徹夜で修行された。
そして、その徹夜が数日間に及んだとき、輝いていた明星が飛来して、口中にはいりしことより、この地が仏法に悉地であると感得された。
そこで、大師は「法性の、室戸といえどわれ住めば、有為のなみかぜ、たたぬ日ぞなき」と詠まれたという。
その後、大同二年(807)唐の国より大望を果たして帰国した大師は、嵯峨天皇の勅願を奉じて再び室戸岬を訪れ伽藍を建立。
虚空菩薩を刻んで本尊として安置した。
寺のその後は、前述の嵯峨天皇はもとより、歴代皇家の尊信を得、また足利幕府も土佐の祈願所に定めたという。
以降も各武将の寄進が多く繁栄を重ねた。
指定を受けた国宝には薬師如来、月光菩薩、如意輪観音などがあり、境内には 大師の奇跡とされている明星石、くわず芋がある。
詠歌
明星の、出でぬるかたの東寺、暗き迷いは、などかあらまじ。
大師が「空海」と改名された所
大師は十八歳で、自分の進む道は仏教だと悟られた。
しかし、当時の奈良仏教には満足出来ず、大峰・高野に入り、阿波の大龍寺まで修行し、ここ室戸の先端に立って、つまり大自然の真ん中に入ることによってほんとの悟りを得た。
それまでの無空、如空、教海から、空海という名前に、この地で改めたのだ。
第一番・竺和山・「霊山寺」・一条院
本尊 釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基 行基菩薩
宗派・真言宗高野派
住所・徳島県鳴門市大麻町坂東
略縁起
天平の頃、聖武天皇の勅願により、行基菩薩が開基した寺。
この開基より時代が経過した弘仁六年、弘法大師は、四国に八十八ヶ所の霊場を開こうと祈願された。
それは、仏教の理、つまり、五転の法則に従うものである。
大師は四国霊場の開創に当たってその著書「十住心論」に位置づけてあるように、四国の地に大日如来の胎蔵界四重円壇のマンダラ道場を求め、各国を発心、修業、菩薩、涅槃とお定めになった。
難しく書きましたが、ようするに心身救済の霊場であり、人間が持っている八十八の煩悩を消滅せんがためのものです。
そこで、大師は四国の東北の地を基点にして右回りの霊場をと考えられて鳴門へ来錫されたとき、空中に光明輝く諸仏を感得した。
大師はその状景から、釈迦如来が印度の鷲峰山(霊鷲山)で説法している姿を連想され、天竺の霊山を移す意で、竺和山・霊山寺と名付け、持仏の釈迦誕生仏を本尊前に納めた後、八十八ヶ所の第一番寺と定められた。
詠歌
霊山の、釈迦のみ前に、めぐりきて、よろずの罪も、消えうせにけり。
札はじめは大師に倣ってこの寺から
四国遍路は、その出身地によって、どこから礼はじめをしても良いと言われるが、正式にはこの霊山寺から出発することになっている。
例えば、三百年以上も前の遍路記、承応二年(1653)澄禅という人の「四国辺路」にも、「大師ハ阿波ノ北分十里ヶ所霊山寺ヲ最初ニシテ阿波土佐伊予讃岐ト順ニ御修行也」とある。
ここ、一番札所霊山寺は、「聖武天皇の勅願により、行基菩薩が開基した寺。」となっています。
弘法大師空海と、行基菩薩は、四国霊場の磁場作りに係わっています。<m(__)m>
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ (महावैरोचन [mahaavairocana])は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる汎神論的な如来(法身仏)の一尊。その光明が遍く照らすところから遍照、または大日という。
三昧耶形は、金剛界曼荼羅では宝塔、胎蔵曼荼羅では五輪塔。種子(種字)は金剛界曼荼羅ではバン(vaM)、胎蔵曼荼羅ではアーク(aaH)またはア(a)。
概要
大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の教主であり、大日経の説く胎蔵曼荼羅中台八葉院九尊の主である。また金剛頂経の説く金剛界曼荼羅五智如来の中心。空海の開いた真言宗において、究極的には修行者自身と一体化すべきものとして最も重要な仏陀である。不動明王は、密教の根本尊である大日如来の化身、あるいはその内証(内心の決意)を表現したものであると見なされている。
後期密教を大幅に取り入れたチベット仏教でも、大日如来は金剛界五仏(五智如来)の中心として尊崇される。チベット仏教では、宝飾品を身に纏わずに通常の如来の姿で表現されたり、あるいは多面仏として描かれることもある。
像形は、宝冠をはじめ瓔珞などの豪華な装身具を身に着けた、菩薩のような姿の坐像として表現される。これは古代インドの王族の姿を模したものである。一般に如来は装身具を一切身に着けない薄衣の姿で表現されるが、大日如来は宇宙そのもの存在を装身具の如く身にまとった者として、特に王者の姿で表されるのである。 印相は、金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結ぶ。
ヴィローチャナとの関連性
大日如来をインド神話のアスラ神族の王ヴィローチャナに求める学説がある。この名が華厳経の教主の毘盧遮那仏(ヴァイローチャナ)と類似することから、毘盧遮那仏から発展した大日如来とも同一視するというもである。この説は、チャーンドギヤ・ウパニシャッドの説話を根拠としているようだ。 また、インドの叙事詩「マハーバーラタ」においては、ヴィローチャナとは単に太陽神のことを指す場合があり、必ずしも特定のアスラ王を意味するわけではない。[1]
アフラ・マズダーとの関連性
大日如来(摩訶毘盧遮那仏、マハー・ヴァイローチャナ)の成立の起源を、ゾロアスター教の善の最高神アフラ・マズダーに求める学説がある。この説は太陽の属性と智の属性、火を信奉することを根拠としている。[2]
華厳経と盧舎那仏
大仏は姿の上では釈迦如来など他の如来像と区別がつかないが、華厳経に説かれる盧舎那仏という名の仏である。華厳経は西暦400年前後に中央アジアで成立し、中国経由で日本へもたらされた仏教経典で、60巻本、80巻本、40巻本の3種類の漢訳本があるが、うち奈良時代に日本へもたらされたのは60巻本と80巻本である。前者は5世紀、東晋の仏駄跋陀羅訳で「旧訳」(くやく)、「六十華厳」といい、後者は7世紀末、唐の実叉難陀訳で「新訳」、「八十華厳」という。盧舎那仏はこの華厳経に説く「蓮華蔵世界」の中心的存在であり、世界の存在そのものを象徴する絶対的な仏である。六十華厳では「盧舎那仏」、八十華厳では「毘盧遮那仏」と表記されるが、これらの原語はサンスクリットの「ヴァイローチャナ」であり、密教における大日如来(マハー・ヴァイローチャナ)と語源を等しくする。
東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、一般に「奈良の大仏」として知られる仏像で、東大寺大仏殿(金堂)の本尊である。聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会(かいげんくようえ、魂入れの儀式)が行われたが、現存する像は中世・近世の補修がはなはだしく、当初の部分は台座、腹、指の一部など、ごく一部が残るにすぎない。「銅造盧舎那仏坐像」の名で彫刻部門の国宝に指定されている。
大仏の正式名称は「盧舎那仏坐像」、大仏殿の正式名称は「東大寺金堂」であるが、本項では以下「大仏」、「大仏殿」と呼称する。
なお、奈良の東大寺は「行基菩薩」が関わったとされております。
「民衆のために活躍した行基は740年(天平12年)から大仏建立に協力する。このため「行基転向論」(民衆のため活動した行基が朝廷側の僧侶になったとする説)があるが、一般的には権力側が行基の民衆に対する影響力を利用したのであり、行基が権力者の側についたのではないと考えられている。741年(天平13年)3月に聖武天皇が恭仁京郊外の泉橋院で行基と会見し、同15年東大寺の大仏造造営の勧進に起用されている。勧進の効果は大きく、745年(天平17年)に朝廷より日本最初の大僧正の位を贈られた。」
以下、四国霊場八十八ヵ所をダイジェストで紹介します。
第七十五番・五岳山・「善通寺」・誕生院
本尊・薬師如来(座像一丈六尺)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派総本山
住所・香川県善通寺市善通寺町3〜3〜1
略縁起
弘法大師ご誕生の霊蹟である。
寺は屏風ヶ浦五岳山誕生院・総本山善通寺と号し、真言宗善通寺派の総本山である。
唐から帰朝した大師は大同二年(807)先祖の氏寺を建立せんとして、父善通郷から寺領として荘園四町余を拝受し、そこにかつて学んだ唐の青竜寺に模した堂宇を建てた。
寺号は父の名をとって、善通寺と命名。山号は背後の五つの山にちなんで五岳山と号し、院号は大師誕生せしところより誕生院と名づけられたという。
境内にはご両親及び稚児大師木像、産湯の井戸、御影池、瞬目大師、二十日橋、後嵯峨、亀山、後宇多の三帝御廊、大樟、法然上人逆修塔、足利尊氏利生塔仙遊ヶ原、西行庵と久之松、旅大師、雲気、大麻など五大明神があり、国宝に行基菩薩作地蔵尊、大師作吉祥天、大師母公筆の法華経序品一巻や三国伝来の金銅錫杖がある。
広大な境内に建つ五重の塔はときとして目も覚めるような黄金色に包まれて映える事がある。
詠歌
われすまば、よもきえはてじ、善通寺、ふかきちかいの、のりのともしび。
八十九メートルの戒壇めぐり
仁王門をくぐれば、西院坊の御影堂に進む。その地下に、能満所願の本尊をお祀りした戒壇めぐりがある。
真っ暗な中を、左手で壁をなでながら89メートルを行く。
だんだん怖くなり「南無大師遍照金剛」が自然に口に出る。中程の、大師がお生まれになった下の所に祭壇が設けられてあり、その御灯明の明るさでほっとする。
第七十三番・我拝師山・「出釈迦寺」・求聞持院
本尊・釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県善通寺市吉原町1091
略縁起
弘法大師七歳の時、仏道にはいる証しを得ようとして、四八一メートルの倭斯濃山(わしのざん)の頂きに立ち「仏道に入り、衆生を救わんとするわが願い、成就するものならば霊験を、さもなくば、賭したこの身を諸仏に奉げる。」と念じて截りたつ断崖から身を躍らせた。と、落下する大師の下方に紫雲がたなびき、蓮華の花に座した釈迦如来が出現「一生成仏」の宣を授け、大師の願いは叶えられたという。
そこで大師は、出現した釈迦如来の尊像を刻んで本尊とし、出釈迦寺と命名の寺をその麓に創建すると共に、得た霊験から山号を我拝師山と改称せられた。
大師が命をかけた霊蹟は捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがけぜんじょう)といい、寺より十八キロほど登った山の断崖に奥の院としてあり、麓の寺と共に衆生済度発願の根本道場として残っている。
詠歌
まよいぬる、とくどぅ衆生、すくわんと、とうとき山に、いずるしゃかでら。
西行法師の山里庵
仁安三年(1168)西行法師がここ讃岐の国へ下って来た。それは一つには歌の道の友であった崇徳上皇の陵(山峰)に詣でることであり、今一つは僧となった身として、弘法大師の遺跡を訪うことであった。
この寺の裏山に山里庵という庵を結んでいたことが、その歌集「山家集」に書かれている。
第二十四番・室戸山・「最御崎寺」(ほつみさきじ)・明星院
本尊・虚空菩薩(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗豊山派
住所・高知県室戸市室戸岬町
略縁起
大師十九歳のとき、室戸岬を訪れ、御蔵洞(みくらどう)という海に面した暗い洞窟の中で求聞持の法を徹夜で修行された。
そして、その徹夜が数日間に及んだとき、輝いていた明星が飛来して、口中にはいりしことより、この地が仏法に悉地であると感得された。
そこで、大師は「法性の、室戸といえどわれ住めば、有為のなみかぜ、たたぬ日ぞなき」と詠まれたという。
その後、大同二年(807)唐の国より大望を果たして帰国した大師は、嵯峨天皇の勅願を奉じて再び室戸岬を訪れ伽藍を建立。
虚空菩薩を刻んで本尊として安置した。
寺のその後は、前述の嵯峨天皇はもとより、歴代皇家の尊信を得、また足利幕府も土佐の祈願所に定めたという。
以降も各武将の寄進が多く繁栄を重ねた。
指定を受けた国宝には薬師如来、月光菩薩、如意輪観音などがあり、境内には 大師の奇跡とされている明星石、くわず芋がある。
詠歌
明星の、出でぬるかたの東寺、暗き迷いは、などかあらまじ。
大師が「空海」と改名された所
大師は十八歳で、自分の進む道は仏教だと悟られた。
しかし、当時の奈良仏教には満足出来ず、大峰・高野に入り、阿波の大龍寺まで修行し、ここ室戸の先端に立って、つまり大自然の真ん中に入ることによってほんとの悟りを得た。
それまでの無空、如空、教海から、空海という名前に、この地で改めたのだ。
第一番・竺和山・「霊山寺」・一条院
本尊 釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基 行基菩薩
宗派・真言宗高野派
住所・徳島県鳴門市大麻町坂東
略縁起
天平の頃、聖武天皇の勅願により、行基菩薩が開基した寺。
この開基より時代が経過した弘仁六年、弘法大師は、四国に八十八ヶ所の霊場を開こうと祈願された。
それは、仏教の理、つまり、五転の法則に従うものである。
大師は四国霊場の開創に当たってその著書「十住心論」に位置づけてあるように、四国の地に大日如来の胎蔵界四重円壇のマンダラ道場を求め、各国を発心、修業、菩薩、涅槃とお定めになった。
難しく書きましたが、ようするに心身救済の霊場であり、人間が持っている八十八の煩悩を消滅せんがためのものです。
そこで、大師は四国の東北の地を基点にして右回りの霊場をと考えられて鳴門へ来錫されたとき、空中に光明輝く諸仏を感得した。
大師はその状景から、釈迦如来が印度の鷲峰山(霊鷲山)で説法している姿を連想され、天竺の霊山を移す意で、竺和山・霊山寺と名付け、持仏の釈迦誕生仏を本尊前に納めた後、八十八ヶ所の第一番寺と定められた。
詠歌
霊山の、釈迦のみ前に、めぐりきて、よろずの罪も、消えうせにけり。
札はじめは大師に倣ってこの寺から
四国遍路は、その出身地によって、どこから礼はじめをしても良いと言われるが、正式にはこの霊山寺から出発することになっている。
例えば、三百年以上も前の遍路記、承応二年(1653)澄禅という人の「四国辺路」にも、「大師ハ阿波ノ北分十里ヶ所霊山寺ヲ最初ニシテ阿波土佐伊予讃岐ト順ニ御修行也」とある。
ここ、一番札所霊山寺は、「聖武天皇の勅願により、行基菩薩が開基した寺。」となっています。
弘法大師空海と、行基菩薩は、四国霊場の磁場作りに係わっています。<m(__)m>
|
|
|
|
|
|
|
|
行基 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
行基のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75494人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9044人