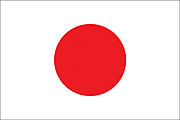気象庁
http://
http://
緊急地震速報のしくみ
緊急地震速報は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報です。
緊急地震速報が有効に活用できる時間を確保するためには、できるだけ迅速に発表しなければなりません。そのため、最初に震源に近い1つの観測点で地震波をとらえた直後から、震源やマグニチュードの推定、到達時刻や震度の予測を開始します。そして、マグニチュードの値ないしは予測された最大震度の値が予め設定した基準を超えた瞬間に、緊急地震速報の第1報を発表します。しかし、解析に使用できるデータが限られているため、十分なデータを得てから行う従来の方法と比べると、精度的にはどうしても劣ります。そのため、その後時間の経過とともに観測点2箇所目、観測点3箇所目と地震波をとらえたた地震観測点の数が増え、利用できるデータが増加するのにあわせて、計算を繰り返して精度の向上を図ることとしました。従って、緊急地震速報とは、第1報発表の迅速性は確保しつつ、時間とともに精度を上げながら複数回発表されるものです。
しかしながら、オンラインで接続されたコンピュータであれば、短時間に次々と発表される速報を処理し、自動制御等に活用することが可能ですが、人に対して伝える際には、見聞きした人が混乱することも予想されますし、すべての内容を言葉や文字で伝えることができません。また、1つの観測点のデータだけでは、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報の可能性もあります。
そのため、1つの観測点のデータから複数回発表する「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」とは別に、テレビやラジオなどを通じて提供する「一般向けの緊急地震速報(警報)」は、複数地点で観測され、強い揺れが予測された場合に原則1回発表することとしました。
なお、緊急地震速報は、地震発生後の地震波を捉えてから発表するものであることから、地震の発生を予知しているわけではありません(いわゆる地震予知ではない)。
緊急地震速報に係る法律上の規定
気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)の施行(平成19年12月1日)に伴い、緊急地震速報は地震動の予報及び警報と位置付けられ、以下のことが法律で規定されました。
注)ここでは、法律の文言をそのまま使用しています。地震動の警報は緊急地震速報(警報)、地震動の予報は緊急地震速報(予報)と必要に応じて読み替えてください。
気象庁による地震動の予報及び警報の実施
気象庁は、発生した断層運動による地震動(以下では単に「地震動」といいます。)の一般の利用に適合する予報及び警報をしなければなりません。
※地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ(地震動)を予想し発表することであり、地震の発生の予想は含みません。
気象庁以外の者に対する地震動の予報の業務の許可
気象庁以外の者が地震動の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
気象庁以外の者による地震動の警報の制限
気象庁以外の者は、地震動の警報をしてはなりません。
地震動の警報の伝達
気象庁は地震動の警報をした場合、直ちに政令で指定された機関(現在は日本放送協会になります。)に通知しなければなりません。通知された日本放送協会は直ちに警報を放送しなければなりません。
また、地震動の予報の業務の許可を受けた者は、気象庁が発表する地震動の警報の迅速な伝達に努めなければなりません。
緊急地震速報と地震動の警報及び予報との関係
地震動の警報及び予報については、以下の区分で運用します。
なお、その名称については、「緊急地震速報」の名称で一般に認知されつつあることを踏まえ、以下のとおり引き続きこの名称を用いて発表します。
地震動の警報及び予報の区分について
内容
地震動警報 最大震度5弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの【注】
地震動予報 最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上等と予想されたときに発表するもの
【注】「一般向け緊急地震速報」並びに「高度利用者向け緊急地震速報」のうち2箇所以上のデータにより最大震度が5弱以上と予想された速報及びその後の一連の速報。
地震動の警報及び予報の名称について
気象庁における発表に当たっては今後とも「緊急地震速報」の名称を用いることとし、警報と予報の区別については次のとおりとします。
用いる名称
地震動警報 「緊急地震速報(警報)」又は「緊急地震速報」
地震動予報 「緊急地震速報(予報)」
なお、予報業務許可事業者が緊急地震速報を発表するに当たっては、気象庁が行う警報と区別するため、提供する緊急地震速報が地震動の予報であることを、利用者に対し周知していただくことが必要です。
緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)の内容や発表条件
ここでは、緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)の発表条件や内容などの解説をします。
一般向けの緊急地震速報(警報)の内容・発表条件
気象庁は平成19年10月1日から、一般向けの緊急地震速報(警報)の発表を開始しました。一般向けの緊急地震速報(警報)の発表条件・内容については次の通りです。
1.一般向けの緊急地震速報(警報)を発表する条件
地震波が2点以上の地震観測点で観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合に発表する。
一般の皆様に伝えられる緊急地震速報(警報)の発表条件は、2点以上の地震観測点で地震波が観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合です。
2点以上の地震観測点で地震波が観測された場合とした理由は、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報を避けるためです。
最大震度5弱以上が予測された場合とした理由は、震度5弱以上になると顕著な被害が生じ始めるため、事前に身構える必要があるためです。
2.一般向けの緊急地震速報(警報)の内容
地震の発生時刻、発生場所(震源)の推定値、地震発生場所の震央地名
強い揺れ(震度5弱以上)が予測される地域及び震度4が予測される地域名(全国を約200地域に分割)(※1)
※地域名については、緊急地震速報の予報区をご覧ください。
(※1)具体的な予測震度と猶予時間は発表しません。
発表する内容は、地震が発生した場所や、震度4以上の揺れが予測された地域名称などです。
具体的な予測震度の値は、±1程度の誤差を伴うものであること、及び、できるだけ続報は避けたいことから発表せず、「強い揺れ」と表現することとしました。震度4以上と予測された地域まで含めて発表するのは、震度を予測する際の誤差のため実際には5弱である可能性があることと、震源域の断層運動の進行により、しばらく後に5弱となる可能性があるというふたつの理由によります。
猶予時間については、気象庁から発表する対象地域の最小単位が、都道府県を3〜4つに分割した程度の広がりを持ち、その中でも場所によってかなり異なるものであるため、発表いたしません。
また、一般向けの緊急地震速報(警報)における続報の発表は、次の通りです。
3.一般向けの緊急地震速報(警報)で続報を発表する場合
緊急地震速報を発表した後の解析により、震度3以下と予測されていた地域が震度5弱以上と予測された場合に、続報を発表する。
続報では、新たに震度5弱以上が予測された地域及び新たに震度4が予測された地域を発表する。
落雷等の地震以外の現象を地震と誤認して発信された緊急地震速報(誤報)のみ取り消すこととし、例えば震度5弱と予測していた地域が震度3以下との予測となった場合などは取り消さない。
高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容・発表条件
平成18年8月1日より先行的に活用できる分野について提供している緊急地震速報は、機器制御などの高度な利用者向けとして、平成19年10月1日以降も、引き続き提供しています。また、各家庭用の端末などで、高度利用者向けの緊急地震速報(予報)を受信し、受信地点の予測震度や主要動到達予想時刻などを表示する等にも利用されています。
高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容・発表条件については次の通りです。
1.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容
地震の発生時刻、地震の発生場所(震源)の推定値
地震の規模(マグニチュード)の推定値
予測される最大震度が震度3以下のときは、
○予測される揺れの大きさの最大(最大予測震度)
予測される最大震度が震度4以上のときは、地域名に加えて
○震度5弱以上と予測される地域の揺れの大きさ(震度)の予測値(予測震度)
○その地域への大きな揺れ(主要動)の到達時刻の予測値(主要動到達予測時刻)
※地域名については、緊急地震速報の予報区をご覧ください。
緊急地震速報(予報)が従来の地震情報と異なる点はその迅速性です。気象庁は緊急地震速報(予報)として下図のように地震を検知してから数秒〜1分程度の間に数回(5〜10回程度)発表します。第1報は迅速性を優先し、その後提供する情報の精度は徐々に高くなっていきます。ほぼ精度が安定したと考えられる時点で最終報を発表し、その地震に対する緊急地震速報の提供を終了します。
2.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の発信条件(※)
気象庁の多機能型地震計設置のいずれかの観測点において、P波またはS波の振幅が100ガル以上となった場合。
地震計で観測された地震波を解析した結果、震源・マグニチュード・各地の予測震度が求まり、そのマグニチュードが3.5以上、または最大予測震度が3以上である場合。
(※)1点の観測点のみの処理結果によって緊急地震速報(予報)を発信した後、所定の時間が経過しても2観測点目の処理が行われなかった場合はノイズと判断し、発表から数秒〜10数秒程度でキャンセル報を発信します。島嶼部など観測点密度の低い地域では、実際の地震であってもキャンセル報を発信する場合があります。なお、この場合には、キャンセル報の発信までに30秒程度かかることがあります。
(※)この基準は変更する場合があります。
なお、緊急地震速報(予報)の処理手法等については、「緊急地震速報の概要や処理手法に関する技術的参考資料」[PDF形式: 285KB]をご覧下さい。
緊急地震速報の入手方法
気象庁は、平成19年10月1日から、一般向けに提供を開始しました。平成18年8月1日から、先行的な提供をしている緊急地震速報は、高度利用者向けとして引き続き提供しています。 一般向け、高度利用者向けの緊急地震速報の入手方法は緊急地震速報の入手方法についてにまとめています。
http://
http://
緊急地震速報のしくみ
緊急地震速報は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報です。
緊急地震速報が有効に活用できる時間を確保するためには、できるだけ迅速に発表しなければなりません。そのため、最初に震源に近い1つの観測点で地震波をとらえた直後から、震源やマグニチュードの推定、到達時刻や震度の予測を開始します。そして、マグニチュードの値ないしは予測された最大震度の値が予め設定した基準を超えた瞬間に、緊急地震速報の第1報を発表します。しかし、解析に使用できるデータが限られているため、十分なデータを得てから行う従来の方法と比べると、精度的にはどうしても劣ります。そのため、その後時間の経過とともに観測点2箇所目、観測点3箇所目と地震波をとらえたた地震観測点の数が増え、利用できるデータが増加するのにあわせて、計算を繰り返して精度の向上を図ることとしました。従って、緊急地震速報とは、第1報発表の迅速性は確保しつつ、時間とともに精度を上げながら複数回発表されるものです。
しかしながら、オンラインで接続されたコンピュータであれば、短時間に次々と発表される速報を処理し、自動制御等に活用することが可能ですが、人に対して伝える際には、見聞きした人が混乱することも予想されますし、すべての内容を言葉や文字で伝えることができません。また、1つの観測点のデータだけでは、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報の可能性もあります。
そのため、1つの観測点のデータから複数回発表する「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」とは別に、テレビやラジオなどを通じて提供する「一般向けの緊急地震速報(警報)」は、複数地点で観測され、強い揺れが予測された場合に原則1回発表することとしました。
なお、緊急地震速報は、地震発生後の地震波を捉えてから発表するものであることから、地震の発生を予知しているわけではありません(いわゆる地震予知ではない)。
緊急地震速報に係る法律上の規定
気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)の施行(平成19年12月1日)に伴い、緊急地震速報は地震動の予報及び警報と位置付けられ、以下のことが法律で規定されました。
注)ここでは、法律の文言をそのまま使用しています。地震動の警報は緊急地震速報(警報)、地震動の予報は緊急地震速報(予報)と必要に応じて読み替えてください。
気象庁による地震動の予報及び警報の実施
気象庁は、発生した断層運動による地震動(以下では単に「地震動」といいます。)の一般の利用に適合する予報及び警報をしなければなりません。
※地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ(地震動)を予想し発表することであり、地震の発生の予想は含みません。
気象庁以外の者に対する地震動の予報の業務の許可
気象庁以外の者が地震動の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
気象庁以外の者による地震動の警報の制限
気象庁以外の者は、地震動の警報をしてはなりません。
地震動の警報の伝達
気象庁は地震動の警報をした場合、直ちに政令で指定された機関(現在は日本放送協会になります。)に通知しなければなりません。通知された日本放送協会は直ちに警報を放送しなければなりません。
また、地震動の予報の業務の許可を受けた者は、気象庁が発表する地震動の警報の迅速な伝達に努めなければなりません。
緊急地震速報と地震動の警報及び予報との関係
地震動の警報及び予報については、以下の区分で運用します。
なお、その名称については、「緊急地震速報」の名称で一般に認知されつつあることを踏まえ、以下のとおり引き続きこの名称を用いて発表します。
地震動の警報及び予報の区分について
内容
地震動警報 最大震度5弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの【注】
地震動予報 最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上等と予想されたときに発表するもの
【注】「一般向け緊急地震速報」並びに「高度利用者向け緊急地震速報」のうち2箇所以上のデータにより最大震度が5弱以上と予想された速報及びその後の一連の速報。
地震動の警報及び予報の名称について
気象庁における発表に当たっては今後とも「緊急地震速報」の名称を用いることとし、警報と予報の区別については次のとおりとします。
用いる名称
地震動警報 「緊急地震速報(警報)」又は「緊急地震速報」
地震動予報 「緊急地震速報(予報)」
なお、予報業務許可事業者が緊急地震速報を発表するに当たっては、気象庁が行う警報と区別するため、提供する緊急地震速報が地震動の予報であることを、利用者に対し周知していただくことが必要です。
緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)の内容や発表条件
ここでは、緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)の発表条件や内容などの解説をします。
一般向けの緊急地震速報(警報)の内容・発表条件
気象庁は平成19年10月1日から、一般向けの緊急地震速報(警報)の発表を開始しました。一般向けの緊急地震速報(警報)の発表条件・内容については次の通りです。
1.一般向けの緊急地震速報(警報)を発表する条件
地震波が2点以上の地震観測点で観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合に発表する。
一般の皆様に伝えられる緊急地震速報(警報)の発表条件は、2点以上の地震観測点で地震波が観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合です。
2点以上の地震観測点で地震波が観測された場合とした理由は、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報を避けるためです。
最大震度5弱以上が予測された場合とした理由は、震度5弱以上になると顕著な被害が生じ始めるため、事前に身構える必要があるためです。
2.一般向けの緊急地震速報(警報)の内容
地震の発生時刻、発生場所(震源)の推定値、地震発生場所の震央地名
強い揺れ(震度5弱以上)が予測される地域及び震度4が予測される地域名(全国を約200地域に分割)(※1)
※地域名については、緊急地震速報の予報区をご覧ください。
(※1)具体的な予測震度と猶予時間は発表しません。
発表する内容は、地震が発生した場所や、震度4以上の揺れが予測された地域名称などです。
具体的な予測震度の値は、±1程度の誤差を伴うものであること、及び、できるだけ続報は避けたいことから発表せず、「強い揺れ」と表現することとしました。震度4以上と予測された地域まで含めて発表するのは、震度を予測する際の誤差のため実際には5弱である可能性があることと、震源域の断層運動の進行により、しばらく後に5弱となる可能性があるというふたつの理由によります。
猶予時間については、気象庁から発表する対象地域の最小単位が、都道府県を3〜4つに分割した程度の広がりを持ち、その中でも場所によってかなり異なるものであるため、発表いたしません。
また、一般向けの緊急地震速報(警報)における続報の発表は、次の通りです。
3.一般向けの緊急地震速報(警報)で続報を発表する場合
緊急地震速報を発表した後の解析により、震度3以下と予測されていた地域が震度5弱以上と予測された場合に、続報を発表する。
続報では、新たに震度5弱以上が予測された地域及び新たに震度4が予測された地域を発表する。
落雷等の地震以外の現象を地震と誤認して発信された緊急地震速報(誤報)のみ取り消すこととし、例えば震度5弱と予測していた地域が震度3以下との予測となった場合などは取り消さない。
高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容・発表条件
平成18年8月1日より先行的に活用できる分野について提供している緊急地震速報は、機器制御などの高度な利用者向けとして、平成19年10月1日以降も、引き続き提供しています。また、各家庭用の端末などで、高度利用者向けの緊急地震速報(予報)を受信し、受信地点の予測震度や主要動到達予想時刻などを表示する等にも利用されています。
高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容・発表条件については次の通りです。
1.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容
地震の発生時刻、地震の発生場所(震源)の推定値
地震の規模(マグニチュード)の推定値
予測される最大震度が震度3以下のときは、
○予測される揺れの大きさの最大(最大予測震度)
予測される最大震度が震度4以上のときは、地域名に加えて
○震度5弱以上と予測される地域の揺れの大きさ(震度)の予測値(予測震度)
○その地域への大きな揺れ(主要動)の到達時刻の予測値(主要動到達予測時刻)
※地域名については、緊急地震速報の予報区をご覧ください。
緊急地震速報(予報)が従来の地震情報と異なる点はその迅速性です。気象庁は緊急地震速報(予報)として下図のように地震を検知してから数秒〜1分程度の間に数回(5〜10回程度)発表します。第1報は迅速性を優先し、その後提供する情報の精度は徐々に高くなっていきます。ほぼ精度が安定したと考えられる時点で最終報を発表し、その地震に対する緊急地震速報の提供を終了します。
2.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の発信条件(※)
気象庁の多機能型地震計設置のいずれかの観測点において、P波またはS波の振幅が100ガル以上となった場合。
地震計で観測された地震波を解析した結果、震源・マグニチュード・各地の予測震度が求まり、そのマグニチュードが3.5以上、または最大予測震度が3以上である場合。
(※)1点の観測点のみの処理結果によって緊急地震速報(予報)を発信した後、所定の時間が経過しても2観測点目の処理が行われなかった場合はノイズと判断し、発表から数秒〜10数秒程度でキャンセル報を発信します。島嶼部など観測点密度の低い地域では、実際の地震であってもキャンセル報を発信する場合があります。なお、この場合には、キャンセル報の発信までに30秒程度かかることがあります。
(※)この基準は変更する場合があります。
なお、緊急地震速報(予報)の処理手法等については、「緊急地震速報の概要や処理手法に関する技術的参考資料」[PDF形式: 285KB]をご覧下さい。
緊急地震速報の入手方法
気象庁は、平成19年10月1日から、一般向けに提供を開始しました。平成18年8月1日から、先行的な提供をしている緊急地震速報は、高度利用者向けとして引き続き提供しています。 一般向け、高度利用者向けの緊急地震速報の入手方法は緊急地震速報の入手方法についてにまとめています。
|
|
|
|
コメント(3)
伊豆地震 気象庁「今後数日〜10日間に5弱〜5強発生の可能性」
2009.12.18 02:49
地震について会見する気象庁地震火山部の横田崇・地震予知情報課長=18日未明、気象庁(撮影・渡守麻衣) 静岡県伊豆で17日午後11時45分ごろ、震度5弱を観測した地震で、気象庁は18日未明に記者会見し、今後数日から10日ほどの間に震度5弱から5強程度の地震が発生する可能性があると説明、注意を呼びかけた。
気象庁によると、震源地は伊豆半島東方沖で震源の深さは約4キロ。地震の規模はマグニチュード5・0と推定される。東海地震に直結する活動ではないといい、海底噴火などの兆候もみられないとしている。
伊豆や伊東などでは17日午後2時ごろから体に感じない揺れを観測。18日未明までに、震度3から震度1の地震が40回以上起きていた。
震源となった伊豆半島東方沖では過去、群発地震がたびたび発生。最近では平成9年3月4日に震度5弱、18年にも震度4の地震が起きていた。
2009.12.18 02:49
地震について会見する気象庁地震火山部の横田崇・地震予知情報課長=18日未明、気象庁(撮影・渡守麻衣) 静岡県伊豆で17日午後11時45分ごろ、震度5弱を観測した地震で、気象庁は18日未明に記者会見し、今後数日から10日ほどの間に震度5弱から5強程度の地震が発生する可能性があると説明、注意を呼びかけた。
気象庁によると、震源地は伊豆半島東方沖で震源の深さは約4キロ。地震の規模はマグニチュード5・0と推定される。東海地震に直結する活動ではないといい、海底噴火などの兆候もみられないとしている。
伊豆や伊東などでは17日午後2時ごろから体に感じない揺れを観測。18日未明までに、震度3から震度1の地震が40回以上起きていた。
震源となった伊豆半島東方沖では過去、群発地震がたびたび発生。最近では平成9年3月4日に震度5弱、18年にも震度4の地震が起きていた。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
日本の各省 コミュニティ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日本の各省 コミュニティのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人