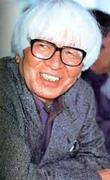|
|
|
|
コメント(21)
江藤新平にしろ大隈重信にしろ能力に関しては高い評価をしていました
特に江藤に関しては、国家の青写真を描く稀有な才能という意味では大久保利通と並ぶという高い評価でした
ただし、二人に共通しているのは、明治維新に参加出来なかったというのは経験にしろ他人に見せる経歴という意味でもマイナス点だとおっしゃっていました
つまり、革命の火の中をくぐり抜けたのはあくまでも薩長だったということですね
そういう経験がない人間というのはどこか坊っちゃんくささがあるというニュアンスを僕は感じました
面白いのは江藤も大隈も西郷の魅力がわからなかったということです
つまり、おおらかな人間力が政治を動かすテコになるということが最後まで理解出来ずに、あくまでも政治を技術だとしか感じることが出来なかった
藩主の鍋島さんは佐賀を開明的な藩にしようとしたりという明君ではありましたが、いかんせん革命に参加するのが遅かったんですね
最後の最後の段階でしたから
それでも誕生したての明治政府が佐賀藩士を多く採用したという事実があるのは、門閥関係なく本当に優秀だったからだろうという評価でした
特に江藤に関しては、国家の青写真を描く稀有な才能という意味では大久保利通と並ぶという高い評価でした
ただし、二人に共通しているのは、明治維新に参加出来なかったというのは経験にしろ他人に見せる経歴という意味でもマイナス点だとおっしゃっていました
つまり、革命の火の中をくぐり抜けたのはあくまでも薩長だったということですね
そういう経験がない人間というのはどこか坊っちゃんくささがあるというニュアンスを僕は感じました
面白いのは江藤も大隈も西郷の魅力がわからなかったということです
つまり、おおらかな人間力が政治を動かすテコになるということが最後まで理解出来ずに、あくまでも政治を技術だとしか感じることが出来なかった
藩主の鍋島さんは佐賀を開明的な藩にしようとしたりという明君ではありましたが、いかんせん革命に参加するのが遅かったんですね
最後の最後の段階でしたから
それでも誕生したての明治政府が佐賀藩士を多く採用したという事実があるのは、門閥関係なく本当に優秀だったからだろうという評価でした
> パタリロ先生さん
江藤新平のことを知りたい場合には、彼を主役とした『歳月』(講談社文庫)という作品がオススメです
一般的な佐賀藩士の家風も含めて、とても詳しく知れると思います
大隈重信の場合は『翔ぶが如く』(文春文庫)という作品に評価が書いてありましたが、どの巻に書いてあったかは忘れてしまいました
何しろ全十巻もあるので読破にはかなり根気が必要です
藩主、鍋島閑ソウ(携帯には漢字がのってませんでした)を主役とした『肥前の妖怪』という短編もオススメです
こちらは『酔って候う』(文春文庫)という短編集の中に掲載されていますが、短い中にもかなり佐賀藩のことが描かれてます
さっき書いたのはあくまでも僕のザッとした印象なので、もしかしたら違う見方をしている方もいるかもしれませんが
江藤新平のことを知りたい場合には、彼を主役とした『歳月』(講談社文庫)という作品がオススメです
一般的な佐賀藩士の家風も含めて、とても詳しく知れると思います
大隈重信の場合は『翔ぶが如く』(文春文庫)という作品に評価が書いてありましたが、どの巻に書いてあったかは忘れてしまいました
何しろ全十巻もあるので読破にはかなり根気が必要です
藩主、鍋島閑ソウ(携帯には漢字がのってませんでした)を主役とした『肥前の妖怪』という短編もオススメです
こちらは『酔って候う』(文春文庫)という短編集の中に掲載されていますが、短い中にもかなり佐賀藩のことが描かれてます
さっき書いたのはあくまでも僕のザッとした印象なので、もしかしたら違う見方をしている方もいるかもしれませんが
江藤さんのファンです〜!
司馬さんの本で見たんかな?
はっきり覚えてのうて、大げさに膨らましてわたしが言いますと、
佐賀藩は「コンスタンチノープル以東、最強の公国」のような?存在やった、と。
佐賀藩は、幕府から長崎管理を任されてたから、
蘭学がしやすかったんでしょうね、
カンソウさんがとびきり強い近代軍を作ってしまった。
明治維新がスムーズにいったんも、最後の段階で佐賀が参加したから?
東京上野の彰義隊を一日で壊滅させたのも、
佐賀が作ったアームストロング砲があった、ということでええですかね?
数年前、ニュースサイトで、江藤さんは、やはりカンソウの密命を受けて、
「脱藩」して京の政界に参加したみたいですね、こっちは確かです(笑
江藤さんは頭がええし、格好ええし、名前もまるまる平民的で大好きです。
川崎ゆきお、というまんが家の作品に『ライカ伝』というのがあり、
そこで「江藤新兵」という名前の、スーツの似合う政治家が出て来て、
関ヶ原における三成をモデルにした働きをします。
戦争弱いんです(泣
作家さん、三成も江藤さんも好きなんが伝わってきました。
この歴史上の二人を一人のキャラとして合体さす、という眼もなかなかでしたw
いっぺん佐賀までいって、「佐賀の七賢人」の跡を探したいです。
→この言い方は、ウィキペディアに載ってました。
大河ドラマで、江藤さんが見たいです!
『歳月』の大河化推進!ww
司馬さんの本で見たんかな?
はっきり覚えてのうて、大げさに膨らましてわたしが言いますと、
佐賀藩は「コンスタンチノープル以東、最強の公国」のような?存在やった、と。
佐賀藩は、幕府から長崎管理を任されてたから、
蘭学がしやすかったんでしょうね、
カンソウさんがとびきり強い近代軍を作ってしまった。
明治維新がスムーズにいったんも、最後の段階で佐賀が参加したから?
東京上野の彰義隊を一日で壊滅させたのも、
佐賀が作ったアームストロング砲があった、ということでええですかね?
数年前、ニュースサイトで、江藤さんは、やはりカンソウの密命を受けて、
「脱藩」して京の政界に参加したみたいですね、こっちは確かです(笑
江藤さんは頭がええし、格好ええし、名前もまるまる平民的で大好きです。
川崎ゆきお、というまんが家の作品に『ライカ伝』というのがあり、
そこで「江藤新兵」という名前の、スーツの似合う政治家が出て来て、
関ヶ原における三成をモデルにした働きをします。
戦争弱いんです(泣
作家さん、三成も江藤さんも好きなんが伝わってきました。
この歴史上の二人を一人のキャラとして合体さす、という眼もなかなかでしたw
いっぺん佐賀までいって、「佐賀の七賢人」の跡を探したいです。
→この言い方は、ウィキペディアに載ってました。
大河ドラマで、江藤さんが見たいです!
『歳月』の大河化推進!ww
佐賀藩関係が述べられている司馬さんの作品としては、
『アームストロング砲』もありますね。
佐賀藩の技術者集団「精錬方」の奮闘ぶりと悲劇が書かれています。
あとは『「明治」という国家』の中で副島種臣が紹介されています。
副島のその学識・人格について、ほぼ絶賛に近い賛辞が書いてあります。
(副島が外務卿として清に赴いたときに、漢籍の知識で本場の中国人官僚を圧倒したんだとか…。)
これは個人的な印象ですが、
司馬先生って、あまり思想をいじくる人よりも、
実務家で一徹でぶれない人(頑固?反骨?)を多く取り上げる傾向があるような気がします。
江藤新平なんかは、その典型だと思います。
その実務能力を下支えするのは、学力だったり知識ですよね。
そういう反骨の実務家ぞろいなのが佐賀藩、というのが司馬先生の観方なんじゃないでしょうか。
『アームストロング砲』もありますね。
佐賀藩の技術者集団「精錬方」の奮闘ぶりと悲劇が書かれています。
あとは『「明治」という国家』の中で副島種臣が紹介されています。
副島のその学識・人格について、ほぼ絶賛に近い賛辞が書いてあります。
(副島が外務卿として清に赴いたときに、漢籍の知識で本場の中国人官僚を圧倒したんだとか…。)
これは個人的な印象ですが、
司馬先生って、あまり思想をいじくる人よりも、
実務家で一徹でぶれない人(頑固?反骨?)を多く取り上げる傾向があるような気がします。
江藤新平なんかは、その典型だと思います。
その実務能力を下支えするのは、学力だったり知識ですよね。
そういう反骨の実務家ぞろいなのが佐賀藩、というのが司馬先生の観方なんじゃないでしょうか。
中公文庫の『司馬遼太郎 歴史のなかの邂逅』6 に、「この気違い勉強」という、大隈と幕末の佐賀藩を題材にしたエッセイ(読売新聞に寄稿したもの)が収録されています。
(佐賀藩の)「その文教熱心はときには気違いじみてさえいる」という評価です。「維新政府の多くの官僚が佐賀藩出身だったことを考えると、気違いじみた文教政策も意味があった」みたいなことばがありました。
「これほどの科学技術をもった藩は徳川三百年をとおして佐賀藩しかなく、薩摩藩がかろうじてその後を追いつける程度にすぎない」という、すごい評価です。
余談ですが、僕は鍋島家のご令嬢と大学時代、同級生でした。
彼女は剣道部に所属し、小柄ですが美人で、僕などは近寄りがたい感じがありましたので、決して「友達」だったわけではありません。なんていうか、「龍馬伝」にでてきた千葉道場のお佐那さま、みたいな感じでしたー。
(佐賀藩の)「その文教熱心はときには気違いじみてさえいる」という評価です。「維新政府の多くの官僚が佐賀藩出身だったことを考えると、気違いじみた文教政策も意味があった」みたいなことばがありました。
「これほどの科学技術をもった藩は徳川三百年をとおして佐賀藩しかなく、薩摩藩がかろうじてその後を追いつける程度にすぎない」という、すごい評価です。
余談ですが、僕は鍋島家のご令嬢と大学時代、同級生でした。
彼女は剣道部に所属し、小柄ですが美人で、僕などは近寄りがたい感じがありましたので、決して「友達」だったわけではありません。なんていうか、「龍馬伝」にでてきた千葉道場のお佐那さま、みたいな感じでしたー。
いま、「歳月」読み終えました。最後まで実に迫力に満ちた流れで、すっかり引き込まれてしまいました。
読み終えて大久保利通がちょっと嫌いになったかもしれない、というのは浅はかな読み方ですね(笑)江藤新平みたいな法律家の知り合い、実は現代にも多いですよね。やはり今の日本の司法制度は佐賀人がつくったということになるのでしょうかね。
こういう法律家的人物という人間の意外な脆さは、佐賀の乱のときの戦いぶりの江藤たちのあまりの粗雑さにあらわれていますね。実によく描かれています。戦争というのは状況判断とか情報の混雑とか、つまり学校秀才的人物が一番苦手にしてしまう世界なんですね。
敗走した江藤が、西郷隆盛とか林有造のところにいって弁舌で決起を促すところはユーモラスでさえありますね。西郷も林も本当に困ったでしょう。二人ともずっと江藤の決起に反対していて、今さら何だ、という感じで。江藤のいっている論理的大義なんてよくわからないわけです。こうしたタイプの法律家エリートっているんですよね(笑)
要するに江藤の弁舌力というのはディベート力ですね。平和なときには力をもつのかもしれないですね。
もし薩摩長州でなくて佐賀が日本の近代を主導したら…と考えると、今よりすごい学歴社会になっていたかもしれないな、と思いました。やっぱり大久保利通は正しかったのかもしれない(笑)
[歳月]は江藤新平が、平民から最初の司法卿と言う稀有な人生を生きて、時の役目を果すと(龍馬の様に)天に帰る。有り得ない人生に焦点を当てていると思いました。若くして不遇の身から立身する為に二重鎖国の中、独り脱藩する命懸けの行動は、身分も暮らしも哀れな我が身に、備わった非凡な才能を開くんだと決意する勇気有る(男)を感じます。 江藤新平は経済感覚も鋭く、古着屋から安く身分に合う服を買う等無駄を嫌った、財政感覚等も好きな処です。 しかし方向音痴で戦争が弱い等不得意な分野も有る等 愛されるべき処も在り好感が持てます。 また司馬遼太郎先生は[誰が日本の法律作ったんや?] この[謎]を分かり安く教えてくれた事に感謝して居ます。小さい頃僕は、(聖徳太子や!!)と言ってました。(笑)教科書に載せて欲しい。 大河ドラマに成ったら、江藤新平役は、大泉 洋さんにやって欲しい。 言い訳が上手いから。 お邪魔いたしました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
司馬遼太郎 更新情報
-
最新のアンケート
司馬遼太郎のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75482人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6442人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人