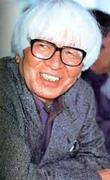次の司馬遼作品は何を読もうか悩んでいたら友人にこれを勧められました。見事にハマりながら読み進めてます…。司馬作品を読んで幕末の志士達の姿が鮮やかに見えたように、ローマの人々の姿がや生活が眼前に浮かびます。
塩野七生さんて、司馬遼太郎賞も受賞されてるんですね。
http://
塩野七生さんて、司馬遼太郎賞も受賞されてるんですね。
http://
|
|
|
|
コメント(41)
「ローマ人の物語」には隠しテーマがある、と思いますよ。
欧米人にとってその歴史上もっとも成功した国はローマである。そしてことあるごと、その成功を参考にしようとする。米国はまさにそのような国家である、と言うことなどです。
なのに日本人はあまりにもローマのことを知らない。
それが塩野さんをしてあの長大な物語を書かせているのでしょう。
「ローマ人の物語」のユリウス・カエサルも良いですが、佐藤賢一の「カエサルを撃て」のカエサルも良い。
ローマに栄光をもたらし、西欧社会の基礎を作ったのがカエサルでしょう。彼自身、それほど大きな影響を自分が後世に与えるとは思ってなかったと思いますが。
後、歴史的に評判の悪い皇帝に同情的で、評判の良い・・たとえばマルクス・アウレリウス帝・・には辛い。
そのあたりが塩野流です。
欧米人にとってその歴史上もっとも成功した国はローマである。そしてことあるごと、その成功を参考にしようとする。米国はまさにそのような国家である、と言うことなどです。
なのに日本人はあまりにもローマのことを知らない。
それが塩野さんをしてあの長大な物語を書かせているのでしょう。
「ローマ人の物語」のユリウス・カエサルも良いですが、佐藤賢一の「カエサルを撃て」のカエサルも良い。
ローマに栄光をもたらし、西欧社会の基礎を作ったのがカエサルでしょう。彼自身、それほど大きな影響を自分が後世に与えるとは思ってなかったと思いますが。
後、歴史的に評判の悪い皇帝に同情的で、評判の良い・・たとえばマルクス・アウレリウス帝・・には辛い。
そのあたりが塩野流です。
小説というよりは伝記といった文章ですよね。
特に「ローマ人の物語」ではそれが顕著です。
何人か「余談」が足りないと書かれていた方がいらっしゃいますが、
その通り小説として読むには文章に面白みがないと思います。
淡々としすぎで事実をそのまま紹介しているだけと言えばいいでしょうか。
扱っている内容や題材そのもの、掘り下げ方などは面白いです。
また、この人も「司馬史観」のような独自の視点を持っているみたいです。
語り口が冷たいので大きく表には出てきませんが、
結構好き嫌い(と言うよりは尊敬に値するかしないかかな)で
人物のクローズアップのされ方や評価度が違いますね。
史学科出身の友人は「そこがだめだ」と言っていましたね。
小説としてはそれでいいと思いますが、
上に書いたように文章がおもしろくないので…。
歴史小説家としては宮城谷昌光の方が司馬遼太郎には近いと思います(こちらも司馬遼太郎賞受賞済み)。
こちらは逆に創作部分が派手すぎるきらいがありますが。
特に「ローマ人の物語」ではそれが顕著です。
何人か「余談」が足りないと書かれていた方がいらっしゃいますが、
その通り小説として読むには文章に面白みがないと思います。
淡々としすぎで事実をそのまま紹介しているだけと言えばいいでしょうか。
扱っている内容や題材そのもの、掘り下げ方などは面白いです。
また、この人も「司馬史観」のような独自の視点を持っているみたいです。
語り口が冷たいので大きく表には出てきませんが、
結構好き嫌い(と言うよりは尊敬に値するかしないかかな)で
人物のクローズアップのされ方や評価度が違いますね。
史学科出身の友人は「そこがだめだ」と言っていましたね。
小説としてはそれでいいと思いますが、
上に書いたように文章がおもしろくないので…。
歴史小説家としては宮城谷昌光の方が司馬遼太郎には近いと思います(こちらも司馬遼太郎賞受賞済み)。
こちらは逆に創作部分が派手すぎるきらいがありますが。
私も丁度「終わりの始まり」の文庫版を読み終えた所です。ここまでで31巻ですよ(^^;
「ローマ人〜」の評価は人それぞれのようですが、私にとってはローマ史入門書としてこれ以上無い良書だと思っています。1000年にも及ぶ歴史を淡々と書き連ねるだけでも無く、かと言って過度に装飾してある訳でもなく、喩えて言うならばタイムトラベルの出来の良いパッケージツアーのような。
当然、パッケージツアーですから細かいところで説明の足りないところや、見落としているところもあるでしょうけど、それはオプショナルツアーなり、個人旅行で補完してくださいって割り切りが大切なのかもしれません。
この本に出会わなければカエサルの呆れんばかりの天才的活躍や、ハンニバルの不屈の闘志を知らずに人生を過ごしただろうと思うと、それだけでもこの本には感謝したい思いです。
「ローマ人〜」の評価は人それぞれのようですが、私にとってはローマ史入門書としてこれ以上無い良書だと思っています。1000年にも及ぶ歴史を淡々と書き連ねるだけでも無く、かと言って過度に装飾してある訳でもなく、喩えて言うならばタイムトラベルの出来の良いパッケージツアーのような。
当然、パッケージツアーですから細かいところで説明の足りないところや、見落としているところもあるでしょうけど、それはオプショナルツアーなり、個人旅行で補完してくださいって割り切りが大切なのかもしれません。
この本に出会わなければカエサルの呆れんばかりの天才的活躍や、ハンニバルの不屈の闘志を知らずに人生を過ごしただろうと思うと、それだけでもこの本には感謝したい思いです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
司馬遼太郎 更新情報
-
最新のアンケート