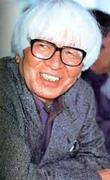|
|
|
|
コメント(4)
主人公も出来も確かに地味〜な感じの歴史ドラマですよね。
木戸孝允や大久保利通・西郷隆盛など登場人物の基礎情報なしには楽しめない不親切な作品でもあると思います。
だいたい江藤新平って誰だっけ?って感じですよね。
逆に言うと、司馬遼太郎づいている人間にとってはなかなか味わい深い。
「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」や「燃えよ剣」や「翔ぶがごとく」を読んで「面白いけどこのエンタテインメントぶりはどうよ?」などと思っている方にとってはちょっと「へ〜」な感じです。
華がない。
闘うのが下手で人間的魅力もあまりない人間が、幕末から維新の中でどう振り回され、使い捨てられていったのか・・・
という生生しさがあるように感じました。
早死にしていった人々が伝説となり。
事を成し遂げた人間が没落してゆく渋みがあったり。
そんな歴史ドラマではなく。
(そういう人々に対して、残された人々は希望やロマンを託したくなってしまいますよね)
良くも悪くもなく、年月が流れていくこと、世の中がうねってゆくことの哀しさと昆虫的な無情さこそがこの作品の魅力だと思います。
プロジェクトXのエンディング「ヘッドライト・テールライト」(中島みゆき)みたいな感じですよね。
♪行く先は降る雨と経る時の中に消えて
流れる歌は英雄のために過ぎても
ヘッドライト・テールライト旅はまだ終わらない
と言っているうちに終わってゆく無数の人生の存在をちょっと感じさせます。
勿論、明治の元勲として日本国の法制度の基礎を作り上げた栄光は、現代の我々からは想像を絶するものがあるのでしょうが。
それにしても江藤新平は地味で、華がない。
でも、そこに光を当てることが出来たのは、司馬遼太郎が積み重ねてきたドラマの数々の功績です。大量の人々に「明治維新」という現象に目を向けさせることに成功してきたからこそ存在しうる作品だと思います。
「竜馬が行く」の成功がなければ「歳月」はほとんど相手にされない小説でしょう。
だからこそ。
だからこその価値をこの小説に感じます。
司馬遼太郎という人が、全身を振り絞って向き合った江戸時代とか幕末とか政治とか戦争とかって、本当のところどうだったんだろう?
という疑問まで喚起させる良品だと思います。
ちなみに・・・
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/quwatoro/bakumatu.shtml
このサイト、いいですね。
小説を読みながら顔写真を出してゆけば楽しさ倍増です。
想像力は限定されることから豊かになっていくことが多々あります。すでに終わってしまったドラマだからこそのトキメキが歴史にはありますよね。
木戸孝允や大久保利通・西郷隆盛など登場人物の基礎情報なしには楽しめない不親切な作品でもあると思います。
だいたい江藤新平って誰だっけ?って感じですよね。
逆に言うと、司馬遼太郎づいている人間にとってはなかなか味わい深い。
「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」や「燃えよ剣」や「翔ぶがごとく」を読んで「面白いけどこのエンタテインメントぶりはどうよ?」などと思っている方にとってはちょっと「へ〜」な感じです。
華がない。
闘うのが下手で人間的魅力もあまりない人間が、幕末から維新の中でどう振り回され、使い捨てられていったのか・・・
という生生しさがあるように感じました。
早死にしていった人々が伝説となり。
事を成し遂げた人間が没落してゆく渋みがあったり。
そんな歴史ドラマではなく。
(そういう人々に対して、残された人々は希望やロマンを託したくなってしまいますよね)
良くも悪くもなく、年月が流れていくこと、世の中がうねってゆくことの哀しさと昆虫的な無情さこそがこの作品の魅力だと思います。
プロジェクトXのエンディング「ヘッドライト・テールライト」(中島みゆき)みたいな感じですよね。
♪行く先は降る雨と経る時の中に消えて
流れる歌は英雄のために過ぎても
ヘッドライト・テールライト旅はまだ終わらない
と言っているうちに終わってゆく無数の人生の存在をちょっと感じさせます。
勿論、明治の元勲として日本国の法制度の基礎を作り上げた栄光は、現代の我々からは想像を絶するものがあるのでしょうが。
それにしても江藤新平は地味で、華がない。
でも、そこに光を当てることが出来たのは、司馬遼太郎が積み重ねてきたドラマの数々の功績です。大量の人々に「明治維新」という現象に目を向けさせることに成功してきたからこそ存在しうる作品だと思います。
「竜馬が行く」の成功がなければ「歳月」はほとんど相手にされない小説でしょう。
だからこそ。
だからこその価値をこの小説に感じます。
司馬遼太郎という人が、全身を振り絞って向き合った江戸時代とか幕末とか政治とか戦争とかって、本当のところどうだったんだろう?
という疑問まで喚起させる良品だと思います。
ちなみに・・・
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/quwatoro/bakumatu.shtml
このサイト、いいですね。
小説を読みながら顔写真を出してゆけば楽しさ倍増です。
想像力は限定されることから豊かになっていくことが多々あります。すでに終わってしまったドラマだからこそのトキメキが歴史にはありますよね。
昨晩読み終えました。前半の江藤新平は颯爽として格好良いですよね。山県有朋を追い詰める場面なんか最高です。ところが後半は読んでてイライラさせられる。義経を読んでる時に感じたようなイライラ感。
共通してるんでしょうか?古代から中世の扉を開けたのは清盛。近世から近代の扉を開けたのは竜馬。いずれも役目を果たすと早々に歴史の舞台から消えていきました(中世から近世の扉を開けた信長も然り)。ところが義経も江藤もその扉を開ける時に主役ではないもののかなり重要な役どころを占めたわけです。いなければ時代は転換しなかったんじゃないか、と。でも役割を果たしてとっとといなくなってしまいました。
虚しく切ない読後感です。
共通してるんでしょうか?古代から中世の扉を開けたのは清盛。近世から近代の扉を開けたのは竜馬。いずれも役目を果たすと早々に歴史の舞台から消えていきました(中世から近世の扉を開けた信長も然り)。ところが義経も江藤もその扉を開ける時に主役ではないもののかなり重要な役どころを占めたわけです。いなければ時代は転換しなかったんじゃないか、と。でも役割を果たしてとっとといなくなってしまいました。
虚しく切ない読後感です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
司馬遼太郎 更新情報
-
最新のアンケート
司馬遼太郎のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75480人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6436人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人