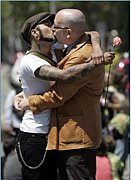READING THOUGHT vol.8
『建てる・住まう・考える』マルティン・ハイデッガー著
このテキストは、1951年にダルムシュタットという場所で行われた講演をもとにしている。この年から始まる10年すなわち1950年代は、近代建築への確信が世界規模で揺らいだ時代である。スミッソン夫妻ら若手たちによってCIAM会議が掻き回される。コルビュジエは、ロンシャンの教会などという、それまでの明快さとはうってかわった奇妙なモノをつくり出す。そんな時代。
ハイデッガーのこの講演が行われたのは、コルビュジエやミースなど近代建築を紹介する展覧会に合わせてであった。展覧会の詳しい中身は判らない。しかし、ヴァイセンホフのジードルンクもその展示に含まれていたことから、少なくとも時代の流れを先取るようなものではなかっただろうことが、推測されよう。
とはいえハイデッガーの講演自体は、時代の潮流に沿う内容のものである。たとえば以下の箇所にも、その反近代建築的な態度は、見受けられる。
_
人々は、当然ながら至る所で、住まいの危機に話を向ける。そして、これを話題にするばかりではなく、その課題に手を着ける。彼らは、住居の供給や住宅建設の振興や団地全体の建設事業を計画することでその危機を取り除こうとする。
しかし、住居の欠乏がこのように厳しく耐え難く、われわれの足かせや脅威になっているとはしても、<住まうことの真の危機>は、ただ住居の不足だけにあるのではない。(・・・)つまり、死すべき者は、住まうことの本性をそのつど初めから探し求めなければならない。
_(45−46頁)
「住まうこと」に関する危機が、供給や計画では取り除けない事柄らしい。ハイデッガーの近代建築への問題意識は、けっきょくすべてここに収束されると言ってよい。
*
タイトルから判る通り、ハイデッガーはとても根本的な話をしている。内容についてはだいたい二つに分けられる。言葉の定義をめぐる思索と、空間や場所という概念の現象学的考察と。
言葉の定義をめぐる思索
ハイデッガーはドイツ人である。思索はドイツ語の語源や歴史的変遷をめぐって、行われる。正直いって、日本語を母国語にする身からでは、あまり実感の伴う内容ではない。
解釈してしまおう。無理矢理にでもハイデッガーの言いたいであろうことを建築家目線で展開すると、きっとこうなる。
「建てる」 :近代建築
「建てる」「住まう」 :懐古主義
「建てる」「住まう」「考える」 :ハイデッガーの建築論
この三項において変動しているファクターは、建築家と施主の関係における<時間>である。上から順に、<非同期><同期><疑似同期>と言い換えて、考えたい。
<非同期>。ここでは建築家と施主はまったく時間を共有していない。建築家は与え、施主は受領する。売ると買うの関係。近代建築は大規模計画と大量生産を基本理念に据え、「建てる」は「住まう」から区別された。建築は瞬間的な行為としての「建てる」に留まる。重層的な時間性を特徴とする「住まう」は、そこではまったく捨象されている。
<同期>は、建築家と施主が完全に時間を共有することである。ハイデッガーは上の近代建築的な考えに抗する。元来「建てること(バウエン)」は、「住まうこと(ヴォーネン)」さらには「存在すること」に帰属するのだと、語源を遡って示す。それはつまり、過去において建築家と施主は同一人物、あるいはそれに準ずる程に親しい関係であったことと、同義である。それが、同期的状況である。これはある種のペシミズムを含む。なぜならそこに近代的な建築家像は必要とされないから。忙しくて細分化した知識しか持ち得ない20世紀以降においては、この場合、建築家は自邸程度しか作れない。リノベーションやセルフビルドの手助け程度の仕事なら、できるが。
最後に、<疑似同期>。建築家と施主が同一ではないにも関わらず、時間を共有している<かのような>状況である。ここで「考えること」という、タイトルに挙げられた最後の言葉が重要になる。「考えること」とは時間性という点において決定的に異なる「建てること」と「住まうこと」、および建築家と施主の、想像的架橋である。ただ、このようなことに対して、ハイデッガーは具体的な解決策を呈示しているわけではない。本書で書かれるのは方法論的な事柄ではなく、あくまでスタンスとか、いやもっと漠然とした、建築家であるための心意気のようなものである。だから、言いっ放しのようにも、感じられる。例えばこんな風に言われたとしても、どうればいいの?
_
住むことと建てること、それが<問いに値するもの>となり、それゆえ何らかの<思索に値するもの>で在り続けるのなら、それだけでも(われわれには)十分であろう。
(・・・)つまり、「考えること」それ自体が、建てることと同じ意味で、ただし別の仕方で、住まうことに帰属するということである。(・・・)
つまり、「建てること」と「考えること」、それらはいずれも同様に、長い経験と絶え間のない修練のアトリエから生まれてくる。
_(44頁)
空間や場所という概念の現象学的考察
一般にハイデッガーは、現象学に基礎をおく哲学者だとされる。現象学には共通のテーマがある。空間である。その語られ方はけっこう、どれも似ているように思われる。
原広司によれば、20世紀において「空間は相対化された」のである。つまり生産されたり、制作されたり、実践されたりするようになった。それまでの空間観はカントに代表されよう。カントは、事物を認識するうえでの前提条件=ア・プリオリなものとして、空間(と時間)を捉える。このとき空間は手が触れられない、絶対的な領域にあったと言える。20世紀になって、その絶対的な領域から空間は落っこちてきた。手が届き、手が加えられるものとなった。こうした空間観は、世紀初頭のポアンカレやマッハらによる数学の領域から、生まれた。
さて、ハイデッガーは本書の中でも様々に空間を言い換え、論じている。
_
これらの四者−大地、天空、神的なもの、死すべき者−は、ひとつの<根源的>な統一によって、唯一の事柄に属している。
_(15頁)
ここで用いられている「大地」と「天空」という言葉に関しては、ほとんど一般的な意味で捉えてよい。「神的なもの」は、要するに人間が把握できないようなルールや他者のことである。後には「摂理」とも、換言される。「死すべき者」とは人間(=現存在)を指す。そして、この四者が出逢い「<根源的>な統一」を示す地点こそ、空間である。
但し、この四者は四者で完結しない。なぜなら死すべき者が「存在する」ということは、「建てること(Bauen」であるから。だから本当は、判り易く言えば、四者(大地、天空、他者、人間)+「建て物」という五者による<根源的な>統一が、空間、ということになる。あくまでそれまでの論述によって「死すべき者」と「建て物」はイコールでほとんど結ばれてしまうから、そういう意味で、空間は四者による「四者の会域」と、表現されるのである。そして「建て物」は、その「立脚地を許し与える」。このような空間は、カント的な<あの唯一の空間>とは全く区別され、「場所」と言われる。
_
橋(=「建て物」)は、ひとつの場所である。そのような物として、橋はひとつの空間を受け容れる。その空間に、大地と天空、神的なものと死すべき者が引き受けられる。
_(29頁)
現代において私たちが使っている、<場所性>という言葉を、思い起こしてもらいたい。私たちが使う場所性とは、普遍性ではなく個別性、抽象的というより手が触れる具体的なものを示したいときに、持ち出される概念である。ハイデッガーの言う、「空間」を受け容れる「場所」とはまさにそのことであり、「建て物」はその発生のための、必要不可欠事として存在しているのである。
フランスの現象学者メルロ=ポンティの、空間についての有名な言葉がある。
_
われわれの身体が空間のなかにあるとか、時間の中にあるとかと、表現してはならない。われわれの身体は、空間や時間に住み込むのである。
_(『知覚の現象学1』235頁)
ハイデッガーの考えも、基本的には同じである。
_
人間と空間の関わりとは、本来の意味で考えた「住まうこと」にほかならない。
_(36頁)
メルロ=ポンティとハイデッガーはどこが違うのか。それは、そのような空間が、「建てること」ではじめて可能なものとして呈示したことに、ほかならない。そして「建てること」とは「住まうこと」であり、「存在すること」であり、しかしその同期的状況は見込めないから「考えること」によって想像的・擬似同期を求め、、、
建築家は、ハイデッガーの現象学の中心にいた。
『建てる・住まう・考える』マルティン・ハイデッガー著
このテキストは、1951年にダルムシュタットという場所で行われた講演をもとにしている。この年から始まる10年すなわち1950年代は、近代建築への確信が世界規模で揺らいだ時代である。スミッソン夫妻ら若手たちによってCIAM会議が掻き回される。コルビュジエは、ロンシャンの教会などという、それまでの明快さとはうってかわった奇妙なモノをつくり出す。そんな時代。
ハイデッガーのこの講演が行われたのは、コルビュジエやミースなど近代建築を紹介する展覧会に合わせてであった。展覧会の詳しい中身は判らない。しかし、ヴァイセンホフのジードルンクもその展示に含まれていたことから、少なくとも時代の流れを先取るようなものではなかっただろうことが、推測されよう。
とはいえハイデッガーの講演自体は、時代の潮流に沿う内容のものである。たとえば以下の箇所にも、その反近代建築的な態度は、見受けられる。
_
人々は、当然ながら至る所で、住まいの危機に話を向ける。そして、これを話題にするばかりではなく、その課題に手を着ける。彼らは、住居の供給や住宅建設の振興や団地全体の建設事業を計画することでその危機を取り除こうとする。
しかし、住居の欠乏がこのように厳しく耐え難く、われわれの足かせや脅威になっているとはしても、<住まうことの真の危機>は、ただ住居の不足だけにあるのではない。(・・・)つまり、死すべき者は、住まうことの本性をそのつど初めから探し求めなければならない。
_(45−46頁)
「住まうこと」に関する危機が、供給や計画では取り除けない事柄らしい。ハイデッガーの近代建築への問題意識は、けっきょくすべてここに収束されると言ってよい。
*
タイトルから判る通り、ハイデッガーはとても根本的な話をしている。内容についてはだいたい二つに分けられる。言葉の定義をめぐる思索と、空間や場所という概念の現象学的考察と。
言葉の定義をめぐる思索
ハイデッガーはドイツ人である。思索はドイツ語の語源や歴史的変遷をめぐって、行われる。正直いって、日本語を母国語にする身からでは、あまり実感の伴う内容ではない。
解釈してしまおう。無理矢理にでもハイデッガーの言いたいであろうことを建築家目線で展開すると、きっとこうなる。
「建てる」 :近代建築
「建てる」「住まう」 :懐古主義
「建てる」「住まう」「考える」 :ハイデッガーの建築論
この三項において変動しているファクターは、建築家と施主の関係における<時間>である。上から順に、<非同期><同期><疑似同期>と言い換えて、考えたい。
<非同期>。ここでは建築家と施主はまったく時間を共有していない。建築家は与え、施主は受領する。売ると買うの関係。近代建築は大規模計画と大量生産を基本理念に据え、「建てる」は「住まう」から区別された。建築は瞬間的な行為としての「建てる」に留まる。重層的な時間性を特徴とする「住まう」は、そこではまったく捨象されている。
<同期>は、建築家と施主が完全に時間を共有することである。ハイデッガーは上の近代建築的な考えに抗する。元来「建てること(バウエン)」は、「住まうこと(ヴォーネン)」さらには「存在すること」に帰属するのだと、語源を遡って示す。それはつまり、過去において建築家と施主は同一人物、あるいはそれに準ずる程に親しい関係であったことと、同義である。それが、同期的状況である。これはある種のペシミズムを含む。なぜならそこに近代的な建築家像は必要とされないから。忙しくて細分化した知識しか持ち得ない20世紀以降においては、この場合、建築家は自邸程度しか作れない。リノベーションやセルフビルドの手助け程度の仕事なら、できるが。
最後に、<疑似同期>。建築家と施主が同一ではないにも関わらず、時間を共有している<かのような>状況である。ここで「考えること」という、タイトルに挙げられた最後の言葉が重要になる。「考えること」とは時間性という点において決定的に異なる「建てること」と「住まうこと」、および建築家と施主の、想像的架橋である。ただ、このようなことに対して、ハイデッガーは具体的な解決策を呈示しているわけではない。本書で書かれるのは方法論的な事柄ではなく、あくまでスタンスとか、いやもっと漠然とした、建築家であるための心意気のようなものである。だから、言いっ放しのようにも、感じられる。例えばこんな風に言われたとしても、どうればいいの?
_
住むことと建てること、それが<問いに値するもの>となり、それゆえ何らかの<思索に値するもの>で在り続けるのなら、それだけでも(われわれには)十分であろう。
(・・・)つまり、「考えること」それ自体が、建てることと同じ意味で、ただし別の仕方で、住まうことに帰属するということである。(・・・)
つまり、「建てること」と「考えること」、それらはいずれも同様に、長い経験と絶え間のない修練のアトリエから生まれてくる。
_(44頁)
空間や場所という概念の現象学的考察
一般にハイデッガーは、現象学に基礎をおく哲学者だとされる。現象学には共通のテーマがある。空間である。その語られ方はけっこう、どれも似ているように思われる。
原広司によれば、20世紀において「空間は相対化された」のである。つまり生産されたり、制作されたり、実践されたりするようになった。それまでの空間観はカントに代表されよう。カントは、事物を認識するうえでの前提条件=ア・プリオリなものとして、空間(と時間)を捉える。このとき空間は手が触れられない、絶対的な領域にあったと言える。20世紀になって、その絶対的な領域から空間は落っこちてきた。手が届き、手が加えられるものとなった。こうした空間観は、世紀初頭のポアンカレやマッハらによる数学の領域から、生まれた。
さて、ハイデッガーは本書の中でも様々に空間を言い換え、論じている。
_
これらの四者−大地、天空、神的なもの、死すべき者−は、ひとつの<根源的>な統一によって、唯一の事柄に属している。
_(15頁)
ここで用いられている「大地」と「天空」という言葉に関しては、ほとんど一般的な意味で捉えてよい。「神的なもの」は、要するに人間が把握できないようなルールや他者のことである。後には「摂理」とも、換言される。「死すべき者」とは人間(=現存在)を指す。そして、この四者が出逢い「<根源的>な統一」を示す地点こそ、空間である。
但し、この四者は四者で完結しない。なぜなら死すべき者が「存在する」ということは、「建てること(Bauen」であるから。だから本当は、判り易く言えば、四者(大地、天空、他者、人間)+「建て物」という五者による<根源的な>統一が、空間、ということになる。あくまでそれまでの論述によって「死すべき者」と「建て物」はイコールでほとんど結ばれてしまうから、そういう意味で、空間は四者による「四者の会域」と、表現されるのである。そして「建て物」は、その「立脚地を許し与える」。このような空間は、カント的な<あの唯一の空間>とは全く区別され、「場所」と言われる。
_
橋(=「建て物」)は、ひとつの場所である。そのような物として、橋はひとつの空間を受け容れる。その空間に、大地と天空、神的なものと死すべき者が引き受けられる。
_(29頁)
現代において私たちが使っている、<場所性>という言葉を、思い起こしてもらいたい。私たちが使う場所性とは、普遍性ではなく個別性、抽象的というより手が触れる具体的なものを示したいときに、持ち出される概念である。ハイデッガーの言う、「空間」を受け容れる「場所」とはまさにそのことであり、「建て物」はその発生のための、必要不可欠事として存在しているのである。
フランスの現象学者メルロ=ポンティの、空間についての有名な言葉がある。
_
われわれの身体が空間のなかにあるとか、時間の中にあるとかと、表現してはならない。われわれの身体は、空間や時間に住み込むのである。
_(『知覚の現象学1』235頁)
ハイデッガーの考えも、基本的には同じである。
_
人間と空間の関わりとは、本来の意味で考えた「住まうこと」にほかならない。
_(36頁)
メルロ=ポンティとハイデッガーはどこが違うのか。それは、そのような空間が、「建てること」ではじめて可能なものとして呈示したことに、ほかならない。そして「建てること」とは「住まうこと」であり、「存在すること」であり、しかしその同期的状況は見込めないから「考えること」によって想像的・擬似同期を求め、、、
建築家は、ハイデッガーの現象学の中心にいた。
|
|
|
|
|
|
|
|
READINGTHOUGT 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
READINGTHOUGTのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170685人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90046人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人