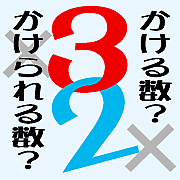私自身は理学部数学科出身です。かけ算の順序に関心を持って以降、とりわけここ数年、算数教育について色々調べています。
等分除・包含除・添加・合併・求残・内包量・外延量などというのも数年前に初めて知りました。
検索で見つけたこの文章を読んで疑問が沸いてきました。
http://
この人自身は大学4年で「わり算の2つの意味」を知ったとあります。そのようなわり算の分類が本質的であるかの如く思っているようにも感じられます。
この人は、「2つの意味」を大学の授業で教わったのだろうか?「一見2つの意味があるように見えるが本質的には同じ事である」とは教わらなかったのだろうか?
>一見同じように見えることだが、導入部分にいて教師がこの違いをしっかり把握しておかなければ、子ども達を混乱させる恐れがある。また、この二つを区別しないと、割り算の計算には本来意味があるはずなのに、計算技術だけを学んでしまうことになり、その後の算数の学びが進みにくくなるのではないだろうか。
これなどは私と認識が180°逆である。
数学者や理学部の学生が等分除と包含除の違いなど意識もしないと思うのだが、数学の理解に支障はないと思う。
教育学部では、一体どのようなことが教えられているのだろうか?、「等分除・包含除・添加・合併・求残・・・」などという概念を教わるのだろうか?「それらは教える上での便宜的区別で本質的なものではない」ときちんと説明されているのだろうか?
このあたりのことを知りたいと思います。
情報お持ちの方は教えて下さい。
等分除・包含除・添加・合併・求残・内包量・外延量などというのも数年前に初めて知りました。
検索で見つけたこの文章を読んで疑問が沸いてきました。
http://
この人自身は大学4年で「わり算の2つの意味」を知ったとあります。そのようなわり算の分類が本質的であるかの如く思っているようにも感じられます。
この人は、「2つの意味」を大学の授業で教わったのだろうか?「一見2つの意味があるように見えるが本質的には同じ事である」とは教わらなかったのだろうか?
>一見同じように見えることだが、導入部分にいて教師がこの違いをしっかり把握しておかなければ、子ども達を混乱させる恐れがある。また、この二つを区別しないと、割り算の計算には本来意味があるはずなのに、計算技術だけを学んでしまうことになり、その後の算数の学びが進みにくくなるのではないだろうか。
これなどは私と認識が180°逆である。
数学者や理学部の学生が等分除と包含除の違いなど意識もしないと思うのだが、数学の理解に支障はないと思う。
教育学部では、一体どのようなことが教えられているのだろうか?、「等分除・包含除・添加・合併・求残・・・」などという概念を教わるのだろうか?「それらは教える上での便宜的区別で本質的なものではない」ときちんと説明されているのだろうか?
このあたりのことを知りたいと思います。
情報お持ちの方は教えて下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
算数「かけ算の順序」を考える 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-