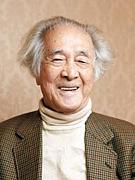|
|
|
|
コメント(46)
>>マーラーの9番について
>日本初演がアマチュアオケだったという記載があったような記憶が。
マーラーの演奏史に関して詳しくないのですが
1967年にコンドラシン指揮 1970年にバーンスタイン
1973年に森正+N響が東京で演奏していると記憶するので、それ以前に日本で
演奏されているとしたらプリングスハイム辺り。
コンドラシンの日本での演奏の録音は発売されています。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/2730337
6番など他の交響曲はプリングスハイムが東京芸大オケと1930年代に
日本初演していているので、その話では?
今、吉田秀和氏は今は、特定の演奏家が面白いといういうより全ての
演奏家がそれなりに価値があるという言い方なのです。
人にお薦めを聞いて、安上がりに良い物を買おうという人に対して
何も参考になることは書いてないと思います。
レヴァインやテンシュテットのアナログ盤が最初に日本で出たとき
新時代のマーラーとして、凄く誉めてましたけど、どこに、それらの
文章が残っているか直ぐに分かりません。
最近の演奏、録音は、あまり聞いてないかもしれませんね。
>日本初演がアマチュアオケだったという記載があったような記憶が。
マーラーの演奏史に関して詳しくないのですが
1967年にコンドラシン指揮 1970年にバーンスタイン
1973年に森正+N響が東京で演奏していると記憶するので、それ以前に日本で
演奏されているとしたらプリングスハイム辺り。
コンドラシンの日本での演奏の録音は発売されています。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/2730337
6番など他の交響曲はプリングスハイムが東京芸大オケと1930年代に
日本初演していているので、その話では?
今、吉田秀和氏は今は、特定の演奏家が面白いといういうより全ての
演奏家がそれなりに価値があるという言い方なのです。
人にお薦めを聞いて、安上がりに良い物を買おうという人に対して
何も参考になることは書いてないと思います。
レヴァインやテンシュテットのアナログ盤が最初に日本で出たとき
新時代のマーラーとして、凄く誉めてましたけど、どこに、それらの
文章が残っているか直ぐに分かりません。
最近の演奏、録音は、あまり聞いてないかもしれませんね。
TO : No.18 モントゥーさん
ワルターが多少控えめだったとすると、バーンスタインはオーバーにいっちゃっているほうだと思う。マーラーの音楽の中からエモーショナルな部分を強調している指揮のような気がしますね。自分がそれになりきったみたいになって、泣いたりわめいたり恍惚としたりして、指揮してますね、あの人は…。
それから自然に対するマーラーの愛が一番すなおにでているのはクーベリックだと思うな。しかし、マーラーの今度は非常に神経質な、それで、非常に退廃したような面というのは、やっぱりクーベリックで聴いているとだめだね。そうゆうものはやっぱりバーンスタインやなんかに、とてもいいところがあるし、しれからショリティだな。
ショルティは、ずいぶんマーラーの鋭い、前進的なものをよくつかまえているような気がする。そのかわり少しやわらかみがなくなっちゃているけどね。
吉田秀和 愛聴盤&参考レコード
交響曲第一番
☆ワルター/コロムビアso. (CS)
☆ジュリーニ/シカゴso. (EMI)
交響曲第二番
バーンスタイン/ロンドンso. (CS)
クレンペラー/フィルハーモニアO. (EMI)
交響曲第三番
☆クーベリック/バイエルン放送so. (DG)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第四番
☆バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
ワルター/ニューヨークpo. (CS)
メンゲルベルク/コンセルトヘボウO. (Fontana)
交響曲第五番
☆ワルター/ニューヨークpo. (CS)
☆バルビローリ/ニュ・フィルハーモニアO. (EMI)
交響曲第六番
☆ショルティ/シカゴso. (Decca)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第七番
☆クレンペラー/フィルハーモニアO. (EMI)
ショルティ/シカゴso. (Decca)
交響曲第八番
ショルティ/シカゴso. (Decca)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第九番
☆ワルター/コロムビアso. (CS)
☆バルビローリ/ベルリンpo. (EMI)
交響曲「大地の歌」
☆フェリア、パツァーク、ワルター/ウィーンpo. (Decca)
☆F=ディースカウ、キング、バーンスタイン/ウィーンpo. (CS)
吉田秀和 音楽を語る(下巻)より 1975年1月25日初版
p.s.シカゴ響とレヴァインが録音した、五,六,七番あたりのRCA盤を推薦していたのを、吉田さんの本で記憶してます。あとは、フィルハーモニアO.とシノーポリが録音した五番(EMI)をレコ芸の連載に書いてました。
ワルターが多少控えめだったとすると、バーンスタインはオーバーにいっちゃっているほうだと思う。マーラーの音楽の中からエモーショナルな部分を強調している指揮のような気がしますね。自分がそれになりきったみたいになって、泣いたりわめいたり恍惚としたりして、指揮してますね、あの人は…。
それから自然に対するマーラーの愛が一番すなおにでているのはクーベリックだと思うな。しかし、マーラーの今度は非常に神経質な、それで、非常に退廃したような面というのは、やっぱりクーベリックで聴いているとだめだね。そうゆうものはやっぱりバーンスタインやなんかに、とてもいいところがあるし、しれからショリティだな。
ショルティは、ずいぶんマーラーの鋭い、前進的なものをよくつかまえているような気がする。そのかわり少しやわらかみがなくなっちゃているけどね。
吉田秀和 愛聴盤&参考レコード
交響曲第一番
☆ワルター/コロムビアso. (CS)
☆ジュリーニ/シカゴso. (EMI)
交響曲第二番
バーンスタイン/ロンドンso. (CS)
クレンペラー/フィルハーモニアO. (EMI)
交響曲第三番
☆クーベリック/バイエルン放送so. (DG)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第四番
☆バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
ワルター/ニューヨークpo. (CS)
メンゲルベルク/コンセルトヘボウO. (Fontana)
交響曲第五番
☆ワルター/ニューヨークpo. (CS)
☆バルビローリ/ニュ・フィルハーモニアO. (EMI)
交響曲第六番
☆ショルティ/シカゴso. (Decca)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第七番
☆クレンペラー/フィルハーモニアO. (EMI)
ショルティ/シカゴso. (Decca)
交響曲第八番
ショルティ/シカゴso. (Decca)
バーンスタイン/ニューヨークpo. (CS)
交響曲第九番
☆ワルター/コロムビアso. (CS)
☆バルビローリ/ベルリンpo. (EMI)
交響曲「大地の歌」
☆フェリア、パツァーク、ワルター/ウィーンpo. (Decca)
☆F=ディースカウ、キング、バーンスタイン/ウィーンpo. (CS)
吉田秀和 音楽を語る(下巻)より 1975年1月25日初版
p.s.シカゴ響とレヴァインが録音した、五,六,七番あたりのRCA盤を推薦していたのを、吉田さんの本で記憶してます。あとは、フィルハーモニアO.とシノーポリが録音した五番(EMI)をレコ芸の連載に書いてました。
音楽展望1990年の「バーンスタインの死」というエッセーに「バーンスタインのマーラーは余人をもってはかえられないもので、私は、それがもう二度と接しられなくなってしまったことを、嘆く」とあります。
1979年の別の文章で、「戦後におけるマーラーの復活、そのブームにはバーンスタインの存在が欠かせない。いやこの人のこういう没我的狂熱的なマーラー支持があったればこそ、作曲者の死後ずっと忘れ、おきざりにされてきたマーラーへの現代の感心が生まれてきたのではないだろうか。そう、私たち今日の人間が持つようになったマーラーの音楽への渇えは、この人が教えたものである。」とあります。
マーラー復活のブームが起こる前から、ずっと音楽に関わってこられたキャリアをお持ちの吉田氏にとって、特にマーラーにこだわる必要はなさそうですが、長期にわたる朝日新聞の音楽展望への連載をみると、マーラーに言及したものは、決して少なくありません。
たとえば79年7月19日のエッセーでは・・・もしマーラーがこれを聞いたら「この男は私を理解した。私の一見複雑にからみあったスコアも、要するに自分の考えをできるだけ正確に伝えようとしたところから来たのであり、この指揮者は、私のスコアに何かをつけ加えようというのではなくて、それを正確に読みほぐすことに全力をつくしたのだ」といったろうと思う。マーラーがこの人の棒でほど、静けさにみち、クリアーで、しかも充実して響いたことはなかったろう。とあります。
吉田氏が激賞しているのは、レヴァインのRCA録音のこと。バーンスタインの巨人的啓示のあとに来た新世代の音楽の到来を歓迎されてます。
1979年の別の文章で、「戦後におけるマーラーの復活、そのブームにはバーンスタインの存在が欠かせない。いやこの人のこういう没我的狂熱的なマーラー支持があったればこそ、作曲者の死後ずっと忘れ、おきざりにされてきたマーラーへの現代の感心が生まれてきたのではないだろうか。そう、私たち今日の人間が持つようになったマーラーの音楽への渇えは、この人が教えたものである。」とあります。
マーラー復活のブームが起こる前から、ずっと音楽に関わってこられたキャリアをお持ちの吉田氏にとって、特にマーラーにこだわる必要はなさそうですが、長期にわたる朝日新聞の音楽展望への連載をみると、マーラーに言及したものは、決して少なくありません。
たとえば79年7月19日のエッセーでは・・・もしマーラーがこれを聞いたら「この男は私を理解した。私の一見複雑にからみあったスコアも、要するに自分の考えをできるだけ正確に伝えようとしたところから来たのであり、この指揮者は、私のスコアに何かをつけ加えようというのではなくて、それを正確に読みほぐすことに全力をつくしたのだ」といったろうと思う。マーラーがこの人の棒でほど、静けさにみち、クリアーで、しかも充実して響いたことはなかったろう。とあります。
吉田氏が激賞しているのは、レヴァインのRCA録音のこと。バーンスタインの巨人的啓示のあとに来た新世代の音楽の到来を歓迎されてます。
音楽展望からもう一つ引用。簡潔にして急所を突いた慧眼としかいいようがない文章。
*************************************************************************
マーラーは旺盛な自我意識に悩まされた人だが、彼は決して自己中心的に終始できず、自分をとりまく外部世界に対し、いつも注意深い態度で立ち向かわずにはいられなかった。
「生と死」とか「復活」とか「人生と自然の意味」とか、自分一個を超えた普遍的な問題への答えを常に求めていた人である。それがマーラーの交響曲の中に、森、花、小鳥、霧、風といった自然に通じる響きが吹き通ってくる理由だし、天使や子供のような人間の隣にいて、しかも人間を超えた存在に対する比類のない柔らかな感応性の働きや豊かな幻想性となって、彼の音楽のいたるところに光と色を与えている理由である。
*************************************************************************
マーラーは旺盛な自我意識に悩まされた人だが、彼は決して自己中心的に終始できず、自分をとりまく外部世界に対し、いつも注意深い態度で立ち向かわずにはいられなかった。
「生と死」とか「復活」とか「人生と自然の意味」とか、自分一個を超えた普遍的な問題への答えを常に求めていた人である。それがマーラーの交響曲の中に、森、花、小鳥、霧、風といった自然に通じる響きが吹き通ってくる理由だし、天使や子供のような人間の隣にいて、しかも人間を超えた存在に対する比類のない柔らかな感応性の働きや豊かな幻想性となって、彼の音楽のいたるところに光と色を与えている理由である。
別のコミュに書いたものですが、参考になると思います。
吉田秀和は、マーラーを語る最初に、マーラーが優れた芸術家であることを精密に論じています。そして、その傍証として、シェーンベルクを引用しています。(以下引用です)
この二十世紀音楽の父親の中で最も非妥協的だった芸術家(シェーンベルクのことです:センマオ注)は、いきなりこう言ってのける。
「多くの言葉を費やすより、ごく端的に言うのが一番良いでしょう。グスタフ・マーラーが最も偉大な人間かつ芸術家の一人だったというのが、私の不動の核心であります、と。ある芸儒家について、人を納得させるやり方は二つしかない。一つはその作品を上演すること、もう一つは作品についての信念を吐露することです」と。(引用終わり)
(「吉田秀和作曲家論集1 ブルックナー・マーラー」128p〜129p)
この後でマーラーの音楽がどのように優れているかシェーンベルクが分析するところも吉田秀和は引用しています。
マーラーが作曲家として、いかに天才であったかということが述べられるわけです。
吉田秀和は、マーラーを高く評価しています。ショパンやチャイコフスキーへの低い評価とは全く異なります。
吉田秀和は、マーラーを語る最初に、マーラーが優れた芸術家であることを精密に論じています。そして、その傍証として、シェーンベルクを引用しています。(以下引用です)
この二十世紀音楽の父親の中で最も非妥協的だった芸術家(シェーンベルクのことです:センマオ注)は、いきなりこう言ってのける。
「多くの言葉を費やすより、ごく端的に言うのが一番良いでしょう。グスタフ・マーラーが最も偉大な人間かつ芸術家の一人だったというのが、私の不動の核心であります、と。ある芸儒家について、人を納得させるやり方は二つしかない。一つはその作品を上演すること、もう一つは作品についての信念を吐露することです」と。(引用終わり)
(「吉田秀和作曲家論集1 ブルックナー・マーラー」128p〜129p)
この後でマーラーの音楽がどのように優れているかシェーンベルクが分析するところも吉田秀和は引用しています。
マーラーが作曲家として、いかに天才であったかということが述べられるわけです。
吉田秀和は、マーラーを高く評価しています。ショパンやチャイコフスキーへの低い評価とは全く異なります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
吉田秀和――音楽評論とは何か 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
吉田秀和――音楽評論とは何かのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75497人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196030人