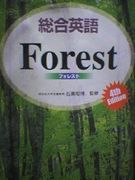In turn, the parents of these children are more likely to b teenagers or to have psychological problems of their own that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.
these childrenとは反社会的行動をとる子供です。
質問は、この訳の答えが、
またこのような子の親は、年齢がまだ10代だったり、自分達自身が心理的な問題をかかえていたりして、子育てが効果的に行えなかったり、厳しい、あるいは一貫性のない子育てになってしまいがちである。
なのですが、私は
またこのような子の親は、子育てが効果的にできなかったり、厳しく、あるいは一貫性のない子育てになるような心理的問題を持っていたり、10代だったりする傾向がある。
としました。
... psychological problems of their own that contribute to ineffective,... のthatは関係代名詞で、psychological problemsを先行詞としました。
質問は、答えのような和訳を導くにはどのような構文理解をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
these childrenとは反社会的行動をとる子供です。
質問は、この訳の答えが、
またこのような子の親は、年齢がまだ10代だったり、自分達自身が心理的な問題をかかえていたりして、子育てが効果的に行えなかったり、厳しい、あるいは一貫性のない子育てになってしまいがちである。
なのですが、私は
またこのような子の親は、子育てが効果的にできなかったり、厳しく、あるいは一貫性のない子育てになるような心理的問題を持っていたり、10代だったりする傾向がある。
としました。
... psychological problems of their own that contribute to ineffective,... のthatは関係代名詞で、psychological problemsを先行詞としました。
質問は、答えのような和訳を導くにはどのような構文理解をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(21)
どんな英文でもそうですが、「和訳」以前に英文そのものを語順に沿って理解することが先決です。
In turn,
the parents of these children 反社会的行動を取る子供たちの親というのは
are more likely よりしがちな傾向がある
(1) to be teenagers まだ10代である
or
(2) to have psychological problems of their own 自らが心理学的問題を抱えている
<どんな「心理学的問題」かというと
that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.
その問題が要因となっている
効果的でない子育ての
乱暴な子育ての
一貫性のない子育ての
骨子:
反社会的行動を取る子供の親にありがちな傾向性
1、まだ10代である
2、親自身が心理的問題を抱えている
2について具体的に言うと、自らが抱えている問題により
(1)子供を効果的に育てられない
(2)子供の育て方が乱暴である
(3)一貫性のない子育てをしてしまう
ここまで分かれば「さあ、こういうことを日本語ネイティブなら、どう表現するだろうか?」と考えればよいのです。
In turn,
the parents of these children 反社会的行動を取る子供たちの親というのは
are more likely よりしがちな傾向がある
(1) to be teenagers まだ10代である
or
(2) to have psychological problems of their own 自らが心理学的問題を抱えている
<どんな「心理学的問題」かというと
that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.
その問題が要因となっている
効果的でない子育ての
乱暴な子育ての
一貫性のない子育ての
骨子:
反社会的行動を取る子供の親にありがちな傾向性
1、まだ10代である
2、親自身が心理的問題を抱えている
2について具体的に言うと、自らが抱えている問題により
(1)子供を効果的に育てられない
(2)子供の育て方が乱暴である
(3)一貫性のない子育てをしてしまう
ここまで分かれば「さあ、こういうことを日本語ネイティブなら、どう表現するだろうか?」と考えればよいのです。
>3 つるももさん
文法構造という観点からいいますと
(1) to be teenagers まだ10代である
or
(2) to have psychological problems of their own 自らが心理学的問題を抱えている
この部分の「or」は「そうでないとすれば」に相当します。つまり(1)と(2)は次のようにも言い表せます。
「反社会的行動を取る子供の親というのは、まだ10代であることが多い。もしそうでないとすると、年齢的にはすでに20台であっても、精神的にまだ未熟であり、(that以下のような)問題を抱えていたりするものなのだ」
つまり「that以下」は(2)の「psychological problems」だけにかかるものです。
このような判別は「英文を語順に従って自然に解釈していく」ことからなされます。つまり「和訳する前に英語を理解する」ことなんです。
文法構造という観点からいいますと
(1) to be teenagers まだ10代である
or
(2) to have psychological problems of their own 自らが心理学的問題を抱えている
この部分の「or」は「そうでないとすれば」に相当します。つまり(1)と(2)は次のようにも言い表せます。
「反社会的行動を取る子供の親というのは、まだ10代であることが多い。もしそうでないとすると、年齢的にはすでに20台であっても、精神的にまだ未熟であり、(that以下のような)問題を抱えていたりするものなのだ」
つまり「that以下」は(2)の「psychological problems」だけにかかるものです。
このような判別は「英文を語順に従って自然に解釈していく」ことからなされます。つまり「和訳する前に英語を理解する」ことなんです。
shootingさんの構文解釈はあっているんです。
なのに和訳は、その構文解釈にのっとっていません。
>またこのような子の親は、子育てが効果的にできなかったり、厳しく、あるいは一貫性のない子育てになるような心理的問題を持っていたり、「10代だったりする傾向がある。 」
初めて見て不思議に感じたのは、なぜ「10代だったりする」を末尾に持ってきたのか?です。
英文では
the parents of these children are more likely to be teenagers
となっており、「そういう子供の親というのは、まだ10代であったりするものだ」が最初にきます。
本来、これだけで文章を打ち切ってもよいのですが、「or (まだ10代でないとすれば)」があとに続いているわけです。
英文は「語順に従って読む」ことがポイントです。
どんなに複雑そうに見える構文であったとしても、「相手が口にした順番でしか言葉は聞こえてこず、そこに書かれている順序でしか単語は目に入ってこない」という大原則を踏まえることが大切です。
なのに和訳は、その構文解釈にのっとっていません。
>またこのような子の親は、子育てが効果的にできなかったり、厳しく、あるいは一貫性のない子育てになるような心理的問題を持っていたり、「10代だったりする傾向がある。 」
初めて見て不思議に感じたのは、なぜ「10代だったりする」を末尾に持ってきたのか?です。
英文では
the parents of these children are more likely to be teenagers
となっており、「そういう子供の親というのは、まだ10代であったりするものだ」が最初にきます。
本来、これだけで文章を打ち切ってもよいのですが、「or (まだ10代でないとすれば)」があとに続いているわけです。
英文は「語順に従って読む」ことがポイントです。
どんなに複雑そうに見える構文であったとしても、「相手が口にした順番でしか言葉は聞こえてこず、そこに書かれている順序でしか単語は目に入ってこない」という大原則を踏まえることが大切です。
「和訳しなさい」という問題に対しても「和訳することを優先目的として英文を読んではならない」んです。これは非常に重要なポイントです。
「和訳できる」ということは「英文が理解できている」からこそですね。英文が理解できていないまま和訳だけできるということはありえないんです。つまり英文を最初に読むときは「和訳しよう」として読むのではなく、英語で表現された内容そのものをまず理解することを目的とします。英語を英語として理解できたあと、頭のチャンネルを英語から日本語に切り替えて、「同じ内容を別言語でアウトプットしなおす」わけです。
今回の英文全体で非常に大切なのは「or」かも知れません。
Do you have a pen or pencil?
こんなシンプルな英文でも、読み方によって意味が違ってきます。
1、ペンか鉛筆のどちからを持ってませんか?どちらでもいいのですが。
この意味を伝えようとするとき話者は「a pen or pencil」を1つのかたまりのように発音します。最初から「ペンまた鉛筆のどちらか(どちらでもいい)」を求めています。
2、ペンを持ってませんか?できればペンが欲しいのですが、「もしないとしたら」鉛筆でもまあ構いません。
こちらの意味の場合、「Do you have a pen?」で、もっとはっきりしたポーズが置かれます。「Do you have a pen? --- or pencil.」のような感じで読まれます。欲しいのは「ペン」なんです。でも、「それがないのならしょうがないから」という気持ちで「or」以下が続きます。
今回の問題文の場合、1よりは2に近い使われ方をしているといえます。
「社会的問題行動を起こす子供の親」というのは「まだ10代という精神的未熟な状態であることが多いのだ」。とまず述べており、「それが年齢的にはもう10代ではないとしても」と or 以下が続いているわけですね。
和訳する前に英文を「音読」されたでしょうか?
適切な和訳に確実にたどり着けるプロセスは次のようなものです。
1、英文そのものを理解する。
(1)英文を音読する(黙読であっても実際の音読をイメージしたもの)。
(2)音声化された英文を通じて意味を汲み取る。この時点ではまだ「和訳」を意識していません。英会話しているときと同じ状態であり、日本語のフィルタを通さずにダイレクトに英文を理解しています。
いわゆる長文読解などではここまでのステップしか踏みません。和訳などしません。
2、英文理解を踏まえて日本語で表現しなおす。
通常の会話などではこのステップは不要です。英語自体はすでに理解されており、それに対する自分の意見や返事もすでにできる状態にあります。しかし「和訳せよ」という要求に答えるために、今理解された英語の内容を日本語に直して表現しなおすわけです。ここから先はもう英語の能力ではなく「日本語表現能力」の領域になります。
試験での「英文和訳」などでは「英文理解の証拠」としての和訳が求められているのですから、
(1)英文に含まれている具体的情報を漏らさず盛り込む
(2)構文に沿った言い回しを心がける。ただし英語と日本語の言語習慣として大きく語順が異なる箇所については「日本人として自然に感じる」ことを優先した表現の工夫を行う。(<長いthat節を伴う場合など特にそうですね)
(3)そこに言葉として書かれていなくても日本語の場合、言葉に表したほうが自然な場合もあるし、英文には単語として現れていても日本語では言葉にしないほうが自然なこともある。
これが試験でなく、書籍の翻訳などになりますと「読者が翻訳結果を読んでいる印象を持たない」ことが非常に大切になってきます。まるで最初から日本人が日本語で書いた文章であるかのようにスムーズに読み勧められるように翻訳者は配慮し、最大の努力を払うのです。(極端な場合は「段落」まるごと入れ替えたりさえします。)
「和訳できる」ということは「英文が理解できている」からこそですね。英文が理解できていないまま和訳だけできるということはありえないんです。つまり英文を最初に読むときは「和訳しよう」として読むのではなく、英語で表現された内容そのものをまず理解することを目的とします。英語を英語として理解できたあと、頭のチャンネルを英語から日本語に切り替えて、「同じ内容を別言語でアウトプットしなおす」わけです。
今回の英文全体で非常に大切なのは「or」かも知れません。
Do you have a pen or pencil?
こんなシンプルな英文でも、読み方によって意味が違ってきます。
1、ペンか鉛筆のどちからを持ってませんか?どちらでもいいのですが。
この意味を伝えようとするとき話者は「a pen or pencil」を1つのかたまりのように発音します。最初から「ペンまた鉛筆のどちらか(どちらでもいい)」を求めています。
2、ペンを持ってませんか?できればペンが欲しいのですが、「もしないとしたら」鉛筆でもまあ構いません。
こちらの意味の場合、「Do you have a pen?」で、もっとはっきりしたポーズが置かれます。「Do you have a pen? --- or pencil.」のような感じで読まれます。欲しいのは「ペン」なんです。でも、「それがないのならしょうがないから」という気持ちで「or」以下が続きます。
今回の問題文の場合、1よりは2に近い使われ方をしているといえます。
「社会的問題行動を起こす子供の親」というのは「まだ10代という精神的未熟な状態であることが多いのだ」。とまず述べており、「それが年齢的にはもう10代ではないとしても」と or 以下が続いているわけですね。
和訳する前に英文を「音読」されたでしょうか?
適切な和訳に確実にたどり着けるプロセスは次のようなものです。
1、英文そのものを理解する。
(1)英文を音読する(黙読であっても実際の音読をイメージしたもの)。
(2)音声化された英文を通じて意味を汲み取る。この時点ではまだ「和訳」を意識していません。英会話しているときと同じ状態であり、日本語のフィルタを通さずにダイレクトに英文を理解しています。
いわゆる長文読解などではここまでのステップしか踏みません。和訳などしません。
2、英文理解を踏まえて日本語で表現しなおす。
通常の会話などではこのステップは不要です。英語自体はすでに理解されており、それに対する自分の意見や返事もすでにできる状態にあります。しかし「和訳せよ」という要求に答えるために、今理解された英語の内容を日本語に直して表現しなおすわけです。ここから先はもう英語の能力ではなく「日本語表現能力」の領域になります。
試験での「英文和訳」などでは「英文理解の証拠」としての和訳が求められているのですから、
(1)英文に含まれている具体的情報を漏らさず盛り込む
(2)構文に沿った言い回しを心がける。ただし英語と日本語の言語習慣として大きく語順が異なる箇所については「日本人として自然に感じる」ことを優先した表現の工夫を行う。(<長いthat節を伴う場合など特にそうですね)
(3)そこに言葉として書かれていなくても日本語の場合、言葉に表したほうが自然な場合もあるし、英文には単語として現れていても日本語では言葉にしないほうが自然なこともある。
これが試験でなく、書籍の翻訳などになりますと「読者が翻訳結果を読んでいる印象を持たない」ことが非常に大切になってきます。まるで最初から日本人が日本語で書いた文章であるかのようにスムーズに読み勧められるように翻訳者は配慮し、最大の努力を払うのです。(極端な場合は「段落」まるごと入れ替えたりさえします。)
こんばんは。お久しぶりです。自分でもあんまりしっくりきてないんですが(なら書くなという手厳しい方もいらっしゃるコミュだとは承知してますが…)、ちょっと横から失礼します。
答えの訳は前から訳し下しているので、to be teenagersまでthat以下をかけているかは必ずしも断言できない気もしますが(訳は少なくとも相当曖昧ですが)、やはり、この英文のthat以下はteenagersまではかかってないと思います。私がすぐに浮かんだ理由は、先行詞をつなげて考えたとき、psychological problems of their own contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parentingという文は違和感がありませんが、teenagers contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parentingはこの文脈ではどうも違和感があるように思われるからです。problemsとteenagersではカテゴリーが著しく違うからですね。言えるとしたら、おそらく「未成年であること(teenage性)」とかであって、teenagerだとはちょっと思えない気がしました。つまり、to be teenager(teenagerであること)を一語で表す名詞だったら、先行詞の可能性はあると思いますが(たとえば、immaturityみたいな名詞とかですかね)、そうではないので、ここではかかってこないのではないかと。
答えの訳は前から訳し下しているので、to be teenagersまでthat以下をかけているかは必ずしも断言できない気もしますが(訳は少なくとも相当曖昧ですが)、やはり、この英文のthat以下はteenagersまではかかってないと思います。私がすぐに浮かんだ理由は、先行詞をつなげて考えたとき、psychological problems of their own contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parentingという文は違和感がありませんが、teenagers contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parentingはこの文脈ではどうも違和感があるように思われるからです。problemsとteenagersではカテゴリーが著しく違うからですね。言えるとしたら、おそらく「未成年であること(teenage性)」とかであって、teenagerだとはちょっと思えない気がしました。つまり、to be teenager(teenagerであること)を一語で表す名詞だったら、先行詞の可能性はあると思いますが(たとえば、immaturityみたいな名詞とかですかね)、そうではないので、ここではかかってこないのではないかと。
>9 つるももさん
どのあたりにひっかかりがあるのか、もう少し説明していただけますでしょうか?
ちょっと不思議に感じたのは
><答えの訳>(that以下が十代にもかかっている)
と書かれているところです。最初の質問文の中にある「答えの訳」は:
またこのような子の親は、年齢がまだ10代だったり、自分達自身が心理的な問題をかかえていたりして、子育てが効果的に行えなかったり、厳しい、あるいは一貫性のない子育てになってしまいがちである。
となっていますが、この訳で「that以下が十代にもかかっている」と読めているのでしょうか?
もしかすると、どこかほんの一箇所勘違いされているだけなのかも知れない気がします。
疑問に感じていらっしゃるポイントをまず理解させていただければと思います。
どのあたりにひっかかりがあるのか、もう少し説明していただけますでしょうか?
ちょっと不思議に感じたのは
><答えの訳>(that以下が十代にもかかっている)
と書かれているところです。最初の質問文の中にある「答えの訳」は:
またこのような子の親は、年齢がまだ10代だったり、自分達自身が心理的な問題をかかえていたりして、子育てが効果的に行えなかったり、厳しい、あるいは一貫性のない子育てになってしまいがちである。
となっていますが、この訳で「that以下が十代にもかかっている」と読めているのでしょうか?
もしかすると、どこかほんの一箇所勘違いされているだけなのかも知れない気がします。
疑問に感じていらっしゃるポイントをまず理解させていただければと思います。
らうんどさん
どうも私の疑問は、文法の問題以前のようです。この場での議論にはそぐわないのかもしれませんが、いったん発言してしまった以上、もう少し説明します。(お分かりいただけるか、自信がありません。)
そうです。最初にその答えの訳を読んだときに、「that以下が十代にもかかっている」と思いました。だからこそ、shootingさんの疑問があるのだと理解しました。
でも、きょろさんのコメントを拝見して、この訳の解釈も一通りではないことが今はわかりました。
和訳はさておき、なぜ私がthat以下がto be teenagersにもかかってくるということにこだわっているかというと、そうでないと、この文が論理的にすっきりしないからです。
<to be teenagers>と<to have psychological problems of their own that 以下 >がorでつながれるような等価のものとは考えられないのです。
teenagersはimmaturityまでは、含意しているかもしれませんが、それだけでは、反社会的行動をとる子供達の親としての問題性まで説明できていません。(未成熟な親のどこが悪いのさ、ということです。)
なぜ、<to have psychological problems of their own>の方だけ、that以下が説明されるのでしょうか。
この文で筆者は、<ineffective, harsh, or inconsistent parenting>こそがthese childrenの問題を引き起こすと主張していると、私は理解しました。
これが私の勘違いなのでしょうね。文法的にそうは読めないということで。
お付き合いいただきありがとうございました。
どうも私の疑問は、文法の問題以前のようです。この場での議論にはそぐわないのかもしれませんが、いったん発言してしまった以上、もう少し説明します。(お分かりいただけるか、自信がありません。)
そうです。最初にその答えの訳を読んだときに、「that以下が十代にもかかっている」と思いました。だからこそ、shootingさんの疑問があるのだと理解しました。
でも、きょろさんのコメントを拝見して、この訳の解釈も一通りではないことが今はわかりました。
和訳はさておき、なぜ私がthat以下がto be teenagersにもかかってくるということにこだわっているかというと、そうでないと、この文が論理的にすっきりしないからです。
<to be teenagers>と<to have psychological problems of their own that 以下 >がorでつながれるような等価のものとは考えられないのです。
teenagersはimmaturityまでは、含意しているかもしれませんが、それだけでは、反社会的行動をとる子供達の親としての問題性まで説明できていません。(未成熟な親のどこが悪いのさ、ということです。)
なぜ、<to have psychological problems of their own>の方だけ、that以下が説明されるのでしょうか。
この文で筆者は、<ineffective, harsh, or inconsistent parenting>こそがthese childrenの問題を引き起こすと主張していると、私は理解しました。
これが私の勘違いなのでしょうね。文法的にそうは読めないということで。
お付き合いいただきありがとうございました。
>つるももさん
どんな英文でも(英文に限りませんが)、語順に従って意味が伝達されていくという原則はご理解されていることと思います。
今回の英文では
(In turn, ) the parents of these children are more likely to be teenagers
ここまでで実は一旦話が完結しているんです。
すなわち「反社会的行動を取る子供の親というのは、往々にしてまだ(自分自身が精神的に未熟で子育てに向けての心の準備さえ整っていない)10代だったりするものだ。
ここまで読んで、読者は「ああ、まだ親自体が子供じゃ、責任ある子育ては無理だな」と感じます。でも、問題行動を取る子の親が常に10代というわけでもないでしょう。
そこで「or」以下により、「実際の年齢が10代ではなく、すでに成人しているとしたら」と、あとの部分が続きます。
前半では「まだ10代」という年齢だけで「親としての資質が十分に成熟していない」ことを読者は理解しますが、実際の年齢が立派な成人をすぎており、普通ならちゃんとした子育てができてもおかしくない」場合もあることに話が展開します。
or to have [ psychological problems of their own] <that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.>
この「or」は「まだ10代でないとすると」の意味。つまり「年齢的には成人に達しており、通常なら立派に子育てができてもおかしくない年齢だとしても」と読むことができます。
そんな年齢であっても、「自分自身が精神的・情緒的な問題を抱えている」、その問題は「上手に子育てできない、育て方が粗雑だ、教育方針に一貫性がない」ことの要因です。
「that以下」が or のあとの「psychological problems」だけを修飾しているといえるのは、先に述べましたとおり、orの直前で一旦文は完結しているからです。
また論理的な観点から見ても「psychological problems」は「子育てのまずさ」につながりますが、前半の「teenagers」は「10代の人たち」という意味であり、
teenagers < that contribute to ineffective,... parenting>
という関係は妙です。これが「まだ10代であるという精神的未熟さ」を先行詞としているのなら論理的つじつまはあいます。しかし「teenager」という名詞それ自体はあくまでも「まだ10代の人」という意味なので、それをthat以下が修飾するというのはしっくりきません。
どんな英文でも(英文に限りませんが)、語順に従って意味が伝達されていくという原則はご理解されていることと思います。
今回の英文では
(In turn, ) the parents of these children are more likely to be teenagers
ここまでで実は一旦話が完結しているんです。
すなわち「反社会的行動を取る子供の親というのは、往々にしてまだ(自分自身が精神的に未熟で子育てに向けての心の準備さえ整っていない)10代だったりするものだ。
ここまで読んで、読者は「ああ、まだ親自体が子供じゃ、責任ある子育ては無理だな」と感じます。でも、問題行動を取る子の親が常に10代というわけでもないでしょう。
そこで「or」以下により、「実際の年齢が10代ではなく、すでに成人しているとしたら」と、あとの部分が続きます。
前半では「まだ10代」という年齢だけで「親としての資質が十分に成熟していない」ことを読者は理解しますが、実際の年齢が立派な成人をすぎており、普通ならちゃんとした子育てができてもおかしくない」場合もあることに話が展開します。
or to have [ psychological problems of their own] <that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.>
この「or」は「まだ10代でないとすると」の意味。つまり「年齢的には成人に達しており、通常なら立派に子育てができてもおかしくない年齢だとしても」と読むことができます。
そんな年齢であっても、「自分自身が精神的・情緒的な問題を抱えている」、その問題は「上手に子育てできない、育て方が粗雑だ、教育方針に一貫性がない」ことの要因です。
「that以下」が or のあとの「psychological problems」だけを修飾しているといえるのは、先に述べましたとおり、orの直前で一旦文は完結しているからです。
また論理的な観点から見ても「psychological problems」は「子育てのまずさ」につながりますが、前半の「teenagers」は「10代の人たち」という意味であり、
teenagers < that contribute to ineffective,... parenting>
という関係は妙です。これが「まだ10代であるという精神的未熟さ」を先行詞としているのなら論理的つじつまはあいます。しかし「teenager」という名詞それ自体はあくまでも「まだ10代の人」という意味なので、それをthat以下が修飾するというのはしっくりきません。
らうんどさん
疑問があります。
1 なぜ、orでいったん文が完結しているといえるのでしょうか。
2 読み手は、<十代である親>がそれだけで親としては問題だと推測するならば、<心理的に問題を抱えている親>も同程度にうまく子育てができないだろうと、そこまでは推測するのではないでしょうか。そこに、なぜ、後者だけthat以下の説明がつくのかという私の疑問が生じているのです。
that以下は、心理的に問題を抱えている親に特有な子育ての問題性ではないと思います。
3 that以下がteeagersを修飾するのはしっくりしないというのは、先にきょろさんもおっしゃっていたことですが、私は、<to be teenagers>全体を修飾していると思います。(文法的にはだめですか?)
{<十代であること>or<問題を抱えていること>}全体をthatで受けることは、文法的に不可ですか。
自分でも、思い込みがあるのかなあと思うのですが、今のところ納得がいってなくて。
すみません。
疑問があります。
1 なぜ、orでいったん文が完結しているといえるのでしょうか。
2 読み手は、<十代である親>がそれだけで親としては問題だと推測するならば、<心理的に問題を抱えている親>も同程度にうまく子育てができないだろうと、そこまでは推測するのではないでしょうか。そこに、なぜ、後者だけthat以下の説明がつくのかという私の疑問が生じているのです。
that以下は、心理的に問題を抱えている親に特有な子育ての問題性ではないと思います。
3 that以下がteeagersを修飾するのはしっくりしないというのは、先にきょろさんもおっしゃっていたことですが、私は、<to be teenagers>全体を修飾していると思います。(文法的にはだめですか?)
{<十代であること>or<問題を抱えていること>}全体をthatで受けることは、文法的に不可ですか。
自分でも、思い込みがあるのかなあと思うのですが、今のところ納得がいってなくて。
すみません。
1 なぜ、orでいったん文が完結しているといえるのでしょうか。
or が等位接続詞として「A、そうでないとしたら B」の意味を表しているからです。
また or のあとには言葉の繰り返しとして以下の部分が省略されています。
A or B は、「Aが先でなければならず」、「AかBのどちらか」という意味ではないのです。
the parents of these children are more likely to be teenagers
or
(the parents are more likely ) to have psychological problems of their own that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.
2 読み手は、<十代である親>がそれだけで親としては問題だと推測するならば、<心理的に問題を抱えている親>も同程度にうまく子育てができないだろうと、そこまでは推測するのではないでしょうか。そこに、なぜ、後者だけthat以下の説明がつくのかという私の疑問が生じているのです。
that以下は、心理的に問題を抱えている親に特有な子育ての問題性ではないと思います。
「まだ10代である」ということは、それだけで「未成熟さ」を象徴します。
「or」のあとは「もう10代ではない」ということをふまえているからこそ、「心理的に問題を抱えている」という内容があるわけです。
(論理展開)
1、子供が反社会的>親が未熟
2、ということは親自体がまだ子供=未成年
3、未成年でないとしても、精神的問題を抱えているため、満足な子育てができない
3 that以下がteeagersを修飾するのはしっくりしないというのは、先にきょろさんもおっしゃっていたことですが、私は、<to be teenagers>全体を修飾していると思います。(文法的にはだめですか?)
{<十代であること>or<問題を抱えていること>}全体をthatで受けることは、文法的に不可ですか。
はい、それは不可です。前の内容を受ける場合は、次のように whichが使われます。
(×)He is still a teenager that contributes to ineffective parenting.
(○)He is still a teenager, which contributes to ineffective parenting.
繰り返しになりますが、語順に沿って自然に読み進めることでおのずからこのような解釈につながると思います。後から訳し上げるようなことはしません。
or が等位接続詞として「A、そうでないとしたら B」の意味を表しているからです。
また or のあとには言葉の繰り返しとして以下の部分が省略されています。
A or B は、「Aが先でなければならず」、「AかBのどちらか」という意味ではないのです。
the parents of these children are more likely to be teenagers
or
(the parents are more likely ) to have psychological problems of their own that contribute to ineffective, harsh, or inconsistent parenting.
2 読み手は、<十代である親>がそれだけで親としては問題だと推測するならば、<心理的に問題を抱えている親>も同程度にうまく子育てができないだろうと、そこまでは推測するのではないでしょうか。そこに、なぜ、後者だけthat以下の説明がつくのかという私の疑問が生じているのです。
that以下は、心理的に問題を抱えている親に特有な子育ての問題性ではないと思います。
「まだ10代である」ということは、それだけで「未成熟さ」を象徴します。
「or」のあとは「もう10代ではない」ということをふまえているからこそ、「心理的に問題を抱えている」という内容があるわけです。
(論理展開)
1、子供が反社会的>親が未熟
2、ということは親自体がまだ子供=未成年
3、未成年でないとしても、精神的問題を抱えているため、満足な子育てができない
3 that以下がteeagersを修飾するのはしっくりしないというのは、先にきょろさんもおっしゃっていたことですが、私は、<to be teenagers>全体を修飾していると思います。(文法的にはだめですか?)
{<十代であること>or<問題を抱えていること>}全体をthatで受けることは、文法的に不可ですか。
はい、それは不可です。前の内容を受ける場合は、次のように whichが使われます。
(×)He is still a teenager that contributes to ineffective parenting.
(○)He is still a teenager, which contributes to ineffective parenting.
繰り返しになりますが、語順に沿って自然に読み進めることでおのずからこのような解釈につながると思います。後から訳し上げるようなことはしません。
お邪魔してすみません。どこで質問しようか考えていたのですが、いつも読まして頂いているここが、レベルが高い方が集まっていて、望ましい答えをして頂けそうなので、ここにお邪魔させて下さい。
2つあります。
?犬がthe grocery store で暴れた話の一番最後での締めの英文です。
You could tell that all he wanted to do was get face to face with the
manager and thank him for the good time he was having in the produce
department, but somehow he ended up pushing the manager over.
ここにいる方相手にごちゃごちゃ書きません。模範解答では、tellの目的節の
thatがdepartment,で終わっていて、「しかし、どういうわけかその犬は結局店長を押し倒してしまったのです。」となっているのですが、この部分もthat節に入れて、「・・・押し倒してしまった、ということがお分かり頂けると思います。」というように訳せる可能性はないのでしょうか。
?健康に関する長文の、日本には超人的な老人が多くが、西欧と比べても、実際 日本人は会社等でも日ごろ体を動かす機会を自らつくり、体を動かす習慣があ るようだ、という流れの、あるパラグラフの1文目です。
This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising
people in Japan who are somoking and drinking their way to early
graves.
もちろん日本語に訳そうと思えばそれらしく「日本語として」意味の通る訳はつくれますが、正直、最後の "their way to early graves"の「英語として」の文法的な構造といいますか、役割が全くわかりません。どうか教えて下さい。
適当なそれらしい答えを出してくれるサイトはいくらでもあるのでしょうが、上記のような議論の出来る皆様の答えが聞きたいのです。どうか、よろしくおねがいします。
2つあります。
?犬がthe grocery store で暴れた話の一番最後での締めの英文です。
You could tell that all he wanted to do was get face to face with the
manager and thank him for the good time he was having in the produce
department, but somehow he ended up pushing the manager over.
ここにいる方相手にごちゃごちゃ書きません。模範解答では、tellの目的節の
thatがdepartment,で終わっていて、「しかし、どういうわけかその犬は結局店長を押し倒してしまったのです。」となっているのですが、この部分もthat節に入れて、「・・・押し倒してしまった、ということがお分かり頂けると思います。」というように訳せる可能性はないのでしょうか。
?健康に関する長文の、日本には超人的な老人が多くが、西欧と比べても、実際 日本人は会社等でも日ごろ体を動かす機会を自らつくり、体を動かす習慣があ るようだ、という流れの、あるパラグラフの1文目です。
This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising
people in Japan who are somoking and drinking their way to early
graves.
もちろん日本語に訳そうと思えばそれらしく「日本語として」意味の通る訳はつくれますが、正直、最後の "their way to early graves"の「英語として」の文法的な構造といいますか、役割が全くわかりません。どうか教えて下さい。
適当なそれらしい答えを出してくれるサイトはいくらでもあるのでしょうが、上記のような議論の出来る皆様の答えが聞きたいのです。どうか、よろしくおねがいします。
1、この部分もthat節に入れて、「・・・押し倒してしまった、ということがお分かり頂けると思います。」というように訳せる可能性はないのでしょうか。
その構造を持つ場合は、but that と接続詞 that が入ります。
I think that 節A and/but that 節B
のようにthinkの目的語となる名詞節を導く場合、節Aの前のthatは省略可能ですが、節Bの前のthatは省けません。それがあるかないかで、構造の違いを明確にしているからです。
2、This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising people in Japan who are smoking and drinking their way to early graves.
人により解釈が分かれるかも知れませんが、one's way を副詞的に理解してよいと思います。
way to early graves は「早死にすること」。直訳的には「早期の墓へと続く道」です。
ですから
who are smoking and drinking their way to early graves
喫煙や飲酒で早死にへと向かっている(人たち)
This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising people in Japan who are smoking and drinking their way to early graves.
>だからといって、ストレスに疲弊し、運動もせず、喫煙や飲酒で早死にへと向かっている何百人もの人たちが日本にもいるという事実を否定するものではない。
その構造を持つ場合は、but that と接続詞 that が入ります。
I think that 節A and/but that 節B
のようにthinkの目的語となる名詞節を導く場合、節Aの前のthatは省略可能ですが、節Bの前のthatは省けません。それがあるかないかで、構造の違いを明確にしているからです。
2、This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising people in Japan who are smoking and drinking their way to early graves.
人により解釈が分かれるかも知れませんが、one's way を副詞的に理解してよいと思います。
way to early graves は「早死にすること」。直訳的には「早期の墓へと続く道」です。
ですから
who are smoking and drinking their way to early graves
喫煙や飲酒で早死にへと向かっている(人たち)
This is not to say there aren't millions of stressed-out, nonexercising people in Japan who are smoking and drinking their way to early graves.
>だからといって、ストレスに疲弊し、運動もせず、喫煙や飲酒で早死にへと向かっている何百人もの人たちが日本にもいるという事実を否定するものではない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75487人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6448人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人