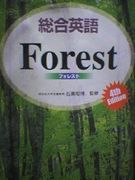英検4級テキストに次のような問題がありました。
A; Who is the tallest ( ) all the boys in the class?
B; Jim is.
1. of 2. at 3. in 4. with
答えはもちろんofですが、説明するのに、ofの後は複数名詞、、、とかではなく、
前置詞の根幹のイメージでもって、説明したいのです。
大西泰斗先生の本を読み、
of →(元の位置から)離れている、分離している
in →(立体的に)囲まれている感じ、内部感覚がある
というふうに認識すると、
この最上級の問題も同じように説明できるのかな?と思い始めました。
私が考えた説明は、
「クラスの男子一人一人(つまり全員)という対象から離れて、
一番背が高いのは誰?と聞いているから、
離れた感覚があるのはof。」
私が考えた説明で大丈夫でしょうか?
それとも、もっといい説明方法がありましたら、教えていただければと思います。
A; Who is the tallest ( ) all the boys in the class?
B; Jim is.
1. of 2. at 3. in 4. with
答えはもちろんofですが、説明するのに、ofの後は複数名詞、、、とかではなく、
前置詞の根幹のイメージでもって、説明したいのです。
大西泰斗先生の本を読み、
of →(元の位置から)離れている、分離している
in →(立体的に)囲まれている感じ、内部感覚がある
というふうに認識すると、
この最上級の問題も同じように説明できるのかな?と思い始めました。
私が考えた説明は、
「クラスの男子一人一人(つまり全員)という対象から離れて、
一番背が高いのは誰?と聞いているから、
離れた感覚があるのはof。」
私が考えた説明で大丈夫でしょうか?
それとも、もっといい説明方法がありましたら、教えていただければと思います。
|
|
|
|
コメント(10)
大西泰斗さんの考え方に沿った「語幹のイメージ」で説明をするのであれば、離れた感覚、というよりも「突出した感覚」というほうが、この場合的確なのではないでしょうか?
「離れた感覚」は間違いではないと思いますが、あくまで本質的な概念であり、それを4級学習者にそのまま説明して終わりにしてしまうには説明不足だと思います。その時々の文脈に合わせた、抽象のはしごを乗り降りするような、具体性のある説明も必要になってくると思います。
日本人にとって"of"は日常的に、誤解も含めて、「何かに所属する、グループ化されたもののひとつ、一部」という感覚があると思います。そういう感覚と「離れた感覚」という説明にはギャップが大きすぎるような気がします。なので、その間を埋めるような具体的な説明をしつつ、最終的に「本質的な語義は『離れた感覚』なんだ」と説明するべきだと思います。それが正しい理解になっているのであれば、ですが(つまり、大西さんの意図する「離れた感覚」と、Oti☆☆さんと私の理解する「離れた感覚」はそれぞれ違う可能性がある、ということです。言葉は言葉でしかありません、大西さんの解説、言葉を全ての状況においてそのまま使うのは不適切だと思います)。
think about ... , consider about ... ,という言葉も「〜について考える」という和訳で日本人にも理解は苦しくないですが、3、4級学習者にとってはthink of ..., consider of ..., も同様の訳になることはなじみのないものだと思います。"of"の一般的な理解と一致しないからです。
このギャップも大西泰斗さんの解釈に沿うならば、「距離感を感じるような(離れた)対象について『考えが及ぶ、考慮する』感覚」という説明がされるべきだと思います。
周知のように、ofは前置詞の中でも非常に多義的な感覚を持つ言葉です。日本人の一般的な理解もofのひとつです。大西泰斗さんの解説は本質的なイメージで、第一義的な語幹だと思われます。他の前置詞についての書籍では、さらに多くの派生した語義を解説したものがあります。つまり、本質的な第一義を元に解釈が派生し、特質性を帯びた「多義的な感覚、そして訳が発生している」という説明をすべきだと思うのです。
Oti☆☆さんの例の"of"は「“所属”のof」です(英英辞書longmanにはこの解説が先頭にあります)。「所属の中で突出している、pick up, あるいはseperateできる存在」ということではないでしょうか。
そういった「抽象のはしご」を乗り降りする解説が必要なんだと思います。ただ、Oti☆☆さんの教えている3、4級学習者の多くはおそらく小・中学生だと思います。その彼らに「本質と特質、抽象と具体、外延と内包」といった言葉を用いずに、それらを説明する必要があるのでしょうね。
「離れた感覚」は間違いではないと思いますが、あくまで本質的な概念であり、それを4級学習者にそのまま説明して終わりにしてしまうには説明不足だと思います。その時々の文脈に合わせた、抽象のはしごを乗り降りするような、具体性のある説明も必要になってくると思います。
日本人にとって"of"は日常的に、誤解も含めて、「何かに所属する、グループ化されたもののひとつ、一部」という感覚があると思います。そういう感覚と「離れた感覚」という説明にはギャップが大きすぎるような気がします。なので、その間を埋めるような具体的な説明をしつつ、最終的に「本質的な語義は『離れた感覚』なんだ」と説明するべきだと思います。それが正しい理解になっているのであれば、ですが(つまり、大西さんの意図する「離れた感覚」と、Oti☆☆さんと私の理解する「離れた感覚」はそれぞれ違う可能性がある、ということです。言葉は言葉でしかありません、大西さんの解説、言葉を全ての状況においてそのまま使うのは不適切だと思います)。
think about ... , consider about ... ,という言葉も「〜について考える」という和訳で日本人にも理解は苦しくないですが、3、4級学習者にとってはthink of ..., consider of ..., も同様の訳になることはなじみのないものだと思います。"of"の一般的な理解と一致しないからです。
このギャップも大西泰斗さんの解釈に沿うならば、「距離感を感じるような(離れた)対象について『考えが及ぶ、考慮する』感覚」という説明がされるべきだと思います。
周知のように、ofは前置詞の中でも非常に多義的な感覚を持つ言葉です。日本人の一般的な理解もofのひとつです。大西泰斗さんの解説は本質的なイメージで、第一義的な語幹だと思われます。他の前置詞についての書籍では、さらに多くの派生した語義を解説したものがあります。つまり、本質的な第一義を元に解釈が派生し、特質性を帯びた「多義的な感覚、そして訳が発生している」という説明をすべきだと思うのです。
Oti☆☆さんの例の"of"は「“所属”のof」です(英英辞書longmanにはこの解説が先頭にあります)。「所属の中で突出している、pick up, あるいはseperateできる存在」ということではないでしょうか。
そういった「抽象のはしご」を乗り降りする解説が必要なんだと思います。ただ、Oti☆☆さんの教えている3、4級学習者の多くはおそらく小・中学生だと思います。その彼らに「本質と特質、抽象と具体、外延と内包」といった言葉を用いずに、それらを説明する必要があるのでしょうね。
たしかに和訳すると“クラスの男子全員「の中で」”となるので、
生徒からしたら of ではなくて in に食いつきたくなりますよね笑
それを単なる機械的な説明・板書ではなく、
<前置詞>のイメージから感覚に訴えるような説明ができたら素晴らしいと
私も以前から思っていましたので、
Oti☆☆さんの試みはすばらしいと思います

Oti☆☆さんは in のご説明の中で<内部感覚>という表現を使われていますが、
もし<内部感覚>ということでいくと、
今回は“クラスの男子全員「の中で」”となりますから
まさに<内部感覚>(つまりinを使うこと)になるのかなと。
でも答えは in ではなくて of ですから、
この説明でいくと、おそらく多くの高校生はあまりしっくりこないと思いますし、
逆に混乱する可能性もあると思います。
of という前置詞については、上でYojiさんがおっしゃっている通りだと思うのですが、
<全体>に対してその<部分・一部>を表すというのが of の中核的な意味ですよね。
私の手元にある大学受験用の問題集の説明には
“後ろが<構成要素>を表す<複数名詞>の場合はofを用い、
後ろが<範囲>を表す<単数名詞>の場合はinを用いる”と書かれています。
私の意見としては、of と in を分ける1つの意味的境界線として
<空間>の存在があると思うのですが、
in は田中茂範先生の著書の定義では「<空間>の中に」というのがコア・イメージですから、
Who is the fastest runner in this class?
という文においては、クラスという単語から<空間>がイメージされます。
しかし、Who is the fastest runner of all the boys? という文では、
<空間>はイメージされませんよね。
このことからすると、Oti☆☆さんが機械的だと思っておられる“of の後には<複数名詞>”
という説明は、実はちゃんとイメージを反映しているのではと思います。
生徒からしたら of ではなくて in に食いつきたくなりますよね笑
それを単なる機械的な説明・板書ではなく、
<前置詞>のイメージから感覚に訴えるような説明ができたら素晴らしいと
私も以前から思っていましたので、
Oti☆☆さんの試みはすばらしいと思います
Oti☆☆さんは in のご説明の中で<内部感覚>という表現を使われていますが、
もし<内部感覚>ということでいくと、
今回は“クラスの男子全員「の中で」”となりますから
まさに<内部感覚>(つまりinを使うこと)になるのかなと。
でも答えは in ではなくて of ですから、
この説明でいくと、おそらく多くの高校生はあまりしっくりこないと思いますし、
逆に混乱する可能性もあると思います。
of という前置詞については、上でYojiさんがおっしゃっている通りだと思うのですが、
<全体>に対してその<部分・一部>を表すというのが of の中核的な意味ですよね。
私の手元にある大学受験用の問題集の説明には
“後ろが<構成要素>を表す<複数名詞>の場合はofを用い、
後ろが<範囲>を表す<単数名詞>の場合はinを用いる”と書かれています。
私の意見としては、of と in を分ける1つの意味的境界線として
<空間>の存在があると思うのですが、
in は田中茂範先生の著書の定義では「<空間>の中に」というのがコア・イメージですから、
Who is the fastest runner in this class?
という文においては、クラスという単語から<空間>がイメージされます。
しかし、Who is the fastest runner of all the boys? という文では、
<空間>はイメージされませんよね。
このことからすると、Oti☆☆さんが機械的だと思っておられる“of の後には<複数名詞>”
という説明は、実はちゃんとイメージを反映しているのではと思います。
また、余談ですが、大西先生と同じ路線で英語にアプローチしている方に、
先ほど挙げた慶応義塾大学教授の田中茂範先生がいらっしゃって、
「話せる英単語ネットワーク 前置詞編」という本を出しているので、
機会がありましたら、ぜひ読んでみてください。
私は大西先生よりも田中茂範先生の方がより説得力があると思っていまして、
例えば大西アプローチでは to のコア・イメージは<方向>になっていますが、
田中アプローチでは to のコア・イメージは<〜と向き合って>という風に設定されています。
その方が I go to school at 8:30. という文において、
学校に到着するのが8:30なのか、
それとも家を出るのが8:30(よって学校に就くのは当然8:30よりも遅くなる)なのか
という部分をきっちり説明できる点が、私がこの方に興味を持った理由の1つです。
もしよろしければ、時間があるときに立ち読みでもしてみてください
先ほど挙げた慶応義塾大学教授の田中茂範先生がいらっしゃって、
「話せる英単語ネットワーク 前置詞編」という本を出しているので、
機会がありましたら、ぜひ読んでみてください。
私は大西先生よりも田中茂範先生の方がより説得力があると思っていまして、
例えば大西アプローチでは to のコア・イメージは<方向>になっていますが、
田中アプローチでは to のコア・イメージは<〜と向き合って>という風に設定されています。
その方が I go to school at 8:30. という文において、
学校に到着するのが8:30なのか、
それとも家を出るのが8:30(よって学校に就くのは当然8:30よりも遅くなる)なのか
という部分をきっちり説明できる点が、私がこの方に興味を持った理由の1つです。
もしよろしければ、時間があるときに立ち読みでもしてみてください
みなさん、たくさんコメント、ありがとうございます。
何度も読み返し、なるほど!と思いました。
>はいやーむさん
すみません。。私の書き方がわかりにくかったですよね。。
>たっつんさん
>「その時々の文脈に合わせた、抽象のはしごを乗り降りするような、具体性のある説明も必要になってくると思います。 」
この言葉にハッとしました。。
中1の子を教えていますが、抽象的な説明だと、余計に混乱させてしまいますよね。
この問題に限らず、抽象のはしごを乗り降りするような具体的な説明を
心がけて教えていきたいと思います。
>Yojiさん
絵を付けてくださってありがとうございます。
ofのイメージがよりわかりやすくなりました。
>碧。+さん
絵を描く、、、という説明、なるほど!と思いました。
>がちゃ(ぴん)☆さん
田中茂範先生の解釈のお話、ありがとうございました。
今度読んでみたいと思います。
I go to school at 8:30.のお話、数ヶ月前に生徒と
論議をかわしたことがありました。。
何度も読み返し、なるほど!と思いました。
>はいやーむさん
すみません。。私の書き方がわかりにくかったですよね。。
>たっつんさん
>「その時々の文脈に合わせた、抽象のはしごを乗り降りするような、具体性のある説明も必要になってくると思います。 」
この言葉にハッとしました。。
中1の子を教えていますが、抽象的な説明だと、余計に混乱させてしまいますよね。
この問題に限らず、抽象のはしごを乗り降りするような具体的な説明を
心がけて教えていきたいと思います。
>Yojiさん
絵を付けてくださってありがとうございます。
ofのイメージがよりわかりやすくなりました。
>碧。+さん
絵を描く、、、という説明、なるほど!と思いました。
>がちゃ(ぴん)☆さん
田中茂範先生の解釈のお話、ありがとうございました。
今度読んでみたいと思います。
I go to school at 8:30.のお話、数ヶ月前に生徒と
論議をかわしたことがありました。。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート