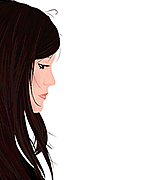僕がこの様な話を書く経緯はこちらに書いています↓
http://
まず、インド。
インドがイギリスと独立戦争を戦っていた昭和19年3月20日、自由インド政府のチャンドラ・ボースという人物がこう宣誓しました。
『インド国民軍はいまや攻撃を開始し、日本帝国陸軍の協力を得て、両群は肩を並べて共同の敵、アメリカ、イギリスおよびその連合国に対し、共同作戦を進めつつあり。
外国侵略軍をインドより放逐せざるを限り、インド民衆の自由なく、アジアの自由と安全はなく、またアメリカ・イギリスの帝国主義戦争の終息もなし。
ここに自由インド政府は、インドの完全開放の日まで、日本の友情と共に戦い抜くべき厳粛なる決意を布告す』
インド国民軍について日本とのエピソードがあります。
共同作戦中の日本人工作員が敵陣へ近づくと英印軍に所属するインド人たちが射撃してきたため、インド国民軍のインド人工作員が日本人工作員の前に立ちはだかり大声で叫びました。
『日本人を殺すな。われわれインド人の独立のために戦っているんだぞ』
いったん射撃は止みましたが、また射撃してきます。
すると今度は日本人工作員が立ち上げって両手を広げヒンズー語で叫びます。
『同胞を殺すな。撃つならまず俺を撃て。俺はお前たちに話しに行くところだ武器は持っていない』
そうすると今度はまたインド工作員が再び日本人工作員の前に両手を広げて立ちます。
この繰り返しにとうとう相手は根負けし、英インド軍の一個大隊すべてが寝返ってしまいました。
続いてインドネシア。
坂井三郎という日本空軍のパイロットがいました。
大戦中、坂井は撃墜王と他国の空軍から呼ばれ日本でも空軍のエースとして尊敬されていました。
昭和17年の初め、オランダ領東インド(今のインドネシア共和国)ジャワ島の敵基地への侵攻途中で発見した敵偵察機を攻撃するために味方編隊から離れた坂井はその偵察機を撃墜した後しばらく飛行していると、侵攻する日本軍から逃れる軍人・民間人を満載したオランダ軍の大型輸送機に遭遇しました。
当時は当該エリアを飛行する敵国機(飛行機への攻撃は軍民・武装の有無は通常問わない)は撃墜する命令が出ていました。
つまり相手の国の飛行機であればどんなものでも撃ち落として良いという事です。
相手は動きの遅い輸送機だった為に撃墜は簡単な相手でしたが、坂井はこの輸送機に敵の重要人物が乗っているのではないかと疑い、生け捕りにする事を考えました。
味方基地へ誘導するために輸送機の横に並んだ時、坂井は輸送機の窓に震え慄く母娘と思われる乗客たちが見えることに気づきました。
その様子を見てさすがに闘志が萎えた坂井は、輸送機を見逃す事に決めました。
坂井は敵機に手を振ってその場を離れ、帰投後上官には
『雲中に見失う』と報告しました。
彼は後に、青山学院中等部時代に英語を教え親切にしてくれたアメリカ人のマーチン夫人と母親が似ており、殺すべきではないと思った、と語りました。
攻撃せず、逃亡を許した軍に背く行為は重罪であり、また軍律違反はいかなる理由にせよ恥ずべきことだと感じていた坂井は戦後の著作にもこの件を記述しませんでしたが、年を重ねるに従って考え方が変わり、終戦から50年近く経った頃の講演会で初めてこのことを明かしました。
坂井はインタビューで
『戦争とは軍人同士が戦うものであり、民間人を攻撃するものではないと信じていた』と答えています。
なおこれと同じ頃、当時輸送機内から坂井の戦闘機を見ていたオランダ人の元従軍看護婦が
『あのパイロットに会って感謝を伝えたい』
と赤十字等の団体を通じて照会したところ、パイロットが有名な坂井三郎であることを知り、非常に驚いたそうです。
2人は再会し、互いの無事を喜び合いました。
続いて昭和天皇
太平洋戦争まっただ中のころのお話です。
昭和18年、アッツ島の守備に就いていた山崎保代部隊長から日本の大本営宛てに激しい戦闘で玉砕を目前にした悲壮な電報が届きました。電文の内容は次のようなものでした。
『自分は、アッツ島守備の大命を拝し守備にあたってまいりましたが、米国海兵隊三個師団が上陸し任務をまっとうできなくなってしまいました。
まことに申し訳ありません。
明朝を期して全軍で突入しますが、同時に一切の通信機を破壊し、暗号書は焼却します。
皇国の無窮をお祈りしております』
昭和天皇は、この報告を静かに聞きそしていくつかの質問をした後、最後に
『アッツ島の山崎部隊長に電報を打て』
と命ぜられました。
『アッツ島部隊は最後まで非常によくやった。そう私が言っていた、と打て』
しかし、その時点ではすでに山崎部隊は玉砕した後で、もうこの世にはいないのです。
また、たとえ電報を打ったとしても、通信機も壊されていますから絶対に届くはずがありません。
昭和天皇の言葉をいぶかった報告者は、おそれながらもそのように申し上げました。
すると昭和天皇は、こう言いました。
『届かなくてもいいから、電報を打ってやれ』
昭和天皇の優しさに触れた報告者ははっとしたその瞬間に涙があふれ出て止まらず、昭和天皇の言葉を手帳に書き写すこともできなくなったそうです。
更に短いですけど昭和天皇のエピソード。
旅行先で庭園を見ている時に案内役の当時の安倍晋太郎農相と。
『ここから先は雑草です』
『雑草という草はない、すべての草は人と同様に生きていて、名前がある』
続いて沖縄での日本人兵士2人の行動。
すでに米軍が沖縄に侵攻していた昭和20年5月のある日、二人の童顔の陸軍将校が佐賀県の鳥栖小学校を突然訪ねてきました。
上野歌子先生が応対すると、二人はこう言いました。
『自分たちは上野音楽学校(現・芸術大)ピアノ科出身の学徒出身兵です。
明日、特攻出撃することになりましたが、学校を出て今日まで演奏会でピアノを弾く機会がありませんでした。
もちろん祖国のために命を捧げる事は本懐ですが、今生の思い出に思いきりピアノを弾いて二人だけの演奏会をやりたいのです。
今日は目達原の基地から、あちらこちらとピアノを求め歩いて、やっとこの小学校にたどりつきましたが、どうぞお願いいたします』
上野先生の心には灼きつく熱いものがこみあげてきました。
『どうぞ兵隊さん、時間のある限り弾いて下さい。私もここで聴かせていただきます』
静かな放課後の音楽教室で、二人の少尉は、代わる代わるピアノに向ってベートーベンの『月光』などの曲を奏でていました。その一時間程の間に、どこから聞きつけたのか二十人程の学童達がいつの間にか集ってきて、一緒にピアノの演奏に耳を傾けていました。
やがて帰隊の時刻も迫ってきた時、上野先生は二人に向って言いました。
『有難うございました。こんな素晴らしいピアノを何年ぶりかで聴かせていただきました。この子供達もあなた方のお姿と一緒に永遠に今日のピアノ演奏を忘れることはないでしょう。
明日はご出発とのことですが、心からご武運を祈らせていただきます。
お別れにこの子供達と『海行かば』を合唱させていただきます』
教室一杯に静かに『海行かば』が流れました。
送られる二人の少尉もいつしか声をあわせて一緒に合唱していました。
帰り際、二人の少尉は
『この戦争はいつかは終わります。しかし今自分達が死ななければ、この国を君たちに残すことはできません』
といって、子供たちの頭をなで、満足の微笑みをたたえながら去って行きました。
翌日の午前、鳥栖小学校の上空に一機の飛行機が現われ、二度、三度と翼を大きく振りながら南の空へ飛び去っていったといいます。
この時のピアノは今も、鳥栖小学校に保存されているそうです。
続いてパラオに関する有名なコピペ
遠い南の島に、日本の歌を歌う老人がいた。
『あそこでみんな死んでいったんだ・・・』
沖に浮かぶ島を指差しながら、老人はつぶやいた。太平洋戦争のとき、その島には日本軍が進駐し陣地が作られた。
老人は村の若者達と共にその作業に参加した。日本兵とは仲良くなって、日本の歌を一緒に歌ったりしたという。
やがて戦況は日本に不利となり、いつ米軍が上陸してもおかしくない状況になった。
仲間達と話し合った彼は代表数人と共に日本の守備隊長のもとを訪れた。自分達も一緒に戦わせて欲しい、と。
それを聞くなり隊長は激高し叫んだという
『帝国軍人が、貴様ら土人と一緒に戦えるか!』
日本人は仲間だと思っていたのに…みせかけだったのか裏切られた想いで、みな悔し涙を流した…
船に乗って島を去る日 日本兵は誰一人見送りに来ない。村の若者達は、悄然と船に乗り込んだ。
しかし船が島を離れた瞬間、日本兵全員が浜に走り出てきた。そして一緒に歌った日本の歌を歌いながら、手を振って彼らを見送った。
先頭には笑顔で手を振るあの隊長が。その瞬間、彼は悟ったという。
あの言葉は、自分達を救うためのものだったのだと・・・。
『この島を訪れる、もろもろの国の旅人たちよ。あなたが日本の国を通過することあらば伝えてほしい。
此の島を死んで守った日本軍守備隊の勇気と祖国を憶う、その心根を』
ちなみにパラオに存在するこの神社は、天照大神と戦死者一万余名の
『護国の英霊』
を御祭神とする神社である。
パラオ共和国大統領トミー・E・レメンゲサウ・ジュニアは、
敗戦から復興し様々な分野において世界を牽引する力になっている今日の日本を称え、また戦時中のパラオ統治に今でも感謝し、パラオは世界で最も親日感情が高い国と言った。
そして当時を知るパラオの長老たちは今でも日本をこう呼ぶという。
『内地』
更にパラオです。
前に書いたトピックでパラオは親日国で国旗は日の丸を参考に作られたと書きました。
今回はその国旗を選択する時のエピソードを書きます。。
パラオの人々は国旗の選択に相当な苦労をしました。応募者はパラオに属する各島の人々でありそれぞれの旗にそれぞれの島とそれぞれのパラオに対する思いがありました。
パラオは歴史と伝統の国です、なので選考委員は真剣でした。
選考にはかなりの期間をかけました。
しかし最終的にあの国旗に決まったのは簡単な理由でした。
『日本の旗に一番似ているから』でした、それだけで最大の人気が集まりました。
日の丸の部分を黄色にしたのは月を現わします。
周囲の青の部分は海を現わします。
月は太陽が出ないと輝くことができません。
つまり月は太陽によって支えられ、月としての生命を持ちます。
太陽とは日本のことです。
海に囲まれたパラオは日本という太陽の反射によって輝かねば生きられないという意味を込めた国旗です。
パラオの人々は戦争中に日の丸を掲げて強大な米軍と戦闘した日本軍兵士たちの勇敢さと純粋さに太陽の様な大きな魅力と尊敬を感じました。
一万に及ぶ日本人たちはパラオの人達に勇気と国を想う心があればアメリカよりも強くなれることを教えて死んだのです。
最後に…ウズベキスタンの話。
ウズベキスタン共和国の首都はタシケントです。
その中心部に国立ナボイ劇場という劇場があります。
レンガ造りの三階建てで観客席は1400人という巨大な建物でタシケントの代表的建造物として今でも威容を誇っています。
この劇場の正面には
『1945年から46年にかけて極東から強制移住させられた数百人の日本人がこの劇場の建設に参加し、その完成に貢献した』
とウズベク語、日本語、英語で表記されたプレートが設置されています。
ウズベキスタンでは第二次世界大戦後、ソ連によってシベリアにいた約2万5千人の日本人抑留者が移送され水力発電所や運河、道路などの建設に従事させられました。
中山恭子さんという元ウズベキスタン大使は在任中にいまも国民に電気を供給している水力発電所の建設を仕切った元現場監督に会いました。
この人物は、まじめに、そして懸命に汗を流していた日本人抑留者たちの思い出を涙ながらに語ったといいます。
捕虜の境遇にあっても勤勉に働く日本人抑留者は当時の地元民に敬意を表されました。
現地の人は日本人たちに『絶対に帰れるぞ!』と励ましながら黒パンを握らせてくれたそうです。
日本人抑留者が現地に残した遺産のシンボルが約500人の抑留者によって2年がかりで建設したナボイ劇場なのです。
レンガ製造から館内の装飾、彫刻まで抑留者が行った。
1966年にウズベキスタンを襲った大地震でタシケント市内の多くの建造物が倒壊した際も、この劇場はビクともせず
『日本人の建物は堅固だ』『日本人の建築技術は高い』という評価が定着しました。
そのためか親日感情が強い中央アジア諸国の中でもウズベキスタンの日本人への好感度は飛び抜けています。
1991年に旧ソ連から独立して新国家建設を進めるウズベキスタンはカリモフ大統領が就任演説の時に言った
『日本の明治維新や戦後復興をモデルとして「日本に見習え」』
を合言葉にしています。
劇場前のプレートの表記についてはカリモフ大統領が
『決して日本人捕虜と表記するな。日本とウズベキスタンは一度も戦争していない』
と厳命したそうです。
2万人の抑留者のうち、800人以上が現地で死亡し各地の墓地に埋葬されましたがその多くは荒れ放題となりました。
しかし元抑留者たちと地元の人たちが協力しあいウズベキスタンでは珍しい募金活動を行い更に目的を知ったウズベキスタン政府の協力も得て日本人墓地が整備されました。
また
『日本に 帰ってもう一度、花見がしたかった』
と言い残して亡くなった抑留者のために日本からサクラの苗木千三百本が送られました。
整備の発起人の一人、中山成彬衆院議員は
『両国友好の証しになってほしい』
と話しています。
過酷な環境の中で日本への帰国を夢見ながらも勤勉に働いてウズベキスタンと日本との友好の絆を残してくれた抑留者に感謝と追悼の意を捧げてこのトピックを終わります。
http://
まず、インド。
インドがイギリスと独立戦争を戦っていた昭和19年3月20日、自由インド政府のチャンドラ・ボースという人物がこう宣誓しました。
『インド国民軍はいまや攻撃を開始し、日本帝国陸軍の協力を得て、両群は肩を並べて共同の敵、アメリカ、イギリスおよびその連合国に対し、共同作戦を進めつつあり。
外国侵略軍をインドより放逐せざるを限り、インド民衆の自由なく、アジアの自由と安全はなく、またアメリカ・イギリスの帝国主義戦争の終息もなし。
ここに自由インド政府は、インドの完全開放の日まで、日本の友情と共に戦い抜くべき厳粛なる決意を布告す』
インド国民軍について日本とのエピソードがあります。
共同作戦中の日本人工作員が敵陣へ近づくと英印軍に所属するインド人たちが射撃してきたため、インド国民軍のインド人工作員が日本人工作員の前に立ちはだかり大声で叫びました。
『日本人を殺すな。われわれインド人の独立のために戦っているんだぞ』
いったん射撃は止みましたが、また射撃してきます。
すると今度は日本人工作員が立ち上げって両手を広げヒンズー語で叫びます。
『同胞を殺すな。撃つならまず俺を撃て。俺はお前たちに話しに行くところだ武器は持っていない』
そうすると今度はまたインド工作員が再び日本人工作員の前に両手を広げて立ちます。
この繰り返しにとうとう相手は根負けし、英インド軍の一個大隊すべてが寝返ってしまいました。
続いてインドネシア。
坂井三郎という日本空軍のパイロットがいました。
大戦中、坂井は撃墜王と他国の空軍から呼ばれ日本でも空軍のエースとして尊敬されていました。
昭和17年の初め、オランダ領東インド(今のインドネシア共和国)ジャワ島の敵基地への侵攻途中で発見した敵偵察機を攻撃するために味方編隊から離れた坂井はその偵察機を撃墜した後しばらく飛行していると、侵攻する日本軍から逃れる軍人・民間人を満載したオランダ軍の大型輸送機に遭遇しました。
当時は当該エリアを飛行する敵国機(飛行機への攻撃は軍民・武装の有無は通常問わない)は撃墜する命令が出ていました。
つまり相手の国の飛行機であればどんなものでも撃ち落として良いという事です。
相手は動きの遅い輸送機だった為に撃墜は簡単な相手でしたが、坂井はこの輸送機に敵の重要人物が乗っているのではないかと疑い、生け捕りにする事を考えました。
味方基地へ誘導するために輸送機の横に並んだ時、坂井は輸送機の窓に震え慄く母娘と思われる乗客たちが見えることに気づきました。
その様子を見てさすがに闘志が萎えた坂井は、輸送機を見逃す事に決めました。
坂井は敵機に手を振ってその場を離れ、帰投後上官には
『雲中に見失う』と報告しました。
彼は後に、青山学院中等部時代に英語を教え親切にしてくれたアメリカ人のマーチン夫人と母親が似ており、殺すべきではないと思った、と語りました。
攻撃せず、逃亡を許した軍に背く行為は重罪であり、また軍律違反はいかなる理由にせよ恥ずべきことだと感じていた坂井は戦後の著作にもこの件を記述しませんでしたが、年を重ねるに従って考え方が変わり、終戦から50年近く経った頃の講演会で初めてこのことを明かしました。
坂井はインタビューで
『戦争とは軍人同士が戦うものであり、民間人を攻撃するものではないと信じていた』と答えています。
なおこれと同じ頃、当時輸送機内から坂井の戦闘機を見ていたオランダ人の元従軍看護婦が
『あのパイロットに会って感謝を伝えたい』
と赤十字等の団体を通じて照会したところ、パイロットが有名な坂井三郎であることを知り、非常に驚いたそうです。
2人は再会し、互いの無事を喜び合いました。
続いて昭和天皇
太平洋戦争まっただ中のころのお話です。
昭和18年、アッツ島の守備に就いていた山崎保代部隊長から日本の大本営宛てに激しい戦闘で玉砕を目前にした悲壮な電報が届きました。電文の内容は次のようなものでした。
『自分は、アッツ島守備の大命を拝し守備にあたってまいりましたが、米国海兵隊三個師団が上陸し任務をまっとうできなくなってしまいました。
まことに申し訳ありません。
明朝を期して全軍で突入しますが、同時に一切の通信機を破壊し、暗号書は焼却します。
皇国の無窮をお祈りしております』
昭和天皇は、この報告を静かに聞きそしていくつかの質問をした後、最後に
『アッツ島の山崎部隊長に電報を打て』
と命ぜられました。
『アッツ島部隊は最後まで非常によくやった。そう私が言っていた、と打て』
しかし、その時点ではすでに山崎部隊は玉砕した後で、もうこの世にはいないのです。
また、たとえ電報を打ったとしても、通信機も壊されていますから絶対に届くはずがありません。
昭和天皇の言葉をいぶかった報告者は、おそれながらもそのように申し上げました。
すると昭和天皇は、こう言いました。
『届かなくてもいいから、電報を打ってやれ』
昭和天皇の優しさに触れた報告者ははっとしたその瞬間に涙があふれ出て止まらず、昭和天皇の言葉を手帳に書き写すこともできなくなったそうです。
更に短いですけど昭和天皇のエピソード。
旅行先で庭園を見ている時に案内役の当時の安倍晋太郎農相と。
『ここから先は雑草です』
『雑草という草はない、すべての草は人と同様に生きていて、名前がある』
続いて沖縄での日本人兵士2人の行動。
すでに米軍が沖縄に侵攻していた昭和20年5月のある日、二人の童顔の陸軍将校が佐賀県の鳥栖小学校を突然訪ねてきました。
上野歌子先生が応対すると、二人はこう言いました。
『自分たちは上野音楽学校(現・芸術大)ピアノ科出身の学徒出身兵です。
明日、特攻出撃することになりましたが、学校を出て今日まで演奏会でピアノを弾く機会がありませんでした。
もちろん祖国のために命を捧げる事は本懐ですが、今生の思い出に思いきりピアノを弾いて二人だけの演奏会をやりたいのです。
今日は目達原の基地から、あちらこちらとピアノを求め歩いて、やっとこの小学校にたどりつきましたが、どうぞお願いいたします』
上野先生の心には灼きつく熱いものがこみあげてきました。
『どうぞ兵隊さん、時間のある限り弾いて下さい。私もここで聴かせていただきます』
静かな放課後の音楽教室で、二人の少尉は、代わる代わるピアノに向ってベートーベンの『月光』などの曲を奏でていました。その一時間程の間に、どこから聞きつけたのか二十人程の学童達がいつの間にか集ってきて、一緒にピアノの演奏に耳を傾けていました。
やがて帰隊の時刻も迫ってきた時、上野先生は二人に向って言いました。
『有難うございました。こんな素晴らしいピアノを何年ぶりかで聴かせていただきました。この子供達もあなた方のお姿と一緒に永遠に今日のピアノ演奏を忘れることはないでしょう。
明日はご出発とのことですが、心からご武運を祈らせていただきます。
お別れにこの子供達と『海行かば』を合唱させていただきます』
教室一杯に静かに『海行かば』が流れました。
送られる二人の少尉もいつしか声をあわせて一緒に合唱していました。
帰り際、二人の少尉は
『この戦争はいつかは終わります。しかし今自分達が死ななければ、この国を君たちに残すことはできません』
といって、子供たちの頭をなで、満足の微笑みをたたえながら去って行きました。
翌日の午前、鳥栖小学校の上空に一機の飛行機が現われ、二度、三度と翼を大きく振りながら南の空へ飛び去っていったといいます。
この時のピアノは今も、鳥栖小学校に保存されているそうです。
続いてパラオに関する有名なコピペ
遠い南の島に、日本の歌を歌う老人がいた。
『あそこでみんな死んでいったんだ・・・』
沖に浮かぶ島を指差しながら、老人はつぶやいた。太平洋戦争のとき、その島には日本軍が進駐し陣地が作られた。
老人は村の若者達と共にその作業に参加した。日本兵とは仲良くなって、日本の歌を一緒に歌ったりしたという。
やがて戦況は日本に不利となり、いつ米軍が上陸してもおかしくない状況になった。
仲間達と話し合った彼は代表数人と共に日本の守備隊長のもとを訪れた。自分達も一緒に戦わせて欲しい、と。
それを聞くなり隊長は激高し叫んだという
『帝国軍人が、貴様ら土人と一緒に戦えるか!』
日本人は仲間だと思っていたのに…みせかけだったのか裏切られた想いで、みな悔し涙を流した…
船に乗って島を去る日 日本兵は誰一人見送りに来ない。村の若者達は、悄然と船に乗り込んだ。
しかし船が島を離れた瞬間、日本兵全員が浜に走り出てきた。そして一緒に歌った日本の歌を歌いながら、手を振って彼らを見送った。
先頭には笑顔で手を振るあの隊長が。その瞬間、彼は悟ったという。
あの言葉は、自分達を救うためのものだったのだと・・・。
『この島を訪れる、もろもろの国の旅人たちよ。あなたが日本の国を通過することあらば伝えてほしい。
此の島を死んで守った日本軍守備隊の勇気と祖国を憶う、その心根を』
ちなみにパラオに存在するこの神社は、天照大神と戦死者一万余名の
『護国の英霊』
を御祭神とする神社である。
パラオ共和国大統領トミー・E・レメンゲサウ・ジュニアは、
敗戦から復興し様々な分野において世界を牽引する力になっている今日の日本を称え、また戦時中のパラオ統治に今でも感謝し、パラオは世界で最も親日感情が高い国と言った。
そして当時を知るパラオの長老たちは今でも日本をこう呼ぶという。
『内地』
更にパラオです。
前に書いたトピックでパラオは親日国で国旗は日の丸を参考に作られたと書きました。
今回はその国旗を選択する時のエピソードを書きます。。
パラオの人々は国旗の選択に相当な苦労をしました。応募者はパラオに属する各島の人々でありそれぞれの旗にそれぞれの島とそれぞれのパラオに対する思いがありました。
パラオは歴史と伝統の国です、なので選考委員は真剣でした。
選考にはかなりの期間をかけました。
しかし最終的にあの国旗に決まったのは簡単な理由でした。
『日本の旗に一番似ているから』でした、それだけで最大の人気が集まりました。
日の丸の部分を黄色にしたのは月を現わします。
周囲の青の部分は海を現わします。
月は太陽が出ないと輝くことができません。
つまり月は太陽によって支えられ、月としての生命を持ちます。
太陽とは日本のことです。
海に囲まれたパラオは日本という太陽の反射によって輝かねば生きられないという意味を込めた国旗です。
パラオの人々は戦争中に日の丸を掲げて強大な米軍と戦闘した日本軍兵士たちの勇敢さと純粋さに太陽の様な大きな魅力と尊敬を感じました。
一万に及ぶ日本人たちはパラオの人達に勇気と国を想う心があればアメリカよりも強くなれることを教えて死んだのです。
最後に…ウズベキスタンの話。
ウズベキスタン共和国の首都はタシケントです。
その中心部に国立ナボイ劇場という劇場があります。
レンガ造りの三階建てで観客席は1400人という巨大な建物でタシケントの代表的建造物として今でも威容を誇っています。
この劇場の正面には
『1945年から46年にかけて極東から強制移住させられた数百人の日本人がこの劇場の建設に参加し、その完成に貢献した』
とウズベク語、日本語、英語で表記されたプレートが設置されています。
ウズベキスタンでは第二次世界大戦後、ソ連によってシベリアにいた約2万5千人の日本人抑留者が移送され水力発電所や運河、道路などの建設に従事させられました。
中山恭子さんという元ウズベキスタン大使は在任中にいまも国民に電気を供給している水力発電所の建設を仕切った元現場監督に会いました。
この人物は、まじめに、そして懸命に汗を流していた日本人抑留者たちの思い出を涙ながらに語ったといいます。
捕虜の境遇にあっても勤勉に働く日本人抑留者は当時の地元民に敬意を表されました。
現地の人は日本人たちに『絶対に帰れるぞ!』と励ましながら黒パンを握らせてくれたそうです。
日本人抑留者が現地に残した遺産のシンボルが約500人の抑留者によって2年がかりで建設したナボイ劇場なのです。
レンガ製造から館内の装飾、彫刻まで抑留者が行った。
1966年にウズベキスタンを襲った大地震でタシケント市内の多くの建造物が倒壊した際も、この劇場はビクともせず
『日本人の建物は堅固だ』『日本人の建築技術は高い』という評価が定着しました。
そのためか親日感情が強い中央アジア諸国の中でもウズベキスタンの日本人への好感度は飛び抜けています。
1991年に旧ソ連から独立して新国家建設を進めるウズベキスタンはカリモフ大統領が就任演説の時に言った
『日本の明治維新や戦後復興をモデルとして「日本に見習え」』
を合言葉にしています。
劇場前のプレートの表記についてはカリモフ大統領が
『決して日本人捕虜と表記するな。日本とウズベキスタンは一度も戦争していない』
と厳命したそうです。
2万人の抑留者のうち、800人以上が現地で死亡し各地の墓地に埋葬されましたがその多くは荒れ放題となりました。
しかし元抑留者たちと地元の人たちが協力しあいウズベキスタンでは珍しい募金活動を行い更に目的を知ったウズベキスタン政府の協力も得て日本人墓地が整備されました。
また
『日本に 帰ってもう一度、花見がしたかった』
と言い残して亡くなった抑留者のために日本からサクラの苗木千三百本が送られました。
整備の発起人の一人、中山成彬衆院議員は
『両国友好の証しになってほしい』
と話しています。
過酷な環境の中で日本への帰国を夢見ながらも勤勉に働いてウズベキスタンと日本との友好の絆を残してくれた抑留者に感謝と追悼の意を捧げてこのトピックを終わります。
|
|
|
|
|
|
|
|
THE 感動する話 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
THE 感動する話のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6420人
- 3位
- 独り言
- 9045人