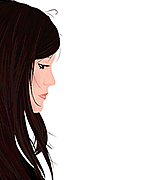昔は政治をする人の事を『政治家』とは呼んでいませんでした。
『民政家』民の為の政治をする人という意味です。
今の山形県南部にある米沢盆地。
戦国時代を終えてここに入ってきたのは上杉謙信で有名な上杉家でした。
しかし関ヶ原の戦いで西軍についたために、上杉家は120万石の領地から30万石にまで減らされます。更に藩主が急死し混乱が起き、半分の15万石にまで減らされました。
しかし家臣を大幅に減らすという事をしなかった為に上杉家は今の日本の様な赤字を抱え込んでしまいます。
その上杉家に九州から養子として来たのが上杉治憲、後の上杉鷹山です。
上杉鷹山は1751年7月20日、日向高鍋藩の藩主秋月種美の次男として生まれました。歴史の教科書にも載っていない鷹山ですが、この人は江戸時代にいた将軍、全ての大名の中でも一番の名君中の名君といわれました。
鷹山の生涯を追っていきます。
江戸時代の各藩は今の都道府県の様に国に依存する経営ではなく、完全に自治権を与えられていました。つまり藩内であればどんな法律を作っても良い、どんな方法で統治しても良いという事です。
つまり会社に近い物がありました。藩主の資質・力量によってその経営内容は大きく左右されました。もっとも江戸後期は一部の藩を除いて、どの藩も貧しく徳川幕府でさえ、財政危機の連続でした。
当時の財政の基盤は米を中心とした農業で、その年の天侯に左右されることが多かったので各藩の経済はきわめて不安定でした。江戸時代を通じて幕府以下どの藩も慢性的な赤字にあえいでいましたが、古い体制では変わりようがなく悪化した経営を建て直すことはまず不可能に近くほとんどの藩が明治以降になってから債務を返済し始めています。
そうした中で米沢藩主、上杉鷹山は改革に成功し財政危機を乗り越えて黒字経営を達成し、更に近隣の藩に援助が出来る程の貯金も多くありました。
鷹山の妻は前藩主の重定の娘で鷹山の2歳年下の幸姫(よしひめ)です。
彼女は脳に障がいがあったと言われています。彼女は1769年に鷹山と婚礼を上げ1782年に30歳という若さで死去するという短い生涯でした。
しかし鷹山は幸姫を心から愛し、女中たちに同情されながらも幸姫が亡くなるまでずっと、ひな遊びやおもちゃ遊びの相手をし2人は仲の良い夫婦として暮らしました。前藩主の重定は娘の遺品を手にして初めて娘が脳に障がいをもっている事を知り、娘への鷹山の愛に涙したそうです。昔は親子といっても会わない事が多かったので前藩主の重定は障がいに気付かなかったそうです。
1766年、数え年16歳になった鷹山は、将軍徳川家治の前で元服し、将軍の一字をもらって治憲(はるのり)と改名しました。鷹山と名乗るのはずっと後に養父の重定が死去してからです。
そして翌1767年に重定が隠退し、鷹山は上杉家の家督を継ぎ第9代米沢藩主となりました。この時、鷹山は17歳です。厳しい状況で迎えた藩主でした。
というのも米沢藩は未曾有といっていいほど藩財政が極端に窮乏し家臣も領民も貧困にあえいでいたからです。
更に悪いことは重なりその年から大凶作が始まりました。
そして鷹山は大倹執行の命令を発します。
短期間に大幅な収入増が見込めぬ以上、できるだけ出費を切りつめなければならないからでした。つまり倹約生活です。しかし給与の低い家臣や領民の貧困を気にもせずに永年特権の上にあぐらをかいてきた藩の上層部は当然若き新藩主の方針に不満でいっぱいでした。しかし鷹山は自らが率先して倹約生活を送ることで大倹を断行しました。
藩主の生活費はそれまで1500両でしたがこれを200両少しまで圧縮しました。日常の食事は一汁一菜、衣服は綿にして、50人もいた奥女中は9人に減らしました。
1769年10月、鷹山は藩主となって初めて米沢に行きました。このとき鷹山は、側近が止めるのもきかず米沢のかなり手前から馬に乗り吹雪の中を堂々と入城したといわれています。
また翌月に行われた恒例の祝儀の宴では倹約中であるということで従来のご馳走料理をやめて、赤飯と酒だけにしました。その途中、鷹山は身分的には最下級の足軽にまで親しく言葉をかけました。
こうした若き新津主の旧習を破る行動は、身分が低い人たちには熱烈に歓迎されましたが、上級家臣や老臣たちの反発を招きました。
彼らはことあるごとに鷹山の新政策を止めさせようと横槍を入れます。
家臣の須田という人は倹約を全くせず浪費を増やし、乗馬の際には高価なチリメン羽織を着用するというように平然と鷹山への当て付けを行っていました。
しかし一方で、鷹山の革新を歓迎し、古い体制を打破して新しい米沢藩をつくろうという側近も少なくありませんでした。
鷹山は竹俣当綱(まさつな)や莅戸善政(のぞきよしまさ)らの強力な援護を得て、藩政改革を進めていきました。
そして1773年、須田をはじめとする譜代の老臣7名が、鷹山に対してついに反旗をひるがえしました。これまで鷹山を中心に改革派が推し進めてきた政策をすべて否定するという訴えを起こしました。
鷹山は藩主になって以来はじめて、重臣たちの反乱にあうという重大な局面に立たされました。しかし鷹山は果断でした。
一応の審査ののち訴状の出された三日後には7人の重臣すべてを閉門、減知するなど処断しました。こののち、改革政策は、見事に成果を上げ始めました。武士も農民の手伝いをする家臣総出で農業に取り組み生産能力の向上を遂げたのです。
これは当時では考えられない事でした、武士を見ると道を開けていた農民が武士に指示を出すと武士は素直に聞く、武士も農民の知識に接する事でお互いを大事に思わなければと思う。これがきっかけで米沢藩では武士が農民を斬るという事件はそれ以降起きませんでした。
鷹山はよく領内の村をまわり、農業の生産力を上げた代表者に褒美を与えました。そして代官の世襲制度を廃止して、優秀で農民思いの人材を代官に登用しました。
また、鷹山は産業の開発にも力を入れました。これまで米沢藩の伝統的産業は、漆、蝋が藩財政の重要な部分を占めていました。しかしこれらの国産物はいずれも衰退していました
そこで漆、桑、楮(こうぞ)各百万本を植樹する計画を立てました。
財源の回復と山間部の農村復興を目指したものでした。縮み織りの染料となる藍の栽培をはじめたのもこの頃のことです。同時に藩営の縮織業を開始しました。
また鷹山が学問を重視したことはよく知られています。彼が興譲館という学校を築いたのは、1782年のことです。鷹山の師匠である細井平洲を招き、身分の上下、年に関わらず領内の人ならば誰でも通えるようにしました。
妻の幸姫は1782年、30歳まで生きて亡くなりました。
その間、鷹山は幸姫がいる江戸屋敷には一人の側室も置きませんでした。当時の藩主の側室の平均人数は7人前後でした。幸姫が悲しむ姿を見たくなかったからだと言われています。
鷹山の側室は、国元の米沢には一人だけいました。お豊の方という人です。このお豊の方は、前藩主重定のいとこにあたります。鷹山より10歳年上であった彼女は教養も高く、鷹山をよく理解した賢婦人でした。
彼女は鷹山の息子を二人もうけましたが、いずれも早くに亡くなっています。しかし鷹山との間はうまくいき、鷹山を支えつづけて81歳まで生きました。
そして1785年、鷹山は35歳の若さで隠退しました。跡を継いだのは前藩主重定の息子、治広でした。
養父重定はこの時まだ健在であり、その実子に藩主の座を譲るというのは、いわば重定を安心させてやりたいという鷹山の優しい心の表われでもありました。
隠退にあたって鷹山が治広に与えた有名な『伝国之辞』は鷹山の政治理念を象徴する名言として知られています。
一、国家は先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべき物には無之候。
一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物には無之候。
一、国家人民の為に立たる君にして、君の為に立たる国家人民には無之候。
隠居した鷹山は米沢城に餐霞館(さんかかん)と名づけた建物を建てそこで暮らしました。生活は藩主の時以上に倹約し年間の生活費も前藩主重定の三分の一以下。
しかしまったく隠退してしまったわけではなく治広をバックアップして、さらに次の11代斉定をも後見して、米沢藩の経営を実質的につかみ続けました。
1822年2月、病に倒れた鷹山は、1カ月の休養の後、3月12日の朝、静かに息を引き取りました。72歳でした。
鷹山の特徴として身分が低い者への尊敬と愛情がありました。言うなれば倹約生活の先輩なわけですから農民からはよく意見を教えてもらいに村まで行きました。
民の生活をよくする為には、日頃農民に接する藩の役人の態度を改めることが根本でした。というのも役人の主な任務は農民から確実に年貢を取り立てることでしたから、彼らは農民に対し斬っても良いという権限があったので農民がしっかり年貢を出しても余分に取って自分の利益にしようという役人が多くいたのです。
そして鷹山はこれら役人の心構えについての文を書き、彼らに教え論しました。その文章を要約すると
『役人は母の赤子に対する心をもって民にのぞめ。
この真心、誠のあるところ愛を生じ、愛は知を生ずる』
というものです。鷹山の心に終始あったものは、ひたすら民を思い民を愛するという事でした。鷹山のこの民に対する姿勢こそ、今の政治家にも必要な物だと思います。
鷹山は藩内の12の地方に『郷村教導出役』という役人もおきました。鷹山が彼らに与えた任務は次の通りです。
天道を敬うことを教える事
父母への孝行を教える事
家内睦まじく親類親しむことを教える事
頼りなき者をいたわって渡世させる事
民の害を除き民の潤益をとり行う事
上に立ち百姓を取扱う諸役人の邪正に注意する事
往来の病人をいたわる事
郷村教導出役の任務は一つに農民の生活を守ることであり、いま一つは農民に人の道を教え倫理の大切さを教えることでした。
鷹山の抜擢をうけた12人はいずれも民に優しく時には厳しいすぐれた人物で、彼らはよく鷹山の意を体し競い合って働きました。
鷹山はしばしばこの12人を呼び出しては直接彼らと語り合い農政の改善に全力を尽くしました。こうして米沢藩の農政は着々とその成果をあげ農民の生活は向上していきました。ここまで藩主自身が農政に心を傾けた君主は江戸期通じて鷹山一人と言っても言い過ぎではありません。他の藩では学者などにこの意見を持った人が現れそれを採用する藩主はいましたが藩主自身が考え動くという事は鷹山以外いませんでした。
鷹山は政治と農業と道徳を一体化して人々に教えていました。
政治は本来、人々の生活を守ることが大前提であり、これができなければ政治家として失格です。
鷹山はこのことに執着し努力を傾けて遂にそれを達成しました。しかしそれだけではなく人々の生活を守るだけが政治の全てではなく、人間としてより人間らしく道徳を大切に立派に生きることを教える事こそが真の政治家であると言葉に残しています。
本当の政治はやはりこの鷹山の言葉を無視して通れないと思います。
鷹山は今の年金や保険の様なものまで作りました。
『五什組合』です。
これは農民たちを助ける組織です。近隣の五軒を五人組として相互に助け合い、村全体が共同体として苦楽をともにするものでした。鷹山は五什組合について次のように定めました。
五人組は常にむつまじく交りて苦楽をともにすること、家族の如くなるべし。
十人組は時々親しく出入りして家事を聞くこと、親類の如くなるべし。
一村は互いに助け合い、互いに救い合いたのもしきこと、朋友の如くなるべし。
組合村は患難にあって助け、隣村よしみ甲斐あるべし。
そして、老いて子なき者、幼にして父母なき者、夫婦のいずれかを失った者、病傷者で生活できない者、死者を出しても葬式を出せない貧しい者、火災にあった者等々、全ての苦しむ者に対し、五人組、十人組、一村が相互扶助することを定めたのです。いわば現在の社会福祉の基盤です。
これは鷹山の民への愛情を示した農村政策であり、決して農民への支配と統制を目的とする制度ではありませんでした。
後アメリカで発表される内村鑑三著の『代表的日本人』の中でこの五什組合のことを
『鷹山の民を最大に考えるこの考えはどこにも存在しなかった。我々はかつて鷹山の米沢領以外、地球の他のいかなる部分においても、これに類したものの公布され、それの実行に移されたるを見たことなしと言明する』
と述べています。
ほかにも鷹山は、老人や病人、妊婦などの弱者を重視する社会福祉政策の充実をはかり、それを実現させました。
鷹山の時代は医者が余りにも少ない時代でしたので病気になっても医者にかかる事ができない者が多く鷹山は藩外で医師を募集し米沢藩では藩の負担で医師の住居から生活に必要なお金すべてを出すと布告し、医師を募集しました。
これによりどれほど多くの人が助けられたかは言うまでもない。
この当時は悲しくも堕胎いわゆる間引は日常化していました。
その要因は、結局子供を生んでも育てられない生活の貧しさにありました。
鷹山は熟慮と協議を重ねた結果、藩の予算からやりくりして6000両の育児資金をつくり出し、子供を育てられない窮民にこれを与えることにしました。
こうして前後約30年の努力を傾注した結果、ついに米沢藩において堕胎間引を無くす事に成功するのでした。
さらに当時、生活苦のため働けなくなった老人は今の時代では信じられない事ですが『食糧減らし』のためしばしば野山に捨てられました。
鷹山はこの忌まわしい習慣の絶滅のために策を講じました。
それは90歳以上のものは亡くなるまで食べてゆける今でいう年金を与え、70歳以上のものは村で責任をもっていたわり世話することを決めました。それのみならず鷹山は、老人を大切にいたわる孝子を褒賞するとともに自ら敬老を実践しました。敬老の日が出来たのも鷹山の心を忘れないためと言われています。
こうして鷹山自ら誠意の限りをつくした敬老養老の実践は、堕胎とともにこの悪い習慣も無くす事に成功しました。
鷹山の50年にわたる努力は遂に米沢藩を変え、日本の歴史上、最も価値ある理想の福祉国家をつくり上げることに成功したのでした。
鷹山が72歳でなくなった時、藩内の全員がその両親を失ったかのように、その悲しみは言語に絶しました。
埋葬の当日、5万人以上の人々が老人を伴い、あるいは幼児をたずさえて沿道に平伏して鷹山のひつぎを拝み、すすり泣き、嗚咽、号泣の声は山野に満ちたそうです。
当時の米沢藩の人口は約4万5千人。他藩からも鷹山を惜しむ人が来たのだと思います。
最後に鷹山がよく言っていた言葉を。
『成せば成る。
成さねば成らぬ何事も
成らぬは人の成さぬなりけり』
『民政家』民の為の政治をする人という意味です。
今の山形県南部にある米沢盆地。
戦国時代を終えてここに入ってきたのは上杉謙信で有名な上杉家でした。
しかし関ヶ原の戦いで西軍についたために、上杉家は120万石の領地から30万石にまで減らされます。更に藩主が急死し混乱が起き、半分の15万石にまで減らされました。
しかし家臣を大幅に減らすという事をしなかった為に上杉家は今の日本の様な赤字を抱え込んでしまいます。
その上杉家に九州から養子として来たのが上杉治憲、後の上杉鷹山です。
上杉鷹山は1751年7月20日、日向高鍋藩の藩主秋月種美の次男として生まれました。歴史の教科書にも載っていない鷹山ですが、この人は江戸時代にいた将軍、全ての大名の中でも一番の名君中の名君といわれました。
鷹山の生涯を追っていきます。
江戸時代の各藩は今の都道府県の様に国に依存する経営ではなく、完全に自治権を与えられていました。つまり藩内であればどんな法律を作っても良い、どんな方法で統治しても良いという事です。
つまり会社に近い物がありました。藩主の資質・力量によってその経営内容は大きく左右されました。もっとも江戸後期は一部の藩を除いて、どの藩も貧しく徳川幕府でさえ、財政危機の連続でした。
当時の財政の基盤は米を中心とした農業で、その年の天侯に左右されることが多かったので各藩の経済はきわめて不安定でした。江戸時代を通じて幕府以下どの藩も慢性的な赤字にあえいでいましたが、古い体制では変わりようがなく悪化した経営を建て直すことはまず不可能に近くほとんどの藩が明治以降になってから債務を返済し始めています。
そうした中で米沢藩主、上杉鷹山は改革に成功し財政危機を乗り越えて黒字経営を達成し、更に近隣の藩に援助が出来る程の貯金も多くありました。
鷹山の妻は前藩主の重定の娘で鷹山の2歳年下の幸姫(よしひめ)です。
彼女は脳に障がいがあったと言われています。彼女は1769年に鷹山と婚礼を上げ1782年に30歳という若さで死去するという短い生涯でした。
しかし鷹山は幸姫を心から愛し、女中たちに同情されながらも幸姫が亡くなるまでずっと、ひな遊びやおもちゃ遊びの相手をし2人は仲の良い夫婦として暮らしました。前藩主の重定は娘の遺品を手にして初めて娘が脳に障がいをもっている事を知り、娘への鷹山の愛に涙したそうです。昔は親子といっても会わない事が多かったので前藩主の重定は障がいに気付かなかったそうです。
1766年、数え年16歳になった鷹山は、将軍徳川家治の前で元服し、将軍の一字をもらって治憲(はるのり)と改名しました。鷹山と名乗るのはずっと後に養父の重定が死去してからです。
そして翌1767年に重定が隠退し、鷹山は上杉家の家督を継ぎ第9代米沢藩主となりました。この時、鷹山は17歳です。厳しい状況で迎えた藩主でした。
というのも米沢藩は未曾有といっていいほど藩財政が極端に窮乏し家臣も領民も貧困にあえいでいたからです。
更に悪いことは重なりその年から大凶作が始まりました。
そして鷹山は大倹執行の命令を発します。
短期間に大幅な収入増が見込めぬ以上、できるだけ出費を切りつめなければならないからでした。つまり倹約生活です。しかし給与の低い家臣や領民の貧困を気にもせずに永年特権の上にあぐらをかいてきた藩の上層部は当然若き新藩主の方針に不満でいっぱいでした。しかし鷹山は自らが率先して倹約生活を送ることで大倹を断行しました。
藩主の生活費はそれまで1500両でしたがこれを200両少しまで圧縮しました。日常の食事は一汁一菜、衣服は綿にして、50人もいた奥女中は9人に減らしました。
1769年10月、鷹山は藩主となって初めて米沢に行きました。このとき鷹山は、側近が止めるのもきかず米沢のかなり手前から馬に乗り吹雪の中を堂々と入城したといわれています。
また翌月に行われた恒例の祝儀の宴では倹約中であるということで従来のご馳走料理をやめて、赤飯と酒だけにしました。その途中、鷹山は身分的には最下級の足軽にまで親しく言葉をかけました。
こうした若き新津主の旧習を破る行動は、身分が低い人たちには熱烈に歓迎されましたが、上級家臣や老臣たちの反発を招きました。
彼らはことあるごとに鷹山の新政策を止めさせようと横槍を入れます。
家臣の須田という人は倹約を全くせず浪費を増やし、乗馬の際には高価なチリメン羽織を着用するというように平然と鷹山への当て付けを行っていました。
しかし一方で、鷹山の革新を歓迎し、古い体制を打破して新しい米沢藩をつくろうという側近も少なくありませんでした。
鷹山は竹俣当綱(まさつな)や莅戸善政(のぞきよしまさ)らの強力な援護を得て、藩政改革を進めていきました。
そして1773年、須田をはじめとする譜代の老臣7名が、鷹山に対してついに反旗をひるがえしました。これまで鷹山を中心に改革派が推し進めてきた政策をすべて否定するという訴えを起こしました。
鷹山は藩主になって以来はじめて、重臣たちの反乱にあうという重大な局面に立たされました。しかし鷹山は果断でした。
一応の審査ののち訴状の出された三日後には7人の重臣すべてを閉門、減知するなど処断しました。こののち、改革政策は、見事に成果を上げ始めました。武士も農民の手伝いをする家臣総出で農業に取り組み生産能力の向上を遂げたのです。
これは当時では考えられない事でした、武士を見ると道を開けていた農民が武士に指示を出すと武士は素直に聞く、武士も農民の知識に接する事でお互いを大事に思わなければと思う。これがきっかけで米沢藩では武士が農民を斬るという事件はそれ以降起きませんでした。
鷹山はよく領内の村をまわり、農業の生産力を上げた代表者に褒美を与えました。そして代官の世襲制度を廃止して、優秀で農民思いの人材を代官に登用しました。
また、鷹山は産業の開発にも力を入れました。これまで米沢藩の伝統的産業は、漆、蝋が藩財政の重要な部分を占めていました。しかしこれらの国産物はいずれも衰退していました
そこで漆、桑、楮(こうぞ)各百万本を植樹する計画を立てました。
財源の回復と山間部の農村復興を目指したものでした。縮み織りの染料となる藍の栽培をはじめたのもこの頃のことです。同時に藩営の縮織業を開始しました。
また鷹山が学問を重視したことはよく知られています。彼が興譲館という学校を築いたのは、1782年のことです。鷹山の師匠である細井平洲を招き、身分の上下、年に関わらず領内の人ならば誰でも通えるようにしました。
妻の幸姫は1782年、30歳まで生きて亡くなりました。
その間、鷹山は幸姫がいる江戸屋敷には一人の側室も置きませんでした。当時の藩主の側室の平均人数は7人前後でした。幸姫が悲しむ姿を見たくなかったからだと言われています。
鷹山の側室は、国元の米沢には一人だけいました。お豊の方という人です。このお豊の方は、前藩主重定のいとこにあたります。鷹山より10歳年上であった彼女は教養も高く、鷹山をよく理解した賢婦人でした。
彼女は鷹山の息子を二人もうけましたが、いずれも早くに亡くなっています。しかし鷹山との間はうまくいき、鷹山を支えつづけて81歳まで生きました。
そして1785年、鷹山は35歳の若さで隠退しました。跡を継いだのは前藩主重定の息子、治広でした。
養父重定はこの時まだ健在であり、その実子に藩主の座を譲るというのは、いわば重定を安心させてやりたいという鷹山の優しい心の表われでもありました。
隠退にあたって鷹山が治広に与えた有名な『伝国之辞』は鷹山の政治理念を象徴する名言として知られています。
一、国家は先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべき物には無之候。
一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物には無之候。
一、国家人民の為に立たる君にして、君の為に立たる国家人民には無之候。
隠居した鷹山は米沢城に餐霞館(さんかかん)と名づけた建物を建てそこで暮らしました。生活は藩主の時以上に倹約し年間の生活費も前藩主重定の三分の一以下。
しかしまったく隠退してしまったわけではなく治広をバックアップして、さらに次の11代斉定をも後見して、米沢藩の経営を実質的につかみ続けました。
1822年2月、病に倒れた鷹山は、1カ月の休養の後、3月12日の朝、静かに息を引き取りました。72歳でした。
鷹山の特徴として身分が低い者への尊敬と愛情がありました。言うなれば倹約生活の先輩なわけですから農民からはよく意見を教えてもらいに村まで行きました。
民の生活をよくする為には、日頃農民に接する藩の役人の態度を改めることが根本でした。というのも役人の主な任務は農民から確実に年貢を取り立てることでしたから、彼らは農民に対し斬っても良いという権限があったので農民がしっかり年貢を出しても余分に取って自分の利益にしようという役人が多くいたのです。
そして鷹山はこれら役人の心構えについての文を書き、彼らに教え論しました。その文章を要約すると
『役人は母の赤子に対する心をもって民にのぞめ。
この真心、誠のあるところ愛を生じ、愛は知を生ずる』
というものです。鷹山の心に終始あったものは、ひたすら民を思い民を愛するという事でした。鷹山のこの民に対する姿勢こそ、今の政治家にも必要な物だと思います。
鷹山は藩内の12の地方に『郷村教導出役』という役人もおきました。鷹山が彼らに与えた任務は次の通りです。
天道を敬うことを教える事
父母への孝行を教える事
家内睦まじく親類親しむことを教える事
頼りなき者をいたわって渡世させる事
民の害を除き民の潤益をとり行う事
上に立ち百姓を取扱う諸役人の邪正に注意する事
往来の病人をいたわる事
郷村教導出役の任務は一つに農民の生活を守ることであり、いま一つは農民に人の道を教え倫理の大切さを教えることでした。
鷹山の抜擢をうけた12人はいずれも民に優しく時には厳しいすぐれた人物で、彼らはよく鷹山の意を体し競い合って働きました。
鷹山はしばしばこの12人を呼び出しては直接彼らと語り合い農政の改善に全力を尽くしました。こうして米沢藩の農政は着々とその成果をあげ農民の生活は向上していきました。ここまで藩主自身が農政に心を傾けた君主は江戸期通じて鷹山一人と言っても言い過ぎではありません。他の藩では学者などにこの意見を持った人が現れそれを採用する藩主はいましたが藩主自身が考え動くという事は鷹山以外いませんでした。
鷹山は政治と農業と道徳を一体化して人々に教えていました。
政治は本来、人々の生活を守ることが大前提であり、これができなければ政治家として失格です。
鷹山はこのことに執着し努力を傾けて遂にそれを達成しました。しかしそれだけではなく人々の生活を守るだけが政治の全てではなく、人間としてより人間らしく道徳を大切に立派に生きることを教える事こそが真の政治家であると言葉に残しています。
本当の政治はやはりこの鷹山の言葉を無視して通れないと思います。
鷹山は今の年金や保険の様なものまで作りました。
『五什組合』です。
これは農民たちを助ける組織です。近隣の五軒を五人組として相互に助け合い、村全体が共同体として苦楽をともにするものでした。鷹山は五什組合について次のように定めました。
五人組は常にむつまじく交りて苦楽をともにすること、家族の如くなるべし。
十人組は時々親しく出入りして家事を聞くこと、親類の如くなるべし。
一村は互いに助け合い、互いに救い合いたのもしきこと、朋友の如くなるべし。
組合村は患難にあって助け、隣村よしみ甲斐あるべし。
そして、老いて子なき者、幼にして父母なき者、夫婦のいずれかを失った者、病傷者で生活できない者、死者を出しても葬式を出せない貧しい者、火災にあった者等々、全ての苦しむ者に対し、五人組、十人組、一村が相互扶助することを定めたのです。いわば現在の社会福祉の基盤です。
これは鷹山の民への愛情を示した農村政策であり、決して農民への支配と統制を目的とする制度ではありませんでした。
後アメリカで発表される内村鑑三著の『代表的日本人』の中でこの五什組合のことを
『鷹山の民を最大に考えるこの考えはどこにも存在しなかった。我々はかつて鷹山の米沢領以外、地球の他のいかなる部分においても、これに類したものの公布され、それの実行に移されたるを見たことなしと言明する』
と述べています。
ほかにも鷹山は、老人や病人、妊婦などの弱者を重視する社会福祉政策の充実をはかり、それを実現させました。
鷹山の時代は医者が余りにも少ない時代でしたので病気になっても医者にかかる事ができない者が多く鷹山は藩外で医師を募集し米沢藩では藩の負担で医師の住居から生活に必要なお金すべてを出すと布告し、医師を募集しました。
これによりどれほど多くの人が助けられたかは言うまでもない。
この当時は悲しくも堕胎いわゆる間引は日常化していました。
その要因は、結局子供を生んでも育てられない生活の貧しさにありました。
鷹山は熟慮と協議を重ねた結果、藩の予算からやりくりして6000両の育児資金をつくり出し、子供を育てられない窮民にこれを与えることにしました。
こうして前後約30年の努力を傾注した結果、ついに米沢藩において堕胎間引を無くす事に成功するのでした。
さらに当時、生活苦のため働けなくなった老人は今の時代では信じられない事ですが『食糧減らし』のためしばしば野山に捨てられました。
鷹山はこの忌まわしい習慣の絶滅のために策を講じました。
それは90歳以上のものは亡くなるまで食べてゆける今でいう年金を与え、70歳以上のものは村で責任をもっていたわり世話することを決めました。それのみならず鷹山は、老人を大切にいたわる孝子を褒賞するとともに自ら敬老を実践しました。敬老の日が出来たのも鷹山の心を忘れないためと言われています。
こうして鷹山自ら誠意の限りをつくした敬老養老の実践は、堕胎とともにこの悪い習慣も無くす事に成功しました。
鷹山の50年にわたる努力は遂に米沢藩を変え、日本の歴史上、最も価値ある理想の福祉国家をつくり上げることに成功したのでした。
鷹山が72歳でなくなった時、藩内の全員がその両親を失ったかのように、その悲しみは言語に絶しました。
埋葬の当日、5万人以上の人々が老人を伴い、あるいは幼児をたずさえて沿道に平伏して鷹山のひつぎを拝み、すすり泣き、嗚咽、号泣の声は山野に満ちたそうです。
当時の米沢藩の人口は約4万5千人。他藩からも鷹山を惜しむ人が来たのだと思います。
最後に鷹山がよく言っていた言葉を。
『成せば成る。
成さねば成らぬ何事も
成らぬは人の成さぬなりけり』
|
|
|
|
|
|
|
|
THE 感動する話 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
THE 感動する話のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90061人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208318人
- 3位
- 酒好き
- 170698人