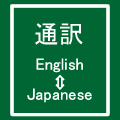●2006年度通訳案内士試験ガイドラインの全文です。
ご参考になさってください。
?.試験全体について
(1)目的
・試験の目的は、「通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(通訳案内士法第5条) であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。
(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、日本地理、日本歴史及び一般常識(産業、経済、政治及び文化)とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・日本地理、日本歴史及び一般常識の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
(3)試験委員
・通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、全ての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。
(5)試験免除
・一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、次回の通訳案内士試験(※)を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
(※)「次回の通訳案内士試験」とは、「当該試験終了後、最初に行われる通訳案内士試験」を指す(本ガイドラインにおいて以下同じ。)。
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、次回の通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・旅行業務取扱管理者試験に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本地理の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。
・歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史の科目についての筆記試験を免除する。
?.外国語(筆記試験)について
(1)試験方法
・外国語の種類は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語(平成18年度試験より追加)の10言語とする。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
(参考)平成17年度英語筆記:英文読解問題1題(24点)、英文和訳問題1題(14点)、和文英訳問題1題(12点)、英語による説明問題1題(12点)、英文の日本語による要約問題1題(10点)、単語英訳問題1題(20点)、単語の穴埋め問題1題(8点)
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
(補足)現行の試験 1問2点 10問 計20点
修正案 1問1点 15問 計15点
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。
?.日本地理について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:3題(32問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、中学校及び高校の地理の教科書並びに地図帳をベースとし、地図や写真を使った問題を3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
IV.日本歴史について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:9題(45問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の歴史についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の日本史Bの教科書をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
V.一般常識について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:4題(42問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の現代社会の教科書をベースにし、新聞(一般紙)に掲載されているような最近の時事問題を加味する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
VI.口述試験について
(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とする。
(2)合否判定
・合否判定については、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)
以上
ご参考になさってください。
?.試験全体について
(1)目的
・試験の目的は、「通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(通訳案内士法第5条) であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。
(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、日本地理、日本歴史及び一般常識(産業、経済、政治及び文化)とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・日本地理、日本歴史及び一般常識の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
(3)試験委員
・通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、全ての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。
(5)試験免除
・一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、次回の通訳案内士試験(※)を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
(※)「次回の通訳案内士試験」とは、「当該試験終了後、最初に行われる通訳案内士試験」を指す(本ガイドラインにおいて以下同じ。)。
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、次回の通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・旅行業務取扱管理者試験に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本地理の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。
・歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史の科目についての筆記試験を免除する。
?.外国語(筆記試験)について
(1)試験方法
・外国語の種類は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語(平成18年度試験より追加)の10言語とする。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
(参考)平成17年度英語筆記:英文読解問題1題(24点)、英文和訳問題1題(14点)、和文英訳問題1題(12点)、英語による説明問題1題(12点)、英文の日本語による要約問題1題(10点)、単語英訳問題1題(20点)、単語の穴埋め問題1題(8点)
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
(補足)現行の試験 1問2点 10問 計20点
修正案 1問1点 15問 計15点
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。
?.日本地理について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:3題(32問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、中学校及び高校の地理の教科書並びに地図帳をベースとし、地図や写真を使った問題を3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
IV.日本歴史について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:9題(45問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の歴史についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の日本史Bの教科書をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
V.一般常識について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:4題(42問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の現代社会の教科書をベースにし、新聞(一般紙)に掲載されているような最近の時事問題を加味する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
VI.口述試験について
(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とする。
(2)合否判定
・合否判定については、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)
以上
|
|
|
|
コメント(1)
●地域限定通訳案内士試験ガイドラインの全文です。
ご参考になさってください。
?.試験全体について
(1)目的
・試験の目的は、「地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客誘致法」という。)第26条第1項)であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。
(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験は、地方自治法第2条第8項による自治事務として実施する。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとし、事業実施地域の制限のない通訳ガイドの登録を得るための試験(以下「通訳案内士試験」という。)と同一の問題を出題することとする。そのため、試験の実施日時については、外国語の筆記試験に関しては、通訳案内士試験の実施日時に合わせるものとする。ただし、外国語以外の筆記試験及び口述試験についてはこの限りではない。
・同一年度に実施される通訳案内士試験と、地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有することとする。
・同一年度に実施される複数の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有する。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事項であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、都道府県で出題のベースとなるテキストを作成し、そのテキストから出題することが望ましい。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・試験の実施回数は、年1回を原則とする。
(3)試験委員
・地域限定通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
・外国語の筆記試験に係る試験委員については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員全員を再任した上で、上記の業務を行わせるものとする。
(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局で構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準点の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・外国語の筆記試験に係る上記の合否判定事務については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員と同一の試験委員により、同一の基準で行う。
・通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、当該地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、すべての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。
(5)試験免除
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する他の外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・地域限定通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、他の都道府県知事が実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、他の都道府県知事が当該試験終了後、最初に実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。
(6)複数都道府県合同試験
・外客誘致法に基づく各「外客来訪促進地域」(いわゆる「国際観光テーマ地区」)を構成する都道府県については、合同で試験を実施することができる。
◆国際観光テーマ地区一覧(平成18年1月1日現在)
○北海道地区 「四季・感動・北海道」 (北海道)
○北東北地区 「発見!もう一つの日本・北緯40°の道」 (青森県、岩手県及び秋田県)
○南東北地区 「“あづま路”〜武家のロマン、日本のふるさと、自然と温泉との出会い〜」(宮城県、山形県、福島県及び栃木県)
○茨城・千葉県地区 「世界から一番近い日本の歴史と未来 〜NARITAからはじまる、日本の自然、歴史から先端技術までに触れる旅〜」 (茨城県及び千葉県)
○上信越地区 「日本の山岳・高原郷と佐渡島 〜美しい自然と温泉を楽しむ旅〜」 (群馬県、新潟県及び長野県)
○東京都地区 「千客万来の世界都市・東京をめざして」(東京都)
○富士箱根伊豆地区 「自然のワンダーランド・富士 −自然と都市、歴史と文化がもてなす日本の旅−」(神奈川県、山梨県及び静岡県)
○北陸地区 「山海神秘の楽園 〜四季彩の温泉回廊〜」 (富山県、石川県及び福井県)
○東海地区 「ハートランド街道 〜日本の匠と世界の産業技術〜」 (岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)
○関西地区 「大阪湾ベイアリアなぎさ街道&関西歴史街道 〜ユニークで多様な観光資源が光り輝く関西・旅の銀河〜」(三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県)
○大阪府地区 「観光立都・大阪 =ターゲットは東アジア」 (大阪府)
○東中四国地区 「日本の心に出会う旅 三海二山」(鳥取県、島根県、岡山県、香川県及び高知県)
○瀬戸内地区 「多島美と地域の伝統 〜海の碧、空の青に染まる一枚の絵」 (広島県、山口県及び愛媛県)
○九州地区 「日本に出会う九州 アジアの玄関、日本の原点(ルーツ)、自然と文化が交差する九州アイランド」(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)
○沖縄地区 「琉球王朝文化が息づく亜熱帯の楽園」 (沖縄県)
・複数の試験地で試験を行う場合は、同一の時間帯に同一の時間割により試験を行うこととする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、合同試験の場合であっても、都道府県ごとに当該都道府県の観光魅力を問う問題を作成し、個別に試験を行う。この場合、受験者が同一年度内に複数の都道府県の試験を受験できるように、都道府県ごとに時間をずらして実施する。
口述試験については、各都道府県が共通の試験委員を選定することで、各都道府県が共通で一度に試験を実施することができることとする。この場合は、合否の判定についても共通で行うこととする。
・口述試験では、通訳案内の実務に関して、受験している都道府県の観光魅力を反映した質問も行う。
・上記の合同試験で複数都道府県の試験に合格した場合であっても、地域限定通訳案内士の登録申請は、本人が登録を希望する個々の都道府県に対してそれぞれ行う。
(7)試験実施事務関連事項
・試験事務を代行させる場合、指定試験機関は、民法第34条に基づく公益法人であり、かつ、本ガイドラインに基づいて適正かつ確実に試験を実施できる体制の整っている団体でなければならない。
・試験事務を代行する指定試験機関は、受験者数と合格者数など試験の実施結果について、都道府県知事に報告しなければならない(外客誘致法第32条第1項)。
・国土交通大臣は、試験事務の適正かつ正確な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験の実施経過と実施結果について、都道府県知事に報告を求める(地方自治法第245条の4第1項)。
?.地域限定通訳案内士の試験実施に対する国土交通大臣の同意の基準について
(1)法定要件
・国土交通大臣の同意の要件は、外客誘致法第4条第3項第5号に規定されており、?「当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること」、?「当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること」、とされている。この要件を満たすかどうかの判断は、その趣旨を踏まえ、具体的には、以下に掲げる基準に基づき行うものとする。
(2)具体的基準
・当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人旅行者数に比し、通訳ガイドの数が不足していること、または今後の外国人旅行者数の増加に伴い、通訳ガイドの数の不足が見込まれること。
あるいは、当該都道府県における通訳ガイドの数自体は不足していないものの、これまでの需要動向等を背景に、その多くが実際に稼働しておらず、当該地域固有の観光魅力についてのより詳しい案内を受けたいという新たな外国人旅行者の需要に十分に応えられていないこと、また、それが、同行案内サービスを提供するボランティアガイドへのニーズの高まり等により、具体的な形で顕在化してきていること。
・試験事務の代行に関すること、試験問題の作成体制及び試験委員に関することが規定されていること。また、指定試験機関が、試験を適正かつ確実に実施できる体制にあること。
・通訳案内士試験と同一の外国語の筆記試験問題を出題することについて、通訳案内士試験の試験事務代行機関との間で共通の試験委員の選任や費用負担等に関する合意がなされていること。
・試験に関する地域問題のテキストを作成しているか、作成する意思があること、又は、テキストを作成する代わりに、試験問題作成のベースとなるような既存の文献等を指定することも可能とする。
・初年度の試験施行要領の案が本ガイドラインに基づき適切に策定されており、かつ、試験導入後当分の間は継続して試験を実施する計画があること。
・当該都道府県における地域限定通訳案内士及び通訳案内士の活動を支援するため、当該都道府県その他の者により、登録後のスキルアップ研修の実施、外国人旅行者とのマッチングシステムの整備、団体の組織化に向けた支援などのフォローアップが行われる見込みがあること。
(3)申請時期
・同意の申請は、通訳案内士試験の公告開始の少なくとも1ヶ月前までに申請するものとする。中断後に初めて実施しようとする場合も同様とする。
?.外国語(筆記試験)について
(1)試験方法
・外国語の筆記試験については、通訳案内士試験と同一の問題を出題することとする。
・外国語の種類は、国の試験で実施している英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語又はタイ語の10言語の中から、?.(2)により国土交通大臣の同意を受けた外客来訪促進計画において定められた言語について、試験を実施する。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。
?.地理について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.歴史について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.産業、経済、政治及び文化について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとする。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.口述試験について
(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とし、受験している都道府県特有の魅力や特色を反映した質問も行う。
(2)合否判定
・合否判定は、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)
以上
ご参考になさってください。
?.試験全体について
(1)目的
・試験の目的は、「地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客誘致法」という。)第26条第1項)であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。
(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験は、地方自治法第2条第8項による自治事務として実施する。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとし、事業実施地域の制限のない通訳ガイドの登録を得るための試験(以下「通訳案内士試験」という。)と同一の問題を出題することとする。そのため、試験の実施日時については、外国語の筆記試験に関しては、通訳案内士試験の実施日時に合わせるものとする。ただし、外国語以外の筆記試験及び口述試験についてはこの限りではない。
・同一年度に実施される通訳案内士試験と、地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有することとする。
・同一年度に実施される複数の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有する。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事項であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、都道府県で出題のベースとなるテキストを作成し、そのテキストから出題することが望ましい。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・試験の実施回数は、年1回を原則とする。
(3)試験委員
・地域限定通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
・外国語の筆記試験に係る試験委員については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員全員を再任した上で、上記の業務を行わせるものとする。
(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局で構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準点の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・外国語の筆記試験に係る上記の合否判定事務については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員と同一の試験委員により、同一の基準で行う。
・通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、当該地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、すべての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。
(5)試験免除
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する他の外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・地域限定通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、他の都道府県知事が実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、他の都道府県知事が当該試験終了後、最初に実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。
(6)複数都道府県合同試験
・外客誘致法に基づく各「外客来訪促進地域」(いわゆる「国際観光テーマ地区」)を構成する都道府県については、合同で試験を実施することができる。
◆国際観光テーマ地区一覧(平成18年1月1日現在)
○北海道地区 「四季・感動・北海道」 (北海道)
○北東北地区 「発見!もう一つの日本・北緯40°の道」 (青森県、岩手県及び秋田県)
○南東北地区 「“あづま路”〜武家のロマン、日本のふるさと、自然と温泉との出会い〜」(宮城県、山形県、福島県及び栃木県)
○茨城・千葉県地区 「世界から一番近い日本の歴史と未来 〜NARITAからはじまる、日本の自然、歴史から先端技術までに触れる旅〜」 (茨城県及び千葉県)
○上信越地区 「日本の山岳・高原郷と佐渡島 〜美しい自然と温泉を楽しむ旅〜」 (群馬県、新潟県及び長野県)
○東京都地区 「千客万来の世界都市・東京をめざして」(東京都)
○富士箱根伊豆地区 「自然のワンダーランド・富士 −自然と都市、歴史と文化がもてなす日本の旅−」(神奈川県、山梨県及び静岡県)
○北陸地区 「山海神秘の楽園 〜四季彩の温泉回廊〜」 (富山県、石川県及び福井県)
○東海地区 「ハートランド街道 〜日本の匠と世界の産業技術〜」 (岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)
○関西地区 「大阪湾ベイアリアなぎさ街道&関西歴史街道 〜ユニークで多様な観光資源が光り輝く関西・旅の銀河〜」(三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県)
○大阪府地区 「観光立都・大阪 =ターゲットは東アジア」 (大阪府)
○東中四国地区 「日本の心に出会う旅 三海二山」(鳥取県、島根県、岡山県、香川県及び高知県)
○瀬戸内地区 「多島美と地域の伝統 〜海の碧、空の青に染まる一枚の絵」 (広島県、山口県及び愛媛県)
○九州地区 「日本に出会う九州 アジアの玄関、日本の原点(ルーツ)、自然と文化が交差する九州アイランド」(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)
○沖縄地区 「琉球王朝文化が息づく亜熱帯の楽園」 (沖縄県)
・複数の試験地で試験を行う場合は、同一の時間帯に同一の時間割により試験を行うこととする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、合同試験の場合であっても、都道府県ごとに当該都道府県の観光魅力を問う問題を作成し、個別に試験を行う。この場合、受験者が同一年度内に複数の都道府県の試験を受験できるように、都道府県ごとに時間をずらして実施する。
口述試験については、各都道府県が共通の試験委員を選定することで、各都道府県が共通で一度に試験を実施することができることとする。この場合は、合否の判定についても共通で行うこととする。
・口述試験では、通訳案内の実務に関して、受験している都道府県の観光魅力を反映した質問も行う。
・上記の合同試験で複数都道府県の試験に合格した場合であっても、地域限定通訳案内士の登録申請は、本人が登録を希望する個々の都道府県に対してそれぞれ行う。
(7)試験実施事務関連事項
・試験事務を代行させる場合、指定試験機関は、民法第34条に基づく公益法人であり、かつ、本ガイドラインに基づいて適正かつ確実に試験を実施できる体制の整っている団体でなければならない。
・試験事務を代行する指定試験機関は、受験者数と合格者数など試験の実施結果について、都道府県知事に報告しなければならない(外客誘致法第32条第1項)。
・国土交通大臣は、試験事務の適正かつ正確な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験の実施経過と実施結果について、都道府県知事に報告を求める(地方自治法第245条の4第1項)。
?.地域限定通訳案内士の試験実施に対する国土交通大臣の同意の基準について
(1)法定要件
・国土交通大臣の同意の要件は、外客誘致法第4条第3項第5号に規定されており、?「当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること」、?「当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること」、とされている。この要件を満たすかどうかの判断は、その趣旨を踏まえ、具体的には、以下に掲げる基準に基づき行うものとする。
(2)具体的基準
・当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人旅行者数に比し、通訳ガイドの数が不足していること、または今後の外国人旅行者数の増加に伴い、通訳ガイドの数の不足が見込まれること。
あるいは、当該都道府県における通訳ガイドの数自体は不足していないものの、これまでの需要動向等を背景に、その多くが実際に稼働しておらず、当該地域固有の観光魅力についてのより詳しい案内を受けたいという新たな外国人旅行者の需要に十分に応えられていないこと、また、それが、同行案内サービスを提供するボランティアガイドへのニーズの高まり等により、具体的な形で顕在化してきていること。
・試験事務の代行に関すること、試験問題の作成体制及び試験委員に関することが規定されていること。また、指定試験機関が、試験を適正かつ確実に実施できる体制にあること。
・通訳案内士試験と同一の外国語の筆記試験問題を出題することについて、通訳案内士試験の試験事務代行機関との間で共通の試験委員の選任や費用負担等に関する合意がなされていること。
・試験に関する地域問題のテキストを作成しているか、作成する意思があること、又は、テキストを作成する代わりに、試験問題作成のベースとなるような既存の文献等を指定することも可能とする。
・初年度の試験施行要領の案が本ガイドラインに基づき適切に策定されており、かつ、試験導入後当分の間は継続して試験を実施する計画があること。
・当該都道府県における地域限定通訳案内士及び通訳案内士の活動を支援するため、当該都道府県その他の者により、登録後のスキルアップ研修の実施、外国人旅行者とのマッチングシステムの整備、団体の組織化に向けた支援などのフォローアップが行われる見込みがあること。
(3)申請時期
・同意の申請は、通訳案内士試験の公告開始の少なくとも1ヶ月前までに申請するものとする。中断後に初めて実施しようとする場合も同様とする。
?.外国語(筆記試験)について
(1)試験方法
・外国語の筆記試験については、通訳案内士試験と同一の問題を出題することとする。
・外国語の種類は、国の試験で実施している英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語又はタイ語の10言語の中から、?.(2)により国土交通大臣の同意を受けた外客来訪促進計画において定められた言語について、試験を実施する。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。
?.地理について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.歴史について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.産業、経済、政治及び文化について
(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとする。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。
(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。
?.口述試験について
(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とし、受験している都道府県特有の魅力や特色を反映した質問も行う。
(2)合否判定
・合否判定は、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)
以上
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
通訳(英語) 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-