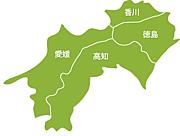◇仏像の伝来
仏教においては、仏像を造ることはとても功徳があると経典にも説かれ、造りやすいように、仏像の特徴を記した経典づくりも行われた。仏像は日本ばかりでなく、インドや中国、朝鮮、ビルマ、タイなどでも造られてきた。ガンダーラやマトゥラーは塑造や石造が多く、中国は石造が多い。これは日本のように木材が多く採れないから石や土の仏像が多い。
日本人が初めて仏像に出合ったのは6世紀頃、朝鮮から仏教が伝えられた時に一緒に運ばれてきた。仏像には、さまざまな種類がある。初めの釈迦像から如来像の種類が増えた。そして如来になる前段階の菩薩像が登場し、インドの在来宗教の神々を仏教に取り込んだ天部像や密教系の明王像、仏弟子や高僧像などが現れた。
◇仏像の製作方法
外来文化の影響やわが国の仏像製作技術の発達などによって、仏像の製作方法も変わった。飛鳥から奈良時代にかけ、国をあげて仏教を興隆させるために、外国から技術者を招いて仏像を造りました。銅像製作のためには、鋳造技術者を中国や朝鮮から招き、その時に塑造や乾漆造の技術も学ぶ。平安時代に入ると石像や木像がふえ、わが国の仏像製作技術も発達したが、定朝があらわれ寄木造りを完成してからは、製作時間が短縮され製作は一層容易になった。
◇仏像の材質
仏像の材料には木・石・土・金属、漆などがあり、仕上げにメッキ、金箔や彩色を施す。これらの材料は時代によって変化する。木・石は彫像、土は塑像、金属は鋳像にする。漆は併用することが多い。
[木彫仏像]
木目の見える木地を彫ったままの木地彫り仕上げの場合と、漆を塗ったり彩色を施したり、金箔を押したり表面を加工する仕上がある。時代が古い木彫仏像では、表面に塗った漆や彩色がはげ落ち、木目の見えていることが多く、木彫と判別できるが、木目が見えない場合でも、木彫は乾漆より彫りのするどいものが多い。木の種類は桧、榧、樟、柘植、白檀などが多い。造りは一木造りと、寄木造りがある。
[乾漆仏像]
漆を塗り固めて造る乾漆仏像は、脱乾漆と木心乾漆の2種類があり、天平年間に用いられた技法。
脱乾漆は、粘土の原型の上に麻布を漆で塗り固め、乾燥後に中の土を取り出して張子を造り、内部を補強して表面を仕上げる。木心乾漆は、木でおおよその原型を造った上に、麻布を漆で塗り固め表面を仕上げる。
[塑像]
粘土で造る塑像の技法は中国伝来のもので、奈良時代のものが多い。塑像の特徴は湿度の影響を受け、干割れがおきたり彩色がはげたりしやすい反面、きめ細かに仕上げる。
[鋳造仏像]
銅合金のものが圧倒的。銅は加工しやすく、入手が比較的容易で、鋳造仏像は、土で原型を造り、蝋を塗って細部を彫刻。そのまわりを土の外型で覆って焼くと蝋が溶けて空洞ができ、そこに溶かした金属を流し込む。型の中で金属が固まって外型をはずすと仏像が現れる。大仏はほとんど銅製で、奈良や鎌倉の大仏が代表的。また、法隆寺の釈迦三尊や薬師寺の薬師三尊も銅製で、多くは金メッキを施して金銅仏。
[石仏]
海外の仏像は、大石仏が多い。日本には巨岩がなく、石造文化が栄えなかった。それでも野仏はかなり造られてきましたが、石がもろかったり風化したりし、また露仏が多いので比較的保存も悪い。その場所にある石に直接彫刻する場合と、切り出した石を彫刻する場合がある。臼杵の石仏が代表的。
仏教においては、仏像を造ることはとても功徳があると経典にも説かれ、造りやすいように、仏像の特徴を記した経典づくりも行われた。仏像は日本ばかりでなく、インドや中国、朝鮮、ビルマ、タイなどでも造られてきた。ガンダーラやマトゥラーは塑造や石造が多く、中国は石造が多い。これは日本のように木材が多く採れないから石や土の仏像が多い。
日本人が初めて仏像に出合ったのは6世紀頃、朝鮮から仏教が伝えられた時に一緒に運ばれてきた。仏像には、さまざまな種類がある。初めの釈迦像から如来像の種類が増えた。そして如来になる前段階の菩薩像が登場し、インドの在来宗教の神々を仏教に取り込んだ天部像や密教系の明王像、仏弟子や高僧像などが現れた。
◇仏像の製作方法
外来文化の影響やわが国の仏像製作技術の発達などによって、仏像の製作方法も変わった。飛鳥から奈良時代にかけ、国をあげて仏教を興隆させるために、外国から技術者を招いて仏像を造りました。銅像製作のためには、鋳造技術者を中国や朝鮮から招き、その時に塑造や乾漆造の技術も学ぶ。平安時代に入ると石像や木像がふえ、わが国の仏像製作技術も発達したが、定朝があらわれ寄木造りを完成してからは、製作時間が短縮され製作は一層容易になった。
◇仏像の材質
仏像の材料には木・石・土・金属、漆などがあり、仕上げにメッキ、金箔や彩色を施す。これらの材料は時代によって変化する。木・石は彫像、土は塑像、金属は鋳像にする。漆は併用することが多い。
[木彫仏像]
木目の見える木地を彫ったままの木地彫り仕上げの場合と、漆を塗ったり彩色を施したり、金箔を押したり表面を加工する仕上がある。時代が古い木彫仏像では、表面に塗った漆や彩色がはげ落ち、木目の見えていることが多く、木彫と判別できるが、木目が見えない場合でも、木彫は乾漆より彫りのするどいものが多い。木の種類は桧、榧、樟、柘植、白檀などが多い。造りは一木造りと、寄木造りがある。
[乾漆仏像]
漆を塗り固めて造る乾漆仏像は、脱乾漆と木心乾漆の2種類があり、天平年間に用いられた技法。
脱乾漆は、粘土の原型の上に麻布を漆で塗り固め、乾燥後に中の土を取り出して張子を造り、内部を補強して表面を仕上げる。木心乾漆は、木でおおよその原型を造った上に、麻布を漆で塗り固め表面を仕上げる。
[塑像]
粘土で造る塑像の技法は中国伝来のもので、奈良時代のものが多い。塑像の特徴は湿度の影響を受け、干割れがおきたり彩色がはげたりしやすい反面、きめ細かに仕上げる。
[鋳造仏像]
銅合金のものが圧倒的。銅は加工しやすく、入手が比較的容易で、鋳造仏像は、土で原型を造り、蝋を塗って細部を彫刻。そのまわりを土の外型で覆って焼くと蝋が溶けて空洞ができ、そこに溶かした金属を流し込む。型の中で金属が固まって外型をはずすと仏像が現れる。大仏はほとんど銅製で、奈良や鎌倉の大仏が代表的。また、法隆寺の釈迦三尊や薬師寺の薬師三尊も銅製で、多くは金メッキを施して金銅仏。
[石仏]
海外の仏像は、大石仏が多い。日本には巨岩がなく、石造文化が栄えなかった。それでも野仏はかなり造られてきましたが、石がもろかったり風化したりし、また露仏が多いので比較的保存も悪い。その場所にある石に直接彫刻する場合と、切り出した石を彫刻する場合がある。臼杵の石仏が代表的。
|
|
|
|
|
|
|
|
遍路のおとも 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
遍路のおとものメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75493人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9044人