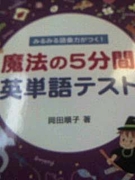|
|
|
|
コメント(22)
非常勤で私立高校勤務です。偏差値30−50程度の生徒が混在しています。
学校としての辞書に対するコンセンサスはなく、電子辞書をいわゆるアドバンストコースの生徒たちのみ持っている状態です。
また、学校指定のメーカーはないようです。
さて、
■予習で辞書を使い単語の意味を調べさせるかどうか
→していません。2年生英語Rのクラスでは巻末の単語リストで調べてノートに書くようには指導しています。
1年生ORCのクラスは基本、予習を課していません。
3年生英?も単語リストを渡して、それを利用して調べる、という感じでしょうか。
■電子辞書のメリット
・キーの並びがJIS配列なので、PC操作に慣れている生徒が大半の環境では、紙ベースの辞書よりもひくのが早い。
・アルファベットのオーダーを覚えていなくても引ける。
・軽い、携帯しやすい。
■デメリット
・「参考書」のようにして使うことができない。
・操作に不慣れな生徒もいる。
・辞書以外の機能を使い、授業中に遊んでしまう。
(私は見たことがないですが、TV付の機種があるようです)
今の勤務校では統一・・・はかなり厳しいものがあるのですが、紙ベースの辞書を統一すると、
「何ページを開いてください」
という言い方が出来るのがいいなぁ、とは思います。
私も辞書には非常に興味があるので、他の方のご意見も聞いてみたいです。
学校としての辞書に対するコンセンサスはなく、電子辞書をいわゆるアドバンストコースの生徒たちのみ持っている状態です。
また、学校指定のメーカーはないようです。
さて、
■予習で辞書を使い単語の意味を調べさせるかどうか
→していません。2年生英語Rのクラスでは巻末の単語リストで調べてノートに書くようには指導しています。
1年生ORCのクラスは基本、予習を課していません。
3年生英?も単語リストを渡して、それを利用して調べる、という感じでしょうか。
■電子辞書のメリット
・キーの並びがJIS配列なので、PC操作に慣れている生徒が大半の環境では、紙ベースの辞書よりもひくのが早い。
・アルファベットのオーダーを覚えていなくても引ける。
・軽い、携帯しやすい。
■デメリット
・「参考書」のようにして使うことができない。
・操作に不慣れな生徒もいる。
・辞書以外の機能を使い、授業中に遊んでしまう。
(私は見たことがないですが、TV付の機種があるようです)
今の勤務校では統一・・・はかなり厳しいものがあるのですが、紙ベースの辞書を統一すると、
「何ページを開いてください」
という言い方が出来るのがいいなぁ、とは思います。
私も辞書には非常に興味があるので、他の方のご意見も聞いてみたいです。
では、じゃんびーさんへのレスのひとつとして。
■ 辞書で単語調べの宿題をだすかどうか
私は、辞書で予習させるより、授業中に未知語をとりだして
例文、英語でのいいかえ、教員のジェスチャーなどで
意味の推測をさせています。
授業に時間がかかるのは、キツイのですが、ある方の研究では
推測のほうが、意味しらべより、4倍の定着度があったといいます。
辞書引きのスキルを高めるのが目的であるならば、
多義語の場合などは、
教科書と同じ意味のやさしい英文を教師が用意して、
その英文に適した意味を探させるのが最初はいいかなとおもっています。
■ うちは紙ベースの辞書を数冊推薦するだけです。電子辞書は推薦はして
いませんが生徒たちは持っているように思います。
紙ベースの辞書は重いので、持ち歩きをいやがるのですが、
むしろ、授業中の活動で使うことが多いので、ロッカーにいれたまま
辞書は授業で使えるように、という指示をしています。
電子辞書は持ち歩きしているみたいです。
今日は時間がないのでまたあとで書きますね。
みなさんもお時間があれば。
中学校では辞書はどう使っているのでしょうか?
■ 辞書で単語調べの宿題をだすかどうか
私は、辞書で予習させるより、授業中に未知語をとりだして
例文、英語でのいいかえ、教員のジェスチャーなどで
意味の推測をさせています。
授業に時間がかかるのは、キツイのですが、ある方の研究では
推測のほうが、意味しらべより、4倍の定着度があったといいます。
辞書引きのスキルを高めるのが目的であるならば、
多義語の場合などは、
教科書と同じ意味のやさしい英文を教師が用意して、
その英文に適した意味を探させるのが最初はいいかなとおもっています。
■ うちは紙ベースの辞書を数冊推薦するだけです。電子辞書は推薦はして
いませんが生徒たちは持っているように思います。
紙ベースの辞書は重いので、持ち歩きをいやがるのですが、
むしろ、授業中の活動で使うことが多いので、ロッカーにいれたまま
辞書は授業で使えるように、という指示をしています。
電子辞書は持ち歩きしているみたいです。
今日は時間がないのでまたあとで書きますね。
みなさんもお時間があれば。
中学校では辞書はどう使っているのでしょうか?
ELEC同友会の語彙指導研究部会の発表で「辞書でボキャビル」をテーマにした発表をしました。
最初にやっていただいたものは「2文字しりとり」。
ふつうのしりとりは最後のひと文字をしりとりしていくのですが、
write の最後の2文字 te をしりとりする、というものです。
ただし、これだとあまりにもむずかしいので、te とet は逆になってもよいことにします。
write-teacher-error-root-tool-loop-open などのようになります。
生徒にやらせるときは、生徒は語彙数が少ないので辞書をつかわなければできません。
制限時間10分でペアで競争してやる活動ですが、制限時間のなかでたくさんしりとりをする際に、生徒の辞書早引きのスキルを狙っている効果があります。
楽しい活動ですので、みなさんもどうぞ。
最初にやっていただいたものは「2文字しりとり」。
ふつうのしりとりは最後のひと文字をしりとりしていくのですが、
write の最後の2文字 te をしりとりする、というものです。
ただし、これだとあまりにもむずかしいので、te とet は逆になってもよいことにします。
write-teacher-error-root-tool-loop-open などのようになります。
生徒にやらせるときは、生徒は語彙数が少ないので辞書をつかわなければできません。
制限時間10分でペアで競争してやる活動ですが、制限時間のなかでたくさんしりとりをする際に、生徒の辞書早引きのスキルを狙っている効果があります。
楽しい活動ですので、みなさんもどうぞ。
二文字しりとりの後に「聴いて推測」という活動を発表しました。
教科書の新出語を( )にしておき、先生が教科書本文を読み、その発音を
もとに、つづりを推測します。たとえば、「サイエンス」と先生が読んだら
生徒はできるだけ、その音をもとにスペリングを推測します。
ふつう「s en se]くらいは分かるのですが、グループでおしえあうと
「sienc/se]くらいに改善します。
その後、教科書の巻末リストで推測したつづりから、単語のただしいスペリングを回答させる、という活動です。
先生が発音した語のスペリングを推測すると、音とつづりの関係性を学ぶことに
効果があり、単語が書ける生徒を育てるのに役立ちます。
教科書の新出語を( )にしておき、先生が教科書本文を読み、その発音を
もとに、つづりを推測します。たとえば、「サイエンス」と先生が読んだら
生徒はできるだけ、その音をもとにスペリングを推測します。
ふつう「s en se]くらいは分かるのですが、グループでおしえあうと
「sienc/se]くらいに改善します。
その後、教科書の巻末リストで推測したつづりから、単語のただしいスペリングを回答させる、という活動です。
先生が発音した語のスペリングを推測すると、音とつづりの関係性を学ぶことに
効果があり、単語が書ける生徒を育てるのに役立ちます。
>13のあとに、
「辞書で自作クローズテスト」という活動をかなり念入りに先生方に体験していただきました。
高校生は、比較的、学校でいくつかの辞書を推薦し、生徒はその中から自分のすきなものを買っているようです。
したがって、違う辞書を生徒が持っている、ということが前提になったタスクです。
教科書のあるレッスンの新出語の定着活動です。
以下が、新出語です。新出語を選ぶ際は、生徒が持っている代表的な辞書を先生方にあらかじめごらんいただき、例文の載っている単語を選びます。
(例)
remind, confident, ability, succeed, opposite
Step 1 違う辞書を持っている生徒同士でペアを組みます。
Step 2 上記の単語を辞書ですべて引いて、辞書の例文を書き出します。
例文はたいてい複数あるので、一番簡単な例文を選ばせます。
Aさんの辞書の例文 (使用辞書 Grand Century, 第2版、三省堂)
You remind me of your father.
She is confident of winning the game.
Cats have the ability to see in the dark.
My brother succeeded in his entrance examination.
Black is opposite to white.
Bさんの辞書の例文 (使用辞書 Genius, 第4版、大修館)
I reminded him of our party tonight.
I am confident of their victory.
She has an unusual ability in music.
He will succeed as a doctor.
We are sitting opposite to each other on the train.
Step 3 新出語の部分を( )に変えて、クローズテストを作成
します。そのままの順番にならないよう、適当に並べ替えます。( )にした単語を選択肢として、問題のしたに書きます。
Aさんが作ったテスト
1 My brother ( ) in his entrance examination.
2 Black is ( )to white.
3 She is ( ) of winning the game.
4 Cats have the ( ) to see in the dark.
5 You ( ) me of your father.
opposite, remind, ability, confident, succeeded
Bさんが作ったテスト
1. We are sitting ( ) to each other on the train.
2.I am ( ) of their victory.
3. I ( ) him of our party tonight.
4. She has an unusual ( ) in music.
5. He will ( ) as a doctor.
confident, abilities, succeed, opposite, remind
Step 4 クローズテストをペアで交換します。
Step 5 パートナーが作ったクローズテストに答えます。
Step 6 パートナーにもどして、採点します。
この活動の効果は、たとえば生徒は「remind]という単語を教科書の文脈でみますが、辞書の例文という違う文脈をみると、またremindという単語に対する
イメージが膨らみます。そのことが語彙の定着を促進します。
また、このタスクでは、ペアの相手の例文もみるので、2回違う文脈の中で
同じ単語について、イメージを膨らませることが可能です。
ということで、非常に定着度の高い活動といえましょう。
「辞書で自作クローズテスト」という活動をかなり念入りに先生方に体験していただきました。
高校生は、比較的、学校でいくつかの辞書を推薦し、生徒はその中から自分のすきなものを買っているようです。
したがって、違う辞書を生徒が持っている、ということが前提になったタスクです。
教科書のあるレッスンの新出語の定着活動です。
以下が、新出語です。新出語を選ぶ際は、生徒が持っている代表的な辞書を先生方にあらかじめごらんいただき、例文の載っている単語を選びます。
(例)
remind, confident, ability, succeed, opposite
Step 1 違う辞書を持っている生徒同士でペアを組みます。
Step 2 上記の単語を辞書ですべて引いて、辞書の例文を書き出します。
例文はたいてい複数あるので、一番簡単な例文を選ばせます。
Aさんの辞書の例文 (使用辞書 Grand Century, 第2版、三省堂)
You remind me of your father.
She is confident of winning the game.
Cats have the ability to see in the dark.
My brother succeeded in his entrance examination.
Black is opposite to white.
Bさんの辞書の例文 (使用辞書 Genius, 第4版、大修館)
I reminded him of our party tonight.
I am confident of their victory.
She has an unusual ability in music.
He will succeed as a doctor.
We are sitting opposite to each other on the train.
Step 3 新出語の部分を( )に変えて、クローズテストを作成
します。そのままの順番にならないよう、適当に並べ替えます。( )にした単語を選択肢として、問題のしたに書きます。
Aさんが作ったテスト
1 My brother ( ) in his entrance examination.
2 Black is ( )to white.
3 She is ( ) of winning the game.
4 Cats have the ( ) to see in the dark.
5 You ( ) me of your father.
opposite, remind, ability, confident, succeeded
Bさんが作ったテスト
1. We are sitting ( ) to each other on the train.
2.I am ( ) of their victory.
3. I ( ) him of our party tonight.
4. She has an unusual ( ) in music.
5. He will ( ) as a doctor.
confident, abilities, succeed, opposite, remind
Step 4 クローズテストをペアで交換します。
Step 5 パートナーが作ったクローズテストに答えます。
Step 6 パートナーにもどして、採点します。
この活動の効果は、たとえば生徒は「remind]という単語を教科書の文脈でみますが、辞書の例文という違う文脈をみると、またremindという単語に対する
イメージが膨らみます。そのことが語彙の定着を促進します。
また、このタスクでは、ペアの相手の例文もみるので、2回違う文脈の中で
同じ単語について、イメージを膨らませることが可能です。
ということで、非常に定着度の高い活動といえましょう。
>14のあとに「辞書の例文を変えよう」という活動を先生方にやっていただきました。
教科書のあるレッスンの新出語の定着活動です。
覚えさせたい新出語を4〜5つ程度選びます。以下が新出語です。
criticize, terrible, attitude, opportunity
先生が、辞書の例文を調べ、以下のような雛形を作ります。
新出語 criticize, terrible, attitude, opportunity
( 人 ) was criticized for ( 〜ing ).
( 人 ) is terrible at ( ものごと ).
( 人 ) has positive attitude toward ( ものごと ).
( 人 ) don’t have much opportunity for (of) (ものごと).
実際の授業ではペアで、一緒に、( )に入る単語を考え、できるだけ
たくさん英作文をします。動詞は、自由に活用してもいいことにします。
ペアでたくさん例文を考えるには、ペアがいろいろな情報を共有していないとできないので、
大会発表では先生方につぎのようなやり方でやっていただきました。
Step 3 先生方ご自身のことで主語をI とし、この雛形の例文を使って自己
表現の文をそれぞれ1文ずつお書きください。
Step 4 ペアの相手の方の例文を読みあい、独断と偏見でペアの方の
性格が一番よく表れていると思う一文をお選びください。
で、このようなやりとりをお願いします。
「あなたは、勤勉な方ですね。なぜならあなたは
I have positive attitude toward my work.と書いていらっしゃる
からです」
この活動の効果ですが、まず、辞書の例文を使って自分のこと、周りのことなどの自己表現をすると自己関与効果が働き、語彙の定着を促進します。
また、先生方にやっていただいた方法では、まず、自己表現のためのライテイングをし、ペアの方の例文を読み、「あなたは勤勉な方ですね、なぜなら〜」以下の文を話し、ペアの相手はそれを聞く、ということで、4技能すべて使うと語彙の定着は促進されます。
教科書のあるレッスンの新出語の定着活動です。
覚えさせたい新出語を4〜5つ程度選びます。以下が新出語です。
criticize, terrible, attitude, opportunity
先生が、辞書の例文を調べ、以下のような雛形を作ります。
新出語 criticize, terrible, attitude, opportunity
( 人 ) was criticized for ( 〜ing ).
( 人 ) is terrible at ( ものごと ).
( 人 ) has positive attitude toward ( ものごと ).
( 人 ) don’t have much opportunity for (of) (ものごと).
実際の授業ではペアで、一緒に、( )に入る単語を考え、できるだけ
たくさん英作文をします。動詞は、自由に活用してもいいことにします。
ペアでたくさん例文を考えるには、ペアがいろいろな情報を共有していないとできないので、
大会発表では先生方につぎのようなやり方でやっていただきました。
Step 3 先生方ご自身のことで主語をI とし、この雛形の例文を使って自己
表現の文をそれぞれ1文ずつお書きください。
Step 4 ペアの相手の方の例文を読みあい、独断と偏見でペアの方の
性格が一番よく表れていると思う一文をお選びください。
で、このようなやりとりをお願いします。
「あなたは、勤勉な方ですね。なぜならあなたは
I have positive attitude toward my work.と書いていらっしゃる
からです」
この活動の効果ですが、まず、辞書の例文を使って自分のこと、周りのことなどの自己表現をすると自己関与効果が働き、語彙の定着を促進します。
また、先生方にやっていただいた方法では、まず、自己表現のためのライテイングをし、ペアの方の例文を読み、「あなたは勤勉な方ですね、なぜなら〜」以下の文を話し、ペアの相手はそれを聞く、ということで、4技能すべて使うと語彙の定着は促進されます。
>15の後に軽く
「コロケーションビンゴ」を説明しましたが、そちらは省略します。
つぎに「共通点は何だ」という活動をやっていただきました。
既習語、未知語にかかわらず、グループごとに単語を辞書で引いて、
その共通点を探す活動です。
Step 1共通点を見つけ出す観点を先生が黒板に書いておきます。
以下のようになります。
「発音・アクセント・品詞・シラブル数」
Step 2 以下の6つのGroup 内の単語を辞書を引かせ、group 内の単語の共通点を探させます。
Group 1 tear, last, bear, land, spring, light, store
Group 2 interrupt, everybody, recognition, generation, environment
Group 3 excellent, curious, dictionary, factory, horrible, stationary
Group 4 conduct, increase, progress, record, reject, import, present
Group 5 comb, psychology, cupboard, rhythm, foreign, bomb
Group 6 intermediate, recommendation, vocabulary, interpretation,
international,
みなさんも謎解きしてみてください。
「コロケーションビンゴ」を説明しましたが、そちらは省略します。
つぎに「共通点は何だ」という活動をやっていただきました。
既習語、未知語にかかわらず、グループごとに単語を辞書で引いて、
その共通点を探す活動です。
Step 1共通点を見つけ出す観点を先生が黒板に書いておきます。
以下のようになります。
「発音・アクセント・品詞・シラブル数」
Step 2 以下の6つのGroup 内の単語を辞書を引かせ、group 内の単語の共通点を探させます。
Group 1 tear, last, bear, land, spring, light, store
Group 2 interrupt, everybody, recognition, generation, environment
Group 3 excellent, curious, dictionary, factory, horrible, stationary
Group 4 conduct, increase, progress, record, reject, import, present
Group 5 comb, psychology, cupboard, rhythm, foreign, bomb
Group 6 intermediate, recommendation, vocabulary, interpretation,
international,
みなさんも謎解きしてみてください。
(高校)ヤントです。
>予習で辞書をひかせて単語の意味調べをさせたりなさいますか?
させます。しかし、教科書のサボがあり、それを見て写してあたかも引いてきたような生徒がたくさんいます。ですから、意味が2〜3あるものは教科書の単語の意味以外の意味をわざと聞いたりして、辞書をしっかり引いてきたか確かめます。
>学校で統一の辞書ですか?
統一させています。しかし、教師によって辞書の使用頻度が違います。
私は、授業中に辞書の「何ページを開いて!」とか指示しますので統一させています。
メリットとしては、全員が同じ感覚で辞書から語彙・用法を習得できる。
デメリットとしては、他に既に辞書を持っている(兄弟のものを使うなど)生徒には、お金の無駄みたいなものがあります。
めちゃくちゃ昔からの訳読法をなさっている大先輩の教員がおられますが、辞書の活用はベテランです。接頭辞・接尾辞や、語源にまつわる話を上手く盛り込まれるので生徒は最初のうち辞書を引くのを嫌がりますが、どんどんと辞書を使うようになっていきます。「この単語は、だれだれの何という本にも出ている」ってなことまで言及されます。
私の実力ではここまでは出来ません。しかし、辞書引き指導は、授業時間内に必ず最低2〜3回はさせます。
>電子辞書は、どのように扱いますか
安くなったとはいえ、まだ電子辞書は統一してもたせていません。
しかし、圧倒的に生徒は持っています。ただ、使い方が悪い生徒が多いのをよく見かけます。見出し語だけで終わるとか。。。用法を見てどういうときに使うのかを知ってほしいです。
私自身、CASIOの英語専用プロモデルを持っていますが、使い勝手が悪いです。用例が良くない。ただ、多義語やジャンプ機能は便利です。
これは英語の達人セミナー(谷口教諭主催)で効果があると聞いていますが、LONGMANと英英辞典が入っているものが効果的だと考えています。OXFORDのはいまいち第二言語習得者にとって良いのかなぁ〜と疑問を持っております。
とにかく高校2年後半ぐらいから、英英辞典を使わせたい。状況に応じた単語を使うためには良いと思っているからです。
あと、大西泰斗先生のネイティヴスピーカーの単語力のような、単語のイメージが分かるものが辞書に盛り込まれていたら良いと思いますし、これはおかじゅんさんがおっしゃっている単語のイメージがわく物が盛り込まれていると共通します。
>予習で辞書をひかせて単語の意味調べをさせたりなさいますか?
させます。しかし、教科書のサボがあり、それを見て写してあたかも引いてきたような生徒がたくさんいます。ですから、意味が2〜3あるものは教科書の単語の意味以外の意味をわざと聞いたりして、辞書をしっかり引いてきたか確かめます。
>学校で統一の辞書ですか?
統一させています。しかし、教師によって辞書の使用頻度が違います。
私は、授業中に辞書の「何ページを開いて!」とか指示しますので統一させています。
メリットとしては、全員が同じ感覚で辞書から語彙・用法を習得できる。
デメリットとしては、他に既に辞書を持っている(兄弟のものを使うなど)生徒には、お金の無駄みたいなものがあります。
めちゃくちゃ昔からの訳読法をなさっている大先輩の教員がおられますが、辞書の活用はベテランです。接頭辞・接尾辞や、語源にまつわる話を上手く盛り込まれるので生徒は最初のうち辞書を引くのを嫌がりますが、どんどんと辞書を使うようになっていきます。「この単語は、だれだれの何という本にも出ている」ってなことまで言及されます。
私の実力ではここまでは出来ません。しかし、辞書引き指導は、授業時間内に必ず最低2〜3回はさせます。
>電子辞書は、どのように扱いますか
安くなったとはいえ、まだ電子辞書は統一してもたせていません。
しかし、圧倒的に生徒は持っています。ただ、使い方が悪い生徒が多いのをよく見かけます。見出し語だけで終わるとか。。。用法を見てどういうときに使うのかを知ってほしいです。
私自身、CASIOの英語専用プロモデルを持っていますが、使い勝手が悪いです。用例が良くない。ただ、多義語やジャンプ機能は便利です。
これは英語の達人セミナー(谷口教諭主催)で効果があると聞いていますが、LONGMANと英英辞典が入っているものが効果的だと考えています。OXFORDのはいまいち第二言語習得者にとって良いのかなぁ〜と疑問を持っております。
とにかく高校2年後半ぐらいから、英英辞典を使わせたい。状況に応じた単語を使うためには良いと思っているからです。
あと、大西泰斗先生のネイティヴスピーカーの単語力のような、単語のイメージが分かるものが辞書に盛り込まれていたら良いと思いますし、これはおかじゅんさんがおっしゃっている単語のイメージがわく物が盛り込まれていると共通します。
>18のヤントさん、遅くなりましたがレスさせていただきます。
1.私は、辞書は家に持ち帰らせないんですよ。というのは
ひとつには、新出単語の導入法として、辞書調べというのは
定着が高くないからです。
もうひとつめは、家に持ち帰らせると教室で辞書活動を行うときに
足並みがそろわないからです。
同友会で、発表した活動は、クラス全員が授業で辞書を持っているという
ことが前提になっています。
2.学校全体で統一辞書採択というのは、ヤントさんのおっしゃるメリット
どおりだと思います。デメリットは、他の友達が持っている辞書の情報
をシェアできないこともあるかと思います。
3.電子辞書について、生徒の使い方がよくない、と言う点について、もう少し
補足していただけますでしょうか?
逆引き、などの機能は使いようで、面白いこともできると思うのですが。
4.英英辞書を使えるレベルの生徒さんなら、英英辞書多いによいかと思い
ます。でも、「状況に応じた単語を使う」のであれば、英英辞書より
教科書の文脈や、わかりやすい英和辞書の文脈をつかって
「こういうときにつかうんだな」と考えさせるほうが生徒には
わかりやすいのではないでしょうか?
あとは、多読ですね。
あと、トピずれですみませんが、私たちは、英語を「第二言語」として学んでいるわけではないので、「第二言語習得理論」に基づく議論を私たちに当てはめるのはいかがなものかと思います。私達は「第二言語習得者」ではないからです。
私はもともとは「第二言語習得理論」の一部である「語彙習得理論」は、「外国語学習理論」という角度から、捕らえなおすべきだと思っていますし、
「外国語学習」のひとつとしての「語彙活動」「辞書指導」であるべきだと思います。
1.私は、辞書は家に持ち帰らせないんですよ。というのは
ひとつには、新出単語の導入法として、辞書調べというのは
定着が高くないからです。
もうひとつめは、家に持ち帰らせると教室で辞書活動を行うときに
足並みがそろわないからです。
同友会で、発表した活動は、クラス全員が授業で辞書を持っているという
ことが前提になっています。
2.学校全体で統一辞書採択というのは、ヤントさんのおっしゃるメリット
どおりだと思います。デメリットは、他の友達が持っている辞書の情報
をシェアできないこともあるかと思います。
3.電子辞書について、生徒の使い方がよくない、と言う点について、もう少し
補足していただけますでしょうか?
逆引き、などの機能は使いようで、面白いこともできると思うのですが。
4.英英辞書を使えるレベルの生徒さんなら、英英辞書多いによいかと思い
ます。でも、「状況に応じた単語を使う」のであれば、英英辞書より
教科書の文脈や、わかりやすい英和辞書の文脈をつかって
「こういうときにつかうんだな」と考えさせるほうが生徒には
わかりやすいのではないでしょうか?
あとは、多読ですね。
あと、トピずれですみませんが、私たちは、英語を「第二言語」として学んでいるわけではないので、「第二言語習得理論」に基づく議論を私たちに当てはめるのはいかがなものかと思います。私達は「第二言語習得者」ではないからです。
私はもともとは「第二言語習得理論」の一部である「語彙習得理論」は、「外国語学習理論」という角度から、捕らえなおすべきだと思っていますし、
「外国語学習」のひとつとしての「語彙活動」「辞書指導」であるべきだと思います。
>おかじゅんさんへ
「電子辞書の使い方が悪い生徒が多いのをよく見かけます。」と私がコメントしたのは、おかじゅんさんのおっしゃるように逆引きやその他、ジャンプ機能、同義語検索など様々な電子辞書の良い点を生徒が使い切れていないということです。もっと簡単に言うと、生徒が操作方法を知っていないという事です。或いは知っていても使わないという事もあります。ただこれだけは指導してやったら済むことなんですが・・・。
(機種によっても違いますし・・・。)
私は、これほどまでに普及している電子辞書を効果的に使う事を英語科内で意見しましたが、皆に持たせるのは、まだコストがかかるなどなどの理由で却下されました。。。
追記)第二言語学習者の言葉を間違えてしまいました。申し訳ありません。おかじゅんさのおっしゃる通りでございます。
「電子辞書の使い方が悪い生徒が多いのをよく見かけます。」と私がコメントしたのは、おかじゅんさんのおっしゃるように逆引きやその他、ジャンプ機能、同義語検索など様々な電子辞書の良い点を生徒が使い切れていないということです。もっと簡単に言うと、生徒が操作方法を知っていないという事です。或いは知っていても使わないという事もあります。ただこれだけは指導してやったら済むことなんですが・・・。
(機種によっても違いますし・・・。)
私は、これほどまでに普及している電子辞書を効果的に使う事を英語科内で意見しましたが、皆に持たせるのは、まだコストがかかるなどなどの理由で却下されました。。。
追記)第二言語学習者の言葉を間違えてしまいました。申し訳ありません。おかじゅんさのおっしゃる通りでございます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
語彙習得理論と語彙指導 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
語彙習得理論と語彙指導のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8448人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208285人