Q 予防対策は
新型インフルエンザ感染拡大を阻止するには、国民一人ひとりの備えが大切だ。未知の感染症の危険性を十分理解し、家庭や職場で必要な対策を実行することが求められる。厚労省は、個人の予防対策として、〈1〉不要不急の外出を控え、不特定多数が集まる場所を避ける〈2〉水やせっけんによる手洗いに加え、消毒用アルコールを使用し、ウイルスに触った手で口や目、鼻に触れない――などが効果的としている。
ウイルスは、患者の咳、くしゃみ、つばの飛沫によって感染する。患者がウイルスをまき散らさないことが重要だ。そのため厚労省は今年9月、口と鼻を覆い、飛沫を捕捉できる目の細かなマスクの着用を求めた。ガーゼマスクよりも、繊維や糸を織らずに加工した「不織布マスク」が効果が高いと推奨している。
流行の第1波は、8週間ほど続くと見込まれる。その間、やむを得ない外出用や発症した場合に備えて1人あたり20〜25枚のマスクを用意するのが適当とする。
社会・経済活動の維持のため各企業の対策も不可欠だ。身内の家族が発症した場合、従業員が看病のために欠勤する状況も考えられる。このため厚労省は、各企業に事業継続計画の立案を求めている。具体的には、一部の従業員が感染しても職場が一斉にストップしないようシフト勤務の導入などを要請している。
同省の試算によると、国内で大流行すると、1日当たりの入院患者数は10万人を超し、欠勤率は10日間で最大40%に及ぶ。銀行の現金自動預け払い機(ATM)が一時的に使えなくなったり、ガソリンが供給停止に陥ったりするなど、社会機能が軒並みストップする事態も懸念されている。そのため、厚労省は、最低2週間分の食糧備蓄を提案し、ホームページ(http://
(2008年11月28日 読売新聞)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
基礎からわかる新型インフルエンザ
Q ワクチンは効く?
事前接種の効果 臨床試験中
新型インフルエンザの感染予防と治療の柱は、抗ウイルス薬とワクチンだ。
厚労省は今年6月、それまでの約2900万人分の薬を備蓄する計画を、国民の45%にあたる約5500万人分の備蓄に増強する方針を打ち出した。ワクチンも、鳥インフルエンザウイルス「H5N1型」をもとにして作った「大流行前(プレパンデミック)ワクチン」と、新型インフルエンザの発生後に作る「大流行ワクチン」の2段階で構える。
3000万人分の確保を目指す、大流行前ワクチンの有効性と安全性を検証するため、今年8月から感染の可能性が高い医師や検疫所の職員ら6400人を対象に臨床試験を始めた。世界に先駆ける試みで、国は有効性が確認されれば、対象者を拡大させる方針だ。
ただし、事前接種には反対する声も根強い。鳥のウイルスをもとに作ったワクチンが、新型ウイルスに効果があるのかどうかは、実際に発生してみるまで分からないからだ。新型インフルエンザがH5N1型からの変異でなければ、まったく効果がない可能性もある。
一方、大流行ワクチンは、実際に発生したウイルスを使って生産する。そのため、現在の生産体制だと全国民分を作るのに発生から1年半かかると見込まれる。国は製造期間の短縮に乗り出したが、その間は大流行前ワクチンと抗ウイルス薬に頼らざるを得ない。
ワクチン接種は基本的に無料になるが、国は今年9月、優先的に接種する対象職種の原案を公表した。社会機能を維持するために重要な97職種(最大1500万人)を優先度順に1〜3の3群に分け、医師や救急隊員、警察官などを最優先職種に指定した。
ワクチン接種者を増やすと、まひなどの重い副作用が発生する確率は100万分の1程度あり、「発生前の段階で接種するには、リスクの方が大きすぎる」と指摘する専門家は少なくない。内閣官房は「予防効果と副作用の発生率などを十分に見極めたうえで、慎重に接種対象を検討したい」と話している。
(2008年11月28日 読売新聞)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
基礎からわかる新型インフルエンザ
Q 次の「新型」は?
検疫・医療対策 国計画に地方は出遅れ
新型インフルエンザは、10〜40年周期で発生する未知の感染症だ。人類が免疫を持たないため、感染すると肺炎などで重症化し、死亡する可能性が高い。多くの人が免疫を獲得することで終息する。
新型インフルエンザ出現の切迫性が高まっているのは、発生の鍵を握る高病原性の鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が、養鶏場と住居が近接する東南アジア、中国などで流行し、多くの犠牲者を出しているからだ。
世界保健機関(WHO)によると、2003年11月以降、世界15か国で387人が感染し、うち245人が死亡。今年だけでも、9月までに感染者36人のうち28人が犠牲になるなど、死亡率は悪化する傾向にある。新型インフルエンザは、この鳥インフルエンザウイルスが変異し、人から人への強い感染力を獲得した時に発生する可能性が高いと考えられている。
鳥インフルエンザが人間から人間へ感染した例は、インドネシア、中国などで患者に頻繁に接触した近親者間などに限られており、新型インフルエンザウイルスへの変異は確認されていない。しかし、国内でもH5N1型ウイルスに感染した鳥が見つかっており、国内で新型インフルエンザが発生する可能性もゼロではない。
人類は、20世紀に入って数回の新型インフルエンザを経験した。最大の被害をもたらしたのが「スペインかぜ」(1918年)。世界中で約4000万人が死亡し、国内だけでも約39万人が犠牲になった。「香港かぜ」(1968年)も世界で約100万人が死亡した。
では、冬になると患者が増える季節性のインフルエンザとどこが違うのか。実は、大きな違いはない。流行を繰り返す「Aソ連(H1N1型)」「A香港(H3N2型)」の原因ウイルスは、それぞれ「スペインかぜ」「香港かぜ」を引き起こしたウイルスの残党だ。インフルエンザで38度以上の発熱や頭痛などの症状に襲われるが、多くの人は抵抗力を持っているので重症化することは少ない。犠牲になるのは免疫がない小児や免疫力が低い高齢者、慢性病患者に集中する。
厚生労働省は、スペインかぜの致死率2%などをもとに、新型インフルエンザが国内で発生した時、最悪2500万人が病院を受診し、64万人が死亡すると推計するが、その試算が甘いとの指摘もある。飛行機などの交通網の発達、都市部への人口集中など世界のどこかで新型インフルエンザが発生しても短期間で感染が広がる可能性がある。
新型インフルエンザの流行に備え、2005年に政府は「新型インフルエンザ対策行動計画」(約100ページ)を策定し、検疫の強化や医薬品の備蓄・投与など、海外での発生、国内での大流行など段階ごとに国、都道府県など自治体が取るべき対応を公表した。
基本方針は、〈1〉海外で発生した場合、国内への流入をできる限り阻止し、発生しても特定地域で封じ込める〈2〉大流行時は、感染拡大を抑える――の2点。国民の健康被害を防ぐ一方で、社会・経済機能の維持を目指す。具体的な施策は、分野別の指針(ガイドライン)に盛り込んだ。
たとえば、「検疫指針」では、新型インフルエンザが海外で発生した場合、発生国から入国可能な空港・港湾を制限し、検疫を強化する。航空会社には直行便の運航自粛を要請する一方、政府専用機や自衛隊機で在外邦人を帰国させ、感染の疑いがある入国者を、空港周辺の宿泊施設に停留させて感染の有無を確認する。
「医療体制」などの指針では、国内で流行した場合、予防・治療のため抗ウイルス薬の投与やワクチンの接種を行い、患者が診察する外来専用の窓口(発熱外来)を設置するとした。病院の収容能力を超えた場合は宿泊施設を使って診療させる。
行動計画や指針は、必要に応じて見直しを重ねる。検疫に関連し、政府は今年11月に、中国、韓国と新型インフルエンザ対策を連携することで合意。感染を最小限に抑えるため、3国のいずれかで患者が発生しても、感染が確定する前から情報交換するが、こうしたことも行動計画などに加えられる。
指針の改定案の中で注目されるのは〈1〉都道府県で患者が1人でも発生した際、その都道府県内の学校を一斉に休校させる〈2〉医療機関が容体を十分に把握している慢性病患者に限り、電話診療やファクスでの処方せん送付を認める――などだ。
こうした対策を実践するため、政府は来年度予算で今年度の8倍にあたる686億円を計上する方針だ。
しかし、流行時に最前線となる自治体の体制整備は遅れている。厳しい財政状況の下、都道府県が半分負担する抗ウイルス薬の備蓄費の確保は難しく、発熱外来設置の準備も遅れている。神田真秋・愛知県知事は、「国からの財政措置なしに、十分な医療や住民支援体制を準備することは難しい」と訴える。専門家からは、市町村の財政力によって治療や生活支援に差が出る可能性を指摘する声も出ている。
(2008年11月28日 読売新聞)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
基礎からわかる新型インフルエンザ
「鳥」から変異 濃厚…国内最悪で64万人死亡
新型インフルエンザの発生が懸念されている。いったん流行すれば多数の国民が犠牲になり、社会・経済活動の停滞や混乱も予想される。国は備蓄する抗ウイルス薬やワクチンなどを中心に感染拡大を抑えようとしているが、地方自治体の患者受け入れ体制、封じ込め策は不十分と指摘される。対策の現状と、個人でどんな備えができるかを探った。
◇
科学部・本間雅江、高田真之が担当しました。
(2008年11月28日 読売新聞)
|
|
|
|
|
|
|
|
「新型インフルエンザ」情報 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
「新型インフルエンザ」情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75493人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9044人
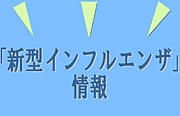











![[dir] 新型インフルエンザ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/0/83/4270083_15s.jpg)











