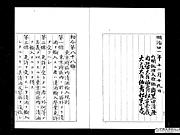昭和47法14で改正
「第五節 住宅貯蓄控除」を「第五節 住宅控除」に改める。
第二章第五節中第四十一条の二の前に次の一款及び款名を加える。
第一款 住宅取得控除
(住宅取得控除)
第四十一条 居住者が、昭和四十七年一月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、その者の住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得(贈与によるものを除く。)して、これらの家屋をその工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合には、その居住の用に供した日の属する年以後三年間の各年分(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年分に限る。)の所得税の額から、これらの家屋の標準取得価額として政令で定める金額に百分の一を乗じて計算した金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、大蔵省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、建築基準法第六条第三項の規定による通知書の写しその他の書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 住宅貯蓄控除
第四十一条の二中「この節」を「この款」に改め、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅貯蓄契約には、第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約で次に掲げる要件を満たすものを含むものとする。
一 前項第一号、第二号、第五号及び第七号に掲げる要件
二 住宅の用に供する家屋又はその敷地を当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体から取得し、当該家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍に相当する金額をこえる場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)を当該支払者又は事業主団体に対し前項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。
三 当該契約が金銭の積立て、預入若しくは信託に関するものである場合には、その積立て、預入若しくは信託の日から頭金の支払をする日までの間その払出しをしないこと又は当該契約が政令で定める有価証券の購入に関するものである場合には、その購入の日から頭金の支払をする日までの間金融機関若しくは第四条の二第一項に規定する証券業者に保管の委託をし、若しくは登録をするものであること。
第四十一条の三第一項中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項」を「第四十一条の二第四項」に改める。
第四十一条の四第一項中「この節」を「この款」に改める。
第四十一条の五第一項中「貯蓄取扱機関」の下に「(第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約にあつては、当該契約を締結した同項第二号に規定する勤労者に係る賃金の支払者。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」を、「第四十一条の二第一項各号」の下に「又は第二項各号」を加える。
ーーーーーーーーーー
昭和48法16で改正
第四十一条第一項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の二第一項第二号中「返済」の下に「又は賦払」を加え、同項第三号中「返済」の下に「又は賦払」を、「以上の金額」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第二項第二号を次のように改める。
二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者若しくは当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から前項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払うか、又は当該家屋若しくはその敷地を支払者等から取得する場合には、当該支払者等に対し同号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。
第四十一条の三第一項中「基づいて積立て等」の下に「(その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる積立て等に限る。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、「それぞれその年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該住宅貯蓄契約が第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の六に相当する金額(その金額が三万円をこえる場合には、三万円)
二 前号に掲げる場合以外の場合 その年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)
ーーーーーーーーー
昭和49法17で改正
第四十一条の六第三項中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条第五項中「第四十一条の三第一項及び第四十一条の四第一項」を「第四十一条の三、第四十一条の四第一項及び第四十一条の五第一項」に改め、第二章第五節中同条を第四十一条の七とする。
第四十一条の五第一項中「第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約」を「財形住宅貯蓄契約」に、「同項第二号」を「第四十一条の三第三項第二号イ」に、「第四十一条の二第一項各号又は第二項各号」を「第四十一条の三第一項各号若しくは第三項各号」に、「要件」を「要件又は同条第四項に規定する要件」に、「に相当する金額」を「(長期財形住宅貯蓄契約につき同項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該契約が同条第三項各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの控除の額から当該契約が長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約であるものとした場合に第四十一条の四第一項の規定により控除されるべき金額を控除した金額)に相当する金額」に改め、同条を第四十一条の六とする。
第四十一条の四第一項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項各号中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条を第四十一条の五とする。
第四十一条の三第一項中「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十一年十二月三十一日」に、「その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる」を「積立期間の初日の属する月の初日以後七年(長期財形住宅貯蓄契約に基づいて行われる積立て等にあつては、十年)以内において行われる」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約」を「長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該住宅貯蓄契約が長期財形住宅貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の八に相当する金額(その金額が四万円を超える場合には、四万円)
第四十一条の三第二項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第四項」を「第四十一条の三第六項」に改め、同条第四項中「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の四第一項」に改め、同条を第四十一条の四とする。
第四十一条の二第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
この款において「住宅貯蓄契約」とは、一般貯蓄契約で住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすもの及び財形住宅貯蓄契約をいう。
第四十一条の二第一項第三号中「こえる」を「超える」に、「次項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項第六号中「若しくは貸付金の返済」を「、貸付金の返済若しくは賦払」に改める。
第四十一条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 この款において「長期財形住宅貯蓄契約」とは、財形住宅貯蓄契約のうち七年以上の期間にわたつて積立て等をするものであることの要件を満たすものをいう。
第四十一条の二第二項中「住宅貯蓄契約には」を「この款において「財形住宅貯蓄契約」とは」に、「含むものとする」を「いう」に改め、同項第一号中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改め、同項第三号中「頭金の支払」の下に「、貸付金の返済若しくは賦払」を加え、同項を同条第三項とする。
二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により支払うものであること。
イ 当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ロ 貯蓄取扱機関から、又はそのあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ハ 支払者等及び貯蓄取扱機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ニ 支払者等から及び貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ホ 当該家屋又はその敷地を支払者等又は貯蓄取扱機関から取得する場合には、当該支払者等又は貯蓄取扱機関に対し第一項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払う方法
第四十一条の二第一項の次に次の一項を加え、同条を第四十一条の三とする。
2 前項に規定する一般貯蓄契約とは、次に掲げる契約で第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当しないものをいう。
一 地方住宅供給公社と締結した地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約
二 住宅金融公庫と締結した住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約
三 沖繩振興開発金融公庫と締結した沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約
四 日本住宅公団と締結した日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券又は宅地債券の購入に関する契約
五 宅地開発公団と締結した宅地開発公団法(昭和四十九年法律第 号)第三十四条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約
六 金融機関その他預貯金の受入れをする者で政令で定めるものと締結した政令で定める預貯金の預入、合同運用信託(貸付信託を除く。)の信託又は貸付信託の受益証券若しくは公社債の購入に関する契約
七 政令で定める保険会社と締結した生命保険契約又は損害保険契約で保険期間の満了後に満期保険金又は満期返戻金を一時に支払う旨の定めのあるもの
第四十一条第一項中「二万円」を「三万円」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章第五節第一款中同条の次に次の一条を加える。
(年末調整に係る住宅取得控除)
第四十一条の二 前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者が、同日の属する年の翌年又は翌々年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書に第五項の規定により交付された証明書を添付して、これをその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第一項の規定により控除される金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならない。
3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)」とする。
二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
5 税務署長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者からその適用に係る金額その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
「第五節 住宅貯蓄控除」を「第五節 住宅控除」に改める。
第二章第五節中第四十一条の二の前に次の一款及び款名を加える。
第一款 住宅取得控除
(住宅取得控除)
第四十一条 居住者が、昭和四十七年一月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、その者の住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得(贈与によるものを除く。)して、これらの家屋をその工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合には、その居住の用に供した日の属する年以後三年間の各年分(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年分に限る。)の所得税の額から、これらの家屋の標準取得価額として政令で定める金額に百分の一を乗じて計算した金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、大蔵省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、建築基準法第六条第三項の規定による通知書の写しその他の書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 住宅貯蓄控除
第四十一条の二中「この節」を「この款」に改め、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅貯蓄契約には、第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約で次に掲げる要件を満たすものを含むものとする。
一 前項第一号、第二号、第五号及び第七号に掲げる要件
二 住宅の用に供する家屋又はその敷地を当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体から取得し、当該家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍に相当する金額をこえる場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)を当該支払者又は事業主団体に対し前項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。
三 当該契約が金銭の積立て、預入若しくは信託に関するものである場合には、その積立て、預入若しくは信託の日から頭金の支払をする日までの間その払出しをしないこと又は当該契約が政令で定める有価証券の購入に関するものである場合には、その購入の日から頭金の支払をする日までの間金融機関若しくは第四条の二第一項に規定する証券業者に保管の委託をし、若しくは登録をするものであること。
第四十一条の三第一項中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項」を「第四十一条の二第四項」に改める。
第四十一条の四第一項中「この節」を「この款」に改める。
第四十一条の五第一項中「貯蓄取扱機関」の下に「(第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約にあつては、当該契約を締結した同項第二号に規定する勤労者に係る賃金の支払者。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」を、「第四十一条の二第一項各号」の下に「又は第二項各号」を加える。
ーーーーーーーーーー
昭和48法16で改正
第四十一条第一項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の二第一項第二号中「返済」の下に「又は賦払」を加え、同項第三号中「返済」の下に「又は賦払」を、「以上の金額」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第二項第二号を次のように改める。
二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者若しくは当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から前項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払うか、又は当該家屋若しくはその敷地を支払者等から取得する場合には、当該支払者等に対し同号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。
第四十一条の三第一項中「基づいて積立て等」の下に「(その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる積立て等に限る。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、「それぞれその年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該住宅貯蓄契約が第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の六に相当する金額(その金額が三万円をこえる場合には、三万円)
二 前号に掲げる場合以外の場合 その年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)
ーーーーーーーーー
昭和49法17で改正
第四十一条の六第三項中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条第五項中「第四十一条の三第一項及び第四十一条の四第一項」を「第四十一条の三、第四十一条の四第一項及び第四十一条の五第一項」に改め、第二章第五節中同条を第四十一条の七とする。
第四十一条の五第一項中「第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約」を「財形住宅貯蓄契約」に、「同項第二号」を「第四十一条の三第三項第二号イ」に、「第四十一条の二第一項各号又は第二項各号」を「第四十一条の三第一項各号若しくは第三項各号」に、「要件」を「要件又は同条第四項に規定する要件」に、「に相当する金額」を「(長期財形住宅貯蓄契約につき同項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該契約が同条第三項各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの控除の額から当該契約が長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約であるものとした場合に第四十一条の四第一項の規定により控除されるべき金額を控除した金額)に相当する金額」に改め、同条を第四十一条の六とする。
第四十一条の四第一項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項各号中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条を第四十一条の五とする。
第四十一条の三第一項中「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十一年十二月三十一日」に、「その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる」を「積立期間の初日の属する月の初日以後七年(長期財形住宅貯蓄契約に基づいて行われる積立て等にあつては、十年)以内において行われる」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約」を「長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該住宅貯蓄契約が長期財形住宅貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の八に相当する金額(その金額が四万円を超える場合には、四万円)
第四十一条の三第二項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第四項」を「第四十一条の三第六項」に改め、同条第四項中「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の四第一項」に改め、同条を第四十一条の四とする。
第四十一条の二第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
この款において「住宅貯蓄契約」とは、一般貯蓄契約で住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすもの及び財形住宅貯蓄契約をいう。
第四十一条の二第一項第三号中「こえる」を「超える」に、「次項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項第六号中「若しくは貸付金の返済」を「、貸付金の返済若しくは賦払」に改める。
第四十一条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 この款において「長期財形住宅貯蓄契約」とは、財形住宅貯蓄契約のうち七年以上の期間にわたつて積立て等をするものであることの要件を満たすものをいう。
第四十一条の二第二項中「住宅貯蓄契約には」を「この款において「財形住宅貯蓄契約」とは」に、「含むものとする」を「いう」に改め、同項第一号中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改め、同項第三号中「頭金の支払」の下に「、貸付金の返済若しくは賦払」を加え、同項を同条第三項とする。
二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により支払うものであること。
イ 当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ロ 貯蓄取扱機関から、又はそのあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ハ 支払者等及び貯蓄取扱機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ニ 支払者等から及び貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
ホ 当該家屋又はその敷地を支払者等又は貯蓄取扱機関から取得する場合には、当該支払者等又は貯蓄取扱機関に対し第一項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払う方法
第四十一条の二第一項の次に次の一項を加え、同条を第四十一条の三とする。
2 前項に規定する一般貯蓄契約とは、次に掲げる契約で第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当しないものをいう。
一 地方住宅供給公社と締結した地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約
二 住宅金融公庫と締結した住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約
三 沖繩振興開発金融公庫と締結した沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約
四 日本住宅公団と締結した日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券又は宅地債券の購入に関する契約
五 宅地開発公団と締結した宅地開発公団法(昭和四十九年法律第 号)第三十四条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約
六 金融機関その他預貯金の受入れをする者で政令で定めるものと締結した政令で定める預貯金の預入、合同運用信託(貸付信託を除く。)の信託又は貸付信託の受益証券若しくは公社債の購入に関する契約
七 政令で定める保険会社と締結した生命保険契約又は損害保険契約で保険期間の満了後に満期保険金又は満期返戻金を一時に支払う旨の定めのあるもの
第四十一条第一項中「二万円」を「三万円」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章第五節第一款中同条の次に次の一条を加える。
(年末調整に係る住宅取得控除)
第四十一条の二 前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者が、同日の属する年の翌年又は翌々年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書に第五項の規定により交付された証明書を添付して、これをその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第一項の規定により控除される金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならない。
3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)」とする。
二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
5 税務署長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者からその適用に係る金額その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
|
|
|
|
|
|
|
|
税務のイロハ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75496人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9045人