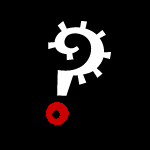対照的な2つの論文をご紹介させていただきます。
・ 「沙羅双樹の花の色 ――笠井潔、探偵小説研究会と決別」
(http://
・ 「本格ミステリに内在する二つの方向性」
(http://
前者は、昨年、日本の「本格ミステリ業界」を揺るがした「『容疑者Xの献身』騒動」の「その後」に関する「評論」。後者は、「本格ミステリ」の原理的考察です。
どちらも、いわゆる「批評」であり「評論」と呼ばれるものですが、その性格は正反対と言っても良いほどの方向性の違いを感じさせるのではないでしょうか。しかし、後者の論文で、
> 相反する「2つの方向性」が、お互いに相手を「安易な合理性」や「安易な意外性」に陥ることを牽制することで、お互いが一体となって高め合う緊張関係。これなくしては、すぐれた本格ミステリ、真に知的な本格ミステリなどあり得ないというのは、物の道理なのだと言えるでしょう。
と論じたように、「批評」も含む真に知的な営為というものは、『相反する「2つの方向性」』を抱接する緊張関係の中にしかありえません。つまり、「現実」と「原理(理論)」とのギャップを引き受ける緊張関係の中でしか、真に知的な営為はなされない、ということです。
しかし、「娯楽としての評論」は、「現実」の問題を無難に等閑視して、抽象的・衒学的な議論を弄ぶことこそが「批評」の本義であるかのように装います。しかし、「批評家」も人間である以上、当たり前の現実の中に生きているのですから、「現実」を無視する態度はおのずと欺瞞的なものにしかなりえません。
例えば、この度刊行された「探偵小説研究会」の会誌『CRITICA』第2号では、千街晶之が二階堂黎人やつずみ綾ほかを扱き下ろすエッセイを、今頃になって発表し、「おわりに」の部分で、
『 明らかに自分に跳ね返ってくるであろう部分も多いことは間違いないから、こういう他者批判的な文章はなるべくなら書きたくないというのが正直なところだ。そもそも過激なことを書いて得意がるというのが嫌いで、中庸と現実主義を尊重することを是としたい。しかし、今までの経験から言えば、過激を嫌い中庸に徹するというのも、それはそれで敵を作りやすいものである(…)。一見、そうは読めないかも知れないが、本稿は私なりの中庸宣言である。それこそ、私以外の人間にはどうでもいいことだけれど。』
と「自己正当化の言い訳」を連ねています。
そもそも「批評」というものは、批評される者の「期待」に沿ってなされる保証などないのだから、恨みを買うことがあるというのは、批評を行う上での大前提でしょう。ところが、千街は「恨まれて損をしたくない」という計算から、これまでは『中庸と現実主義を尊重する』と言えば聞こえの良い「無難主義」でやってきた。ところが、それでも二階堂黎人などから憎まれたために、世渡りとしての「無難主義」をかなぐり捨てて、初めてあからさまな「本音」を吐いたのです。
他者の文章に関して、自身が「そうとしか読めない」が故に『そもそも過激なことを書いて得意がるというのが嫌い』だなどと評する論者が『そうは読めないかも知れないが、本稿は私なりの中庸宣言である。』などと宣言するのは、あまりに得手勝手というものでしょう。自分でも『私以外の人間にはどうでもいいことだ』と思うのなら、こんな「言い訳」などしないのが、批評家の覚悟であり矜持というものなのではないでしょうか。
結局これは、「現実」を蔑ろにして「娯楽としての評論」に徹してきた評論家が、ここに来て「現実」の逆襲を受け、その矛盾した本質を暴露したのだと言えるでしょう。
いろんな意味で、みなさんにも『CRITICA』第2号をお薦めしたいと思います。
・ 「沙羅双樹の花の色 ――笠井潔、探偵小説研究会と決別」
(http://
・ 「本格ミステリに内在する二つの方向性」
(http://
前者は、昨年、日本の「本格ミステリ業界」を揺るがした「『容疑者Xの献身』騒動」の「その後」に関する「評論」。後者は、「本格ミステリ」の原理的考察です。
どちらも、いわゆる「批評」であり「評論」と呼ばれるものですが、その性格は正反対と言っても良いほどの方向性の違いを感じさせるのではないでしょうか。しかし、後者の論文で、
> 相反する「2つの方向性」が、お互いに相手を「安易な合理性」や「安易な意外性」に陥ることを牽制することで、お互いが一体となって高め合う緊張関係。これなくしては、すぐれた本格ミステリ、真に知的な本格ミステリなどあり得ないというのは、物の道理なのだと言えるでしょう。
と論じたように、「批評」も含む真に知的な営為というものは、『相反する「2つの方向性」』を抱接する緊張関係の中にしかありえません。つまり、「現実」と「原理(理論)」とのギャップを引き受ける緊張関係の中でしか、真に知的な営為はなされない、ということです。
しかし、「娯楽としての評論」は、「現実」の問題を無難に等閑視して、抽象的・衒学的な議論を弄ぶことこそが「批評」の本義であるかのように装います。しかし、「批評家」も人間である以上、当たり前の現実の中に生きているのですから、「現実」を無視する態度はおのずと欺瞞的なものにしかなりえません。
例えば、この度刊行された「探偵小説研究会」の会誌『CRITICA』第2号では、千街晶之が二階堂黎人やつずみ綾ほかを扱き下ろすエッセイを、今頃になって発表し、「おわりに」の部分で、
『 明らかに自分に跳ね返ってくるであろう部分も多いことは間違いないから、こういう他者批判的な文章はなるべくなら書きたくないというのが正直なところだ。そもそも過激なことを書いて得意がるというのが嫌いで、中庸と現実主義を尊重することを是としたい。しかし、今までの経験から言えば、過激を嫌い中庸に徹するというのも、それはそれで敵を作りやすいものである(…)。一見、そうは読めないかも知れないが、本稿は私なりの中庸宣言である。それこそ、私以外の人間にはどうでもいいことだけれど。』
と「自己正当化の言い訳」を連ねています。
そもそも「批評」というものは、批評される者の「期待」に沿ってなされる保証などないのだから、恨みを買うことがあるというのは、批評を行う上での大前提でしょう。ところが、千街は「恨まれて損をしたくない」という計算から、これまでは『中庸と現実主義を尊重する』と言えば聞こえの良い「無難主義」でやってきた。ところが、それでも二階堂黎人などから憎まれたために、世渡りとしての「無難主義」をかなぐり捨てて、初めてあからさまな「本音」を吐いたのです。
他者の文章に関して、自身が「そうとしか読めない」が故に『そもそも過激なことを書いて得意がるというのが嫌い』だなどと評する論者が『そうは読めないかも知れないが、本稿は私なりの中庸宣言である。』などと宣言するのは、あまりに得手勝手というものでしょう。自分でも『私以外の人間にはどうでもいいことだ』と思うのなら、こんな「言い訳」などしないのが、批評家の覚悟であり矜持というものなのではないでしょうか。
結局これは、「現実」を蔑ろにして「娯楽としての評論」に徹してきた評論家が、ここに来て「現実」の逆襲を受け、その矛盾した本質を暴露したのだと言えるでしょう。
いろんな意味で、みなさんにも『CRITICA』第2号をお薦めしたいと思います。
|
|
|
|
コメント(1)
「ミステリ批評の現在」を考える叩き台として、『SRマンスリー』2007年7月号に掲載された拙論、
・ 「本格ミステリと哲学趣味」
(http://mixi.jp/view_diary.pl?id=544183862&owner_id=856746)
をご紹介させていただきます。
笠井潔がミステリの世界に「現代思想」を持ち込むまでは、ミステリ批評というものは、善かれ悪しかれ「ナイーブ」なものでしかありませんでした。しかし近年、笠井潔や法月綸太郎の主導により、現代思想の知見を取り込んだミステリ批評が、当たり前になってきています。
無論それ自体は、大いにけっこうなことなのですが、そのおかげで批評の質が上がったかといえば、必ずしもそうとは言いがたい。なぜなら、思想や哲学といったものは、口まねこそ簡単ですが、それを引き受けることは容易なことではないからです。
思想・哲学的な専門用語が文章のそこここにちりばめられ、一見したところそれ自体が、思想・哲学的な専門論文の深みに達しているかの印象を与える場合も、じつのところそれは、「『黒死館殺人事件』的な知」の頽落形態でしかない場合が少なくない。
そもそも思想や哲学というものは、そんなにお易くないし、ちょっとした「お勉強」で身につくようなものならば、それは思想や哲学と呼ぶに値しない「単なる知識」でしかないのでしょう。
・ 「本格ミステリと哲学趣味」
(http://mixi.jp/view_diary.pl?id=544183862&owner_id=856746)
をご紹介させていただきます。
笠井潔がミステリの世界に「現代思想」を持ち込むまでは、ミステリ批評というものは、善かれ悪しかれ「ナイーブ」なものでしかありませんでした。しかし近年、笠井潔や法月綸太郎の主導により、現代思想の知見を取り込んだミステリ批評が、当たり前になってきています。
無論それ自体は、大いにけっこうなことなのですが、そのおかげで批評の質が上がったかといえば、必ずしもそうとは言いがたい。なぜなら、思想や哲学といったものは、口まねこそ簡単ですが、それを引き受けることは容易なことではないからです。
思想・哲学的な専門用語が文章のそこここにちりばめられ、一見したところそれ自体が、思想・哲学的な専門論文の深みに達しているかの印象を与える場合も、じつのところそれは、「『黒死館殺人事件』的な知」の頽落形態でしかない場合が少なくない。
そもそも思想や哲学というものは、そんなにお易くないし、ちょっとした「お勉強」で身につくようなものならば、それは思想や哲学と呼ぶに値しない「単なる知識」でしかないのでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
このミステリーはすごい? 更新情報
-
最新のアンケート