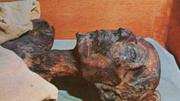エジプトといえばまず思い出すのは古王国時代のピラミッドの威容であり、新王国時代のテーベの大神殿…即ち全盛時代の古代エジプトである。
しかし2000年以上にわたり世界の文明の中心であった古代エジプトがなぜ跡形もなく消えてしまったのか、その衰亡の時代についてはあまり興味が払われていないようである。
古代エジプトに比べればごく短期間の(西)ローマ帝国がギボンの衰亡史をはじめ“ローマはなぜ滅びたのか”という主題で巻き返し繰り返し語られるのと比べるとこれはあまりにも片手落ちではないだろうか。
という趣旨でこんなトピックを立ち上げてみました。皆さん大いに語り合いましょう。
いや古代エジプトは滅びていない、今のアラブ人がその後継者だという意見でも歓迎です。(現代エジプトのアラブ人はどういう意識なのかな?)
…とはいえやはり一般的にはアケメネス朝ペルシアによる2度目の占領が古代エジプトの滅亡でしょうか。それ以後はペルシア人、ギリシア人、ローマ人、アラブ人が主役となって、“エジプト人”らしき存在はいつの間にか消えてしまっているし…
別にギボンのように衰亡の原因を探り歴史から教訓を得ようというような高尚な?趣味ではなく、単に滅んだものの滅びゆくプロセスに対する興味から立てたトピックです。
堂々たる大ピラミッドの近くには、ピラミッド時代末期の日干し煉瓦製の半分崩れ落ちた瓦礫の山があってこれもまた趣が… そしてエジプトの諸王では、アッシリア占領時代とペルシア(カンビュセス)占領時代の挾間のネコ2世に、滅亡寸前の最後の輝きを感じます。
エジプトの最大の魅力は今は亡き滅んだものが、バビロンやニネヴェと違ってそのままの形で遺跡として眼前に見ることができることでしょうが、それだけにその主が消えた時代に思いを馳せるのは興深く感じます。
|
|
|
|
コメント(29)
エジプトを初めて訪問して上空から眺めたときまず驚くのはナイル河谷の10−20km程度の狭い巾にしか緑豊かな居住地帯がなく、その両側にはどこまでも続く砂漠が広がっていることである。こんな狭い地域ではたして大文明を支える巨大人口を養えるものだろうか?
エジプトの古代遺跡の壁画には豊かな水をたたえた人々の暮らしを描いたものが多いため、このような北サハラの乾燥化・砂漠化こそが古代エジプトの衰退の原因であるとする説もある。
しかしながら結論から云えばこの説は全くの間違いのようだ。この地域の砂漠化が現代のような状況になってから古代エジプト文明は興ったのだし、またナイルの両岸地域というのは集中して耕作すれば決して狭くはない。広大な地域を必要とするのは牧畜を中心とした文明であり、土地生産性の高い農業を行なえばこの程度の地域で充分なのである。(ただし人口が数千万を超え億に近い現代では少し狭いような気もする)
その証拠に古代エジプト文明が滅びてからも、プトレマイオス朝はヘレニズム国家としては最も豊かで強力な国家であったし、ローマ時代は世界の穀倉としての生産力を誇り、アラブ時代になってからもここ1000年ほどはカイロはイスラム世界の中心であり続けムスリムの最も豊かな都として十字軍やナポレオンなどに代表される西洋社会に認識されている。
古代エジプトの衰亡はその豊かさに翳りが生じたからではなく、豊かさを保ちながら古代エジプト人自身・古代エジプト文明自体の中の何らかの要素により滅んでいったと考えざるをえない。
エジプトの古代遺跡の壁画には豊かな水をたたえた人々の暮らしを描いたものが多いため、このような北サハラの乾燥化・砂漠化こそが古代エジプトの衰退の原因であるとする説もある。
しかしながら結論から云えばこの説は全くの間違いのようだ。この地域の砂漠化が現代のような状況になってから古代エジプト文明は興ったのだし、またナイルの両岸地域というのは集中して耕作すれば決して狭くはない。広大な地域を必要とするのは牧畜を中心とした文明であり、土地生産性の高い農業を行なえばこの程度の地域で充分なのである。(ただし人口が数千万を超え億に近い現代では少し狭いような気もする)
その証拠に古代エジプト文明が滅びてからも、プトレマイオス朝はヘレニズム国家としては最も豊かで強力な国家であったし、ローマ時代は世界の穀倉としての生産力を誇り、アラブ時代になってからもここ1000年ほどはカイロはイスラム世界の中心であり続けムスリムの最も豊かな都として十字軍やナポレオンなどに代表される西洋社会に認識されている。
古代エジプトの衰亡はその豊かさに翳りが生じたからではなく、豊かさを保ちながら古代エジプト人自身・古代エジプト文明自体の中の何らかの要素により滅んでいったと考えざるをえない。
初めてカイロを訪問したときに驚くのはナイル河の小ささ・狭さである。カイロ空港に着陸する少し前に横切る紅海(世界の大河には紅海以上の巾を持つものもいくつかある)をナイル河と勘違いする人もいるほど、世界最長の大河ナイル(私の子供の頃は世界最長はミシシッピと教わったのだが、近頃川の長さのカウント法が変わったようだ)に対する期待は大きい。それがカイロの市内を流れるナイル川は何ということか。これでは大阪の淀川といい勝負ではないか。
しかしながら上流のテーベまで行くと全く状況は異なる。東岸の迷路のような大神殿を抜けると目の前に広大なゆったりとしたナイルの流れが現れる。はるかかなたの西岸のデル・エル・バハリの岩山に沈む夕日。夢にまで見たイメージ通りのナイル、そしてエジプトである。
このテーベからカイロまでの間に何が起こっているのか?
日本(というか世界の大半)のように川というのは支流を集めて下流になるほど広くなるという常識は、両岸が砂漠のナイルには通用しない。
ナイルが下流になるほど狭くなる理由は乾燥地帯を流れるため支流がないことや蒸発の影響が大きいこともあるが、何といっても両岸の農業のため水を供給しているからである。
まさにエジプトはナイル河の賜物であり、古代エジプト文明の政治体制やその衰亡の理由もナイル河との係わりを抜きにしては語れないだろう。
ナイル河を利用した農業の一番大きな特徴は、それが大規模な土木工事や水利事業を必要としないことであり、これが古代エジプトの最大の強みでありまた逆にそれが弱みとなってついには衰亡に至ったのではないだろうか。
しかしながら上流のテーベまで行くと全く状況は異なる。東岸の迷路のような大神殿を抜けると目の前に広大なゆったりとしたナイルの流れが現れる。はるかかなたの西岸のデル・エル・バハリの岩山に沈む夕日。夢にまで見たイメージ通りのナイル、そしてエジプトである。
このテーベからカイロまでの間に何が起こっているのか?
日本(というか世界の大半)のように川というのは支流を集めて下流になるほど広くなるという常識は、両岸が砂漠のナイルには通用しない。
ナイルが下流になるほど狭くなる理由は乾燥地帯を流れるため支流がないことや蒸発の影響が大きいこともあるが、何といっても両岸の農業のため水を供給しているからである。
まさにエジプトはナイル河の賜物であり、古代エジプト文明の政治体制やその衰亡の理由もナイル河との係わりを抜きにしては語れないだろう。
ナイル河を利用した農業の一番大きな特徴は、それが大規模な土木工事や水利事業を必要としないことであり、これが古代エジプトの最大の強みでありまた逆にそれが弱みとなってついには衰亡に至ったのではないだろうか。
現在ではアスワンに巨大ダムができてナイルの氾濫は人為的に止められてしまったが、それまでの1万年近く、ナイル河谷では氾濫農法というべき特殊な農業が行なわれていた。
これは毎年必ず青ナイル上流が雨季にあるときナイルは増水・氾濫して、河谷は冠水してしまう。その水が引いた後は上流から流されてきた肥沃な黒土が残され、そこで生産性の高い農業を行なうという他にあまり例を見ないシステムであり、これが古代エジプト文明を支えた生産力の源泉となっている。
このシステムは氾濫後の農地の再測定・再配分を必要とするため高度の統治機構を必要とし、また氾濫の程度によりどの標高の農地まで冠水するかを知るための情報網が必要であって、これを行なうために古代エジプトでは中央集権的な強大な王権を伴う統治制度ができ古代エジプト文明として発展した…と書いてあるような解説書が多いがはたしてそうだろうか?
何もしなくても勝手に河自体が氾濫して灌漑してくれるのなら、これは極めて楽な話でむしろ高度な統治機構などは必要ないのではないだろうか。
メソポタミアの巨大運河や網の目のような地下水路、黄河の氾濫を抑えるための治水事業、これらはすべて強大な中央集権機構を必要としそれが文明として発展してきたが、エジプトはそれらの普通の?文明とは全く逆に、何もしなくても豊かであるという利点を最大に生かして発展した文明のような気がする。
古王国のピラミッドのような生産につながらない大工事は、農業インフラに大工事を必要としないからできた贅沢であろうし、神官が勢力を持っていたというのもナイルの氾濫という人間がコントロールできないことを神に祈るところからきたのだろう。
このような事情のため、どうも古代エジプトの指導者・諸王の類は他の文明に比べ指導力・カリスマ性といったものに極めて乏しい。民族・文明を率いる力強さに欠けており“顔”が見えてこないのである。
新王国時代になると単純に氾濫を待つだけでなく、灌漑用のはねつるべのようなものが考案され、少しは利水事業らしきものが行われるようになって指導力・政治力も必要となり、トトメス3世やラムセス2世のような強大な王が登場してきた。それでもやはりメソポタミアの強烈な個性を持つ諸王に比べると影が薄く、何だかエジプト王というのは神性のような部分ばかりが強調されて、政治家・軍人としての資質はあまり問われなかったのではないかと思うし、王がその状態なら統治機構も似たようなものであったろう。
それでも何もしないでも豊かという利点を生かして数千年は近隣に君臨してきたが、やがてメソポタミアやその外縁に強大な統一勢力が成立し、直接それらの勢力と争うようになると、エジプトのこの政治力・指導力に欠ける点は致命的であり、そのために豊かさを保ったまま競争に敗れて滅んでいったのではないだろうか。
ナイルの恵みは古代エジプト文明を生んだが、あまりにもその恵みが大きすぎたのが逆に仇となって滅んでいったような気がする。
これは毎年必ず青ナイル上流が雨季にあるときナイルは増水・氾濫して、河谷は冠水してしまう。その水が引いた後は上流から流されてきた肥沃な黒土が残され、そこで生産性の高い農業を行なうという他にあまり例を見ないシステムであり、これが古代エジプト文明を支えた生産力の源泉となっている。
このシステムは氾濫後の農地の再測定・再配分を必要とするため高度の統治機構を必要とし、また氾濫の程度によりどの標高の農地まで冠水するかを知るための情報網が必要であって、これを行なうために古代エジプトでは中央集権的な強大な王権を伴う統治制度ができ古代エジプト文明として発展した…と書いてあるような解説書が多いがはたしてそうだろうか?
何もしなくても勝手に河自体が氾濫して灌漑してくれるのなら、これは極めて楽な話でむしろ高度な統治機構などは必要ないのではないだろうか。
メソポタミアの巨大運河や網の目のような地下水路、黄河の氾濫を抑えるための治水事業、これらはすべて強大な中央集権機構を必要としそれが文明として発展してきたが、エジプトはそれらの普通の?文明とは全く逆に、何もしなくても豊かであるという利点を最大に生かして発展した文明のような気がする。
古王国のピラミッドのような生産につながらない大工事は、農業インフラに大工事を必要としないからできた贅沢であろうし、神官が勢力を持っていたというのもナイルの氾濫という人間がコントロールできないことを神に祈るところからきたのだろう。
このような事情のため、どうも古代エジプトの指導者・諸王の類は他の文明に比べ指導力・カリスマ性といったものに極めて乏しい。民族・文明を率いる力強さに欠けており“顔”が見えてこないのである。
新王国時代になると単純に氾濫を待つだけでなく、灌漑用のはねつるべのようなものが考案され、少しは利水事業らしきものが行われるようになって指導力・政治力も必要となり、トトメス3世やラムセス2世のような強大な王が登場してきた。それでもやはりメソポタミアの強烈な個性を持つ諸王に比べると影が薄く、何だかエジプト王というのは神性のような部分ばかりが強調されて、政治家・軍人としての資質はあまり問われなかったのではないかと思うし、王がその状態なら統治機構も似たようなものであったろう。
それでも何もしないでも豊かという利点を生かして数千年は近隣に君臨してきたが、やがてメソポタミアやその外縁に強大な統一勢力が成立し、直接それらの勢力と争うようになると、エジプトのこの政治力・指導力に欠ける点は致命的であり、そのために豊かさを保ったまま競争に敗れて滅んでいったのではないだろうか。
ナイルの恵みは古代エジプト文明を生んだが、あまりにもその恵みが大きすぎたのが逆に仇となって滅んでいったような気がする。
ヒヨコさん
書き込みありがとうございます。これまであまり反響がなかったものでちょっと拍子抜けしていたのですが、今後も大いに語り合って盛り上げていきましょう。
云われるように、古代エジプト語がいつ頃まで話されていたかは非常に興味がある点であり、本トピックの古代エジプト衰亡史に関し一番重要な点かもしれません。
ローマがいつ滅びたのかは東西両ローマ帝国の滅亡のときということで年号どころか何月何日というところまで特定できますが、古代エジプトはというと解釈が難しいですね。政治的な古代エジプトの滅亡はそれ以後エジプト人の政権ができなかったということからアケメネス朝ペルシアによる2度目の占領時ということでいいと思いますが、古代エジプトはローマ帝国のような特定の政治体制ではなく連続する文明であると解釈するならば、古代エジプト語が使用されている限り古代エジプト文明は滅んでいないともいえます。
その古代エジプト語はアレクサンドロス以後のヘレニズム時代、プトレマイオス朝の全盛期にあってもまだ民衆の大部分は使用していたと思われます。ロゼッタストーンは支配階級の言葉であるギリシア語と民衆の言葉である古代エジプト語で書かれており(古代エジプト語の方は二つの筆記体で書かれているので合計3言語)、その当時は古代エジプト語はまだバリバリの現役の言葉でした。
その当時のギリシア語はまさに世界共通語といってもよく、シーザーによるローマ帝国のエジプト征服以後も(東)ローマ帝国の本体がすぐギリシア人に乗っ取られてしまい、エジプトにおける支配階級の言語はずっとギリシア語ということになります。
キリスト教との関係においても、キリスト生誕以前から当時世界第一の文化都市であったアレクサンドリアに住むユダヤ人(市内人口の半分近くを占めたという説もある)はコスモポリタンとしてヘブライ語よりギリシア語を話す傾向があり、旧約聖書もギリシア語訳の方が権威?を持つようになりました。キリスト教誕生以後はその傾向が加速され、ユダヤ人やギリシア人の間に急速に広まっていったキリスト教はエジプトの国教?としてギリシア語の聖典と共に発展していきました。コンスタンチノープルの権威が確立する前は、エジプトこそが(東方)キリスト教の中心であったと思います。
おそらくその頃は古代エジプト語を話す民衆もかなりの部分がキリスト教化されていたのでしょうが、彼らは古代エジプト語の最終形態というべきコプト語を用いていました。
そこへ現代エジプト人であるアラブ人によるエジプト征服です。
その結果大部分のエジプト人はムスリムになったのですが、一部のエジプト人はアラブ人との同化を拒み、コプト教徒として現代までキリスト教の信仰を守り続けています。ですから古代エジプト語を守ってきたのはキリスト教徒ということになりそうです。
しかしなからコプト教徒もキリスト教は守リ続けたものの、言葉はだんだんとアラビア語を話す人口が増えていき、ついに17世紀にはコプト語は死語になったとされています。もしかするとシナイの山奥あたりにはまだコプト語を話す連中が残っているかもしれませんが、現代エジプト政府はアラブ人の代表格を自認してそういうことには関心を示さないでしょうから…
ここで面白いと思うのはキリスト教徒として生き残ったのはギリシア語を話すエジプト人ではなく、古代エジプト人の末裔としてコプト語を話すエジプト人であるということです。
このことを考えると、ギリシア人による1000年にわたるエジプト支配というのは皮相的なものにとどまり、古代エジプト人はしぶとく生き延びてきたのかなという気もします。
書き込みありがとうございます。これまであまり反響がなかったものでちょっと拍子抜けしていたのですが、今後も大いに語り合って盛り上げていきましょう。
云われるように、古代エジプト語がいつ頃まで話されていたかは非常に興味がある点であり、本トピックの古代エジプト衰亡史に関し一番重要な点かもしれません。
ローマがいつ滅びたのかは東西両ローマ帝国の滅亡のときということで年号どころか何月何日というところまで特定できますが、古代エジプトはというと解釈が難しいですね。政治的な古代エジプトの滅亡はそれ以後エジプト人の政権ができなかったということからアケメネス朝ペルシアによる2度目の占領時ということでいいと思いますが、古代エジプトはローマ帝国のような特定の政治体制ではなく連続する文明であると解釈するならば、古代エジプト語が使用されている限り古代エジプト文明は滅んでいないともいえます。
その古代エジプト語はアレクサンドロス以後のヘレニズム時代、プトレマイオス朝の全盛期にあってもまだ民衆の大部分は使用していたと思われます。ロゼッタストーンは支配階級の言葉であるギリシア語と民衆の言葉である古代エジプト語で書かれており(古代エジプト語の方は二つの筆記体で書かれているので合計3言語)、その当時は古代エジプト語はまだバリバリの現役の言葉でした。
その当時のギリシア語はまさに世界共通語といってもよく、シーザーによるローマ帝国のエジプト征服以後も(東)ローマ帝国の本体がすぐギリシア人に乗っ取られてしまい、エジプトにおける支配階級の言語はずっとギリシア語ということになります。
キリスト教との関係においても、キリスト生誕以前から当時世界第一の文化都市であったアレクサンドリアに住むユダヤ人(市内人口の半分近くを占めたという説もある)はコスモポリタンとしてヘブライ語よりギリシア語を話す傾向があり、旧約聖書もギリシア語訳の方が権威?を持つようになりました。キリスト教誕生以後はその傾向が加速され、ユダヤ人やギリシア人の間に急速に広まっていったキリスト教はエジプトの国教?としてギリシア語の聖典と共に発展していきました。コンスタンチノープルの権威が確立する前は、エジプトこそが(東方)キリスト教の中心であったと思います。
おそらくその頃は古代エジプト語を話す民衆もかなりの部分がキリスト教化されていたのでしょうが、彼らは古代エジプト語の最終形態というべきコプト語を用いていました。
そこへ現代エジプト人であるアラブ人によるエジプト征服です。
その結果大部分のエジプト人はムスリムになったのですが、一部のエジプト人はアラブ人との同化を拒み、コプト教徒として現代までキリスト教の信仰を守り続けています。ですから古代エジプト語を守ってきたのはキリスト教徒ということになりそうです。
しかしなからコプト教徒もキリスト教は守リ続けたものの、言葉はだんだんとアラビア語を話す人口が増えていき、ついに17世紀にはコプト語は死語になったとされています。もしかするとシナイの山奥あたりにはまだコプト語を話す連中が残っているかもしれませんが、現代エジプト政府はアラブ人の代表格を自認してそういうことには関心を示さないでしょうから…
ここで面白いと思うのはキリスト教徒として生き残ったのはギリシア語を話すエジプト人ではなく、古代エジプト人の末裔としてコプト語を話すエジプト人であるということです。
このことを考えると、ギリシア人による1000年にわたるエジプト支配というのは皮相的なものにとどまり、古代エジプト人はしぶとく生き延びてきたのかなという気もします。
Stephen Cabotさん
すご〜〜〜〜い!
おもしろいです!
>その当時のギリシア語はまさに世界共通語といってもよく、シーザーによるローマ帝国のエジプト征服以後も(東)ローマ帝国の本体がすぐギリシア人に乗っ取られてしまい、エジプトにおける支配階級の言語はずっとギリシア語ということになります。
プトレマイオス朝エジプトがローマ軍に征服されたので、てっきり、ローマ人が古代ローマ語で支配を続けていたんだと思っていました。
今まで、王朝支配については念頭にあったのですが、王朝滅亡後の民衆が、文化をどう継承していったのかは、視野にありませんでした。
キリスト教から別れたコプト教がエジプトで信仰されているっていうの、どこかで読んだことがあります。
ということは、コプト教徒が最終的なエジプト文明の継承者っていうことになるんですね。
アレキサンドリアの図書館がローマ軍に破壊されたため、古代エジプトに存在した多くの叡智が失われてしまったって、どこかの本で読みました。
でも、それとは別に、エジプト人のおじいちゃんやおばあちゃんたちが、子供に孫に伝えた文化、それはそれで、微笑ましくて尊いですね。
すご〜〜〜〜い!
おもしろいです!
>その当時のギリシア語はまさに世界共通語といってもよく、シーザーによるローマ帝国のエジプト征服以後も(東)ローマ帝国の本体がすぐギリシア人に乗っ取られてしまい、エジプトにおける支配階級の言語はずっとギリシア語ということになります。
プトレマイオス朝エジプトがローマ軍に征服されたので、てっきり、ローマ人が古代ローマ語で支配を続けていたんだと思っていました。
今まで、王朝支配については念頭にあったのですが、王朝滅亡後の民衆が、文化をどう継承していったのかは、視野にありませんでした。
キリスト教から別れたコプト教がエジプトで信仰されているっていうの、どこかで読んだことがあります。
ということは、コプト教徒が最終的なエジプト文明の継承者っていうことになるんですね。
アレキサンドリアの図書館がローマ軍に破壊されたため、古代エジプトに存在した多くの叡智が失われてしまったって、どこかの本で読みました。
でも、それとは別に、エジプト人のおじいちゃんやおばあちゃんたちが、子供に孫に伝えた文化、それはそれで、微笑ましくて尊いですね。
ヒヨコさん
古代エジプトの一番の繁栄期は新王国の18・19王朝時代でしょうが、紛争がなかった時代というよりも盛んに外征をおこなった時代といえるでしょうか。まあ外征を行ったということは国力が充実して攻め込むことが多く攻め込まれることはなかったという意味で、エジプト国内は平和であったかもしれませんが・・・
もっともたいていの国はその国力がピークに達した後に急速に衰えるものだし、古代エジプトもその例外ではありませんでしたが・・・
エジプトにはラテン語時代というのはほぼないといってもいいと思います。ローマ人はプラクティカルな民族で、東地中海の共通語であるギリシア語に代えてラテン語を押し付けるということはあまりしなかったのではないでしょうか。
古代エジプトの一番の繁栄期は新王国の18・19王朝時代でしょうが、紛争がなかった時代というよりも盛んに外征をおこなった時代といえるでしょうか。まあ外征を行ったということは国力が充実して攻め込むことが多く攻め込まれることはなかったという意味で、エジプト国内は平和であったかもしれませんが・・・
もっともたいていの国はその国力がピークに達した後に急速に衰えるものだし、古代エジプトもその例外ではありませんでしたが・・・
エジプトにはラテン語時代というのはほぼないといってもいいと思います。ローマ人はプラクティカルな民族で、東地中海の共通語であるギリシア語に代えてラテン語を押し付けるということはあまりしなかったのではないでしょうか。
ちょっと以前にカルタゴ史ブームというのがあり、各種の書籍やテレビの特番で競うように取り上げられた。そのストーリーはだいたいワンパターンで日本をカルタゴになぞらえたものであり、海洋貿易国家として繁栄を極めたカルタゴがやがては領邦型国家のローマとの戦いに敗れて滅んでいく歴史を、ローマを米国(中国という取り上げ方のものも少しあった)になぞらえて警鐘を鳴らした…というよりも自虐的史観?から面白がって取り上げたものである。
しかしながらこんな見当違いの比喩はないのではなかろうか。日本が海洋貿易型の国家であったことは一度もないし、日本はカルタゴとローマのどちらに似ているかといえば、国家の成り立ちや国民性を考えるとどちらかといえばローマであろう。
このような比喩に意味があるかどうかは別にして、日本と似ている国を探すとすればそれは古代エジプトではないだろうか。
砂漠に囲まれているため対外的な交渉をそれほど必要としないという意味では海に囲まれた日本と良く似ているし、ナイルの氾濫による恵みで国土が豊かであるという意味では、水資源が豊富で緑豊かな肥沃な自然を持つ日本と共通している。
日本は資源小国などと云われているようだが、別に石油が地下に眠る砂漠の国が豊かなわけではない。国土の豊かさは自然・地勢と人間の関係の総合力であり、そういう意味では日本は歴史的に世界屈指の豊かな国であったといえるし、古代エジプトのナイル両岸やデルタ地方の豊かさと相通じるものがある。
最近日本では古代エジプトがブームになっているようで、このある意味マニアックなコミュにも大変な人数の参加者がいるが、その原因のひとつとして日本と共通するものがあるので何となく懐かしさのような感覚や共感を憶えるからではないだろうか。豊かな自然に恵まれ外敵もあまりいなかったため、穏やかでのんびりした国民性が形成され…
そしてその共通性が、何もしなくても豊かであり対外的な争いや苦労もあまりなかったため政治力・指導力を欠いていたという古代エジプトの衰亡原因ではないかと推定されることに関しても共通だとしたら…
何だか昨今の日本の事情を考えると笑い事ではないかもしれない。
しかしながらこんな見当違いの比喩はないのではなかろうか。日本が海洋貿易型の国家であったことは一度もないし、日本はカルタゴとローマのどちらに似ているかといえば、国家の成り立ちや国民性を考えるとどちらかといえばローマであろう。
このような比喩に意味があるかどうかは別にして、日本と似ている国を探すとすればそれは古代エジプトではないだろうか。
砂漠に囲まれているため対外的な交渉をそれほど必要としないという意味では海に囲まれた日本と良く似ているし、ナイルの氾濫による恵みで国土が豊かであるという意味では、水資源が豊富で緑豊かな肥沃な自然を持つ日本と共通している。
日本は資源小国などと云われているようだが、別に石油が地下に眠る砂漠の国が豊かなわけではない。国土の豊かさは自然・地勢と人間の関係の総合力であり、そういう意味では日本は歴史的に世界屈指の豊かな国であったといえるし、古代エジプトのナイル両岸やデルタ地方の豊かさと相通じるものがある。
最近日本では古代エジプトがブームになっているようで、このある意味マニアックなコミュにも大変な人数の参加者がいるが、その原因のひとつとして日本と共通するものがあるので何となく懐かしさのような感覚や共感を憶えるからではないだろうか。豊かな自然に恵まれ外敵もあまりいなかったため、穏やかでのんびりした国民性が形成され…
そしてその共通性が、何もしなくても豊かであり対外的な争いや苦労もあまりなかったため政治力・指導力を欠いていたという古代エジプトの衰亡原因ではないかと推定されることに関しても共通だとしたら…
何だか昨今の日本の事情を考えると笑い事ではないかもしれない。
聖書に出てくるエジプト
古代エジプト人、またその後千年にわたりエジプトを支配したギリシア人は、記録・歴史を書き残すことに比較的熱心な国民であり、エジプト史を学ぶ人は参考資料には事欠かない。
これに対してユダヤ人というのは歴史よりも宗教というか形而上の事柄に熱心な国民であり、彼らが代々書きついできた聖書は歴史書というよりも歴史的事象を含む宗教書というべきであろう。
古代エジプトの衰亡史を考えるにあたり、そんな聖書を参考にすることに意味があるのか?…というと、ユダヤ人の歴史観・世界観というのは古代エジプトのそれに強く影響というか、エジプトという存在に対するアンチテーゼがユダヤという概念であって、聖書にはその影響が色濃く残っていると思う。
おまけにその時代からして、聖書の最重要主題と思われる「出エジプト」はエジプト新王国時代の全盛期と重なり、ここからエジプトの衰退が始まると考えれば(多くの国はその全盛期の直後から急激に衰退が始まる)その衰亡史はイスラエルの歴史と完全に重なっており、イスラエル王国を滅ぼしたアッシリアにエジプト王国も滅ぼされ、ユダ王国の遺民をバビロン捕囚からパレスチナに帰還させたアケメネス朝ペルシアにより古代エジプトは最終的に滅亡している。
であるならば、ユダヤ人から見たエジプト、即ち聖書に出てくるエジプトというのは古代エジプトの衰亡史をある一貫した観点から描写している資料として重要なのではないだろうか。
中世から近世のヨーロッパにおけるエジプトを含むオリエントの歴史研究は、社会全体がキリスト教の強い影響下にあったため、聖書の記述に頼っている部分が多かった。そのためにピラミッドはヨセフ(アブラハムの曾孫で奴隷として連れ去られたエジプトで宰相に抜擢された)が食料を貯蔵した倉庫であるといった珍説がまかり通り、近世考古学が登場するや聖書は歴史研究におけるある種のタブーとして無視されてきたのだが、これはそろそろ見直すべきときではないだろうか。
というところで本論に入ると、聖書に出てくるエジプトで一番有名なのは「出エジプト(エクソダス)」であることは論を待たないが、これはエジプトで奴隷にされていたユダヤ人がモーゼに率いられて脱出し、パレスチナに帰還して建国するという物語である。その脱出の途中で紅海(異説もある)が割れて海を渡ることができたが、追撃してきたエジプト軍は海に飲まれてしまうというエピソードがそのクライマックスであり、映画などにはよく取り上げられている。
このときのパロ(ファラオ)は誰かははっきりと聖書には書かれていないのだが、諸事情からラムセス2世というのが通説となっている。
筆者はこの出エジプトからユダヤ人の歴史は実質的に開始されたと考えている。
即ちこのときモーゼに率いられて脱出した奴隷の集団がユダヤ人という同族意識を持って現代まで続くユダヤ人を形成してきたのであろう。
なおモーゼは誕生時にナイル川に小船で流され、ファラオの息女に拾われて養子として育てられたが、あるとき神からの召命を受けてユダヤ人を率いてエジプトを脱出することを決意したとされている。
しかしながらこれは、モーゼは実際にラムセス2世の一族(兄弟?)であって王位継承の権力争いに敗れたため奴隷の一群を引き連れてパレスチナに亡命したと考える方が自然ではないだろうか。そして奴隷の一群といってもそれは軍事力・経済力を兼ね備えた外国人のコミュニティーのようなものであり、その多くはシリア・パレスチナ一帯から数百年にわたって豊かなナイルデルタ地帯に流入してきた武装難民というべき存在だったと思われる。
(この稿続く)
古代エジプト人、またその後千年にわたりエジプトを支配したギリシア人は、記録・歴史を書き残すことに比較的熱心な国民であり、エジプト史を学ぶ人は参考資料には事欠かない。
これに対してユダヤ人というのは歴史よりも宗教というか形而上の事柄に熱心な国民であり、彼らが代々書きついできた聖書は歴史書というよりも歴史的事象を含む宗教書というべきであろう。
古代エジプトの衰亡史を考えるにあたり、そんな聖書を参考にすることに意味があるのか?…というと、ユダヤ人の歴史観・世界観というのは古代エジプトのそれに強く影響というか、エジプトという存在に対するアンチテーゼがユダヤという概念であって、聖書にはその影響が色濃く残っていると思う。
おまけにその時代からして、聖書の最重要主題と思われる「出エジプト」はエジプト新王国時代の全盛期と重なり、ここからエジプトの衰退が始まると考えれば(多くの国はその全盛期の直後から急激に衰退が始まる)その衰亡史はイスラエルの歴史と完全に重なっており、イスラエル王国を滅ぼしたアッシリアにエジプト王国も滅ぼされ、ユダ王国の遺民をバビロン捕囚からパレスチナに帰還させたアケメネス朝ペルシアにより古代エジプトは最終的に滅亡している。
であるならば、ユダヤ人から見たエジプト、即ち聖書に出てくるエジプトというのは古代エジプトの衰亡史をある一貫した観点から描写している資料として重要なのではないだろうか。
中世から近世のヨーロッパにおけるエジプトを含むオリエントの歴史研究は、社会全体がキリスト教の強い影響下にあったため、聖書の記述に頼っている部分が多かった。そのためにピラミッドはヨセフ(アブラハムの曾孫で奴隷として連れ去られたエジプトで宰相に抜擢された)が食料を貯蔵した倉庫であるといった珍説がまかり通り、近世考古学が登場するや聖書は歴史研究におけるある種のタブーとして無視されてきたのだが、これはそろそろ見直すべきときではないだろうか。
というところで本論に入ると、聖書に出てくるエジプトで一番有名なのは「出エジプト(エクソダス)」であることは論を待たないが、これはエジプトで奴隷にされていたユダヤ人がモーゼに率いられて脱出し、パレスチナに帰還して建国するという物語である。その脱出の途中で紅海(異説もある)が割れて海を渡ることができたが、追撃してきたエジプト軍は海に飲まれてしまうというエピソードがそのクライマックスであり、映画などにはよく取り上げられている。
このときのパロ(ファラオ)は誰かははっきりと聖書には書かれていないのだが、諸事情からラムセス2世というのが通説となっている。
筆者はこの出エジプトからユダヤ人の歴史は実質的に開始されたと考えている。
即ちこのときモーゼに率いられて脱出した奴隷の集団がユダヤ人という同族意識を持って現代まで続くユダヤ人を形成してきたのであろう。
なおモーゼは誕生時にナイル川に小船で流され、ファラオの息女に拾われて養子として育てられたが、あるとき神からの召命を受けてユダヤ人を率いてエジプトを脱出することを決意したとされている。
しかしながらこれは、モーゼは実際にラムセス2世の一族(兄弟?)であって王位継承の権力争いに敗れたため奴隷の一群を引き連れてパレスチナに亡命したと考える方が自然ではないだろうか。そして奴隷の一群といってもそれは軍事力・経済力を兼ね備えた外国人のコミュニティーのようなものであり、その多くはシリア・パレスチナ一帯から数百年にわたって豊かなナイルデルタ地帯に流入してきた武装難民というべき存在だったと思われる。
(この稿続く)
聖書に出てくるエジプト(承前)
ユダヤ教に始まり、キリスト教やイスラム教に分派していった一神教の起源はエジプト第18王朝のアメンヘテプ4世(在位紀元前1364−1347)が行なった宗教改革であるという説がある。アメンヘテプ4世はテーベのアメン神の権威から脱却すべく、太陽神アテンを唯一の神として自らと一体化すべく名前もイクナアテンと変え、首都もテーベからアマルナに移した。この改革は結果的には成功せず、次代のツタンカーメン王は信仰も首都も元に戻してしまうのだが、この唯一神への信仰はエジプト王家の一部の勢力に伝えられてきたというのは充分考えられることであろう。
モーゼによる出エジプトはアマルナ時代から120−130年後と思われるので、その間隠れキリシタンのように信仰が続いてきたと考えれば時代的にもだいたい符合している。
ラムセス2世の兄弟またはその一族と推定されるモーゼはその一神教を護ってきた王族であって、彼はこの信仰をエジプトから脱出する奴隷の一団をまとめるための精神的な支柱として利用したのであろう。
この奴隷の一団はヒクソスの時代から数百年にわたりシリア・パレスチナから豊かなナイルデルタに流入したと思われる武装難民が、エジプト王の許可を得て一種の外国人自治区を形成していたものと思われ、このような雑多な集団をまとめ、ユダヤ人というひとつの民族であるとして団結させるには神に選ばれ導かれた一族というコンセプトは有効であったのものと思われる。
それではモーゼは全く何もそのような伝統も共通点もない奴隷の一群に突然そのような考え方を持ち込んだのかというと、もちろんそうではなくそんな強引なやり方では誰もついてくるはずはないだろう。
聖書によれば、ユダヤ民族の始祖とされパレスチナに神の導きにより定着したアブラハムの息子がイサク、その息子がヤコブ(別名イスラエル)であり、ヤコブの息子12人がエジプトに流浪してきてその子孫がイスラエルの12支族を形成したとされている。
その12支族のうち最も栄えたのは後にダビデ王・ソロモン大王を出したユダ族(ユダヤ人という呼び名はこのユダ族からとられたものであり、後に世界史に大きな影響を与えるイエス・キリストもユダ族の出身)であるが、聖書ではアブラハム・イサク・ヤコブとその12人の息子たちの言行は詳しく述べるものの、それ以後の代については少しも触れていない。ところがそれから数百年の後に数十万人に増えた12支族が突然出エジプトを敢行することになっている。
となればこの12支族というかユダヤ人という概念そのものはエジプト史の中で形成されたというしかなく、それはエジプト史の中でいかなる位置付けとなるのだろうか?
(この稿続く)
ユダヤ教に始まり、キリスト教やイスラム教に分派していった一神教の起源はエジプト第18王朝のアメンヘテプ4世(在位紀元前1364−1347)が行なった宗教改革であるという説がある。アメンヘテプ4世はテーベのアメン神の権威から脱却すべく、太陽神アテンを唯一の神として自らと一体化すべく名前もイクナアテンと変え、首都もテーベからアマルナに移した。この改革は結果的には成功せず、次代のツタンカーメン王は信仰も首都も元に戻してしまうのだが、この唯一神への信仰はエジプト王家の一部の勢力に伝えられてきたというのは充分考えられることであろう。
モーゼによる出エジプトはアマルナ時代から120−130年後と思われるので、その間隠れキリシタンのように信仰が続いてきたと考えれば時代的にもだいたい符合している。
ラムセス2世の兄弟またはその一族と推定されるモーゼはその一神教を護ってきた王族であって、彼はこの信仰をエジプトから脱出する奴隷の一団をまとめるための精神的な支柱として利用したのであろう。
この奴隷の一団はヒクソスの時代から数百年にわたりシリア・パレスチナから豊かなナイルデルタに流入したと思われる武装難民が、エジプト王の許可を得て一種の外国人自治区を形成していたものと思われ、このような雑多な集団をまとめ、ユダヤ人というひとつの民族であるとして団結させるには神に選ばれ導かれた一族というコンセプトは有効であったのものと思われる。
それではモーゼは全く何もそのような伝統も共通点もない奴隷の一群に突然そのような考え方を持ち込んだのかというと、もちろんそうではなくそんな強引なやり方では誰もついてくるはずはないだろう。
聖書によれば、ユダヤ民族の始祖とされパレスチナに神の導きにより定着したアブラハムの息子がイサク、その息子がヤコブ(別名イスラエル)であり、ヤコブの息子12人がエジプトに流浪してきてその子孫がイスラエルの12支族を形成したとされている。
その12支族のうち最も栄えたのは後にダビデ王・ソロモン大王を出したユダ族(ユダヤ人という呼び名はこのユダ族からとられたものであり、後に世界史に大きな影響を与えるイエス・キリストもユダ族の出身)であるが、聖書ではアブラハム・イサク・ヤコブとその12人の息子たちの言行は詳しく述べるものの、それ以後の代については少しも触れていない。ところがそれから数百年の後に数十万人に増えた12支族が突然出エジプトを敢行することになっている。
となればこの12支族というかユダヤ人という概念そのものはエジプト史の中で形成されたというしかなく、それはエジプト史の中でいかなる位置付けとなるのだろうか?
(この稿続く)
聖書に出てくるエジプト(承前)
ユダヤ人の出エジプトが紀元前13世紀末の第19王朝時代として、それまでの年月(聖書によればエジプト移住から約400年)でいかにしてエジプト史の中でユダヤ人なるもののアイデンティティーが確立されていったのであろうか?
その前に簡単にその後のユダヤ人史についてふれておく。
出エジプトから40年ほどかけてパレスチナに“帰還”したユダヤ人は、先住民族と戦いながら支配地を広げていくが、その頃は12支族は独立した存在であった。それが海岸部に住む強大なペリシテ人(パレスチナと言う呼び名はこのペリシテ人に因む)と戦うべく団結して紀元前1040年のサウルによる統一イスラエル王国が成立し、これ以降はほぼ年代が確定できる“歴史時代”となっていく。
ベニヤミン支族出身のサウル王はペリシテ人との戦いで敗死するが、続いて即位したユダ支族出身のダビデ王がほぼ現在のイスラエルの地を統一し、エルサレムを奪取して首都とする。その息子のソロモン大王の時代が全盛期でエルサレムに神殿を建設し、オリエント第一の強国となる。ソロモン大王の死後イスラエルは10支族からなるイスラエル王国(北王国)とユダ族とベニヤミン族の2支族からなるユダ王国(南王国)に分裂するがイスラエル王国は紀元前722年にアッシリアに、ユダ王国は紀元前586年に新バビロニアに滅ぼされる。バビロニアに滅ぼされた2支族はバビロン捕囚を経てパレスチナに帰還して国家・神殿を再建するが(第二神殿時代)、今度は紀元前後にローマ帝国に滅ぼされて世界中に離散するものの、最近になってイスラエルを建国して二千年ぶりに復活した。
即ち現代まで続くユダヤ人の歴史というのはユダ王国の2支族の歴史である。そしてイスラエル王国の10支族は歴史の闇の中に消えてしまったとされており、実はその10支族はシルクロードを通って日本に来て云々といった話はトンデモ本(一概に否定するわけではないが)の世界では定番になっている。
ところでその12支族というのは、ユダヤ民族の始祖とされるアブラハムの孫のヤコブの12人の息子の子孫とされている。しかしながら実際にはヤコブの息子の一人であるヨセフの息子のエフライムとマナセがヤコブの養子となったため、その子孫は13支族を形成することになる。これが12支族と呼ばれるようになったのは、レビ支族は神の命令で祭祀を司る部族として残りの12支族の中に分散して暮らし、支族単位で行なわれる軍事・経済行動には参加しないためである。
バビロンから帰還して現代ユダヤ人を形成したのはユダ王国の2支族だけではなくレビ支族の一部も含まれており、モーゼはこのレビ支族に属し、モーゼの兄アーロンの子孫が代々祭司長を勤めることになっている。
これは常識的に考えればレビ支族というのは、元々一般のユダヤ人とは異なる出自であり、聖なる数12への数合せのために祖父と孫の養子縁組といったあまり例がない説話が作られたのであろう。
そしてモーゼがラムセス2世の兄弟かその一族であるならば、レビ族というのはエジプト人の一神教を奉ずる神官勢力であるというのは充分考えられる。また聖書中ではユダヤ人とレビ族という並列に解釈できるような表現もあり、出エジプト以前にはレビ支族はユダヤ人とはみなされていなかった可能性が高い。
そして聖書の中で繰り返し語られるのは、神はユダヤ人をエジプト人の奴隷状態から救い出した恩人(恩神?)であるということであり、この恩を忘れたユダヤ人を神は罰したり悔い改めたので許したりということが延々と繰り返されている。
即ちユダヤ人とはエジプトに対するアンチテーゼであり、エジプト人から神によって解放されたのがユダヤ人であるという概念をモーゼはじめレビ支族を形成したエジプト人が持ち込んだのであろう。
このように自らのアイデンティティーを否定することにより新たな自我を確立するというのは宗教の世界では一般的に行なわれていることであり、ユダヤ人の歴史はエジプトという存在を否定するところから始まったといえる。
このような歴史観ではじまったユダヤ史は必然的にレビ支族がその中心的存在であったが、ダビデ王以後はユダ支族が中心となってその第2期を迎え、ついにダビデ王直系の子孫とされるイエス・キリストの登場で最高潮に達する。
そしてダビデ王以降の聖書に書かれたエジプトはこれまでとは違う調子で語られることになる。
(この稿続く)
ユダヤ人の出エジプトが紀元前13世紀末の第19王朝時代として、それまでの年月(聖書によればエジプト移住から約400年)でいかにしてエジプト史の中でユダヤ人なるもののアイデンティティーが確立されていったのであろうか?
その前に簡単にその後のユダヤ人史についてふれておく。
出エジプトから40年ほどかけてパレスチナに“帰還”したユダヤ人は、先住民族と戦いながら支配地を広げていくが、その頃は12支族は独立した存在であった。それが海岸部に住む強大なペリシテ人(パレスチナと言う呼び名はこのペリシテ人に因む)と戦うべく団結して紀元前1040年のサウルによる統一イスラエル王国が成立し、これ以降はほぼ年代が確定できる“歴史時代”となっていく。
ベニヤミン支族出身のサウル王はペリシテ人との戦いで敗死するが、続いて即位したユダ支族出身のダビデ王がほぼ現在のイスラエルの地を統一し、エルサレムを奪取して首都とする。その息子のソロモン大王の時代が全盛期でエルサレムに神殿を建設し、オリエント第一の強国となる。ソロモン大王の死後イスラエルは10支族からなるイスラエル王国(北王国)とユダ族とベニヤミン族の2支族からなるユダ王国(南王国)に分裂するがイスラエル王国は紀元前722年にアッシリアに、ユダ王国は紀元前586年に新バビロニアに滅ぼされる。バビロニアに滅ぼされた2支族はバビロン捕囚を経てパレスチナに帰還して国家・神殿を再建するが(第二神殿時代)、今度は紀元前後にローマ帝国に滅ぼされて世界中に離散するものの、最近になってイスラエルを建国して二千年ぶりに復活した。
即ち現代まで続くユダヤ人の歴史というのはユダ王国の2支族の歴史である。そしてイスラエル王国の10支族は歴史の闇の中に消えてしまったとされており、実はその10支族はシルクロードを通って日本に来て云々といった話はトンデモ本(一概に否定するわけではないが)の世界では定番になっている。
ところでその12支族というのは、ユダヤ民族の始祖とされるアブラハムの孫のヤコブの12人の息子の子孫とされている。しかしながら実際にはヤコブの息子の一人であるヨセフの息子のエフライムとマナセがヤコブの養子となったため、その子孫は13支族を形成することになる。これが12支族と呼ばれるようになったのは、レビ支族は神の命令で祭祀を司る部族として残りの12支族の中に分散して暮らし、支族単位で行なわれる軍事・経済行動には参加しないためである。
バビロンから帰還して現代ユダヤ人を形成したのはユダ王国の2支族だけではなくレビ支族の一部も含まれており、モーゼはこのレビ支族に属し、モーゼの兄アーロンの子孫が代々祭司長を勤めることになっている。
これは常識的に考えればレビ支族というのは、元々一般のユダヤ人とは異なる出自であり、聖なる数12への数合せのために祖父と孫の養子縁組といったあまり例がない説話が作られたのであろう。
そしてモーゼがラムセス2世の兄弟かその一族であるならば、レビ族というのはエジプト人の一神教を奉ずる神官勢力であるというのは充分考えられる。また聖書中ではユダヤ人とレビ族という並列に解釈できるような表現もあり、出エジプト以前にはレビ支族はユダヤ人とはみなされていなかった可能性が高い。
そして聖書の中で繰り返し語られるのは、神はユダヤ人をエジプト人の奴隷状態から救い出した恩人(恩神?)であるということであり、この恩を忘れたユダヤ人を神は罰したり悔い改めたので許したりということが延々と繰り返されている。
即ちユダヤ人とはエジプトに対するアンチテーゼであり、エジプト人から神によって解放されたのがユダヤ人であるという概念をモーゼはじめレビ支族を形成したエジプト人が持ち込んだのであろう。
このように自らのアイデンティティーを否定することにより新たな自我を確立するというのは宗教の世界では一般的に行なわれていることであり、ユダヤ人の歴史はエジプトという存在を否定するところから始まったといえる。
このような歴史観ではじまったユダヤ史は必然的にレビ支族がその中心的存在であったが、ダビデ王以後はユダ支族が中心となってその第2期を迎え、ついにダビデ王直系の子孫とされるイエス・キリストの登場で最高潮に達する。
そしてダビデ王以降の聖書に書かれたエジプトはこれまでとは違う調子で語られることになる。
(この稿続く)
聖書に出てくるエジプト(承前)
聖書というのは読めば読むほど出エジプトが最大のテーマであり、これを云いたいために前後のエピソードがあるといってもいいくらいであると感じる。
即ち出エジプトの前のエピソードというのは、なぜユダヤ人がエジプトに奴隷として存在するのかを説明する導入部であると考えられる。そして出エジプト後のエピソードというのは、エジプトから連れ出すためにモーゼが神と結んだ契約を民が破ったため、民に天罰が下っては預言者が神にとりなすことの繰り返しと位置付けられる。これはイエス・キリスト登場以後の新約聖書も同様であり、イエスは預言者(あるいはメシア)であって“民”の範囲をユダヤ人以外にも拡大しただけと考えれば、これもまた出エジプトの延長線上にあるといえる。
これはアブラハムもモーゼもイエスもマホメットも預言者(もちろん最後に現れたマホメットが最高にエライという位置付けなのであるが)とするイスラムの考え方に近い。そしてキリスト教も成立初期段階ではこのような教義であったと考えられ、イエスの神性が認められるのはかなり後のことであろう。
キリスト教のその後の世界史に与えた影響を考えれば、世界史上の最重要事件のひとつといってもよい出エジプトがなぜおきたのか? それはモーゼがユダヤ人であったからではなく、元々はエジプト人であったモーゼが出エジプトという事件を起こすことによりユダヤ人という概念を創ったからであるというのが、これまでに述べてきたことの結論である。
なおこの結論は現在も議論されている“ユダヤ人とは何か”という課題に対してもひとつの示唆となるのではないかと思われる。ハザール人問題(7世紀の中央アジアのトルコ系民族でユダヤ教に集団改宗したという説がある)やサマリア人問題(これについては別に述べるつもり)、そしてドイッチャーやサルトルの著作などこの問題はさんざん議論されているが、結局は“自らをユダヤ人と考える人がユダヤ人である”というのが平凡ながら最大公約数的な定義であろうと思われ、それはユダヤ人の起源から考えればある意味当然の帰結といえるだろう。
さてこのようにエジプトから逃れてきたユダヤ人(エジプトから逃れることによってユダヤ人となった人々というべきか)であるが、パレスチナを征服・定住以後しばらくは聖書にはエジプトに関する記述はほとんどなくなる。これはパレスチナでの小競り合いが小部族同士(当時はイスラエルも統一国家は形成していない)の局地戦であり、エジプトも当時は衰退が始まりこの地方まで勢力を伸ばすことはできない時代であったからである。
それが統一イスラエル建国、そしてダビデ・ソロモンの両王の時代になるとイスラエルはオリエントの堂々たるメジャープレーヤーとなりエジプトとの関係が復活してくる。そしてその時代はさらにスーパー大国としてアッシリア・バビロニア・アケメネス朝ペルシアが次々に台頭してきて、イスラエルもエジプトもその波に飲み込まれて滅亡することになるのだが、そこでエジプトの衰亡はどのように描かれているのか?
(この稿続く)
聖書というのは読めば読むほど出エジプトが最大のテーマであり、これを云いたいために前後のエピソードがあるといってもいいくらいであると感じる。
即ち出エジプトの前のエピソードというのは、なぜユダヤ人がエジプトに奴隷として存在するのかを説明する導入部であると考えられる。そして出エジプト後のエピソードというのは、エジプトから連れ出すためにモーゼが神と結んだ契約を民が破ったため、民に天罰が下っては預言者が神にとりなすことの繰り返しと位置付けられる。これはイエス・キリスト登場以後の新約聖書も同様であり、イエスは預言者(あるいはメシア)であって“民”の範囲をユダヤ人以外にも拡大しただけと考えれば、これもまた出エジプトの延長線上にあるといえる。
これはアブラハムもモーゼもイエスもマホメットも預言者(もちろん最後に現れたマホメットが最高にエライという位置付けなのであるが)とするイスラムの考え方に近い。そしてキリスト教も成立初期段階ではこのような教義であったと考えられ、イエスの神性が認められるのはかなり後のことであろう。
キリスト教のその後の世界史に与えた影響を考えれば、世界史上の最重要事件のひとつといってもよい出エジプトがなぜおきたのか? それはモーゼがユダヤ人であったからではなく、元々はエジプト人であったモーゼが出エジプトという事件を起こすことによりユダヤ人という概念を創ったからであるというのが、これまでに述べてきたことの結論である。
なおこの結論は現在も議論されている“ユダヤ人とは何か”という課題に対してもひとつの示唆となるのではないかと思われる。ハザール人問題(7世紀の中央アジアのトルコ系民族でユダヤ教に集団改宗したという説がある)やサマリア人問題(これについては別に述べるつもり)、そしてドイッチャーやサルトルの著作などこの問題はさんざん議論されているが、結局は“自らをユダヤ人と考える人がユダヤ人である”というのが平凡ながら最大公約数的な定義であろうと思われ、それはユダヤ人の起源から考えればある意味当然の帰結といえるだろう。
さてこのようにエジプトから逃れてきたユダヤ人(エジプトから逃れることによってユダヤ人となった人々というべきか)であるが、パレスチナを征服・定住以後しばらくは聖書にはエジプトに関する記述はほとんどなくなる。これはパレスチナでの小競り合いが小部族同士(当時はイスラエルも統一国家は形成していない)の局地戦であり、エジプトも当時は衰退が始まりこの地方まで勢力を伸ばすことはできない時代であったからである。
それが統一イスラエル建国、そしてダビデ・ソロモンの両王の時代になるとイスラエルはオリエントの堂々たるメジャープレーヤーとなりエジプトとの関係が復活してくる。そしてその時代はさらにスーパー大国としてアッシリア・バビロニア・アケメネス朝ペルシアが次々に台頭してきて、イスラエルもエジプトもその波に飲み込まれて滅亡することになるのだが、そこでエジプトの衰亡はどのように描かれているのか?
(この稿続く)
馬形進さん
これまで述べてきた日本人と古代エジプト人が似ているのではないかというのは、良く言えば自主独立悪く云えば排他的なところに現われていると思います。
したがって日本人も古代エジプト人も他の民族を積極的に取り込もうとはしていないためその活動範囲は古代からあまり広がっていません。
これと正反対なのは中国人であり、こちらは中国文化を受け入れれば中国人ということでその範囲はどんどん広がっています。
もともと中国人というのは黄河中流域の中原に住む少数民族だったと思われ、それが周囲の民族を次々に取り込んで膨れ上がっていったのだと思います。歴代の統一王朝にせよ純粋に中国人の王朝といえるのは漢と宋くらいであって、あとはすべて異民族系の王朝と云ってもいいでしょう。つい100年ほど前まで中国を支配していた女真族は現在中国人と同化しつつあり、これで満州地域は中国に飲み込まれたといっていいかもしれません…となると次はどこか?
この差はどこにあるのか?
地勢からくるものかもしれません。日本の豊かな山河やエジプトのナイル流域の豊かさに対して、中国の大地は一般的な印象と異なり峻厳であり人が手を加えて初めて人が住めるようになります。ナイルが運ぶ黒土は肥沃な恵みの土であるのに対し、黄河が運ぶ黄土(文字通り河が土で黄色いのには驚きました)はあまり農業に適していません。
これまで述べてきた日本人と古代エジプト人が似ているのではないかというのは、良く言えば自主独立悪く云えば排他的なところに現われていると思います。
したがって日本人も古代エジプト人も他の民族を積極的に取り込もうとはしていないためその活動範囲は古代からあまり広がっていません。
これと正反対なのは中国人であり、こちらは中国文化を受け入れれば中国人ということでその範囲はどんどん広がっています。
もともと中国人というのは黄河中流域の中原に住む少数民族だったと思われ、それが周囲の民族を次々に取り込んで膨れ上がっていったのだと思います。歴代の統一王朝にせよ純粋に中国人の王朝といえるのは漢と宋くらいであって、あとはすべて異民族系の王朝と云ってもいいでしょう。つい100年ほど前まで中国を支配していた女真族は現在中国人と同化しつつあり、これで満州地域は中国に飲み込まれたといっていいかもしれません…となると次はどこか?
この差はどこにあるのか?
地勢からくるものかもしれません。日本の豊かな山河やエジプトのナイル流域の豊かさに対して、中国の大地は一般的な印象と異なり峻厳であり人が手を加えて初めて人が住めるようになります。ナイルが運ぶ黒土は肥沃な恵みの土であるのに対し、黄河が運ぶ黄土(文字通り河が土で黄色いのには驚きました)はあまり農業に適していません。
リドリー・スコットの“エクソダス“がまもなく公開されるようで、予告編が上映され始めた。セシル・B・デ・ミルの57年版十戒から60年近くがたっており、どんな作品になるのか楽しみである。
“聖書に出てくるエジプト“を書いていたが、ここ5年ほど中断。やはり前に書いた様に出エジプトが聖書の最大のテーマであるだけに、それ以後のエジプトの記載にはどうも精彩がなく、あまり取り上げる気持ちにならないうちにこの新作映画がもうすぐ公開なので久しぶりの書き込みを。
ユダヤ人の物語であるからエジプトはどうしても悪役・脇役になるのはやむを得ないが、それでもこれまでの映画で古代エジプトを詳細に描いているのは57年版十戒だと思うので今回も愉しみである。
聖書にはこの時代のファラオはパロ(ファラオ)とあるのみで、名前は記されていないのだがお約束事?として一番派手なラムセス2世ということになっており、57年版はユル・ブリンナー、そして今回はジョエル・エドガートンである。ジョエル・エドガートン?うーん知らんなあという感じで、最近では“華麗なるギャツビー”でデカプリオの初恋の人の夫を演じていたらしいがあまり印象にない。
こういうストーリーの作品は悪役に主役以上の存在感を出す大物を起用しないと格好がつかないもので、ヘストンに対するブリンナーはまさにその好例であるが、今回のモーゼはバットマンのクリスチャン・ベールだからはたして大丈夫か・・・
まあ役者はともかくリドリー・スコットは細部に凝る方だから古代エジプトのリアルな描写には期待できそうである。
“聖書に出てくるエジプト“を書いていたが、ここ5年ほど中断。やはり前に書いた様に出エジプトが聖書の最大のテーマであるだけに、それ以後のエジプトの記載にはどうも精彩がなく、あまり取り上げる気持ちにならないうちにこの新作映画がもうすぐ公開なので久しぶりの書き込みを。
ユダヤ人の物語であるからエジプトはどうしても悪役・脇役になるのはやむを得ないが、それでもこれまでの映画で古代エジプトを詳細に描いているのは57年版十戒だと思うので今回も愉しみである。
聖書にはこの時代のファラオはパロ(ファラオ)とあるのみで、名前は記されていないのだがお約束事?として一番派手なラムセス2世ということになっており、57年版はユル・ブリンナー、そして今回はジョエル・エドガートンである。ジョエル・エドガートン?うーん知らんなあという感じで、最近では“華麗なるギャツビー”でデカプリオの初恋の人の夫を演じていたらしいがあまり印象にない。
こういうストーリーの作品は悪役に主役以上の存在感を出す大物を起用しないと格好がつかないもので、ヘストンに対するブリンナーはまさにその好例であるが、今回のモーゼはバットマンのクリスチャン・ベールだからはたして大丈夫か・・・
まあ役者はともかくリドリー・スコットは細部に凝る方だから古代エジプトのリアルな描写には期待できそうである。
>>[25]、
エクソダスみたいですねぇ!
古代エジプトはいつほろんだのかというのは自分ではよくわかりません。ローマ時代も古代エジプトなんじゃないかと漠然とは考えていました。
エジプトはピラミッド時代から、数理的な文化センターの役割を果たしていますよね!そこにギリシア人が加わったからなのか、ローマ時代もとても文化センターですよね!更にイスラム時代も同様で、野蛮なヨーロッパへのルネッサンス期への文化の橋渡しを演じています!
こう考えると、自分は古代エジプトが終わったのって、アレキサンドリアを継承した文化センターが終わったころなんじゃないかなぁなんて勝手に考えています!オスマン帝国時代のエジプトの事はまだよく勉強していないのですが、多分、オスマン帝国時代に文化センターはイスタンブールに移ったのではないでしょうか??
エクソダスみたいですねぇ!
古代エジプトはいつほろんだのかというのは自分ではよくわかりません。ローマ時代も古代エジプトなんじゃないかと漠然とは考えていました。
エジプトはピラミッド時代から、数理的な文化センターの役割を果たしていますよね!そこにギリシア人が加わったからなのか、ローマ時代もとても文化センターですよね!更にイスラム時代も同様で、野蛮なヨーロッパへのルネッサンス期への文化の橋渡しを演じています!
こう考えると、自分は古代エジプトが終わったのって、アレキサンドリアを継承した文化センターが終わったころなんじゃないかなぁなんて勝手に考えています!オスマン帝国時代のエジプトの事はまだよく勉強していないのですが、多分、オスマン帝国時代に文化センターはイスタンブールに移ったのではないでしょうか??
最近の主流となりつつある考え方ではユダヤ人の歴史は出エジプトどころか千年近い後のバビロン捕囚くらいまでしか遡れないというのが正直なところのようです。
したがってダビデやソロモンの栄華もすべて神話に過ぎず、バビロニアに連行されたパレスチナ出身の民族が自分たちのアイデンティティーを創作するために壮大な神話体系を創り出したということになります。
ソロモン(がいたとされる)時代のパレスチナからは壮大な遺跡は出土せず、原始的な民族が暮らしていたと推定されるために導かれる結論であり、ロマンがない話ではありますがまあそんなものでしょうか。
こういう説は当時のエジプトの記録には出エジプトのことは全く出てこないため昔からありましたが、自分たちが負けたことは意図的に無視したか大エジプトにとってはそれほど重要な反乱ではなかったのだろうということで片付けられてきました。
この説が正しいとすれば出エジプト以後は聖書にはエジプトに関する記述がほとんどないことは納得できますし、バビロン捕囚のデジャヴとしてエジプトに関するエピソードは位置付けられるのかもしれません。
したがってダビデやソロモンの栄華もすべて神話に過ぎず、バビロニアに連行されたパレスチナ出身の民族が自分たちのアイデンティティーを創作するために壮大な神話体系を創り出したということになります。
ソロモン(がいたとされる)時代のパレスチナからは壮大な遺跡は出土せず、原始的な民族が暮らしていたと推定されるために導かれる結論であり、ロマンがない話ではありますがまあそんなものでしょうか。
こういう説は当時のエジプトの記録には出エジプトのことは全く出てこないため昔からありましたが、自分たちが負けたことは意図的に無視したか大エジプトにとってはそれほど重要な反乱ではなかったのだろうということで片付けられてきました。
この説が正しいとすれば出エジプト以後は聖書にはエジプトに関する記述がほとんどないことは納得できますし、バビロン捕囚のデジャヴとしてエジプトに関するエピソードは位置付けられるのかもしれません。
ユダヤ人の歴史がバビロン捕囚までしか遡れないと書いた前書き込みは言いすぎで、考古学的に確実視されているのはというニュアンスです。
現段階ではアッシリアによるイスラエル王国の滅亡(BC722)はほぼ史実とされているし、ソロモン王の治世からアッシリアによる侵攻までの2−300年の間のどこかの時点から聖書の記載はほぼ史実とみなされており、ユダヤ国家の基礎を築いた創業者は当然いただろうから、その人物をダビデ・ソロモンに託して少々盛ったとしても、それは神話に過ぎないとまでは云えない。ただし出エジプトまで遡ると神話の要素が強くなるが、ユダヤ人(と後世呼ばれるようになった民族)の中にエジプトからの武装難民が中心勢力としてあったことを反映した神話である可能性は高いというのが現段階での客観的な見解でしょうか。
このようにほぼ史実とか考古学的にはまだ確実とは云えないというのは、文献による推定が多く発掘により確かめられていないからでありこれは世界の古代史研究ではむしろ通常のことです。
これに対して古代エジプト史は”発掘”するまでもなく現在も眼前に大ピラミッドが聳え立っているのですから大ピラミッド内部には何の文字も残されていなかったとしてもこれは史実として疑う余地がありませんが、何の記録も残っていないだけにヨセフの倉庫だとか宇宙人などを持ち出してくる”自由な発想”が可能であり、それが古代エジプト史に夢を与えていると言えるでしょうか。
2009年から”聖書に出てくるエジプト”というこの駄文を書き始め、10年以上中断していましたが尻切れトンボ状態ながら一応これで終了とします。当時はmixiもまだ勢いがあったのですが今やいつサービスが終了してもおかしくないし・・・
35年ほど前に訪問したエジプトのイメージを元に書いていたのですが、死ぬまでにはもう一度行きたいものです。
現段階ではアッシリアによるイスラエル王国の滅亡(BC722)はほぼ史実とされているし、ソロモン王の治世からアッシリアによる侵攻までの2−300年の間のどこかの時点から聖書の記載はほぼ史実とみなされており、ユダヤ国家の基礎を築いた創業者は当然いただろうから、その人物をダビデ・ソロモンに託して少々盛ったとしても、それは神話に過ぎないとまでは云えない。ただし出エジプトまで遡ると神話の要素が強くなるが、ユダヤ人(と後世呼ばれるようになった民族)の中にエジプトからの武装難民が中心勢力としてあったことを反映した神話である可能性は高いというのが現段階での客観的な見解でしょうか。
このようにほぼ史実とか考古学的にはまだ確実とは云えないというのは、文献による推定が多く発掘により確かめられていないからでありこれは世界の古代史研究ではむしろ通常のことです。
これに対して古代エジプト史は”発掘”するまでもなく現在も眼前に大ピラミッドが聳え立っているのですから大ピラミッド内部には何の文字も残されていなかったとしてもこれは史実として疑う余地がありませんが、何の記録も残っていないだけにヨセフの倉庫だとか宇宙人などを持ち出してくる”自由な発想”が可能であり、それが古代エジプト史に夢を与えていると言えるでしょうか。
2009年から”聖書に出てくるエジプト”というこの駄文を書き始め、10年以上中断していましたが尻切れトンボ状態ながら一応これで終了とします。当時はmixiもまだ勢いがあったのですが今やいつサービスが終了してもおかしくないし・・・
35年ほど前に訪問したエジプトのイメージを元に書いていたのですが、死ぬまでにはもう一度行きたいものです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
古代エジプト 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-