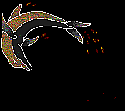金華山の山頂からは何らかの遺跡らしきものが出土するが、戦国時代の城築により壊滅状態。
金華山山系の上加納山を中心に、山麓にはかつては50数基の古墳があったことが知られている。
周辺の古墳を見ても、金華山の南側から東にかけて集中しています。
■稲葉山と伊奈波神社と因幡の関係
岐阜の金華山は通称名で、今でも稲葉山が正式名称なのだとか。
ではなぜ「イナバ」なのか。
因幡の白兎や大国主にまつわる伝説があるわけでもなく、伊奈波神社があるからイナバ山だとか、イナバ山だから伊奈波神社が祀られたでは卵が先かニワトリが先かになってしまいます。
ここからはわたしの推測でしかありませんが、美濃と因幡には日子坐王が深く関係しています。
この地を開拓したという日子坐王の一族が、イナバ山にイナバ大明神を祀ったのがはじまりではないかと…
鳥取(因幡国)の稲葉神社では、稲葉大明神が降臨して稲作を伝えたときに当地を稲庭(いなば)と命名したと伝わり、漢字表記の変換により稲場、稲羽、稲葉、因幡となったようです。
ちなみに、京都(丹後国)にある稲葉神社ではこの稲葉大明神を豊受大神と同神としています。
その丹後地方では豊受大神が稲作をはじめ半月状の苗代をつくったと伝わり、田庭、田場、丹波となり、但馬の地名にもつながるようです。
鳥取にも稲葉大明神が伝えたとされる古苗代とか大苗代と呼ばれる半月状の苗代があり、九月九日(上弦の頃)にお祭りをしていたとか。
イナバにまつわる話は尽きませんがここで話を戻すと、岐阜の伊奈波神社のご祭神は伊奈波大明神ですから、現在の金華山にこの神様をお祀りして稲作がはじまったことにより稲葉山と呼ばれるようになったのではないかと思います。
■日子坐王(彦坐王)による美濃の開拓
因幡国造は成務天皇の代に日子坐王の子によってはじまりますが、美濃の稲葉山周辺にも日子坐王一族がやってきて開拓したという伝承があり、伊奈波神社と縁の深い伊波乃西神社に日子坐王の墓があります。
岐阜金華山から東に向かって古墳が集中してますが、長良川左岸にある清水山の中腹に日子坐王の墓があり、その麓に伊波乃西神社が鎮座しています。
しかし、但馬の粟鹿神社にも日子坐王命の御陵と伝える古墳があるという。
なんでこんな場所にという感じですが、それでも伊波乃西神社にある墓の方が宮内庁管轄となっています。
伊奈乃西神社の祭神は日子坐命とその子、八爪入日子命(八爪命こと大根王)。
日子坐王の皇子=丹波道主の娘である日葉酢姫は、垂仁天皇に嫁ぎ五十瓊敷入彦命(伊奈波神社主神)と景行天皇を産む。
五十瓊敷入彦の后は渟熨斗姫命(金神社主神)である。
方県津神社の祭神、丹波之河上之摩須郎女命は丹波道主命の妻であり日葉酢姫の母である。
日子坐命墓
http://
伊波乃西神社
http://
方県津神社
http://
また、日子坐王の孫には曙立王がいます。
古事記には伊勢の佐奈造の祖は曙立王と記されており、手力男命を祀る佐奈神社には曙立王命が配祀されている。
美濃に手力雄神社が2社あるのも、そんな縁があるのかもしれません...
▽二つの手力雄神社
http://
■式内社美濃国厚見郡「物部神社」
伊奈波神社がある場所はもともと黒龍大神が祀られていた谷であり、戦国時代に城を築くため丸山にあった伊奈波神社を現在地へ遷座したと伝わる。
同じタイミングだったかどうかは不明だが、戦国時代まで南麓にあった式内社物部神社も伊奈波神社に合祀される。
伊奈波神社こそ物部神社だったとする説もありますが、わたしはもともと別だったとする説をとっています。
丸山は金華山山系の北西に位置し、現在その麓には岐阜公園や護国神社があります。
とりあえずここで、金華山山頂にあったであろう本宮に対して伊奈波神社が里宮だったという可能性はなくなります。
一方、式内社の物部神社(伊奈波神社は式内社ではない)は金華山の南麓に位置する岩戸にあったとされ、その跡形は微塵もないがこちらが里宮だったと推測しています。
つまり、その本宮となる山頂には古代からの祭祀遺跡があったのではないかと感じています。
金華山周辺はもともと厚見郡とか稲葉郡という地名で、三野後(みののしり)という国でもありました。
西の三野前(みののさき)国造が日子坐王の子八瓜命によってはじまったのに対し、東の三野後国造は物部氏の賀夫良命によりはじまった。
もしかしたら、因幡国造の日子坐王の系統と物部氏は同族なのかもしれません。
ちなみに、稲沢市の地名由来は稲葉村と小沢村の合併によるもので、尾張国の稲葉にも稲葉神社と金神社があります。
美濃国厚見郡の物部神社に物部十千根命がいたころ、尾張国中島郡には物部印葉連公と物部金弓連公がいたという記録があります。
そのまま印葉連公は稲葉神社、金弓連公は金神社につながる気がします。
▽式内社美濃国厚見郡三座について
http://
■五十瓊敷入彦と陸奥の金石伝説
伊奈波神社の祭神である五十瓊敷入彦は、父である垂仁天皇から因幡守を命ぜられます。
五十瓊敷入彦の弟、大足彦は後の景行天皇。
景行天皇の第二皇子が日本武です。
ときは景行天皇の時代。
景行は自分の息子に陸奥の金石を手に入れるよう命じたが失敗に終わったので、次に兄の五十瓊敷入彦に陸奥遠征を命じました。
兄は陸奥の金石を無事手にして都に戻る途中、見方の裏切りにより朝敵の汚名をきせられました。
逆賊とされていることを知らず、五十瓊敷入彦一行は美濃に差し掛かったところで朝廷軍に討たれます。
するとその金石がみるみる山となって身を隠し生きのびたとか、山中に入って一族もろとも死んでしまったとか。
その後、景行の夢枕には因幡大菩薩となった五十瓊敷入彦が現れた。
天皇の座を狙っていると騙されて殺してしまった兄が無実だったことを知ると、この山に因幡大菩薩を祀った。
・・・これは後世の後付的な部分もあるかと思いますが、稲葉山の由来としては最も相応しい伝承かもしれません。
...
金華山山系の上加納山を中心に、山麓にはかつては50数基の古墳があったことが知られている。
周辺の古墳を見ても、金華山の南側から東にかけて集中しています。
■稲葉山と伊奈波神社と因幡の関係
岐阜の金華山は通称名で、今でも稲葉山が正式名称なのだとか。
ではなぜ「イナバ」なのか。
因幡の白兎や大国主にまつわる伝説があるわけでもなく、伊奈波神社があるからイナバ山だとか、イナバ山だから伊奈波神社が祀られたでは卵が先かニワトリが先かになってしまいます。
ここからはわたしの推測でしかありませんが、美濃と因幡には日子坐王が深く関係しています。
この地を開拓したという日子坐王の一族が、イナバ山にイナバ大明神を祀ったのがはじまりではないかと…
鳥取(因幡国)の稲葉神社では、稲葉大明神が降臨して稲作を伝えたときに当地を稲庭(いなば)と命名したと伝わり、漢字表記の変換により稲場、稲羽、稲葉、因幡となったようです。
ちなみに、京都(丹後国)にある稲葉神社ではこの稲葉大明神を豊受大神と同神としています。
その丹後地方では豊受大神が稲作をはじめ半月状の苗代をつくったと伝わり、田庭、田場、丹波となり、但馬の地名にもつながるようです。
鳥取にも稲葉大明神が伝えたとされる古苗代とか大苗代と呼ばれる半月状の苗代があり、九月九日(上弦の頃)にお祭りをしていたとか。
イナバにまつわる話は尽きませんがここで話を戻すと、岐阜の伊奈波神社のご祭神は伊奈波大明神ですから、現在の金華山にこの神様をお祀りして稲作がはじまったことにより稲葉山と呼ばれるようになったのではないかと思います。
■日子坐王(彦坐王)による美濃の開拓
因幡国造は成務天皇の代に日子坐王の子によってはじまりますが、美濃の稲葉山周辺にも日子坐王一族がやってきて開拓したという伝承があり、伊奈波神社と縁の深い伊波乃西神社に日子坐王の墓があります。
岐阜金華山から東に向かって古墳が集中してますが、長良川左岸にある清水山の中腹に日子坐王の墓があり、その麓に伊波乃西神社が鎮座しています。
しかし、但馬の粟鹿神社にも日子坐王命の御陵と伝える古墳があるという。
なんでこんな場所にという感じですが、それでも伊波乃西神社にある墓の方が宮内庁管轄となっています。
伊奈乃西神社の祭神は日子坐命とその子、八爪入日子命(八爪命こと大根王)。
日子坐王の皇子=丹波道主の娘である日葉酢姫は、垂仁天皇に嫁ぎ五十瓊敷入彦命(伊奈波神社主神)と景行天皇を産む。
五十瓊敷入彦の后は渟熨斗姫命(金神社主神)である。
方県津神社の祭神、丹波之河上之摩須郎女命は丹波道主命の妻であり日葉酢姫の母である。
日子坐命墓
http://
伊波乃西神社
http://
方県津神社
http://
また、日子坐王の孫には曙立王がいます。
古事記には伊勢の佐奈造の祖は曙立王と記されており、手力男命を祀る佐奈神社には曙立王命が配祀されている。
美濃に手力雄神社が2社あるのも、そんな縁があるのかもしれません...
▽二つの手力雄神社
http://
■式内社美濃国厚見郡「物部神社」
伊奈波神社がある場所はもともと黒龍大神が祀られていた谷であり、戦国時代に城を築くため丸山にあった伊奈波神社を現在地へ遷座したと伝わる。
同じタイミングだったかどうかは不明だが、戦国時代まで南麓にあった式内社物部神社も伊奈波神社に合祀される。
伊奈波神社こそ物部神社だったとする説もありますが、わたしはもともと別だったとする説をとっています。
丸山は金華山山系の北西に位置し、現在その麓には岐阜公園や護国神社があります。
とりあえずここで、金華山山頂にあったであろう本宮に対して伊奈波神社が里宮だったという可能性はなくなります。
一方、式内社の物部神社(伊奈波神社は式内社ではない)は金華山の南麓に位置する岩戸にあったとされ、その跡形は微塵もないがこちらが里宮だったと推測しています。
つまり、その本宮となる山頂には古代からの祭祀遺跡があったのではないかと感じています。
金華山周辺はもともと厚見郡とか稲葉郡という地名で、三野後(みののしり)という国でもありました。
西の三野前(みののさき)国造が日子坐王の子八瓜命によってはじまったのに対し、東の三野後国造は物部氏の賀夫良命によりはじまった。
もしかしたら、因幡国造の日子坐王の系統と物部氏は同族なのかもしれません。
ちなみに、稲沢市の地名由来は稲葉村と小沢村の合併によるもので、尾張国の稲葉にも稲葉神社と金神社があります。
美濃国厚見郡の物部神社に物部十千根命がいたころ、尾張国中島郡には物部印葉連公と物部金弓連公がいたという記録があります。
そのまま印葉連公は稲葉神社、金弓連公は金神社につながる気がします。
▽式内社美濃国厚見郡三座について
http://
■五十瓊敷入彦と陸奥の金石伝説
伊奈波神社の祭神である五十瓊敷入彦は、父である垂仁天皇から因幡守を命ぜられます。
五十瓊敷入彦の弟、大足彦は後の景行天皇。
景行天皇の第二皇子が日本武です。
ときは景行天皇の時代。
景行は自分の息子に陸奥の金石を手に入れるよう命じたが失敗に終わったので、次に兄の五十瓊敷入彦に陸奥遠征を命じました。
兄は陸奥の金石を無事手にして都に戻る途中、見方の裏切りにより朝敵の汚名をきせられました。
逆賊とされていることを知らず、五十瓊敷入彦一行は美濃に差し掛かったところで朝廷軍に討たれます。
するとその金石がみるみる山となって身を隠し生きのびたとか、山中に入って一族もろとも死んでしまったとか。
その後、景行の夢枕には因幡大菩薩となった五十瓊敷入彦が現れた。
天皇の座を狙っていると騙されて殺してしまった兄が無実だったことを知ると、この山に因幡大菩薩を祀った。
・・・これは後世の後付的な部分もあるかと思いますが、稲葉山の由来としては最も相応しい伝承かもしれません。
...
|
|
|
|
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75501人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196033人
- 3位
- 独り言
- 9047人