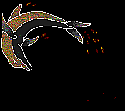縄文族ネットワーク [太陽の道] トピック(2007年2月作成)
http://
『日本書紀』は仁徳天皇六五年、和珥臣の祖・武振熊(タケフルクマ)が飛騨国の怪人・宿儺(スクナ)を退治したと伝える。
「六十五年、飛騨国に一人有り。宿儺と曰ふ。其れ為人、体を一にして両の面有り。面各相背けり。頂合ひて項無し。各手足有り。其れ膝有りて膕踵無し。力多にして軽く捷し。左右に剣を佩きて、四の手に並に弓矢を用ふ。是を以て、皇命に随はず。人民を掠略みて楽とす。是に、和珥臣の祖難波根子武振熊を遣して誅さしむ」
原文ではたったの八四文字、この話は『日本書紀』にのみあって『古事記』にはない。
しかも一度登場して誅殺されたあと正史に姿を見せないが、濃飛ではいまでも敬愛されている。
それでも美濃・飛騨の現地では両面宿儺への信仰に根強いものがあり、多くの古寺が両面宿儺を開基として「両面さま」「両面僧都」などと尊称している。
円空もこの土地感情に共感して、心をこめて両面宿儺を刻んでいる。
もちろん両面宿儺に関しては奥が深すぎて諸説あり。
なぜ大和朝廷が、応神朝の創建に活躍した有力な将軍・武振熊をわざわざ山深い辺地の凶賊一人のために派遣しなければならなかったか?
飛騨には大和朝廷にとって、高天原にも匹敵するほど重要な何かがあったのではないか...
例えば谷川健一氏の説によれば...
「美濃、飛騨は大和朝廷にまつろわない異族の国である。両面宿儺はその首長であると考えられている。」
としていて、これが一般的な解釈なのでは?
仁徳天皇六五年といえば西暦三七五年、つまり四世紀後半の古墳時代。
九州系景行王朝が神功、応神の時代に畿内に入った頃とちょうど重なります。
東方を支配した縄文の飛騨王朝の存在がちらつきます。
飛騨における古史古伝のひとつ、「竹内文献」。
その中では飛騨のことが「日球国」「日玉国」などと表記され、ピラミッド日本起源説をはじめ世界の中心たる大宮が置かれたと記されている。
昭和初期に成立した偽史とされるが、真意は別としてそうした隠された歴史があることは確かだと思います。
高山市南方にある位山にはピラミッドといわれた巨石群があり、方位計測に用いられたという。
位山を御神体山とする水無神社が古くから飛騨国一之宮として崇敬されながら、その祭神も諸説あって定かではない。
宿儺が座した位山は分水嶺で、太平洋側と日本海側の文化の双璧であり、ここを制したものが広大な支配力を持つことで飛騨王朝が実在した可能性があります。
両面宿儺の諸説に関して実在したとかしないとか、二人の人物を併せたとか、兄弟双生児であるとか。
また同一人物としてあげられるのが、日本武尊(ヤマトタケル)=別名ヤマトヲグナ、少彦名命(スクナヒコナ)、大碓・小碓、忍熊王(オシクマノミコ)であるともいわれています。
忍熊王とは第十四代仲哀天皇第二皇子のこと。
慣例として皇位につくはずが阻害され、神功皇后や武内宿禰らの軍のため淡海(近江)国瀬田川畔に追いつめられた。
『古事記』では宿儺を退治した武振熊が忍熊王を近江で入水に追い込んだとしているが、『日本書紀』ではその役を武内宿禰が果たしたことになっている。
しかし記紀ではっきり死んだとされている忍熊王が、越前に逃れたという伝説がある。
越前国の二ノ宮に国幣小社剣大明神(丹生軍織田町鎮座)があり、祭神はなんと忍熊王。
実は身代りを立てて越前国角鹿に遁れ後海路をへて織田荘の山間に入られ、織田郷開拓の祖神になられたというのが剣大明神社記の教うるところである。
そして、この剣大明神の神官家の一族からは後に戦国武将・織田信長が出ている。
また、大陸から来た神話が伝説化したとする説もある。
インドのヴェーダ神話に現れる至高の双神格ミトラ−ヴァルナ、ローマ神話の双面神ヤヌスとダブるイメージがある。
ミトラ−ヴァルナから分離独立した神ミトラが仏教に取り入れられて弥勒(ミロク)となり、さらに一世紀末頃のローマではミトラスの名で「不敗の神、太陽神」として崇拝されたこと。
これらの伝承が六世紀の新羅における弥勒崇拝に見受けられ、飛騨の宿儺は新羅系の勢力から弥勒=ミトラとして祭られたのではないかとする。
ヤマトタケルにも畿内を守護する神人と、畿内に侵攻する禍々しきものという二面性がある。
ヤマトタケルから見れば伊吹山の山神は畿内の東北(鬼門)に陣取る悪神である。
しかし、畿内から見ればヤマトタケル自身が東北から侵入する鬼神であった。
伊吹山頂には日本武尊像と共に弥勒像が祭られており、ここにも弥勒信仰と両面宿儺との関係が指摘される。
参考サイト:
両面宿儺伝説をめぐる奇想
http://
■位山と水無神社
神通川の上流、宮川の水源地である位山(くらいやま)を御神体山とする水無(みなし)神社。
その由緒には、神代の昔より表裏日本の分水嶺位山に鎮座せられ神通川、飛彈川の水主、水分の神として崇められたとある。
御祭神は、水無大神、御歳大神、を主神とし大己貴命、神武天皇、応神天皇、他11柱。
古くから飛騨国一之宮として崇敬されながら、その祭神は諸説あって定かではない。
水無神社の前方には小円墳、神楽山(前方後円墳)、位山が一直線上に並んでいるという。
さらに水無神社奥社から位山山頂(1529m)付近にかけて巨石群が点在し、天の岩戸や祭壇石など、古代からの巨石崇拝や太陽信仰に関係があるという。
位山の旧名は愛宝山(あわやま)だったが、その名前が示すように太古この地で天皇が位を授かったといわれています。
神武天皇が位山を訪れたという伝説が残っており、そのとき身一つにして面二つ手四本の両面四手の怪異な姿をした神が飛来し神武に王位を授けたので、この山を位山と呼ふようになったという。
また歴代天皇の即位の時は位山から伐採したイチイの木で笏(しゃく)を作り、太古より由緒のある一位の木の山としても知られる。
天智天皇が近江大津の宮を造営する際にこの山の木が使われ、その時に天皇から官位が与えられたため位山と呼ばれるようになったともいう...
▽金山巨石群の古代太陽暦
http://
■両面宿儺伝承
飛騨の千光寺や金山鎮守山、美濃国武儀日龍峰寺、肥田瀬暁堂寺では「飛騨国蜂賀の岩窟より宿儺出現」と伝えられ、乗鞍岳の麓、日面・出羽ヶ平(現高山市丹生川町)の岩窟がその地とされています。
各地に残された恩顧の伝説から、神祭りの司祭者として飛騨から美濃に及ぶ地域を統率し、農耕の指導者としても偉業を成したと考えられています...
*日龍峰寺(関市下之保)・・・コメント[01]
*暁堂寺(関市肥田瀬)・・・コメント[02]
*鎮守山観音堂(下呂市金山町)・・・コメント[03]
*千光寺(高山市丹生川町)
■円空の両面宿儺像
袈裟山千光寺は、仁徳時代に両面宿儺が開創したという寺伝を持つ。
貞享二年(1685)、円空はこの寺で両面宿儺を彫像し、ここを拠点として宿儺ゆかりの奥飛騨を行脚している...
▽長良川から見た円空と飛騨のエンクサマ
http://
...
http://
『日本書紀』は仁徳天皇六五年、和珥臣の祖・武振熊(タケフルクマ)が飛騨国の怪人・宿儺(スクナ)を退治したと伝える。
「六十五年、飛騨国に一人有り。宿儺と曰ふ。其れ為人、体を一にして両の面有り。面各相背けり。頂合ひて項無し。各手足有り。其れ膝有りて膕踵無し。力多にして軽く捷し。左右に剣を佩きて、四の手に並に弓矢を用ふ。是を以て、皇命に随はず。人民を掠略みて楽とす。是に、和珥臣の祖難波根子武振熊を遣して誅さしむ」
原文ではたったの八四文字、この話は『日本書紀』にのみあって『古事記』にはない。
しかも一度登場して誅殺されたあと正史に姿を見せないが、濃飛ではいまでも敬愛されている。
それでも美濃・飛騨の現地では両面宿儺への信仰に根強いものがあり、多くの古寺が両面宿儺を開基として「両面さま」「両面僧都」などと尊称している。
円空もこの土地感情に共感して、心をこめて両面宿儺を刻んでいる。
もちろん両面宿儺に関しては奥が深すぎて諸説あり。
なぜ大和朝廷が、応神朝の創建に活躍した有力な将軍・武振熊をわざわざ山深い辺地の凶賊一人のために派遣しなければならなかったか?
飛騨には大和朝廷にとって、高天原にも匹敵するほど重要な何かがあったのではないか...
例えば谷川健一氏の説によれば...
「美濃、飛騨は大和朝廷にまつろわない異族の国である。両面宿儺はその首長であると考えられている。」
としていて、これが一般的な解釈なのでは?
仁徳天皇六五年といえば西暦三七五年、つまり四世紀後半の古墳時代。
九州系景行王朝が神功、応神の時代に畿内に入った頃とちょうど重なります。
東方を支配した縄文の飛騨王朝の存在がちらつきます。
飛騨における古史古伝のひとつ、「竹内文献」。
その中では飛騨のことが「日球国」「日玉国」などと表記され、ピラミッド日本起源説をはじめ世界の中心たる大宮が置かれたと記されている。
昭和初期に成立した偽史とされるが、真意は別としてそうした隠された歴史があることは確かだと思います。
高山市南方にある位山にはピラミッドといわれた巨石群があり、方位計測に用いられたという。
位山を御神体山とする水無神社が古くから飛騨国一之宮として崇敬されながら、その祭神も諸説あって定かではない。
宿儺が座した位山は分水嶺で、太平洋側と日本海側の文化の双璧であり、ここを制したものが広大な支配力を持つことで飛騨王朝が実在した可能性があります。
両面宿儺の諸説に関して実在したとかしないとか、二人の人物を併せたとか、兄弟双生児であるとか。
また同一人物としてあげられるのが、日本武尊(ヤマトタケル)=別名ヤマトヲグナ、少彦名命(スクナヒコナ)、大碓・小碓、忍熊王(オシクマノミコ)であるともいわれています。
忍熊王とは第十四代仲哀天皇第二皇子のこと。
慣例として皇位につくはずが阻害され、神功皇后や武内宿禰らの軍のため淡海(近江)国瀬田川畔に追いつめられた。
『古事記』では宿儺を退治した武振熊が忍熊王を近江で入水に追い込んだとしているが、『日本書紀』ではその役を武内宿禰が果たしたことになっている。
しかし記紀ではっきり死んだとされている忍熊王が、越前に逃れたという伝説がある。
越前国の二ノ宮に国幣小社剣大明神(丹生軍織田町鎮座)があり、祭神はなんと忍熊王。
実は身代りを立てて越前国角鹿に遁れ後海路をへて織田荘の山間に入られ、織田郷開拓の祖神になられたというのが剣大明神社記の教うるところである。
そして、この剣大明神の神官家の一族からは後に戦国武将・織田信長が出ている。
また、大陸から来た神話が伝説化したとする説もある。
インドのヴェーダ神話に現れる至高の双神格ミトラ−ヴァルナ、ローマ神話の双面神ヤヌスとダブるイメージがある。
ミトラ−ヴァルナから分離独立した神ミトラが仏教に取り入れられて弥勒(ミロク)となり、さらに一世紀末頃のローマではミトラスの名で「不敗の神、太陽神」として崇拝されたこと。
これらの伝承が六世紀の新羅における弥勒崇拝に見受けられ、飛騨の宿儺は新羅系の勢力から弥勒=ミトラとして祭られたのではないかとする。
ヤマトタケルにも畿内を守護する神人と、畿内に侵攻する禍々しきものという二面性がある。
ヤマトタケルから見れば伊吹山の山神は畿内の東北(鬼門)に陣取る悪神である。
しかし、畿内から見ればヤマトタケル自身が東北から侵入する鬼神であった。
伊吹山頂には日本武尊像と共に弥勒像が祭られており、ここにも弥勒信仰と両面宿儺との関係が指摘される。
参考サイト:
両面宿儺伝説をめぐる奇想
http://
■位山と水無神社
神通川の上流、宮川の水源地である位山(くらいやま)を御神体山とする水無(みなし)神社。
その由緒には、神代の昔より表裏日本の分水嶺位山に鎮座せられ神通川、飛彈川の水主、水分の神として崇められたとある。
御祭神は、水無大神、御歳大神、を主神とし大己貴命、神武天皇、応神天皇、他11柱。
古くから飛騨国一之宮として崇敬されながら、その祭神は諸説あって定かではない。
水無神社の前方には小円墳、神楽山(前方後円墳)、位山が一直線上に並んでいるという。
さらに水無神社奥社から位山山頂(1529m)付近にかけて巨石群が点在し、天の岩戸や祭壇石など、古代からの巨石崇拝や太陽信仰に関係があるという。
位山の旧名は愛宝山(あわやま)だったが、その名前が示すように太古この地で天皇が位を授かったといわれています。
神武天皇が位山を訪れたという伝説が残っており、そのとき身一つにして面二つ手四本の両面四手の怪異な姿をした神が飛来し神武に王位を授けたので、この山を位山と呼ふようになったという。
また歴代天皇の即位の時は位山から伐採したイチイの木で笏(しゃく)を作り、太古より由緒のある一位の木の山としても知られる。
天智天皇が近江大津の宮を造営する際にこの山の木が使われ、その時に天皇から官位が与えられたため位山と呼ばれるようになったともいう...
▽金山巨石群の古代太陽暦
http://
■両面宿儺伝承
飛騨の千光寺や金山鎮守山、美濃国武儀日龍峰寺、肥田瀬暁堂寺では「飛騨国蜂賀の岩窟より宿儺出現」と伝えられ、乗鞍岳の麓、日面・出羽ヶ平(現高山市丹生川町)の岩窟がその地とされています。
各地に残された恩顧の伝説から、神祭りの司祭者として飛騨から美濃に及ぶ地域を統率し、農耕の指導者としても偉業を成したと考えられています...
*日龍峰寺(関市下之保)・・・コメント[01]
*暁堂寺(関市肥田瀬)・・・コメント[02]
*鎮守山観音堂(下呂市金山町)・・・コメント[03]
*千光寺(高山市丹生川町)
■円空の両面宿儺像
袈裟山千光寺は、仁徳時代に両面宿儺が開創したという寺伝を持つ。
貞享二年(1685)、円空はこの寺で両面宿儺を彫像し、ここを拠点として宿儺ゆかりの奥飛騨を行脚している...
▽長良川から見た円空と飛騨のエンクサマ
http://
...
|
|
|
|
コメント(7)
■日龍峰寺(関市下之保)
高沢山の山頂にある高沢観音こと日龍峯寺は、5世紀前半創建の県内最古の寺。
開祖とされる両面宿儺による悪龍退治の救民伝説が残っています。
飛騨の千光寺と同じ創建伝承を持ち、どちらも真言宗でご本尊は十一面千手観音である...
以下、公式ホームページより抜粋
http://www8.ocn.ne.jp/~takasawa/
自伝によると仁徳天皇の時代(五世紀前半)、飛騨の国に両面宿儺という豪族がいました。
両面宿儺は当地の豪族として権勢を誇っていた。
この異人天皇の聞に達し都に上り、御対面した。
その帰り、美濃加茂野ヶ原で休憩していると、何処からともなく鳩二羽が不思議なさえずりをなして、高沢の峰に飛び去った。
異人不思議に思い里人に尋ねると、「高沢の山脈に池あり、神龍住みて近郷の村人に危害を及ぼす」と聞き、はるかの峰に登り大悲の陀羅尼を唱え神龍を退散させこの峰に寺を開創したと云う。
...
高沢山の山頂にある高沢観音こと日龍峯寺は、5世紀前半創建の県内最古の寺。
開祖とされる両面宿儺による悪龍退治の救民伝説が残っています。
飛騨の千光寺と同じ創建伝承を持ち、どちらも真言宗でご本尊は十一面千手観音である...
以下、公式ホームページより抜粋
http://www8.ocn.ne.jp/~takasawa/
自伝によると仁徳天皇の時代(五世紀前半)、飛騨の国に両面宿儺という豪族がいました。
両面宿儺は当地の豪族として権勢を誇っていた。
この異人天皇の聞に達し都に上り、御対面した。
その帰り、美濃加茂野ヶ原で休憩していると、何処からともなく鳩二羽が不思議なさえずりをなして、高沢の峰に飛び去った。
異人不思議に思い里人に尋ねると、「高沢の山脈に池あり、神龍住みて近郷の村人に危害を及ぼす」と聞き、はるかの峰に登り大悲の陀羅尼を唱え神龍を退散させこの峰に寺を開創したと云う。
...
■鎮守山観音堂(下呂市金山町)
両面宿儺が37日間大陀羅尼をとなえ、国家安全・五穀豊穣を祈願して以来この山を鎮守山と呼ぶようになった。
村人が堂を新築して霊験あらたかな観音をむかえて祀った。
聖観音立像を中心とし左右に石仏35体を祀る現在の観音堂は弘化 3年(1846年)に再建されたもの。
両面宿儺と武振熊伝説
仁徳天皇の頃(西暦400年頃)、飛騨の地に大和朝廷に従わない、両面宿儺という人物がいた。
宿儺は二つの顔と四本の手を持つ怪人で、大和朝廷側の追討の将、難波根子武振熊(なにわのねこたけふるくま)と激しい戦いを繰り広げた。
宿儺は武振熊を向かえ撃つため、金山町の鎮守山に駐留し、その後武儀群下之保、高沢に飛び去ったという。
一方武振熊は、高沢で宿儺を破り、宿儺を追って飛騨の入り口である、金山町中津原に至り大岩の上に八幡様を勧請し、ここで戦勝を祈願した。
そのため、この大岩は「根子岩」(ねこいわ)と呼ばれている。
現在この地には下原八幡神社を祭り祭神は仁徳の先帝、応神と神功皇后で、古い飛騨街道に沿って、ここから高山までの(※)八幡神社にその伝説を残す。
(※)中津原(八幡神社)→乗政(水無八幡神社)→下呂(水無八幡神社)→上呂(久津八幡神社)→山之口(位山八幡神社)→一宮(水無八幡神社)→石浦(若宮八幡神社)→丹生川(相山八幡神社)
ちなみに、近くにある金山巨石群の岩屋(岩蔭遺跡)にも両面宿儺がいたんじゃないかと思うほどそっくりな「ヒヒ退治伝説」が残ってます...
▽金山巨石群の古代太陽暦
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39564520&comm_id=3180326
...
両面宿儺が37日間大陀羅尼をとなえ、国家安全・五穀豊穣を祈願して以来この山を鎮守山と呼ぶようになった。
村人が堂を新築して霊験あらたかな観音をむかえて祀った。
聖観音立像を中心とし左右に石仏35体を祀る現在の観音堂は弘化 3年(1846年)に再建されたもの。
両面宿儺と武振熊伝説
仁徳天皇の頃(西暦400年頃)、飛騨の地に大和朝廷に従わない、両面宿儺という人物がいた。
宿儺は二つの顔と四本の手を持つ怪人で、大和朝廷側の追討の将、難波根子武振熊(なにわのねこたけふるくま)と激しい戦いを繰り広げた。
宿儺は武振熊を向かえ撃つため、金山町の鎮守山に駐留し、その後武儀群下之保、高沢に飛び去ったという。
一方武振熊は、高沢で宿儺を破り、宿儺を追って飛騨の入り口である、金山町中津原に至り大岩の上に八幡様を勧請し、ここで戦勝を祈願した。
そのため、この大岩は「根子岩」(ねこいわ)と呼ばれている。
現在この地には下原八幡神社を祭り祭神は仁徳の先帝、応神と神功皇后で、古い飛騨街道に沿って、ここから高山までの(※)八幡神社にその伝説を残す。
(※)中津原(八幡神社)→乗政(水無八幡神社)→下呂(水無八幡神社)→上呂(久津八幡神社)→山之口(位山八幡神社)→一宮(水無八幡神社)→石浦(若宮八幡神社)→丹生川(相山八幡神社)
ちなみに、近くにある金山巨石群の岩屋(岩蔭遺跡)にも両面宿儺がいたんじゃないかと思うほどそっくりな「ヒヒ退治伝説」が残ってます...
▽金山巨石群の古代太陽暦
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39564520&comm_id=3180326
...
>>[005]
いや、僕は風*月さんには心底驚いて居ます。
僕もかつては似た様な事をやってたつもりでしたが、恥ずかしく成りました(笑)
日本のルーツ飛騨 って本を20代の飛騨への一人旅の時にお土産屋さん(穂高ロープウェイの近くの)で見付けて、いまだに愛読してます(笑)
ちなみにこの揺拝所に
修験道節律道場大峰蛇之倉七尾山
のステッカーを見付け、僕の合気の稽古の結願の地と決めました。
今年7月20日奇しくも泰澄大師の誕生日であり、木役小角開基・木曾御嶽山の地で開眼・会得しました。まあ、全然まだまだですけど。
トピ違いですが…
先日9月3日に白山登拝して来ました。
体調不良でしたがその根源をぶっ壊してやろうと登拝したら、2度本当に「死」を感じました(笑)
凄い山でした、白山。
麓の神社は泰澄さん開基で白山三所権現を祀ってるのですが、物凄い陰の気で巨岩と巨木が一体に成ってるモノが三座?三柱、坐すのですが見た目は民俗学の言う「神」です。有り難いモノでは無い。
只ただ、圧倒的でした。
それから何故か泰澄さん絡みの金沢市限定の天狗・九萬坊大権現との縁があり、その中に泰澄さん開基のお寺、
黒壁山・薬王寺
の境内の中に奥之院があり、岩窟も在りましたのでお篭りして来ました。
九萬坊大権現とは熊野修験行者だとする説があり、白山を拓いた泰澄さんを祝福したそうです。
実は三人組で、
九萬坊大権現
八萬坊大権現
照若坊大権現
が何処の九萬坊大権現でも祀られています。
元々は白山三所権現と同一視をされて居たとか居ないとか。
トピ違い失礼しました。
いや、僕は風*月さんには心底驚いて居ます。
僕もかつては似た様な事をやってたつもりでしたが、恥ずかしく成りました(笑)
日本のルーツ飛騨 って本を20代の飛騨への一人旅の時にお土産屋さん(穂高ロープウェイの近くの)で見付けて、いまだに愛読してます(笑)
ちなみにこの揺拝所に
修験道節律道場大峰蛇之倉七尾山
のステッカーを見付け、僕の合気の稽古の結願の地と決めました。
今年7月20日奇しくも泰澄大師の誕生日であり、木役小角開基・木曾御嶽山の地で開眼・会得しました。まあ、全然まだまだですけど。
トピ違いですが…
先日9月3日に白山登拝して来ました。
体調不良でしたがその根源をぶっ壊してやろうと登拝したら、2度本当に「死」を感じました(笑)
凄い山でした、白山。
麓の神社は泰澄さん開基で白山三所権現を祀ってるのですが、物凄い陰の気で巨岩と巨木が一体に成ってるモノが三座?三柱、坐すのですが見た目は民俗学の言う「神」です。有り難いモノでは無い。
只ただ、圧倒的でした。
それから何故か泰澄さん絡みの金沢市限定の天狗・九萬坊大権現との縁があり、その中に泰澄さん開基のお寺、
黒壁山・薬王寺
の境内の中に奥之院があり、岩窟も在りましたのでお篭りして来ました。
九萬坊大権現とは熊野修験行者だとする説があり、白山を拓いた泰澄さんを祝福したそうです。
実は三人組で、
九萬坊大権現
八萬坊大権現
照若坊大権現
が何処の九萬坊大権現でも祀られています。
元々は白山三所権現と同一視をされて居たとか居ないとか。
トピ違い失礼しました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89995人
- 3位
- 酒好き
- 170648人