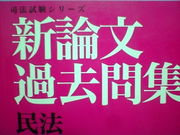|
|
|
|
コメント(5)
「答案」
1、Aが考えている2つの制度の関係をいかにとらえるべきか。
両制度の趣旨・要件・効果が関係してくるため、以下検討する。
2、制度趣旨について
(1) 110条は表見代理に基く。
すなわち、真正な代理権があるとの外観が存在し、その外観作出について本人に帰責性がある場合には、過失なく外観を信頼した相手方を保護しようとするものである。
(2) 715条は報償責任の法理に基づく。
すなわち、被用者を利用して利益をあげている者は、被用者によって生じた損
害についても責任を負うべき、という考えに基づく。
(3) このように、両者の制度趣旨は異なっている。
3 要件について
(1) 表見代理による請求が認められるための要件は、?基本代理権があること、?権限逸脱行為があること、?権限逸脱について善意・無過失であることである。
(2) 使用者責任による請求が認められるための要件は、?使用関係にあること、?職務を行うについてであること、?被用者が709条の要件を満たすこと、?使用者に免責事由がないこと、?職務の範囲外の行為から損害が生じている場合にはそれについて善意・無重過失であることである。
(3) 碓かに、715条では、「職務を行うについて」という要件が認められにくいようにも思える点、および、使用者の免責事由が定められている点で、要件が厳格なようにも思え
る。
しかし、職務としての外形があれば、「職務を行うについて」と認められるし、使用者の免責事由はほとんど認められないから、これらの点を理由に、715条の要件を厳格ということはできない。
さらに、110条では、基本代理権の認定が厳しいこと、および、軽過失のないことまで要求されることから、要件が厳格であるといえる。
以上より、使用者責任による請求の方が、表見責任による請求よりも要件が緩やかといえる。
4 効果について
(1) 表見代理に基く請求の場合、無権代理人のした行為が本人に帰属することから、代金全額の請求が認められる。
(2) 使用者責任に基づく請求の場合、使用者に対して代金相当額を損害賠償として請求しうるが、過失相殺(722条2項)によって減額される余地がある。
(3) よって、要件を満たした場合についてみると、表見代理による請求の方が、請求額全額が認められやすいといえる。
5 では、両者の関係をいかにとらえるべきか。
まず、確かに、本件のごとき取引的不法行為の事例において、本人・使用者に金銭を請求しうるという点は共通するも、前述のように、趣旨・要件・効果において大きく異なっている以上、両者を融合させる説はとりえない。
さらに、両者の競合を認めるべきか、一方を優先させるべきか。
思うに、要件は厳しいが金額をすべて認められる表見代理を主張してきた場合にそれを否定する理由はないし、他方、全額の請求は認められない可能性があるが、要件の緩やかな使用者責任を主張してきた場合にも、それを否定する理由はない。
すなわち、両者を競合させるべきである。
以上
1、Aが考えている2つの制度の関係をいかにとらえるべきか。
両制度の趣旨・要件・効果が関係してくるため、以下検討する。
2、制度趣旨について
(1) 110条は表見代理に基く。
すなわち、真正な代理権があるとの外観が存在し、その外観作出について本人に帰責性がある場合には、過失なく外観を信頼した相手方を保護しようとするものである。
(2) 715条は報償責任の法理に基づく。
すなわち、被用者を利用して利益をあげている者は、被用者によって生じた損
害についても責任を負うべき、という考えに基づく。
(3) このように、両者の制度趣旨は異なっている。
3 要件について
(1) 表見代理による請求が認められるための要件は、?基本代理権があること、?権限逸脱行為があること、?権限逸脱について善意・無過失であることである。
(2) 使用者責任による請求が認められるための要件は、?使用関係にあること、?職務を行うについてであること、?被用者が709条の要件を満たすこと、?使用者に免責事由がないこと、?職務の範囲外の行為から損害が生じている場合にはそれについて善意・無重過失であることである。
(3) 碓かに、715条では、「職務を行うについて」という要件が認められにくいようにも思える点、および、使用者の免責事由が定められている点で、要件が厳格なようにも思え
る。
しかし、職務としての外形があれば、「職務を行うについて」と認められるし、使用者の免責事由はほとんど認められないから、これらの点を理由に、715条の要件を厳格ということはできない。
さらに、110条では、基本代理権の認定が厳しいこと、および、軽過失のないことまで要求されることから、要件が厳格であるといえる。
以上より、使用者責任による請求の方が、表見責任による請求よりも要件が緩やかといえる。
4 効果について
(1) 表見代理に基く請求の場合、無権代理人のした行為が本人に帰属することから、代金全額の請求が認められる。
(2) 使用者責任に基づく請求の場合、使用者に対して代金相当額を損害賠償として請求しうるが、過失相殺(722条2項)によって減額される余地がある。
(3) よって、要件を満たした場合についてみると、表見代理による請求の方が、請求額全額が認められやすいといえる。
5 では、両者の関係をいかにとらえるべきか。
まず、確かに、本件のごとき取引的不法行為の事例において、本人・使用者に金銭を請求しうるという点は共通するも、前述のように、趣旨・要件・効果において大きく異なっている以上、両者を融合させる説はとりえない。
さらに、両者の競合を認めるべきか、一方を優先させるべきか。
思うに、要件は厳しいが金額をすべて認められる表見代理を主張してきた場合にそれを否定する理由はないし、他方、全額の請求は認められない可能性があるが、要件の緩やかな使用者責任を主張してきた場合にも、それを否定する理由はない。
すなわち、両者を競合させるべきである。
以上
「答案の解説」
事例問題というより、ほぼ1行問題です。
聞かれているのは、表見代理(民法第110条)と使用者責任(同法第715条)の二つの制度の関係。
となれば、両制度の趣旨・要件・効果を述べた後、両制度の関係に入っていくのがオーソドックスな方法ではないでしょうか。
2、まず、制度趣旨について、
110条は表見代理に、715条は報償責任の法理に基づくので、
両者の制度趣旨は異なっています。
3 要件について
(1) 表見代理の要件は、?基本代理権、?権限逸脱行為、?善意・無過失。
(2) 使用者責任の要件は、?使用関係、?職務を行うについて、?被用者が709条の要件を満たす、?免責事由がない、?職務の範囲外の場合、善意・無重過失。
(3) 110条では、基本代理権の認定が厳しいこと、軽過失のないことまで要求されることから、使用者責任による方が、表見責任によるよりも要件が緩やかといえる。
4 効果について
(1) 表見代理の場合、代金全額の請求が認められる。
(2) 使用者責任に基づく請求の場合、過失相殺(722条2項)によって減額される余地がある。
(3) よって、表見代理による請求の方が、請求額全額が認められやすいといえる。
5 では、両者の関係をいかにとらえるべきか。
両者の共通点を述べた後、両制度の趣旨・要件・効果が異なっていることを述べ、
両者の融合は認められないが、両者の競合は認めて良いのではないかとまとめて終わりました。
出題意図としては、両者の適用関係が聞かれているようです。
すなわち、表見代理が外観法理に基くことは当然ですが、
使用者責任も、外形標準説をとると、外形に対する信頼が問題となるので、
両者の適用領域が重なってきます。
じゃあ、110条と715条のどちらを優先させるの、と聞きたかったのではないでしょうか。
結論として、競合説をとりましたが、110条優先適用説も充分書けると思います。
事例問題というより、ほぼ1行問題です。
聞かれているのは、表見代理(民法第110条)と使用者責任(同法第715条)の二つの制度の関係。
となれば、両制度の趣旨・要件・効果を述べた後、両制度の関係に入っていくのがオーソドックスな方法ではないでしょうか。
2、まず、制度趣旨について、
110条は表見代理に、715条は報償責任の法理に基づくので、
両者の制度趣旨は異なっています。
3 要件について
(1) 表見代理の要件は、?基本代理権、?権限逸脱行為、?善意・無過失。
(2) 使用者責任の要件は、?使用関係、?職務を行うについて、?被用者が709条の要件を満たす、?免責事由がない、?職務の範囲外の場合、善意・無重過失。
(3) 110条では、基本代理権の認定が厳しいこと、軽過失のないことまで要求されることから、使用者責任による方が、表見責任によるよりも要件が緩やかといえる。
4 効果について
(1) 表見代理の場合、代金全額の請求が認められる。
(2) 使用者責任に基づく請求の場合、過失相殺(722条2項)によって減額される余地がある。
(3) よって、表見代理による請求の方が、請求額全額が認められやすいといえる。
5 では、両者の関係をいかにとらえるべきか。
両者の共通点を述べた後、両制度の趣旨・要件・効果が異なっていることを述べ、
両者の融合は認められないが、両者の競合は認めて良いのではないかとまとめて終わりました。
出題意図としては、両者の適用関係が聞かれているようです。
すなわち、表見代理が外観法理に基くことは当然ですが、
使用者責任も、外形標準説をとると、外形に対する信頼が問題となるので、
両者の適用領域が重なってきます。
じゃあ、110条と715条のどちらを優先させるの、と聞きたかったのではないでしょうか。
結論として、競合説をとりましたが、110条優先適用説も充分書けると思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
論文試験対策「民法」 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-