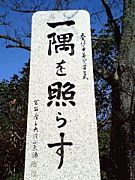五計
安岡正篤 照心語録 p86
生計・身計・家計・老計・死計の五つを宋の朱新仲は人生の五計という。
窮極我々の人生はこの五計を出ない。
“生計”は人生いかに生くべきかという、特に身心健康法のこと。
これを基にしてどうゆう社会生活・家庭生活を営むかが“身計・家計”である。
現代のように汚染された大衆文明社会にあって、人生の計を立ててゆくことは
非常に難しい。
個人の努力と同時に社会学的にも真剣に考慮されなくてはならぬ問題だ。
我々は“老いる”ということが必至の問題にあるにもかかわらず、とかく老を嫌う。
老を嫌う間は人間もまだ未熟だ。
歳とともに思想・学問が進み老いることに深い意義と喜びと誇りを持つようになるのが本当だ。
“老”という文字には三つの意味がある。一つは歳をとる。一つは練れる。三つは“考”と通用して、
思考が深まり、完成するという意味だ。
老いるとは単に馬齢を加えることではない。
その間に経験を積み、思想を深め、自己・人生を完成させていく努力の過程
なければならない。これを“老計”という。
それはまず学ぶことだ。学問は歳をとるほどよい。百歳になっての学問は、
実に深い味があろうと思う。老いてボケるというのは学問をしないからにすぎない。
革命・建設は決して青年だけでやれるものではない。
幾多の革命の歴史を徴しても、有為の青年の背後に必ず老先達がいる。
島津斉彬の薩摩藩における、周布政之助、村田清風の長州における等、みな同じである。
先輩と後輩の美しい協調があって初めて大業は成るのだ。
幕末・明治の青年たちには先輩に学ぼうという熱意があった。
先輩たちもそういう青年たちを非常に愛し、薫陶した。
現代のように軽薄青年と無志操な老人が相寄ったところで、
新時代の建設が出来るはずがない。
人生の五計の一つにいかに老いるかという老計があるが、
歳と共に多くの人生の苦難を経ていよいよ溌剌としてこそ、
真に老の価値がある。
女は幾人子供を産もうと瑞々しくあるのが本当だ。
老計はそのまま“死計”でもある。
いかに死すべきかは、いかに生くべきかと同じことだ。
死ぬということは、人間の性霊が限定された生から無限定の生に遷化することだからである。
仏教に有名な三身の輪がある。
一を法身(性命・性霊の本体)。
二に報身(法身が感覚的存在に発したもの)。
三を応身(法身・報身が要請に応じて形に現れたもの)という。
我々が死することは、この法身に返って尽未来際千変万化してゆくことだ。
幾多の先哲が歳月を超えて現代の我々に生きているのもこれである。
その意味で幽霊譚というのは非常に面白い。
人間の性命・性霊の理法を劇的に表現し、人間の芸術的道徳を与えたものだからだ。
幽霊にもなれないような人格では無力である。
〜〜〜〜〜〜〜
久しぶりに読んだ本です。
老いを考える年になったのだと
我ながら 自責の念があります。
日々 大切に生きます。
読んでいただき ありがとうございました。
安岡正篤 照心語録 p86
生計・身計・家計・老計・死計の五つを宋の朱新仲は人生の五計という。
窮極我々の人生はこの五計を出ない。
“生計”は人生いかに生くべきかという、特に身心健康法のこと。
これを基にしてどうゆう社会生活・家庭生活を営むかが“身計・家計”である。
現代のように汚染された大衆文明社会にあって、人生の計を立ててゆくことは
非常に難しい。
個人の努力と同時に社会学的にも真剣に考慮されなくてはならぬ問題だ。
我々は“老いる”ということが必至の問題にあるにもかかわらず、とかく老を嫌う。
老を嫌う間は人間もまだ未熟だ。
歳とともに思想・学問が進み老いることに深い意義と喜びと誇りを持つようになるのが本当だ。
“老”という文字には三つの意味がある。一つは歳をとる。一つは練れる。三つは“考”と通用して、
思考が深まり、完成するという意味だ。
老いるとは単に馬齢を加えることではない。
その間に経験を積み、思想を深め、自己・人生を完成させていく努力の過程
なければならない。これを“老計”という。
それはまず学ぶことだ。学問は歳をとるほどよい。百歳になっての学問は、
実に深い味があろうと思う。老いてボケるというのは学問をしないからにすぎない。
革命・建設は決して青年だけでやれるものではない。
幾多の革命の歴史を徴しても、有為の青年の背後に必ず老先達がいる。
島津斉彬の薩摩藩における、周布政之助、村田清風の長州における等、みな同じである。
先輩と後輩の美しい協調があって初めて大業は成るのだ。
幕末・明治の青年たちには先輩に学ぼうという熱意があった。
先輩たちもそういう青年たちを非常に愛し、薫陶した。
現代のように軽薄青年と無志操な老人が相寄ったところで、
新時代の建設が出来るはずがない。
人生の五計の一つにいかに老いるかという老計があるが、
歳と共に多くの人生の苦難を経ていよいよ溌剌としてこそ、
真に老の価値がある。
女は幾人子供を産もうと瑞々しくあるのが本当だ。
老計はそのまま“死計”でもある。
いかに死すべきかは、いかに生くべきかと同じことだ。
死ぬということは、人間の性霊が限定された生から無限定の生に遷化することだからである。
仏教に有名な三身の輪がある。
一を法身(性命・性霊の本体)。
二に報身(法身が感覚的存在に発したもの)。
三を応身(法身・報身が要請に応じて形に現れたもの)という。
我々が死することは、この法身に返って尽未来際千変万化してゆくことだ。
幾多の先哲が歳月を超えて現代の我々に生きているのもこれである。
その意味で幽霊譚というのは非常に面白い。
人間の性命・性霊の理法を劇的に表現し、人間の芸術的道徳を与えたものだからだ。
幽霊にもなれないような人格では無力である。
〜〜〜〜〜〜〜
久しぶりに読んだ本です。
老いを考える年になったのだと
我ながら 自責の念があります。
日々 大切に生きます。
読んでいただき ありがとうございました。
|
|
|
|
|
|
|
|
岡山 賢人塾 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
岡山 賢人塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208326人
- 3位
- 酒好き
- 170699人