学生時代に習った『歴史』や『美術』の教科書に載っている泰西名画をみて過去の巨匠の作品の素晴らしさに惹かれ、多くの日本人の西洋美術マニアは、原画を観てみたいと海外旅行にでかける人も多いですが、多額の経費がかかりますが、世界の名画を訪ねるツアーを繰り返しているひとも多いでしょう。そういうマニアの為に「泰西名画」が次々日本に招来される事も多くなり、嬉しい限りである。
巨匠の名画は、一つ一つが独立した存在であり、『○○展』という名のもとに美術館の壁に、競い合うように並べられてみると、これまた教科書的に視えて、本物であるのに関わらず、観客にもまれつつ、たんたんと流してみてしまうものですね。じっくり見直すのは、家に帰ってきて美術書や画集で見直すということになります。
リヒテンシュタイン美術館のある国の『リヒテンシュタイン侯国』は、小さな国で、昔から知っていることといえば、レオナルドダビンチの絵を豪華な切手にしてそれを収入の糧にもしているということでした。
その国自体は、オーストリアとスイスの間にある同国の国家元首であるリヒテンシュタイン侯爵家は、「優れた美術品収集こそが一族の栄誉との家訓」とのもとに、500年以上にわたってヨーロッパ美術の名品を収集してきましたそうです。その数は3万点に及び、英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクションといわれているとか。今回の日本展では、同コレクションから名品を選りすぐり、日本で初めて公開とのこと。世界屈指のルーベンス・コレクションからは、愛娘を描いた《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像(写真1)》などが来日。ラファエッロ、クラナッハ、レンブラント、ヴァン・ダイクをはじめとする巨匠たちの名画や、華麗な工芸品が一堂に並びます。
名門貴族リヒテンシュタイン侯爵家が収集した美術コレクションは、19世紀頃から公開されていたようですが、第二次世界大戦以降は一般の目に触れる機会はごく限られていたようで、ようやく2004年にウィーンの「夏の離宮」で一部が公開されるようになったようです。 外部での展覧会としては、1985-86年にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された大規模なコレクション展のほかは、ほとんど例がなく、日本でも四半世紀にわたって美術関係者の間で展覧会実現の努力が重ねられ、このたび、世界が羨む侯爵家の「秘宝」が初めて来日することになった、とネットやチラシに載ってありました。
京都展では、いくつかに別れた展示ブースには標題がつけられていました。
『圧巻バロックサロン』=ウィーン郊外ロッサウの侯爵家の「夏の離宮」は、華麗なバロック様式を特徴とし、その室内には今もなお、いにしえの宮廷さながらに、侯爵家の所蔵する絵画、彫刻、工芸品、家具調度が一堂に並べられています。本展では、その室内装飾と展示様式にもとづいた「バロック・サロン」を設け、華やかなバロック宮殿の雰囲気を再現します。総合芸術としてのバロック空間を体感していただけます。
『ヨーロッパ絵画史を至宝でたどる名画ギャラリー』=侯爵家の珠玉の絵画コレクションから選りすぐられた名画によって、ルネサンスからバロック、新古典主義までの西洋絵画史をたどります。ラファエッロ、クラナッハ、レンブラント、ヴァン・ダイクら巨匠たちの名画のほか、19世紀前半に中欧で流行したビーダーマイヤー様式の優美な絵画も並びます。
『この展覧会の見どころ』=名門貴族リヒテンシュタイン侯爵家が収集した美術コレクションは、総数約3万点にのぼり、英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクションといわれます。すでに19世紀には公開されていましたが、このたび、世界が羨む侯爵家の「秘宝」が初めて来日となるとのこと。
私が行った時の会場は、それほどの混雑はなく、自分の観たい絵の前にも、スムースにいけて、じっくりと鑑賞できました。
絵画以外に彫刻や工芸品も展示されていて、展覧会を鑑賞するというより、まさに美術館そのものを逍遥してる感じで鑑賞できてよかったです。
初公開と銘うっているものの、美術雑誌に掲載されている大家の一級品はなく、有名な巨匠の作品を原画で観れるという展覧会でした。
さて、大家の名画を観たうえでの感想ということにうつります。
こういう写実主義の絵を一堂にならべらてあるの光景を観ると、明治以後文明開化で、西洋美術に目覚めた日本人画家が、ヨーロッパに留学して、緻密な写実主義の膨大なコレクションを観て、自分の画力のなさにショックをうけるそうです。
大半の画家が、筆タッチののこる当時の流行の『印象派絵画』にとびついたのがわかるし、とうの印象派の画家の方も、日本人が見捨てていた『浮世絵』に啓発されていたというのも面白いとおもう。 岡目八目ですね。
時を同じくして併催されている『ゴッホ展』の方が長蛇の列でした。「あるてふことの不思議さよ!」と言った岸田劉生は、西洋写実主義のほうに傾倒したが、現代の日本人は『印象派』の方が好きなようです。
私が受けてきた学校の美術教育も『印象派』的な絵画技法だったので、筆跡をのこさない油彩画技法は授業では習えませんでした。写実絵画の方は、『写真』技術の登場ではやらなくなったし、写実絵画時代隆盛期には、つかう絵具は画家がアトリエで顔料から自作していたので、外では器材が多くて持ち運びができないので、外の現場では描けないのに対し、絵調合した絵具をつめられる「チューブ絵具」が発明されて、郊外で、写生で風景画も描けるようになったので、風景画が流行るようになり、そうして生まれた『印象派』の絵が人気になるのもうなづけます。
私としては、写実主義の絵の方にまだまだ心が惹かれます。
今回の招来作品では、リューベンス(写真1)が呼び物になってはいるものの、私は彼の作風がそれほど好きではなく、
自分が気に入った作品と言えば、ヴァン・ダイクの『マリア・デ・タンスの肖像』(写真3の絵)と、」クリストファー・アローリの『ホロフェルネスの首を持つユイディット』(写真2)でした。
父親ときていた幼い男の子が写真??の絵を観て父に何の絵と尋ねていたので、私が『ダビデとゴリアテ』という絵で聖書にある逸話を説明してあげました。
リヒテンシュタイン展は、日本ではこの京都展が最後ですよ(平成25年6月9日(日)迄)。
巨匠の名画は、一つ一つが独立した存在であり、『○○展』という名のもとに美術館の壁に、競い合うように並べられてみると、これまた教科書的に視えて、本物であるのに関わらず、観客にもまれつつ、たんたんと流してみてしまうものですね。じっくり見直すのは、家に帰ってきて美術書や画集で見直すということになります。
リヒテンシュタイン美術館のある国の『リヒテンシュタイン侯国』は、小さな国で、昔から知っていることといえば、レオナルドダビンチの絵を豪華な切手にしてそれを収入の糧にもしているということでした。
その国自体は、オーストリアとスイスの間にある同国の国家元首であるリヒテンシュタイン侯爵家は、「優れた美術品収集こそが一族の栄誉との家訓」とのもとに、500年以上にわたってヨーロッパ美術の名品を収集してきましたそうです。その数は3万点に及び、英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクションといわれているとか。今回の日本展では、同コレクションから名品を選りすぐり、日本で初めて公開とのこと。世界屈指のルーベンス・コレクションからは、愛娘を描いた《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像(写真1)》などが来日。ラファエッロ、クラナッハ、レンブラント、ヴァン・ダイクをはじめとする巨匠たちの名画や、華麗な工芸品が一堂に並びます。
名門貴族リヒテンシュタイン侯爵家が収集した美術コレクションは、19世紀頃から公開されていたようですが、第二次世界大戦以降は一般の目に触れる機会はごく限られていたようで、ようやく2004年にウィーンの「夏の離宮」で一部が公開されるようになったようです。 外部での展覧会としては、1985-86年にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された大規模なコレクション展のほかは、ほとんど例がなく、日本でも四半世紀にわたって美術関係者の間で展覧会実現の努力が重ねられ、このたび、世界が羨む侯爵家の「秘宝」が初めて来日することになった、とネットやチラシに載ってありました。
京都展では、いくつかに別れた展示ブースには標題がつけられていました。
『圧巻バロックサロン』=ウィーン郊外ロッサウの侯爵家の「夏の離宮」は、華麗なバロック様式を特徴とし、その室内には今もなお、いにしえの宮廷さながらに、侯爵家の所蔵する絵画、彫刻、工芸品、家具調度が一堂に並べられています。本展では、その室内装飾と展示様式にもとづいた「バロック・サロン」を設け、華やかなバロック宮殿の雰囲気を再現します。総合芸術としてのバロック空間を体感していただけます。
『ヨーロッパ絵画史を至宝でたどる名画ギャラリー』=侯爵家の珠玉の絵画コレクションから選りすぐられた名画によって、ルネサンスからバロック、新古典主義までの西洋絵画史をたどります。ラファエッロ、クラナッハ、レンブラント、ヴァン・ダイクら巨匠たちの名画のほか、19世紀前半に中欧で流行したビーダーマイヤー様式の優美な絵画も並びます。
『この展覧会の見どころ』=名門貴族リヒテンシュタイン侯爵家が収集した美術コレクションは、総数約3万点にのぼり、英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクションといわれます。すでに19世紀には公開されていましたが、このたび、世界が羨む侯爵家の「秘宝」が初めて来日となるとのこと。
私が行った時の会場は、それほどの混雑はなく、自分の観たい絵の前にも、スムースにいけて、じっくりと鑑賞できました。
絵画以外に彫刻や工芸品も展示されていて、展覧会を鑑賞するというより、まさに美術館そのものを逍遥してる感じで鑑賞できてよかったです。
初公開と銘うっているものの、美術雑誌に掲載されている大家の一級品はなく、有名な巨匠の作品を原画で観れるという展覧会でした。
さて、大家の名画を観たうえでの感想ということにうつります。
こういう写実主義の絵を一堂にならべらてあるの光景を観ると、明治以後文明開化で、西洋美術に目覚めた日本人画家が、ヨーロッパに留学して、緻密な写実主義の膨大なコレクションを観て、自分の画力のなさにショックをうけるそうです。
大半の画家が、筆タッチののこる当時の流行の『印象派絵画』にとびついたのがわかるし、とうの印象派の画家の方も、日本人が見捨てていた『浮世絵』に啓発されていたというのも面白いとおもう。 岡目八目ですね。
時を同じくして併催されている『ゴッホ展』の方が長蛇の列でした。「あるてふことの不思議さよ!」と言った岸田劉生は、西洋写実主義のほうに傾倒したが、現代の日本人は『印象派』の方が好きなようです。
私が受けてきた学校の美術教育も『印象派』的な絵画技法だったので、筆跡をのこさない油彩画技法は授業では習えませんでした。写実絵画の方は、『写真』技術の登場ではやらなくなったし、写実絵画時代隆盛期には、つかう絵具は画家がアトリエで顔料から自作していたので、外では器材が多くて持ち運びができないので、外の現場では描けないのに対し、絵調合した絵具をつめられる「チューブ絵具」が発明されて、郊外で、写生で風景画も描けるようになったので、風景画が流行るようになり、そうして生まれた『印象派』の絵が人気になるのもうなづけます。
私としては、写実主義の絵の方にまだまだ心が惹かれます。
今回の招来作品では、リューベンス(写真1)が呼び物になってはいるものの、私は彼の作風がそれほど好きではなく、
自分が気に入った作品と言えば、ヴァン・ダイクの『マリア・デ・タンスの肖像』(写真3の絵)と、」クリストファー・アローリの『ホロフェルネスの首を持つユイディット』(写真2)でした。
父親ときていた幼い男の子が写真??の絵を観て父に何の絵と尋ねていたので、私が『ダビデとゴリアテ』という絵で聖書にある逸話を説明してあげました。
リヒテンシュタイン展は、日本ではこの京都展が最後ですよ(平成25年6月9日(日)迄)。
|
|
|
|
コメント(2)
近現代の絵画は、絵から感性がわいてくるの有る無しで、その絵がいい絵とか好かないと言えるけど、ルネサンス期の絵は、表現は写実であっても寓意画が多く、絵に「標題」のある絵で、その標題の背景の意味がわからなければ、ただ、写真みたいに描けてる絵として見ると、絵の深さがわからないですね。私と一緒に観に行ってた家内は、茶華道の師範をしているので、東洋の山水画の方が自然な気分で絵を楽しめけど西洋絵画はわかりにくいわ‥‥と言ってました。
『ダビデとゴリアテ』の絵とか、『ホロフェルネスの首を持つユイディット』の絵などは、旧約聖書を読んで知っている人には、絵の世界の中に入り込んで味わえる絵になるんだけど、 それを知らない少年の目には、「何と怖い絵」としか思えないし、なんでこんな絵を描いたの?と父親に訊くだろう。
私の娘が3才のころの話ですが、私の持ってる美術書に興味を示したので、一つ一つ教えてたら、字も読めないのにいつの間にか覚えてしまい、本物を見せてみようと思い、法隆寺に連れて行ったら、金堂に入ると、「釈迦三尊がある」、宝物館に入ると「百済観音もある」って声をあげて感動してた。次々国宝の仏像名を3歳の子供が叫ぶので、周りにいた修学旅行生やお寺の坊さんも驚いていた。
『ダビデとゴリアテ』の絵とか、『ホロフェルネスの首を持つユイディット』の絵などは、旧約聖書を読んで知っている人には、絵の世界の中に入り込んで味わえる絵になるんだけど、 それを知らない少年の目には、「何と怖い絵」としか思えないし、なんでこんな絵を描いたの?と父親に訊くだろう。
私の娘が3才のころの話ですが、私の持ってる美術書に興味を示したので、一つ一つ教えてたら、字も読めないのにいつの間にか覚えてしまい、本物を見せてみようと思い、法隆寺に連れて行ったら、金堂に入ると、「釈迦三尊がある」、宝物館に入ると「百済観音もある」って声をあげて感動してた。次々国宝の仏像名を3歳の子供が叫ぶので、周りにいた修学旅行生やお寺の坊さんも驚いていた。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
絵画論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
絵画論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37840人
- 2位
- 酒好き
- 170673人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89537人
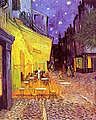
















![[芸術家×アート好]交流コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/71/77/297177_54s.gif)






