暗黙のうちに、コミュニティ『絵画論』で、副管理人から管理人アップとなってしまいました。
もともと好きなコミュニティで、参加当時から色々書込みしてましたが・・・
あれこれと多趣味で、日常も多忙なうえ、ミクシィのマイミクとのおつきあいも忙しく、更にお絵描きにもハマっているので、ここしばらく『絵画論』のコミュの運営をさぼっておりました。ごめんなさい!!
久しぶりにコメントします。以前からの経緯で、当『絵画論』のコミュでは洋の東西に関わらず、『絵画全般』にわたって論議するコミュにしておりますので、絵画の事から彫刻についてでも結構ですので、気軽に書込みしてくださいね。
さて、上村松園の『序の舞』についてとりあげてみます。
上村松園の『序の舞』(写真1)という絵が以前から好きでした。これぞ、近代日本画だと思っておりました。
そんな折りに、少し前ですが、NHK-BSで映画『序の舞』がオンエアーされました。私のかってな憶測で、描かれた作品の絵柄を観て、映画『序の舞』は、京都の芸子さんの舞踊をしきる井上流の井上八千代さんの伝記映画(ポスターをみただけでも京都の祇園の花柳界の裏話とおもってしまうデザイン)とばかり思い込んでいました。録画してみてみたら・・・なんと上村松園の伝記映画(写真2)だったのです。
みなさんは映画『序の舞』はみたことがありますか?
映画『序の舞』=(1983)」の中島貞夫、撮影は「白蛇抄」の森田富士郎がそれぞれ担当。
製作年 : 1984年
製作国 : 日本
配給 : 東映
キャスト(役名)?-?序の舞
岡田茉莉子?オカダマリコ ?(島村勢以)
名取裕子?ナトリユウコ ?(島村津也)
風間杜夫?カザマモリオ ?(西内太鳳)
水沢アキ?ミズサワアキ ?(島村志満)
三田村邦彦?ミタムラクニヒコ ?(村上徳二)
「序の舞」キャスト一覧
スタッフ?-?序の舞
監督 中島貞夫?ナカジマサダオ
原作 宮尾登美子?ミヤオトミコ
脚本 松田寛夫?マツダヒロオ
企画 日下部五朗?クサカベゴロウ 奈村協?
撮影 森田富士郎?モリタフジオ
音楽 黛敏郎?マユズミトシロウ
美術 井川徳道?イカワノリミチ 佐野義和?サノヨシカズ
編集 市田勇?イチダイサム
録音 栗山日出登?
●あらすじ=安政五年、洛北・大宮村の貧しい農家の娘・勢以は、京都の葉茶屋ちきりやに養女に出された。彼女が二十歳の年に、養父母・島村夫婦が相次いで世を去った。翌明治三年、勢以は婿養子をとったが、五年後には夫に先立たれ、二十六歳という女盛りで二児をかかえた後家になった。それからの勢以は、長女・志満と次女・津也を女手ひとつで育て、生計を支えるために、自ら女を捨てようとする。やがて時は流れ、絵に熱中しはじめた津也は、図画の西内先生のすすめもあって、小学校を卒業すると京でも有数の松溪画塾へ通うことになった。明治二十三年、第三回内国観業博覧会に津也が出品した「四季美人図」が一等褒状を射とめた。すでに師・松溪から「松翠」の雅号を授かっている津也は、早くも天才少女と騒がれる身となっており、勢以も津也の絵の情熱と才能を認めざるを得なくなった。その頃、西内先生がヨーロッパへ留学することになり、津也にとって大きな悲しみとなる。また、村上徳二という青年が松溪塾に入塾し、彼は津也に好意を抱くようになった。松溪の千枚描きに立会った日の夜、津也は師の誘いのままに、料亭へ出向き、抱かれる。徳二に片想いをしていた志満は、本家ちきりやのお内儀のすすめで西陣へ嫁いで行った。津也は絵に打込み、次々と賞をかち取っていったが、画塾内では松溪と津也の仲を言いたてるものもいた。月日が流れ、津也は妊娠した。それに気づいた勢以は、娘を激しく責め、相手が松溪と知り、津也に絵を禁じた。そして勢以は、津也の子を里子に出すことに決め、祇園で芸者をしていた喜代次を頼る。その喜代次の手引で、見知らぬ土地の農家で女児を出産した津也は、京には帰らず、東京にいる徳二を頼って行った。徳二との暮しの中でも、津也の中の絵への想いは捨てきれず、偶然、新聞で見かけた“西内太鳳ヨーロッパ帰朝展"の報に、津也は出かけて行く。そして、徳二に置手紙を残し、西内の滞在する長浜の昌徳寺に走った。西内は弟子にしてほしいと頼む津也のひたむきさに心動かされ、京に戻ると彼女に一軒の家を与えて絵の修業を続けさせた。明治二十九年、津也の「人生の春」が第五回日本美術院展の第一等に輝いた。光彩堂の招きでとある割烹に出向いた津也は、その席で松溪と再会する。かたくなな態度をとっていた津也も、老いた旧師が涙を流すのを見て、再び彼の腕の中に沈んで行った。津也はまた妊娠し、そのことを松溪に告げる。すると思いのほか“誰の子か"と冷たく突き放された。松溪は津也が太鳳の世話になっていることが面白くなく、ある展覧会の審査院として彼と顔を合わせた際、暴言を吐きちらした。津也と松溪の関係が続いていたことを知って激怒した太鳳は、津也に破門を言い渡す。津也は福井の高浜へ出かけ、おろし薬を飲んだ。漁師の電報で勢以は、すべてを許し、津也はちきりやで男の子を産んだが、父なし子を生んだことで世間の風当りはひどかった。三ヵ月後、津也は破門を許されて画壇に復帰した。大正七年、第一回文展の会場で、松翠の「母子」が注目を集めていた。そして、その前に立ちつくす松溪の姿があった。
いやぁ驚きました! 上村松園は、京都生れで、女流の美人画家なので、京都の豪商の上品な令嬢だとばかり思っていたら、波瀾万丈の情熱家だったということが解り、カルチャーショックでした。
人名事典などだけ読んでいても、彼女のはげしい情炎などは浮かんでこず、映画にでてくるような情景が全く思いもしませんでした。
■上村松園=(1875?1949)日本画家。本名津禰(つね)。明治8年4月23日京都に生まれる。1887年(明治20)京都府画学校に入学、鈴木松年(しようねん)に師事したが、翌年中退して松年塾に入り、さらに幸野楳嶺(こうのばいれい)、ついで竹内栖鳳(せいほう)に学んだ。90年第3回内国勧業博覧会で『四季美人図』が褒賞となり、その後日本美術協会、日本青年絵画共進会などに出品を続けて美人画に独自の境地を開いていった。1907年(明治40)の第1回文展で『長夜』が、翌年の第2回文展で『月かげ』が三等賞を受賞して画名が高まり、15年(大正4)第9回文展で『花がたみ』が二等賞になり、翌年永久無鑑査に推された。さらに24年帝展委員、34年(昭和9)帝展参与、41年帝国芸術院会員。48年(昭和23)に女性としては初めての文化勲章を受けたが、翌昭和24年8月28日、疎開先の奈良県平城(へいじよう)村の山荘で永眠。その画風は四条派の伝統を基礎にしてそれに近代感覚を盛ったもので、良家の、あるいは町方の女性を主題に清新な作品を描き続け、前期の情緒的な表現から後期の理知的表現への変化を認めることができる。前期を代表するのは前記の初期文展出品の二作のほか『焔(ほのお)』『娘深雪(むすめみゆき)』などで、後期には『母子』『序の舞』『雪月花』『夕暮』『晩秋』などがある。
*なお、(写真3)は本人の絵画制作中の実写真です!
さすが、宮尾登美子の筆に掛かると見事な女性の生き様が浮かび上がってきました。映画を見たら、画家本人の筆になる随筆などにも見当たらない、彼女出生の隠された秘話まででてきていました。映画に寄ると彼女は養女だったようなのです。
皆さんからの描き込みがあれば、更にに続けますが・・・・
とりあえず、絵画作品のタイトルとしての『序の舞』についてですが・・・
私は雅楽が好きなので『序の舞』という語句は以前から知っておりました。雅楽に合わせて踊る舞楽には『序』『破』『急』という三部構成で演奏して舞う形式があります。それから来ているのかと思っておりました。
ところが、あらためて調べてみると・・・謡曲の世界にも序之舞というのがあるようです。
●序之舞(じょのまい)=非常にゆったりしたテンポの、品格のある舞。大小物、太鼓入りの2種類があります。白拍子、遊女、高貴な女性の霊、女体の神霊・精霊等の舞と位置づけられます。羽衣、井筒、江口など。
これによると、上村松園が描いた『序の舞』が、絵柄とタイトルがぴたりとハマりますね。
そこで、このコミュのみなさんの『序の舞』を観た感じとかのコメントをよせてください。
その後、調べたコメント等を加えていきます。よろしく。
もともと好きなコミュニティで、参加当時から色々書込みしてましたが・・・
あれこれと多趣味で、日常も多忙なうえ、ミクシィのマイミクとのおつきあいも忙しく、更にお絵描きにもハマっているので、ここしばらく『絵画論』のコミュの運営をさぼっておりました。ごめんなさい!!
久しぶりにコメントします。以前からの経緯で、当『絵画論』のコミュでは洋の東西に関わらず、『絵画全般』にわたって論議するコミュにしておりますので、絵画の事から彫刻についてでも結構ですので、気軽に書込みしてくださいね。
さて、上村松園の『序の舞』についてとりあげてみます。
上村松園の『序の舞』(写真1)という絵が以前から好きでした。これぞ、近代日本画だと思っておりました。
そんな折りに、少し前ですが、NHK-BSで映画『序の舞』がオンエアーされました。私のかってな憶測で、描かれた作品の絵柄を観て、映画『序の舞』は、京都の芸子さんの舞踊をしきる井上流の井上八千代さんの伝記映画(ポスターをみただけでも京都の祇園の花柳界の裏話とおもってしまうデザイン)とばかり思い込んでいました。録画してみてみたら・・・なんと上村松園の伝記映画(写真2)だったのです。
みなさんは映画『序の舞』はみたことがありますか?
映画『序の舞』=(1983)」の中島貞夫、撮影は「白蛇抄」の森田富士郎がそれぞれ担当。
製作年 : 1984年
製作国 : 日本
配給 : 東映
キャスト(役名)?-?序の舞
岡田茉莉子?オカダマリコ ?(島村勢以)
名取裕子?ナトリユウコ ?(島村津也)
風間杜夫?カザマモリオ ?(西内太鳳)
水沢アキ?ミズサワアキ ?(島村志満)
三田村邦彦?ミタムラクニヒコ ?(村上徳二)
「序の舞」キャスト一覧
スタッフ?-?序の舞
監督 中島貞夫?ナカジマサダオ
原作 宮尾登美子?ミヤオトミコ
脚本 松田寛夫?マツダヒロオ
企画 日下部五朗?クサカベゴロウ 奈村協?
撮影 森田富士郎?モリタフジオ
音楽 黛敏郎?マユズミトシロウ
美術 井川徳道?イカワノリミチ 佐野義和?サノヨシカズ
編集 市田勇?イチダイサム
録音 栗山日出登?
●あらすじ=安政五年、洛北・大宮村の貧しい農家の娘・勢以は、京都の葉茶屋ちきりやに養女に出された。彼女が二十歳の年に、養父母・島村夫婦が相次いで世を去った。翌明治三年、勢以は婿養子をとったが、五年後には夫に先立たれ、二十六歳という女盛りで二児をかかえた後家になった。それからの勢以は、長女・志満と次女・津也を女手ひとつで育て、生計を支えるために、自ら女を捨てようとする。やがて時は流れ、絵に熱中しはじめた津也は、図画の西内先生のすすめもあって、小学校を卒業すると京でも有数の松溪画塾へ通うことになった。明治二十三年、第三回内国観業博覧会に津也が出品した「四季美人図」が一等褒状を射とめた。すでに師・松溪から「松翠」の雅号を授かっている津也は、早くも天才少女と騒がれる身となっており、勢以も津也の絵の情熱と才能を認めざるを得なくなった。その頃、西内先生がヨーロッパへ留学することになり、津也にとって大きな悲しみとなる。また、村上徳二という青年が松溪塾に入塾し、彼は津也に好意を抱くようになった。松溪の千枚描きに立会った日の夜、津也は師の誘いのままに、料亭へ出向き、抱かれる。徳二に片想いをしていた志満は、本家ちきりやのお内儀のすすめで西陣へ嫁いで行った。津也は絵に打込み、次々と賞をかち取っていったが、画塾内では松溪と津也の仲を言いたてるものもいた。月日が流れ、津也は妊娠した。それに気づいた勢以は、娘を激しく責め、相手が松溪と知り、津也に絵を禁じた。そして勢以は、津也の子を里子に出すことに決め、祇園で芸者をしていた喜代次を頼る。その喜代次の手引で、見知らぬ土地の農家で女児を出産した津也は、京には帰らず、東京にいる徳二を頼って行った。徳二との暮しの中でも、津也の中の絵への想いは捨てきれず、偶然、新聞で見かけた“西内太鳳ヨーロッパ帰朝展"の報に、津也は出かけて行く。そして、徳二に置手紙を残し、西内の滞在する長浜の昌徳寺に走った。西内は弟子にしてほしいと頼む津也のひたむきさに心動かされ、京に戻ると彼女に一軒の家を与えて絵の修業を続けさせた。明治二十九年、津也の「人生の春」が第五回日本美術院展の第一等に輝いた。光彩堂の招きでとある割烹に出向いた津也は、その席で松溪と再会する。かたくなな態度をとっていた津也も、老いた旧師が涙を流すのを見て、再び彼の腕の中に沈んで行った。津也はまた妊娠し、そのことを松溪に告げる。すると思いのほか“誰の子か"と冷たく突き放された。松溪は津也が太鳳の世話になっていることが面白くなく、ある展覧会の審査院として彼と顔を合わせた際、暴言を吐きちらした。津也と松溪の関係が続いていたことを知って激怒した太鳳は、津也に破門を言い渡す。津也は福井の高浜へ出かけ、おろし薬を飲んだ。漁師の電報で勢以は、すべてを許し、津也はちきりやで男の子を産んだが、父なし子を生んだことで世間の風当りはひどかった。三ヵ月後、津也は破門を許されて画壇に復帰した。大正七年、第一回文展の会場で、松翠の「母子」が注目を集めていた。そして、その前に立ちつくす松溪の姿があった。
いやぁ驚きました! 上村松園は、京都生れで、女流の美人画家なので、京都の豪商の上品な令嬢だとばかり思っていたら、波瀾万丈の情熱家だったということが解り、カルチャーショックでした。
人名事典などだけ読んでいても、彼女のはげしい情炎などは浮かんでこず、映画にでてくるような情景が全く思いもしませんでした。
■上村松園=(1875?1949)日本画家。本名津禰(つね)。明治8年4月23日京都に生まれる。1887年(明治20)京都府画学校に入学、鈴木松年(しようねん)に師事したが、翌年中退して松年塾に入り、さらに幸野楳嶺(こうのばいれい)、ついで竹内栖鳳(せいほう)に学んだ。90年第3回内国勧業博覧会で『四季美人図』が褒賞となり、その後日本美術協会、日本青年絵画共進会などに出品を続けて美人画に独自の境地を開いていった。1907年(明治40)の第1回文展で『長夜』が、翌年の第2回文展で『月かげ』が三等賞を受賞して画名が高まり、15年(大正4)第9回文展で『花がたみ』が二等賞になり、翌年永久無鑑査に推された。さらに24年帝展委員、34年(昭和9)帝展参与、41年帝国芸術院会員。48年(昭和23)に女性としては初めての文化勲章を受けたが、翌昭和24年8月28日、疎開先の奈良県平城(へいじよう)村の山荘で永眠。その画風は四条派の伝統を基礎にしてそれに近代感覚を盛ったもので、良家の、あるいは町方の女性を主題に清新な作品を描き続け、前期の情緒的な表現から後期の理知的表現への変化を認めることができる。前期を代表するのは前記の初期文展出品の二作のほか『焔(ほのお)』『娘深雪(むすめみゆき)』などで、後期には『母子』『序の舞』『雪月花』『夕暮』『晩秋』などがある。
*なお、(写真3)は本人の絵画制作中の実写真です!
さすが、宮尾登美子の筆に掛かると見事な女性の生き様が浮かび上がってきました。映画を見たら、画家本人の筆になる随筆などにも見当たらない、彼女出生の隠された秘話まででてきていました。映画に寄ると彼女は養女だったようなのです。
皆さんからの描き込みがあれば、更にに続けますが・・・・
とりあえず、絵画作品のタイトルとしての『序の舞』についてですが・・・
私は雅楽が好きなので『序の舞』という語句は以前から知っておりました。雅楽に合わせて踊る舞楽には『序』『破』『急』という三部構成で演奏して舞う形式があります。それから来ているのかと思っておりました。
ところが、あらためて調べてみると・・・謡曲の世界にも序之舞というのがあるようです。
●序之舞(じょのまい)=非常にゆったりしたテンポの、品格のある舞。大小物、太鼓入りの2種類があります。白拍子、遊女、高貴な女性の霊、女体の神霊・精霊等の舞と位置づけられます。羽衣、井筒、江口など。
これによると、上村松園が描いた『序の舞』が、絵柄とタイトルがぴたりとハマりますね。
そこで、このコミュのみなさんの『序の舞』を観た感じとかのコメントをよせてください。
その後、調べたコメント等を加えていきます。よろしく。
|
|
|
|
コメント(2)
絵画を好きになって、特定の画家に興味を持ち、画家の絵に対する思いを知る為に、画家本人が描いた画論や書籍を読んでみようようとしても、数も発行部数も少なく、それゆえ高価な価格で、なかなか手に入れて読む事が困難ですが・・・
こと、今回とりあげた上村松園の『画論』よんだことがおありでしょうか?
発見しましたよ!彼女の『画論」がいとも簡単に手に入り読めるんですよ。しかも無料で読めるんです。
下記の彼女の著作のリストです!
1 あゝ二十年 やっと御下命画を完成した私のよろこび
2 朝顔日記の深雪と淀君 (新字新仮名、作品ID:46524)
3 あのころ ??幼ものがたり??(新字新仮名、作品ID:46525)
4 浮世絵画家の肉筆 ??花は霞を透してひとしおの風情があるもの
5 絵だけ
6 絵筆に描き残す亡びゆく美しさ (新字新仮名、作品ID:49743)
7 応挙と其の時代が好き (新字旧仮名、作品ID:47979)
8 大田垣蓮月尼のこと (新字新仮名、作品ID:49742)
9 幼き頃の想い出 (新字新仮名、作品ID:47301)
10 帯の巾が広すぎる (新字新仮名、作品ID:49741)
11 思ひ出 (新字旧仮名、作品ID:47980)
12 想い出 絵の道五十年の足跡を顧みて(新字新仮名、作品ID:49740)
13 女の顔 (新字新仮名、作品ID:49739)
14 女の話・花の話 (新字新仮名、作品ID:47302)
15 画学校時代 (新字新仮名、作品ID:2407)
16 画室談義 (新字新仮名、作品ID:47304)
17 画道と女性 ??喜久子姫御用の「春秋屏風」その他?
18 画筆に生きる五十年 ??皇太后陛下御下命画に二十一年間の精進をこめて上納
19 軽女
20 簡潔の美 (新字新仮名、作品ID:47294)
21 寛政時代の娘納涼風俗 (新字新仮名、作品ID:49738)
22 北穂天狗の思い出 (新字新仮名、作品ID:49737)
23 砧 (新字新仮名、作品ID:49736)
24 絹と紙の話と師弟の間柄の話 (新字新仮名、作品ID:47307)
25 旧作 (新字新仮名、作品ID:43005)
26 九龍虫 (新字新仮名、作品ID:43006)
27 京のその頃 (新字新仮名、作品ID:47308)
28 京の夏景色 (新字新仮名、作品ID:47334)
29 苦楽 ある人の問いに答えて??絵を作る時の作家の心境について私はこう考えています。(新字新仮名、作品ID:47333)
30 芸術三昧即信仰 生きることに悶えた四十代(新字新仮名、作品ID:49735)
31 健康と仕事 (新字新仮名、作品ID:47332)
32 今日になるまで (新字新仮名、作品ID:49734)
33 税所敦子孝養図 (新字新仮名、作品ID:47331)
34 最初の出品画 ??四季美人図??(新字新仮名、作品ID:47330)
35 作画について (新字新仮名、作品ID:46526)
36 座右第一品 (新字新仮名、作品ID:47329)
37 三人の師 (新字新仮名、作品ID:46527)
38 「汐くみ」の画に就いて (新字新仮名、作品ID:46523)
39 四条通附近 (新字新仮名、作品ID:47328)
40 写生帖の思ひ出 (新字旧仮名、作品ID:47981)
41 車中有感 (新字新仮名、作品ID:46528)
42 三味線の胴 (新字新仮名、作品ID:49733)
43 縮図帖 (新字新仮名、作品ID:47327)
44 随想 (新字新仮名、作品ID:49732)
45 好きな髷のことなど (新字新仮名、作品ID:46529)
46 砂書きの老人 (新字新仮名、作品ID:43007)
47 棲霞軒雑記 (新字新仮名、作品ID:47326)
48 栖鳳先生を憶う (新字新仮名、作品ID:49731)
49 双語 (新字新仮名、作品ID:47325)
50 「草紙洗」を描いて (新字新仮名、作品ID:47297)
字数の関係で以下省略しますが
合計で83作の著作が、下記のネット図書館の『青空文庫」で閲覧する事ができます。勿論無料で、テキストファイルとしてパソコンにも録り込めるんですよ!
http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person355.html#sakuhin_list_1
青空文庫に上村松園の著作があることは知っておりました。まだじっくりと読んではいませんが、一度開いて読んでみてください!こんなに多くの本人の著作が自由に読めるんですよ!
こと、今回とりあげた上村松園の『画論』よんだことがおありでしょうか?
発見しましたよ!彼女の『画論」がいとも簡単に手に入り読めるんですよ。しかも無料で読めるんです。
下記の彼女の著作のリストです!
1 あゝ二十年 やっと御下命画を完成した私のよろこび
2 朝顔日記の深雪と淀君 (新字新仮名、作品ID:46524)
3 あのころ ??幼ものがたり??(新字新仮名、作品ID:46525)
4 浮世絵画家の肉筆 ??花は霞を透してひとしおの風情があるもの
5 絵だけ
6 絵筆に描き残す亡びゆく美しさ (新字新仮名、作品ID:49743)
7 応挙と其の時代が好き (新字旧仮名、作品ID:47979)
8 大田垣蓮月尼のこと (新字新仮名、作品ID:49742)
9 幼き頃の想い出 (新字新仮名、作品ID:47301)
10 帯の巾が広すぎる (新字新仮名、作品ID:49741)
11 思ひ出 (新字旧仮名、作品ID:47980)
12 想い出 絵の道五十年の足跡を顧みて(新字新仮名、作品ID:49740)
13 女の顔 (新字新仮名、作品ID:49739)
14 女の話・花の話 (新字新仮名、作品ID:47302)
15 画学校時代 (新字新仮名、作品ID:2407)
16 画室談義 (新字新仮名、作品ID:47304)
17 画道と女性 ??喜久子姫御用の「春秋屏風」その他?
18 画筆に生きる五十年 ??皇太后陛下御下命画に二十一年間の精進をこめて上納
19 軽女
20 簡潔の美 (新字新仮名、作品ID:47294)
21 寛政時代の娘納涼風俗 (新字新仮名、作品ID:49738)
22 北穂天狗の思い出 (新字新仮名、作品ID:49737)
23 砧 (新字新仮名、作品ID:49736)
24 絹と紙の話と師弟の間柄の話 (新字新仮名、作品ID:47307)
25 旧作 (新字新仮名、作品ID:43005)
26 九龍虫 (新字新仮名、作品ID:43006)
27 京のその頃 (新字新仮名、作品ID:47308)
28 京の夏景色 (新字新仮名、作品ID:47334)
29 苦楽 ある人の問いに答えて??絵を作る時の作家の心境について私はこう考えています。(新字新仮名、作品ID:47333)
30 芸術三昧即信仰 生きることに悶えた四十代(新字新仮名、作品ID:49735)
31 健康と仕事 (新字新仮名、作品ID:47332)
32 今日になるまで (新字新仮名、作品ID:49734)
33 税所敦子孝養図 (新字新仮名、作品ID:47331)
34 最初の出品画 ??四季美人図??(新字新仮名、作品ID:47330)
35 作画について (新字新仮名、作品ID:46526)
36 座右第一品 (新字新仮名、作品ID:47329)
37 三人の師 (新字新仮名、作品ID:46527)
38 「汐くみ」の画に就いて (新字新仮名、作品ID:46523)
39 四条通附近 (新字新仮名、作品ID:47328)
40 写生帖の思ひ出 (新字旧仮名、作品ID:47981)
41 車中有感 (新字新仮名、作品ID:46528)
42 三味線の胴 (新字新仮名、作品ID:49733)
43 縮図帖 (新字新仮名、作品ID:47327)
44 随想 (新字新仮名、作品ID:49732)
45 好きな髷のことなど (新字新仮名、作品ID:46529)
46 砂書きの老人 (新字新仮名、作品ID:43007)
47 棲霞軒雑記 (新字新仮名、作品ID:47326)
48 栖鳳先生を憶う (新字新仮名、作品ID:49731)
49 双語 (新字新仮名、作品ID:47325)
50 「草紙洗」を描いて (新字新仮名、作品ID:47297)
字数の関係で以下省略しますが
合計で83作の著作が、下記のネット図書館の『青空文庫」で閲覧する事ができます。勿論無料で、テキストファイルとしてパソコンにも録り込めるんですよ!
http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person355.html#sakuhin_list_1
青空文庫に上村松園の著作があることは知っておりました。まだじっくりと読んではいませんが、一度開いて読んでみてください!こんなに多くの本人の著作が自由に読めるんですよ!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
絵画論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
絵画論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人
- 3位
- 酒好き
- 170692人
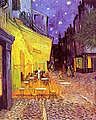
















![[芸術家×アート好]交流コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/71/77/297177_54s.gif)






