絵画ファンのコミュなので、ご覧になっている方があるかもしれませんが、NHK-BSのシリーズ『迷宮美術館』の放送で=すべての道はアートに=(道を題材にした名画特集)を見ていて、さすがぁ!・・・と感動したので、ここで紹介したいと思います。
俵屋宗達といえば『風神・雷神図屏風』(写真1)が有名ですね。ところが上記の放送でとりあげられていたのが『蔦の細道図屏風』(写真2/3 )という作品なのです。
■俵屋宗達=生没年は不詳。桃山から江戸初期の画家ですね。出身・伝記はつまびらかでないそうですが、およそ1600年(慶長5)ごろから1630年代にかけて活躍しました。京都の上層町衆の1人と思われ、公卿の烏丸光広(からすまみつひろ)や茶人千少庵(せんのしようあん)、書・陶芸・漆芸家として名高い本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)らとの親密な交際があったことでも有名ですね。『風神雷神図』(国宝、京都・建仁寺)をはじめ、『松島図』(ワシントン、フリーア美術館)、『関屋澪標(せきやみおつくし)図』(国宝、東京・静嘉堂(せいかどう))、『舞楽図』(重文、京都・醍醐(だいご)寺)などの傑作が有名。いずれも大胆な構図と金地に鮮麗な彩色を生かし、桃山障屏画(しようへいが)にかわる新しい装飾画様式を確立しました。
その『新しい装飾画様式』の例が『蔦の細道図屏風』(6曲2双の屏風)だというのです。
この作品は、俵屋宗達が描いた「蔦の細道図屏風」は、平安時代のプレイボーイの在原業平を書いた『伊勢物語』の第九段「業平東下り」の場面を描いたもので、緑青の平塗りで土坡を表し、金地を濃淡に二分して空と細道を象徴的に示した2枚の屏風絵なのです。パッとみれば、単純化した装飾的絵画にしか見えませんが、どれが道でどれが空なんだかよくわかりませんよね。道が空に続いてるようにも見えるし、道に蔦の葉があるし・・・・。
また屏風にはに『伊勢物語』の一節を公卿の烏丸光広(からすまみつひろ)の筆で書かれていますが、その書も蔦の葉に見立てているというのです。単なる漫画の吹き出しではなく、構図的にも考えられていて、粋なアイデアですね。オシャレですね。もう一つ驚いたのが、この屏風は、左右どちらに入れ替えてもつらなった『絵』として成り立つようにデザインされているのです。個々に掲載した『蔦の細道図屏風』の画像(写真2)はネットで検索して見つけて来たのですが、画素数が低いので詳細にはご覧頂けないのですが、そこで(写真2)をもとにに2枚の屏風を私が左右すげかえたのが(写真3 )なんです。どうでしょう?もう俵屋宗達は、感覚がまるでデザイナーそのものですね。
「蔦の細道図屏風」は重要文化財で、京都の相国寺蔵ということらしいですが、お寺にいけば、普段も見れるのでしょうかね?。実物を見てみたいですねぇ。皆さんも機会があったらお見逃しなく!
なんと、左右どちらでもつながる以外に『迷宮美術館』では、展覧会場では、屏風の展示は、写真みたいにケースの中でまっすぐひろげて襖のようにして掲示していますが、本来の立て方のように蛇腹で並べると、正面からだと全景が見れるし左側とか右側からとか斜めにみたら、またそれぞれの違った光景の『絵』にも見えるんだって!
まったく、こころにくい演出の絵ですねぇ・・・・・!
俵屋宗達といえば『風神・雷神図屏風』(写真1)が有名ですね。ところが上記の放送でとりあげられていたのが『蔦の細道図屏風』(写真2/3 )という作品なのです。
■俵屋宗達=生没年は不詳。桃山から江戸初期の画家ですね。出身・伝記はつまびらかでないそうですが、およそ1600年(慶長5)ごろから1630年代にかけて活躍しました。京都の上層町衆の1人と思われ、公卿の烏丸光広(からすまみつひろ)や茶人千少庵(せんのしようあん)、書・陶芸・漆芸家として名高い本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)らとの親密な交際があったことでも有名ですね。『風神雷神図』(国宝、京都・建仁寺)をはじめ、『松島図』(ワシントン、フリーア美術館)、『関屋澪標(せきやみおつくし)図』(国宝、東京・静嘉堂(せいかどう))、『舞楽図』(重文、京都・醍醐(だいご)寺)などの傑作が有名。いずれも大胆な構図と金地に鮮麗な彩色を生かし、桃山障屏画(しようへいが)にかわる新しい装飾画様式を確立しました。
その『新しい装飾画様式』の例が『蔦の細道図屏風』(6曲2双の屏風)だというのです。
この作品は、俵屋宗達が描いた「蔦の細道図屏風」は、平安時代のプレイボーイの在原業平を書いた『伊勢物語』の第九段「業平東下り」の場面を描いたもので、緑青の平塗りで土坡を表し、金地を濃淡に二分して空と細道を象徴的に示した2枚の屏風絵なのです。パッとみれば、単純化した装飾的絵画にしか見えませんが、どれが道でどれが空なんだかよくわかりませんよね。道が空に続いてるようにも見えるし、道に蔦の葉があるし・・・・。
また屏風にはに『伊勢物語』の一節を公卿の烏丸光広(からすまみつひろ)の筆で書かれていますが、その書も蔦の葉に見立てているというのです。単なる漫画の吹き出しではなく、構図的にも考えられていて、粋なアイデアですね。オシャレですね。もう一つ驚いたのが、この屏風は、左右どちらに入れ替えてもつらなった『絵』として成り立つようにデザインされているのです。個々に掲載した『蔦の細道図屏風』の画像(写真2)はネットで検索して見つけて来たのですが、画素数が低いので詳細にはご覧頂けないのですが、そこで(写真2)をもとにに2枚の屏風を私が左右すげかえたのが(写真3 )なんです。どうでしょう?もう俵屋宗達は、感覚がまるでデザイナーそのものですね。
「蔦の細道図屏風」は重要文化財で、京都の相国寺蔵ということらしいですが、お寺にいけば、普段も見れるのでしょうかね?。実物を見てみたいですねぇ。皆さんも機会があったらお見逃しなく!
なんと、左右どちらでもつながる以外に『迷宮美術館』では、展覧会場では、屏風の展示は、写真みたいにケースの中でまっすぐひろげて襖のようにして掲示していますが、本来の立て方のように蛇腹で並べると、正面からだと全景が見れるし左側とか右側からとか斜めにみたら、またそれぞれの違った光景の『絵』にも見えるんだって!
まったく、こころにくい演出の絵ですねぇ・・・・・!
|
|
|
|
|
|
|
|
絵画論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
絵画論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人
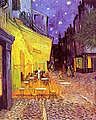
















![[芸術家×アート好]交流コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/71/77/297177_54s.gif)






