風景画にスポットをあててみました。
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(写真3=ターナーの自画像)
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallard William Turner, 1775年4月23日 - 1851年12月19日)は、18世紀末?19世紀のイギリスのロマン主義の画家です。イギリスを代表する国民的画家であるとともに、西洋絵画史における最初の本格的な風景画家の一人といわれています。
大学受験の勉強に使っていた旺文社の英語の参考書に、フランスのアランという哲学者の「名言」に、ターナーのことが出ていたのが私が彼の作品に関心をもつきっかけでした。その「名言」では
「ターナーは文盲だった。それ故に、彼の絵が他の画家より色彩が豊かな作品となったのだ」というような内容だった。文字が読めなかったので、理屈にとらわれることなく、逆に感性のあふれる画風ができたとアランは評価しているのです。 そこで、あらためて彼の経歴を調べてみました。
ターナー(人物・経歴)=1775年ロンドンのコヴェント・ガーデンに理髪師の子として生まれる。母親は精神疾患をもち、息子の世話を十分にすることができなかった。そのために彼は学校教育もほとんど受けず、特異な環境で少年時代を過ごしたようである(*アランはこの少年期の境遇の事を指摘していたのだろう)。
13歳の時、風景画家トーマス・マートンに弟子入りし、絵画の基礎を学んだそうです。当時の「風景画家」の仕事は、特定の場所の風景を念入りに再現した「名所絵」のような作品を制作するという、今で言う写真屋さんのようなものだった。マートンの元で1年ほど修業したターナーは、ロイヤル・アカデミー附属美術学校に入学。1797年にはロイヤル・アカデミーに油彩画を初出品し、1799年には24歳の若さでロイヤル・アカデミー準会員となり、1802年、27歳の時には同・正会員となっている。
ターナーにとって転機となったのが、1819年、44歳の時のイタリア旅行であったらしい。ルネサンス期以来、長らく西洋美術の中心地であったイタリアへ行くことは、イギリスのような北方の国の画家たちにとってのあこがれであり、ターナーもその例外ではなかった。イタリアの明るい陽光と色彩に魅せられたターナーは、特にヴェネツィアの街をこよなく愛し、その後も何度も訪れ、多くのスケッチを残している。イタリア旅行後の作品は、画面における大気と光の効果を追求することに主眼がおかれ、そのため、描かれている事物の形態はあいまいになり、ほとんど抽象に近づいている作品もあるそうです。
彩色の傾向=ターナーが好んで使用した色は黄色である。現存している彼の絵具箱では色の大半が黄色系統の色で占められているそうです。逆に、嫌いな色は緑色のようで、緑を極力使わないよう苦心していた。ターナーは知人の一人に対して「木を描かずに済めばありがたい」とまで語っている。また別の知人から、ヤシの木を黄色く描いているところを注意された時には、激しく動揺している。こんなエピソードも聴いた事があります。ロンドンの市街の大火の時に、人々が驚きあって狼狽しているのに、ターナーは夜空に広がる炎に感嘆して、ひたすら大火の模様をスケッチしていたそうです。
(写真2=『雨、蒸気、スピード‐グレート・ウェスタン鉄道』 (1844) )=1842年に制作された『吹雪‐港の沖合の蒸気船』では、蒸気船はぼんやりとした塊に過ぎず、巨大な波、水しぶき、吹雪といった自然の巨大なエネルギーを描き出している。この姿勢で描かれた彼の作品は、「印象派」を30年も先取りした先駆的な作品であったが、発表当時は、「石鹸水と水漆喰で描かれた」などと酷評されている。又、この作品を制作するために、ターナーはマストに4時間も縛りつけてもらい、嵐の様子をを観察していたという逸話が残っています。
代表作は何と言っても「 解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号」(1838)」(写真1)です。
テメレーア (戦列艦)=(HMS Temerarious, 1798) はイギリス海軍の軍艦で、98門搭載の二等戦列艦。トラファルガー海戦に参加している。世界的にはターナーの絵画に描かれたことで著名な船になっている。同名の軍艦としてはイギリス海軍では2代目で、1938年に描かれた掲出の「解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号」(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)は、世界的な名画と言われ、2005年に行われたイギリス国内の一般投票により「最も偉大なイギリス絵画」に選ばれているそうです。日本語では「戦艦テメレール号」となっていますが、原語では「Fighting Temerarious」であり、トラファルガーでの奮闘をたたえる愛称となっている。
一枚の絵としては、一日の終わりの夕映えの中を、任務を負えてスクラップ化されるために曳航されている嘗ての戦艦の姿を描いた絵である。この絵は、単なる夕方の港を描いた風景画ではなく、観る人がみれば、栄光ある戦歴の戦艦も引退をむかえるときがきたという、まさに人生の黄昏を風景上にあらわしていとも受け止められ、これぞ名画中の名画といわれる由縁なのです。
三島由紀夫も、この絵にいたく感動していたようで、そこから小説「午後の曳航」という作品を発表している。
この三島由紀夫の小説は、日本のみならず、海外でも評価され、映画化までされています。
映画「午後の曳航」=とある港町を舞台に、少年と未亡人である母親の前に現れた男との関係や心の葛藤を描いた作品。サラ・マイルズ、クリス・クリストファーソンほか出演。
スタッフ/キャスト
出演者:サラ・マイルズ/クリス・クリストファーソン/ジョナサン・カーン
監督:ルイス・ジョン・カリーノ
原作:三島由紀夫
撮影は、英国映画界の重鎮ダグラス・スローカムで、青く冷たい海の映像は極めて印象的。ジョニー・マンデルのスコアは映画音楽でも屈指の名曲である。
あらすじ=英国の港町。13歳の少年ジョナサンは、母のアンとふたり暮らしをしていた。ある日、母にせがんで大きな外洋船ベル号の見学に出かけたジョナサンは、そこで出会った二等航海士のジムに強烈な憧憬を抱くようになる。そして未亡人となって久しいアンもまた、逞しいジムに官能を覚える。三島由紀夫の中期の代表作であり、「金閣寺」と並んで海外でも人気の高く、「午後の曳航」を日英合作による映画化がなされたのです。
一枚の絵からでも、多大な影響を与えるものなのですね!
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(写真3=ターナーの自画像)
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallard William Turner, 1775年4月23日 - 1851年12月19日)は、18世紀末?19世紀のイギリスのロマン主義の画家です。イギリスを代表する国民的画家であるとともに、西洋絵画史における最初の本格的な風景画家の一人といわれています。
大学受験の勉強に使っていた旺文社の英語の参考書に、フランスのアランという哲学者の「名言」に、ターナーのことが出ていたのが私が彼の作品に関心をもつきっかけでした。その「名言」では
「ターナーは文盲だった。それ故に、彼の絵が他の画家より色彩が豊かな作品となったのだ」というような内容だった。文字が読めなかったので、理屈にとらわれることなく、逆に感性のあふれる画風ができたとアランは評価しているのです。 そこで、あらためて彼の経歴を調べてみました。
ターナー(人物・経歴)=1775年ロンドンのコヴェント・ガーデンに理髪師の子として生まれる。母親は精神疾患をもち、息子の世話を十分にすることができなかった。そのために彼は学校教育もほとんど受けず、特異な環境で少年時代を過ごしたようである(*アランはこの少年期の境遇の事を指摘していたのだろう)。
13歳の時、風景画家トーマス・マートンに弟子入りし、絵画の基礎を学んだそうです。当時の「風景画家」の仕事は、特定の場所の風景を念入りに再現した「名所絵」のような作品を制作するという、今で言う写真屋さんのようなものだった。マートンの元で1年ほど修業したターナーは、ロイヤル・アカデミー附属美術学校に入学。1797年にはロイヤル・アカデミーに油彩画を初出品し、1799年には24歳の若さでロイヤル・アカデミー準会員となり、1802年、27歳の時には同・正会員となっている。
ターナーにとって転機となったのが、1819年、44歳の時のイタリア旅行であったらしい。ルネサンス期以来、長らく西洋美術の中心地であったイタリアへ行くことは、イギリスのような北方の国の画家たちにとってのあこがれであり、ターナーもその例外ではなかった。イタリアの明るい陽光と色彩に魅せられたターナーは、特にヴェネツィアの街をこよなく愛し、その後も何度も訪れ、多くのスケッチを残している。イタリア旅行後の作品は、画面における大気と光の効果を追求することに主眼がおかれ、そのため、描かれている事物の形態はあいまいになり、ほとんど抽象に近づいている作品もあるそうです。
彩色の傾向=ターナーが好んで使用した色は黄色である。現存している彼の絵具箱では色の大半が黄色系統の色で占められているそうです。逆に、嫌いな色は緑色のようで、緑を極力使わないよう苦心していた。ターナーは知人の一人に対して「木を描かずに済めばありがたい」とまで語っている。また別の知人から、ヤシの木を黄色く描いているところを注意された時には、激しく動揺している。こんなエピソードも聴いた事があります。ロンドンの市街の大火の時に、人々が驚きあって狼狽しているのに、ターナーは夜空に広がる炎に感嘆して、ひたすら大火の模様をスケッチしていたそうです。
(写真2=『雨、蒸気、スピード‐グレート・ウェスタン鉄道』 (1844) )=1842年に制作された『吹雪‐港の沖合の蒸気船』では、蒸気船はぼんやりとした塊に過ぎず、巨大な波、水しぶき、吹雪といった自然の巨大なエネルギーを描き出している。この姿勢で描かれた彼の作品は、「印象派」を30年も先取りした先駆的な作品であったが、発表当時は、「石鹸水と水漆喰で描かれた」などと酷評されている。又、この作品を制作するために、ターナーはマストに4時間も縛りつけてもらい、嵐の様子をを観察していたという逸話が残っています。
代表作は何と言っても「 解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号」(1838)」(写真1)です。
テメレーア (戦列艦)=(HMS Temerarious, 1798) はイギリス海軍の軍艦で、98門搭載の二等戦列艦。トラファルガー海戦に参加している。世界的にはターナーの絵画に描かれたことで著名な船になっている。同名の軍艦としてはイギリス海軍では2代目で、1938年に描かれた掲出の「解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号」(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)は、世界的な名画と言われ、2005年に行われたイギリス国内の一般投票により「最も偉大なイギリス絵画」に選ばれているそうです。日本語では「戦艦テメレール号」となっていますが、原語では「Fighting Temerarious」であり、トラファルガーでの奮闘をたたえる愛称となっている。
一枚の絵としては、一日の終わりの夕映えの中を、任務を負えてスクラップ化されるために曳航されている嘗ての戦艦の姿を描いた絵である。この絵は、単なる夕方の港を描いた風景画ではなく、観る人がみれば、栄光ある戦歴の戦艦も引退をむかえるときがきたという、まさに人生の黄昏を風景上にあらわしていとも受け止められ、これぞ名画中の名画といわれる由縁なのです。
三島由紀夫も、この絵にいたく感動していたようで、そこから小説「午後の曳航」という作品を発表している。
この三島由紀夫の小説は、日本のみならず、海外でも評価され、映画化までされています。
映画「午後の曳航」=とある港町を舞台に、少年と未亡人である母親の前に現れた男との関係や心の葛藤を描いた作品。サラ・マイルズ、クリス・クリストファーソンほか出演。
スタッフ/キャスト
出演者:サラ・マイルズ/クリス・クリストファーソン/ジョナサン・カーン
監督:ルイス・ジョン・カリーノ
原作:三島由紀夫
撮影は、英国映画界の重鎮ダグラス・スローカムで、青く冷たい海の映像は極めて印象的。ジョニー・マンデルのスコアは映画音楽でも屈指の名曲である。
あらすじ=英国の港町。13歳の少年ジョナサンは、母のアンとふたり暮らしをしていた。ある日、母にせがんで大きな外洋船ベル号の見学に出かけたジョナサンは、そこで出会った二等航海士のジムに強烈な憧憬を抱くようになる。そして未亡人となって久しいアンもまた、逞しいジムに官能を覚える。三島由紀夫の中期の代表作であり、「金閣寺」と並んで海外でも人気の高く、「午後の曳航」を日英合作による映画化がなされたのです。
一枚の絵からでも、多大な影響を与えるものなのですね!
|
|
|
|
コメント(9)
>ミニーさんへ
お帰りなさい。
いろいろな、発見があったでしょうね。
>りゅうぞうさんへ
いつも、詳細なコメントで、勉強させて頂いてます。
私のターナーとの出会いは、昭和45年に東京の国立西洋美術館で「英国風景画展 ターナー/コンスタンブルとその周辺」で見たのが最初ですが、あまり強い印象はなかったのか、どのような絵をみたか覚えていません。(東京の他、京都国立西洋美術館でも開催されています)
その後、洋書(ABRAMS社)の画集で接しているのですが、抽象画のような風景画に驚いたものです。初期の、難破船や大岩に破壊される山小屋の絵との違いが興味深いです。
ターナーは、1796年頃までは水彩画を専門にし、地誌的な伝統による仕事をしている。
1796年か1797年にロイヤル・アカデミーに最初の油絵を出品。1797年に出品した2作は、オランダ17世紀の海洋画の影響をうけているそうです。
また、1819年にはじめてイタリアに旅行し、それ以後の油絵は、既に水彩画でなしとげた、淡彩の輝きを帯びるようになったらしいです。
後期のターナーは、魔術的な光の効果をもつものの、かえって不人気になり、ただラスキンが「近代画家論」により弁護する側にまわった経緯があるとの事。
ターナーは、遺言により、300点ちかい絵と2万点ちかい水彩画・素描を国家に寄贈したそうです。
以上は、Peter and Linda Murray著「西洋美術事典(普及版)」(美術出版社発行 1968年4月初版)に基づいています。
ターナーは、日本人には親しみの有る画家の一人と思います。
私は、後期の抽象画のような風景画、そして生涯を通じて見られる色彩に魅かれています。
そう言えば、夏目漱石の「坊ちゃん」に、「ターナー島」の言葉があったの思いだしました。
お帰りなさい。
いろいろな、発見があったでしょうね。
>りゅうぞうさんへ
いつも、詳細なコメントで、勉強させて頂いてます。
私のターナーとの出会いは、昭和45年に東京の国立西洋美術館で「英国風景画展 ターナー/コンスタンブルとその周辺」で見たのが最初ですが、あまり強い印象はなかったのか、どのような絵をみたか覚えていません。(東京の他、京都国立西洋美術館でも開催されています)
その後、洋書(ABRAMS社)の画集で接しているのですが、抽象画のような風景画に驚いたものです。初期の、難破船や大岩に破壊される山小屋の絵との違いが興味深いです。
ターナーは、1796年頃までは水彩画を専門にし、地誌的な伝統による仕事をしている。
1796年か1797年にロイヤル・アカデミーに最初の油絵を出品。1797年に出品した2作は、オランダ17世紀の海洋画の影響をうけているそうです。
また、1819年にはじめてイタリアに旅行し、それ以後の油絵は、既に水彩画でなしとげた、淡彩の輝きを帯びるようになったらしいです。
後期のターナーは、魔術的な光の効果をもつものの、かえって不人気になり、ただラスキンが「近代画家論」により弁護する側にまわった経緯があるとの事。
ターナーは、遺言により、300点ちかい絵と2万点ちかい水彩画・素描を国家に寄贈したそうです。
以上は、Peter and Linda Murray著「西洋美術事典(普及版)」(美術出版社発行 1968年4月初版)に基づいています。
ターナーは、日本人には親しみの有る画家の一人と思います。
私は、後期の抽象画のような風景画、そして生涯を通じて見られる色彩に魅かれています。
そう言えば、夏目漱石の「坊ちゃん」に、「ターナー島」の言葉があったの思いだしました。
街のモーツァルトさんへ
調べてみたら出てきましたよ「ターナー島」が・・・
(夏目漱石 小説「坊ちゃん」より)
向こう側を見ると青島が浮いている。これは人の住まない島だそうだ。よく見ると石と松ばかりだ。なるほど石と松ばかりじゃ住めっこない。赤シャツは、しきりに眺望していい景色だと言っている。野だは絶景でげすと言っている。絶景だかなんだか知らないが、いい心持には相違ない。ひろびろとした海の上で、潮風に吹かれるのは薬だと思った。いやに腹が減る。「あの松を見たまえ、幹がまっすぐで、上が傘のように開いてターナーの絵にありそうだね」と赤シャツが野だに言うと、野だは「全くターナーですね。どうもあの曲がりぐあいったらありませんね。ターナーそっくりですよ。」と得意顔である。ターナーとはなんのことだか知らないが、聞かないでも困らないことだから黙っていた。舟は島を右に見てぐるりと回った。波は全くない。これで海だとは受け取りにくいほど平らだ。赤シャツのおかげではなはだ愉快だ。できることなら、あの島の上へ上がってみたいと思ったから、あの岩のある所へは舟はつけられないんですかと聞いてみた。つけられんこともないですが、釣りをするには、あまり岸じゃいけないですと赤シャツが異議を申し立てた。俺は黙っていた。すると野だがどうです教頭、これからあの島をターナー島と名づけようじゃありませんかとよけいな発議をした。赤シャツはそいつはおもしろい、われわれはこれからそう言おうと賛成した。このわれわれのうちにおれもはいってるなら迷惑だ。おれには青島でたくさんだ。 ・・・・
島は、愛媛県松山市高浜町1丁目の沖合い150メートルにあるそうです。
調べてみたら出てきましたよ「ターナー島」が・・・
(夏目漱石 小説「坊ちゃん」より)
向こう側を見ると青島が浮いている。これは人の住まない島だそうだ。よく見ると石と松ばかりだ。なるほど石と松ばかりじゃ住めっこない。赤シャツは、しきりに眺望していい景色だと言っている。野だは絶景でげすと言っている。絶景だかなんだか知らないが、いい心持には相違ない。ひろびろとした海の上で、潮風に吹かれるのは薬だと思った。いやに腹が減る。「あの松を見たまえ、幹がまっすぐで、上が傘のように開いてターナーの絵にありそうだね」と赤シャツが野だに言うと、野だは「全くターナーですね。どうもあの曲がりぐあいったらありませんね。ターナーそっくりですよ。」と得意顔である。ターナーとはなんのことだか知らないが、聞かないでも困らないことだから黙っていた。舟は島を右に見てぐるりと回った。波は全くない。これで海だとは受け取りにくいほど平らだ。赤シャツのおかげではなはだ愉快だ。できることなら、あの島の上へ上がってみたいと思ったから、あの岩のある所へは舟はつけられないんですかと聞いてみた。つけられんこともないですが、釣りをするには、あまり岸じゃいけないですと赤シャツが異議を申し立てた。俺は黙っていた。すると野だがどうです教頭、これからあの島をターナー島と名づけようじゃありませんかとよけいな発議をした。赤シャツはそいつはおもしろい、われわれはこれからそう言おうと賛成した。このわれわれのうちにおれもはいってるなら迷惑だ。おれには青島でたくさんだ。 ・・・・
島は、愛媛県松山市高浜町1丁目の沖合い150メートルにあるそうです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
絵画論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
絵画論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37864人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人
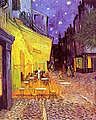
















![[芸術家×アート好]交流コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/71/77/297177_54s.gif)






