1975年11月14日 スペインとモロッコ王国、モーリタニアがマドリード協定を締結。スペイン撤退後の西サハラ分割について密約 。
1976年2月26日 スペインが西サハラを放棄 。
1976年2月29日 ポリサリオ解放戦線がサハラ・アラブ民主共和国の独立を宣言 。
そしてアルジェリアの首都アルジェで亡命政権サハラ・アラブ民主共和国 (SADR) を樹立した。
1976年4月14日 モロッコ王国とモーリタニアが西サハラの分割ラインを決定。
そしてモーリタニア とモロッコ王国 が分割統治を開始する。
1979年8月5日モーリタニア政府はポリサリオ戦線と単独和平協定を締結し、西サハラ領有権を正式に放棄した。
1979年8月14日 モロッコ王国が西サハラのほぼ全域を軍事占領 =
モーリタニアが放棄した領域までモロッコ軍が現在まで国土を不法占領中で
サハラ・アラブ民主共和国はアルジェリア領内の難民キャンプで亡命政府を作っている。
ちなみに
『モロッコでは「砂の壁」を建設して、西サハラの主要部分をゲリラの「解放区」と切り離して、モロッコ支配の既成事実作りを進めている。この砂の壁とは、砂漠に鉄条網を張り巡らして、都市がある沿岸部とゲリラが出没する内陸の砂漠との行き来を遮断するというもの。なんだかイスラエルがパレスチナ自治区を取り囲んで建設した壁に似ているが、実際にイスラエルの協力で建設しています。 』
だそうです。
軍事占領国モロッコ王ハサン2世は、【以前に存在したモロッコとサハラウィーとのあいだの忠誠関係を引いて、みずからの立ち位置を強化するるとともに、公に司法裁判所の自決権に関する判断についてなんらの言及もしていない(この態度は7年後、アフリカ統一機構で正式に住民投票に同意するまで続く)。そして勧告意見が発行に先立って、スペイン領サハラに対し「祖国の再統合」のため「緑の行進」を組織すると発表したのである。
主権にかかわるモロッコ側の議論
モロッコによれば、モロッコ国家による主権の行使は、スルターンに対する公的な忠誠誓約によって特徴的に表現されているとする。この忠誠がスペインによる占領の数世紀前から存在しており、かつそれは法的、政治的関係であった、というのがモロッコの意見である。】
君主制国家の王による占領は現在も続いている。
84年からはアフリカ統一機構(OAU)=現在のアフリカ連合(AU)にも国家として加盟。
国土も国民も政府もあったが、
国土を軍事占領で奪われ、
国民は他国へ避難して難民となり、逆に他国民の移住が行われ国民の入れ替わりが行われ、
政府も他国から国家承認を取り消されたりしている、
もしかしたら、地球上から消されてしまう可能性のある国家。
ps
アフリカ・中南米・南アジア諸国を中心に約80か国から国家承認を得ているとも言われるが、
取り消しや凍結があり判断が難しい。
以下コピペ参照↓
http://
マダガスカル 1976/2/28 2005/6/4凍結
ブルンディ 1976/3/1 2006/5/5凍結
アルジェリア 1976/3/6
ベニン 1976/3/11 1997/3/21取消
アンゴラ 1976/3/11
モザンビーク 1976/3/13
ギニア・ビサウ 1976/3/15 1997/4/2取消
2000/9/29
朝鮮民主主義人民共和国 1976/3/16
トーゴ 1976/3/17 1997/6/18取消
ルワンダ 1976/4/1
イエメン人民民主共和国 1977/2/2 イエメン共和国に承継も実態はなし
セイシェル 1977/10/25
コンゴ(ブラザヴィル) 1978/6/3 1996/9/13取消
サントーメ・プリンシペ 1978/6/22 1996/10/23取消
パナマ 1978/6/23
赤道ギニア 1978/11/3 1980/5/ 取消
タンザニア 1978/11/9
エチオピア 1979/2/24
ヴェトナム 1979/3/2
カンボジア 1979/4/10 2006/8/14取消
ラオス 1979/5/9
アフガニスタン 1979/5/23 2002/7/12取消
カーボ・ベルデ 1979/7/4
グレナダ 1979/8/20
ガーナ 1979/8/24 2001/5/凍結
ガイアナ 1979/9/1
ドミニカ 1979/9/1
セントルシア 1979/9/1 1989/3/取消?のち復交?
ジャマイカ 1979/9/4
ウガンダ 1979/9/6
ニカラグア 1979/9/6 2000/7/21住民投票まで凍結
2007/1/12
メキシコ 1979/9/8
レソト 1979/10/9
ザンビア 1979/10/12
キューバ 1980/1/20
イラン 1980/2/27
シエラ・レオネ 1980/3/27 2002〜2003年ごろ凍結
シリア 1980/4/15
リビア 1980/4/15
スワジランド 1980/4/28 1997/7/4取消
ボツワナ 1980/5/14
ジンバブウェ 1980/7/3
チャド 1980/7/4 1997/5/9取消。のち復交
マリ 1980/7/4
コスタ・リカ 1980/10/30
ヴァヌアツ 1980/11/27 2000/11/取消
パプア・ニューギニア 1981/8/12
トゥヴァル 1981/8/12 2000/9/15取消。復交へ?
キリバス 1981/8/12 2000/9/15取消
ナウル 1981/8/12 2000/9/15取消?のち復交?
ソロモン諸島 1981/8/12 1989/1/取消
モーリシャス 1982/7/1
ベネズエラ 1982/8/3
スリナム 1982/8/11
ボリビア 1982/12/14
エクアドル 1983/11/14 2004/6/11取消
2006/2/8
モーリタニア 1984/2/27
ブルキナ・ファソ 1984/3/4 1996/6/5取消
ペルー 1984/8/16 1996/10 関係停止
ナイジェリア 1984/11/12
ユーゴスラヴィア 1984/11/28 国家解体により承認消滅
コロンビア 1985/2/27
リベリア 1985/7/31 1997/9/5取消。復交の兆し。
インド 1985/10/1 2000/6/26取消
グアテマラ 1986/4/10 1998/4/凍結
ドミニカ共和国 1986/6/24 2002/5/23凍結
トリニダード・トバゴ 1986/11/1
ベリーズ 1986/11/18
セントクリストファー・ネヴィス 1987/2/25
アンティーグァ・バーブーダ 1987/2/27
アルバニア 1987/12/29 2004/11/9取消
バルバドス 1988/2/27
エルサルバドル 1989/7/31 1997/4/取消
ホンジュラス 1989/11/8 2000/1/凍結
ナミビア 1990/6/11
マラウイ 1994/11/16 2001/6取消
2002/3/24
パラグアイ 2000/2 2000/7/25凍結
セントヴィンセント・グレナディーン 2002/2/14
東ティモール 2002/5/20
南アフリカ 2004/9/15
ケニア 2005/6/25 2006/10/22一時凍結
ウルグアイ 2005/12/26
ハイチ 2006/11/22
※はじめに
承認の「取消」とは、RASDに対する国家承認そのものを取り消すことである。「凍結」とは、「住民投票により独立かモロッコ併合かをサハラウイが選択するまで、投票結果を先決しない」ことを理由としてRASDとの関係を一時凍結するという意味である。いずれも国連和平プロセスが始動した1990年代に、モロッコおよびフランスの外交攻勢によって広がった動きである。
国家承認は国際法により定められた法的行為で、一部の例外を除き外交関係樹立の共同コミュニケ等が公文書として公表されるため、明確にその事実関係が確認できる(2002年以降の承認に関する共同声明等は本HPの「資料」コーナーに訳出)。これに対し「国家承認の凍結・取消」は本来的には国際法上予定されていない行為であり(国交断絶は国家承認の取消を意味しない)、公文書による通達も行われないため、事実関係の確認が困難である。当該国政府が明確にRASD承認の取消・凍結を声明した場合は明示意思として確認できるが、モロッコの国営通信社MAPなどが報道しただけで、当該国の公式発表等によるフォローがない場合も少なくない(当然、モロッコ側による単なるプロパガンダということもある)。例えばウェブ百科事典"Wikipedia"の承認国リストはモロッコ側メディアによる「承認取り消し」報道を無批判的に採用しており、実証性に乏しい。他方、RASD駐アルジェリア大使館の承認国リストでも一部の国にRASDとの実際的関係を現在維持していない旨が注記されている。RASD側の現状認識を反映しているという意味では信用性が高いが、後に述べるような外交行動の実際を充分に反映しておらず、やや「甘い」見積もりであることは否めない。
この事実関係を類推するうえで有力な材料は、国連総会の西サハラ自決問題に関する決議での投票行動である。当該決議は、国連和平プロセスの始動後は無投票で採択されることが多かったが、2004年、2006年は投票により採択されている。いずれの投票でも反対はなく、モロッコはいずれも棄権しているので、棄権している国はモロッコに同調していると見るべきである(なお、日本はいずれも棄権)。
ARSOウェブサイトの承認国リストで「取消」に疑問符が付されている国および「凍結」とされている国の投票行動を見ていく(2004年、2006年)。ドミニカ共和国(棄権、棄権)、グアテマラ(棄権、棄権)、ホンジュラス(棄権、棄権)、ニカラグア(棄権、棄権)、シエラ・レオネ(棄権、棄権)、ガーナ(欠席、棄権)、パラグアイ(欠席、棄権)の承認取消・凍結は間違いないといえる(ただし、ニカラグアは2007年1月のオルテガ政権復帰とともに国交を回復)。他方、ドミニカ国(賛成、賛成)については取消の事実自体ないと考えられる。またコロンビア(賛成、欠席)も凍結の実態はないと見るべきであろう。承認国であっても外交上の配慮から欠席するケースはたびたび見られるからである(例えばモロッコの脅威を直接的に感じる立場にあるモーリタニアや、アラブ連盟に属するシリア、リビアなど)。
取消がARSOウェブ上で確言されている国であっても、セントルシア(賛成、賛成)、ナウル(賛成、賛成)については取消の情報自体が誤りであるか、2004年以前にRASDとの国交を回復している可能性が高い。チャド(欠席、賛成)、トゥヴァル(欠席、賛成)も国交を回復しているか、回復に向かいつつある可能性がある。マラウイ(欠席、賛成)については国交回復の情報が投票行動で裏づけられている。リベリア(賛成、欠席)もRASD承認を取り消した親仏テーラー政権が2003年に崩壊後、モロッコ側に傾いていた姿勢を修正しつつあるようだ。実際に、エクアドルやハイチはRASDと国交を回復、樹立したことで棄権から賛成に転じている。
一方で、MAPが承認取消・凍結の情報を流したものの事実関係が確認されていなかったブルンディとカンボジアは、賛成から棄権に転じたことで取消の事実が確認された。マダガスカルも2005年の承認取消後となる今年の総会では欠席から棄権に転じた。アルバニア(棄権、棄権)もすでに承認を取消ないし凍結していると見なさざるをえない。ただし、コスタ・リカは2度とも棄権しているものの、コンセンサスの不成立が棄権の理由であり、植民地独立付与宣言に基づく解決を支持し特定国の領有権主張を拒否する1975年以来の立場は変わらない旨を声明しているので(2006年)、例外的に承認は継続しているものと判断できる。
以上の基準に従い、承認取消ないし凍結が確実と考えられる国については、緑字で国名を表記している。
なお、イエメンについてはこれまで、1990年の南北イエメン統合後も旧南イエメンによるRASD承認を取り消した事実が確認できなかったため、旧南イエメンの承認を統合後も承継したものとして扱ってきた。しかし、同国は国連総会決議を2004年、2006年ともに棄権しているので、承認の実態はないものと判断せざるを得ず、旧ユーゴスラヴィアと同様の赤字表記に変更した。サーレハ現大統領を輩出している旧北イエメンはRASDを承認していなかったので、1994年の内戦で旧南イエメン政権勢力がサーレハ政権に粉砕されて後、RASDへの承認は実質的に取り消されたものと推測される。
☆2005年11月27〜30日のモロッコ国王ムハマッド6世の国賓招聘によって、モロッコの西サハラ違法占領に対する日本の政治的支持が名実ともに顕わになった。これは自決権行使を願望する西サハラ人民(サハラウイ)に対する明らかな敵対行為であるばかりではない。現役の安保理非常任理事国であり、常任理事国への野心を広言する日本が、自ら安保理決議に背を向ける姿勢を鮮明にしたという意味で、ブッシュ米政権によるイラク戦争への加担に勝るとも劣らぬ深刻な反国連行動である。しかも、かかる行為が「皇室外交」を利用して行われたことによって、「皇室外交」の信頼性さえ傷つけかねない事態が惹起されることになった。
モロッコ国王国賓招聘の政治的意味−象徴的側面
今回のモロッコ国王国賓招聘は、それ自体がモロッコの西サハラ違法占領に対する支持を象徴的に示した政治的儀式であるといっても過言ではない。
第一に、時期そのものの持つ意味である。モロッコが国際司法裁判所の勧告意見と一連の国連総会による自決支持決議を無視して、西サハラに「緑の行進」と称する越境侵略行動を実施したのは、1975年11月である。2005年11月はまさしく「緑の行進」30周年にあたるのである。そのような時にわざわざタイミングを合わせて、国賓という最高級の待遇で、侵略・占領の最高責任者であるモロッコ国王を日本に招聘したことは、否応なくモロッコの占領支配を正当化し祝福するという意味を伴わざるを得ない。
第二に、西サハラ占領地域などで2005年5月以降、「インティファーダ」とまで呼ばれる大規模なサハラウイの非暴力抵抗闘争と、これに対するモロッコ当局の激しい弾圧が続く中での招聘だということである。すでに占領地域やモロッコ国内で、人権状況の改善や自決権の確立を求めて平和的デモを行ったサハラウイの人権活動家、学生、一般民衆が相次いで拘束され、その数は延べ数百人に上るとみられている。拘束された者の多くが激しい拷問にさらされているといわれ、10月31日には31歳の青年ランバルキ・マハユーブ氏が拷問死した。モロッコ当局は事実検証のため現地を訪問したジャーナリストらを拘束・追放したり、欧州各国の議員視察団を空港で追い返すなど、徹底したアクセス拒否で事実隠蔽を図っているが、ジャーナリストや国際人権団体の努力で事実は明るみにされ、厳しい国際的指弾を受けている。アムネスティ・インターナショナルや、100人以上の欧州議会(欧州連合:EUの議会)議員らが政治犯の釈放や人権侵害停止を求める声明を相次いで発表している。かかる状況の中でモロッコ国王を国賓招聘したことは、日本が西サハラにおけるモロッコの人権侵害、抵抗運動弾圧を容認し、サハラウイの自決の叫びを真っ向から否定する立場をとることを、世界に宣言したに等しい行為である。
第三に、今回モロッコ国王を国賓として招聘したことによって、皇室外交があからさまに政治利用されてしまったことである。憲法上、日本国の「象徴」であり政治不関与を旨とする皇室の外交は、その性質として必然的に友好親善を誇る以外の意味を持ち得ない。それは裏返せば、違法な西サハラ占領を度外視したモロッコとの友好親善の姿勢を日本国がとることの「象徴」とみなされても仕方がないということである。現に上記のような事態にもかかわらず、皇室外交によって演出された親善ムードの中で、新規の円借款供与や無償資金協力等が取り決められ、両国関係のさらなる強化と、TICADプロセスに謳われる「アフリカにおける南南協力」の一環としての日本−モロッコ三角協力の推進が宣言された(2)。対モロッコ政治・経済協力強化の舞台装置として皇室外交は政府により利用されたと、言わざるを得ない。
要するに、日本は西サハラ侵略30周年を期する重要な年に、しかもサハラウイに対する甚だしい人権侵害が継続する状況において、侵略と抑圧の最高責任者たるモロッコ国王を、最高級の友好親善の姿勢をもって遇したのである。日本の親モロッコ、反サハラウイの政治姿勢を鮮明に示すものとして、その象徴的意味はあまりに大きい。
1976年2月26日 スペインが西サハラを放棄 。
1976年2月29日 ポリサリオ解放戦線がサハラ・アラブ民主共和国の独立を宣言 。
そしてアルジェリアの首都アルジェで亡命政権サハラ・アラブ民主共和国 (SADR) を樹立した。
1976年4月14日 モロッコ王国とモーリタニアが西サハラの分割ラインを決定。
そしてモーリタニア とモロッコ王国 が分割統治を開始する。
1979年8月5日モーリタニア政府はポリサリオ戦線と単独和平協定を締結し、西サハラ領有権を正式に放棄した。
1979年8月14日 モロッコ王国が西サハラのほぼ全域を軍事占領 =
モーリタニアが放棄した領域までモロッコ軍が現在まで国土を不法占領中で
サハラ・アラブ民主共和国はアルジェリア領内の難民キャンプで亡命政府を作っている。
ちなみに
『モロッコでは「砂の壁」を建設して、西サハラの主要部分をゲリラの「解放区」と切り離して、モロッコ支配の既成事実作りを進めている。この砂の壁とは、砂漠に鉄条網を張り巡らして、都市がある沿岸部とゲリラが出没する内陸の砂漠との行き来を遮断するというもの。なんだかイスラエルがパレスチナ自治区を取り囲んで建設した壁に似ているが、実際にイスラエルの協力で建設しています。 』
だそうです。
軍事占領国モロッコ王ハサン2世は、【以前に存在したモロッコとサハラウィーとのあいだの忠誠関係を引いて、みずからの立ち位置を強化するるとともに、公に司法裁判所の自決権に関する判断についてなんらの言及もしていない(この態度は7年後、アフリカ統一機構で正式に住民投票に同意するまで続く)。そして勧告意見が発行に先立って、スペイン領サハラに対し「祖国の再統合」のため「緑の行進」を組織すると発表したのである。
主権にかかわるモロッコ側の議論
モロッコによれば、モロッコ国家による主権の行使は、スルターンに対する公的な忠誠誓約によって特徴的に表現されているとする。この忠誠がスペインによる占領の数世紀前から存在しており、かつそれは法的、政治的関係であった、というのがモロッコの意見である。】
君主制国家の王による占領は現在も続いている。
84年からはアフリカ統一機構(OAU)=現在のアフリカ連合(AU)にも国家として加盟。
国土も国民も政府もあったが、
国土を軍事占領で奪われ、
国民は他国へ避難して難民となり、逆に他国民の移住が行われ国民の入れ替わりが行われ、
政府も他国から国家承認を取り消されたりしている、
もしかしたら、地球上から消されてしまう可能性のある国家。
ps
アフリカ・中南米・南アジア諸国を中心に約80か国から国家承認を得ているとも言われるが、
取り消しや凍結があり判断が難しい。
以下コピペ参照↓
http://
マダガスカル 1976/2/28 2005/6/4凍結
ブルンディ 1976/3/1 2006/5/5凍結
アルジェリア 1976/3/6
ベニン 1976/3/11 1997/3/21取消
アンゴラ 1976/3/11
モザンビーク 1976/3/13
ギニア・ビサウ 1976/3/15 1997/4/2取消
2000/9/29
朝鮮民主主義人民共和国 1976/3/16
トーゴ 1976/3/17 1997/6/18取消
ルワンダ 1976/4/1
イエメン人民民主共和国 1977/2/2 イエメン共和国に承継も実態はなし
セイシェル 1977/10/25
コンゴ(ブラザヴィル) 1978/6/3 1996/9/13取消
サントーメ・プリンシペ 1978/6/22 1996/10/23取消
パナマ 1978/6/23
赤道ギニア 1978/11/3 1980/5/ 取消
タンザニア 1978/11/9
エチオピア 1979/2/24
ヴェトナム 1979/3/2
カンボジア 1979/4/10 2006/8/14取消
ラオス 1979/5/9
アフガニスタン 1979/5/23 2002/7/12取消
カーボ・ベルデ 1979/7/4
グレナダ 1979/8/20
ガーナ 1979/8/24 2001/5/凍結
ガイアナ 1979/9/1
ドミニカ 1979/9/1
セントルシア 1979/9/1 1989/3/取消?のち復交?
ジャマイカ 1979/9/4
ウガンダ 1979/9/6
ニカラグア 1979/9/6 2000/7/21住民投票まで凍結
2007/1/12
メキシコ 1979/9/8
レソト 1979/10/9
ザンビア 1979/10/12
キューバ 1980/1/20
イラン 1980/2/27
シエラ・レオネ 1980/3/27 2002〜2003年ごろ凍結
シリア 1980/4/15
リビア 1980/4/15
スワジランド 1980/4/28 1997/7/4取消
ボツワナ 1980/5/14
ジンバブウェ 1980/7/3
チャド 1980/7/4 1997/5/9取消。のち復交
マリ 1980/7/4
コスタ・リカ 1980/10/30
ヴァヌアツ 1980/11/27 2000/11/取消
パプア・ニューギニア 1981/8/12
トゥヴァル 1981/8/12 2000/9/15取消。復交へ?
キリバス 1981/8/12 2000/9/15取消
ナウル 1981/8/12 2000/9/15取消?のち復交?
ソロモン諸島 1981/8/12 1989/1/取消
モーリシャス 1982/7/1
ベネズエラ 1982/8/3
スリナム 1982/8/11
ボリビア 1982/12/14
エクアドル 1983/11/14 2004/6/11取消
2006/2/8
モーリタニア 1984/2/27
ブルキナ・ファソ 1984/3/4 1996/6/5取消
ペルー 1984/8/16 1996/10 関係停止
ナイジェリア 1984/11/12
ユーゴスラヴィア 1984/11/28 国家解体により承認消滅
コロンビア 1985/2/27
リベリア 1985/7/31 1997/9/5取消。復交の兆し。
インド 1985/10/1 2000/6/26取消
グアテマラ 1986/4/10 1998/4/凍結
ドミニカ共和国 1986/6/24 2002/5/23凍結
トリニダード・トバゴ 1986/11/1
ベリーズ 1986/11/18
セントクリストファー・ネヴィス 1987/2/25
アンティーグァ・バーブーダ 1987/2/27
アルバニア 1987/12/29 2004/11/9取消
バルバドス 1988/2/27
エルサルバドル 1989/7/31 1997/4/取消
ホンジュラス 1989/11/8 2000/1/凍結
ナミビア 1990/6/11
マラウイ 1994/11/16 2001/6取消
2002/3/24
パラグアイ 2000/2 2000/7/25凍結
セントヴィンセント・グレナディーン 2002/2/14
東ティモール 2002/5/20
南アフリカ 2004/9/15
ケニア 2005/6/25 2006/10/22一時凍結
ウルグアイ 2005/12/26
ハイチ 2006/11/22
※はじめに
承認の「取消」とは、RASDに対する国家承認そのものを取り消すことである。「凍結」とは、「住民投票により独立かモロッコ併合かをサハラウイが選択するまで、投票結果を先決しない」ことを理由としてRASDとの関係を一時凍結するという意味である。いずれも国連和平プロセスが始動した1990年代に、モロッコおよびフランスの外交攻勢によって広がった動きである。
国家承認は国際法により定められた法的行為で、一部の例外を除き外交関係樹立の共同コミュニケ等が公文書として公表されるため、明確にその事実関係が確認できる(2002年以降の承認に関する共同声明等は本HPの「資料」コーナーに訳出)。これに対し「国家承認の凍結・取消」は本来的には国際法上予定されていない行為であり(国交断絶は国家承認の取消を意味しない)、公文書による通達も行われないため、事実関係の確認が困難である。当該国政府が明確にRASD承認の取消・凍結を声明した場合は明示意思として確認できるが、モロッコの国営通信社MAPなどが報道しただけで、当該国の公式発表等によるフォローがない場合も少なくない(当然、モロッコ側による単なるプロパガンダということもある)。例えばウェブ百科事典"Wikipedia"の承認国リストはモロッコ側メディアによる「承認取り消し」報道を無批判的に採用しており、実証性に乏しい。他方、RASD駐アルジェリア大使館の承認国リストでも一部の国にRASDとの実際的関係を現在維持していない旨が注記されている。RASD側の現状認識を反映しているという意味では信用性が高いが、後に述べるような外交行動の実際を充分に反映しておらず、やや「甘い」見積もりであることは否めない。
この事実関係を類推するうえで有力な材料は、国連総会の西サハラ自決問題に関する決議での投票行動である。当該決議は、国連和平プロセスの始動後は無投票で採択されることが多かったが、2004年、2006年は投票により採択されている。いずれの投票でも反対はなく、モロッコはいずれも棄権しているので、棄権している国はモロッコに同調していると見るべきである(なお、日本はいずれも棄権)。
ARSOウェブサイトの承認国リストで「取消」に疑問符が付されている国および「凍結」とされている国の投票行動を見ていく(2004年、2006年)。ドミニカ共和国(棄権、棄権)、グアテマラ(棄権、棄権)、ホンジュラス(棄権、棄権)、ニカラグア(棄権、棄権)、シエラ・レオネ(棄権、棄権)、ガーナ(欠席、棄権)、パラグアイ(欠席、棄権)の承認取消・凍結は間違いないといえる(ただし、ニカラグアは2007年1月のオルテガ政権復帰とともに国交を回復)。他方、ドミニカ国(賛成、賛成)については取消の事実自体ないと考えられる。またコロンビア(賛成、欠席)も凍結の実態はないと見るべきであろう。承認国であっても外交上の配慮から欠席するケースはたびたび見られるからである(例えばモロッコの脅威を直接的に感じる立場にあるモーリタニアや、アラブ連盟に属するシリア、リビアなど)。
取消がARSOウェブ上で確言されている国であっても、セントルシア(賛成、賛成)、ナウル(賛成、賛成)については取消の情報自体が誤りであるか、2004年以前にRASDとの国交を回復している可能性が高い。チャド(欠席、賛成)、トゥヴァル(欠席、賛成)も国交を回復しているか、回復に向かいつつある可能性がある。マラウイ(欠席、賛成)については国交回復の情報が投票行動で裏づけられている。リベリア(賛成、欠席)もRASD承認を取り消した親仏テーラー政権が2003年に崩壊後、モロッコ側に傾いていた姿勢を修正しつつあるようだ。実際に、エクアドルやハイチはRASDと国交を回復、樹立したことで棄権から賛成に転じている。
一方で、MAPが承認取消・凍結の情報を流したものの事実関係が確認されていなかったブルンディとカンボジアは、賛成から棄権に転じたことで取消の事実が確認された。マダガスカルも2005年の承認取消後となる今年の総会では欠席から棄権に転じた。アルバニア(棄権、棄権)もすでに承認を取消ないし凍結していると見なさざるをえない。ただし、コスタ・リカは2度とも棄権しているものの、コンセンサスの不成立が棄権の理由であり、植民地独立付与宣言に基づく解決を支持し特定国の領有権主張を拒否する1975年以来の立場は変わらない旨を声明しているので(2006年)、例外的に承認は継続しているものと判断できる。
以上の基準に従い、承認取消ないし凍結が確実と考えられる国については、緑字で国名を表記している。
なお、イエメンについてはこれまで、1990年の南北イエメン統合後も旧南イエメンによるRASD承認を取り消した事実が確認できなかったため、旧南イエメンの承認を統合後も承継したものとして扱ってきた。しかし、同国は国連総会決議を2004年、2006年ともに棄権しているので、承認の実態はないものと判断せざるを得ず、旧ユーゴスラヴィアと同様の赤字表記に変更した。サーレハ現大統領を輩出している旧北イエメンはRASDを承認していなかったので、1994年の内戦で旧南イエメン政権勢力がサーレハ政権に粉砕されて後、RASDへの承認は実質的に取り消されたものと推測される。
☆2005年11月27〜30日のモロッコ国王ムハマッド6世の国賓招聘によって、モロッコの西サハラ違法占領に対する日本の政治的支持が名実ともに顕わになった。これは自決権行使を願望する西サハラ人民(サハラウイ)に対する明らかな敵対行為であるばかりではない。現役の安保理非常任理事国であり、常任理事国への野心を広言する日本が、自ら安保理決議に背を向ける姿勢を鮮明にしたという意味で、ブッシュ米政権によるイラク戦争への加担に勝るとも劣らぬ深刻な反国連行動である。しかも、かかる行為が「皇室外交」を利用して行われたことによって、「皇室外交」の信頼性さえ傷つけかねない事態が惹起されることになった。
モロッコ国王国賓招聘の政治的意味−象徴的側面
今回のモロッコ国王国賓招聘は、それ自体がモロッコの西サハラ違法占領に対する支持を象徴的に示した政治的儀式であるといっても過言ではない。
第一に、時期そのものの持つ意味である。モロッコが国際司法裁判所の勧告意見と一連の国連総会による自決支持決議を無視して、西サハラに「緑の行進」と称する越境侵略行動を実施したのは、1975年11月である。2005年11月はまさしく「緑の行進」30周年にあたるのである。そのような時にわざわざタイミングを合わせて、国賓という最高級の待遇で、侵略・占領の最高責任者であるモロッコ国王を日本に招聘したことは、否応なくモロッコの占領支配を正当化し祝福するという意味を伴わざるを得ない。
第二に、西サハラ占領地域などで2005年5月以降、「インティファーダ」とまで呼ばれる大規模なサハラウイの非暴力抵抗闘争と、これに対するモロッコ当局の激しい弾圧が続く中での招聘だということである。すでに占領地域やモロッコ国内で、人権状況の改善や自決権の確立を求めて平和的デモを行ったサハラウイの人権活動家、学生、一般民衆が相次いで拘束され、その数は延べ数百人に上るとみられている。拘束された者の多くが激しい拷問にさらされているといわれ、10月31日には31歳の青年ランバルキ・マハユーブ氏が拷問死した。モロッコ当局は事実検証のため現地を訪問したジャーナリストらを拘束・追放したり、欧州各国の議員視察団を空港で追い返すなど、徹底したアクセス拒否で事実隠蔽を図っているが、ジャーナリストや国際人権団体の努力で事実は明るみにされ、厳しい国際的指弾を受けている。アムネスティ・インターナショナルや、100人以上の欧州議会(欧州連合:EUの議会)議員らが政治犯の釈放や人権侵害停止を求める声明を相次いで発表している。かかる状況の中でモロッコ国王を国賓招聘したことは、日本が西サハラにおけるモロッコの人権侵害、抵抗運動弾圧を容認し、サハラウイの自決の叫びを真っ向から否定する立場をとることを、世界に宣言したに等しい行為である。
第三に、今回モロッコ国王を国賓として招聘したことによって、皇室外交があからさまに政治利用されてしまったことである。憲法上、日本国の「象徴」であり政治不関与を旨とする皇室の外交は、その性質として必然的に友好親善を誇る以外の意味を持ち得ない。それは裏返せば、違法な西サハラ占領を度外視したモロッコとの友好親善の姿勢を日本国がとることの「象徴」とみなされても仕方がないということである。現に上記のような事態にもかかわらず、皇室外交によって演出された親善ムードの中で、新規の円借款供与や無償資金協力等が取り決められ、両国関係のさらなる強化と、TICADプロセスに謳われる「アフリカにおける南南協力」の一環としての日本−モロッコ三角協力の推進が宣言された(2)。対モロッコ政治・経済協力強化の舞台装置として皇室外交は政府により利用されたと、言わざるを得ない。
要するに、日本は西サハラ侵略30周年を期する重要な年に、しかもサハラウイに対する甚だしい人権侵害が継続する状況において、侵略と抑圧の最高責任者たるモロッコ国王を、最高級の友好親善の姿勢をもって遇したのである。日本の親モロッコ、反サハラウイの政治姿勢を鮮明に示すものとして、その象徴的意味はあまりに大きい。
|
|
|
|
|
|
|
|
独立してない独立国地域 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
独立してない独立国地域のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75481人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6441人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人
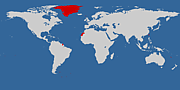











![札幌市[起業/副業/独立]中古車屋](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/97/20/6019720_149s.jpg)






