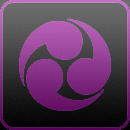はじめまして。
「藤原氏族・宇都宮氏」というコミュニティを開いているMakoと申します。
http://
同じ宇都宮氏(宇都宮家)についてのコミュということで、兄弟あるいは姉妹コミュのような感覚で参加させていただきました。よろしくお願いします。
嫡流の下野宇都宮氏についてはお詳しいようですので、庶流の豊前宇都宮氏と並ぶもう一つの筑後宇都宮氏について簡単に紹介させていただきます。
筑後宇都宮氏の遠祖は、宇都宮氏代6代(宇都宮朝綱を初代として)の宇都宮貞綱の弟の宇都宮泰宗になります。
貞綱は元寇の時に日本側の最高司令官として九州に下りますが、その時に同行した泰宗は、筑後瀬高にあった藤原北家の徳大寺家の荘園管理のため瀬高の大木城を本拠地にしました。泰宗の嫡子の時景は常陸の武茂荘を継ぎ武茂氏の祖となります。泰宗の次子の貞泰は京都におりましたが四国伊予の喜多の地頭になっていた頃、南朝方の懐良親王を迎え、九州へ向かいました。同族の豊前宇都宮氏は北朝方だったので、南朝方の貞泰は筑後大木に向い、同地を本拠地とし、懐良親王を九州南朝の拠点である肥後の菊池氏のもとへ送り届けます。
宇都宮貞泰の嫡子の宇都宮貞久と次子の貞邦、貞久の子の懐久は、九州の南朝と北朝が大激突した大保原の合戦(筑後川の戦い)に出陣し、貞邦と懐久は討ち死にします。
その後、南朝方は凋落し、懐久の嫡子で、祖父の貞久に育てられた宇都宮久憲の頃は浪々に近い身上になっていました。
そんな折り、やはり南朝方で、菊池武敏が足利尊氏を迎え撃った多々良浜の戦いで当主の蒲池武久が討ち死にし、男子の跡継ぎもないまま女地頭として家を守ってきた蒲池武久の娘と出会い、夫婦となり、蒲池家の名跡と遺領を継ぎます。それまでの蒲池氏は、嵯峨源氏の源融(『源氏物語』の光源氏の実在モデルとされる公家)の玄孫で、肥前神埼にあった天皇家直轄の荘園管理のために九州に来た源満末の子で源平合戦の勲功で、筑後三潴郡の地頭となった源久直(蒲池久直)の子孫でした。久憲以前の嵯峨源氏の蒲池氏を「前蒲池」、久憲以後の宇都宮氏の蒲池氏は「後蒲池」というそうです。
蒲池久憲の6代後の蒲池氏16代の蒲池鑑盛と従兄弟の鑑広の頃が全盛期で、柳川城の蒲池本家は12万石(1万2千町)を、山下城の分家は8万石(8千町)を領し、義心は鉄のごとしといわれた義将として名高い本家の蒲池鑑盛は筑後を統括していました。
この蒲池鑑盛は、柳川に落ち延びてきた肥前の龍造寺家兼を、敵方であるにもかかわらず戦以外の場で救いを求めてきた者は助けるという心情から保護し、家兼の肥前復帰を助け、またやはり肥前を追われてきた龍造寺隆信を保護し、龍造寺氏を滅亡から救いました。龍造寺隆信はこの恩から娘の玉鶴姫を、鑑盛の嫡子の鎮漣(鎮並)の妻とします。
ところが龍造寺隆信は、筑後を狙い、蒲池鎮漣と対立し、2万の軍勢で柳川城を攻めますが、縦横にクリークを配し九州随一の難攻不落の城とされた柳川城を攻めあぐみ、和解することになります。まともに攻めたのでは歯が立たないと見た隆信は重臣の鍋島直茂と謀り、蒲池鎮漣を肥前で騙し討ちにし、残った鎮漣の一族の冷酷な皆殺しを命じ、凄惨な柳川の戦いが行われ、蒲池氏本家は滅びます。
http://
それでも蒲池鎮漣の娘で長崎に落ち延びた徳子(徳姫)や、鎮漣の兄で家老だった鎮久の子の貞久、鎮漣の弟の統安(鎮安)の子で僧籍にあった応誉その他が生き残ります。
徳子の子孫には、幕末に西国郡代となった2千石の旗本の窪田鎮勝(蒲池鎮克)がいますし、応誉は、柳川藩祖の立花宗茂に招かれて宗茂の正室の菩提寺を建立し、その子孫は住職家となると共に還俗して蒲池家を再興し、柳川藩家老格になります。
歌手の松田聖子(蒲池法子)さんは、この柳川藩家老格の蒲池家の子孫で、幕末の蒲池鎮之のひ孫が聖子さんの父親になります。聖子さんの家の家紋は、宇都宮久憲以来の宇都宮氏の紋である「左三巴」です。
宇都宮久憲の子孫には、その弟の資綱の子孫で、宇都宮泰宗の大木城を継いだ大木氏の子孫の大木喬任は、政府要職を歴任し華族(伯爵)に列せられています。
また、西国郡代の窪田鎮勝の嫡子で大身旗本の窪田鎮章は鳥羽伏見の戦いで幕府軍を指揮し、新撰組と共に戦い戦死していますが、鎮章の兄の蒲池鎮厚の娘が作家の広津和郎の母親です。
そのほか、筑後宇都宮氏としての蒲池氏の子孫はたくさんおられます。
「藤原氏族・宇都宮氏」というコミュニティを開いているMakoと申します。
http://
同じ宇都宮氏(宇都宮家)についてのコミュということで、兄弟あるいは姉妹コミュのような感覚で参加させていただきました。よろしくお願いします。
嫡流の下野宇都宮氏についてはお詳しいようですので、庶流の豊前宇都宮氏と並ぶもう一つの筑後宇都宮氏について簡単に紹介させていただきます。
筑後宇都宮氏の遠祖は、宇都宮氏代6代(宇都宮朝綱を初代として)の宇都宮貞綱の弟の宇都宮泰宗になります。
貞綱は元寇の時に日本側の最高司令官として九州に下りますが、その時に同行した泰宗は、筑後瀬高にあった藤原北家の徳大寺家の荘園管理のため瀬高の大木城を本拠地にしました。泰宗の嫡子の時景は常陸の武茂荘を継ぎ武茂氏の祖となります。泰宗の次子の貞泰は京都におりましたが四国伊予の喜多の地頭になっていた頃、南朝方の懐良親王を迎え、九州へ向かいました。同族の豊前宇都宮氏は北朝方だったので、南朝方の貞泰は筑後大木に向い、同地を本拠地とし、懐良親王を九州南朝の拠点である肥後の菊池氏のもとへ送り届けます。
宇都宮貞泰の嫡子の宇都宮貞久と次子の貞邦、貞久の子の懐久は、九州の南朝と北朝が大激突した大保原の合戦(筑後川の戦い)に出陣し、貞邦と懐久は討ち死にします。
その後、南朝方は凋落し、懐久の嫡子で、祖父の貞久に育てられた宇都宮久憲の頃は浪々に近い身上になっていました。
そんな折り、やはり南朝方で、菊池武敏が足利尊氏を迎え撃った多々良浜の戦いで当主の蒲池武久が討ち死にし、男子の跡継ぎもないまま女地頭として家を守ってきた蒲池武久の娘と出会い、夫婦となり、蒲池家の名跡と遺領を継ぎます。それまでの蒲池氏は、嵯峨源氏の源融(『源氏物語』の光源氏の実在モデルとされる公家)の玄孫で、肥前神埼にあった天皇家直轄の荘園管理のために九州に来た源満末の子で源平合戦の勲功で、筑後三潴郡の地頭となった源久直(蒲池久直)の子孫でした。久憲以前の嵯峨源氏の蒲池氏を「前蒲池」、久憲以後の宇都宮氏の蒲池氏は「後蒲池」というそうです。
蒲池久憲の6代後の蒲池氏16代の蒲池鑑盛と従兄弟の鑑広の頃が全盛期で、柳川城の蒲池本家は12万石(1万2千町)を、山下城の分家は8万石(8千町)を領し、義心は鉄のごとしといわれた義将として名高い本家の蒲池鑑盛は筑後を統括していました。
この蒲池鑑盛は、柳川に落ち延びてきた肥前の龍造寺家兼を、敵方であるにもかかわらず戦以外の場で救いを求めてきた者は助けるという心情から保護し、家兼の肥前復帰を助け、またやはり肥前を追われてきた龍造寺隆信を保護し、龍造寺氏を滅亡から救いました。龍造寺隆信はこの恩から娘の玉鶴姫を、鑑盛の嫡子の鎮漣(鎮並)の妻とします。
ところが龍造寺隆信は、筑後を狙い、蒲池鎮漣と対立し、2万の軍勢で柳川城を攻めますが、縦横にクリークを配し九州随一の難攻不落の城とされた柳川城を攻めあぐみ、和解することになります。まともに攻めたのでは歯が立たないと見た隆信は重臣の鍋島直茂と謀り、蒲池鎮漣を肥前で騙し討ちにし、残った鎮漣の一族の冷酷な皆殺しを命じ、凄惨な柳川の戦いが行われ、蒲池氏本家は滅びます。
http://
それでも蒲池鎮漣の娘で長崎に落ち延びた徳子(徳姫)や、鎮漣の兄で家老だった鎮久の子の貞久、鎮漣の弟の統安(鎮安)の子で僧籍にあった応誉その他が生き残ります。
徳子の子孫には、幕末に西国郡代となった2千石の旗本の窪田鎮勝(蒲池鎮克)がいますし、応誉は、柳川藩祖の立花宗茂に招かれて宗茂の正室の菩提寺を建立し、その子孫は住職家となると共に還俗して蒲池家を再興し、柳川藩家老格になります。
歌手の松田聖子(蒲池法子)さんは、この柳川藩家老格の蒲池家の子孫で、幕末の蒲池鎮之のひ孫が聖子さんの父親になります。聖子さんの家の家紋は、宇都宮久憲以来の宇都宮氏の紋である「左三巴」です。
宇都宮久憲の子孫には、その弟の資綱の子孫で、宇都宮泰宗の大木城を継いだ大木氏の子孫の大木喬任は、政府要職を歴任し華族(伯爵)に列せられています。
また、西国郡代の窪田鎮勝の嫡子で大身旗本の窪田鎮章は鳥羽伏見の戦いで幕府軍を指揮し、新撰組と共に戦い戦死していますが、鎮章の兄の蒲池鎮厚の娘が作家の広津和郎の母親です。
そのほか、筑後宇都宮氏としての蒲池氏の子孫はたくさんおられます。
|
|
|
|
コメント(2)
源三圓が蒲池氏の婿養子になるのは次のような経緯です。
蒲池氏は、源久直を初代としますが、父の源満末は、従五位下の位で京都から肥前国神埼に荘官としてくだり、土地の山代氏(松浦氏の一族)の力を背景に武士として土着。同地は平家の日宋貿易の根拠地で、松浦一族はそれに関係し、また平家の家人でもありました。
源平合戦の壇ノ浦の戦いの時、源氏方の水軍は、松浦氏の本家筋の摂津の渡辺氏(大江山の酒呑童子退治で有名な源頼光の四天王筆頭の渡辺綱が祖)であり、平家方の水軍が松浦氏でした。この時、源久直も山代氏と共に平家方にありました。ところが合戦の後半で松浦氏は源氏方に寝返り、平家は敗れます。この功により、松浦氏や菊池氏その他の九州の元平家方の武家は、鎌倉幕府の御家人として生き残ります。源久直も筑後国三潴郡の地頭職になります。
ところが、源頼朝は、元平家方の九州の武家を信じておらず、自分の代官を兼ね、九州の武家に対する抑えとして、関東では無名に近い大友氏、島津氏、少弐氏を守護職として九州に送ります。九州の武家は、彼らの下に置かれ、その不満が、幕府打倒の承久の乱への参加になります。蒲池氏も蒲池行房が天皇方で参加しますが、結果は幕府側の勝利に終わり、戦後処分として蒲池氏は家系断絶の危機に直面します。そこで蒲池行房は、薩摩にあった蒲池氏の飛び地の領地で終生蟄居の身となり、行房の娘は、源満末以来、関係の深い松浦一族の山代氏から婿養子を迎えます(山代氏は承久の乱には不参加でした)。それが源圓(みなもと・の・つぶら)であり、三男なので源三圓(げんざ・つぶら)と呼ばれた人物です。
源圓が蒲池氏の祖とされるのは(『蒲池物語』や『筑後国史』など)、彼が、妻の生家である蒲池氏とは別に、妻の生家の名跡と所領を相続し、新しく蒲池の家を興したからだそうです。
宇都宮久憲が蒲池氏を継ぐ経緯はそうですね。
南朝方で多々良浜の合戦で討ち死にした蒲池武久の娘は夢を見て、久留米郊外の高良大社へお参りし、そこでやはり夢のお告げでお参りに来ていた宇都宮久憲と運命の出会いをすることになります。
宇都宮久憲の家は、元は下野の宇都宮氏本家の一族で、上にも書きましたが筑後国瀬高の荘官職として下向した宇都宮泰宗の次男の貞泰を祖とし、泰宗の嫡子の時景を祖とする武茂氏と同族になります(蒲池氏分家の菩提寺である西念寺に現在も伝わる蒲池家系図の正式名称は「下野宇都宮氏正統系図」と題されています)。
以上のことからすると、蒲池氏は、まず、嵯峨源氏の蒲池氏があり、次いで嵯峨源氏の松浦氏系の蒲池氏が跡を継ぎ、さらに宇都宮氏系の蒲池氏が跡を継いだことになります。
このように蒲池氏の名跡が、婿養子によって継がれていったことは、蒲池氏が太田亮が言うように「筑後屈指の名族」の一つの証になるだろうと思います。
江戸時代に蒲池氏の子孫の一つから宇都宮氏が再興されます。
蒲池鎮漣(鎮並)が騙し討ちで殺され、柳川の戦いで蒲池氏(柳川の本家)が滅んだ時、鎮漣の兄で落胤だったことから家老だった蒲池鎮久(彼も鎮漣と同じく肥前での龍造寺氏の襲撃で討ち死に)の子の蒲池貞久は、龍造寺氏の中でも隆信とは距離を置いていた龍造寺家晴の家臣となります。家晴は、龍造寺氏には大恩のある蒲池氏の血筋を守ろうとしたようです。家晴の一族は、江戸時代の鍋島藩時代は諫早氏となりますが、その重臣だった蒲池氏の一族が、祖の宇都宮久憲の名跡を再興し、宇都宮氏(諫早宇都宮氏)を興します。
日本陸軍の三太郎大将の1人とされる宇都宮太郎大将はその子孫であり、国会議員だった宇都宮徳馬はその子になります。また、昭和の5・15事件で有名な三上卓海軍中尉の妻の宇都宮わかは、宇都宮太郎の姪になります。
蒲池氏は、源久直を初代としますが、父の源満末は、従五位下の位で京都から肥前国神埼に荘官としてくだり、土地の山代氏(松浦氏の一族)の力を背景に武士として土着。同地は平家の日宋貿易の根拠地で、松浦一族はそれに関係し、また平家の家人でもありました。
源平合戦の壇ノ浦の戦いの時、源氏方の水軍は、松浦氏の本家筋の摂津の渡辺氏(大江山の酒呑童子退治で有名な源頼光の四天王筆頭の渡辺綱が祖)であり、平家方の水軍が松浦氏でした。この時、源久直も山代氏と共に平家方にありました。ところが合戦の後半で松浦氏は源氏方に寝返り、平家は敗れます。この功により、松浦氏や菊池氏その他の九州の元平家方の武家は、鎌倉幕府の御家人として生き残ります。源久直も筑後国三潴郡の地頭職になります。
ところが、源頼朝は、元平家方の九州の武家を信じておらず、自分の代官を兼ね、九州の武家に対する抑えとして、関東では無名に近い大友氏、島津氏、少弐氏を守護職として九州に送ります。九州の武家は、彼らの下に置かれ、その不満が、幕府打倒の承久の乱への参加になります。蒲池氏も蒲池行房が天皇方で参加しますが、結果は幕府側の勝利に終わり、戦後処分として蒲池氏は家系断絶の危機に直面します。そこで蒲池行房は、薩摩にあった蒲池氏の飛び地の領地で終生蟄居の身となり、行房の娘は、源満末以来、関係の深い松浦一族の山代氏から婿養子を迎えます(山代氏は承久の乱には不参加でした)。それが源圓(みなもと・の・つぶら)であり、三男なので源三圓(げんざ・つぶら)と呼ばれた人物です。
源圓が蒲池氏の祖とされるのは(『蒲池物語』や『筑後国史』など)、彼が、妻の生家である蒲池氏とは別に、妻の生家の名跡と所領を相続し、新しく蒲池の家を興したからだそうです。
宇都宮久憲が蒲池氏を継ぐ経緯はそうですね。
南朝方で多々良浜の合戦で討ち死にした蒲池武久の娘は夢を見て、久留米郊外の高良大社へお参りし、そこでやはり夢のお告げでお参りに来ていた宇都宮久憲と運命の出会いをすることになります。
宇都宮久憲の家は、元は下野の宇都宮氏本家の一族で、上にも書きましたが筑後国瀬高の荘官職として下向した宇都宮泰宗の次男の貞泰を祖とし、泰宗の嫡子の時景を祖とする武茂氏と同族になります(蒲池氏分家の菩提寺である西念寺に現在も伝わる蒲池家系図の正式名称は「下野宇都宮氏正統系図」と題されています)。
以上のことからすると、蒲池氏は、まず、嵯峨源氏の蒲池氏があり、次いで嵯峨源氏の松浦氏系の蒲池氏が跡を継ぎ、さらに宇都宮氏系の蒲池氏が跡を継いだことになります。
このように蒲池氏の名跡が、婿養子によって継がれていったことは、蒲池氏が太田亮が言うように「筑後屈指の名族」の一つの証になるだろうと思います。
江戸時代に蒲池氏の子孫の一つから宇都宮氏が再興されます。
蒲池鎮漣(鎮並)が騙し討ちで殺され、柳川の戦いで蒲池氏(柳川の本家)が滅んだ時、鎮漣の兄で落胤だったことから家老だった蒲池鎮久(彼も鎮漣と同じく肥前での龍造寺氏の襲撃で討ち死に)の子の蒲池貞久は、龍造寺氏の中でも隆信とは距離を置いていた龍造寺家晴の家臣となります。家晴は、龍造寺氏には大恩のある蒲池氏の血筋を守ろうとしたようです。家晴の一族は、江戸時代の鍋島藩時代は諫早氏となりますが、その重臣だった蒲池氏の一族が、祖の宇都宮久憲の名跡を再興し、宇都宮氏(諫早宇都宮氏)を興します。
日本陸軍の三太郎大将の1人とされる宇都宮太郎大将はその子孫であり、国会議員だった宇都宮徳馬はその子になります。また、昭和の5・15事件で有名な三上卓海軍中尉の妻の宇都宮わかは、宇都宮太郎の姪になります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
宇都宮家 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
宇都宮家のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人