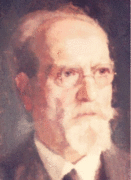|
|
|
|
コメント(55)
一度このコミュニティを抜けて、再び舞い戻ってきました。
ねぎとろです。
私のタケダ批判が誹謗中傷の域を出ないもの、という意見をいただいておりましたのに
返答せずに申し訳ないです。
たしかに、私個人の意見だけで読む価値はない、それどころか有害な本だ、と談じています。
書き方がよくなかったかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
以下、書き方を変えて、長々と再度タケダ批判をしたいと思います。
私も昔、何冊かタケダセイジの本は読みました。
現象学入門だとかハイデガー入門だとかそのたぐいのものでしたが、
あまりにひどいので破り捨てました。
冗談ではなくて、本当にやぶりました。
現物が手元にないのでここのこの記述が決定的に間違っているとか
根本的な誤解がここにあるとか、そういうことがいえません。
以下の文章はうろ覚えにもとづくものです。
よろしくおねがいします。
タケダセイジの本になんの価値があるんでしょう?
わかりやすいんですか?
なにがわかりやすいんでしょう?
わかりやすい例がある?
しかし、よくよく読み直してください。
それまで説明しようとしていた理論的な部分と、そのあと例示している事柄は、かみあっていますか?
超越論的な次元の話を、日常的な次元にひきずりおろして無理矢理な話をつくっていませんか?
現象学の根本的な発想のひとつは、現象学的エポケーにあるのに、まるでそれにそぐわない例をあげてはいませんか?
例をふと思い出しました。
リンゴと、それをいろんな生物が見ているイラストがありました。
カントの図式、ということで
「生物によって見え方が違う、完全な認識は神が有する」そういうようなことを書いていた気がします。
しかし現象学は「完全な認識は神が有する」というのがないのだ、みたいなことを書いていた気がします。
これはとんでもないデマカセですよね。
カントがそんな図式的なことを考えていたわけはないし、
フッサールについても同様です。
現象学的エポケーは、自然的態度における存在措定を括弧に入れる(判断中止する)ことで、現象学の主題である純粋意識の領域を開くという方法的概念で、
それはフッサール自身長年何度も問い直して精査していった概念です。
なのにタケダは、きわめて通俗的な自然的態度を持ち出してわけのわからない説明をしています。
エポケーの話に、自然的態度を持ち込んだようなものを示してはいけませんよね。
そこの区別はしっかりとして、なおかつ遂行様態の話をする等が妥当ではないでしょうか。
フッサール自身はまるでとっていなかった図式を使って、
フッサールの言っていることとはまるで異なることを説明しているんですから、
たとえそれがどれだけわかりやすかったとしても、全く意味はないのはわかりますよね。
タケダにならって”わかりやすい”例を挙げると、
あるひとに、アコースティックギターの弾き方を質問したのに
同じギターだからということでエレキギターのエフェクターの話だけを(それも自慢げに)されたとすれば
その話の出来不出来に関係なく、それは全く無意味な回答ですよね。
そのとき、「ギターの話だから一緒じゃないか」といわれたら、むっときますよね。
タケダの本って、全部そんなかんじなんです。
ギターなら、アコギとエレキは見た目が違うからすぐわかりますが、
哲学はそのちがいがわかりにくいんです、初学者には。
タケダセイジの文章は下劣だと思います。
フッサールやハイデガーの本を読めば当たり前に理解できることを、
まるで自分が世紀の大発見をしたかのように大げさに書き殴っているからです。
そして、自分を偉く見せたいがために、
哲学的な問題をまったく無視して強引なストーリーを作り上げたりもします。
これまた下劣ですよね。
「手前存在よりも手許存在を根源的とすることで、ハイデガーは近代哲学を乗り越えたのだ」
とかいう具合に。(この例は適当にかきましたが、だいたいこんなかんじでしたよね)
強引なストーリーをでっちあげているかどうかは、根拠付けを行っているか否かを見ればすぐわかります。
「私の考えでは、AはBなのである」
という言い方をしているとき、十中八九、無根拠です。
こんな無意味なことが許されるはずありません。
社会で言うと、予算要求などをするときに
「何千万の予算をください。試算はしてませんが、私の考えではこれくらい必要です」といったところで
あほか、といわれるのがオチです。
タケダは本の中で徹頭徹尾こんなトンチンカンな発言をくりかえしているんです。
入門書であればこそ、こんなに無意味な(それどころか有害な)文章を書いてはいけないはずです。
たとえば、小学生でまちがったことを教えたら、その子は一生その先入見の下で生きることになります。
だから、初学者の学習内容はきわめて慎重に精査されなければならないんです。
哲学の初学時だって一緒ですよね。
そういえばタケダの『プラトン入門』を立ち読みでぺらっとめくったとき、
ハイデガーのことが書いてました。
びっくりしましたよ。
「ハイデガーは無を実体化して考えているからだめだ」みたいなことを書いていたからです。
それが、まがりなりにも以前にハイデガーの入門書を書いた人間の言うことでしょうか?
ハイデガーがどれだけ、無を、いわゆる「実体」的な思考法に巻き込まないようにしようと注意を払って思索していたか。
そのことをまるで知らないのか、まったく無視しているんです、タケダという人間は。
そしてハイデガーにおける無の思索は、ハイデガーの思索の根幹部分に関わる思索であって、とりちがえてはいけないところです。
そこの点についてこれだけ手抜きの解釈を垂れ流していいわけがないんです。
タケダ本人の思想等は知りません。
しかし、以上の点に見られる彼の思想的な不誠実から推測するに、
読むに値する本だとは思えないんです、どうしても。
タケダの本を読む人は、
彼が力強く主張する事柄が、その前後でしっかり根拠づけられているか確認してみてください。
単に感覚的にわかる、ではなくて、論理的に説明されているかという観点で。
長々とすいませんでした。
私は、哲学が好きです。
だから、哲学に興味をもってくれているひとがタケダの本なんかを手に取るのが口惜しいんです。
タケダのなんかより、もっといい本はいくらでもあるんです。
そっちを読んで、「哲学は合わない」と思うなら、それは仕方ないと思います。
でも、タケダのみたいな無価値な本を読んで時間を無駄遣いして「哲学は結局こんなもの」と思われるのが口惜しいんです。
谷徹『これが現象学だ』はいい本だと思います。
このコミュニティではぜひこういう本を推薦していただきたいものです。
ねぎとろです。
私のタケダ批判が誹謗中傷の域を出ないもの、という意見をいただいておりましたのに
返答せずに申し訳ないです。
たしかに、私個人の意見だけで読む価値はない、それどころか有害な本だ、と談じています。
書き方がよくなかったかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
以下、書き方を変えて、長々と再度タケダ批判をしたいと思います。
私も昔、何冊かタケダセイジの本は読みました。
現象学入門だとかハイデガー入門だとかそのたぐいのものでしたが、
あまりにひどいので破り捨てました。
冗談ではなくて、本当にやぶりました。
現物が手元にないのでここのこの記述が決定的に間違っているとか
根本的な誤解がここにあるとか、そういうことがいえません。
以下の文章はうろ覚えにもとづくものです。
よろしくおねがいします。
タケダセイジの本になんの価値があるんでしょう?
わかりやすいんですか?
なにがわかりやすいんでしょう?
わかりやすい例がある?
しかし、よくよく読み直してください。
それまで説明しようとしていた理論的な部分と、そのあと例示している事柄は、かみあっていますか?
超越論的な次元の話を、日常的な次元にひきずりおろして無理矢理な話をつくっていませんか?
現象学の根本的な発想のひとつは、現象学的エポケーにあるのに、まるでそれにそぐわない例をあげてはいませんか?
例をふと思い出しました。
リンゴと、それをいろんな生物が見ているイラストがありました。
カントの図式、ということで
「生物によって見え方が違う、完全な認識は神が有する」そういうようなことを書いていた気がします。
しかし現象学は「完全な認識は神が有する」というのがないのだ、みたいなことを書いていた気がします。
これはとんでもないデマカセですよね。
カントがそんな図式的なことを考えていたわけはないし、
フッサールについても同様です。
現象学的エポケーは、自然的態度における存在措定を括弧に入れる(判断中止する)ことで、現象学の主題である純粋意識の領域を開くという方法的概念で、
それはフッサール自身長年何度も問い直して精査していった概念です。
なのにタケダは、きわめて通俗的な自然的態度を持ち出してわけのわからない説明をしています。
エポケーの話に、自然的態度を持ち込んだようなものを示してはいけませんよね。
そこの区別はしっかりとして、なおかつ遂行様態の話をする等が妥当ではないでしょうか。
フッサール自身はまるでとっていなかった図式を使って、
フッサールの言っていることとはまるで異なることを説明しているんですから、
たとえそれがどれだけわかりやすかったとしても、全く意味はないのはわかりますよね。
タケダにならって”わかりやすい”例を挙げると、
あるひとに、アコースティックギターの弾き方を質問したのに
同じギターだからということでエレキギターのエフェクターの話だけを(それも自慢げに)されたとすれば
その話の出来不出来に関係なく、それは全く無意味な回答ですよね。
そのとき、「ギターの話だから一緒じゃないか」といわれたら、むっときますよね。
タケダの本って、全部そんなかんじなんです。
ギターなら、アコギとエレキは見た目が違うからすぐわかりますが、
哲学はそのちがいがわかりにくいんです、初学者には。
タケダセイジの文章は下劣だと思います。
フッサールやハイデガーの本を読めば当たり前に理解できることを、
まるで自分が世紀の大発見をしたかのように大げさに書き殴っているからです。
そして、自分を偉く見せたいがために、
哲学的な問題をまったく無視して強引なストーリーを作り上げたりもします。
これまた下劣ですよね。
「手前存在よりも手許存在を根源的とすることで、ハイデガーは近代哲学を乗り越えたのだ」
とかいう具合に。(この例は適当にかきましたが、だいたいこんなかんじでしたよね)
強引なストーリーをでっちあげているかどうかは、根拠付けを行っているか否かを見ればすぐわかります。
「私の考えでは、AはBなのである」
という言い方をしているとき、十中八九、無根拠です。
こんな無意味なことが許されるはずありません。
社会で言うと、予算要求などをするときに
「何千万の予算をください。試算はしてませんが、私の考えではこれくらい必要です」といったところで
あほか、といわれるのがオチです。
タケダは本の中で徹頭徹尾こんなトンチンカンな発言をくりかえしているんです。
入門書であればこそ、こんなに無意味な(それどころか有害な)文章を書いてはいけないはずです。
たとえば、小学生でまちがったことを教えたら、その子は一生その先入見の下で生きることになります。
だから、初学者の学習内容はきわめて慎重に精査されなければならないんです。
哲学の初学時だって一緒ですよね。
そういえばタケダの『プラトン入門』を立ち読みでぺらっとめくったとき、
ハイデガーのことが書いてました。
びっくりしましたよ。
「ハイデガーは無を実体化して考えているからだめだ」みたいなことを書いていたからです。
それが、まがりなりにも以前にハイデガーの入門書を書いた人間の言うことでしょうか?
ハイデガーがどれだけ、無を、いわゆる「実体」的な思考法に巻き込まないようにしようと注意を払って思索していたか。
そのことをまるで知らないのか、まったく無視しているんです、タケダという人間は。
そしてハイデガーにおける無の思索は、ハイデガーの思索の根幹部分に関わる思索であって、とりちがえてはいけないところです。
そこの点についてこれだけ手抜きの解釈を垂れ流していいわけがないんです。
タケダ本人の思想等は知りません。
しかし、以上の点に見られる彼の思想的な不誠実から推測するに、
読むに値する本だとは思えないんです、どうしても。
タケダの本を読む人は、
彼が力強く主張する事柄が、その前後でしっかり根拠づけられているか確認してみてください。
単に感覚的にわかる、ではなくて、論理的に説明されているかという観点で。
長々とすいませんでした。
私は、哲学が好きです。
だから、哲学に興味をもってくれているひとがタケダの本なんかを手に取るのが口惜しいんです。
タケダのなんかより、もっといい本はいくらでもあるんです。
そっちを読んで、「哲学は合わない」と思うなら、それは仕方ないと思います。
でも、タケダのみたいな無価値な本を読んで時間を無駄遣いして「哲学は結局こんなもの」と思われるのが口惜しいんです。
谷徹『これが現象学だ』はいい本だと思います。
このコミュニティではぜひこういう本を推薦していただきたいものです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
エドムント・フッサール 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
エドムント・フッサールのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75496人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9045人