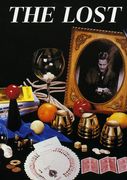LEIPZIG, NATE (1873-1939)
スウェーデンのストックホルム生まれ。
十代の頃にアメリカ移住。
もともとは光学研磨、つまりレンズ製造者として生計を立てていた。
30歳くらいの頃から本格的プロ活動を始める。
主にボードビルで活躍し、アメリカのみならず世界中を駆け巡った。
ライプチッヒの演技の特徴は、クロースアップの演技をステージで通用するくらいまでに高めた事だろう。
そのほとんどの演技はカードマジックである。
代表作は”カードフライト”と”スラップエーセス”。
いずれもヒリヤードの『アートオブマジック』に解説されている。
カードマジック以外でも”シガレットペーパーの復活”や”葉巻のプロダクション”、”スタックオブクォーター”などの傑作も多い。
ダイ・バーノンは師匠とあおぎ、プロとしての哲学を学んだ。
以下の言葉は、バーノンの脳裏に刻まれた事だろう。
「ダイ、私は50年もマジックをやっていて気づいた事は、観客は紳士にだまされる事を喜ぶものなのだ、という事だね。」
「人間的に好かれれば、その人の行うマジックも好かれるものなのだ、という事を覚えておきなさい。」
後にギャンソンが著しバーノンの名前でライプチッヒの本(Dai Vernon's Tribute to Nate Leipzig)が出版された。
『スターズオブマジック』(http://
ライプチッヒの二つの格言。
「少しでも興味がなさそうに見えたら、すぐに別のマジックに移るべきである。」
「強く望まれない限りは、マジックをしてはいけない。」
「カード奇術の専門家にとってなんと魅力に富んだ名であろうか。今世紀初期にボードビルの有名人であった彼は、依然としてほかとは比べものにならないほど器用なスライハンドの奇術師としての地位を保持している。そのスライハンドは、柔軟な指と抜け目ない頭脳とによって生み出されるとても巧みなものである。彼は器用で、抜け目のない奇術師であり、取り入る方法を心得、熟達している。奇術のユーモアは度を越しさえしなければとても楽しいものなのである。
彼は娯楽的奇術の名人である。」
J. N. ヒリヤード
ダイ・バーノン
http://
スウェーデンのストックホルム生まれ。
十代の頃にアメリカ移住。
もともとは光学研磨、つまりレンズ製造者として生計を立てていた。
30歳くらいの頃から本格的プロ活動を始める。
主にボードビルで活躍し、アメリカのみならず世界中を駆け巡った。
ライプチッヒの演技の特徴は、クロースアップの演技をステージで通用するくらいまでに高めた事だろう。
そのほとんどの演技はカードマジックである。
代表作は”カードフライト”と”スラップエーセス”。
いずれもヒリヤードの『アートオブマジック』に解説されている。
カードマジック以外でも”シガレットペーパーの復活”や”葉巻のプロダクション”、”スタックオブクォーター”などの傑作も多い。
ダイ・バーノンは師匠とあおぎ、プロとしての哲学を学んだ。
以下の言葉は、バーノンの脳裏に刻まれた事だろう。
「ダイ、私は50年もマジックをやっていて気づいた事は、観客は紳士にだまされる事を喜ぶものなのだ、という事だね。」
「人間的に好かれれば、その人の行うマジックも好かれるものなのだ、という事を覚えておきなさい。」
後にギャンソンが著しバーノンの名前でライプチッヒの本(Dai Vernon's Tribute to Nate Leipzig)が出版された。
『スターズオブマジック』(http://
ライプチッヒの二つの格言。
「少しでも興味がなさそうに見えたら、すぐに別のマジックに移るべきである。」
「強く望まれない限りは、マジックをしてはいけない。」
「カード奇術の専門家にとってなんと魅力に富んだ名であろうか。今世紀初期にボードビルの有名人であった彼は、依然としてほかとは比べものにならないほど器用なスライハンドの奇術師としての地位を保持している。そのスライハンドは、柔軟な指と抜け目ない頭脳とによって生み出されるとても巧みなものである。彼は器用で、抜け目のない奇術師であり、取り入る方法を心得、熟達している。奇術のユーモアは度を越しさえしなければとても楽しいものなのである。
彼は娯楽的奇術の名人である。」
J. N. ヒリヤード
ダイ・バーノン
http://
|
|
|
|
コメント(44)
ライプチッヒのマジックで現在でも充分通じるマジックの一つは”シガー(葉巻)”のマジックです。
現象の一部はターベルコースにも記載されていますが、普通の小さなパース(小銭入れ)からでかい葉巻が、にゅう、と現れる、というものです。
ターベルコースなどを読むと今なのがはたして面白いんだろうか?と思っていましたが、実際行うと大変一般受けする現象です。
ライプチッヒのやり方はターベルとはまた違うのですが、現在では、エリック・デキャンプ師、クリス・ケナー師などが受け継いでいます。
私自身はフォクシーシガーを用いて行っています。
意外なところでは、根本毅さんもシガーの手順を発表しています。
現象の一部はターベルコースにも記載されていますが、普通の小さなパース(小銭入れ)からでかい葉巻が、にゅう、と現れる、というものです。
ターベルコースなどを読むと今なのがはたして面白いんだろうか?と思っていましたが、実際行うと大変一般受けする現象です。
ライプチッヒのやり方はターベルとはまた違うのですが、現在では、エリック・デキャンプ師、クリス・ケナー師などが受け継いでいます。
私自身はフォクシーシガーを用いて行っています。
意外なところでは、根本毅さんもシガーの手順を発表しています。
昭和38年力書房の『トップマジック39』の巻頭に”葉巻(シガー)のマニピュレーション”が載っています。
解説は高木重朗先生です。
名手ライプチッヒの手順を元にして組み立て直した、と書いてあります。
「日本では、葉巻があまり親しまれていないので、これを使った奇術はさほど行われていません。これに反して、欧米では非常に盛んに行われており、これを呼び物にしている奇術師もあります。
葉巻の奇術は、技法は同じようでもシガレット(紙巻きタバコ)とは異なった感覚を持っていますから、手練奇術の新しい分野として、研究する必要があると思います。」
高木重朗
手順を見る限りシンプルで素晴らしい手順です。
基本的現象は、ガマ口(小銭入れ)を開けるとそれよりも大きい葉巻が出てきます。
もちろん葉巻もガマ口も改めますが、何の仕掛けもありません。
もう一度ガマ口を開けるともう一本葉巻が出てきます。
ガマ口をしまい、葉巻もしまい、客に渡した葉巻もしまいますが、空中から葉巻が出現します。
ポケットにしまってもしまっても出現します。
最後は完璧(両手を改める)に葉巻が消失します。
再びガマ口をポケットから取り出し、葉巻が出現して終わります。
クロースアップとしてもサロンとしても通用する手順です。
原案や、他の改案との比較をいずれ行いたいと思います。
解説は高木重朗先生です。
名手ライプチッヒの手順を元にして組み立て直した、と書いてあります。
「日本では、葉巻があまり親しまれていないので、これを使った奇術はさほど行われていません。これに反して、欧米では非常に盛んに行われており、これを呼び物にしている奇術師もあります。
葉巻の奇術は、技法は同じようでもシガレット(紙巻きタバコ)とは異なった感覚を持っていますから、手練奇術の新しい分野として、研究する必要があると思います。」
高木重朗
手順を見る限りシンプルで素晴らしい手順です。
基本的現象は、ガマ口(小銭入れ)を開けるとそれよりも大きい葉巻が出てきます。
もちろん葉巻もガマ口も改めますが、何の仕掛けもありません。
もう一度ガマ口を開けるともう一本葉巻が出てきます。
ガマ口をしまい、葉巻もしまい、客に渡した葉巻もしまいますが、空中から葉巻が出現します。
ポケットにしまってもしまっても出現します。
最後は完璧(両手を改める)に葉巻が消失します。
再びガマ口をポケットから取り出し、葉巻が出現して終わります。
クロースアップとしてもサロンとしても通用する手順です。
原案や、他の改案との比較をいずれ行いたいと思います。
ライプチッヒの本名は、ネイサン・ライプチッガー(Nathan Leipziger)です。8人兄弟(男7人,女1人)の下から3番目ですから、かなりの大家族です。
ライプチッヒの父はロシア人です。
もともとはロシアに住んでいたようですが、若い頃にはスウェーデンに移住したようです。
その後アメリカにも渡り、ニューヨークでは奥さんを見つけました。4人の子供に恵まれ、スエーデンのストックホルムに戻ってからネイトが生まれました。
ライプチッヒの父はわりと成功したようで、自分の子供たちには充分な教育を施していたようです。
絵を書く事、音楽、そしてなぜかマジック。
初めて見たマジシャンは、どうも親戚のおじさんのようです。
ライプチッヒの父はロシア人です。
もともとはロシアに住んでいたようですが、若い頃にはスウェーデンに移住したようです。
その後アメリカにも渡り、ニューヨークでは奥さんを見つけました。4人の子供に恵まれ、スエーデンのストックホルムに戻ってからネイトが生まれました。
ライプチッヒの父はわりと成功したようで、自分の子供たちには充分な教育を施していたようです。
絵を書く事、音楽、そしてなぜかマジック。
初めて見たマジシャンは、どうも親戚のおじさんのようです。
10代の頃には再び家族はアメリカに移住。ミシガン州はデトロイトです。
父親の芸術に対する理解なのか、その才能なのか、一家はそうした事に長けていました。
ネイトのお兄さんに至ってはその後、絵の才能を見いだされ、新聞のポンチ絵漫画家として成功を収めています。
ネイト自身がマジックに興味を持ったのは少年時代であり、母親のお兄さん(叔父)の影響です。プロではなかったようですが、サーカスなどで行う本格派のマジシャンだったそうです。
彼の手ほどきをうけクロースアップマジックを身につけるようになり、家族や友達に見せていたのです。
しかし、そうした事はつかの間の幸せだったようです。
父親の仕事の失敗から経済状況が悪くなり、12歳からネイトは働かなくてはなりませんでした。
眼鏡屋のブラック社(L. Black & Co)で丁稚奉公をはじめたのです。
父親の芸術に対する理解なのか、その才能なのか、一家はそうした事に長けていました。
ネイトのお兄さんに至ってはその後、絵の才能を見いだされ、新聞のポンチ絵漫画家として成功を収めています。
ネイト自身がマジックに興味を持ったのは少年時代であり、母親のお兄さん(叔父)の影響です。プロではなかったようですが、サーカスなどで行う本格派のマジシャンだったそうです。
彼の手ほどきをうけクロースアップマジックを身につけるようになり、家族や友達に見せていたのです。
しかし、そうした事はつかの間の幸せだったようです。
父親の仕事の失敗から経済状況が悪くなり、12歳からネイトは働かなくてはなりませんでした。
眼鏡屋のブラック社(L. Black & Co)で丁稚奉公をはじめたのです。
丁稚奉公をはじめたネイトは、次第に仕事に興味を持ち出し、真面目な性格が会社でも気に入られ、光学研磨技術つまりレンズについての勉強をしていくのです。
結果的に17年もの間、同じ会社に勤めたのです。
ライプチッヒの学者のような真面目な性格は会社で培われ、エンターテイナーとしての資質は叔父の教育によって芽生えたのでしょう。
一見矛盾するその二つの資質が上手くブレンドされたのです。
会社勤めをしながらもネイトは決してマジックの勉強を怠りませんでした。
友人たちにも好評だったようです。
ではなぜ、プロマジシャンを志す事になったのでしょうか?
それはある一人のマジシャンの演技を見てしまったからにほかなりません。
そのネイト・ライプチッヒ誕生のきっかけとなった偉大なマジシャンとは!
かのアレキサンダー・ハーマン,その人だったのです。
アレキサンダー・ハーマン
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=9836341&comm_id=236730
結果的に17年もの間、同じ会社に勤めたのです。
ライプチッヒの学者のような真面目な性格は会社で培われ、エンターテイナーとしての資質は叔父の教育によって芽生えたのでしょう。
一見矛盾するその二つの資質が上手くブレンドされたのです。
会社勤めをしながらもネイトは決してマジックの勉強を怠りませんでした。
友人たちにも好評だったようです。
ではなぜ、プロマジシャンを志す事になったのでしょうか?
それはある一人のマジシャンの演技を見てしまったからにほかなりません。
そのネイト・ライプチッヒ誕生のきっかけとなった偉大なマジシャンとは!
かのアレキサンダー・ハーマン,その人だったのです。
アレキサンダー・ハーマン
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=9836341&comm_id=236730
10代の頃のネイトは友達同士で手品を見せあっていました。
もっぱらお金のないネイトはスライハンドばかりで技術を磨き、マジック道具は友達から見せてもらったり、貸してもらっているような状態でした。そうやって知識と技術を増やしていたのです。
そんな頃です。
かの偉大なるアレキサンダー・ハーマンが地元デトロイトのオペラハウスにやってきたのは。
初めて見るプロマジシャンのフルイブニングショーをさっそく見に行ってきました。
もちろんお金がないので一番安い席しか買えませんでしたが、その日はネイト少年にとってもっとも衝撃を受けた日だった事でしょう。
もちろんハーマンの素晴らしいマジックに衝撃を受ける少年は少なくありませんでした。
しかし、ネイトが他の少年たちと全く違っていたのは、マジックのネタやタネに感銘を受けたのではなく、ハーマン自身の持つオーラでした。
それはパフォーマンスのスタイルでもあります。
ハーマン自身の個性が観客を魅了してやまない、そうした部分がもっともネイト少年の心に刻まれたのです。
もっぱらお金のないネイトはスライハンドばかりで技術を磨き、マジック道具は友達から見せてもらったり、貸してもらっているような状態でした。そうやって知識と技術を増やしていたのです。
そんな頃です。
かの偉大なるアレキサンダー・ハーマンが地元デトロイトのオペラハウスにやってきたのは。
初めて見るプロマジシャンのフルイブニングショーをさっそく見に行ってきました。
もちろんお金がないので一番安い席しか買えませんでしたが、その日はネイト少年にとってもっとも衝撃を受けた日だった事でしょう。
もちろんハーマンの素晴らしいマジックに衝撃を受ける少年は少なくありませんでした。
しかし、ネイトが他の少年たちと全く違っていたのは、マジックのネタやタネに感銘を受けたのではなく、ハーマン自身の持つオーラでした。
それはパフォーマンスのスタイルでもあります。
ハーマン自身の個性が観客を魅了してやまない、そうした部分がもっともネイト少年の心に刻まれたのです。
アレキサンダー・ハーマンがいかに当時の人々に影響を与えていたかがわかります。
ハーマンがいなければ、ライプチッヒもサーストンもこの世に生まれることはなかったのですから。
ライプチッヒは後に自伝にこのハーマンの素晴らしさについて記述しています。
「誰もハーマンにはなれず、ハーマンは独自のスタイルを持っていた。彼がステージに上がれば観客は一挙手一投足に注目し、にっこりと微笑むと皆は一様に魅了される。マジックウォンドの先端に流れるような指先から本物のオレンジが出現した時は、まさにマジックだった…。そしてなによりも繰り広げられるトリックのひとつひとつに本当のユーモアがあった。」
そんなマジック好きなネイトに会社の同僚がある一冊のコピーを渡してくれました。
イギリスで出版された『シークレットアウト(The Secret Out)』というマジック教本です。
ネイトはこれを読み真剣にマジックを勉強するのです。
一冊をマスターしたら次、と何冊ものマジックの本から知識をどんどん得ていきました。
ハーマンがいなければ、ライプチッヒもサーストンもこの世に生まれることはなかったのですから。
ライプチッヒは後に自伝にこのハーマンの素晴らしさについて記述しています。
「誰もハーマンにはなれず、ハーマンは独自のスタイルを持っていた。彼がステージに上がれば観客は一挙手一投足に注目し、にっこりと微笑むと皆は一様に魅了される。マジックウォンドの先端に流れるような指先から本物のオレンジが出現した時は、まさにマジックだった…。そしてなによりも繰り広げられるトリックのひとつひとつに本当のユーモアがあった。」
そんなマジック好きなネイトに会社の同僚がある一冊のコピーを渡してくれました。
イギリスで出版された『シークレットアウト(The Secret Out)』というマジック教本です。
ネイトはこれを読み真剣にマジックを勉強するのです。
一冊をマスターしたら次、と何冊ものマジックの本から知識をどんどん得ていきました。
ギャンソンによるバーノンタッチの実例の一つにライプチッヒの話があります。
ライプチッヒが観客にカードを選ばせるときには、ピークコントロールを使います。
しかし、観客が術者のデックをピークしようとしたときにライプチッヒはこう言うのです。
「ちょっとカードを1枚思い浮かべて下さい。」
実際は観客が分けたところのカードを見て覚えるだけに過ぎないことなのに「ちょっとカードを1枚思い浮かべて下さい。」というセリフによって、それを見ている大勢の観客は、そのお客がデックに触ったことさえも忘れてしまい、ただ単にその一人の観客が頭に描いたカードを当ててしまうように錯覚してしまうのです。
こうしたサトルティによって単なるカード当てがまるで超能力のように感じさせてしまうのです。もちろんこうした手法をカード奇術に取り入れたのはライプチッヒが最初の様です。
ライプチッヒが観客にカードを選ばせるときには、ピークコントロールを使います。
しかし、観客が術者のデックをピークしようとしたときにライプチッヒはこう言うのです。
「ちょっとカードを1枚思い浮かべて下さい。」
実際は観客が分けたところのカードを見て覚えるだけに過ぎないことなのに「ちょっとカードを1枚思い浮かべて下さい。」というセリフによって、それを見ている大勢の観客は、そのお客がデックに触ったことさえも忘れてしまい、ただ単にその一人の観客が頭に描いたカードを当ててしまうように錯覚してしまうのです。
こうしたサトルティによって単なるカード当てがまるで超能力のように感じさせてしまうのです。もちろんこうした手法をカード奇術に取り入れたのはライプチッヒが最初の様です。
久々の書き込みです。
先日、神戸奇術研究会主催の『神戸マジックコンベンション』に参加しました。
その二次会にてRYUSEI師が演じられた奇術が秀逸でした。
現象は(うろ覚えですが・・・)
13枚のスペードをシャッフルしてグラスに入れておきます。
13枚のハートをシャッフルし、その中から1枚選んでもらい元に戻します。
グラスのスペードを出し、ハートのパケットの横におきます。
両方のトップを1枚ずつ表向けていくと・・・何と! シャッフルされたハートとグラスの中に入っていたスペードの順番が一致しています。
しかも、スペードの中の1枚が裏向いています。その枚数目のハートが、まさに選ばれたカードなのです。
あまり見かけない現象で、非常に受け、一様に頭を悩ませていました。
そこで、RYUSEI師から「Leipzigの奇術ですよ」とのヒントが。
帰宅後、早速“Dai Vernon's Tribute to Nate Leipzig”を読み直すと“Sympathetic 13” p.176 として同現象の作品が掲載されています。
読んだ記憶はあるのですが、とても受けそうでない気がして、忘却の彼方へ行ってました。
読み直して、どうやらRYUSEI師、かなりアレンジを加えているであろうことに気付きました。
とは言え、原案もなかなか興味深い作品で、Leipzigらしい『クロースアップネタをステージでやる』的な趣向。
この本は200ページ弱ですが、まだまだ研究の余地もあり、古典的なものでも十分通用することを、今回のRYUSEI師の演技で改めて感じました。
先日、神戸奇術研究会主催の『神戸マジックコンベンション』に参加しました。
その二次会にてRYUSEI師が演じられた奇術が秀逸でした。
現象は(うろ覚えですが・・・)
13枚のスペードをシャッフルしてグラスに入れておきます。
13枚のハートをシャッフルし、その中から1枚選んでもらい元に戻します。
グラスのスペードを出し、ハートのパケットの横におきます。
両方のトップを1枚ずつ表向けていくと・・・何と! シャッフルされたハートとグラスの中に入っていたスペードの順番が一致しています。
しかも、スペードの中の1枚が裏向いています。その枚数目のハートが、まさに選ばれたカードなのです。
あまり見かけない現象で、非常に受け、一様に頭を悩ませていました。
そこで、RYUSEI師から「Leipzigの奇術ですよ」とのヒントが。
帰宅後、早速“Dai Vernon's Tribute to Nate Leipzig”を読み直すと“Sympathetic 13” p.176 として同現象の作品が掲載されています。
読んだ記憶はあるのですが、とても受けそうでない気がして、忘却の彼方へ行ってました。
読み直して、どうやらRYUSEI師、かなりアレンジを加えているであろうことに気付きました。
とは言え、原案もなかなか興味深い作品で、Leipzigらしい『クロースアップネタをステージでやる』的な趣向。
この本は200ページ弱ですが、まだまだ研究の余地もあり、古典的なものでも十分通用することを、今回のRYUSEI師の演技で改めて感じました。
センパ13。
実は日本のテレビで、若い人がこれを実演していたのを見たのだ。
さらにそのずいぶん前に、根本さんのところでこれを売っていたのだった!!やー、失敗した、買っておけばよかったと思って地団太した。
そしてテレビの少し前に、松田著トリックカード事典に、この記述があったことも、思い出した!!ご覧下さい。
さらに、その記述にディングルのカフマン本にバリエーションあり、と見て、読んでみたものの、これはまったく良く分からないものだった。
もちろんレギュラーでは出来ない!買っておけば、と思ったものの、それはホイル製のものだったらしい。しかし根元解説には、レギュラーで行う誰かのバリエーションも載っていた様子。買った人がうらやましい。しかも、買った人は忘れていると思う。
コウスケさんの見解。これは私にはちょっと意外なものでした。先にテレビの実演を見たからなのかもしれませんが、誰がやっても鉄板のとりネタになりうるものという認識をしていたのです。
具体的に、どんなところに、実演への困難があるものと思われますか?教えていただけると勉強になります。
実は日本のテレビで、若い人がこれを実演していたのを見たのだ。
さらにそのずいぶん前に、根本さんのところでこれを売っていたのだった!!やー、失敗した、買っておけばよかったと思って地団太した。
そしてテレビの少し前に、松田著トリックカード事典に、この記述があったことも、思い出した!!ご覧下さい。
さらに、その記述にディングルのカフマン本にバリエーションあり、と見て、読んでみたものの、これはまったく良く分からないものだった。
もちろんレギュラーでは出来ない!買っておけば、と思ったものの、それはホイル製のものだったらしい。しかし根元解説には、レギュラーで行う誰かのバリエーションも載っていた様子。買った人がうらやましい。しかも、買った人は忘れていると思う。
コウスケさんの見解。これは私にはちょっと意外なものでした。先にテレビの実演を見たからなのかもしれませんが、誰がやっても鉄板のとりネタになりうるものという認識をしていたのです。
具体的に、どんなところに、実演への困難があるものと思われますか?教えていただけると勉強になります。
「申し分のない天才芸を身につけているライプチッヒ氏は、いとも簡単に奇術を行うので誰にもそれが即席のものに見える。
彼にとってスライハンドはとても手慣れたものなのでさまざまな技法を、それをどのようにして行うのかなどと少しも考えないで無意識のうちに行う。
それでもやはり彼自身も告白しているが、仕掛けを使って奇術の効果を上げることができると分かったときは、彼は仕掛けを使うのを躊躇しない。
客をどのような手段で煙にまくかは重要なことではない、という事をマジシャンは心に留めておくといい。
ネイト・ライプチッヒほど、若いマジシャンにその芸をまねるのをすすめられる者はいない。」
J. N. ヒリヤード
彼にとってスライハンドはとても手慣れたものなのでさまざまな技法を、それをどのようにして行うのかなどと少しも考えないで無意識のうちに行う。
それでもやはり彼自身も告白しているが、仕掛けを使って奇術の効果を上げることができると分かったときは、彼は仕掛けを使うのを躊躇しない。
客をどのような手段で煙にまくかは重要なことではない、という事をマジシャンは心に留めておくといい。
ネイト・ライプチッヒほど、若いマジシャンにその芸をまねるのをすすめられる者はいない。」
J. N. ヒリヤード
>ヒリヤードのライプチッヒ評は、彼個人の評でもありますが、奇術を演じるものすべてに対しての『至言』だと思います。
同感ですね。
このヒリヤードの言葉は、名著『グレーターマジック』のものです。
そしてこの言葉にあとに続くのがそれを具体化した2作品が紹介されているのです。
それこそが”シンパセティック・クラブ”すなわちシンパセティックカードなのです。
たった二つの作品だけでも深く掘り下げるとライプチッヒの凄さが伝わってくるでしょう。
Locke さん。
Jorg Alexanderの「The Sympathetic Ten」 全く知りませんし、映像も持っていません。最近の方ですか?
同感ですね。
このヒリヤードの言葉は、名著『グレーターマジック』のものです。
そしてこの言葉にあとに続くのがそれを具体化した2作品が紹介されているのです。
それこそが”シンパセティック・クラブ”すなわちシンパセティックカードなのです。
たった二つの作品だけでも深く掘り下げるとライプチッヒの凄さが伝わってくるでしょう。
Locke さん。
Jorg Alexanderの「The Sympathetic Ten」 全く知りませんし、映像も持っていません。最近の方ですか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-