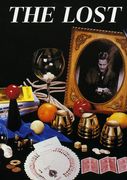『唐土秘事海(もろこしひじのうみ)』 Morokoshi-Hiji-no-Umi
「とうどひじのうみ」と読む説もある。
半紙本二冊。上巻は絵入り目録、下巻はその伝授19条。
著者は、多賀谷環中仙。刊行年月日も板元も不明。
初版は享保年間と推定され、後に含霊軒の蔵権となった。
表題に「唐土」とあり、上巻の目録も唐人を描くが内容はそうではなく、明治期にすべてを西洋手品と称した類と同じであり珍奇さを狙っているものであろう。
「紙にて作りたる魚を動かす」「天人めがねの伝授(三角プリズム)」「ビードロの臥竜竹」「灯心に魂を入れうごかす」「座敷に俄かにかけひを作る(サイフォン)」「月代・額・肘・尻にて笛を吹く(風琴)」「作りたる竜をはたらかす(水銀利用)」「絵を水へいれ外の絵にかへる(秘密インク)」など、科学遊戯的なもの多く、「ひよく包という不思議の術」や「きせるを二つに折り左右に持ちてたばこを呑む術」など目新しい。
水中より乾いた砂を取り出す「五色の砂の曲」や、これと同巧異曲の「水中へ五色の水を入れ別々に汲み分ける事」「白き紙を水中にて五色に染める事」など、色彩を積極的に使用して効果を上げ、五色の水はビードロのつぼに入れて持ち出す演出である。こんなところ異国的な唐土の題名に通じるのかもしれない。
水からくりの「蝋燭の真より水を出す事」は水芸の最も古い種明かしであり、江戸末期には種々の物が作られた。
http://
近藤勝『日本奇術文献ノート35』(1954)p2「國書解題より」服部静夫
『奇術研究 第6号』(1957 力書房)p32「奇術文献を語る・和書の部」山本慶一
『ワンツースリー 24号』(1999 日本奇術協会)p6「『噴水の術』の手品考・其の二」平岩白風
『ワンツースリー 31号』(2001 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の二」平岩白風
『ワンツースリー 40号』(2003 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十一」平岩白風
「とうどひじのうみ」と読む説もある。
半紙本二冊。上巻は絵入り目録、下巻はその伝授19条。
著者は、多賀谷環中仙。刊行年月日も板元も不明。
初版は享保年間と推定され、後に含霊軒の蔵権となった。
表題に「唐土」とあり、上巻の目録も唐人を描くが内容はそうではなく、明治期にすべてを西洋手品と称した類と同じであり珍奇さを狙っているものであろう。
「紙にて作りたる魚を動かす」「天人めがねの伝授(三角プリズム)」「ビードロの臥竜竹」「灯心に魂を入れうごかす」「座敷に俄かにかけひを作る(サイフォン)」「月代・額・肘・尻にて笛を吹く(風琴)」「作りたる竜をはたらかす(水銀利用)」「絵を水へいれ外の絵にかへる(秘密インク)」など、科学遊戯的なもの多く、「ひよく包という不思議の術」や「きせるを二つに折り左右に持ちてたばこを呑む術」など目新しい。
水中より乾いた砂を取り出す「五色の砂の曲」や、これと同巧異曲の「水中へ五色の水を入れ別々に汲み分ける事」「白き紙を水中にて五色に染める事」など、色彩を積極的に使用して効果を上げ、五色の水はビードロのつぼに入れて持ち出す演出である。こんなところ異国的な唐土の題名に通じるのかもしれない。
水からくりの「蝋燭の真より水を出す事」は水芸の最も古い種明かしであり、江戸末期には種々の物が作られた。
http://
近藤勝『日本奇術文献ノート35』(1954)p2「國書解題より」服部静夫
『奇術研究 第6号』(1957 力書房)p32「奇術文献を語る・和書の部」山本慶一
『ワンツースリー 24号』(1999 日本奇術協会)p6「『噴水の術』の手品考・其の二」平岩白風
『ワンツースリー 31号』(2001 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の二」平岩白風
『ワンツースリー 40号』(2003 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十一」平岩白風
|
|
|
|
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-