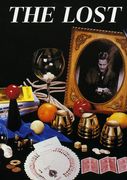『珍曲たはふれ草』(ちんきょくたわむれくさ)
半紙本二冊。上巻に目録、下巻に40種の座敷手品を解説。
著者は続編により鬼友(兼勝)であることが認められるもの詳細は分からない。
成立年代も不明であるが、続編が享保14年なのでそれ以前であろう。
針を用いて手のひらに立てる「楊枝の曲」「貫ぎたる銭を2人にて引ぱらせ置、真中より抜く事(二本の紐)」「はな紙を玉子にする事(紙玉子)」「紙を餅又は栗饅頭にする事(ハンカチーフボール」「砂を水へ入かきまぜて本のごとく乾ける砂にしてちらす事」「縄切(ロープ切り)」「はな紙にて人形を作り踊らす事(ジャリ糸使用)」「鼻紙を手の内にてもみ落花となして散らす事(花吹雪)」など。
「十二のゑと獣の通力」ではさくらをあいけんと呼び、「算盤にても又手を叩きてもいふ事を知らす事」の暗号をあいもんと称して霊交術的な演技が示されている。
「銭を一文つなぎ両はしを二人にひっぱらせ置其銭をぬいてとる事」では、従来のタネとは異なり、銭を割り捨て、かわりの銭を出す方法を用いている。
科学遊戯的なものとしてあぶり出し、水出し、豆汁の粘着性を利用した秘密インクをはじめ、「茶碗に水を入、紙にて包みこぼれぬ事」「火を水の中へ入・消えぬ事」「水の上に文字をすゆる事」など。
この本は評判が良く、版にして六種以上、板木も三度以上刻み返され、発行部数も多い。こうした事は初期本では珍しく、またこれの一部改変したものが(俗に『仙術たはむれ草』)発行されている。
『奇術研究第2号』(1956 力書房)p38「奇術文献を語る 和書の部 二」山本慶一
『ワンツースリー 43号』(2004 日本奇術協会)p14「『伝授本』の手品考・其の十四」平岩白風
半紙本二冊。上巻に目録、下巻に40種の座敷手品を解説。
著者は続編により鬼友(兼勝)であることが認められるもの詳細は分からない。
成立年代も不明であるが、続編が享保14年なのでそれ以前であろう。
針を用いて手のひらに立てる「楊枝の曲」「貫ぎたる銭を2人にて引ぱらせ置、真中より抜く事(二本の紐)」「はな紙を玉子にする事(紙玉子)」「紙を餅又は栗饅頭にする事(ハンカチーフボール」「砂を水へ入かきまぜて本のごとく乾ける砂にしてちらす事」「縄切(ロープ切り)」「はな紙にて人形を作り踊らす事(ジャリ糸使用)」「鼻紙を手の内にてもみ落花となして散らす事(花吹雪)」など。
「十二のゑと獣の通力」ではさくらをあいけんと呼び、「算盤にても又手を叩きてもいふ事を知らす事」の暗号をあいもんと称して霊交術的な演技が示されている。
「銭を一文つなぎ両はしを二人にひっぱらせ置其銭をぬいてとる事」では、従来のタネとは異なり、銭を割り捨て、かわりの銭を出す方法を用いている。
科学遊戯的なものとしてあぶり出し、水出し、豆汁の粘着性を利用した秘密インクをはじめ、「茶碗に水を入、紙にて包みこぼれぬ事」「火を水の中へ入・消えぬ事」「水の上に文字をすゆる事」など。
この本は評判が良く、版にして六種以上、板木も三度以上刻み返され、発行部数も多い。こうした事は初期本では珍しく、またこれの一部改変したものが(俗に『仙術たはむれ草』)発行されている。
『奇術研究第2号』(1956 力書房)p38「奇術文献を語る 和書の部 二」山本慶一
『ワンツースリー 43号』(2004 日本奇術協会)p14「『伝授本』の手品考・其の十四」平岩白風
|
|
|
|
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-