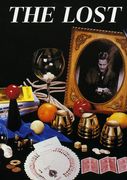『璣訓蒙鑑草(からくりきんもうかがみぐさ)』 Karakuri-Kinmo-Kagamigusa
半紙本二冊。
江戸初期の〈からくり〉解説書。1730年(享保15)刊。多賀谷環中仙撰。川枝豊信画。〈拾珍(しゆうちん)/御伽(おとぎ)〉と角書(つのがき)がある。2巻3冊。
上巻で当時の代表的な〈からくり〉28種の図を掲げ,下巻でそれぞれにつき図解・種明しをした書。〈からくり〉の装置は滑車やてこを利用した糸からくりが9種を占め,ポンプ,ばね,歯車,水銀を用いたものが各1種,その他は奇術,手品に類するものである。
「いろは人形」「太鼓」「道成寺」「小かぢ」「天鼓」「蟻通玉」「百挺からうす」「人形を人にかくさせ人形が占ふ」「三本の扇の内人の取りたるを占ふ」の諸からくりは、ともに糸からくりであり、糸の所在を分からないようにし不思議にしてある。
「人形吹矢をふく」「人形はなれて向ふへ行又はたらく」「人形犬に乗る」「人形文字を書く」「三段がへりかるわざ人形」の諸からくりは、機械人形。
「天神記僧正の車」「唐人の笛吹き」「人形三味線をひく」「などのからくり人形は、人間(子供等)が隠れて入り機械人形を装うもの。
この他、ろくろを使用した「首ひき人形」「や一日に四十里余走る人力の自動車「陸船車」などが珍しい。
また水からくりでは五色の水をあつかう「錦竜水」や、ひっきりなしに水の落ちる「異竜竹」「水の中へ人形つかひながらはいる」「茶釜の水茶となる」などからくりとして優れている。
「玉子ひよことなり」「ひよこ籠へ入り鶏となる」仕掛け物、竹田の独楽の他、大魔術的なものとして奈落を利用する「五寸の箱の中へ人形を使いながら入る」「鳩、鉢の子に入り仏となる」などのからくりがある。
昭和4年の稀書複製会本は、後の含霊軒発行の松竹梅(三冊)を復刻したもの。
『奇術研究第5号』(1957 力書房)p41「奇術文献を語る・和書の部」山本慶一
『ザ・マジック 8号』(1991 東京堂出版)p44「日本の奇術文献4」山本慶一
『ワンツースリー 22号』(1999 日本奇術協会)p2「見世物絡繰の手品考」平岩白風
『ワンツースリー 46号』(2005 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十五」平岩白風
半紙本二冊。
江戸初期の〈からくり〉解説書。1730年(享保15)刊。多賀谷環中仙撰。川枝豊信画。〈拾珍(しゆうちん)/御伽(おとぎ)〉と角書(つのがき)がある。2巻3冊。
上巻で当時の代表的な〈からくり〉28種の図を掲げ,下巻でそれぞれにつき図解・種明しをした書。〈からくり〉の装置は滑車やてこを利用した糸からくりが9種を占め,ポンプ,ばね,歯車,水銀を用いたものが各1種,その他は奇術,手品に類するものである。
「いろは人形」「太鼓」「道成寺」「小かぢ」「天鼓」「蟻通玉」「百挺からうす」「人形を人にかくさせ人形が占ふ」「三本の扇の内人の取りたるを占ふ」の諸からくりは、ともに糸からくりであり、糸の所在を分からないようにし不思議にしてある。
「人形吹矢をふく」「人形はなれて向ふへ行又はたらく」「人形犬に乗る」「人形文字を書く」「三段がへりかるわざ人形」の諸からくりは、機械人形。
「天神記僧正の車」「唐人の笛吹き」「人形三味線をひく」「などのからくり人形は、人間(子供等)が隠れて入り機械人形を装うもの。
この他、ろくろを使用した「首ひき人形」「や一日に四十里余走る人力の自動車「陸船車」などが珍しい。
また水からくりでは五色の水をあつかう「錦竜水」や、ひっきりなしに水の落ちる「異竜竹」「水の中へ人形つかひながらはいる」「茶釜の水茶となる」などからくりとして優れている。
「玉子ひよことなり」「ひよこ籠へ入り鶏となる」仕掛け物、竹田の独楽の他、大魔術的なものとして奈落を利用する「五寸の箱の中へ人形を使いながら入る」「鳩、鉢の子に入り仏となる」などのからくりがある。
昭和4年の稀書複製会本は、後の含霊軒発行の松竹梅(三冊)を復刻したもの。
『奇術研究第5号』(1957 力書房)p41「奇術文献を語る・和書の部」山本慶一
『ザ・マジック 8号』(1991 東京堂出版)p44「日本の奇術文献4」山本慶一
『ワンツースリー 22号』(1999 日本奇術協会)p2「見世物絡繰の手品考」平岩白風
『ワンツースリー 46号』(2005 日本奇術協会)p2「『伝授本』の手品考・其の十五」平岩白風
|
|
|
|
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-