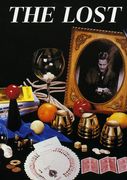[クラシックマジック研究] トピック
2006年02月01日
17:55
?4A-2 『出現系』
??kushio
関連トピック
『4A』
http://
『4枚のAを使うカードマジック』と一言で言っても、実に、本当に、たくさんの作品があります。表現される現象も、移動(消失や交換)、出現、変化、etc....
そこで、上記トピックでは、そこで既に話題に上がっている通り『移動系』を任せることにして、ここでは『出現系』の現象を表現するものを扱えれば、上記『4A』トピック内で話題がごちゃごちゃになるよりも良いのではないか、と思い、思い切って新トピックを立てさせて頂きました。
『私のエースオープナー自慢』から『技法お悩み相談』、はたまた『DVD捜索願い』から『4Aカッティングの歴史』まで、4A出現に関する話題なら、初心者から大師匠まで率直にマメ知識やアイデアを交換しましょう。宜しくお願いします。
書き込み
全てを表示??[ 1 2 ]??最新の10件を表示
2006年02月01日
18:13
? ??1:?kushio
mixiでは初めてトピックを立てさせて頂いたので、緊張しています(^^;
立てた張本人ですから、1つ書き込んでみます。
いろいろな4A出現がありますが、お客さんに思い切りシャッフルしてもらった後に行うものとして、"Prefiguration"(by L. Jennings - T. Ogden、カードマジック入門事典p.236)を利用できないか、と考えています。
※最近DVD版が発売された『Stars of Magic』シリーズではF. Garcia師のところで"Quadruple Coincidence"として演技/解説されてました
ところが出したいものをエースと決めてしまうと、例の『探しながらセットアップ』の部分がもたついてしまいます。これは単に私の練習不足が原因、というのも大いにあると思いますが、パターやハンドリングに何かアイデアは無いでしょうか。
いきなり何か変な話題で申し訳ありませんが、『正統派』でなくてもどんどん話題にして欲しいな、という思いを込めて書き込んでみました。
2006年02月02日
08:04
? ??2:?BJ
トム・オグデンやジョン・マレーなど、何人かの人が、ジェニングスのPrefigurationのバリエーションを発表していますね。
Jhon MarryのSpectacular Prediction Coincidenceは、かなり面白いです。Close-Up Magic Of Frank Garciaの中で、やはり Garciaによって解説されていますから、読んでみて下さい。参考になると思います。
2006年02月02日
13:03
? ??3:?BJ
すみません。出勤前のあたふたしている時に、このトピを見てしまったので、トピずれをしてるようです。
なので、昼食時を利用して改めて書き込みます。
しかし、Prefigurationの改案から考察したいので、やはりPrefigurationに触れます。読んでいる方も、そのマジックを知らない場合があるので、その方が親切でしょう。
Prefigurationは、原案がL. Jennings ですが、日本では、T.Ogdenのバリエーションの方がkushioさんの書き込みにある高木本で紹介されています。
これは、入門書なので、技術がやさしいという意味で採用したのだと思いますが、何度かにわたって、カードをテーブルに置いて行くことが、実際、初心者がやるとなると、技術は楽でも不自然さが目立ちます。これが目立たなくなるほどに練習するのなら、原案の方を練習された方が、出来上がった時には、自然さがこちらの方が良いと思います。
少なくとも、僕は推薦します。
原案は、The Classic Magic of Larry Jenningsに載っています。
そこで、このPrefigurationが、さらに上記の僕の書き込みのようにJhon Marry達によって改案されて行くのですが、kushioさんの希望する、他のカード。ここではエースですが、それを取り出すための改案に行きつきます。
Mike CloseのFour-Tune Hunter がそれです。これなら、Prefiguration で言う4〜8までのカードには、限定はされなくなります。出典は、Mikeの著書のPowerful Magic です。
kushioさんへの答えは、この本を読んでいただければ解決です。
しかし、原書ですから、日本語しか駄目な方がいるでしょう。
そういう方のために、朗報を書きます(^O^)
このMike CloseのFour-Tune Hunter のさらなる改案を、荒木一郎氏が東京堂出版「カード奇術あ・ら・カルト」の中に発表されています。
別のトピでも書きましたが、日本では、荒木氏の書かれる改案というのは、実に手順が良くまとまっていて、氏の書かれる本は、どれもカードマニア必携の本と言えるでしょう。
もし、kushioさんがお持ちでないのなら、この際、手に入れて下さい。技法は難しいものを沢山使いますが、書かれている作品は、手順、プロット共に文句無く素晴らしいものばかりです。
この中の「幸せの狩人」がそうです。このマジックは、荒木本にはSpectacular Prediction Coincidenceの改案としか書かれていませんが、もとを正せば Jenningsの作ったPrefiguration の改案の改案の改案なのです。
これで、kushioさんの課題は、さらに解決します(^O^)
2006年02月02日
17:29
? ??4:?RYUSEI
参考のため、ジョンマレー氏による作品は、マジックハウスにて刊行されているフランクガルシアのレクチャーノートに記載されています。
また、こうした作品の共通する事は最初のセッティングでしょう。4Aを不思議に見せる為には観客がデックを改める、もしくはシャッフルするのが前提にある事と思います。観客の目の前で堂々とセッティングしてしまうプレフィグレーションが名作たるゆえんでしょう。
しかし、エースを用いて同じ現象を行うとなれば、タイトルは失念しましたが、同じくジェニングスの作品で『クラシック〜』の続編の『ネオクラシック』に収録されています。彼自身はエースではなくキングを用いています。あらかじめ4Kをパームしておき、リプレイスメントする方法です。
荒木氏の作品に関してはまた本を探して見ます。
2006年02月02日
19:51
? ??5:?BJ
このPrefigurationのコメントとして、原作者の Jenningsが、こんな事を言っています。
「知らない民家に招待されたときに演じる、これはパーフェクトなマジックだ。家の人が、君がマジシャンだと気がついたとき、きっと、その家にある汚いカード(古くなったカード)を君の手に乗せて、何かのミラクルを期待するだろう。
そんなとき、相手に十分にデックをシャッフルさせて、このマジックを演じてみよう、そうすれば、ラストに4枚のメイツがテーブルの上に乗る事になるだろう。君は、もう何も説明する必要がなくなる」
というような事です。
2006年02月03日
00:09
? ??6:?JunK
>BJさん
>荒木一郎氏が東京堂出版「カード奇術あ・ら・カルト」の中
>この中の「幸せの狩人」がそうです。
シンプルな中に、Triumph現象まで入っている、テンポの良いマジックだと思います。
"Prefiguration"では、Four of Kindは、Aceではなく4か
か5か6あたりで無いと演じにくいと思います。
しかし"幸せの狩人"は、観客が指定したいずれのカードでも演じられます。もちろんAceも。
使う技法は、スプレッドカル、ハーフパス、リフルシャフル、スリーカードキャッチ、程度です。
同じ本の"ギャンブラーの伝説"も4A出現です。ポーカーデモンストレーションのようなプロットです。サッカートリックで締めくくります。
でもやはり"幸せの狩人" の方がシンプルでパンチが効いてるな。
2006年02月03日
16:03
? ??7:?kushio
変な話題?を振ったにも関わらず、みなさまコメントありがとうございます。
「カード奇術あ・ら・カルト」は、『上級向け作品集』ということで、私に実演可能かどうかというよりも『上級向けってことはゴテゴテしてるんだろうな』という勝手な先入観で敬遠しておりました。不明を恥じるばかりです。
さて原案のPrefigurationについてもう少し突っ込んでみたいのですが、やはり4〜7あたりがターゲットにしやすいのは明らかです。しかし都合の良くない場合も当然発生します。すると、組み上げる作業におけるハンドリングが1つ増えます(カットするだけですが)。これはエースを出そう!とする場合と同じです。
※ちなみに呈示するときは『A・C・E』とスペリングして3枚出します
そうすると、「せっかくシャッフルしたのに、結局自分で組み直してるやんか」という(客の脳内であれ発言であれ)ツッコミが来る危険が高まります。そうでなくても、元々異なるハンドリング(リバースカウントのような『カット』と本当のカット)が入っているのが急所ですし。
実際にPrefigurationをレパートリーにされている方々は、そのあたりをパターだけで対処しているんでしょうか?何かこう、テンポや視線の使い方などに『コツ』みたいなのがあるんでしょうか?
>BJさま
原書ですが、やはり系統的な研究には必要なんでしょうねぇ‥‥。私の場合、個人的なことですが、本業で英語文献を読まざるを得ない(駆け出しの科学者です)ので、趣味のことまで英語に漬かりたくないというのがあって、手を出す気になかなかなれません(DVDなどで聞くのはさほど苦ではないのですが‥‥)。頂く情報は貴重です。
できればBJさんのような方に和訳本を執筆して頂きたいものです(^^;
2006年02月03日
16:11
? ??8:?kushio
連続投稿失礼します。書き忘れました。
>BJさま
私が目にしているのはOgden版のようですが、Jennings版のほうがハンドリングがより自然であるとのこと。
ここはmixiで外の掲示板などと違いますから、もう少し突っ込んだところを紹介して頂けると嬉しいのですが、無理でしょうか?
2006年02月03日
17:02
? ??9:?BJ
Jennings バージョンでは、相手にシャッフルさせたあと、その状態のままデックを表向きにして、予言のカードを取り出す時、トップカードをグリンプスします。
同時に、フェイスから、グリンプスしたカードより1つ下の数の枚数を数え、7をグリンプスしたなら、6を数えるのです。
1枚1枚、リバースするのではなく、スプレッドしながら秘かに数えます。
その6枚目の下に小指(中指でもいいです)を挟んでおき、さらにデックを両手の間にスプレッドして行きます。
7のカードを見つけたら、それを手前側からずらして、手前側でカルをすると思って下さい。
その7を右手小指で作ったブレークの間に入れてしまいます。
何気なくやるんですよ。
つづけてスプレッドして行き、7が出たら、今度はアップジョグします。
もう一枚の7も、アップジョグし、どちらを予言にするか、ちょっと考える振りをします。そして、トップから7枚のカードを秘かに左手でくって行き、左手をデックからその7枚と一緒に外し、左側にある7を取り上げて、左手パケットのフェイスに揃え、そのまま、次の7を取り上げ、これにした!という感じでテーブルに置きます。
左手のパケットは、すぐに右手のデックと揃えて持ちます。
これで、トップに7,上から8枚目に7、ボトムから7枚目に7があり、テーブルに7が置かれました。
ちょっと時間がなくなってしまったので、この続きは、次回に書き込みます。
連続ものになって済みません。
2006年02月03日
17:17
? ?10:?CULL
Jenningsの原案では、まずトップをGlimpsして、それと同じ数字のカード3枚を使うので、うまくいけば、最初のカットは不必要です。
そのあとのSet Upは“予言カード”を探すためにデックを広げているという動作のうちに行われ、Vernon Wedgeが使用されるので、テーブルを使ってカットする、という作業も排除されています。
それとは別に、カードマジック事典のP.213に載っている“ひょっこり現れる3 Pop-over Treys”という作品も、もっとシンプルで同じような効果があると思います。
それと、この作品の場合、最初に3枚の同数のカードをパームしておき、客のシャッフル後にアッドすれば、セット完了ですので、自分のデックを使用する、あるいは少し前に3枚をパームしポケットに隠しておくなどすれば、Prefigurationより強いインパクトが得られるかも知れません。
2006年02月03日
17:22
? ?11:?CULL
失礼、仕事をしながら書き込んでたら、BJさんが詳細な説明を先に書き込まれ、前後しました。
2006年02月04日
00:58
? ?12:?BJ
書き込まないで欲しいというメッセージがありましたので、ここで終了します。
すみません。
ただ、付け足しとして、最初の6枚を数えているときに、7が含まれた場合ですが、これは単にカルして7枚目に持って行くのが良いと思います。
後は、デックを表向きにして、大体、半ばくらいのところを客にフォースするようにし、ここから半分ずつにデックを分け、トップカードをフォースした形にし、これを裏向きにテーブルに置きます。
後は、なんとなく分かると思います。
2006年02月04日
06:58
? ?13:?RYUSEI
BJさんへ
せっかくお話が盛り上がっているところなのに、書き込まないで欲しい、というメッセージはどなたからあったのでしょうか、教えて頂けないでしょうか?
2006年02月04日
15:26
? ?14:?kushio
>BJさま(Cc:RYUSEIさま)
直メッセージってことですよね?‥‥まぁ、そんなこともあると思います。またの機会に御知恵を拝借させて下さい。
Jennings版Prefigurationについて詳細な御説明、望外でした。ありがとうございます。検討・修錬して試演し、観客からのリアクションなどを手掛かりに、その手順の違いによる効果の違いなど考えてみたいと思います。
>CULLさま
Pop-over Treysですか。あれも面白い原理、というかアイデアですね。ただ、パーム及びアディションを使うとなると、せっかくの『仕事の少なさ』が犠牲になるような気もします‥‥手順に入ってしまえば確かにクリーンで面白いのですが‥‥。
ちなみに実際にCULLさんはレパートリーとして演じておられますか?(私は以前に検討しただけで実演したことはありません)。もしそうでしたら、気をつけているポイント、コツや工夫などはありますでしょうか。良い作品ですし、このトピックをお読みになった方々の中に、今後この作品を『お気に入り』にする人が居られるかもしれませんし、参考にさせて頂きたいのですが、どうでしょう?
2006年02月04日
18:48
? ?15:?BJ
>RYUSEIさん
誤解があるといけないので、もう一度、書き込んでおきます。
僕に対してのメッセージは、決して悪意のあるものではなく、手短に言うと、「結論が出ていないのに書き込みをつづけて行くことは混乱をまねく」という意味のメッセージです。
好意も十分に感じられる話なので、自主的に書き込みをストップした次第です。
やめろ!と命令されたり、理不尽なメッセージをもらったわけではありません。
自分は、自分に対しての好意と取っているので、書き手の公表をする必要はないでしょう。
2006年02月04日
19:25
? ?16:?CULL
kushioさん、毎度!
実はPop-over Treysをレパートリーにはしていません。
というのは、同じような現象で、もっと他にやりたい奇術がたくさんあるので、入れる余地がないのです。
で、この奇術をなぜ推すかというと、主に講習用に使って、好評だからです。
パームのくだりを省いても十分通用する奇術ですし、パームを使えばよりインパクトの強いものとなるので、練習に発展性があるところも、習った人の満足度が高いようです。
実際、カードマジック事典の記載があまりにも淡白なので、この本を持っていても、ほとんど見過ごされていることも、ある意味面白いところではあります。
教えた後で「事典に載ってるよ」というと大抵「えぇーー! もう一回読み直そ。」という返事が返ってきます(笑)
2006年02月04日
19:50
? ?17:?RYUSEI
BJさんへ
了解いたしました。ご返答ありがとうございます。
プリフィグレイションに関して自分は無理にエースを使う必要がないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
エース(または絵札)のような特別なカードは、逆に観客にその特別感を植え付ける事になるような気がします。
通常の4エースは、連続して、あるいは即座にエースを出現させます。
演者、もしくは観客が意図的に出現させる現象がほとんどではないでしょうか。
このプリフィグレイションの場合は最初の予言が当たる、という時点で観客が演技が終わったと考え、終わったと思いきや3枚目が現れ、もしやと観客が思った時にたまたま4枚そろってしまう、という畳み掛けるような現象を表現したかったのではないでしょうか。
通常のスポットカード(字札)の方がリアリティがあるように思えるのですが…。
2006年02月04日
20:33
? ?18:?kushio
CULLさま:
(技術的に)簡単な作品でも、演じる際には難しい作品と同じレベルの心配りが必要だと思っています。講習のときには、どこが(演じる際の)ポイントだ、と言っていますか?
>教えた後で「事典に載ってるよ」というと大抵「えぇーー! もう一回読み直そ。」という返事が返ってきます(笑)
あの事典ですから、さもありなん、というかんじですね(笑)
ちなみに、CULLさん御用達の4A出現は何ですか?昔は○○に凝っていたけれど最近は△△がお気に入りだ、とか‥‥
RYUSEIさま:
>プリフィグレイションに関して自分は無理にエースを使う必要がないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
あ、いや、その通りなんですけども、4Aに関連した話題、としてごにょごにょ‥‥(笑)
私がプレフィグレーションを演じるときは、今のところは確かに仰る通り普通のスポットカードを出し、『ツイスティング4』などにつなげています。しかし、Aのほうが映える作品もありますよね?それらにつなげるために、プレフィグレーションのもつ『フェアーさ』を持ちこめないか、という発想での、話題提案でした。
ですが、RYUSEIさんの仰る『畳み掛けるような』というのは考えていませんでした。そう言われると、確かにそれがプレフィグレーションの『良さ』のような気がしてきました。
2006年02月04日
21:48
? ?19:?CULL
Pop-over Treysに関しては、やはり『客が切ったデックでいきなり行われたようにみえること』が重要だと思います。
ですから、パームを使わない場合はやはり、セットに気付かれない事は重要だと思いますので、次のような方法を薦めています。
まずデックをよく切ってもらいます。
その後デックをざっと見て、2,3枚同じ数字のカードがくっ付いているものを探します。そして、それがトップに来るようにカットし、残りのカードを何気なくトップに移し、最終的に同じ数のカードがトップになるようにします。
以上の作業は、例えばSandwich Effectに使うための2枚のJackを探す作業にまぎれて行います。そしてPop-over Treysの前にSadwich Effectを行うのです。
所謂、Time Misdirectionです。
僕がやっている『4枚のA(あるいは同数のカード)が出てくる現象』は色々ありますが、よく使うのは以下のようなものです。
Earl Nelson's Sleeve Aces
Jonahtan Neal Brown's Benihana Aces
松田道弘のマニアのためのカードマジックp.60に収載されている『エース・オープナーの効果』
David Solomon's Cutting Ten (Solomon's Mind p.27)
以上の4つは長年のお気に入りです。とても良い奇術です。
ただし、下の2作品はどちらかというと『Spectator Cutting Aces』です。
2006年02月04日
22:18
? ?20:?RYUSEI
自分は「ひょっこり現れる3(Pop-over Treys)」を初めて見たのは高木先生の小学館「マジック入門」です。
心理学的巧妙さを兼ね備えたまさに初心者に向いている傑作だと自分も思います。
ただ技術的な面白さにかける為、初心者から中級者へと移行するに従ってレパートリーから外れていくような気がします。
その演出上、3を使う必要性があり、その他のスポットカード(もしくはエース)だと論理性がかけると思われるのですが、どういった形でフォローしているのでしょうか。
プレフィグレーション的にエースで行う作品としてはやはりジェニングスですが、事典216ページにある「差し込んだカードと一致するカード(Stabbed Coincidence)」が近いのではないでしょうか。
自分はキングの出現として用い、ビジターなどにつなげていました。
2006年02月05日
00:44
? ?21:?BJ
言わずにはいられなくなったので、書き込みます。
色々な検討がなされていて、面白いのですが、ただただ何かを羅列している感は、否めません。
僕の考えですが、たとえば、Prefiguration というテーマが出たとしたら、それをもう少し掘り下げるように考えるのはどうでしょうか。
もともと、kushioさんのPrefigurationへのこだわりから出た事ですから、このマジックについて色々検討してみると、もっと深いところからマジックを考察でき、実際に演じるときの大きなプラスになると思います。
あのマジックがいい、自分はこのマジックでやっているといくら書かれても、そのマジックをどうとらえ、どう演じるかは、人によって違います。
同じマジックを演じても、まるで面白くなくなってしまう場合もあります。
ひつとのマジックを、もっと掘り下げて話してみたら、出来ない人の参考にも、もっとなるんじゃないでしょうか。
たとえば、CULLさんの書き込みでは、Prefiguration には Vernon Wedgeが使用されるので、と簡単に書き、それで終わっています。
正確に言えば、使用されているのは、Vernon Wedge ではなく、Vernon の Wedge Break を使った、Larry の Wedge Cul です。
では、Wedge Cull とはどんなテクニックなのか。そして、一体、どれだけの人が Wedge Cull についての知識があるのでしょう。
それにもっと大事なことは、このテクニックを実際に使うのは、かなりのカードマニアでも難しいということです。
それをどうやって演じているのかが、大事なポイントです。これが下手だったり、使い物にならない方法だったりしたら、Prefiguration はマジックとして成り立たなくなってしまうでしょう。
僕ならこうやるという意見があると思います。実際に自分は、やさしく出来る方法を考えたことがあり、それを使っています。他の方の考えた、より素晴らしい方法もあるでしょう。
また、たたみかける、とRYUSEIさんが、表現していましたが、それは RYUSEI さん流であって、他の考え方もあります。
ひとつのマジックに対して、それが議題に出されたら、そういう細かいところをしっかりと勉強して行くことが、マジック全体が向上する術だと、僕は考えます。
いかがでしょうか。
2006年02月05日
01:32
? ?22:?CULL
確かに・・・(笑)
もともとの御題が『出現系A』ということだったので、話題の焦点がボケる事も承知でしたが、色々な人が読んで楽しいかな、という思いで関連奇術にも触れました。(実際、Kushioさん自身、それにも興味を持たれたようですし。)
Prefiguration については、BJさんが言われる通り、ちょっと特殊なMultiple Controlが行われるのですが、これは手元に文献を持たない多くの人に、絵なしではちょっと説明しづらい面もありますよねぇ。
そして(これはあくまでも僕の個人的な意見ではありますが)このJennigsによるアプローチは、一般客に与える現象のインパクトと比較すると「少々しんどすぎる」という印象があるのです。
要するに『全く何もしなかったような印象を与えることが、一般奇術家には困難』と思われるわけです。実際、予めセットしておく方法以外に、良いアイディアも持っていませんし。
というわけで、そう考えると『もっと実用的で、同じような印象を与える奇術に触れておく』ということも、情報提供として意味があるかな、と感じて書き込みました。
ただ、BJさんの指摘されるような意味では、書き込むタイミングが早すぎた感も否めません。
2006年02月05日
05:51
? ?23:?RYUSEI
原案のプレフィグレイションに関しては、ジェニングスが表現したい演出は下記のような事ではないでしょうか。
観客に自由にシャッフルさせたあと…。
1、予言のカードを術者が一枚選んで、テーブルに置く。
2、デックから一枚ずつテーブルに配ってゆき、好きなところでストップと言わせ、偶然選ばれたカードの数字を使うことにする。
3、その数字の枚数をテーブルにある二つのパケットをお互いに持ち、一緒に配る。
4、その枚数目のカードをお互いにオープンにすると数字が一致している、しかも配った数字とも一致している。
5、そして予言の数字とも一致している。
つまり、原案においては、畳み掛けるというよりは、現象が起きた時には既に必然的に3枚のカードがオープンになっている、という事です。
そして予言のカードを最後ドラマチックにオープンにすれば、4枚のカードがそろう、というものではないでしょうか。
それに対してオグデン版では、一枚ずつオープンにしていく事に味わいがあるような気がします。
どちらが良い、というのではなく演じる人の好みかも知れません。
またセッティング方法に関しても
原案が意図している事はデックをテーブルに置きたくなかったのではないでしょうか。
入門という意味ではオグデン版の方がセットしやすいのですが、テーブルに置く、という動作の為にどうしてもセット臭さが出てしまう危険性あります。
かといって原案では、最初のブレイク(バーノンブレイク?)の部分が難しく、されに自分に向けてのカルの動作に違和感を持つ人もいるでしょう。
いずれにせよ、自然に行えば問題はないのでしょうが…。
ただこれもやはり好みの問題だと思います。
2006年02月05日
06:04
? ?24:?BJ
Jennings の演出で大事なことがあります。
龍生さんのプロットでは、単なるCoincidence になりますね。しかし、Jennings は、influence という言葉を使ってこのマジックを演じています。それは、ミスディレクションにもつながっていて、かなり大事な要素になっているんです。
つまり、龍生さんの考えと少し異なる演出となり、Jennings をしっかりと習うことは、単にマジックを覚えることではなく、マジックを上達するのに非常に参考になる個所があるんです。
手順によってのみ、マジックを覚えたと言ってはいけない、と言うことです。
2006年02月05日
08:13
? ?25:?BJ
欲求不満になる文章なので付け足します。
言いたい事は、マジックを面白くする要素は手順も大事ですが、それだけではマジックにならないということです。
一番は、演出、あるいは作品の心でしょう。どう演じるかです。これはテクニックも大いに含まれます。
CULLさんが言われる、「Jennigsによるアプローチは、一般客に与える現象のインパクトと比較すると「少々しんどすぎる」という印象がある」は、個人的な意見であってマジックの価値を意味するものではありません。もちろん、ご本人もそうおっしゃっていますが。
米国に、VernonのTwisting Aces を好きじゃないと言う僕の友人がいます。Ace の変化が分かりにくく、客受けがしないという理由です。
しかし、僕は Twisting Aces が大好きです。客はかならず喜び、驚きます。やはり、天才の作った作品です。しっかりと、その価値を把握すれば、Twisting Aces は誰がやっても素晴らしいマジックになります。そうではない、と言う時は、やり方が悪いだけです。
すみません、CULLさん、気を悪くしないで下さい。
僕自身は、いつもそう思っていますから、自分は、天才の作品に対して、あれは好きじゃないとは言えないんです。自分が、その価値を把握出来ていないと考えるからです。
そして、Twisting Aces は、幾多のバリエーションが作られましたが、どんなに素晴らしいバリエーションが作られようと、原案の価値は、まったく下がることはありません。
つまり、マジックを作る人は天才です。バリエーションを作る人は、天才ではなく、秀才と僕は考えます。
以前にも、他のコミュに書き込みましたが、天才に触れることが大事なことなんです。そして、自分を謙虚にし、天才が何をしようとしてるのかを把握しようとしながら、マジックを覚える。
それが僕のやり方です。
押し付けはしませんが、それが良いマジックを演じられるようになる秘訣です。
Prefigurationを僕が演じると、人は驚き楽しみます。Jennings の考えた心を演じようとするからだと思います。
テクニックと、表現される作品のバランスは、決して、悪くありません。手順も完璧に考えられています。
たとえば、前回に手順を書きましたが、あの後、Jennings は、カードを表向きにします。このとき、フェイスにあるカードを見て、このカードを相手に意識させて、influence の話をします。
influence の日本語訳ですが、こういのが一番難しいです。影響、誘導、感応、伝染もありますね、色々と辞書に意味が出ていますが、どれも少しずつニュアンスが違います。それをみんな一緒にしたもの、と言った方がいいか。
これがマジックを面白くするだけではなく、ミスディレクションになります。
つまり、フェイスのカードを見て、次に同じカードが来るまで、influence の話をしながらテーブルにカードを一枚ずつ置いて行くのです。
これは、次のカードと何か関係があるように客に思わせながら、実は、デックの半分くらいのところで客にストップをさせるための手段(フォース)になっています。
何も言わずにカードを置きながら相手にストップをかけさせるより、色々な点でマジックに膨らみが出ます。
同じカードが出たところで、続けてカードを置いて行きますからと言い、客が influence を感じたところでストップをかけて貰います。これでデックの半分くらいのところで客がストップをかけることになります。
客はこのinfluenceの話によって、二つのミスディレクションを受け入れています。
つまり、1つ目は、先に述べましたが、二つ目は、客がストップをかけたときに、テーブルに置いたカードを示し、ここで貴方は、influence を感じたわけですね、と強調します。
これは、マジシャンが誘導したのではなく、あなたの気持ちでストップしたところです。
このとき、左手に持った残りのデックを裏向きにして、では、貴方のストップをかけたところ、こちらは表向きになっているので、次のカードをテーブルに置きます。
と、左手のトップカードをテーブルに置きます。
客は、influence の話をされているため、それがトップにあったカードだという事から、気を引き離されてしまっています。
これでフォースは完全です。
というような具合です。
ちょっとまとまりませんでしたか。でも、言わんとしてる事は分かっていただけると思いますが。
2006年02月05日
08:23
? ?26:?BJ
付けたし。
>RYUSEIさん
>>最初のブレイク(バーノンブレイク?)
Vernon Break ではなく、
>Vernon の Wedge Break を使った、Larry の Wedge Cullです。
と、自分の書き込みに書きました。
ですから、Wedge Breakです。しっかり読んで下さい。
2006年02月05日
08:50
? ?27:?RYUSEI
なるほど。
ウェッジブレイクですね。
話が飛びますが、実際にウェッジカルをやっているのを故片倉氏から見せてもらった事があります。しかし他の人でそれを行っている人を見た事がありません。
一枚ならいざ知らず、4枚、それを行うコツのようなものはありますか?
演出面においてもインフルーエンスの話までは考えた事がありませんでした。オグデン版のプレフィグレイションの場合、どうしても同じ数字のカードが二枚並ぶところにやましさを感じてしまう事もあり、早めに過ぎ去ろうとしていました。
確かに、最初に術者が「う〜ん」と悩みながら、やっと何かを感じて一枚を選び出すわけですから、演出上、観客にも何かを感じたら止めてもらう方が論理的ですね。
さてインフルーエンスを訳すのが難しいとの事ですが、根本的な疑問としてプレフィグレイションをなんと訳すのが一番ピンと来るのでしょう?
2006年02月05日
15:09
? ?28:?RYUSEI
ちなみにジョン・マレー氏の『Spectaculer Prediction Coincidence』は、その名前からもコインシデンスです。
ガルシアのレクチャーノートを見れば、ジョンマレーの名前はあるのですが、ジェニングス、オグデンの名前は見当たりません。が、全く同等のものだと思います。
セットのやり方そのものはオグデン式と全く同じです。それ以外は微妙に違います。しかし、ほとんど同じものに見えます。
あえて違いを言うのならば、カードをオープンしていくディスプレイが違います。
ちなみにこの小冊子の中で、キングの場合は「K、I、N、G」とスペルで行いましょう、と解決方法が述べてあります。
2006年02月05日
16:56
? ?29:?Tango
BJさん、あなたの分析はあまりに鋭い!
是非演技を拝見したいところです。
ちょっと話題が逸れてしまうかもしれませんが、言葉についての考察を・・
単なるTrickを本物のMagicに変えるのは、確固たる主題に基づく一貫して適切な演出だろうと思います。
ここでの要点はPrefigurationと言うことでしょう。
これは、かなり古めかしい感じの単語で、予言とか予示とか約されてると思います(pre=前もって+figure=形を思い浮かべる)
その文脈でinfluence(なにかのエネルギーが、流れ[flow]入る[in]イメージ)という言葉を用いた場合、一種の超自然的な影響力と言ったニュアンスがもたらされるのだろうと思います。
一昔前の欧米人なら、Mesmerism(催眠術‐と言うより催眠実験と呼ぶべきか)をイメージする可能性もありそうです。
(どこかでPower of Influenceを暗示の力と約しているのをみた記憶がありますが、この辺りの意を汲んだものなのでしょう)
かなり遠回りしてしまいましたが、Prefigurationと名付け、influenceという単語を用いた=それにみあった演技をしなければMagicではなくTrickにすぎなくなると言うことなのかもしれません。
ああ、天才って凄い!(一人で勝手に感動してしまった・・・)
2006年02月05日
20:18
? ?30:?kushio
Prefigurationの話。
突然『はっ!もしや!?』と思い出して、おそらく国内では『入門者はコレを読め』と言われる確率が最も高いと思われる『ラリージェニングスのカードマジック入門』(加藤氏の本)を見ますと、載ってました(^^;
読んでたはずなのに‥‥
BJさんの『influence』のお話、すぐには(実感を伴った)理解には至りませんです‥‥上記の解説本、およびもちろん以前の書き込みを参考に、研究してみます。私自身はJenningsではないですから、実演してみるまでにはまだそれなりに紆余曲折あると思いますが、それにしてもPrefigurationだけでここまで話が掘り下げられることに快感を覚えつつあります。当たり前ですが、プロアマ問わずみんなマジック好きやねんなーと思います(笑)
‥‥トピ立てて良かった (^O^)
2006年02月05日
20:29
? ?31:?kushio
既に4Aとちゃう話題やんけ!という声はひとまず置いといて、Pop-over Treysの話。
CULLさま:
Time Misdirectionとしての『前フリ手順の中でのセット』‥‥言われてみれば当たり前ですが、そうか、やっぱり&なるほどな、というかんじです。上手く表現できないのですが。
私の感覚では、あの『リバースカウントの原理』(仮称)をダイレクトに使っていますので、タイミングとかパターというか、『流れ』をおろそかにすると、カンの良い人が相手の最悪の場合『そんなん当たり前やん』と思われかねないリスクがあるように思います。
ちなみに、私もいくつかの4A出現をやったりしますが、(事典のPop-over Treysの前頁にある)『AとKの出現』と、有名な『Ace Bonanza』が、結局いちばんウケが良かったりして、複雑な気分になったりします(^^;
2006年02月05日
20:38
? ?32:?kushio
連続投稿失礼します。分けたほうが良いかな、と思ったもので‥‥。
BJさま:
話題が並行してしまうのは、mixiトピックであっても、やはり或る種のBBSですから、やむないことでしょう。むしろ忘れた頃に堀り下がった昔の話題が出てきたりすることによって活気が出てくることもありますから、そのあたりは気楽に行きましょう。もちろんとことん行くのも、どちらさまもwelcomeでしょうし(^^
もし必要なら、『○○の話題は別トピック立てましょう』ということも、おそらく皆さんにも受け容れられやすいことでしょう。
ちなみに、最初に変化球で話題を振ったので、一段落したら、正統派っぽく(?)バーノン教授の『Cutting the Aces』の話題を振る予定だったのですが、私の思惑を良い意味で外れ、このように興がのってきたので「教授の作品だから、そのうち誰かが言うだろう」と思ってやめたのでした(笑)
2006年02月05日
22:58
? ?33:?BJ
>23-RYUSEIさん
念のために書き込んでおきます。
Prefiguration の手順ですが、1と2は、その通りですが、3と4は違っています。
客と共にカードを置いて行くのではなく、マジシャン自身がラストまで行います。
やはり、最後までマジシャンのinitiative によって演技を行う事で、すべてのタイミングがマジシャンのものとなり、マジシャンの作品になります。
相手を入れるのも、その人の好みにはなるでしょうが、原案の良さを追求するなら、マジシャンのinitiative によって進行させるべきと思います。
2006年02月06日
13:53
? ?34:?RYUSEI
私自身は原案をレパートリーからはずしていたのには理由があります。
1、ウェッジカルを用いる最初のセットアップの不安。
2、あまりにも大胆なフォースにおける不安。
でした。
そしてまさにその二点を改良したのが、オグデン式でありマレー式でしょう。
そしてまた、トム・オグデン氏のコメディタッチのキャラクターによって軽快に演じられている作品である、と考えています。
その反面、セットの方法に何らかの怪しさが残る結果となってしまっている部分があります。
つまり、その二点さえクリアされれば、現象としての完成度は原案に軍配が上がるのではないでしょうか。
BJさんへ
原案についての知識ありがとうございます。
さてオグデン式とマレー式ですが、明確な違いは何なのでしょう。
また、欧米においてはどちらの作品として認知されているのでしょう。
原著を持っていないのでわかりませんが、ガルシアはなぜジェニングスのことを述べなかったのでしょうか?
2006年02月06日
18:20
? ?35:?BJ
まず、RTUSEIさんの読まれた原案は、加藤英夫さんの「L.Jのカードマジック入門」だと思います。
あれは、原案とは異なります。
入門書のために加藤さんが改案しています。
ですから、前回に書いた influence を含む、 Jennings の心はいっさい入っていません。ラストの相手と一緒にカードを置いて行く、も加藤さんのアイディアです。
Wedge Cull すら使われていません。とにかく、やさしく出来るようにした事により、原案の雰囲気は消されてしまっています。
あれでは、最初の予言(ではないのですが、とりあえず)のカードをデックから探し出すところから、まるで違うものになっています。
実際には、原案だと2枚のカードのどちらかを考える状態にはなりますが、加藤さんの改案だと、四枚も、それを考えながらカードをくっている状態になり、不自然です。
2006年02月07日
04:09
? ?36:?RYUSEI
なるほど。
その通りです。加藤さんの本で学びました。
という事は、原案にあるウェッジカル(Wedge Cull)というのは、どう説明すればよいのでしょうか。
術者自身がイニシャチブをとるとありますが、2枚目、3枚目のカードをどのようにめくるのが本来のやり方なのでしょう。
2006年02月01日
17:55
?4A-2 『出現系』
??kushio
関連トピック
『4A』
http://
『4枚のAを使うカードマジック』と一言で言っても、実に、本当に、たくさんの作品があります。表現される現象も、移動(消失や交換)、出現、変化、etc....
そこで、上記トピックでは、そこで既に話題に上がっている通り『移動系』を任せることにして、ここでは『出現系』の現象を表現するものを扱えれば、上記『4A』トピック内で話題がごちゃごちゃになるよりも良いのではないか、と思い、思い切って新トピックを立てさせて頂きました。
『私のエースオープナー自慢』から『技法お悩み相談』、はたまた『DVD捜索願い』から『4Aカッティングの歴史』まで、4A出現に関する話題なら、初心者から大師匠まで率直にマメ知識やアイデアを交換しましょう。宜しくお願いします。
書き込み
全てを表示??[ 1 2 ]??最新の10件を表示
2006年02月01日
18:13
? ??1:?kushio
mixiでは初めてトピックを立てさせて頂いたので、緊張しています(^^;
立てた張本人ですから、1つ書き込んでみます。
いろいろな4A出現がありますが、お客さんに思い切りシャッフルしてもらった後に行うものとして、"Prefiguration"(by L. Jennings - T. Ogden、カードマジック入門事典p.236)を利用できないか、と考えています。
※最近DVD版が発売された『Stars of Magic』シリーズではF. Garcia師のところで"Quadruple Coincidence"として演技/解説されてました
ところが出したいものをエースと決めてしまうと、例の『探しながらセットアップ』の部分がもたついてしまいます。これは単に私の練習不足が原因、というのも大いにあると思いますが、パターやハンドリングに何かアイデアは無いでしょうか。
いきなり何か変な話題で申し訳ありませんが、『正統派』でなくてもどんどん話題にして欲しいな、という思いを込めて書き込んでみました。
2006年02月02日
08:04
? ??2:?BJ
トム・オグデンやジョン・マレーなど、何人かの人が、ジェニングスのPrefigurationのバリエーションを発表していますね。
Jhon MarryのSpectacular Prediction Coincidenceは、かなり面白いです。Close-Up Magic Of Frank Garciaの中で、やはり Garciaによって解説されていますから、読んでみて下さい。参考になると思います。
2006年02月02日
13:03
? ??3:?BJ
すみません。出勤前のあたふたしている時に、このトピを見てしまったので、トピずれをしてるようです。
なので、昼食時を利用して改めて書き込みます。
しかし、Prefigurationの改案から考察したいので、やはりPrefigurationに触れます。読んでいる方も、そのマジックを知らない場合があるので、その方が親切でしょう。
Prefigurationは、原案がL. Jennings ですが、日本では、T.Ogdenのバリエーションの方がkushioさんの書き込みにある高木本で紹介されています。
これは、入門書なので、技術がやさしいという意味で採用したのだと思いますが、何度かにわたって、カードをテーブルに置いて行くことが、実際、初心者がやるとなると、技術は楽でも不自然さが目立ちます。これが目立たなくなるほどに練習するのなら、原案の方を練習された方が、出来上がった時には、自然さがこちらの方が良いと思います。
少なくとも、僕は推薦します。
原案は、The Classic Magic of Larry Jenningsに載っています。
そこで、このPrefigurationが、さらに上記の僕の書き込みのようにJhon Marry達によって改案されて行くのですが、kushioさんの希望する、他のカード。ここではエースですが、それを取り出すための改案に行きつきます。
Mike CloseのFour-Tune Hunter がそれです。これなら、Prefiguration で言う4〜8までのカードには、限定はされなくなります。出典は、Mikeの著書のPowerful Magic です。
kushioさんへの答えは、この本を読んでいただければ解決です。
しかし、原書ですから、日本語しか駄目な方がいるでしょう。
そういう方のために、朗報を書きます(^O^)
このMike CloseのFour-Tune Hunter のさらなる改案を、荒木一郎氏が東京堂出版「カード奇術あ・ら・カルト」の中に発表されています。
別のトピでも書きましたが、日本では、荒木氏の書かれる改案というのは、実に手順が良くまとまっていて、氏の書かれる本は、どれもカードマニア必携の本と言えるでしょう。
もし、kushioさんがお持ちでないのなら、この際、手に入れて下さい。技法は難しいものを沢山使いますが、書かれている作品は、手順、プロット共に文句無く素晴らしいものばかりです。
この中の「幸せの狩人」がそうです。このマジックは、荒木本にはSpectacular Prediction Coincidenceの改案としか書かれていませんが、もとを正せば Jenningsの作ったPrefiguration の改案の改案の改案なのです。
これで、kushioさんの課題は、さらに解決します(^O^)
2006年02月02日
17:29
? ??4:?RYUSEI
参考のため、ジョンマレー氏による作品は、マジックハウスにて刊行されているフランクガルシアのレクチャーノートに記載されています。
また、こうした作品の共通する事は最初のセッティングでしょう。4Aを不思議に見せる為には観客がデックを改める、もしくはシャッフルするのが前提にある事と思います。観客の目の前で堂々とセッティングしてしまうプレフィグレーションが名作たるゆえんでしょう。
しかし、エースを用いて同じ現象を行うとなれば、タイトルは失念しましたが、同じくジェニングスの作品で『クラシック〜』の続編の『ネオクラシック』に収録されています。彼自身はエースではなくキングを用いています。あらかじめ4Kをパームしておき、リプレイスメントする方法です。
荒木氏の作品に関してはまた本を探して見ます。
2006年02月02日
19:51
? ??5:?BJ
このPrefigurationのコメントとして、原作者の Jenningsが、こんな事を言っています。
「知らない民家に招待されたときに演じる、これはパーフェクトなマジックだ。家の人が、君がマジシャンだと気がついたとき、きっと、その家にある汚いカード(古くなったカード)を君の手に乗せて、何かのミラクルを期待するだろう。
そんなとき、相手に十分にデックをシャッフルさせて、このマジックを演じてみよう、そうすれば、ラストに4枚のメイツがテーブルの上に乗る事になるだろう。君は、もう何も説明する必要がなくなる」
というような事です。
2006年02月03日
00:09
? ??6:?JunK
>BJさん
>荒木一郎氏が東京堂出版「カード奇術あ・ら・カルト」の中
>この中の「幸せの狩人」がそうです。
シンプルな中に、Triumph現象まで入っている、テンポの良いマジックだと思います。
"Prefiguration"では、Four of Kindは、Aceではなく4か
か5か6あたりで無いと演じにくいと思います。
しかし"幸せの狩人"は、観客が指定したいずれのカードでも演じられます。もちろんAceも。
使う技法は、スプレッドカル、ハーフパス、リフルシャフル、スリーカードキャッチ、程度です。
同じ本の"ギャンブラーの伝説"も4A出現です。ポーカーデモンストレーションのようなプロットです。サッカートリックで締めくくります。
でもやはり"幸せの狩人" の方がシンプルでパンチが効いてるな。
2006年02月03日
16:03
? ??7:?kushio
変な話題?を振ったにも関わらず、みなさまコメントありがとうございます。
「カード奇術あ・ら・カルト」は、『上級向け作品集』ということで、私に実演可能かどうかというよりも『上級向けってことはゴテゴテしてるんだろうな』という勝手な先入観で敬遠しておりました。不明を恥じるばかりです。
さて原案のPrefigurationについてもう少し突っ込んでみたいのですが、やはり4〜7あたりがターゲットにしやすいのは明らかです。しかし都合の良くない場合も当然発生します。すると、組み上げる作業におけるハンドリングが1つ増えます(カットするだけですが)。これはエースを出そう!とする場合と同じです。
※ちなみに呈示するときは『A・C・E』とスペリングして3枚出します
そうすると、「せっかくシャッフルしたのに、結局自分で組み直してるやんか」という(客の脳内であれ発言であれ)ツッコミが来る危険が高まります。そうでなくても、元々異なるハンドリング(リバースカウントのような『カット』と本当のカット)が入っているのが急所ですし。
実際にPrefigurationをレパートリーにされている方々は、そのあたりをパターだけで対処しているんでしょうか?何かこう、テンポや視線の使い方などに『コツ』みたいなのがあるんでしょうか?
>BJさま
原書ですが、やはり系統的な研究には必要なんでしょうねぇ‥‥。私の場合、個人的なことですが、本業で英語文献を読まざるを得ない(駆け出しの科学者です)ので、趣味のことまで英語に漬かりたくないというのがあって、手を出す気になかなかなれません(DVDなどで聞くのはさほど苦ではないのですが‥‥)。頂く情報は貴重です。
できればBJさんのような方に和訳本を執筆して頂きたいものです(^^;
2006年02月03日
16:11
? ??8:?kushio
連続投稿失礼します。書き忘れました。
>BJさま
私が目にしているのはOgden版のようですが、Jennings版のほうがハンドリングがより自然であるとのこと。
ここはmixiで外の掲示板などと違いますから、もう少し突っ込んだところを紹介して頂けると嬉しいのですが、無理でしょうか?
2006年02月03日
17:02
? ??9:?BJ
Jennings バージョンでは、相手にシャッフルさせたあと、その状態のままデックを表向きにして、予言のカードを取り出す時、トップカードをグリンプスします。
同時に、フェイスから、グリンプスしたカードより1つ下の数の枚数を数え、7をグリンプスしたなら、6を数えるのです。
1枚1枚、リバースするのではなく、スプレッドしながら秘かに数えます。
その6枚目の下に小指(中指でもいいです)を挟んでおき、さらにデックを両手の間にスプレッドして行きます。
7のカードを見つけたら、それを手前側からずらして、手前側でカルをすると思って下さい。
その7を右手小指で作ったブレークの間に入れてしまいます。
何気なくやるんですよ。
つづけてスプレッドして行き、7が出たら、今度はアップジョグします。
もう一枚の7も、アップジョグし、どちらを予言にするか、ちょっと考える振りをします。そして、トップから7枚のカードを秘かに左手でくって行き、左手をデックからその7枚と一緒に外し、左側にある7を取り上げて、左手パケットのフェイスに揃え、そのまま、次の7を取り上げ、これにした!という感じでテーブルに置きます。
左手のパケットは、すぐに右手のデックと揃えて持ちます。
これで、トップに7,上から8枚目に7、ボトムから7枚目に7があり、テーブルに7が置かれました。
ちょっと時間がなくなってしまったので、この続きは、次回に書き込みます。
連続ものになって済みません。
2006年02月03日
17:17
? ?10:?CULL
Jenningsの原案では、まずトップをGlimpsして、それと同じ数字のカード3枚を使うので、うまくいけば、最初のカットは不必要です。
そのあとのSet Upは“予言カード”を探すためにデックを広げているという動作のうちに行われ、Vernon Wedgeが使用されるので、テーブルを使ってカットする、という作業も排除されています。
それとは別に、カードマジック事典のP.213に載っている“ひょっこり現れる3 Pop-over Treys”という作品も、もっとシンプルで同じような効果があると思います。
それと、この作品の場合、最初に3枚の同数のカードをパームしておき、客のシャッフル後にアッドすれば、セット完了ですので、自分のデックを使用する、あるいは少し前に3枚をパームしポケットに隠しておくなどすれば、Prefigurationより強いインパクトが得られるかも知れません。
2006年02月03日
17:22
? ?11:?CULL
失礼、仕事をしながら書き込んでたら、BJさんが詳細な説明を先に書き込まれ、前後しました。
2006年02月04日
00:58
? ?12:?BJ
書き込まないで欲しいというメッセージがありましたので、ここで終了します。
すみません。
ただ、付け足しとして、最初の6枚を数えているときに、7が含まれた場合ですが、これは単にカルして7枚目に持って行くのが良いと思います。
後は、デックを表向きにして、大体、半ばくらいのところを客にフォースするようにし、ここから半分ずつにデックを分け、トップカードをフォースした形にし、これを裏向きにテーブルに置きます。
後は、なんとなく分かると思います。
2006年02月04日
06:58
? ?13:?RYUSEI
BJさんへ
せっかくお話が盛り上がっているところなのに、書き込まないで欲しい、というメッセージはどなたからあったのでしょうか、教えて頂けないでしょうか?
2006年02月04日
15:26
? ?14:?kushio
>BJさま(Cc:RYUSEIさま)
直メッセージってことですよね?‥‥まぁ、そんなこともあると思います。またの機会に御知恵を拝借させて下さい。
Jennings版Prefigurationについて詳細な御説明、望外でした。ありがとうございます。検討・修錬して試演し、観客からのリアクションなどを手掛かりに、その手順の違いによる効果の違いなど考えてみたいと思います。
>CULLさま
Pop-over Treysですか。あれも面白い原理、というかアイデアですね。ただ、パーム及びアディションを使うとなると、せっかくの『仕事の少なさ』が犠牲になるような気もします‥‥手順に入ってしまえば確かにクリーンで面白いのですが‥‥。
ちなみに実際にCULLさんはレパートリーとして演じておられますか?(私は以前に検討しただけで実演したことはありません)。もしそうでしたら、気をつけているポイント、コツや工夫などはありますでしょうか。良い作品ですし、このトピックをお読みになった方々の中に、今後この作品を『お気に入り』にする人が居られるかもしれませんし、参考にさせて頂きたいのですが、どうでしょう?
2006年02月04日
18:48
? ?15:?BJ
>RYUSEIさん
誤解があるといけないので、もう一度、書き込んでおきます。
僕に対してのメッセージは、決して悪意のあるものではなく、手短に言うと、「結論が出ていないのに書き込みをつづけて行くことは混乱をまねく」という意味のメッセージです。
好意も十分に感じられる話なので、自主的に書き込みをストップした次第です。
やめろ!と命令されたり、理不尽なメッセージをもらったわけではありません。
自分は、自分に対しての好意と取っているので、書き手の公表をする必要はないでしょう。
2006年02月04日
19:25
? ?16:?CULL
kushioさん、毎度!
実はPop-over Treysをレパートリーにはしていません。
というのは、同じような現象で、もっと他にやりたい奇術がたくさんあるので、入れる余地がないのです。
で、この奇術をなぜ推すかというと、主に講習用に使って、好評だからです。
パームのくだりを省いても十分通用する奇術ですし、パームを使えばよりインパクトの強いものとなるので、練習に発展性があるところも、習った人の満足度が高いようです。
実際、カードマジック事典の記載があまりにも淡白なので、この本を持っていても、ほとんど見過ごされていることも、ある意味面白いところではあります。
教えた後で「事典に載ってるよ」というと大抵「えぇーー! もう一回読み直そ。」という返事が返ってきます(笑)
2006年02月04日
19:50
? ?17:?RYUSEI
BJさんへ
了解いたしました。ご返答ありがとうございます。
プリフィグレイションに関して自分は無理にエースを使う必要がないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
エース(または絵札)のような特別なカードは、逆に観客にその特別感を植え付ける事になるような気がします。
通常の4エースは、連続して、あるいは即座にエースを出現させます。
演者、もしくは観客が意図的に出現させる現象がほとんどではないでしょうか。
このプリフィグレイションの場合は最初の予言が当たる、という時点で観客が演技が終わったと考え、終わったと思いきや3枚目が現れ、もしやと観客が思った時にたまたま4枚そろってしまう、という畳み掛けるような現象を表現したかったのではないでしょうか。
通常のスポットカード(字札)の方がリアリティがあるように思えるのですが…。
2006年02月04日
20:33
? ?18:?kushio
CULLさま:
(技術的に)簡単な作品でも、演じる際には難しい作品と同じレベルの心配りが必要だと思っています。講習のときには、どこが(演じる際の)ポイントだ、と言っていますか?
>教えた後で「事典に載ってるよ」というと大抵「えぇーー! もう一回読み直そ。」という返事が返ってきます(笑)
あの事典ですから、さもありなん、というかんじですね(笑)
ちなみに、CULLさん御用達の4A出現は何ですか?昔は○○に凝っていたけれど最近は△△がお気に入りだ、とか‥‥
RYUSEIさま:
>プリフィグレイションに関して自分は無理にエースを使う必要がないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
あ、いや、その通りなんですけども、4Aに関連した話題、としてごにょごにょ‥‥(笑)
私がプレフィグレーションを演じるときは、今のところは確かに仰る通り普通のスポットカードを出し、『ツイスティング4』などにつなげています。しかし、Aのほうが映える作品もありますよね?それらにつなげるために、プレフィグレーションのもつ『フェアーさ』を持ちこめないか、という発想での、話題提案でした。
ですが、RYUSEIさんの仰る『畳み掛けるような』というのは考えていませんでした。そう言われると、確かにそれがプレフィグレーションの『良さ』のような気がしてきました。
2006年02月04日
21:48
? ?19:?CULL
Pop-over Treysに関しては、やはり『客が切ったデックでいきなり行われたようにみえること』が重要だと思います。
ですから、パームを使わない場合はやはり、セットに気付かれない事は重要だと思いますので、次のような方法を薦めています。
まずデックをよく切ってもらいます。
その後デックをざっと見て、2,3枚同じ数字のカードがくっ付いているものを探します。そして、それがトップに来るようにカットし、残りのカードを何気なくトップに移し、最終的に同じ数のカードがトップになるようにします。
以上の作業は、例えばSandwich Effectに使うための2枚のJackを探す作業にまぎれて行います。そしてPop-over Treysの前にSadwich Effectを行うのです。
所謂、Time Misdirectionです。
僕がやっている『4枚のA(あるいは同数のカード)が出てくる現象』は色々ありますが、よく使うのは以下のようなものです。
Earl Nelson's Sleeve Aces
Jonahtan Neal Brown's Benihana Aces
松田道弘のマニアのためのカードマジックp.60に収載されている『エース・オープナーの効果』
David Solomon's Cutting Ten (Solomon's Mind p.27)
以上の4つは長年のお気に入りです。とても良い奇術です。
ただし、下の2作品はどちらかというと『Spectator Cutting Aces』です。
2006年02月04日
22:18
? ?20:?RYUSEI
自分は「ひょっこり現れる3(Pop-over Treys)」を初めて見たのは高木先生の小学館「マジック入門」です。
心理学的巧妙さを兼ね備えたまさに初心者に向いている傑作だと自分も思います。
ただ技術的な面白さにかける為、初心者から中級者へと移行するに従ってレパートリーから外れていくような気がします。
その演出上、3を使う必要性があり、その他のスポットカード(もしくはエース)だと論理性がかけると思われるのですが、どういった形でフォローしているのでしょうか。
プレフィグレーション的にエースで行う作品としてはやはりジェニングスですが、事典216ページにある「差し込んだカードと一致するカード(Stabbed Coincidence)」が近いのではないでしょうか。
自分はキングの出現として用い、ビジターなどにつなげていました。
2006年02月05日
00:44
? ?21:?BJ
言わずにはいられなくなったので、書き込みます。
色々な検討がなされていて、面白いのですが、ただただ何かを羅列している感は、否めません。
僕の考えですが、たとえば、Prefiguration というテーマが出たとしたら、それをもう少し掘り下げるように考えるのはどうでしょうか。
もともと、kushioさんのPrefigurationへのこだわりから出た事ですから、このマジックについて色々検討してみると、もっと深いところからマジックを考察でき、実際に演じるときの大きなプラスになると思います。
あのマジックがいい、自分はこのマジックでやっているといくら書かれても、そのマジックをどうとらえ、どう演じるかは、人によって違います。
同じマジックを演じても、まるで面白くなくなってしまう場合もあります。
ひつとのマジックを、もっと掘り下げて話してみたら、出来ない人の参考にも、もっとなるんじゃないでしょうか。
たとえば、CULLさんの書き込みでは、Prefiguration には Vernon Wedgeが使用されるので、と簡単に書き、それで終わっています。
正確に言えば、使用されているのは、Vernon Wedge ではなく、Vernon の Wedge Break を使った、Larry の Wedge Cul です。
では、Wedge Cull とはどんなテクニックなのか。そして、一体、どれだけの人が Wedge Cull についての知識があるのでしょう。
それにもっと大事なことは、このテクニックを実際に使うのは、かなりのカードマニアでも難しいということです。
それをどうやって演じているのかが、大事なポイントです。これが下手だったり、使い物にならない方法だったりしたら、Prefiguration はマジックとして成り立たなくなってしまうでしょう。
僕ならこうやるという意見があると思います。実際に自分は、やさしく出来る方法を考えたことがあり、それを使っています。他の方の考えた、より素晴らしい方法もあるでしょう。
また、たたみかける、とRYUSEIさんが、表現していましたが、それは RYUSEI さん流であって、他の考え方もあります。
ひとつのマジックに対して、それが議題に出されたら、そういう細かいところをしっかりと勉強して行くことが、マジック全体が向上する術だと、僕は考えます。
いかがでしょうか。
2006年02月05日
01:32
? ?22:?CULL
確かに・・・(笑)
もともとの御題が『出現系A』ということだったので、話題の焦点がボケる事も承知でしたが、色々な人が読んで楽しいかな、という思いで関連奇術にも触れました。(実際、Kushioさん自身、それにも興味を持たれたようですし。)
Prefiguration については、BJさんが言われる通り、ちょっと特殊なMultiple Controlが行われるのですが、これは手元に文献を持たない多くの人に、絵なしではちょっと説明しづらい面もありますよねぇ。
そして(これはあくまでも僕の個人的な意見ではありますが)このJennigsによるアプローチは、一般客に与える現象のインパクトと比較すると「少々しんどすぎる」という印象があるのです。
要するに『全く何もしなかったような印象を与えることが、一般奇術家には困難』と思われるわけです。実際、予めセットしておく方法以外に、良いアイディアも持っていませんし。
というわけで、そう考えると『もっと実用的で、同じような印象を与える奇術に触れておく』ということも、情報提供として意味があるかな、と感じて書き込みました。
ただ、BJさんの指摘されるような意味では、書き込むタイミングが早すぎた感も否めません。
2006年02月05日
05:51
? ?23:?RYUSEI
原案のプレフィグレイションに関しては、ジェニングスが表現したい演出は下記のような事ではないでしょうか。
観客に自由にシャッフルさせたあと…。
1、予言のカードを術者が一枚選んで、テーブルに置く。
2、デックから一枚ずつテーブルに配ってゆき、好きなところでストップと言わせ、偶然選ばれたカードの数字を使うことにする。
3、その数字の枚数をテーブルにある二つのパケットをお互いに持ち、一緒に配る。
4、その枚数目のカードをお互いにオープンにすると数字が一致している、しかも配った数字とも一致している。
5、そして予言の数字とも一致している。
つまり、原案においては、畳み掛けるというよりは、現象が起きた時には既に必然的に3枚のカードがオープンになっている、という事です。
そして予言のカードを最後ドラマチックにオープンにすれば、4枚のカードがそろう、というものではないでしょうか。
それに対してオグデン版では、一枚ずつオープンにしていく事に味わいがあるような気がします。
どちらが良い、というのではなく演じる人の好みかも知れません。
またセッティング方法に関しても
原案が意図している事はデックをテーブルに置きたくなかったのではないでしょうか。
入門という意味ではオグデン版の方がセットしやすいのですが、テーブルに置く、という動作の為にどうしてもセット臭さが出てしまう危険性あります。
かといって原案では、最初のブレイク(バーノンブレイク?)の部分が難しく、されに自分に向けてのカルの動作に違和感を持つ人もいるでしょう。
いずれにせよ、自然に行えば問題はないのでしょうが…。
ただこれもやはり好みの問題だと思います。
2006年02月05日
06:04
? ?24:?BJ
Jennings の演出で大事なことがあります。
龍生さんのプロットでは、単なるCoincidence になりますね。しかし、Jennings は、influence という言葉を使ってこのマジックを演じています。それは、ミスディレクションにもつながっていて、かなり大事な要素になっているんです。
つまり、龍生さんの考えと少し異なる演出となり、Jennings をしっかりと習うことは、単にマジックを覚えることではなく、マジックを上達するのに非常に参考になる個所があるんです。
手順によってのみ、マジックを覚えたと言ってはいけない、と言うことです。
2006年02月05日
08:13
? ?25:?BJ
欲求不満になる文章なので付け足します。
言いたい事は、マジックを面白くする要素は手順も大事ですが、それだけではマジックにならないということです。
一番は、演出、あるいは作品の心でしょう。どう演じるかです。これはテクニックも大いに含まれます。
CULLさんが言われる、「Jennigsによるアプローチは、一般客に与える現象のインパクトと比較すると「少々しんどすぎる」という印象がある」は、個人的な意見であってマジックの価値を意味するものではありません。もちろん、ご本人もそうおっしゃっていますが。
米国に、VernonのTwisting Aces を好きじゃないと言う僕の友人がいます。Ace の変化が分かりにくく、客受けがしないという理由です。
しかし、僕は Twisting Aces が大好きです。客はかならず喜び、驚きます。やはり、天才の作った作品です。しっかりと、その価値を把握すれば、Twisting Aces は誰がやっても素晴らしいマジックになります。そうではない、と言う時は、やり方が悪いだけです。
すみません、CULLさん、気を悪くしないで下さい。
僕自身は、いつもそう思っていますから、自分は、天才の作品に対して、あれは好きじゃないとは言えないんです。自分が、その価値を把握出来ていないと考えるからです。
そして、Twisting Aces は、幾多のバリエーションが作られましたが、どんなに素晴らしいバリエーションが作られようと、原案の価値は、まったく下がることはありません。
つまり、マジックを作る人は天才です。バリエーションを作る人は、天才ではなく、秀才と僕は考えます。
以前にも、他のコミュに書き込みましたが、天才に触れることが大事なことなんです。そして、自分を謙虚にし、天才が何をしようとしてるのかを把握しようとしながら、マジックを覚える。
それが僕のやり方です。
押し付けはしませんが、それが良いマジックを演じられるようになる秘訣です。
Prefigurationを僕が演じると、人は驚き楽しみます。Jennings の考えた心を演じようとするからだと思います。
テクニックと、表現される作品のバランスは、決して、悪くありません。手順も完璧に考えられています。
たとえば、前回に手順を書きましたが、あの後、Jennings は、カードを表向きにします。このとき、フェイスにあるカードを見て、このカードを相手に意識させて、influence の話をします。
influence の日本語訳ですが、こういのが一番難しいです。影響、誘導、感応、伝染もありますね、色々と辞書に意味が出ていますが、どれも少しずつニュアンスが違います。それをみんな一緒にしたもの、と言った方がいいか。
これがマジックを面白くするだけではなく、ミスディレクションになります。
つまり、フェイスのカードを見て、次に同じカードが来るまで、influence の話をしながらテーブルにカードを一枚ずつ置いて行くのです。
これは、次のカードと何か関係があるように客に思わせながら、実は、デックの半分くらいのところで客にストップをさせるための手段(フォース)になっています。
何も言わずにカードを置きながら相手にストップをかけさせるより、色々な点でマジックに膨らみが出ます。
同じカードが出たところで、続けてカードを置いて行きますからと言い、客が influence を感じたところでストップをかけて貰います。これでデックの半分くらいのところで客がストップをかけることになります。
客はこのinfluenceの話によって、二つのミスディレクションを受け入れています。
つまり、1つ目は、先に述べましたが、二つ目は、客がストップをかけたときに、テーブルに置いたカードを示し、ここで貴方は、influence を感じたわけですね、と強調します。
これは、マジシャンが誘導したのではなく、あなたの気持ちでストップしたところです。
このとき、左手に持った残りのデックを裏向きにして、では、貴方のストップをかけたところ、こちらは表向きになっているので、次のカードをテーブルに置きます。
と、左手のトップカードをテーブルに置きます。
客は、influence の話をされているため、それがトップにあったカードだという事から、気を引き離されてしまっています。
これでフォースは完全です。
というような具合です。
ちょっとまとまりませんでしたか。でも、言わんとしてる事は分かっていただけると思いますが。
2006年02月05日
08:23
? ?26:?BJ
付けたし。
>RYUSEIさん
>>最初のブレイク(バーノンブレイク?)
Vernon Break ではなく、
>Vernon の Wedge Break を使った、Larry の Wedge Cullです。
と、自分の書き込みに書きました。
ですから、Wedge Breakです。しっかり読んで下さい。
2006年02月05日
08:50
? ?27:?RYUSEI
なるほど。
ウェッジブレイクですね。
話が飛びますが、実際にウェッジカルをやっているのを故片倉氏から見せてもらった事があります。しかし他の人でそれを行っている人を見た事がありません。
一枚ならいざ知らず、4枚、それを行うコツのようなものはありますか?
演出面においてもインフルーエンスの話までは考えた事がありませんでした。オグデン版のプレフィグレイションの場合、どうしても同じ数字のカードが二枚並ぶところにやましさを感じてしまう事もあり、早めに過ぎ去ろうとしていました。
確かに、最初に術者が「う〜ん」と悩みながら、やっと何かを感じて一枚を選び出すわけですから、演出上、観客にも何かを感じたら止めてもらう方が論理的ですね。
さてインフルーエンスを訳すのが難しいとの事ですが、根本的な疑問としてプレフィグレイションをなんと訳すのが一番ピンと来るのでしょう?
2006年02月05日
15:09
? ?28:?RYUSEI
ちなみにジョン・マレー氏の『Spectaculer Prediction Coincidence』は、その名前からもコインシデンスです。
ガルシアのレクチャーノートを見れば、ジョンマレーの名前はあるのですが、ジェニングス、オグデンの名前は見当たりません。が、全く同等のものだと思います。
セットのやり方そのものはオグデン式と全く同じです。それ以外は微妙に違います。しかし、ほとんど同じものに見えます。
あえて違いを言うのならば、カードをオープンしていくディスプレイが違います。
ちなみにこの小冊子の中で、キングの場合は「K、I、N、G」とスペルで行いましょう、と解決方法が述べてあります。
2006年02月05日
16:56
? ?29:?Tango
BJさん、あなたの分析はあまりに鋭い!
是非演技を拝見したいところです。
ちょっと話題が逸れてしまうかもしれませんが、言葉についての考察を・・
単なるTrickを本物のMagicに変えるのは、確固たる主題に基づく一貫して適切な演出だろうと思います。
ここでの要点はPrefigurationと言うことでしょう。
これは、かなり古めかしい感じの単語で、予言とか予示とか約されてると思います(pre=前もって+figure=形を思い浮かべる)
その文脈でinfluence(なにかのエネルギーが、流れ[flow]入る[in]イメージ)という言葉を用いた場合、一種の超自然的な影響力と言ったニュアンスがもたらされるのだろうと思います。
一昔前の欧米人なら、Mesmerism(催眠術‐と言うより催眠実験と呼ぶべきか)をイメージする可能性もありそうです。
(どこかでPower of Influenceを暗示の力と約しているのをみた記憶がありますが、この辺りの意を汲んだものなのでしょう)
かなり遠回りしてしまいましたが、Prefigurationと名付け、influenceという単語を用いた=それにみあった演技をしなければMagicではなくTrickにすぎなくなると言うことなのかもしれません。
ああ、天才って凄い!(一人で勝手に感動してしまった・・・)
2006年02月05日
20:18
? ?30:?kushio
Prefigurationの話。
突然『はっ!もしや!?』と思い出して、おそらく国内では『入門者はコレを読め』と言われる確率が最も高いと思われる『ラリージェニングスのカードマジック入門』(加藤氏の本)を見ますと、載ってました(^^;
読んでたはずなのに‥‥
BJさんの『influence』のお話、すぐには(実感を伴った)理解には至りませんです‥‥上記の解説本、およびもちろん以前の書き込みを参考に、研究してみます。私自身はJenningsではないですから、実演してみるまでにはまだそれなりに紆余曲折あると思いますが、それにしてもPrefigurationだけでここまで話が掘り下げられることに快感を覚えつつあります。当たり前ですが、プロアマ問わずみんなマジック好きやねんなーと思います(笑)
‥‥トピ立てて良かった (^O^)
2006年02月05日
20:29
? ?31:?kushio
既に4Aとちゃう話題やんけ!という声はひとまず置いといて、Pop-over Treysの話。
CULLさま:
Time Misdirectionとしての『前フリ手順の中でのセット』‥‥言われてみれば当たり前ですが、そうか、やっぱり&なるほどな、というかんじです。上手く表現できないのですが。
私の感覚では、あの『リバースカウントの原理』(仮称)をダイレクトに使っていますので、タイミングとかパターというか、『流れ』をおろそかにすると、カンの良い人が相手の最悪の場合『そんなん当たり前やん』と思われかねないリスクがあるように思います。
ちなみに、私もいくつかの4A出現をやったりしますが、(事典のPop-over Treysの前頁にある)『AとKの出現』と、有名な『Ace Bonanza』が、結局いちばんウケが良かったりして、複雑な気分になったりします(^^;
2006年02月05日
20:38
? ?32:?kushio
連続投稿失礼します。分けたほうが良いかな、と思ったもので‥‥。
BJさま:
話題が並行してしまうのは、mixiトピックであっても、やはり或る種のBBSですから、やむないことでしょう。むしろ忘れた頃に堀り下がった昔の話題が出てきたりすることによって活気が出てくることもありますから、そのあたりは気楽に行きましょう。もちろんとことん行くのも、どちらさまもwelcomeでしょうし(^^
もし必要なら、『○○の話題は別トピック立てましょう』ということも、おそらく皆さんにも受け容れられやすいことでしょう。
ちなみに、最初に変化球で話題を振ったので、一段落したら、正統派っぽく(?)バーノン教授の『Cutting the Aces』の話題を振る予定だったのですが、私の思惑を良い意味で外れ、このように興がのってきたので「教授の作品だから、そのうち誰かが言うだろう」と思ってやめたのでした(笑)
2006年02月05日
22:58
? ?33:?BJ
>23-RYUSEIさん
念のために書き込んでおきます。
Prefiguration の手順ですが、1と2は、その通りですが、3と4は違っています。
客と共にカードを置いて行くのではなく、マジシャン自身がラストまで行います。
やはり、最後までマジシャンのinitiative によって演技を行う事で、すべてのタイミングがマジシャンのものとなり、マジシャンの作品になります。
相手を入れるのも、その人の好みにはなるでしょうが、原案の良さを追求するなら、マジシャンのinitiative によって進行させるべきと思います。
2006年02月06日
13:53
? ?34:?RYUSEI
私自身は原案をレパートリーからはずしていたのには理由があります。
1、ウェッジカルを用いる最初のセットアップの不安。
2、あまりにも大胆なフォースにおける不安。
でした。
そしてまさにその二点を改良したのが、オグデン式でありマレー式でしょう。
そしてまた、トム・オグデン氏のコメディタッチのキャラクターによって軽快に演じられている作品である、と考えています。
その反面、セットの方法に何らかの怪しさが残る結果となってしまっている部分があります。
つまり、その二点さえクリアされれば、現象としての完成度は原案に軍配が上がるのではないでしょうか。
BJさんへ
原案についての知識ありがとうございます。
さてオグデン式とマレー式ですが、明確な違いは何なのでしょう。
また、欧米においてはどちらの作品として認知されているのでしょう。
原著を持っていないのでわかりませんが、ガルシアはなぜジェニングスのことを述べなかったのでしょうか?
2006年02月06日
18:20
? ?35:?BJ
まず、RTUSEIさんの読まれた原案は、加藤英夫さんの「L.Jのカードマジック入門」だと思います。
あれは、原案とは異なります。
入門書のために加藤さんが改案しています。
ですから、前回に書いた influence を含む、 Jennings の心はいっさい入っていません。ラストの相手と一緒にカードを置いて行く、も加藤さんのアイディアです。
Wedge Cull すら使われていません。とにかく、やさしく出来るようにした事により、原案の雰囲気は消されてしまっています。
あれでは、最初の予言(ではないのですが、とりあえず)のカードをデックから探し出すところから、まるで違うものになっています。
実際には、原案だと2枚のカードのどちらかを考える状態にはなりますが、加藤さんの改案だと、四枚も、それを考えながらカードをくっている状態になり、不自然です。
2006年02月07日
04:09
? ?36:?RYUSEI
なるほど。
その通りです。加藤さんの本で学びました。
という事は、原案にあるウェッジカル(Wedge Cull)というのは、どう説明すればよいのでしょうか。
術者自身がイニシャチブをとるとありますが、2枚目、3枚目のカードをどのようにめくるのが本来のやり方なのでしょう。
|
|
|
|
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
クラシックマジック研究のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90052人