2011年の相場について、少しじっくりと考えてみたい。
私は、二つの切り口から分析していこうと思う。
1.2011年の相場を考えるには、2011年にいたるまでの相場の流れ(歴史)と2012年以降の未来を考える必要があること。
2.相場を動かす要因として、「市場的な要因」、「政府の存在」、「社会の変化」の3点から検討する。
今回は、1の2011年にいたるまでの相場の流れを中心に、「市場的な要因」、「政府の存在」、「社会の変化」に対する私の考えをまとめていたい。
少し結論めいたことを先に言ってしまうが、私はここ数年で相場を動かす「市場的な要因」が大きく変わったと思っている。すなわち最近の市場では「リスク許容力」という観点で、市場が変動するようになった。一昔前は、市場の注目は「米国の双子の赤字問題」であったり、「日本の貿易黒字」であったり、「米国の雇用統計」、あるいは「インフレ率」であった。こういう指標に相場は大きく反応したものだ。しかし、最近では相場を動かすメインドライバーは、「世界の投資家のリスク許容力」であり、「市場の変動率(ボラティリティー)」である。
リスク許容力が強い環境=市場の変動率が低い状況=世界が安定している状況では、株価などの資産価格が上昇し、高金利通貨が買われ、低金利国の通貨が売られる。こういう流れである。
どうして、そういう市場環境になったのか。その辺に注目する必要があるだろう。
2001年以降、世界の主要国は一斉に利下げを開始した。米国でITバブルが崩壊したり、米国同時多発テロの混乱があったりと、世界経済、国際社会が混乱していたことが背景にある。
2003年になると、世界経済は回復基調に入る。世界中の株価、住宅価格が上昇し、各国は順じ低金利の修正局面に移行していく。日本だけは取り残され、株価も冴えず、日銀が量的緩和政策を終了するのは2006年まで遅れることになる。ちなみに日本の社会的な特徴としては、2000年にユニクロが台頭し、2004年から2005年はレクサスや高級家電ブームが起こり、日常生活は180円スニーカーなどで節約する一方で、一点物は高価なものを求めるムードであった。
世界経済は2003年から2007年まで驚くほどの安定期に入る。大きな事件はほとんどなく、危機も起こらない。順調に株価は上昇し、グルーバルマネー、オイルマネー、キャリートレードという言葉が新聞に連日掲載されていた。私は、この時期は非常に重要であったと考えている。
なぜなら世界が安定していたことで、エマージング諸国の発展・インフラ整備、法整備がこの間にかなり進行したからだ。すなわち、これまでの世界では何だかんだいって米国、日本、欧州、イギリスといった先進国にしか本格的に投資はできなかったのである。それがエマージング諸国に投資しても安心な環境になった。このことは、その後の世界のお金の流れを大きく変えていくことになったのである。BRICSという言葉もこの時期から一般的になっていく。なにしろ2000年から2007年までに世界のGDPは23.5%上昇した。凄い成長である。日本でさえ12.2%成長した。中国にいたっては90.3%の成長である。重要なことは、単に世界経済が成長したことではなく、非常に国際社会が安定し、平和であり、市場の変動率が過去例のないほど低下したという環境がポイントなのである。そして、この世界の黄金期があったからこそ、グローバルマネーが本当の意味で世界中を駆け巡るようになり、投資家のリスク許容力ということが、市場の注目になっていくのである。
為替相場にとっても、この影響は顕著に現れた。2002年から現在に至るまでドルは一方向に「ドル下落トレンド」となっている。(2005年は一時的にドル高となったが)何故持続的なドル安が起こるのか?それは米国が経常収支の赤字を補うだけの海外からの資金流入を集めにくくなっているからである。経常赤字そのものが問題なのではない。1999年から2001年は、米国の経常赤字は増加していたが、ITバブルに沸く米国には、資金がどんどん流入し、ドル高となっていた。しかし、2003年から2007年の世界の黄金期にエマージング諸国への投資ができるようになったことで、米国へ向かう資金は減少したのだ。また世界が平和であったため、米国の武力を前提とした通貨の信用力はあまり重要ではなくなった。しかも世界経済が好調な期間は、貿易が活発化して米国の赤字はどんどん膨れ上がる。このために米ドルは一方向にドル安となっているのだ。その急激なドル安に我々が鈍感なのは、その時期に同時に「円安ブーム」が発生し、市場では「ドル安」と「円安」が同時に発生し、ドル円相場はあまり大きな動きがなかったからであろう。
この2006年から2007年の日本では、外貨投資ブーム、FXトレード人気、軽自動車ブーム、プチプレミアブームが起こった。一方で高級品は売れなくなる。
さて2007年夏に米国でサブプライム問題が起こる。ITバブル崩壊後に株価が大幅に下落しても、住宅市場は崩れなかった。それほど米国における住宅の右肩上がり神話は強かったが、ついに住宅市場が混乱し始めた。この問題は複雑かつ広範囲で、時間が経過するにつれ深刻な問題であることが分かり始めた。もう既にこの頃の米国は非農業者部門雇用者数はマイナスになっており、景気もかなり落ち込んでいたことは認識しておく必要がある。そしてベア・スターンズ証券会社が破綻、そして2008年9月にはフレディーマック、ファニーメイという米国住宅市場の根幹をなすGSEが公的管理化に置かれたほか、米国最大の保険会社AIGも国の管理下となる。そして9月15日、リーマンブラザーズが破綻する。ここからは、日が経つほど市場は混乱し、いわゆる「100年に一度の危機」と呼ばれるメルトダウンが加速する。
そして、これ以降、市場では「政府の存在」が著しく大きくなる。それは今も続いている。各国の政府はこの危機を乗り切るために協調して、史上最大の金融緩和政策に踏み切り、応急処置に奔走するとともに、これまでの金融のありかたという哲学的な問題まで介入し、米国は「金融規制を強化」する方向に進んでいく。
2009年の前半は相変わらず不安定だった。市場は悪いニュースに常に敏感になり、3月には世界の株価がこの危機の底値をつける。例えばNYダウは3月9日に6,547.05まで下落、日経平均株価も3月10日に7千54円98銭の安値を記録した。ちなみにこの頃の原油価格は1バレル30ドル後半から40ドル前半である。
しかし、各国の金融政策、大規模な財政政策が功を奏し、3月以降世界の株価は急激に反転する。6月には米国を代表する自動車会社GMが破産法を申請したが、株価の勢いはまったく揺るがなかった。ドル円相場も1月の87円台から4月には101円45銭まで円安となり、米国の長期金利お2008年末の2.1%から5月には3.7%まで上昇していた。世界経済回復モードである。
オバマ大統領も7月末には「リセッションの終わりが見え始めている」と強気のコメントをした。オバマ大統領といえば、7月に支持率が60%を割り込んだと思ったら、8月には早くも50%割れと、人気が急激に低下していったのがこの時期である。日本では政権交代が実現し、民主党政権が誕生している。
2009年はこのまま平穏に終わるかと思った矢先に11月にドバイショックが起こり、一時的に市場は混乱し、投資家のリスク許容力は低下、ドル円相場は88円から85円09銭まで円高となる。しかし市場はすぐに落ち着きを取り戻した。
こういう流れの中で2010年に突入していったのである。
次回は2010年と2011年について進んでいこう。
私は、二つの切り口から分析していこうと思う。
1.2011年の相場を考えるには、2011年にいたるまでの相場の流れ(歴史)と2012年以降の未来を考える必要があること。
2.相場を動かす要因として、「市場的な要因」、「政府の存在」、「社会の変化」の3点から検討する。
今回は、1の2011年にいたるまでの相場の流れを中心に、「市場的な要因」、「政府の存在」、「社会の変化」に対する私の考えをまとめていたい。
少し結論めいたことを先に言ってしまうが、私はここ数年で相場を動かす「市場的な要因」が大きく変わったと思っている。すなわち最近の市場では「リスク許容力」という観点で、市場が変動するようになった。一昔前は、市場の注目は「米国の双子の赤字問題」であったり、「日本の貿易黒字」であったり、「米国の雇用統計」、あるいは「インフレ率」であった。こういう指標に相場は大きく反応したものだ。しかし、最近では相場を動かすメインドライバーは、「世界の投資家のリスク許容力」であり、「市場の変動率(ボラティリティー)」である。
リスク許容力が強い環境=市場の変動率が低い状況=世界が安定している状況では、株価などの資産価格が上昇し、高金利通貨が買われ、低金利国の通貨が売られる。こういう流れである。
どうして、そういう市場環境になったのか。その辺に注目する必要があるだろう。
2001年以降、世界の主要国は一斉に利下げを開始した。米国でITバブルが崩壊したり、米国同時多発テロの混乱があったりと、世界経済、国際社会が混乱していたことが背景にある。
2003年になると、世界経済は回復基調に入る。世界中の株価、住宅価格が上昇し、各国は順じ低金利の修正局面に移行していく。日本だけは取り残され、株価も冴えず、日銀が量的緩和政策を終了するのは2006年まで遅れることになる。ちなみに日本の社会的な特徴としては、2000年にユニクロが台頭し、2004年から2005年はレクサスや高級家電ブームが起こり、日常生活は180円スニーカーなどで節約する一方で、一点物は高価なものを求めるムードであった。
世界経済は2003年から2007年まで驚くほどの安定期に入る。大きな事件はほとんどなく、危機も起こらない。順調に株価は上昇し、グルーバルマネー、オイルマネー、キャリートレードという言葉が新聞に連日掲載されていた。私は、この時期は非常に重要であったと考えている。
なぜなら世界が安定していたことで、エマージング諸国の発展・インフラ整備、法整備がこの間にかなり進行したからだ。すなわち、これまでの世界では何だかんだいって米国、日本、欧州、イギリスといった先進国にしか本格的に投資はできなかったのである。それがエマージング諸国に投資しても安心な環境になった。このことは、その後の世界のお金の流れを大きく変えていくことになったのである。BRICSという言葉もこの時期から一般的になっていく。なにしろ2000年から2007年までに世界のGDPは23.5%上昇した。凄い成長である。日本でさえ12.2%成長した。中国にいたっては90.3%の成長である。重要なことは、単に世界経済が成長したことではなく、非常に国際社会が安定し、平和であり、市場の変動率が過去例のないほど低下したという環境がポイントなのである。そして、この世界の黄金期があったからこそ、グローバルマネーが本当の意味で世界中を駆け巡るようになり、投資家のリスク許容力ということが、市場の注目になっていくのである。
為替相場にとっても、この影響は顕著に現れた。2002年から現在に至るまでドルは一方向に「ドル下落トレンド」となっている。(2005年は一時的にドル高となったが)何故持続的なドル安が起こるのか?それは米国が経常収支の赤字を補うだけの海外からの資金流入を集めにくくなっているからである。経常赤字そのものが問題なのではない。1999年から2001年は、米国の経常赤字は増加していたが、ITバブルに沸く米国には、資金がどんどん流入し、ドル高となっていた。しかし、2003年から2007年の世界の黄金期にエマージング諸国への投資ができるようになったことで、米国へ向かう資金は減少したのだ。また世界が平和であったため、米国の武力を前提とした通貨の信用力はあまり重要ではなくなった。しかも世界経済が好調な期間は、貿易が活発化して米国の赤字はどんどん膨れ上がる。このために米ドルは一方向にドル安となっているのだ。その急激なドル安に我々が鈍感なのは、その時期に同時に「円安ブーム」が発生し、市場では「ドル安」と「円安」が同時に発生し、ドル円相場はあまり大きな動きがなかったからであろう。
この2006年から2007年の日本では、外貨投資ブーム、FXトレード人気、軽自動車ブーム、プチプレミアブームが起こった。一方で高級品は売れなくなる。
さて2007年夏に米国でサブプライム問題が起こる。ITバブル崩壊後に株価が大幅に下落しても、住宅市場は崩れなかった。それほど米国における住宅の右肩上がり神話は強かったが、ついに住宅市場が混乱し始めた。この問題は複雑かつ広範囲で、時間が経過するにつれ深刻な問題であることが分かり始めた。もう既にこの頃の米国は非農業者部門雇用者数はマイナスになっており、景気もかなり落ち込んでいたことは認識しておく必要がある。そしてベア・スターンズ証券会社が破綻、そして2008年9月にはフレディーマック、ファニーメイという米国住宅市場の根幹をなすGSEが公的管理化に置かれたほか、米国最大の保険会社AIGも国の管理下となる。そして9月15日、リーマンブラザーズが破綻する。ここからは、日が経つほど市場は混乱し、いわゆる「100年に一度の危機」と呼ばれるメルトダウンが加速する。
そして、これ以降、市場では「政府の存在」が著しく大きくなる。それは今も続いている。各国の政府はこの危機を乗り切るために協調して、史上最大の金融緩和政策に踏み切り、応急処置に奔走するとともに、これまでの金融のありかたという哲学的な問題まで介入し、米国は「金融規制を強化」する方向に進んでいく。
2009年の前半は相変わらず不安定だった。市場は悪いニュースに常に敏感になり、3月には世界の株価がこの危機の底値をつける。例えばNYダウは3月9日に6,547.05まで下落、日経平均株価も3月10日に7千54円98銭の安値を記録した。ちなみにこの頃の原油価格は1バレル30ドル後半から40ドル前半である。
しかし、各国の金融政策、大規模な財政政策が功を奏し、3月以降世界の株価は急激に反転する。6月には米国を代表する自動車会社GMが破産法を申請したが、株価の勢いはまったく揺るがなかった。ドル円相場も1月の87円台から4月には101円45銭まで円安となり、米国の長期金利お2008年末の2.1%から5月には3.7%まで上昇していた。世界経済回復モードである。
オバマ大統領も7月末には「リセッションの終わりが見え始めている」と強気のコメントをした。オバマ大統領といえば、7月に支持率が60%を割り込んだと思ったら、8月には早くも50%割れと、人気が急激に低下していったのがこの時期である。日本では政権交代が実現し、民主党政権が誕生している。
2009年はこのまま平穏に終わるかと思った矢先に11月にドバイショックが起こり、一時的に市場は混乱し、投資家のリスク許容力は低下、ドル円相場は88円から85円09銭まで円高となる。しかし市場はすぐに落ち着きを取り戻した。
こういう流れの中で2010年に突入していったのである。
次回は2010年と2011年について進んでいこう。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
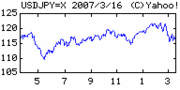














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)







