17週
8/10〜8/16
宇宙の言葉が語る−
「お前の霊の深みに
私の宇宙の拡がりを与えれば
いつか私をお前の中に
見つけ出せるであろう。」
この言葉を今
感覚の門を通して
魂の奥底にまで私は沈める。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
----------------------------
今年は、義父の初盆を迎える。
仏教では、死者の霊は死後七日ごとに冥土の裁判を受け、
四十九日に最後の審判が下され
故人の死後の行き場所が決まる重要な日と言われている。
四十九日までの間を『中陰』(ちゅういん)と言い、
その間の供養を『中陰供養』という。
四十九日は中陰の終わりの日として『満中陰』、
『尽中陰』ともいい、
それまで身につけていた死者のけがれがとれるので
『忌明け』となるというのだ。
仏教では、49日で仏様になるというのである。
だから、故人に対して(仏様)に対して
私たちを守ってくださいというお祈りをするのであろう。
しかし、シュタイナーを学び
死後の世界について知ると
仏教で言う「仏様」になるには、
気の遠くなるような年月を要するのである。
シュタイナーは、
比較的最近までは、
生者と死者とのあいだの生き生きとした交流が、
今日よりずっと活発だったと語っている。
しかし、近年、生者と死者との交流は、
次第に困難になってきているという。
昔は祈りのなかに、
死者のことを思う人々から、
暖かい愛の息吹が流れてくるのを、
死者たちの心魂は、
容易に感じることができたとのことである。
確かに、私の明治生まれの祖母は、
毎朝、毎晩、仏壇の前で先祖のため
お経を熱心にあげていたのを思い起こす。
このことが、書かれてある
『精神科学からみた死後の生』(シュタイナー 西川隆範訳)をみてみよう。
「比較的最近まで、生者と死者とのあいだのいきいきとした交流が、
今日よりずっと活発だったことが見出されます。
生者と死者との交流は、
次第に困難になってきました。
昔は祈りのなかに、
死者のことを思う人々から、
暖かい愛の息吹が流れてくるのを、
死者たちの心魂は、
容易に感じることができました。
今日のような、
外的なことがらばかりが重視される文化では、
死者はそのような愛の息吹を感じられなくなっています。
今日では、死者たちは生者から断絶されています。
地上に生きている者たちの心魂のなかで
何が生じているのかを見るのが、
死者たちには大変に困難になっています。」
そして「精神科学を通して生者と死者との間に再び橋を架けるのが、
人智学的な生活の実践的な課題の一つなのです。」と語っている。
この本によると死者と生者との交流に関して、
『死者も養分を必要とする』ということである。
そこでふと思った。
供養とは死者が必要としている養分を地上から送ることではなかろうか。
では、どのようにして養分を送ることができるのか。
死者は人間の思考と理念を、
養分として必要とするのである。
「死者は、友人や親族のところにやって来ます。
死者は、それらの人々が眠りの中に持ち込んだ
思考・理念から、養分を吸収しようとします。
しかし、自分の養分になるものを何も見出せないことが多いのです。
私達が一日中、物質的な生活の理念のみに関わり、
物質界で行われていることのみ目を向け、
眠る前に精神界への思考を持たないとします。
そうすると、私達は死者に養分を提供することができません。」と語っている。
この世で霊学の敵であった人たちも
死の門を通った後では、
霊学をこの上なく熱心に求めようとしている。
そして、死者となったその人に対しては、
霊的に深い内容をもった書物、
聖書やお経を読んであげること以上によい供養はないという。
生前の死者の姿を生き生きと心に思い浮かべながら、
心の中で、または、低い声で、
死者達に読んで聞かせる。
そうすれば、それが、死者に対して、
最も好ましい働きかけになる。
朗読をして励ましてあげる。
そうすると、死者達は、
提供されたものを深い感謝と共に受け取る。
そして、素晴らしい地上との共同生活を生じさせることができるのである。
まずは、
「いきいきと死者のことを考え、
私達が死者と共に体験したことを、
目に見えるような形で示す思考を死者に送ると、
私達は死者を大いに助けることができます。
抽象的な表象を、
死者は理解しません。
生前の死者と共に体験したことを、
具象的にいきいきと思い浮かべて、
その思考を死者に送ろうとすると、
その思考は死者のところへと流れていきます。
心魂に浮かぶそのイメージを、
死者は一個の窓のように感じます。
その窓をとおして、
死者は地上世界を覗くのです。
私達が死者に送るイメージは一個の窓のようなものであり、
その窓をとおして、死者は私達の世界を眺めます。」
そして、人間が地上で本を読むと、
霊魂存在たちもその本を読み始めるとのことである。
つまり、本に書かれていることが、
いきいきとした人間の思考内容になると、
霊魂存在たちは
人間の思考内容を読むことができるのである。
死者に向かって、
精神的なことがらの書かれた本を読むことは、
とても死者のためになるのである。
「まず、思いを死者に向けます。
死者のことを思い出し、
死者が自分の前に立っているか、
座っている姿を思い浮かべます。
大きな声で読む必要はありません。
書かれている内容を考え抜くのです。
それが、死者のための読書なのである。
表面的に読むのは不十分であり、
一語一語考えて言葉を発する必要があるのだ。」
人智学は単なる理論なのでなく、
人生に働きかけて、
生者と死者との間の壁を取り除く。
断絶に橋が架けられるのである。
死者達に読んで聞かせること以上によい助言はない。
ところで、
死者は霊界で教え諭してくれるような
霊的存在を見出すことができないのか?
見出すことができない。
死者は、生前結びつきのあった
霊的存在達としか関係がもてないのである。
この世で知ることのなかった神霊や死者達に出会っても、
死者はその存在を素通りしてしまう。
死者は自分と関係があった人々が地上で体験していることを、
心魂界から見る。
死者は死の直後から、地上で共に生きた、
いまも地上に生きている人々を通して、
地上の出来事すべてを体験できるのがわかるのである。
どんなに役だってくれそうな存在に出会っても、
生前、関係がなかったら何の役にもたってくれないのだ。
最後に『瞑想と祈りのことば』(西川隆範訳より一部抜粋)の
「死者のための祈り」 を書きながら、
感謝と共に祈りをささげたい。
わたしの愛が、
あなたを包む覆いになりますように。
あなたの暑さを冷やし、
あなたの寒さを暖め、
供養を捧げつつ、ひとつに織りなされますように。
愛を担い、
光を贈られ、高みへと生きていきますように。
わたしの心の暖かな生命が、
あなたの魂へと流れていき、
あなたの寒さを暖め、
あなたの暑さを和らげますように。
霊の世界で
わたしの思考があなたの思考のなかに生き、
あなたの思考がわたしの思考のなかに生きますように。
わたしの魂の愛があなたへと向かいますように。
わたしの愛の意味があなたへと流れていきますように。
わたしの魂の愛と、わたしの愛の意味が、
希望の高み、
愛の領域で、
あなたを支え、あなたを助けますように。
あなたがいる霊の世界を
わたしは見上げます。
わたしの愛があなたの暑さを和らげ、
わたしの愛があなたの寒さを和らげますように。
わたしの愛があなたに届き、
あなたを助けて、
霊の暗闇から
霊の光へといたる
道を見出すことができますように。
参考文献: 『死後の生活』(高橋 巌訳 イザラ書房)
『精神科学からみた死後の生』(西川隆範訳 風濤社)
『瞑想と祈りのことば』(西川隆範訳 イザラ書房)
8/10〜8/16
宇宙の言葉が語る−
「お前の霊の深みに
私の宇宙の拡がりを与えれば
いつか私をお前の中に
見つけ出せるであろう。」
この言葉を今
感覚の門を通して
魂の奥底にまで私は沈める。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
----------------------------
今年は、義父の初盆を迎える。
仏教では、死者の霊は死後七日ごとに冥土の裁判を受け、
四十九日に最後の審判が下され
故人の死後の行き場所が決まる重要な日と言われている。
四十九日までの間を『中陰』(ちゅういん)と言い、
その間の供養を『中陰供養』という。
四十九日は中陰の終わりの日として『満中陰』、
『尽中陰』ともいい、
それまで身につけていた死者のけがれがとれるので
『忌明け』となるというのだ。
仏教では、49日で仏様になるというのである。
だから、故人に対して(仏様)に対して
私たちを守ってくださいというお祈りをするのであろう。
しかし、シュタイナーを学び
死後の世界について知ると
仏教で言う「仏様」になるには、
気の遠くなるような年月を要するのである。
シュタイナーは、
比較的最近までは、
生者と死者とのあいだの生き生きとした交流が、
今日よりずっと活発だったと語っている。
しかし、近年、生者と死者との交流は、
次第に困難になってきているという。
昔は祈りのなかに、
死者のことを思う人々から、
暖かい愛の息吹が流れてくるのを、
死者たちの心魂は、
容易に感じることができたとのことである。
確かに、私の明治生まれの祖母は、
毎朝、毎晩、仏壇の前で先祖のため
お経を熱心にあげていたのを思い起こす。
このことが、書かれてある
『精神科学からみた死後の生』(シュタイナー 西川隆範訳)をみてみよう。
「比較的最近まで、生者と死者とのあいだのいきいきとした交流が、
今日よりずっと活発だったことが見出されます。
生者と死者との交流は、
次第に困難になってきました。
昔は祈りのなかに、
死者のことを思う人々から、
暖かい愛の息吹が流れてくるのを、
死者たちの心魂は、
容易に感じることができました。
今日のような、
外的なことがらばかりが重視される文化では、
死者はそのような愛の息吹を感じられなくなっています。
今日では、死者たちは生者から断絶されています。
地上に生きている者たちの心魂のなかで
何が生じているのかを見るのが、
死者たちには大変に困難になっています。」
そして「精神科学を通して生者と死者との間に再び橋を架けるのが、
人智学的な生活の実践的な課題の一つなのです。」と語っている。
この本によると死者と生者との交流に関して、
『死者も養分を必要とする』ということである。
そこでふと思った。
供養とは死者が必要としている養分を地上から送ることではなかろうか。
では、どのようにして養分を送ることができるのか。
死者は人間の思考と理念を、
養分として必要とするのである。
「死者は、友人や親族のところにやって来ます。
死者は、それらの人々が眠りの中に持ち込んだ
思考・理念から、養分を吸収しようとします。
しかし、自分の養分になるものを何も見出せないことが多いのです。
私達が一日中、物質的な生活の理念のみに関わり、
物質界で行われていることのみ目を向け、
眠る前に精神界への思考を持たないとします。
そうすると、私達は死者に養分を提供することができません。」と語っている。
この世で霊学の敵であった人たちも
死の門を通った後では、
霊学をこの上なく熱心に求めようとしている。
そして、死者となったその人に対しては、
霊的に深い内容をもった書物、
聖書やお経を読んであげること以上によい供養はないという。
生前の死者の姿を生き生きと心に思い浮かべながら、
心の中で、または、低い声で、
死者達に読んで聞かせる。
そうすれば、それが、死者に対して、
最も好ましい働きかけになる。
朗読をして励ましてあげる。
そうすると、死者達は、
提供されたものを深い感謝と共に受け取る。
そして、素晴らしい地上との共同生活を生じさせることができるのである。
まずは、
「いきいきと死者のことを考え、
私達が死者と共に体験したことを、
目に見えるような形で示す思考を死者に送ると、
私達は死者を大いに助けることができます。
抽象的な表象を、
死者は理解しません。
生前の死者と共に体験したことを、
具象的にいきいきと思い浮かべて、
その思考を死者に送ろうとすると、
その思考は死者のところへと流れていきます。
心魂に浮かぶそのイメージを、
死者は一個の窓のように感じます。
その窓をとおして、
死者は地上世界を覗くのです。
私達が死者に送るイメージは一個の窓のようなものであり、
その窓をとおして、死者は私達の世界を眺めます。」
そして、人間が地上で本を読むと、
霊魂存在たちもその本を読み始めるとのことである。
つまり、本に書かれていることが、
いきいきとした人間の思考内容になると、
霊魂存在たちは
人間の思考内容を読むことができるのである。
死者に向かって、
精神的なことがらの書かれた本を読むことは、
とても死者のためになるのである。
「まず、思いを死者に向けます。
死者のことを思い出し、
死者が自分の前に立っているか、
座っている姿を思い浮かべます。
大きな声で読む必要はありません。
書かれている内容を考え抜くのです。
それが、死者のための読書なのである。
表面的に読むのは不十分であり、
一語一語考えて言葉を発する必要があるのだ。」
人智学は単なる理論なのでなく、
人生に働きかけて、
生者と死者との間の壁を取り除く。
断絶に橋が架けられるのである。
死者達に読んで聞かせること以上によい助言はない。
ところで、
死者は霊界で教え諭してくれるような
霊的存在を見出すことができないのか?
見出すことができない。
死者は、生前結びつきのあった
霊的存在達としか関係がもてないのである。
この世で知ることのなかった神霊や死者達に出会っても、
死者はその存在を素通りしてしまう。
死者は自分と関係があった人々が地上で体験していることを、
心魂界から見る。
死者は死の直後から、地上で共に生きた、
いまも地上に生きている人々を通して、
地上の出来事すべてを体験できるのがわかるのである。
どんなに役だってくれそうな存在に出会っても、
生前、関係がなかったら何の役にもたってくれないのだ。
最後に『瞑想と祈りのことば』(西川隆範訳より一部抜粋)の
「死者のための祈り」 を書きながら、
感謝と共に祈りをささげたい。
わたしの愛が、
あなたを包む覆いになりますように。
あなたの暑さを冷やし、
あなたの寒さを暖め、
供養を捧げつつ、ひとつに織りなされますように。
愛を担い、
光を贈られ、高みへと生きていきますように。
わたしの心の暖かな生命が、
あなたの魂へと流れていき、
あなたの寒さを暖め、
あなたの暑さを和らげますように。
霊の世界で
わたしの思考があなたの思考のなかに生き、
あなたの思考がわたしの思考のなかに生きますように。
わたしの魂の愛があなたへと向かいますように。
わたしの愛の意味があなたへと流れていきますように。
わたしの魂の愛と、わたしの愛の意味が、
希望の高み、
愛の領域で、
あなたを支え、あなたを助けますように。
あなたがいる霊の世界を
わたしは見上げます。
わたしの愛があなたの暑さを和らげ、
わたしの愛があなたの寒さを和らげますように。
わたしの愛があなたに届き、
あなたを助けて、
霊の暗闇から
霊の光へといたる
道を見出すことができますように。
参考文献: 『死後の生活』(高橋 巌訳 イザラ書房)
『精神科学からみた死後の生』(西川隆範訳 風濤社)
『瞑想と祈りのことば』(西川隆範訳 イザラ書房)
|
|
|
|
コメント(5)
笑◎^∇^◎みかん♪ さん
kikiさん
あめじすとさん
コメントありがとうございます。
旧のお盆(月遅れのお盆) でいうと
今日は盆明け、送り火の日ですね。
昨夜は、こちらでも花火大会がありました。
先祖供養の送り火とおもって
花火を鑑賞していました。
一年に一度帰ってくるという
先祖を迎えるために迎え火を燃やし、
各家庭にある仏壇でおもてなしをしてから、
再び送り火によって
あの世に帰っていただこうという風習は、
今後も長く続いてほしいものです。
自分という人間がこの世に生まれる
根拠となった
ご先祖さまを大切にし、
「おかげさまで」
という言葉で代表される
日本人独特の謙虚さを
お盆の行事を通して
培っていきたいものですね。
ありがとうございました。
kikiさん
あめじすとさん
コメントありがとうございます。
旧のお盆(月遅れのお盆) でいうと
今日は盆明け、送り火の日ですね。
昨夜は、こちらでも花火大会がありました。
先祖供養の送り火とおもって
花火を鑑賞していました。
一年に一度帰ってくるという
先祖を迎えるために迎え火を燃やし、
各家庭にある仏壇でおもてなしをしてから、
再び送り火によって
あの世に帰っていただこうという風習は、
今後も長く続いてほしいものです。
自分という人間がこの世に生まれる
根拠となった
ご先祖さまを大切にし、
「おかげさまで」
という言葉で代表される
日本人独特の謙虚さを
お盆の行事を通して
培っていきたいものですね。
ありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
シュタイナー的生活を楽しむ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
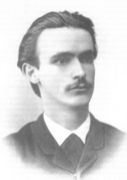











![[dir]メンヘル系コミュ総合](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/64/3/66403_123s.gif)










